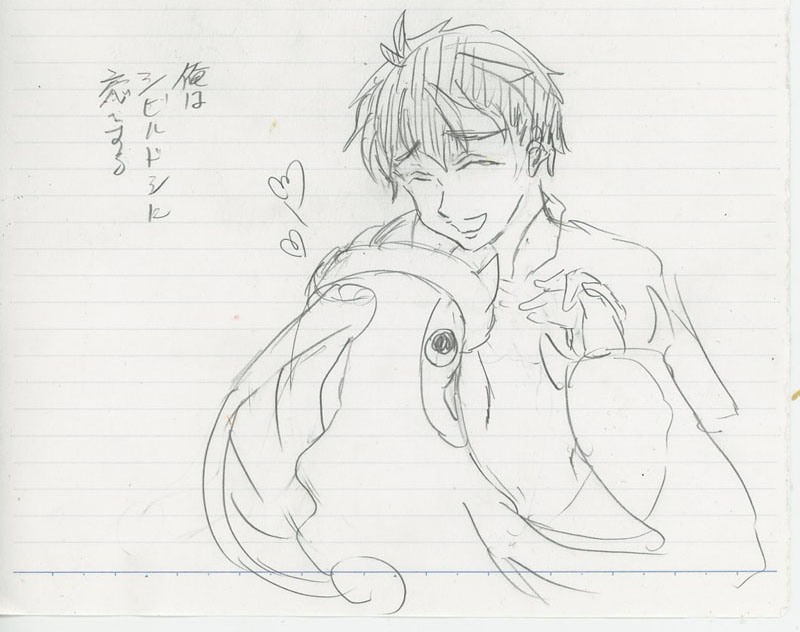「すいませーん! 店員さん、生二つ追加で!」
「あ、この炎帝ってやつ。水割りお願いしまーす」
「オニオンリング頼んだの誰ー?」
「あれ? 春岡、もう帰るの?」
スポーツ施設兼ポケモンバトル場のリトルコートを用いた練習試合の打ち上げということで、俺の所属しているテニスサークルはライモンシティの居酒屋に集まっている。もうかれこれ二時間は飲んだのでは無いだろうか、試合相手だった他大学の奴らも一緒になって盛り上がっている中鞄を持って席を立つと隣に座っていた同期が俺に気づいて尋ねてきた。ああ、と頷いて上着を羽織る。
「明日俺一限あんだよ。しかも必修、出席重視」
「それはご愁傷様。あ、そうだ。俺二限行けるかわかんねーからもし居なかったら代返よろしく。どうせあの講義、出欠カードだろ」
「甘えるな」
短く切り捨ててそいつの頭を軽く小突く。いてっ、と肩を竦めた同期と他のサークル員たちに手を振って貸し切りになっている一室を出ると、酒を運んできたポケモンとすれ違った。緑の身体をふわふわとさせ、頭に咲いた大きな黄色い花の上にお盆を乗せて器用に飛んでいく。何と言う名前だったっけ、確か草タイプだったはずだけれども。
「あっがとーっしたー」
学生バイトであろう店員の声と共に自動ドアが閉まる。ドアの先に広がるライモンの街並みは、夜の十一時を回ったのにも関わらずとても明るい。立ち並ぶ飲食店やコンビニには沢山の客が出入りしていて、若い女の子とマラカッチが一緒に客引きをしている。居酒屋花びらの舞、いかがですかー、という高い声に合わせてマラカッチが放った花びらが路上に散らばった。
流石にミュージカル場や遊園地は閉まっているけれどもバトルサブウェイはまだまだ開いているらしく多くのトレーナーが老若男女を問わず辺りに溢れていた。サニーゴを抱えたスーツ姿の男性、イーブイの進化形をそれぞれ連れた女子校生の群れ、ゴチルゼルとランクルスを伴った初老の夫婦。ランクルスの首にかかっている球体が鈍く光っている。
リードをつけたデルビルを連れて歩くトレーナーを横目に、俺はライモンの西に向かう。店先の電気に照らされた街をどんどん直進して、深夜勤務の警備員に会釈をしながら休憩所もそのまま通り過ぎる。五番道路に出ると、今朝来る時には営業していたトレーラーハウスの中がすっかり暗くなっていた。時間のせいか人通りは少なく、ちょっと離れた草むらにいる野生のポケモンもヤブクロンが数匹うろついているだけである。
中途半端に欠けた月を、ヤミカラスが横切っていった。まだうっすら耳に届くライモンの喧騒と、どこからか響いてくるレパルダスだかチョロネコの鳴き声をぼんやりと聞きながら大学名と俺の名前が印字された学生証を取り出す。
「お願いします」
「はい、確認致しました。どうぞー」
防犯上の理由だか何だかで、ここを渡る時には身分証明書が必要になったのはいつからだっただろうか。俺が幼い頃、新興宗教の過激派が何人か入り込んで迷惑行為をはたらいたのがきっかけらしいけれどもいちいち見せなければならないのは正直面倒くさい。
係員の声を背中で聞いて数歩歩いた先に見えるのは、リザードンが羽を広げた姿に似ていることでお馴染みの跳ね橋だ。運良く橋が下がっていて、俺は誰もいない歩道に足を踏み入れる。日中ならばコアルヒーが飛んでいるけれども人間同様今は不在らしく、橋に落とされた影は鉄筋が描く幾何学模様だけだ。
ゴールデンウィークも終わり、大分温かくなってきた。暑すぎず寒すぎず、心地良い風が吹いている。ずっとこのくらいの気温なら良いのにな、などと考えているとブロロロ……と轟音が響き、直後車道を走るトラックに追い越された。もわっとした空気が俺を包み、思わず目を閉じて砂煙から顔を覆う。
「…………ん?」
軽く咳き込み、顔を上げた俺の口から息と共に呟きが漏れた。開いた視界に入ったのは、転落を防ぐための鉄筋の向こうに佇む物影。暗くてあまり見えないけれど、身長やぼやけたシルエットから判断するに恐らく人の気がした。
(まさか、飛び降り……!?)
そんな考えが頭をよぎると同時に背中が震える。嫌な話だけれど、全く無いわけでは無い。この鉄筋部分だって数年前の自殺未遂を機に強化されたのだ。
どうしよう、と考えるも何の案も思いつかない。こんなことは初めてだし、まさか自分がこういう場面に出くわすなんて今まで思いもしなかった。どうすればいいんだろう。とりあえず止めなくては、という考えと、余計な刺激を与えない方が、という考えが交差する。
「あ、あのー……」
全く考えが湧かないが、まず話しかけてみることにした。あわよくば、よろしくない方向から意識を背けてくれないかと期待しながら恐る恐る声をかける。
「そんなところにいたら、危ないですよー……? ほら、ここって結構深いですし……」
我ながらなんとも情けない。危なくて深いからここを選んでいるんだろう、と心の中で自分に突っ込んだけれどももう遅かった。十数メートルほど離れたその影は俺の声が届いているのかいないのか動く様子は無い。反応が無いことに若干傷ついたけれど、それでもまだ飛び降りる気配が無いことに安堵する。
「何があったかはわかりませんし、俺あなたのこと何もわかりませんけど……ええと、あんまり思い詰めない方が……その……」
未だ何も返してくれない人影に心が折れそうだ。せめて誰か他の人が通りがかってくれたら、とは思うもののその希望は敵いそうに無い。先程のトラックを最後に車すら通らず、夜行性の鳥ポケモンの羽音が虚しく響く。
もう見なかったことにして通り過ぎてしまいたかったが、明日の朝に『跳ね橋で飛び降り自殺』などというニュースを見るのは気分が悪い。仕方が無いのでもう少し粘ることにして、ちょっと近づいてみることにした。刺激しないように、少しずつ、少しずつと自分に言い聞かせる。
「ほら、そう人生悪いことばっかりじゃ無いと思いますし……ね? あの、だから、……ええっと……そんなことはしない方がいいと思うっていうか……」
語彙力の乏しい俺の口からは碌な言葉が出てこない。相変わらず返事は無いし気の利いたことは言えないしで、俺は飲み会を早退したことを後悔した。こんなことならば徹夜コースであの場に残っていれば良かったのだ、何が一限だ、無駄に意識を高くした俺の馬鹿野郎。
内心で泣き言を漏らしつつ、俺は拙い言葉を続ける。次第にはっきりしてきた人影は闇に同化した紺色で、でもところどころは黄色と白でぼんやり光っている。思っていたよりも大きい、若い人だろうか。ならば尚更止めないと、と気持ちが焦る。
「だから、そんな早く決めちゃわないで……もし何か嫌なことがあっても、その……自分の好きな道を選ぶのもありかな、って……」
もう自分でも何を言っているのかわからない。下手にこんなこと言わない方が良いのでは無いだろうか、と思いつつもどうにか言葉を続けないといたたまれない気分だった。
「えっと、俺で良ければ、話聞き……ま…………え?」
と、そこまで言ったところで俺は何か違和感を覚えた。俺と人影の距離は、鉄筋を挟んでもう数メートル。もう大分鮮明になったその人影は、紺色の全身をつやつやとした粘膜が覆っている。
「ええと、話……聞き…………話……?」
俺の声が闇に漂っていく。長い首から伸びている頭部の後方では触覚がうねり、そこと背中で白のヒレが揺れていた。ゆっくりと視線を下にずらすとわずかながらその体躯と橋との間には空間がある。しんと静まり返った空気の中で、ばちばちと静電気が弾けるような音がする。ゆっくりとくねらせた全長の半分はありそうなほど長い両腕の先では電流が小さく迸っている。鉄筋越しに見える、ぽっかり空いた大きな口には牙が覗いている。
紺の身体に描かれたいくつかの黄色い斑点が時折薄く輝く。視線を上に戻した俺の目と、その斑点の中でも一際大きい黄色の真ん中にある瞳がばっちり合う。ぎょろりとした赤い目が俺をじっと見つめていて、数秒の沈黙が俺と人影、もとい、
「シビル……ドン…………」
ポケモンに対して必死に語りかけていた俺と、その不審な人間をどう思っているのかふよふよと浮いている一匹のシビルドンを包んだ。
◆
「それじゃあね、杏弥。しばらく会えないと思うけれどメールは送るから」
十五になって半年ほど経った姉がリュックサックのジッパーを閉めて俺に言ったのは、原因不明の大寒波がイッシュの一部を襲った年だった。俺たちが住んでいたヒウンシティもそこまででは無いとは言え、大分寒かったのを今でも覚えている。
「うん」
「『憩いの調べ』の珈琲券、渡しといたわよね。使って」
「うん」
「あんまりパソコンばっかりやるんじゃないわよ」
「わかってるよ」
イッシュでも有数のお嬢様校の中等部を卒業した姉は、母の反対を振り切ってポケモントレーナーとしての旅に出ることにしたのだ。反対を振り切った、と言うよりもほぼ無断で、と言った方が正しいかもしれないけれど。トレーナー免許は小学校でほとんど強制的に取らされたし、トレーナーに対してこの世界は大分寛容だ。親の援助など無くても何とかやっていけるから、と姉は言う。
普通だったら十歳が旅立ちの年齢とされているけれど、姉はまだ遅く無い、出来るだけのことはやってみせると誰にともなく呟いて手元のモンスターボールを撫でた。中に入っているのは以前から姉が仲良くしていたマメパトの進化形、ハトーボーだ。
「あんな小さい子がチャンピオンになっちゃったんだもん。私だって、何もせずにはいられない」
姉が旅立ちを決めた理由の一つは、イッシュポケモンリーグの新チャンピオンの誕生だ。アイリスという名の少女、いや、見ようによってはまだ幼女とも言える彼女は年齢に見合わぬ強さを誇り、ジムリーダーの器だけでは収まらずに頂点まで登り詰めた。
テレビのニュース番組がそれを報じた日、姉の決意は既に固まっていたのだろう。幼いチャンピオンが生まれたこととはまた別に、実際には姉の旅立つもう一つの理由があった。あんたに全部押し付けるみたいで悪いけれど、とバツの悪そうな顔をした姉は「ごめんね」という言葉の後にこう続けた。
「私、もう、母さんの考えに付き合うのは限界なの」
◆
「…………おい、杏弥! 杏弥ったら」
「……あ、悪い」
リベラルアーツだか一般教養だか、何だかよくわからないが俺の通う大学では学部の専門科目以外に基礎的なことを広く学ぶ講義を取らなくてはいけない。シンオウ地方に語り継がれているという神話を説明している文学部教授の声は眠気を誘うにはもってこいの性質で、既に大講義室にいる生徒の三分の二はねむり状態に陥っている。催眠術のプロフェッショナルと言われるスリーパーをもってしても、ここまでの効果は引き出せないのでは無いかと思ってしまうほどに酷い有様だ。
俺自身もまた昨日の飲み会の影響と、それに加えて昨晩に起きた奇妙な出来事のお陰でちっとも眠れなかったこととで思わずうつらうつらしてしまっていた。遠いようで昨日のことみたいにも感じられる、何年前かの夢を見た気がする。この夢は時偶見るけれどもどうしてこのタイミングで、と少し疑問に思ったが頭の奥底にしまいこんだ。小声で話しかけてきた友人へと言葉を返す。
「……で、何の用だ? カクタス……」
「いや、何っていうか。眠そうだったから起こしてやったっていうか? あとハート送ってくれると助かる」
「うーい……」
うとうとしている間に進んでしまった板書を急いで写しながらスマホのゲームアプリを呼び出す。ポケモンの頭部を可愛らしくデフォルメしたものを繋げて消していくこのゲームは全国の学生を中心に流行っており、ハートはゲームが出来る回数を増やすためのものだ。
ホルビーのアニメーションと共にLINEの通知が友人のスマホに現れ、彼は黒い目を細めて「サンキュー」と言った。
「そういや、今日お前夜空いてる? 近くに新しい店出来たらしくてさ、サイユウ料理専門店で料理だけじゃなくって地酒が美味いって……」
いつもの癖で、空いてる、と返そうとした俺の言葉が喉元で止まる。門限などは無い一人暮らし、彼女もいないしポケモンもいない、バイトだって今日は入っていない。特に縛られるものは無いから普段だったら二つ返事で応じるところだ。
だけど今日は事情が違う。黙り込んでしまった俺を、真っ黒な髪を揺らして怪訝そうに見てきた友人からふと目を逸らしてしまうと同時に、昨夜のことが脳裏に浮かんだ。
「…………あ、その、……いや、何でもないんだ。ごめんな、うん。忘れてくれ。それじゃあ、うん」
わからなかったとは言え、シビルドンに対して色々と語ってしまった俺は物凄く決まりが悪くなって、意味の無い言い訳をつらつらと並べながらその場をゆっくりと立ち去ろうとした。いくらシビルドン相手でも流石に恥ずかしい。ぼんやりと酔っていた頭は一気に覚めたけど、入れ替わりで顔の熱は急上昇していた。
「ああ、本当に何でもないから。うん、大丈夫、大丈夫だから」
何が大丈夫なのかはわからないけれど、とりあえず何か言ってないと恥ずかしさで叫びだしてしまいそうだったのだ。シビルドンが俺の言葉を理解しているかは不明だが、今はどうでもいい。引きつり笑いを浮かべつつ、俺はシビルドンからじわじわと距離をとる。
「でもほら、勘違いで良かったよ。飛び込む自殺者はいなかったんだ! なんつって……」
二つの巨大な目玉がこちらに向けられているのが異様に恥ずかしくて、一刻も早くこの場を立ち去りたくて仕方が無い。橋を歩くスピードを少しずつ上げていく。
「まあ、そんなわけだから、俺はこのくらいで……えーと、…………えー……」
もう言うことも見つからず、たまらなくなって走り出そうとして俺はそれをやめた。先程からちょっとずつ距離を置いていたはずなのに、シビルドンは俺の近くにいたままなのだ。それどころか、俺が自殺者と思って話しかけていた時よりも近くにいるように思えて仕方無い。実際、いつの間に入ってきたのか鉄筋を越えたこちら側へとやって来ていて、濡れた鱗が月明かりに照らされててらてらと光っているのがすぐ傍に見えた。
俺は無言で一歩後ずさる。と、シビルドンが一歩分の距離をふよ、と俺へと詰める。
今度は三歩右へとずれる。と、シビルドンは三歩分をふよふよと浮いて移動する。
次に、試しに前へと進んでみる。すると、シビルドンが嬉しそうにうねって俺へと少し近づいた。艷やかに光る鱗がますます近いものとなる。
「あの、えーと…………君……」
さっきとはまた違う意味で気まずくなった俺は、ヒレを風になびかせているシビルドンへと尋ねかける。しかし何と言ってよいのかわからないし、シビルドンから返事があるとも思えない。人っ子一人、チョロネコ一匹通らない橋の上での沈黙、再び。
いつまでも黙っているわけにもいかず、俺は仕方無しに歩き出す。当然のような顔をして、と言っても俺はシビルドンの表情の違いはよくわからないけれども、ともかくシビルドンは俺についてくる。道中、落ちていた羽を拾おうと足を一旦止めるとシビルドンの進みも止まる。俺が再び歩き出すと、シビルドンも動き出す。
「……………………」
振り返ると大きな球状の瞳がしっかり俺に向いているのがわかる。しかしそれを拒絶することはどうにも出来なくて、次の行動を選びかねたまま、俺は橋の終わりが近づいてきたことに気がついた。
そして、シビルドンは結局俺の家まで着いてきてしまったのだ。ポケモンを持っている学生などごまんといるし、下宿先のアパートでポケモンが禁止されているわけでは無いから不都合は特に無い。べトベトンやダストダスのように臭いがきつかったり、マグマッグみたいなアパートが耐えきれないくらいの身体的特徴があったり、ホエルオーなどの巨大なポケモンだと特別な申請が必要らしいけれど、シビルドンならばそれには引っかからないだろう。
昨日少し調べたところ、見た目に反して水タイプでは無く電気タイプのようだし水槽もいらない。そもそも、ごく普通に陸上にいたのだから魚系のポケモンのように常時水に入っていなくても大丈夫なのだろう。餌も市販のポケモンフーズや木の実で良さそうだから、実質的な困り事は特に思いつかなかった。
それに加えて、シビルドンはライモンジムリーダーのカミツレやサブウェイマスターが使っていることもあって有名なポケモンである。と同時に、それだけ強い種類なのだ。ということは誰かの手持ちである確率も高く、邪険に扱うわけにはいかないように思われた。少し様子を見て、ポケモンセンターに届けを出すなりインターネットの掲示板やSNSで持ち主を探すなどして手を打つべきだろう。
だから、とりあえずの手段としてシビルドンをアパートに待たせているというわけだ。浴槽に水を張ってやったら気に入ったみたいで、俺が寝ている間も大人しくしてくれていたから悪さをすることも無さそうだ。
「すまん、今日はちょっと……あんまり具合が良くなくて。風邪っぽいんだよね」
「えっ、そうなの? マジかー、また別の日にすっかー」
「悪いな」
「いやいや、俺は全然大丈夫だけど。お大事にな」
適当に言葉を濁して肩を竦めるポーズをとると、友人は心配そうな顔をした。軽い嘘をついたことに若干の罪悪感が芽生えるけど、先々週あたりに別の講義でレポートを肩代わりしてやったのでチャラにしてもらおう。そんなことを心の中で考える。
「……えー、それでだな、こんな話もあって…昔は人とポケモンが結婚していたことについてなんだが、こういった記述があって……『昔は、人もポケモンも同じだったから普通のこと』と……」
「ポケモンと結婚かー。ま、サーナイトとか綺麗だしなー。でも俺ならムウマージだわ、驚かされたくね?」
教授の説明を聞き、年上好きの友人は適当な口調で言う。神話のように実際に結婚するかどうかは置いておくとして男ならば、というか女でも、誰しも一度は「ポケモンとつき合うならばどのポケモンがいいか」という話で盛り上がることがあると思う。俺自身はあまりよくわからないけれど、サーナイトやミミロップ、イーブイ一派が不動の地位をしめている中、友人のような若干マイナー勢も確かに存在しているらしい。余談だが、先日電車で隣席した男女が「ピジョンと結婚したい」「いやピジョットだよ」「確かにピジョットもいいけどなんか捨てられそうな顔してるじゃん」「私が迎えに行くから」「ヒノヤコマもなかなか」「いいね」などと話していたから鳥系のポケモンもそれなりの人気を誇っているようだ。
しかし、先述の通り俺はそこまで考えてみたことが無い。はいはい、と適当に友人の言葉を流して「え? ムウマージなの? 俺ルージュラ派だわ」と会話に割り込んできた前の席の男に会話を受け継ぐ。すぐさま友人はそいつと口論を始めた。あれはどうもビッチ臭がする、いやそこがいいんだ、それを言うならそっちこそメンヘラ感ある、と徐々に声量がヒートアップしていく。
教授に注意されるのも時間の問題だな、と考えつつ俺はレジュメに目を落とす。書いてあるのは講義の内容、他の神話についての説明。その中の一つにこういうものがある。海や川に生息するポケモンを食べた後、その骨を綺麗にして水へと帰すとまた戻ってくる、と。
そんな文字列が、人とポケモンは同じだったと書かれた隣に並んでいた。
◆
姉が旅立ちの場所に選んだのは遠く離れたホウエン地方だった。「こっちと違ってあそこは温暖らしいからね」と言っていたけれど、本当にそれだけとは思えない。意識的にかそれとも無意識か、どちらにせよこの場所から少しでも離れたいと願っていたのだろう。
姉が離れたかった存在。それは、俺たちの母親だ。
俺たちの母親は、大のポケモン嫌いだった。嫌い、という言葉がぴったりでは無いように思えるが、他に合う表現が見つからないのだからそう言っておく。
母には兄が一人いて、幼い母はその兄を大変慕っていたという。母は昔カゴメタウンに住んでいたのだが、そこでは子供がポケモントレーナーとして旅立つ習慣が現代でも他の街より色濃く残っていて、母の兄もまた、十歳の誕生日を迎えると共にトレーナー修行の旅を始めた。
その頃はまだ、母も他の子供と同じようにポケモンと接していた。家の近くでマメパトやヨーテリーを見たら素直にはしゃいだし、近所の人の持っているポケモンを触らせてもらったりもしていた。兄の旅立ちの際には、別れる寂しさと同時に羨ましさを感じてもいた。ポケモンセンターでもらえる初心者向けポケモン、ツタージャを連れて家を後にした兄を、母は手を振って見送った。
母の心境に大きな変化が訪れたのは、それから半年ほど経った日のことだった。母の家に届いた一つの電話、シッポウシティのポケモンセンターからの連絡。それは、ヤグルマの森で母の兄がペンドラーに襲われた、というものだった。
◆
日も傾きかけてきた大学構内は生徒やそのポケモン、また一部の野生ポケモンで賑わっている。今から帰る者やサークル活動に向かう者、五限・六限の授業のために今来た者だので混み合っていた。喫煙所では、皮ジャンを羽織った主人の真似をするようにズルッグが枝を口にくわえている。チェックシャツの男子生徒の群れの周りをコイルやレアコイルがふわふわと追いかけ、一歩遅れて追随するジバコイルが異様な存在感を放っている。パステルカラーのスカートをはためかせてすれ違った女子大生の腕にはそれとよく似た色のペロッパフが抱かれていたけれど、あのポケモンは確かべたべたしていたはず。綺麗に巻かれた髪にこびりついたりしないのだろうか。
これから学会でもあるのか、いかにも教授然とした様子の老人とフーディンを横目に門をくぐる。本当ならば今日は俺もサークルがあったけれど休ませてもらうことにした。元々そんなに熱心な方では無いし、大して問題は無いだろう。
いつもならば、大学に近い学生アパートまでまっすぐ帰るか、そうでなくてもせいぜい居酒屋かコンビニに寄るだけの道のり。しかし今日は違う、常日頃とは逆方向にしばらく歩いたところにあるバス停で立ち止まる。老婦人とその荷物を代わりに持っているダーテングの後ろに並んで数分待つと、エンジン音と共にホドモエシティ内循環バスがやってきた。
プリペイドカードが認証されたのを確認してから後ろの方の席に着く。前に座っているおさげ髪、小学生くらいの真面目そうな女の子はこれから塾だろうか、まだ十歳にはなっていなそうだから隣で大人しくしているブルーはさしずめ親が着いて行かせたお目付け役だろう。進化系のグランブルならまだしも、小さい妖精ポケモンが不審者を追い払えるかどうかは置いておくとして、自分が彼くらいの年齢だった頃を思い出す。中学受験のため同じように塾へと通っていたけれども、ポケモンをつけられるなんてことは無かった。むしろ、ポケモンに気をつけろと言われていたくらいなのだから。
俺の視線に気がついたか、ブルーがこちらを振り返って唸り声をあげだしたので慌てて目を逸らす。勇敢な性格だと予想されるから、うっかり噛みつかれでもしたらたまらない。
窓の外に顔を向ける。大分日も長くなってきて、五時前でもまだまだ明るい。いい感じに浮かんだ雲と、そこを横切っていくスワンナたちを何となく眺めていると車内アナウンスが響いた。
「ポケモンセンター前ー、ポケモンセンター前ー」
もう着いたのか、と思いながら降車ボタンを押す。ほどなくして止まったバスから出ると、件のブルーが窓ガラス越しからまだ俺のことを見ていた。小学生をカツアゲしそうなタイプには見えないだろうけど、さてはロリコンにでも思われたのだろうか。何とも複雑な気持ちになる。
バス停から目と鼻の先にあるポケモンセンター、そしてその内部に併設されているフレンドリィショップ。フーズにボールに傷薬、技マシンやスプレーに加えて能力アップの各種栄養剤、果ては脱出アイテムまで。ポケモン関連の道具なら大概がここで揃うというから驚きだ。
いらっしゃいませー、という店員の声と共に自動ドアが開く。ポケモンを持っていない身としては馴染みの無い店だけど、店内には平日だというのに結構な人数がいた。
傍らのグライオンと技マシンを吟味しているサラリーマンや、「やっぱ高いよなー」「でもスピーダーならいけんじゃね?」と高価な栄養剤を前に嘆く、二進化系のポケモンをそれぞれ連れた男子高校生の後ろを通り過ぎて目当ての売場へと向かう。本当に色々なものが売っていて圧倒されてしまいそうだ。前に一度友人のつき合いで着いてきただけだから、こういう店の勝手がよくわからない。
しばし迷ってから、やっとポケモンフーズ売場へと辿り着く。と、ここでまたしても俺は悩んでしまった。
何が困るって、ポケモンフーズの種類が多すぎる。タイプ別、年齢別、タマゴグループ別。ここまではわかる。お腹の弱いポケモン向け、産卵前のポケモン向け、ポケルス感染中のポケモン向け。こういうのも、まあ、わかる。
しかしだ。乾燥木の実入り、クラッシュポロック入り、ブロムヘキシン配合、ドライマトマの激辛フーズ、サントアンヌ号御用達、エンジュ老舗の味、ミルタンクおばさんシリーズ、エトセトラ、エトセトラ。こんなに並べ立てられて、きちんと自分のポケモンに合うものを買って帰れるトレーナーが果たしているというのだろうか。俺はそうは思えない、テンガン山のように積まれた箱と缶詰を前に俺は頭を抱えそうになる。この前の春休みに仲間内で遊びにいった、広すぎることで有名なカロス地方のミアレシティでだってこんなには迷わなかったと思う。
「失礼しますー」
「あ、すいません……」
そんな俺を余所に、後ろから若い女性が手を伸ばす。ひょいひょい、といくつかのフーズが籠の中に入れられていくが、そのどれもがバラバラだ。絶対迷うだろこれ、という俺の予想は早くも打ち砕かれる。呆気にとられている俺を、女性の連れていたブースターが去り際馬鹿にするような目で見上げてきた。
結局、店員さんの力を借りながら乾燥タイプのものと缶詰を一つずつ選ぶこととなった。シビルドンの性格はわからなかったから、どの性格にも好まれるタイプのものである。大きな口をぽっかりと開けたシビルドンはいかにも能天気そうで味のことなど頓着しそうには見えなかったが、人もポケモンも見た目で判断するわけにはいかない。
ちょっとは工夫がある方がおいしいだろうと、色々な木の実が入っているカリカリと「フエン温泉熟成タイプ」という文句がコータスの絵と共に書かれた缶詰を籠に入れる。
「ご飯の他にもおやつがあると喜ばれますよー」と、店員に言われるままにパウンドケーキのような形状に切り分けられたポフィンも手にとってしまう。シンオウ地方から広まった手作りのお菓子だったはずだけれど、これは便利なことに個包装になっている。色々あるんだな、と感心しつつお徳用のものを買ってみることにした。
他にも、コンビニよりも安売りされていたおいしい水のペットボトルを何本かとヒウンアイスの市販バージョンを一箱籠へしまう。一通り辺りを見渡してからレジに向かおうと方向転換すると、ボール売り場の脇の本と何やらキラキラしたものに目を惹かれた。
最近、若い女の子を中心に人気のボールシール。モンスターボールにセットしておくと、ポケモンが出てきた時に華やかで可愛らしい演出が出来るというものだ。ハートや音符、星の形をした色とりどりのシールが所狭しと並んでいる。傍にある本は、どうやらシールのコーディネート法が書かれたものらしい。
コンテストやミュージカルのようにポケモンを飾り立てるだけでなく、モンスターボールまでもを装飾する時代。常に流行を追いかけねばならない女子は大変だな、なんてことを考えて視線を隣にシフトする。赤と白、その他色々なデザインの手のひらサイズに収まる球体。その中の一つに手を伸ばしかけて、誰にアピールするでもなく首を横に振った。何も取らずにレジへと向かう。
ピッ、ピッ、とレジから出る電子音がいくつか鳴った後、店員が「あっ」と口を開いた。なんだろう、と思う間もなく俺の前に紙製の箱が置かれる。
「只今キャンペーン中でして、二千円以上お買い求めいただいたお客様に抽選会を行ってるんですよ。ハズレなしなので是非ー」
「はあ」
ハズレなし、という言葉に若干の期待を抱いて俺は箱の中へ手を突っ込む。一番くじにつきものの、中が見えないようになっている紙片を店員に手渡すと「G賞ですね」と淡々とした答えが返ってきた。Gというアルファベットから考えるにかなり下の方の賞だろうが、現実はそんなものだ。何ももらえないよりはいい。
「少々お待ちください」
レジ下から賞品を探し出すために店員がしゃがむと、その後ろに貼ってあったポスターがよく見えた。初夏のトレーナー応援キャンペーン、というポップな字体の両脇に、新緑を身に纏ったシキジカとメブキジカの絵が踊っている。A賞は豪華栄養剤詰め合わせ、B賞はフレンドリィショップオリジナルデザインのミュージカルグッズ、C賞はポケじゃらし十個セット。結構羽振りが良さそうなキャンペーンだ。
お待たせいたしました、との声と共に店員が身体を起こす。片手で軽く持てる程度の小さい箱、大きさから考えると先程中学生たちが買う買わないで揉めていた、安い方の栄養剤か。どうせならシビルドンが食べられるようなポケモン用お菓子とかならいいんだけど。まあ、G賞にそこまで期待する方がアレだろう。
しかし、その箱に入っているものが何だかわかるなり、俺は思わずたじろいでしまった。
「あの、これ……」
「こちらG賞になります、当店オリジナルデザインのモンスターボールでございます」
「……えっと、あ、……」
「お買い上げ、二六八〇円になります。またのお越しをお待ちしておりまーす」
慌てて言おうとした言葉は言葉にならず、店員はあれよあれよというままにモンスターボールをビニール袋にしまってしまう。俺はそれ以上為す術も無く、仕方無しにそのままポケモンセンターの前でまたバスを待つことにした。
◆
母の兄は重体だった。普通のポケモンだったら事はまだ軽く済んだのかもしれなかったけれど、運の悪いことにペンドラーは毒を持っている。その長い尾で弾き飛ばされたことによる物理的な衝撃だけで無く、首の爪から発せられる猛毒が兄の身体に回ってしまったのだ。
幸い命は助かったものの、母の兄はその猛毒から歩く力を失い、全身を麻痺が一生つきまとうこととなった。気を失う寸前ライブキャスターで非常連絡を取った兄が病院へ搬送された時、兄の手持ちであったはずのジャノビーの姿はそこに無かった。
母がポケモンを毛嫌い、と言うよりかは憎むようになったのはそれからだ。ベッドに横たわり、動けなくなった兄を見て、母は兄をそんな目に遭わせたペンドラーを激しく恨んだ。ペンドラーだけでは無い、兄を助けずどこかへ逃げてしまったジャノビーを、そして、そんな危険で、恐ろしくて、薄情なポケモンを。
そして勿論、母が旅に出ることなど無かったし、母と同じくポケモンを持っていない父と結婚してポケモンとの遭遇が比較的少ないヒウンシティで暮らしてから生まれた俺たちにもポケモントレーナーとしての旅をさせることは無かった。俺と姉がポケモンと接触することを母は少しでも避けさせ、あまりポケモンと関わるなと毎日のように言い聞かせていた。
自分の意見をそれほど持たない性格の俺としては、「まあそんなものか」くらいに母のことを昔からどこか冷静に捉え、何となく言うことを聞いていたのだけど姉はそうでは無かった。旅に出る習慣がほとんど残っていないヒウンでも、トレーナーの免許を取れる程度の教育は学校で施される。野生ポケモンが少なくても、電信柱にはマメパトがとまっているし、路地裏ではヤブクロンやミネズミがゴミを漁っているし、下水道ではベトベターたちが悪臭を放っている。セントラルエリアの広場では猿ポケモンと共にダンサーが踊り、ギタリストがレパルダスと一緒に甘い言葉を歌い、スキンヘッドのいかつい男はワルビルと並んでガンを垂れている。ポケモンジムには毎日のようにトレーナーが訪れている。バトルやミュージカル、他の地方のコンテストの様子はテレビや雑誌などで散々報じられている。
姉とポケモンが触れ合う機会などいくらでもあった。姉は、母にポケモンから引き離されれば離されるほど、ポケモンに惹かれていった。
ポケモンへの興味が膨らんだ姉が中学生になる頃。いつものように、ポケモンを持っている同級生たちと一緒に街の中庭で遊んだ帰り道に、姉は一羽のマメパトが路地裏で倒れているのを見つけた。餌を探している最中に何かにぶつかったか、それとも他のポケモンとバトルになって傷ついたのかは定かでは無かったが、姉は急いでそのマメパトに駆け寄りポケモンセンターへと連れていった。
助けが早かったこともあり、マメパトは元気な姿へと回復した。ジョーイさんにお礼を言い、安心した姉はマメパトを元の場所へと帰そうとしたが、マメパトは姉に懐いてしまったらしく、なかなか離れようとしなかった。「ついてきちゃダメ」と姉が何度も言い聞かせても、マメパトはひょこひょこと身体を揺らしながら姉を追いかけ、振り返った姉をまん丸の目で覗くのだ。
姉は悩んだ。母にきつく言われているから、このマメパトを家に連れ帰るわけにはいかない。しかしこのまま別れるのは悲しいし、自分とここまで仲良くなったポケモンは初めてだ。じっと見上てくるマメパトを前にして、姉は考えを巡らせた。
結果、友達に協力してもらいながら姉は母に内緒でマメパトを育てていた。ご飯をあげたり、ブラッシングしたり、バトルをしてみたり。あんただけに教えてあげる、と深夜にこっそり部屋に呼ばれた俺は灰色の毛玉が姉の布団で寝息を立てているのを見たこともある。
しばらくの間、そうやって姉とマメパトは平和で幸せな日常を過ごしていた。楽しそうな姉を見て俺も悪い気はしなかったし、姉が時々触らせてくれる丸っこいマメパトはかわいかった。母は何も知らず、相変わらずポケモンには近づくなと俺たちに注意していた。
そして、姉が旅立ちを決めた半月前にそれは起こった。なんて事は無い、マメパトの存在が母にバレたのである。いや、「マメパトだった」存在と言った方が正しいだろう。それは、マメパトがハトーボーへと進化してすぐのことだった。
小さくていかにも弱そうなマメパトならばまだ良かったのかもしれない。しかしハトーボーともなると身体もそれなりに大きく、力も強まっている。それに加えて、これは俺の考えすぎかもしれないが、第二進化系という特徴。それはかつて母の兄を見捨てたというジャノビーと同じだ。
俺たちの家がある高層マンションの14階、大通りに面した姉の部屋。塾から電話が来たんだけど、とノックをせずにそこへと入った母は窓にとまったハトーボーに餌をあげている姉と、一羽のポケモンを見つけて激しく怒った。ハトーボーは当然追い出されたし、姉は数日間の外出を禁じられた。それだけでは無い、姉がお小遣いでこつこつ買い集めていたポケモンに関する本、ポケモンをかたどったぬいぐるみ、ポケモンの絵が描かれた文房具、ポケモンを扱う、ジムリーダーであるアーティが描いた絵画……。ポケモンに関するものは、母の手によって全て捨てられた。
閉じられた部屋の中で、姉が何をどう考えていたのかは俺の知るところでは無い。しかし、謹慎期間が終わると共に姉はモンスターボールを一つ、フレンドリィショップで買ってきた。その中には、よほど姉を慕っていたのだろう、母に手酷い仕打ちを受けたにも関わらず電信柱で姉のことをじっと待っていたハトーボーが入っていることなど聞かなくてもわかった。
それからの姉の行動は早かった。学校や役所によるトレーナー支援制度の力を借りて、旅のための準備を始めた。こっそり印鑑まで持ち出して、父の筆跡を懸命に真似て
書類までこしらえていたのを知った時は流石に驚いたが、その時には既に姉はほとんどの支度を終えていたのだ。
そうして、姉は旅立っていった。一切のポケモンが消えた部屋から、ポケモンが溢れる外へと。
◆
階段をいくつか上り、廊下を進んで一番奥の部屋の前に立つ。ポケットから取り出した鍵を扉の穴に突っ込んで軽く回すと、がちゃりという聞き慣れた音が響いた。
「……ただいま」
いつもならば誰も待っていない部屋、帰りの挨拶なんてするわけが無い。ただ、一応今日は客人を待たせている。客人という表現が正しいのかよくわからなかったが、とりあえずそんなことを言ってみた。と、
「うわっ!」
ばたん、と風呂場のドアが勢いよく開き、次いで俺の身体に衝撃が走る。背中に腕を回され、力を込められる感覚。骨が少しばかり嫌な音を立て、両手に持っていたビニール袋を玄関先に落としてしまう。
強盗か、それとも俺に恨みがある殺人犯か。或いは俺の秘められし力に目をつけてどこかへ連れ去ろうとする特殊機関か何かか? そんな馬鹿な考えが頭をよぎるが、それは痛みに続いて感じられた、いくらかの刺激によって打ち消された。
「……おい、お前……」
その刺激は、冬など乾燥している日に金属のドアノブに触った時のものによく似ていた。つまり静電気なのだが、それよりも若干強い。その静電気を俺に向けて放った張本人、俺を力強く抱きしめている電気ウナギへと声を喉から絞り出す。
シビルドンは腕の力で海から這い出し、そしてまたその腕で獲物を海の底まで引きずり込むと情報サイトに書いてあった。なるほどそれだけの力は確かに備わっているようだ。こんな力で捕らえられたら抵抗出来そうにも無い。
しかしここは海では無く俺の家だから引きずり込まれる心配は無いし、そもそも俺は獲物じゃない。長い身体を絡みつかせてくるシビルドンの腹を片足でつつき、どうにか離れさせる。まあちょっと待ってくれ、という意味を込めてぬめりを帯びた表面を自由になった手で軽く叩く。
肺が締め付けられていたせいで少し荒くなった呼吸を整えている俺をきょとんとした顔で見ているシビルドンに、「俺に攻撃しようとしたのか?」と尋ねてみると、シビルドンは口を閉じて身体を揺らした。その様子がまるで「違う」と言っているように見えたから、質問を変えることにする。
「じゃあ……ただいまのつもりだった、とか?」
今度は口が開き、何度か頭部が縦に振られる。心なしか口も半月型になっているように見えた。とりあえず敵意を持たれてはいないらしいことに安堵するも束の間、嬉しそうな様子でシビルドンの腕が伸びてきたので急いで手で制す。
「お前がそうしてくれるのはありがたいんだけど、その……ちょっと苦しかったから、もうちょっと優しくお願い出来るか……? それと」
伝わるかどうかわからないが、割と真剣に頼んでからシビルドンの後ろを指さす。
「あと少し、乾いてから来てくれると嬉しかったな、なんて……」
俺が指さした先をシビルドンが身をくねらせて振り返る。風呂場から玄関までの短い距離は、床から少しばかり浮いているシビルドンから滴り落ちた浴槽の水で濡れていた。同じように、その水を纏っていたシビルドンに抱きつかれた俺の服も大雨に降られた時みたいになっている。
自分のしたことをどうやら理解したようで、シビルドンが俺の方に向き直る。空洞のような口は閉じられ、がっくりと頭垂れた。そこから伸びる長い触覚もしょんぼりしたみたいに床へ垂れ下がっているように見える。
先ほど両腕に帯びていた弱い電流ももう消えてしまった。何とも言えない沈黙に耐えきれず、俺は上げた腕を下ろして玄関に落としたビニール袋を拾い上げる。靴を脱いで部屋に上がり、シビルドンの横を通り過ぎる時に一言だけ告げる。
「でも、……その、出迎えてくれるのは嬉しかったから……怒ってるわけじゃ」
いくら相手がポケモンとは言え、面と向かって言うのが恥ずかしかったから背を向けてしまったわけだがそれは失敗だったようである。俺の言葉に安心したのか、シビルドンはすぐさま身を翻して今度は後ろから抱きつき、しっかり電流もセットで飛びかかってきた。不意打ちの衝撃に驚き、またしても袋を落としてしまった俺はその中から転がり出た品物を広い集めつつ、スキンシップの仕方について言い聞かせる羽目になった。
「NO MASTER」
フレンドリィショップのパーソナルカラーである白と青。その二色をあしらった、爽やかなデザインのモンスターボールは電子音と共にそんな文字列を表示させた。
シビルドンを部屋に待機させ、濡れた服を籠に放り込んでシャワーを浴びてから夕食を準備した。スーパーで特売だったラーメンに、これまた安売りされていた野菜適当に切ったものを乗せる。どう考えても先ほど買ったポケモンフーズの方が遙かに高級品だが、シビルドンがおいしそうに食べているため良いことにした。
胸鰭が発達したと思しき両腕は力が強いだけで無く結構器用らしい。フーズが盛られた皿をうまい具合に持ち上げ、大きな口へと少しずつ入れていく。鋭い牙とその行儀の良さが少しばかりミスマッチだ。
生卵を落としたラーメンをすすりながらシビルドンの食事風景を観察していた俺は、なし崩し的に受け取ってしまったモンスターボールの存在を思い出した。床に転がしておいた袋から取り出し、箱やビニールの包装をはがす。手のひらにフィットする球体は、蛍光灯の白い光を反射してつるりと光ってみせた。
NO MASTER、主人無し。つまり、このシビルドンは野生ということだ。そう言えば、かつてサークルの誰かがシビルドンの進化前であるシビシラスを捕まえに、電気石の洞穴へ行くと言っていた気がする。ここからそう遠く無いから、こいつもそこから来たのだろう。
ちなみに、続いて表示された「FEMALE」によるとこいつはどうやら雌のようだ。全裸で部屋の中を歩き回る癖が無くて良かった、などと思う。ポケモン相手に何を恥ずかしがる必要があるのかは不明だけど、やっぱり多少は思うところがあったりもするのだ。特にタマゴグループ「ひとがた」のポケモンたちには遠慮してしまうと俺は思うのだが、世のトレーナーたちはどうしているのだろう。
「お前、トレーナーはいないんだよな?」
俺の問いかけに、ちょうどフーズを食べ終えたらしいシビルドンがこちらを見る。首を傾げるような動作をしたので「誰かのポケモンだったのか?」と言ってみると、こくりと頷いた。どうやら、センターに届け出をする必要は無さそうだ。
じゃあどうするべきかな、と考えている俺にシビルドンが身を寄せてくる。さてはラーメンを横取りする気か、と用心した俺は素早く椀を抱え込んだがそうでは無かったらしい。
さっきと同じように、しかしさっきよりは随分と弱い力で俺の首に後ろからシビルドンが腕を回してくる。ぬるっとした感触はどことなくプールサイドに落ちている葉っぱ踏んだ時のものを思い出させる。黄身が絡んだ麺をすする俺の首筋から背中、シビルドンが密着しているところに静電気がぴりぴりと走り、それが何やらシビルドンなりのじゃれつきであることに思い至ったのは数分後だった。
この短時間で随分懐かれちゃったな、とぼんやり思う。箸をくわえて空いた片手で頭を少し撫でてやると、頬の黄色い斑点を俺の頬に擦りつけてきた。粘膜が顔にべったりついたが、ティッシュで拭き取るのも何となく申し訳ない。
『……次に、先日ソウリュウシティで行われたドラゴンポケモン限定バトル大会の模様です……』
垂れ流しになっていたテレビのニュース、アナウンサーが話題を切り替える。VTRが現れ、流れ出す歓声にシビルドンが反応してテレビの方に顔を向けた。その隙にさっとティッシュで頬を拭う。
『ルキ、流星群だ!』
青年がテレビの中で高らかに叫ぶ。大会の優勝者らしい彼は俺と同い年くらいか、少し下に見えた。ルキというのは、今大技を決めて相手のカイリューを倒したサザンドラのことだろう。
ポケモンに名前をつけるトレーナーは多い。公式用語ではニックネームと言われているが、実際のところそれ以外の名前でポケモンが呼ばれることなどほとんどと言って良いほど無いだろう。よって、その名前はポケモンの正式な名前とほぼ同義だ。
トレーナーとしてつけた名前なら、ポケモンセンターでの申請によって公的な名前とすることも出来る。だから仮に俺がこのシビルドンをボールで捕まえて何らかの名前をつけたとしたら、シビルドンに揺るがない名を、俺の手で与えることが可能なのだ。
画面では青年の活躍がダイジェストで流れている。それを背景に、片手に握ったままだった球体を瞳に映す。
仮に、俺がこのシビルドンを捕まえたら。
「……ああ、いや。何でも無い」
動きを止めた俺を訝しんだか、テレビの方から視線を戻したシビルドンに首を振る。残りを飲み干すようにして器を空にし、バトルの様子を映し続けていたテレビを消した。
「そろそろ寝るか。明日、俺バイト早番なんだ」
言いながら立ち上がり、軽く頭を撫でてからシビルドンの腕を払う。何か言いたげな、中途半端に開いた口からさりげなく目を逸らした。
シンクへ行きがてら、滅多に開くことの無い引き出しのさらに奥へとボールをしまう。テレビを消してしまったせいで訪れた沈黙、それを破るためというわけでも無かったけれど何とは無しに俺は問いかけた。
「そういえば……お前、どこで寝る?」
◆
姉が家からいなくなり、しばらくの間は大騒ぎだった。警察に連絡すると母は主張したが、トレーナーとしての姉の安否は十分に確認出来たため、それ以上の手は打てない。旅を中断させるとなると、「子供の自由を奪う」という理由で今度は母が責められてしまう可能性すらあるのだ。
結果、毎週一度は映像つきの電話で連絡をとるという父が提案した条件で母は渋々納得した。と同時に、姉をどこか他人のように捉えた節があった。自分の言うことを聞かず、自分が憎むポケモンを選んだ姉。そんな姉はもう、母にとって遠い存在ともなりえたのだろう。
自分で言うのもどうかと思うが、それに引き替え、俺は聞き分けの良い子供だった。ポケモンにさしたる興味も見せず、母の言う通り、必要以上にポケモンに近づくこともしなかった。姉が俺だけに送ってくれる南の地方の景色やそこに住むポケモンには心を踊らせたり、友達の家で見せてもらったバトルの映像やポケモンの漫画を面白く感じたりはしていた。同級生のポケモンを羨ましく思うこともあったし、時々街で見かけるアーティジムリーダーは格好良かった。
けれど、自分がポケモンを持つという気は起きなかった。今までのように、誰かとポケモンを少し離れたところで見るだけだった。これ以上自分の子供に裏切られたら母がかわいそうだという気持ちもあったし、俺まで旅だったらまたしても姉の負担が増えてしまうかもしれないという不安もあった。
それに、母ほどでは無いが父もまたポケモン、というかポケモントレーナーに対してあまり良い印象を持ってはいなかった。基本的には姉の時のように俺たちの自主性を認めてくれるし、「お母さんには内緒だからな」と、ポケモン関連のおもちゃや漫画などを買ってくれたりバトル見学へと連れていってくれたりもした。それでもやはり、言動の隅っこや行動の端々からトレーナーを快く思っていないことが感じられた。
中学二年生の時、ふとした時に父にそれを尋ねたことがある。父は母みたいに自分が何故ポケモンを嫌うのかを話したことは無かったから気になったのだ。
「お前たちに会わせたことは無いが、俺には従兄弟がいてな。トレーナー修行に出たけれどもドロップアウトして、そのまま引きこもりだ。自分のポケモンも放り出して」
そう言った父の顔は陰っていたから、それ以上のことは聞く気になれなかったし、当時はそこまで気にもならなかったため話はそこで終わりになった。少なくとも、父がポケモンを持たない理由、そして俺や姉がトレーナーになることに対して暗に反対していた理由ははっきりわかった。
◆
暑い。
じめっとした空気が肌に纏わりつく不快感で、俺は嫌な感じに目を覚ました。何か夢を見ていたような、そうでも無いような。リゾートデザートでイワパレスに追いかけられる夢だった気もするし、むしむしするセッカの湿原でオタマロに取り囲まれる夢だった気もする。真夏の観覧車、「にげる」の使えない密室で山男と……いや、どうせ碌な夢じゃないだろうからもうやめよう。
とにかく夢見が悪いのは確かで、俺は隣で寝息を立てているシビルドンを見て無意識のうちに安堵する。
こいつがここで寝るようになってから、つまり俺の家にやって来てから早一ヶ月。女の子が若い男の隣で毎晩寝るというのはいかがなものかと最初は思わなくも無かったが、電気ウナギのポケモンを人間の女の子と同等に扱うべきかどうかは俺には判断しかねた。
この一月の間、変わったことは特に無い。大学もサークルもアルバイトも平穏に過ぎ、シビルドンも初日以降は俺の家の廊下をびしょ濡れにすること無く、少し密着しすぎな部分を抜かせば大変利口なポケモンだった。
本当に何も無く、強いて言うなら大分暑くなったとか、友人が欠席しすぎて単位を危うくしているとか、サークルの後輩のビリリダマが室内で爆発して危うく警察沙汰になったとか、バイトの先輩に四天王の一人にして人気作家のシキミのサインを自慢されたとか、その程度だ。サイン会で見た本物は写真よりもずっと胸がでかかったなどとのたまっていたが、シャンデラに焼き尽くされればいいと思う。
本当に何も無かった。
俺がシビルドンを捕まえることも無かったし、名前をつけることも無かった。
ボールをしまった引き出しを、開けることすらしなかった。
ところで、今は俺の隣で熟睡しているシビルドンだが、昨晩少し揉めてしまった。
どこで気に触ったのかは未だ不明だが、いつものように夕飯を食べながらテレビを見ていた時だ。俺はタイムセールで30%引きになっていたコンビニ弁当をつつきながら、歌番組とそれに興味を示しているシビルドンを半々くらいで眺めていたのだ。
アコギを携えた男性ボーカリストが歌い終え、くろいメガネの司会者といくつか言葉を交わす。ライブの日程やニューシングルの宣伝をはさみ、拍手と共に彼が去ると入れ替わりで出てきたのは最近人気沸騰中のアイドルグループだった。
「おっ」
俺の口から思わず声が漏れる。ピカチュウ、パチリス、デデンネ、プラスルとマイナン、エモンガをそれぞれ連れた五人の女の子は、電気ポケモンと一緒にアグレッシブなパフォーマンスをすることで有名だ。大ファンというわけでは無いけれども、こうしてテレビに出ると反応してしまうくらいには彼女たちを魅力的だと思っている。
ちなみに俺の贔屓はデデンネを肩に乗せた緑の子で、彼女もデデンネと同じくメンバー内で一番小柄なのだが……それはどうでもいい。
弁当を食べる手を一旦止めて番組に集中する。リーダーの子がピカチュウを胸に抱いて司会者といくつか会話をする間も客席から歓声が飛んでおり、流石の人気を感じさせた。
それでは、と司会者が話を切り上げて彼女たちをステージに誘導する。この春出た新曲、確か路上で配っているティッシュをもらうと曲がフルで聴けるというサービスがあったものだ。それを含む二、三曲のメドレーらしい。
ステージライトが暗くなる。始まるな、と思って若干身を乗り出した矢先、何故だか画面まで暗くなった。
「!?」
考えられたのは停電だが、今日はすこぶる良い天気で電線が駄目になりそうも無い。ブレーカーが落ちようにも、そこまで電気を使っていたわけでも無い。そもそも消えたのはテレビだけで、蛍光灯はこうこうとしたままだし冷蔵庫もぶうん、と唸っている。
一瞬何事かと思った俺だが、その原因はすぐにわかった。さっきまで俺と一緒にテレビを見ながら缶詰タイプのポケモンフーズを食べていたシビルドンが、いつの間にやらテレビに向かって電流を放ったらしい。シビルドンの全身にはまだ小さな電流が迸っているが、テレビに気をとられていたせいで全く気がつかなかった。
「おい! 何してくれるんだ、壊れるだろ!?」
意識しないうちに、怒った声が俺の口から出る。慌ててリモコンを操作するが映像も音声もぷちぷち途切れていて、テレビは明らかに不調を訴えていた。
「何のつもりか知らないが、こんなことしちゃ絶対駄目だからな!?」
数分の間途切れ途切れの状態が続き、無事に元通りになるもその頃には既に曲が終わり、神話上のポケモンであるジガルデを模した決めポーズをした五人と拍手が流れただけだった。見たかったものを見れなかったことよりも、思いもよらない悪戯をされたことへの怒りがつのる。
画面の中の電気ポケモンを攻撃したかったのか、それともただの好奇心か。思い当たる理由はその程度だったけど、何にしても今後またこういうことをされたら困りものだ。俺はシビルドンにきつく言い含めようと説教したが、シビルドンは何度言ってもつん、とそっぽを向いたままだった。
「あのなあ、わかってるのか? お前……」
何を言っても、歌番組が終わっても、シビルドンは機嫌を直してくれなかった。部屋の隅を陣取り、蜷局を巻くようにして精神的ひかりのかべを張りやがったシビルドンは結局寝るまでその様子だったのである。まったく、機嫌を損ねたいのは俺の方だというのに。
しかし、彼女がいつものように抱きついてきたり静電気を放ってくることなく朝を迎えることになった俺は、心の中で違和感のようなものを覚えていた。一ヶ月も同居したとなると、やはり慣れというか習慣のようになっているのだろうか。昨日の帰宅時にやられた包容と放電が、実際よりも昔のもののように感じられる。
「……あ、起きたか?」
昨晩の回想をしつつ、そんなことを考えていたら隣で眠っていたシビルドンが身じろぎした。一人用のベッドで一緒に寝るのは狭くないかと心配したのだが、このポケモンは細長かったため問題は無かった。腕の脇にあった鰭に手を伸ばす。
が、俺の手を振り払うようにして彼女が身体をくねらした。どう考えても避けられている、そのことに軽く衝撃を受ける。これはまだ怒っているのだろうか、たぶん、いや、絶対そうだ。
「あのな、別にお前が嫌いなわけじゃなくって……ああいうことされたら、単純に困るだけなんだけど……」
昨日も言ったことを繰り返すが、シビルドンは聞く耳を持たない。耳がどこだかわからないけれど、明らかに聞こえているはずなのに。
俺に背鰭を向け、狸寝入りをしている彼女に思わず溜息をつく。このまま機嫌を損ねたままだと、もしかしたら出て行ってしまうのでは無いだろうか、そんな考えが頭をよぎる。同時に視界に入ってきたのはモンスターボールを閉まった引き出し。
あれを開けて、中のボールを使ったら、なんて発想が脳裏に浮かんだ。
俺はベッドから立ち上がる。はだけた布団を彼女にかけ直してやると群青の身体がぴくりと動いたが気づかない振りをした。
窓のカーテンを開けると驚くほどに良い天気で、青く広がった雲一つ無い空をマメパトたちが横切っていった。見下ろした道路を、自転車に乗った男性やランニング中の若者が通り過ぎる。近くの民家の車庫で家族が出かける支度をしていた。ミュージカルだー、とはしゃぐ小さな姉妹と一緒になって二匹のミネズミがその足下で跳ね回る。
絶好のお出かけ日よりの日曜日。壁の時計が指している時刻は、まだ九時を回っていなかった。
もう一度、例の引き出しに視線をずらす。視界の端にいるのはそっぽを向いたままのシビルドン。
「…………あのさ、」
あの家族の準備が済んだのか、窓の外からエンジン音が聞こえてくる。隣の部屋では住人がヤンチャムに叩き起こされているらしく、ヤンチャムの鳴き声よりもうるさく隣人の「あと五分!」という悲痛な叫びが響いてきた。どすんどすん、と騒がしい物音までする。
引き出しまでの距離はほんの数メートルだったが、そこに行ってボールを取り出す代わりに、俺は彼女に提案をしてみた。
「あのさ、どこかに遊びにいってみないか?」
「おい、そんな焦るな! 人にぶつか……あ、すいません……、ちょっと待てって!」
とぼけた顔に反して意外と素早く移動するシビルドンを必死に追いかけ、俺は人混みを急ぐ。誰かとの衝突を注意したのは良いけれど、実際ぶつかったのはひょいひょいと器用に人の間をすり抜けていくシビルドンでは無く俺の方だった。
損ねた機嫌はどこへやら、実に楽しそうに繁華街を行く彼女は少し人波が落ち着いた空間で止まってから振り返り、「早く早く」と言わんばかりに片手を動かす。その様子に嘆息しかけた息を吸い直し、先ほどよりもスピードを上げて青の長身の元へと向かう。走る俺に、近くを歩く婦人の連れたパンプジンが迷惑そうに目を細めた。
「PWT行きバスはこちらになりまーす! お乗りになるお客様はお急ぎくださいー! PWT行きバス、十二時の便、まもなく発車しまーす!」
案内人の声に続いて、彼の頭にとまったコアルヒーがくわくわっ、と鳴き声をあげる。海岸をイメージしたらしいガイドの制服の胸元にはコアルヒーのシルエットがあるから、あれは業務用のポケモンだろうか。
俺の住むアパートや大学がある地区はそうでも無かったのに、観光ホテルが連なる港側はやはり人が多い。日曜日ということもあり、遊びにきた人や店の客引きでライモンシティに負けずとも劣らない混み具合だ。PWTへと向かうバスは、ギラギラと目を光らせたトレーナーがひしめき合っていて溢れだしそうなほどだ。
やっとシビルドンに追いつき、待ちくたびれたとばかりにうねる身体の隣に並ぶ。普段は大学とアパート、バイト先周りで生活が解決するし、サークルの何かがあるとなると同じ街で賑わっているこのエリアよりもライモンへと足を運ぶから、こちらへ来るのは久しぶりだ。少人数講義で知り合った奴らと来た時のことを思い出すが、ずいぶんと店が変わっている。
CD屋やレパルダスのシルエットをロゴに据えたスポーツショップ、ボーマンダとフライゴンが目印のホウエン発メンズファッション店。所狭しと建っている店々に心が揺れるが、今日の目的地はここでは無い。ホミカちゃんの歌が爆音で流れるパンク系のアパレルショップを横目にしばらく進むと、アーケード街の入り口が見えてきた。
ホドモエマーケット。PWTにも負けないくらいの集客数を誇る、ホドモエ自慢のスポットだ。観光客だけでなく、俺みたいなホドモエの住民も多数遊びに来てる。
「なあ」
この街のジムリーダーで中心的存在、ヤーコンのパートナーであるドリュウズが描かれた看板を見上げ、感心したような顔のシビルドンに話しかける。牙ののぞく口許は出かけると告げた時から緩んでいるように見え、それに少し苦笑してしまった。考えてみれば、彼女が俺の所に来てからこうして外へ連れ出すのは初めてのことである。この喜びようも無理は無いだろう。
「先に昼飯にしないか? 朝あまり食べれなかったし、俺、腹減って……」
同意を求めるようにしてシビルドンの顔をのぞき込む。抗議の色は見えなかったので俺は大きな屋根の中へと一歩を踏み出すが、どうやら見慣れぬ土地に後込みしているらしいシビルドンは今になって緊張したように動けないでいた。出した足をひっこめ、彼女の横に戻る。
「大丈夫だって、ポケモンもいっぱいいるんだし」
言いながら、片手を彼女の手へと差し伸べる。一瞬の間を置いた後、俺の手のひらに、俺よりも大きいそれが重なった。爪が掠り、小さな痛みが走ったけれども気にしないことにして冷たい手を握る。
もうシビルドンは安心したらしく、相変わらず浮かれた調子でふよふよと進み出した。久しぶりにも思える静電気の感覚が繋いだ手から伝わってきて、俺まで楽しくなってくる。
こうして、ポケモンと一緒にどこかへ出かけるなんて思ってもいなかった。
シママとポニータと共に俺たちの側を駆け抜いていった少年を見て、ふとそんなことを考えた。
ジュゴンのマークのコーヒーショップを出て、改めて辺りを見渡す。ホドモエマーケットはポケモンと人間、どちらも楽しめる作りになっているためポケモン同伴で入れる店がほとんどで、みんなポケモンをボールから出したまま買い物をしていた。俺にとってはそれが助かることこの上ない。
「まあ、だからここに来たんだけどな」
そう一人ごちた俺を急かすようにして、シビルドンは繋いだ手を引っ張る。俺の分と彼女の分、コーヒーショップで支払いをする時も手を放してくれなくて「なつき度高いですねえ」と、緑色のエプロンをかけた優男の店員に感心半分、からかい半分の口調で言われた時には顔が熱くなった。
流石に食べる時は離れてくれたけれど、店を出るなり片手を出して催促してきたので繋がざるをえなかった。
「適当に回ってみるか、なんかいいものあるかもしれないし」
手作りのダルマッカ達磨を売っているお土産屋や、クマシュンを連れた親父が氷をその場で砕いてくれるかき氷屋。ココロモリをお供におばあさんが怪しげな水晶玉を覗きこんでいる占いは恋愛運を見てくれるらしい。
時折ばちばちと身を光らせるシビルドンは少しばかり周りの目をひいたけれど、攻撃する気が無いためそこまで困らなかった。一度だけ、すれ違ったカップルがペアルックの如く連れていた二匹のプルリルにうっかりあたってしまい、水色とピンクの触手をビリビリさせてしまった時には急いで謝ったけれども。
ともかく、片手に弱い痺れを感じながら俺とシビルドンはマーケットを進む。エリートトレーナーをゲストに呼んだメラルバ品評会をやっていたり、ご当地アイドルがギアルに囲まれて路上ライブを行っていたりと店以外も賑やかだ。道中、等身大のバチュル饅頭を一つ買って半分を自分の口に、もう半分をシビルドンの口に入れてやる。黄身餡の甘みが広がって、俺と彼女は顔を見合わせて笑った。
「あれ、もしかして春岡くん?」
そんな言葉を背中に受けたのは、漢方薬の専門店を冷やかしている最中だった。臭いからして不味そうな漢方がひしめきあう店先は異臭が酷く、そしてそれを誤魔化すために店主が連れてきたのであろうフレフワンが対抗すうようにして香りを放っているが、相乗効果で余計悲劇的になっていることは言うまでも無い。
その声に振り返ると、そこにはモルフォンを肩に乗せた美女が立っていた。綺麗な金髪を一つに結い、白いスカートをふんわりと揺らしたこの女性に見覚えがあって俺は少しの間思案する。やがていくつかの記憶と共に、一つの名前に行き当たった。
「……マートルさん! えっと、買い物?」
「そうそう! うわー、なんか久しぶりだね」
色素の薄い肌が、スケルトンの屋根から漏れる太陽光でさらに白く見える。マートルさんは一年生の頃、グループワークで一緒の班になった学部の知り合いだが最近会っていなかったのだ。その名の元になった花と同じく、可憐でおじょうさま然とした美人だけれども、モルフォンやアイアント、アギルダーといった虫ポケモン好きというギャップで軽く有名人である。
「よく俺だとわかったな」と感嘆を漏らすと、「さっき呟いてたから。『バチュルなう』って」とタイムラインを見せてきた。いくつかのツイートに混じり、俺の撮った饅頭の写真が表示されている。なるほど。
「元気だった?」
「まあまあ、かな。あ、ジムリーダー論とってる?」
「とってるけどやばい。毎回小レポート書かされるし、出席厳しいしさ。もう落単確定もぞろぞろいる」
「うわー、そうなんだ。とらなくって良かった。でも、どうせ春岡くん大丈夫なんでしょ?」
「そんなこと無いって。あ、キャリアモデル特講Dってマートルさんとってるんだっけ」
「うん、あれテスト難しそうだよね。今度知り合い集めて勉強しよう?」
「そうだな、カクタスにも声かけるか……」
「そろそろゼミ一次募集締め切りだけど決めた?」
「うーん、まだ悩み中、早く決めないと」
同じ学部ということもあって話が弾む。退屈したのか、モルフォンは近くの電気屋に引き寄せられていったが、マートルさんいわく「いつものこと」だから大丈夫らしい。
しばらくゼミについての会話が続いたが、不意に片手が引っ張られる感覚がしてそちらを見る。
「あっ……」
目を向けると、シビルドンが黙って俺を見下ろしていた。そういえばかなり待たせてしまった、口を結んだ彼女に俺はごめん、と言おうとする。しかしその言葉を告げようと息を吸ったところでマートルさんが「へえ」と先を越した。
「そういえば春岡くん、ポケモン持ってたんだ。去年は持ってないって言ってたし、ポケモン関連のツイートも全然無いからてっきりノントレーナーなのかと思ってたよ」
「あ、いや……こいつは」
シビルドンを見てそう言ったマートルさんに、俺は口ごもってしまう。シビルドンは俺のポケモンでは無い。かと言って野生のポケモンだと言うのも微妙な気がして、その場を誤魔化すように俺はもごもごと「まあ」とだけ返す。
「かわいいねー! カミツレさんやクダリさんが使ってるのテレビで見て、いいなって思ってたんだけど、やっぱり実際に見るともっとかわいい!」
一般的に見てシビルドンが「かわいい」部類に入るのかは置いておくとして、マートルさんの基準ではそういうことになるのだろう。青い瞳をきらきらさせてシビルドンに見入っているマートルさんの笑顔に、俺は深く考えるのをやめた。
そんなマートルさんは何か言いたげな、しかし遠慮しているような様子で両手を組んでいる。その仕草に「どうしたの?」と尋ねると、ちょっと言い淀んだ後にマートルさんはもじもじと言った。
「ねえ、ちょっと触ってもいい? そのシビルドンちゃん」
「ああ、もちろん」
そんなことか、と思って俺はすぐに答える。過剰なほどにスキンシップをとってくるシビルドンならば、多分嫌がることも無いだろう。俺の言葉を受け、嬉しそうに笑ったマートルさんが手を伸ばす。
しかし、
「きゃあっ!」
「!? おい、お前っ、……!」
ばちっ、という音、光った空気。小さな悲鳴をあげてマートルさんが手をひっこめる。
「何するんだ、危ないだろ!?」
弱いとは言え、今のは確実に攻撃性を持った電流だった。俺は驚きつつもシビルドンに詰め寄るが、何も悪びれていない様子でつん、とそっぽを向いた。昨晩と重なるその感じに、思わず頭に血が上る。
「あのな、お前昨日からどうしたんだ? どうしてこんなことするんだ!」
つい大きな声を出してしまった俺をシビルドンが睨んでくる。が、言葉は止まらない。
「何のつもりがわからないけど、変な悪戯はやめてくれ!」
そう言った途端、シビルドンの身体が一度震えた。流石に言い過ぎたということに気づくが遅い。通行人が何事かと俺たちの方を見てくる。
彼女が頭を垂れる。うつむいてしまったその角度から、顔を見ることはかなわない。ふらふらと揺れる触覚に、俺は次に発する言葉をさぐる。しかしうまいものが見つからず、小さく震える彼女の身体を走る電流を眺めることしか出来なかった。
「あの、私は大丈夫だから……」
片手を押さえていたマートルさんが言う。そうだ、シビルドンのことばかり考えてはいられない。まずは謝らないといけないのだ。そう思って、俺がマートルさんの方に向き直った途端である。
何かが真っ正面からぶつかる衝撃が身体を駆け巡った。同時に繋いでいた手が振り払われ、俺はバランスを崩して地面に座り込む。
「痛っ……おい! 待っ……、待て!」
その衝撃が頭突きによるものだということに考えが至ったのは、朝も感じた存外早いスピードで、シビルドンが俺の前から逃げていってからだった。透き通った尾鰭が人の中へと消えていく。
「……嘘、だろ…………」
呆然として、俺は立つことすら忘れて頭突きを喰らった頬をぼんやりと押さえる。だってその頬は、擦りつけられこそしても、勢いよくぶつかられるだなんて今までありえなかったのに。
ほっぺすりすりだなんて覚えない癖に、と窘めたのは今頭突きをかましてきたのと同じ彼女なのだ。それなのに、なんで。どうして。
「ごめんね、私、怒らせちゃったみたいで」
「いや、そんな……こっちこそ、手、すいません」
「いいよいいよ、このくらい。それより早く追いかけてあげないと」
申し訳なさそうな顔をして謝ってきたマートルさんに急いで返事をする。が、首を横に振ったマートルさんは俺の腕を引っ張って立たせながらシビルドンが去った方向を指さした。
「せっかく一緒に来てたんだもんね。邪魔した私が悪いんだよ。ちゃんと、あの子と仲直りして」
私もスミレちゃんとショッピング続けるからさ、と笑ったマートルさんは、異変を察して戻ってきたモルフォンを抱き上げた。紫の羽を揺らしたモルフォンまでもが、俺を急かすように大きな目玉を動かす。
しどろもどろになりつつも頷いて、もう一度だけ頭を下げた。そして走りだそうとした俺に、マートルさんは含み笑いをしながら奇妙なことを言ってみせたのだけれど、その真意を聞くことは今すべきことでは無い。だけど、どういう意味だったのだろうか。
「春岡くんも隅に置けないねえ……ね、スミレちゃん?」
ショーウインドウの前で浮遊し、ガラスの中をじっと見つめているシビルドンを見つけたのは三分ほど走った後だった。サークルもやっているし結構運動している方だが、全力疾走ともなると流石に息が切れる。呼吸を整えながら上を見てみると、パールルの殻に寄り添うヤミラミが洒落たタッチで描かれた看板が目に入った。店の雰囲気からして、恐らくアクセサリーショップだろう。
俺には縁の無い、普段ならば気後れするような店だが今は気にしていられない。ショーウインドウを一匹で眺めている彼女を、周囲の人たちが不思議そうな目で遠巻きに眺めている。迷子ポケモンとして連絡される前にどうにかしなくては。
「…………なあ、」
何と言って良いのかわからないので、とりあえず声をかけてみる。しかし俺に気がついた彼女はばち、と牽制するように電流を纏って一歩分の距離を開けた。
「ええと……あの……」
彼女との最初の会話から何も成長していない、貧困すぎる俺のボキャブラリー。言葉にならない言葉を呟きながら彼女に一歩近づくたびに、彼女はその分俺から離れる。ショーケースの前でじりじりと移動するシビルドンとキョドる男を、さっきまでとは別の不思議を覚えている目で通行人が見てきた。
「……これ、気に入ったのか?」
仕方が無いので話題を変えることにする。ガラスの中に目を向けると、そこには綺麗なアクセサリーがいくつも飾ってあった。ドレディアをモチーフとしたブローチや、ハクリューが指に巻き付くようになるリングに施された宝石が日の光に輝く。
しかし彼女が見ているのはそういう人間用では無く、その隣にあるポケモンのためのアクセサリーだろう。ビロード製のリボン、神話の世界に登場するポケモンたちの彫刻入りの王冠。カロスから買い取ったのか、メガストーンをはめ込むための台座も売っている。
「こういうの、好きなんだな」
中でもいっそう彼女の視線を集めている腕輪を見ながらそう呟く。上品な銀の輪の中央できらきらと光る、黄色いジュエルと同じ色の斑点に囲まれた目は俺の方に向いてくれない。
だけど、それ以上シビルドンが俺から離れていくことはなかった。ショーウインドウの中、正確にはアクセサリーの隣に添えられている数字を見て少し思案する。人間のものはとても手が出そうに無いが、こっちなら、まあ。
「ちょっと待ってろ。いいな、待ってるんだぞ。待っててくれ」
よくよく言い聞かせてから、いかにも瀟洒といった感じの扉を開く。きょとんとしつつもその場から動かないでくれている彼女の視線を背中に入った店内は、俺にとっては場違いな内装とこれまた場違いの客層だった。
蛍ポケモンのコンビそっちのけで指輪を吟味しているラブラブカップルや、白い毛並みを整えたニャスパーのためにペンダントを見繕っているマダムの間を肩身を狭くしつつ抜け、レジに急ぐ。スタイリッシュかつ品の良い雰囲気を漂わせたおとなのおねえさんは、いらっしゃいませもそこそこに「彼女さんへのプレゼントですか?」と見当違いなことを言い放ったので慌てて首を振った。違います、と切羽詰まった声を出してしまった俺をラブラブカップルが見てきて、気まずいのといらいらすることこの上無い。
ショーケースの中にあったもので、と説明するとすぐに納得してもらえた。表の中から多分これだろうと見合ったサイズを選び、会計を済ませる。レジ台の下から綺麗な包装紙とリボンが取り出されたので、「大丈夫です」と告げた。
「すぐ渡しますから、その箱のままで……」
店員のおねえさんは一瞬首を傾げかけ、しかし「かしこまりました」と包装の手を止めた。俺に腕輪を手渡しながらふふ、と笑う。
「もしかして……さっきからお外にいるシビルドンさんに、ですか?」
「えっ、……はい、まあ」
その笑みが先程のマートルさんに重なって、俺は再度不思議に思った。マダムまでもが微笑ましいものを見る目で俺に笑いかけてきて、気恥ずかしさで店を出る。
扉を閉め、ショーウインドウの前に彼女がいることを確認して胸を撫で下ろした。そのまま箱を開けかけて、だが、さっきこの手を跳ね退けられたことを思い出して後込みする。彼女の方もそれは同じようで、俺から遠ざかりはしないものの気まずそうに俯き、鰭を風に漂わせた。
相手の出方を探ることしばし、観念した俺から口を開く。
「…………腕、」
どうにかそれだけ言うと、彼女は疑問混じりの目をしながらも片腕を上げてくれた。数歩近づいて、シンプルな小箱から腕輪を取り出す。
恥ずかしいような照れくさいような、今更ながらに自分の気取った行動を客観的に見てしまって彼女と目を合わせることが出来ない。そこに秘めた力よりもずっと細い青の手首に銀の輪をはめて、そこで初めて視線を上にすることが出来た。握り拳ほどの眼球が、驚いたようにぱちぱちと瞬きをする。
「ええと、うん、……似合ってんじゃねえの?」
言いながら自分の手を引っ込めて、しまった、と後悔する。この流れで繋いで、そのまま引っ張ってしまえば良かったのに。彼女は触覚を揺らしてもじもじしているし、何ともいえない空気は振り出しに戻った。
ちらり、と彼女が俺と目を合わす。本当に、こんなのガラじゃないんだけど。
「ほら」
わざと彼女から背を半分向けて、片手を差し伸べた。小箱をポケットに押し込んで、若干小さな声になってしまいながらも言う。
「さっきは悪かった。折角お前と遊びに来たのに……本当ごめん」
でもお前だってもうあんな危ないことすんなよな、と言い加えると、彼女はこくりと頷いた。その様子に思わず笑ってしまってから「ほら」と手を軽く振る。すうっ、と近づき、彼女が俺の手をとった。そこに流れたのはいつもの弱い静電気で、突っぱねるような電流では無い。ぴり、と心地よい感覚が片腕に走る。
全身に安堵が広がり、俺はふとマートルさんにシビルドンが無事見つかったことを報告するべきかと思った。ポケットから携帯を取り出そうと空いている片手を動かし、
「こら、あまりくっつくなって」
やっぱり後でいいか、と思い直して、肩にもたれてきた彼女に仕返しするようにして群青の脇腹に軽くぶつかってやった。
「おい、そんなに強く握るな、爪がささって痛……ん?」
先程と同じように、シビルドンと共に色々な店を冷やかしながらしばらく歩くと人だかりにぶつかった。彼女と顔を見合わせ、一緒になって首を捻る。沢山の人とポケモンが盛り上がっている所へ近づき、その中心へと目を凝らした。
「ベリル、ギガドレイン!」
小さいとは言え立派な森を甲羅に宿したポケモンに、ロングのワンピースを履いた女性が指示している。そういえばここはマーケット内の広場だった、ポケモンバトルが行われているのも当たり前だ。
ベリルという名前らしい、フィールドに立つドダイトスが大きく口を開けた。深く吸った息が緑色に染まっている。あの呼吸に巻き込まれると自身の体力を吸い取られてしまうのだ。
「かわせ、パパイヤ!」
しかし相手のトレーナー、そしてバッフロンの反応は素早かった。蹄が地面を蹴り、砂煙を上げながらフィールドの隅へ滑り込む。
「突っ走れ! アフロブレイクだ!」
勢いをつけたその状態で、バッフロンがドダイトスに踊りかかる。技を出していたため隙が出来たドダイトスは避けることもかなわず、大きな頭部と鋭い角の衝撃をもろに喰らってしまった。得意技を発揮したバッフロンが飛び退き、トレーナーと共に臨戦状態を維持している。
ドダイトスはしばらくぐらぐらと揺れつつも意識を保っていたが、やがてどしん、と轟音を立てて地面に倒れた。女性は歯噛みし、バッフロンと少年トレーナーが喜びを表すように跳ねる。ギャラリーが大きく沸き立った。
「ベリル、お疲れ様……よろしく! オニキス!」
ドダイトスを戻し、女性がダーテングを繰り出す。一層奮い立った様子のバッフロンが先手必勝とばかりに角を構えて駆けだした。さらに白熱する観客の中、前にいた青年が俺たちに気がついて振り返った。
「あれ、今来たとこ?」
「あ、はい。なんか盛り上がってるな、って……」
「いいよね〜、あのバッフロン。僕もさっきバトルしてみたんだけど、すぐ負けちゃって。カゲちゃんはこういうの向いてないからやめとこうって言ったんだけど」
穏和そうなその青年は、カゲボウズを抱いて苦笑した。ぼろぼろのそいつが「何見てんだてめえ」みたいな目で睨んできたので、俺とシビルドンは慌てて目を逸らす。
それに全く気がついていない青年はそのカゲボウズがかわいくてしょうがないらしく、しばらく一人でべらべら喋っていたが、不意に「そういえば」と首を傾げた。
「君のシビルドンも素敵だねえ。バトルには出ないの?」
その言葉に、俺は答えを選びかねる。
バトル。ポケモンを、戦わせるもの。
「えと、俺は……」
シビルドンは俺のポケモンでは無い。だけど、戦わせるくらいなら可能だし、トレーナーじゃ無くたってポケモンセンターは利用出来る。ポケモンバトルが出来ないということは、全然無いのだ。
だけど。俺はシビルドンの方をちらりと見る。してもしなくてもどっちでもいいけど、という風な顔をしたシビルドンは、この成り行きに対してあまり興味を持っていなそうだ。
フィールドでは相変わらず歓声が響いている。ダーテングの葉がバッフロンを切り裂いたようだ、少年の悲痛な声が聞こえた。
悲喜交々と、技と指示が飛び交うポケモンバトル。俺はそれをじっと見つめてから、青年に顔を向ける。
「いえ、今日は見に来てるだけなんで。せっかくのこいつと遊びに来たのに、傷つけちゃったら元も子も無いですから」
「そうなんだ、仲良さそうだもんね。僕も羨ましいなあ、カゲちゃんとそんな風に手、繋げたらいいのに……あっごめん怒らないで、カゲちゃんはそのままで十分かわいいよ!」
笑って頷いた青年はどうやら余計なことを言ったらしく、弱っている割に結構強力そうなシャドーボールをカゲボウズに至近距離でお見舞いされて身悶えた。生命力を削るその技に青ざめだしたのでちょっと心配になったが、顔が嬉しそうだったので良いことにしておく。
それでは、と青年に軽く会釈して俺は広場から歩き出す。漆黒の魔弾攻撃は未だ続いていたが、多分あの人なら大丈夫なんだろう、多分。
ギガインパクト、と少年の声がする。続いて広場中に響きわたったバッフロンの慟哭。とても強い威力を発することが出来る代償として、しばらく動けないほどの衝撃を自身も負うほどの技。相手だけでなく、自分のことさえも傷つける技。
トレーナーは、当たり前のように、そんなことを、命じて、
「…………いや、何でも無いよ」
黙ってしまった俺の腕を、シビルドンがちょい、と引っ張った。取り繕うようにして首を振る。
「ほら、あの店覗いてみないか? 写真展開催中、世界の未発見グループだってさ」
まだ何か引っかかっていそうに俺の目を覗き込んでいるシビルドンの顔からさりげなく視線を外し、俺は繋いだ手半ば強引に引いた。
◆
ポケモンを持たないまま、俺の時は過ぎていった。そこそこ良いところの高校に合格し、部活に勉強に学校行事に、となかなか充実した学校生活を送ったと思う。部活に明け暮れて成績を若干下げつつも、死に物狂いの受験期間を経て、なんとか国立大である帆巴大学に受かることも出来た。ホドモエシティで一人暮らしをすることに対し、母はやはり最初反対していたが、今までの俺から判断して大丈夫だろうと許可してくれた。
どうやらポケモントレーナーとしての才能を秘めていたらしい姉の活躍も嬉しかった。遠く離れた南のことだが、姉の名前や写真がインターネットや新聞、テレビに登場し出した。そしてその回数はどんどん増え、今では雑誌の取材に応じていることもある。もはやケンホロウとなったいつかのマメパトを初めとする、強力なポケモンを繰り出してフィールドを駆け回る姉の姿は輝いていた。
何も困ることなど無かった。
大学は楽しいし、一人暮らしは気楽で良い。姉も元気でやっていて、マメに連絡をくれる。父も母も相変わらず。
俺が悩むことなんか、何も無かったのだ。
ポケモンのことで悩む必要など、どこにも無いのだ。