
このフォームからは投稿できません。
[もどる] [新規投稿] [新規順タイトル表示] [ツリー表示] [新着順記事] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
|
|

|
|
> はじめましてでしょうか? どうも、きとかげと申します。
> 流しそうめん面白かったです。
> うどんがミュウっぽいけれど、主人公がそうと気づいてないところなんか、とっても好みです。
> 田舎の糞っぷりが悲しいくらい伝わってくる導入部も好きです。いや、住んでる方はそんなこと言ってられないんだろうけど……
ありがとうございます。
今年の夏、奇跡的に大都会のポケモンセンターへ行きまして、そこで買った人形のミュウがとても気持ちよかったので、思い出して見に来たらコメントがついていてびっくりしました。
あまりの糞っぷりにもうポケモンGOをやってないので、自分はもう完全にトレーナーでもなんでもない何かになってしまいましたが……
気が向いたらまたミュウの話を書きたいです。
※語り手はガシャガシャと同じ人です。
珍しいポケモンの捕獲。この手の任務をこなしているとハズれを引く事はよくある。例えば近海にゲンシカイオーガが出現した情報を調査してみれば、正体はゲンシカイオーガの姿を模倣したヨワシの群だったり、かつてカントー地方を脅かした規格外のゴースト「ブラックフォッグ」の再来かと思えば、今尚当時のトラウマを引きずる被害者たちの悪夢を再現して暴走したムシャーナだったり、酷いときは人間の言葉を喋るヤドランを発見しので、接触してみれば精巧なコスプレをしたプロの怪獣マニアだったり、ハズレを引く度に情報班の連中をしばき倒してやりたい衝動に駆られるが、どんな眉唾物でも当たりはあるので念のため調査しなければならない。
例えば、こんな捕獲指令が舞い込んできた事もある。
『怪奇アンノーン人の脅威!我々の知らないうちにアンノーンと人間はすり変わっていた!?もしかしたら貴方自身も既に・・・?』そんな見出しのオカルト雑誌を上司から手渡され、調べてこいと言われた時は、ポケモンマフィアから足を洗うか真剣に悩んだ。
本題に入る前に、そもそもアンノーン人とは何なのか解説しよう。あの受け取ったオカルト雑誌の特集記事によると何らかの原因で遺跡を追い出されたアンノーンの群が人間に寄生した状態の事を言うらしい。俺はてっきりビルドアップされた逞しい肉体を黒タイツと単眼の覆面で包み込んだ正体不明のボディアーティスト集団の事かと思ったが違うようだ。
体長0.5mのアンノーンの群がどうやって人に寄生しているかと言えば、ポケモン特有の縮小能力を活用している。寄生する理由は諸説あるようだが、この雑誌一押しの有力説は人間の優れた想像力を求めているとの事らしい。
アンノーンは単体では何も起こらないが、二匹以上並ぶと何かの力が芽生える習性がある。群るアンノーンは自分達の習性を理解しているが、力を最大限に発揮する頭・・・・・・理由や目的・意思・自我に欠ける為、人間を依代にするそうだ。そして依代になった人間「アンノーン人」は全能な神の如き力を思うがままに扱えるようになるらしい。
三文小説みたいなゴシップ記事だと最初は馬鹿にして読んでいたが、情報班が他に寄越した資料の中には、この記事の信憑性を裏付ける事例があった。
かつて美しい高原の町「グリーンフィールド」が何の前触れなく結晶に覆われた怪現象・通称「結晶塔事件」世間一般ではアンノーンの群が暴走して起きた事件として処理されたが、実際は一人の少女が意図せずアンノーンの群を使役して起きた事件である。当時の映像資料を目にして俺はようやく考えを改めた。
しかし、こんな大層な力を持つアンノーン人がどこに潜伏しているのやら皆目見当がつかなかったが、今回に限って情報班の連中はすこぶる有能で、資料の中にはアンノーン人とされる人物の写真と地図がしっかり用意されてあった。
信憑性が高くなるにつれて俺は頭を悩ませた。こんなヤツ等どうやって捕獲できるのやら。当時の俺は幹部候補生で、自由に使える部下なんて組織から支給されるポケモンぐらいしかいない。
まったく下っ端はつらいよ。しかし上司から直々に任された以上体を張って何らかの成果を残さなければならない。俺は足りない知恵を振り絞って、アンノーン人がいるとされる現地に赴いた。
そこは何てことのない地方都市の路地裏だった。結晶で覆い尽くされているとか、異次元の迷宮と化していたりなんかしておらず、とりあえずは一安心である。
ターゲットが潜伏しているのは、黒煉瓦が積み上げられた洋風の建物で、正面には厳かな彫刻が施された両開きの黒い扉が客人を待ちかまえている。
すぐ真上には、青白い不思議な炎を灯すランプと、紫色の看板が飾られており、控え目な文字で【Witch's store】という店名が記されていた。
入り口の両脇にはアーチ型の大窓があり、窓際に取り付けられた一枚板の棚には、無数のジャック・オー・ランタンに紛れて、大小様々な南瓜のお化けのようなポケモン・バケッチャが潜んでおり、目が合うなり、南瓜部分の目を橙色に輝かせる。
ゴシック調の外観は、周囲の建物と比べれば、少しばかり浮いているが、独特の洗練された雰囲気を漂わせていた。
窓を覗き込もうとすると、突然、青白い炎を灯すシャンデリア・・・いざないポケモン・シャンデラが、窓の向こ側からすり抜けてやってきた。
普通のポケモンには真似できないゴーストタイプ特有の悪戯だ。シャンデラは不可視の念動力で店の扉を開けながら、黄色い円らな瞳を、横に細めながら弓の形をつくるように微笑んだ。
何かと思えば、頭に灯る青白い炎を活発に揺らしながら、開けた扉を、ヒョコヒョコ出たり入ったり繰り返しては、こちらの顔色をうかがっている。どうやら、客を呼び込もうとしているようだ。
随分と人懐っこいポケモンが出迎えてきたが油断大敵だ。俺が緊急脱出用のテレポート係りとして連れてきた「脱出王」のフーディンは、鋭い眼光を緩めることなく警戒心を強めている。
こいつとは長い付き合いになるが、幾多の場数を踏んでるだけありヤバイ雰囲気をそれとなく察知できるのだ。いよいよアンノーン人の存在が現実味を帯びてきた気がした。
覚悟を決めて店に入ると、店内は青白い幽玄な光に包み込まれていた。白と黒の市松模様の床が広がり、壁を一面を覆い隠す陳列棚や、展示用テーブルは、アンティークで統一されている。
陳列された商品は、漢方薬やポケモンに持たせるような道具、アクセサリーや指輪・宝石、絵画や陶器・古美術品や古道具、レンガのように分厚い革装本、ポケモン象った異形の仮面など品物を見る限り骨董屋のようだ。
座布団の上に鎮座するドデカい金の玉に、ハクリューの首回りに付いていそうな蒼玉、ドンファンの立派な牙にオドシシの奇妙な角、エアームドの羽根を加工した刀剣、ボスゴドラを丸々加工したような、重厚だが誰も着こなせそうにない甲冑。
何かしらの条約に触れそうな危険な品々の中には生きたポケモンも紛れ込んでおり、灯火が消えて眠りこける蝋燭ポケモン・ヒトモシや、鞘に収められたまま、幾つものベルトで封印された番いの刀剣ポケモン・ニダンギル、鏡の如き光沢を放つ生きた銅鏡・ドーミラー、硝子瓶に閉じ込められた真っ黒なガス状ポケモン・ゴーストは、硝子の壁に四本指を押し当てながら、怨めしそうにこちらを睨みつけている。
一見、落ち着いた雰囲気だが、よく見渡せば奇妙な珍品が隅々まで用意されており、魔女の店と名乗るだけのオカルトな趣味は充実しているようだ。
カウンターは店の奥側にあり、店番らしき少女が椅子に座りながら、接客そっちのけで、何やら物書きに勤しんでいる。アレが今回のターゲットであるアンノーン人らしい。
赤毛を肩まで伸ばし、不健康そうな色白の顔に、玉虫色の不思議な瞳を宿しており、服装はシンプルというか地味で、飾り気のない黒い長袖の服は、いかにもオカルトマニアらしい格好だ。
足音を立てながら近づくと、ようやく気がついた様子で「あらぁ、いらっしゃいませぇ」と、気の抜けた挨拶で歓迎してくれるが、来客にそれ以上の関心を示すことはなく、再び作業に没頭している。
淡いクリーム色の用紙と睨めっこをしながら、七色の羽ペンを細々と動かし、見慣れない文字を書き連ねている。
その文体は、古代文字と酷似した姿のシンボルポケモン・アンノーンそのものだ。
まるで何かに取り憑かれているかのように、好奇の目にさらされていようとも、まるでお構いなしに、彼女はひたすらその奇妙な行為に熱中している。
俺は思わず笑っちゃったよ。千載一遇のチャンスとはこの事だ。俺は油断しきっている完全に無防備な少女に話しかけた。
「なぁ欲しいものがあるんだが、ここにあるかな?」
「うーん・・・欲しいものってなぁに?」
「お前だよ」
少女の七色に輝く瞳に映る俺は、目や鼻を後頭部に押し退けて、顔面丸々大きな穴が空いたかのような大口を開く怪物だ。
豆鉄砲を食らったマメパトのような顔をする少女を、無貌の怪物は俺の体から離れながらあっという間に丸飲みにしてしまったかと思えば、全身を覆い尽くす黒い革製の拘束具に変貌する。
こいつが俺の今回の切札「百面相」のメタモン。本来は人間の体に纏いつく変装専用の改造メタモンだが、使い方次第ではこのように相手を拘束してしまう事も容易にできてしまう対人特化のプロフェッショナルだ。
さらにダメ押しのブースト、ポケモンの力を数倍に引き上げる合成薬物に対PSI能力に対抗するべく悪タイプ特有のエスパー抗体細胞をブレンドした特製の合成薬物が注入されている。並のポケモン程度では百面相の拘束は絶対に解けないだろう。しかし相手は並みでは済まされないイレギュラー。
拘束を難なく解いてしまうのは時間の問題。だからこそ迅速に脱出する。脱出王のテレポート先は組織のポケモンバトル訓練施設。ポケモンの力(レベル)を人為的に操作(フラット化)する空間にアンノーン人を閉じ込めて、じっくり腰を据えて捕獲するのだ。
「脱出王!頼むぞ!!!」
俺の号令を合図に脱出王は俺とターゲットを連れて瞬間移動を行うが、消え去ったのは脱出王だけで二度とこの場に戻ってくる事はなかった。
脱出王はコードネーム通り脱出する事・テレポート能力に特化した改造フーディンだ。どんなにPSI能力が制限された空間だろうと問答無用に脱出してしまうのだが、今回は自慢のテレポート能力を駆使する前に、この場から追放されたらしい。
残された俺にアンノーン人は囁いてきた。
「野蛮なヒトたちね」
刹那、百面相は内側から突き破られた。孔から黒い羽虫のようなものが無数に湧いてで来るかと思えば、目を凝らして見るとそいつはミリサイズの小型アンノーンの群だ。
そして百面相の穴は縦に大きく広がっていき、中からアンノーン人の少女が何事もなかったかのように脱出した。その顔の表面には無数の小型アンノーンが小魚のようにワラワラと泳いでいるようだ。空中を舞う小型アンノーンは彼女の周りで渦を巻くように滞空しており、無数の瞳は一様にギロリと俺を観察している。
「でも面白いわ」
息を飲む俺をよそにアンノーン人は余裕そうな笑みを浮かべてきた。こっちは最悪の気分だと言うのにな。
「貴方たちのこと読みたいな」
読むとは、この段階では意味が丸で分からなかったが、ただで読ませる物は持ち合わせちゃいない。プランA が失敗したなら次はプランBに移行するだけだ。
「ごちゃごちゃ煩いな。俺の指示に従わないなら爆発するぞ・・・!」
俺はコートをめくり上げて、マルマイン仕込みの爆弾ベストをアンノーン人に見せつけた。
ここからは話がどのように組み立てられていったかの記録です。性癖が爆発してますのでご注意を。
ルパパトがヤバヤバのヤバすぎである。特にWレッドの関係性が尊い!
↓
お、今年もポケストやるのか、なになに三題は……マスク!?マスカレイドマスク!快盗!いやWレッドいけるやん!!!!よっしゃそんな感じに書いたろ。神経衰弱はあれだな、コバケンさんの「神経衰弱……そんなでもないだろ!」からの「ドミノ並べ大変そう、神経衰弱だ」でいこう。波音……よし、サザナミタウンだ。
↓
片や軽薄でしなやかでえっちな、マスカレイドマスクした青年。おにーさんって呼ばせたいな。もう片方は真面目堅物生真面目男性。ふしだらって言わせたろ。対比がっつり入れたろ。えっちな非日常感出したいから真夜中。今年の夏は熱すぎたから真夜中に活動してたし、この空気感入れよう。
↓
感想貰えるんだから今年はしっかり書くぞ。文字数に収まるように情報は絞ろう。こいつら名付けなくていいな。青年の過去も、そんなに文字数割かなくてもいいように。
↓
Wレッドは戦闘スタイルも真逆、そこを入れたい。バトル描写不慣れだけどチャレンジチャレンジ。メインはバトルじゃなくてバトルを通して干渉し合うふたりのこころだし。
↓
つまり手持ちポケモンも真逆。おにーさんは真面目だからニックネームつけてないけど、青年はつけるやろ。アデューって言わせたいし、マスカレイドマスクやし、フランス語統一したろ。いやここイッシュ!まあ親がカロス人てことで。タイトルもフランス語、マスクネームもおフランスかぶれで。
↓
神経衰弱のくだりは閑話休題的に。同僚のイメージは世紀末デイズの緑くんだ。しかしコバケンさんのあれだとテンポ悪いな。うーん。やっぱり神経衰弱させよう。いや(おそらくは)狭い事務所でなんで神経衰弱だ。ババ抜きにしろ。あ、それ入れよう。うーん、なんかしっくりこない。あ、神経衰弱したからババ抜き(謎フレーズ降臨)。これでいいや。ギャグな昼はえっちな夜との対比に使おう。メリハリついた。
↓
しかしおにーさんこいつ何者だ?このバトル描写、指示を省いたり阿吽の呼吸だったりで強者同士でないと成立しないもんなー……イッシュのバトル関連施設……サブウェイ!よし決まり、神経衰弱のくだりに伏線仕込んどこ。
↓
まっすぐな言葉はガツンと響く。青年にガツンとぶつけよう。しかし深くは踏み込まず、尊重する。そんな姿勢も素敵で、だから青年は話してくれる。尊い。月も隠して、ふたりだけの秘密にしよう。本心は止めてほしくない、でも他人がどうこう言えない。だから血が滲むほど拳握っちゃう。青年もこれすごい衝撃だろうな、泣いちゃうのを我慢しちゃう。尊い……。多分この会話がなかったらバトルやめてた。
↓
おにーさんのまっすぐなだけじゃないバトルスタイルが!青年の心に火をつけ!!!!崩れ落ちて震えるほどゾクゾクさせちゃうんだ!!!!ここはえっちさマシマシにしよう。うへへへへ。エンニュート使ってほしいなあ。
↓
再会は当初は街中ですれ違うくらいの予定だったけど、これはもう思い切りバトルさせたげたいな。神経衰弱のくだりで同僚出してたからここの流れスムーズ。
↓
(投稿後)アデューで終わるんだから始まりはボンソワールだろ、編集編集。
↓
Wレッドをポケモン世界に落とし込んだ話になったな。おかげで書きやすかったし。しかしWレッドはほんとにしんどいし、尊い……(ルパパト沼に戻る)
Q.結局何が書きたかったのか?
A.この関係性尊いよね!!!!!
月と、星と、静かな波に、思考が研ぎ澄まされていく。
サザナミタウン。短い休暇を過ごす地に、ここを選んだのは正解だった。
涼しい潮風に身を委ね、波音に耳をすませる。
「bonsoir――おにーさん」
「うおっ」
余りの静けさに微睡みかけていた所に、不意に声が聞こえて肩が戦慄いた。
波打ち際に立ち、此方を覗き込んでいたのは軽薄な雰囲気を纏う青年。アロハシャツを着ている所は昼間見かける観光客と変わらないが、大きく違うのは――目元を覆う蒼のマスカレイドマスク。
「こんな時間にひとりでなにしてんの」
「人の勝手だろう」
「暇なら俺といいことしない?」
「……生憎だが俺はそのようなふしだらな誘いは」
「ちーがうってー。てかふしだらって。ウケる」
青年はけらけらと笑う。いきなり現れて何なんだ、失礼な奴だ。
「おにーさんトレーナーなんでしょ」
ひとしきり笑った青年は、俺の腰のモンスターボールを指差す。
「ね、俺とバトルしてよ」
複雑な蒼の紋様の向こうに、にやりと細められる瞳が見えた。
なんだかよく分からんが、トレーナーたるもの挑まれた勝負は受けて立つのがマナーだ。例えそれが不審者相手であろうとも。
「1対1でいいか」
「いーよ」
距離を取って向かい合う。真夜中と言えどここは宿泊地からは離れている。多少なら騒がしくしても問題ないだろう。
ボールからバッフロンを繰り出す。蹴る足に砂が舞った。
「リュンヌ、頼むよ」
青年がぽんと投げたボールからは、レパルダスがふわりと現れた。前足を舐めながら、こちらを見ている。
「いつでもどーぞ」
「……ではこちらから、行かせてもらう」
ぶんと腕を振り抜き指示を飛ばすと、バッフロンは走り出す。
「アイアンヘッド!」
飛び込んだ所を、レパルダスは颯爽とかわし姿を消す。否、バッフロンの腹側に潜り込んでいる。
「みだれひっかき」
容赦の無い斬撃。だが鍛えられた体には些細なダメージに過ぎない。
「リベンジ!」
思い切り体をねじり、弾き飛ばす。とっ、と。レパルダスはしなやかに着地した。
「すなかけ!」
その指示と共に砂が舞い上がる。
目眩ましか。的確にフィールドを利用している。だが弱い。バッフロンにアイコンタクトを取り、咆哮で吹き飛ばした先に標的を捉えた。
「そこだ! アフロブレイク!」
レパルダスは怯んで、反応が一瞬遅れた。
――当たる!
そう確信した瞬間、レパルダスが砂浜を蹴った。
空を舞う、月光に冴える紫色。しなやかに体をねじり、堕ちていく。
「つじぎり」
すれ違いざま、的確に急所をつく。
気付いた時には、バッフロンは足を着いていた。
息を飲むほどの美しさだった。
「……勝負、あったね」
「あ、ああ……」
青年はしばらくぼんやりとしていたが、レパルダスをボールに戻すと、こちらを見た。
「ね、おにーさん。また明日、ここで会お」
こちらを見つめる凪いだ瞳を、どこかで見たような気がした。
翌日の昼。耳元でバイブレーションがうるさい。寝ぼけ眼で携帯を見ると、同僚からだった。
「んだよ……」
『おー、お前さ、来年度のダイヤ改正案、あれどこ置いたよ』
「ああ? あー、あれだ、そのヤブクロンのフィギュア乗ってる棚の」
『おっ、ちょっと待ってくれ……よっしゃあ1抜け!』
「……てめえ何してやがる?」
『いやー、今いる奴らでババ抜きしたら盛り上がってよー』
「おい、仕事中だろ」
『硬いこと言うなよー、このクソ暑いのに夏休みのお子様方が毎日毎日挑んできてて、こちとら神経衰弱してんだよ。だからババ抜きをだな』
ぶち。
通話を強制終了し、ついでに電源も切って枕元に投げた。雑談するために電話してきたのかあいつは。せっかくの休暇を邪魔しやがって。というかなんだ、神経衰弱してるからババ抜きって。意味が分からん。
イライラしてきたので、二度寝することにした。
今宵の月は、全てを見透かすように明るい。
妖しい煌めきに照らされ跳ね回るコジョンドは、軽やかにこちらを翻弄する。
「ダンセ、今だ!」
ダブルチョップで的確に弱点をつかんとするコジョンドを、ドラゴンクローで受け止める。
「クリムガン、そのまま押し切れ!」
青と赤の竜はしかと大地を踏み締め、コジョンドを鋭く睨む。ぶつかり合う力は五分五分か。しなやかさだけでは無い、確かな力も備わっている。
「ダンセ、けたぐり!」
「っ、クリムガン!」
しまった。組み合う2体に気を取られていた。
コジョンドのしなやかな蹴りに、足元を掬われる――こちらの読み通りに。
「ふぇっ!?」
青年の喫驚する声が聞こえて、口角を上げる。
視界にはいくつもの、青と赤と、赤と青。
「かげ、ぶんしん……?」
「力押しだけだと思ったか? 昨日のお前の動きは覚えている。これくらいは想定済みだ」
息を吐き、あからさまに挑発してみせる。額に滲んだ汗が流れていくのが分かった。
さあ、お前はどう出る?
「……ふふっ、くふふ……」
呆気に取られていた青年は、やがて妖しく笑いだす。
「ははっ、あはははは……! いいね、いいじゃん、おにーさん!」
爛々と輝く瞳に、炎が灯るのが分かった。
「ダンセ、片っ端からはどうだん!」
青く光るエネルギー弾が分身を消していく。
しかし勢いが余ったのか、砂煙があちこちに立ち上る。
「やばっ……」
コジョンドが相手を見失った。
今がチャンスだ。
雄叫びを上げ、正面からぶつかる。『ばかぢから』だ。
「ダンセ!」
寸前で気付いたコジョンドは受け止める。やはりそう簡単には倒れないか。
「行け!」
腕を思い切り振り抜く。
凄まじい力にコジョンドははね飛ばされ、地に伏した。
俺も、青年も、肩で荒い呼吸をしていた。
「勝負あったな」
「……うん。お疲れ、ダンセ」
青年はコジョンドをボールに戻すと、そのままぺしゃりと崩れ落ちる。
「おい、大丈夫か」
俺もクリムガンを戻してかけよると、青年は自らの腕で体を抱いて震えていた。
「はは……おにーさん、何者……?」
「名乗るほどの者じゃない」
「うそ。だって俺、こんなにぞくぞくしたの久しぶりだもん」
俺を見上げる、ギラギラと輝く瞳。
俺は……この目を、知っている。
翌日の昼。眠りから覚め、寝ぼけ眼でバトルレコーダーを起動する。当時、録画を何度も何度も見返したそれは、数年前のイッシュリーグ決勝戦。
その敗者は、イッシュとカロスのエリートトレーナーの子で、このリーグの後に行方不明になった。
それ自体は特に珍しいことではない。あと一歩で優勝を逃したトレーナーが自暴自棄になり、失踪するのはよくあることだ。
ただ、あいつの、あいつのポケモンの、舞うような戦い方がやけに焼き付いて、しばらく離れなかった。
画面の中で、華麗に舞うポケモンと、真剣な眼差しのトレーナー。勝利を求めギラギラと輝く瞳、敗北を喫した瞬間の酷く凪いだ瞳――間違いない。
月と、星と、静かな波音。砂浜に座り、寄せては返す波を見つめる。
暫く後に聞こえてきたのは、最初の日は気付かなかった微かな足音。
「あれ、いた」
そして、軽やかな声。
「今日は約束してないのに」
「お前と話がしたかった。それに、俺の休暇は今日で終わりだ。明日の朝には帰らねばならん」
「ふーん」
青年は俺の隣に腰を降ろした。
ふたりでしばらく波を眺める。
何度目かの波が引いた時、意を決して口を開いた。
「気付いたんだ。お前の素顔に」
「やっぱり?」
「驚かないのか」
「おにーさん、大分バトルに詳しいみたいだし? だったら知ってるかもなって」
「最初は幽霊かと思ったんだがな」
「あはは、ひどーい」
それきり、会話が途切れる。ざり、と砂をなぞるサンダルが見えた。
「なにもきかないの」
「余計な詮索はしない。話したければ勝手に話すと良い」
ふっと頭上が暗くなる。見上げると、月が雲に隠れていた。
「……俺さあ、あの時、自分の力全部出しきったの。だから、負けたのすごいショックだったんだよね。全力出したから悔いはないなんて、言えない。やっぱり、勝ちたかったもん」
青年はすん、と鼻を鳴らす。
「辛くて、苦しくて、こころがぐちゃぐちゃになって、逃げた。世間から俺のこと隠したくて、親のこれ借りた」
マスカレイドマスクをこつ、とつつく音が聞こえた。
「……そんな物を着けていたら余計に目立つだろう」
「目立つけどさあ、仮面つけた変な男としか思われないでしょ。俺だとばれなきゃ何でもいいし」
最近の若い子の感覚はよく分からない。
「それで、なにもする気が起きないから、ここ数年色んなとこふらふらしてた。ここにきたのもきまぐれなんだよね」
「ならば何故一昨日、俺に声をかけた」
「んー、なんでだろ、よくわかんない。でも一目見て分かったんだよね、この人強いって。そしたらなんか、我慢できなかった」
思ったよりも強かったし。青年は楽しそうに笑いながらそう続けた。
「おにーさんとバトルすんの、すっごい楽しかったよ。俺……もう未練ないや」
ぽつりと呟かれた言葉に、拳を握る。
「俺は、あの日のお前の戦う姿に感動したんだ」
視界の端で青年の動きが止まる。
「俺がお前のことを覚えていたのは、お前の戦いぶりが好ましかったからだ。だからこそ、お前があの日勝てなかったのが悔しかったし、お前が表舞台から姿を消したのは、心底惜しいと思った。ここでお前と出会えて、お前と戦えたのが……嬉しい」
視線を感じる。こちらを見ているのだろう青年は、暫くしてほうと熱い息を吐いた。
「……ははは、熱烈」
掠れた声は、潤みを帯びていた。
「おにーさんてさ、まっすぐだよね。そんな風に言ってもらえるなんて、なんか得した気分」
照れくさそうに笑っていた青年は、やがて決意を固めた様だった。
「……俺も、おにーさんに出会えてよかった!」
振り切るように立ち上がって砂を払う。
「もう行くよ。ありがと、おにーさん。――adieu!」
足早に遠ざかっていく音が聞こえる。
しばらくすると、もう波音しか聞こえない。
月が、残された俺を照らし始める。
握り締めていた拳を開くと、手のひらに血が滲んでいた。
休暇が終わり日常に戻っても、時折あの数日間を思い出す。
バトルをやめるのも、続けるのも、本人の自由だ。外野がうるさく言っていいことではない。
だが、願わくばあいつと、もう一度。
そろそろ夏も終わるのに、じんわりと汗ばむ気候だ。
今日もまた、挑戦者を乗せた電車は走る。
――ライモンシティ、バトルサブウェイ。ここが俺のフィールドだ。
「おい、おい、聞いたかよ!」
同僚が慌ただしい様子で事務所に飛び込んでくる。
「すげー奴が来たんだよ! ノボリさん負かすなんていつ以来だ!?」
「うるさい、興奮し過ぎだ」
「これが騒がずにいられるかよ!? いいから来いって!」
扉も閉めずに飛び出して行く同僚の後を不承不承追う。
構内の人はまばらだ。そろそろ夏休みのお子様方も後回しにしていた宿題に取りかかる頃だろう。
「ほら、あいつあいつ! 次、お前出るだろ?あいつと戦うってことだぞ!」
同僚が指差す先にいた奴を見て、目を見開く。
ボールをぽん、ぽんと投げては受け止める、まだあどけなさが残る青年。
その強い瞳は、もう蒼に隠されてはいない。
心臓の辺りが熱くなる。激しく鼓動しているのが分かった。
「どーすんだよ、流石のお前も負けちまうかもだぞ!」
「俺を誰だと思ってる?」
「いや確かにお前はノボリさんたちも認める連勝ストッパーだけどさあ!」
「分かっているじゃないか」
さあ、決着をつけるとしよう。
久しぶりに楽しいバトルが出来そうだ。
残酷な表現があるかもしれません
これは犯した罪の数々が忍び寄る足音の回顧録。
▼
最近ふと気がつくと妙な耳鳴りがする。
音の正体は分からない。ただ何かが足を立てて遠くから近づいて来ているような錯覚に陥る。
気の知れた同期に話してみると「お前それ憑かれてるよ」とか大真面目な顔で言ってくるのだから笑っちゃうよ。
仕事柄怨みを買うのは馴れている。復讐されるのも覚悟の内・・・・・・なんてカッコつけるつもりはないが、泣く子も黙るポケモンマフィアがクローゼットの中やらベットの下に忍び込んでいるようなオバケにビビってちゃ面子も丸潰れだろう?
しかし、うちの組織は妙に迷信深い連中が集まっており、俺の方がはみ出し者みたいな扱いを受けている。
例えば先月の仕事だ。
ターゲットは×××自然保護区×地点に密かに生息する「虫姫」と呼ばれる全身黒色の特殊変異態のビークイン。こいつの特殊能力を例えるなら「虫タイプ限定の生きたポケモンボックス」だ。
小難しい原理は省くが、要するに虫姫は支配下にある無数の虫ポケモン達を自在に縮小させて胴体の巣に保管する事ができ、戦闘になれば巣の虫ポケモンたちを一斉に解き放つ。解き放たれた虫ポケモンは虫姫に完全に統率されており「攻撃指令」が下れば最後、小さな田舎町くらいなら半日待たずに地図から消してしまえる。地元の伝説によると古から戦が起こり虫姫の聖域が脅かされそうになる度に虫姫が出現し、人間の住処を無差別に蹂躙していた言い伝えが複数残っており、下手すれば一国の軍事力に匹敵する戦闘力を有する規格外の化物である。
たかが虫ポケモンの群だと思うかもしれないが侮っちゃいけない。例えば空から大爆発を覚えたクヌギダマやらフォレトスが夕立のように降り注ぐ光景を想像してみれば、どれだけヤバイなヤツか分かってれるだろう?しかもそいつがポケットの中に収まるモンスターボールで持ち運びできるなら?世界中の軍事国家やテロリストが興味を引く隠密的且つ奇襲性に優れた生物兵器なのだ。
うちの組織は数世代先の未来を往く(自称)スゲー科学の力を駆使して、ついに長年行方を追跡してきたターゲットを補足する事に成功したらしい。俺はそんなヤベーヤツの捕獲或いはDNAサンプルの奪取を特命の任務として任された。お分かりいただけただろうか?うちの組織はブラックを塗り潰した光も届かないダーク組織である。
まぁそれはさておき俺も自殺願望者ではないし、上も俺に勝算があるから任せてくれたのだ。けして無茶振りじゃない。
誰が言ったっか?笑えるB級映画のキャッチコピーだったかな?
「バケモンにはバケモンをぶつければいい」
シンプルでワクワクしてくるゴキゲンな解答である。
俺の切り札は「底無し沼」うちの組織がDNAを弄り回し薬物投与を繰返したとっておきの改造ベトベトンだ。
こいつは重度の肉体改造の末、寿命はモンスターボールから解放後数日しか持たないが、大地を融解しては一体化を繰返し辺りを侵食、一帯の地盤を液状化し、あらゆる物を引きずり込んで吸収してしまう。
一体化した土地は本物の身体の如く変幻自在に操る事ができ、いくら破壊しても再生を繰り返す。こいつを止めるには寿命が尽きるのを待つか、液状化した地の奥底に潜伏する本体を殺さなければならないだろう。虫姫よりこいつの方がヤベーだろうと思うかもしれないが、こいつはあくまで造り物。天然モノのイレギュラーと価値を比べるのはナンセンスだ。
話が脱線してきたからそろそろ本題に入ろうか。俺は部下を引き連れ、虫姫捕獲作戦を実行するべく現地に訪れ「底無し沼」を解放した。広大な自然保護区の中を地道に探索する気は毛頭ない。
底無し沼は最初こそ通常のベトベトンと何ら変わりない大きさと姿をしているが、瞬く間に草原に溶け込み姿を消す。
後は待つだけ。さすがに地盤の液状化は一瞬で済むものではない。数日は安全な場所で待機する必要がある。現場にはジェットパックやらエスパータイプのポケモン・ガスマスク等を支給した数名の部下と監視ドローンを待機させ、自分は数キロ離れた安全地帯にキャンプを張り、監視モニターで現場の様子を確認する。
一日経てば最初に底無し沼を解放した場所に草木は存在しない。ただ薄汚れた黒紫色の沼が一面に広がっている。数日経てば自然保護区の草木は大地に泥濘みいつでも沈んでしまいそうだ。生息していた野性のポケモンは?数日の命を全力で燃やす底無し沼の糧となってくれただろう。
作戦の準備は整った。次は虫姫を誘き寄せる。方法は簡単、底無し沼に暴れるように指示を出せばいい。自分は被害の届かない安全地帯で特殊な電波を流すだけのお仕事だ。
電波を受信した底無し沼は波打つように暴れだし、沼から一本の巨腕が伸びたかと思えば辺りを凪ぎ払い、一帯の木々は底無し沼に完全に飲み込まれようとしていた。
その時、ようやく満を持して木々の陰からヤツが現れた。
事前の情報通り全身真っ黒で赤い瞳をギラギラ輝かせるビークイン。通常の個体よりも体長は大きく4〜5メートルくらいはあるだろう。よくそんな図体で今まで潜伏していたものだ。
今まで静観していた眠れる暴威は、怒りを爆発させるかのように胴体の巣から虫ポケモンの大群を解き放つ。
ターゲットはもちろん黒幕の俺でも空中で待機する部下でもなく、聖域を脅かしたヘドロの怪物。沼から生え出て暴れ狂う巨腕を標的に嵐の如く獰猛な「攻撃指令」が発令される。
胴体の巣から一斉に小蝿のようなものが湧いてきたかと思えば、縮小させていた体を元のサイズに戻す。バタフリーにスピアー・モルフォン・ストライク・レディバ・レディアン・ヤンヤンマ・メガヤンマ・ヘラクロス・アゲハント・ドクケイル・アメモース・テッカニン・バルビート・イルミーゼ・ガーメイル・ビビヨン・クワガノン・アブリー・アブリボン・・・さらには見たことのない奴等まで、大群がまるで一つの生き物と化したかのように一糸乱れぬ動きで突撃する。
しかし、この場に限っては悪手だ。全力を出せるなら突破する事もできたかもしれないが、地上が底無し沼に占拠されている状態では飛行能力を持つ虫ポケモンしか呼び出せない。地の利が「攻撃指令」の威力を半減させている。
案の定ヘドロの巨腕は、突撃してくる虫ポケモンたちを次々と飲み込み、底無し沼に取り込んでいく。
そして新たな獲物を知覚した底無し沼は全貌を顕にする。×地点が丸々超巨大なベトベトンと化した。
底無し沼もいつ死んでもおかしくない状態である。必死に生き長らえようとエネルギー源を求めているのだ。
対する虫姫は大群の攻撃が敵に効果がないとわかるや否や、即座に「攻撃指令」を解除し、虫ポケモンの群を自分の周囲に滞空させて「防御指令」を発動させながら、顕在した底無し沼から逃れようと距離を取ろうとしていた。
人間が語り継ぐ物騒な言い伝えにより誤解されがちだが、こいつの本質は獰猛で規格外の戦闘力ではなく、数多の虫ポケモンを保存しながら使役する特異な生存戦略にある。虫ポケモンたちが共同生活を送る母体が優先する事柄は戦闘や復讐ではなく何よりも生存だ。人間と明確に敵対する選択をしながら今日まで孤独な種を繋ぎ止めてきた秘訣は引き際を見誤らなかったからだろう。
底無し沼は最早天災に等しい怪物と化している。まともに相手をしていては虫ポケモンの共同体は全滅してしまうのは目に見えて分かる事だ。
もっとも生に執着する底無し沼も易々と虫姫たちを逃がそうとしない。虫姫目掛けて沼に沈んだ大量の木々をロケット弾のように発射する。
虫姫を守ろうと群は壁になるが、木々は群に直撃した途端、爆発を巻き起こす。底無し沼は体内で様々な毒素を生成しており、爆発性の科学物質を化合する芸当もできるのだ。しかし、群の壁は予想していたよりもかなりの強度を誇り付け焼き刃の爆発攻撃ではビクともしないようだ。
だが底無し沼は攻撃の手を緩めず、木製ミサイルを乱射し続ける。決して防御指令を発動した群の壁は崩せないが、底無し沼の狙いは別にある。
爆発攻撃を防ぐ度に壁を形成する虫ポケモンの群は、徐々に崩れかけてきた。今まで苛烈な攻撃を難なく耐えてきたのに突然意識を失い墜落し、ドボンドボンと沼の中に沈んでいく。
爆発攻撃は時間稼ぎの為の目眩ましに過ぎない。虫姫が底無し沼の狙いに気がついたのは、辺りに撒き散らされた神経ガスに体を蝕まれ墜落した後の事だろう。
極上の獲物を仕留めた底無し沼は大口を開けて待ち構えていたが、かかさずジェットパックで滞空させていた部下が虫姫を保護する。
墜落する虫姫に向けて投げつけられたのは、どんなポケモンでも必ず捕獲してしまう究極の性能を誇るマスターボール。母体を守る群は崩壊しかけており、生き残りも毒に蝕まれた状態では思うように体を動かせず、虫姫はあっけなく捕まえる事ができた。
獲物を横取りされた底無し沼は怒り狂い、部下たちに攻撃を仕掛けようとするが、迅速にエスパータイプのポケモンにテレポートを使わせて拠点に帰還させた。
現場に残された底無し沼は我を忘れて暴れ狂う。さすがにこのまま放置する訳にもいかないので、暴走電波で最終指令を与える。
底無し沼の体内に含まれる無数の毒素は爆発性の科学物質に化合する事ができるのだ。ポケモンリーグの関係者が異変を察知して現場に到着した頃には、辺り一面は殺風景な爆心地と化しているだろう。
一匹のポケモンを捕獲するのにここまでするのは異常かもしれないが、環境破壊のケアはうちのフロント企業の十八番だから都合がいいらしい。
まったく良くできた酷いマッチポンプだ。うちの「若様」は本当に末恐ろしいお方だよ。
虫姫捕獲に成功したら俺も今頃若様の側近に昇格できたかもしれないが、世の中は中々上手くいかない。
ここまで話が上手すぎるぐらい順調に仕事は進んでいたが、俺は最後の最後で虫姫に出し抜かれた。
俺の部下たちが拠点に帰還してくるや否や、いけ好かない上司にお宝を誇らしげに見せびらかせる間もなく、手中に収まっていたハズのマスターボールは内側から破壊された。
虫姫の巣の中に待機していた全ての虫ポケモンが一丸となり、伝説のポケモンすら沈黙させるマスターボールの絶対的な捕縛力を崩して見せたのだ。どんなに完璧なモンスターボールだろうと収用限度を超えれば壊れてしまうらしい。後は語るには惨すぎる地獄絵図である。
部下たちは体の一部残して全滅した。俺は幸いキャンプの中で待機していたおかげで、逃走する事を主眼とした虫姫の残党から狙われる事はなかった。悪運が強いとはこの事だ。
虫姫本体は胴体の巣が張り裂けた状態で絶命し、置き去りにされていた。神経ガスに侵されていた事もあり体の自由は効かないハズだが、巣の中で待機していた群に指示を出す余力はあったのだろうか、或いは群が母体を見放して暴走したのかはわからない。しかし暴走していたのならば俺はあの場で死んでいた事だろう。
博士や同僚にこの事を話したら、巣の中にいた新たな母体候補に全てを託し、自分を犠牲にして群を無理やりマスターボールの中で解放した可能性もあるらしい。まぁ終わったことだからもうどうでもいい話だがね。
生きたまま捕獲する事は叶わなかったが、虫姫の死骸を持ち帰りDNAサンプルを入手できただけ上出来である。
しかし、気にくわないのがここからだ。若様は虫姫の死骸を標本にでもするかと思ったが、どういうわけか墓まで立てて埋葬し慰霊式を開いたのだ。しかも俺の可愛い部下たちや底無し沼よりも先にだ。
何でも輝かしい未来の礎となるポケモンは手厚く葬るそうだ。俺を含め複数の幹部がそんな茶番に付き合わされたんだぜ?とんだ偽善者倶楽部で笑ってしまいそうになったが、他の幹部連中は大真面目に参加してるから呆れたよ。
同期に気はたしかなのか確認してみたら「こういう事こそ謙虚であらねばならない」とか抜かしやがる。ポケモン殺しの常習犯が奇麗事ばかり並べて何を取り繕うつもりなんだ?
▼
・・・この頃は、そんな風に思っていた。
でも今になっては理解できる。
そう言えば、この耳鳴りはいつ頃から始まったけ?
ガシャガシャ・・・ガシャガシャ・・・
<ご注意>
・この小説には、残酷な行為等の表現が具体的に、多数含まれます
・レーティングとしてはR18Gとなっております
prologue, 1 week ago.
そのアブソルは必死に逃げていた。体は既に傷だらけで満身創痍の状態だった。
走る速度も次第に遅くなっていった。追いつかれるのは時間の問題のように思えた。
アブソルはなんとか自分を鼓舞して逃げ切ろうとした。だが。
(どうせ後一週間か……)
そんなことを言う声が自信の胸から聞こえてきた。
何かを思い出したアブソルは急に気持ちが折れ始める。疲れと痛みに呼応してその場に倒れてしまった。振り向くと見える位置まで追手はもう来ている。彼の命運はここで尽きた。
早く意識を失いたかった。痛くないように殺されたかった。しかしこんなにボロボロであるにも関わらず、意外と意識はちゃんとしている。ここで諦めるのは甘えだ、ということなのだろうか。
諦めるなと言われても、一度体を横にしてしまうと起き上がるのは容易ではない。多大なエネルギーがいるものだ。ポケモンバトルで例えるならばとっくに戦闘不能の状態を越えている彼には、流石にそこまでの力は残されていなかった。
ようやく追手がアブソルの所まで来る。倒れてからここまでの時間は恐ろしい程ゆっくりに感じられた。
彼の命を奪おうとする存在は横たわる彼の体を眺める。
その男の隣には、一匹のポケモンがいる。
「よし、こいつを連れて行け」
眼の前のアブソルが動けない状態であることを確認すると、男はパートナーのポケモンにそう命令した。
大型であるそのポケモンはアブソルを乱暴に掴み自身の肩に乗せた。
男と一匹のポケモンはアブソルを連れたまま村へと戻っていった。
一先ず命は救われたと楽観できる程、アブソルは世間知らずではなかった。
この後自分の身に何が起きるかは分かっている。
村へと連れて行かれた後に自分は殺される。大勢の民衆の前に晒され、罵声を浴びせられながら焼かれるのだろう。自分の悲鳴を聞いた人間共は一斉に歓喜の声を上げるはずだ。
人間達の『恨み』のはけ口に、自分はされるという訳だ。
山を抜け、大川に架けられた橋を渡り、村へと辿り着いた。
その村は長閑な村だった。
建てられている家から少し貧しさは感じられるが、人々はそれなりに活き活きと暮らしていた。村の子どもたちは元気に川遊びをしている。市場に至ってはこれ以上ない賑わいを見せていた。不穏な空気はこれっぽっちも流れていなかった。
アブソルを倒した男が村に戻ってきたとき、住民達はなるべくそっちを見ないようにしていた。
アブソルの予想とは異なり、村の人達人たちが罵声を浴びせてきたり石をこっちへ投げつけてきたりはしなかった。
どちらかと言うと一般住民は「なるべく関わりたくない」という心理が働いているようだった。
「まいったなーここもう一杯かよ」
男は自宅の倉庫を開けながらそう言った。倉庫の中は確かにクワやフィールドカートと言った農作業の道具で詰まっていた。他に、全く使われていない防災頭巾やリュックサックもあった。水を入れたペットボトルも数本置かれていた。
「人目につかない所に置いとかないとなあ。しゃあねえな、少し片付けるか」
男はしぶしぶ汚い倉庫の奥へと入り込んでいこうとしていた。
「おいおい貸してやるよ、俺んちの倉庫」
隣の家からこっちの庭の様子を覗いていた男がいた。その男の横には、小さな女の子がいた。
その女の子とアブソルは目が合っていた。無表情で傷ついたアブソルを見つめながら父親のズボンを叩いていた。
「俺んちの倉庫は空だ。ケモノ一匹ぐらい余裕で入る。その変わり、分け前いくらかくれよ」
「お前なあ、一匹ポケモン捕まえるのどれだけ大変か分かってんのか。アブソルは自分から人を襲わない分まだ楽だけどな」
「いいじゃねぇか。俺はポケモントレーナーじゃねぇし、お前みたいにじゃんじゃん捕まえてお金貰える奴が羨ましい」
「じゃんじゃん捕まえられる訳ないだろ……。まあいいや。明日の朝まで倉庫使わせてくれるんだな。ならいくらか金やるよ。例の場所にアブソル届けた後でな。いいかくれぐれも逃がすなよ」
こうしてアブソルを連れた男は隣人の家の倉庫を使わせてもらうことになった。
逃げ去る等という滑稽な事態が起きぬように、倉庫には鍵をしっかりとかける。更にはアブソルを縄で縛り付ける。
「ほんとに何もねえなこの中。大丈夫か」
広々と空間の空いている場所に新聞紙を何枚かひいてその上についさっき気を失わせておいたアブソルを投げ捨てた。
夜になってアブソルは目を覚ます。まだ自分は生きていることに気がつく。扉の隙間から微かに家内の光が漏れてきており、一応周りの様子は把握できた。ここが倉庫内であることと、自分は頑丈な縄で縛られていることに気がつく。
自分が殺されるのはまた明日という訳か。人間達の会話を聞く限りどこかに届けられてそこで殺されるのだろう。殺すのならさっさと殺して欲しかった。
この倉庫はぱっと見る限りそこまで頑丈そうには見えなかった。辻斬りで穴を開けて出口を作ることも可能はゼロとは言い切れない。自分を縛りつけるこの縄だってやってみれば引きちぎれるかもしれない。
だがそんなことすれば家内にいる人間が何事かと来るだろう。再び気を失うまで痛めつけられるのは怖い。だがうまく行けば逃げられる可能性も、これまたゼロとは言い切れない。
アブソルは相反する二つの気持ちで葛藤していた。
どうせ後一週間で終わってしまうのだから藻掻いても仕方がないという気持ち。一秒でも長く生きられる望みがあるのなら最後まで粘るべきという気持ち。
しかしありとあらゆる所に付けられた傷の痛みによって、除々に前者の方に気が振れていく。
でも、それでもまだ、完全に振れ切れる所までは行っていなかった。
一つだけやりたいことが残っていたから、彼はまだ諦められないでいた。しかし、それが成功する確率は圧倒的に低かった。もし成功したらそれは『革命』と呼んでも差し支えないものだった。
静かな野望の火が酷く傷つけられた体の中に、しかし今もなお燃え尽きた灰とならずに燻っている。
自分は英雄になれるんじゃないかという愚かな自信。人間から幾度となく散々な目に合わされて蓄積された恨み。それらがある限りその火は決して消えることはない。
弱く、けれども確固として未だに燃えるその火は、彼をゆっくりとだが確実に押し上げた。そして、意を決して倉庫をぶち破ろうとしたそのときのことだった。
倉庫の鍵をカチャカチャと開ける音が聞こえた。
扉が開かれて中から出てきたのは、先程見たこの倉庫の持ち主である男とその娘だった。
「随分と傷つけられちゃってまあまあまあ。ひでえことするなあ全く」
男はとぼけたような口調でそんなことを言う。
その言葉にアブソルは反発を覚えていた。いや、お前たち人間が傷つけて捕まえたのだろう。酷いも何もお前たちがやったことだ。
一方で少女の方は何も言わずやはりアブソルとじっと目を合わせていた。
「良かったな。お前助けてやるよ。この子が一アブソルのこと助けたいって言ったんだからな。そんな睨まないで感謝してやれよ」
男はアブソルの縄をほどいてやり、倉庫から出してやった。この行為は明らかにあの隣人への裏切り行為である。分け前を貰えるどころか、損害賠償を請求されてもおかしくはない。
縄をほどかれたアブソルへと少女と近づいていった。そして手に持った草をアブソルの側にそっと置いた。
「これ、秘密基地で見つけたの。食べて」
訝しい表情で見つめながらも、言われた通りアブソルはその草を食べた。見た目は普通の雑草だったが、味がとんでもなく苦かった。アブソルは思わず吐き出しそうになったがなんとか全部食べ終えた。
全部食べ終えたアブソルの体からみるみるうちに傷がなくなっていく。痛みも完全にどこかへ飛んでしまった。
噂で聞いたことはあった。今食べた草は「ふっかつそう」と呼ばれるものだ。とても苦味が強いが食べるだけで瀕死状態からでさえも復活できる。
普段山に暮らしていてもほとんど見かけることのないふっかつそうを、その少女は持っていた。
家の玄関を父親が開けた。家の中の様子が分かった。ぱっと見はごくごく平凡そうな家に見えた。
玄関から見える階段の踏面の一つには、缶ジュースがたくさん入ったダンボールが置かれていた。
「おかえりー」
母親と思わしき女性が、和室からスリッパを履いて出てくる。和室にはタンスが置かれていて、その上には何かが入ったダンボールがあった。
母親はアブソルを見た瞬間それまでにこやかだった表情を急に変える。
「え……? なんで倉庫のアブソル連れ出してんの」
「百合がさ、助けたいって言うから助けたんだ。今日中にでも野生に返しにいくわ」
「……私はいいけど、あなた大丈夫なの。知らないわよ」
「後で土下座しとくよ。とりあえず中入れさせてやってくれ。たぶんこいつめっちゃ疲れてっから」
部屋に入ると一人のおばあさんがいた。おばあさんは映りが悪くなっているテレビを何度もガンガンと叩いている。
「おい、またテレビ映らなくなっちまったよ」
「そのうち良くなるわよ。今は電波悪いから。あんま叩かないで。余計壊れちゃうよ」
おばあさんは諦めてテレビを消してしまった。
部屋の柱には幾つも亀裂が入っていた。家自体ももう古く、大きめの地震でも来たらすぐに倒れてしまいそうな雰囲気だった。冷蔵庫や本棚や食器棚と言った家具は色々あるが、それらは一つとして金具で固定されていたりはしない。冷蔵庫の上にはさっきのタンスと同様に、やはり何が入っているのか分からない箱が置かれていた。
どうやらこの家は四人家族のようだった。家族全員がテーブルの前に座った。テーブルの上には料理が置かれていた。ホエルオーの大和煮と、キノコの炒めものと、味噌汁と、ごはんが、それぞれ一人ずつ分配されていた。
「はい百合、烏龍茶で良いでしょ。お父さんはこっちのコーヒーで」
母親が階段に置いてあった缶ジュースを取ってきて皆に配った。
「どうする、アブソルに何食べさせる?」
「……何もねえな。しゃあない乾パンで良いだろ。そこの、テレビの横に置いてある奴」
「大丈夫これ? ちょっとまって埃が」
母親は袋に付いていた埃をティッシュで拭いてから、乾パンを皿に盛り付けてアブソルに渡した。
「食べる? これも?」
アブソルの眼の前に座っていた女の子はホエルオーの大和煮をアブソルの方に更に半分ほど乗せた。
家族は黙々と食事をしていた。あまりにも静か過ぎたので父親が気まずさを感じてテレビを付けた。さっきと違ってテレビの映りはだいぶ良い。天気予報のアナウンサーがもう夏も終わりであることを伝えている。
女の子は結局おかずが足りなくなって大和煮のたれをごはんにかけて食べていた。その様子を見てアブソルは少し申し訳なく感じたが、お腹が空いていたので彼も黙々と食べていた。
「この後どうする? アブソル野生に返すの」
「そうだな。夜中だったらこのへんは人気ないし、まあ大丈夫だろ。最悪一人、二人に見つかったとしても逃げられるだろうし。川沿い歩いていけば山まで道一本でいけるから、川沿いまでついていってそこから独りで帰ってもらおう」
「私も行く」
「百合は明日学校でしょ。駄目よ、早く寝ないと。授業中眠くなるよ」
「明日は避難訓練やって道徳の授業やって終わりだし大丈夫」
「午前中で終わりなの? だったら、うーん、まあいいか。お父さんと一緒に行ってきなさい」
夜中の十二時に、父親と女の子とアブソルは、川沿いを歩いていた。
「じゃあこの辺までで良いか。じゃあな、気をつけて帰れよ」
村から抜ける所で二人と一匹は別れることにした。
少女は最後もまたアブソルの目をじっと見つめていた。そして一言こう言ったのだ。
「また会おうね」
アブソルはしっかりと頷いてやった。
去っていく二人の後ろ姿を見ながら、アブソルは、
(人間にも良い人がいるんだなあ)
そんなことをうっかり考えてしまっていた。
独りになったアブソルは誰もいない川沿いを静かにかけていく。この村の下流には立派なダムが存在しており、水が滝のごとく落ちる音が彼の足音をかき消してくれた。
突然、彼の角が激しく傷んだ。
思わず蹲る。何かに角を貫かれるような痛みだった。痛みは直ぐに収まったが違和感はいつまでも残っていた。
この種類の痛みは少し前にも受けた覚えがあった。
「この村が……」
九月。季節は秋。ホウエン地方の片隅の、長閑な村。この村で近い将来何かが起こる。
このアブソルの名は『リュート』と言った。リュートはこの村に降り注ぐとある『災い』を予言していた。
ダムは貯水地に溜まった水を一定間隔で規則正しく落下させている。くすんだ緑色が水の表面を覆っていた。
====================================
タイトル:制約のない
作:逆行・まーむる
====================================
1 month ago.
アブソルというポケモンは「天災の元凶」と言われ、人々から恨まれ憎まれ、拷問や虐殺なども定期的にされていた。だが真実は正反対で、アブソルには天災を起こす力はなく、変わりに災いをキャッチする能力が備わっていて、下心のない善意で人々に災いを知らせているだけである。
その事は科学が跋扈し、迷信が駆逐された今となっては社会的常識になっており、中学入試で問題として出されることもある。また、仮に一国の司令塔たる面々が「アブソルのせいで地震が起きた」などと発言しようものなら、不祥事の範疇を遥かに越えた悪言となるだろう。
だがその科学が浸透しきっていないこの時代では、アブソルの真実について知る者はほとんどいなかった。誰かの虚言が伝承となった方を人々は信じていた。
たまに正しい事実を訴える者も居たが、直ぐに集中批判を浴びて沈下させられた。人々にとってアブソルの真実は不都合なものであり、受け入れたくないものだから浸透しなかった。出来ることなら災害は全てアブソルが引き起こしたということにしたかったのだ。
人は理不尽には理由を求める。何かしらの悲劇が発生した場合、どこかに必ず原因がありそれを解決すれば、二度と同じ悲劇は起こらなくなると信じたくなる。
最も原因として抜擢しやすい存在、それこそがアブソルというポケモンだった。
アブソルが予知できる災いは多岐に渡る。
地震や台風と言った自然の力であるものや、火事や工事事故などの人為的な理由によるもの。ただし怪我人が数人出るに留まるような災害はキャッチしない。例えば、地震であれば人死が起きない程度の規模のものはアブソルでも予知できない。
災いが起こる約一ヶ月前から、アブソルの角は激しく痛むようになる。災いをキャッチするアブソルは、群れの中で一匹か二匹のみであることが多い。
当日になるとアブソルはどの場所でどの災害が、いつ起こるのかをはっきりとキャッチする。災害が起こったときの情景が脳内を駆け巡るらしい。
アブソルは直ぐ様その場所まで、一心不乱に駆け出す。辿り着いたらなるべく目立つ所で災いが来るまで吼え続ける。見る人から見たら、狂ったように。
人々はそんなアブソルを見かけたら直ぐに避難を開始する。アブソルは時間に余裕を持って知らせに来るので、人々が逃げ遅れるということは少ないが、老人や怪我人は助からないことも多い。また誰も死ななかったとしても、作物や住宅への損害は防ぐことが出来ない。
そして災いを知らせる役目を全うしたアブソルは、その災いに巻き込まれて死ぬことが多かった。
だが、悲劇はそこで終わらない。
憎しみの感情を抱いた人間は、アブソルの住処へ向かう。あの獣は私達の住処を荒らしたのだから、私達も彼らの住処を荒らしても良いだろう。そんな論理によって行いを正当化しつつ、彼らはアブソルを殺害する。もう二度と災いが起こりませんようにと祈りながら生き物を殺生する。
しかし流石に全滅させるようなことはしなかった。まだ子供のアブソルには災いを齎す力はないと信じ、殺さずに但し拷問はした。そんな事で、今日まで多くのアブソルが犠牲になってきた。
迷信を妄信的に信じる、そして実行力のある人間達の手によって、その時代では一般的なトレーナーでも、アブソルを捕まえてくるだけで報酬が貰える制度が導入されていた。殺さなくても捕まえるだけで良いというのが、自らの手を汚したくない人達にとって都合が良かった。
しかしアブソル達の行動にはある疑問も浮かんでくる。
――災いが起きても知らせに行ったりせず、無視をしていれば良いのではないか。
無視をすることが道徳的に良いか悪いかは関係ない。生死をかけた状況において道徳は意味をなさない。
災いを知らせに行かなければ人間に勘違いされることはない。至極簡単なことのように思える。
だが、実はアブソルは、行きたくなくても行ってしまうのだ。
本人がどんなに拒んだとしても、アブソルという種族には『本能』がある。災いを知らせる者として先祖代々受け継がれた性質によって、本人の意識とは別物の、動物としての反射で動いてしまうのだ。
だからアブソルは自らの死をこれまで避けることが出来ないでいた。
アブソル達は、本当は人間の犠牲になんか絶対になりたくなかった。誰もが人間を憎んでいたし、自分達の愚かな本能もまた憎しみの対象だった。
本日人間に殺されるかと思いきや別の人間達に助けられるという不思議な体験をしたリュートもまた、災いをキャッチしたアブソルのうちの一匹だった。
リュートの母親と父親は、まだ幼い頃に殺されてしまった。
リュートがまだ幼い頃。群れのアブソルの一匹が災いをキャッチした後に山狩りに来た人間達の手によって。
その時はまだ、リュートは自分達アブソルが何故そこまで迫害されるのか知らない幼子だった。逃げるのよと優しく、しかし切羽詰まった声でリュートに話し掛ける母親。お父さんはどこに行くの? と逃げる母親とは正反対の方向に走っていく父親の姿を見て無垢に聞くリュート。
母親が答える前に聞こえたのは、その父親の悲鳴だった。断末魔だった。
逃げるのよ! と母親は再度強く言った。お父さんは! とリュートは叫んだ。母親は、一瞬の躊躇いを見せながらも、言った。人間によって殺されたのよ!
リュートは訳も分からず走った。
必死に、母親の背だけを追って走った。その間、どこをどうやって走ったのか、どれだけ走ったのか、隣に誰が居たのか、何を聞いたのか、どんな感情だったのか、リュートの記憶にはない。
あるのは、空を駆ける鋼の肉体を持つ鳥が、自分と母親を見つけた所からだった。
その硬質な翼が唐突に母親を空から切り裂いた。
母親は悲鳴を上げた。その四肢の至る所に鈍色の翼が突き刺さり、リュートが身を寄せて温かみを感じていたその毛皮が赤に染まった。母親は崩れ落ち、そしてリュートに叫んだ。逃げなさい!
リュートは走り続けて疲れ果てていた。けれども、言った。嫌だ!
リュートは、それを思い返してしまう度に逃げれば良かったと心底後悔した。様々な長物を持った人間がそう時間の経たない内にやってきて、リュートと母親を強引に、そして無慈悲に引き離した。
残虐な嗤いを浮かべた人間達の顔。リュートは幾ら叫ぼうとも、母親が幾ら叫ぼうとも、それはその人間の嗜虐をそそらせるだけだった。
まず、土を耕す目的で作られたそれが、母親の体に勢い良く突き立てられた。耳をつんざく悲鳴が全身を襲った。それをうるさく思った人間の手によって鈍器が頭に叩きつけられた。そのアブソルの特徴である角に当たった。二度、三度、しかしそれは中々に折れず、人間は渋々というように、角度を変えてまた頭を叩いた。今度は頭に当たった。母親の悲鳴は息絶え絶えだった。
内臓が抉られる頃には、母親はもう、静かになっていた。どこも見ていない虚ろな目をしていたのをリュートは今でも克明に覚えている。その顔が潰される瞬間も。そして明らかに死んだ後も、人々は幾許かの間、母親を半ば狂ったかのように憎しみを込めて叩き、潰し、引き裂いていた。肉体的な反応が様々な長物が叩きつけられる度に起こっていた。
そして、母親がもう、生前の姿を全く留めなくなった頃に、その幾多の嗤いを浮かべた沢山の顔は、沢山の目はリュートに向いた。
母親の血で濡れたその長物が、殺さないよう弱めに、しかし確実に痛みを、苦しみを与えるようにリュートの体を、幾度となく襲った。リュートの体は、母親の血で塗れ、その口には、特に血走った人間の手によってその母親の臓物を押し込まれていた。
気を失ったリュートは、そして最後に母親の臓腑の上に放置された。
気付いて、口に入っているものが、自分の身の下に敷かれているものが母親だったものだと気付いて、リュートは狂った。
リュートは、とても両親を愛していた。健全に育ち、深く両親に愛されていた。だからこそ、母親が逃げろと言えども逃げなかった。そして誰よりも凄惨な拷問を受けた。
リュートの人々に対する憎しみは誰よりも深かった。
そんなリュートが災いをキャッチしたときは酷く苦しみ、悔しい感情で一杯になった。自分も人間達に恩恵を与え、その後死ぬことになってしまうのだろうか。そんな事は絶対に嫌だった。
どんなアブソルでも災いをキャッチした場合、圧倒的な恐怖と戦いながら残り一ヶ月を送らないといけなくなる。もうすぐに死んでしまいたいと何度となく思う。どこかへと消えてしまった者もいる。発狂した者がいる。とにかくひどい有様を周囲に見せつける羽目になるのだ。
リュートも例に漏れなかった。悔しくて悲しくて、夜中に思い切り泣いた。人間になんの報復もできないまま両親と同じように死んでいくなんて。
アブソルの平均寿命は百才とポケモンの中でも上位に位置する長さである。
だがただでさえ厳しい自然環境、更には殺害されてしまうこともあって、百才まで無事に生きることができるアブソルは殆ど居ない。
自分が寿命で生を終えられるなんてリュートは全く期待していなかった。ある程度は殺されることを覚悟していたつもりだった。しかし、どうやらつもりだけだったようだ。
死の宣告を実際に受けて見ると、こうも悲しく悔しく、発狂したい気持ちを必死に抑えないといけなくなる。
2 week ago.
災いが訪れるまで後、二週間。リュートが人間に襲われ、そして助けられた日の一週間前。リュートは現実逃避をするべく、山を何の意味もなく虚ろな目で歩き回っていた。適当に歩き回っているだけのアブソルを見て他のポケモン達は訝しがっていた。
そんな時の事だった。
リュートは気付けば森の奥へと来てしまっていた。殆ど来た事の無い場所。引き返す頃にはもう夜になってしまう。貴重な残り僅かな一日を無駄にしてしまったと思いつつも、足は森の更に奥へ奥へと自ずと引っ張られていった。とにかく新しい風景を見続けて現実から目を逸し続けたいと思っていた。
血のように真っ赤な夕焼けが山の斜面を照らす頃、リュートは小さな洞窟を見つけた。彼はその、現実から目を背けたいという思いからか、その洞窟の中にするりと入っていった。洞窟の中にはズバットやゴルバットと言った定番のポケモンすらもいなかった。この洞窟が異端な場所であると彼はすぐに気が付いた。
しかし、洞窟は意外にもそこまで深くはなかった。すぐに行き止まりに直面した。何も面白いものがないように思われたが、その行き止まりの場所には見覚えがありすぎるものがあった。
不自然な程に綺麗な長方形の形をしている岩があった。その中央には窪みがあり、そこにアブソルの角が置かれていた。それが古いものだとは一目でわかったが、鋭さと三日月のようなその形は変わらず保たれていた。
周囲には花が添えられていた。また、少し距離を置いた場所には何故か一本の縄がバラバラに引き裂かれて置かれていた。
刃のような形をした青い角。災いをキャッチするときに激しく痛む角。この角があるからいけないんだと思い、木にぶつけ続けたこともある角。
なぜそれが、こんな場所にあるのだろう。
何度木にぶつけても角が折れる事なんて無かった。母親の角も、人間に幾ら長物を叩きつけられようが折れる事は無かった。早々簡単に折れるものではない。
「あれアブソルじゃん。そんな所で何してるの?」
自分のことを種族名で呼ぶ謎の声にリュートは咄嗟に振り向いた。そこにはナゾノクサがいた。
「あ、ごめん。つい気になってこの洞窟に入ってきてしまった」
「いや謝らなくていいよ。ここ、僕の家とかじゃないし。ここは誰でも自由に出入りオーケーだよ」
取り敢えず、自分に危害を加えてくるようなポケモンではないようだ。この辺りで暮らしているポケモンだろうか。この角のことを何か知っているのかもしれない。
「あのちょっと聞きたいんだけど、この角ってなんでここにあるの? 大事そうな場所に置かれているけど」
ナゾノクサはリュートを訝しい目で見つめていた。
「自分はこの辺りのこと、何も知らないんだ。教えてほしい」
「う、うん。いいけど。君の方が詳しいはずなんだけどなあ」
そう前置きしてナゾノクサはこの角の説明を始めた。この角は一体誰のもので、何故こんな場所にあるのか。祀られるというと少し大げさだが、何故こんな丁寧に整えられた上で置かれているのか。
今もなおアブソルに対する人間の醜い仕打ちは続いているが昔は更に酷かった。今よりも災害に対する対策措置がなくて被害が大きくなるため、食い止めるべくアブソルを徹底的に虐殺した。
しかし当然災害は一向に減らない。そこで人間は最終手段を計画した。その計画は、山全体を焼き払いこの辺りのアブソルを全滅させるというものだった。その時代でも既にポケモンを捕らえる技術が広まっていたので、ポケモンの力を借りて山を焼く事はそこまで難しくなかった。
山を焼いた場合アブソルだけでなく他のポケモンも犠牲になることになる。計画を知った全てのポケモン達の群れが絶望に染まっていた。抵抗しようにも、人間の方が勢力は遥かに大きかった。
そんな時、『災害』がやってきた。
火山の噴火が起こったのだ。火口で爆発的な噴火が発生し、火砕流が一瞬にして村を飲み込んだ。勿論、大勢の人間が亡くなった。人々はもはや山を焼いている場合では無くなった。焼こうとしていた山とは勿論別の山であるが、まるで大規模な自然破壊を咎められたかのようだった。
その後人間達はもう二度と、山を丸ごと焼くような無差別的は殺害行為は行わないと誓った。
この災害であるが、他の災害とは一つ、違う点があった。この災害では予知したアブソルが人間達に向けて伝達をしなかったのだ。こんな事は初めてだった。
アブソルが山から降りて来なかった為、人々は災害が来ることを知り得なかった。だから逃げ遅れ、死者が遥かに膨れ上がったのだ。
災害を予知したのに知らせに行かなかったアブソルは『英雄』として讃えられた。唯一アブソルとしての本能に打ち勝った存在だった。
今も尚、この山の英雄として称えられているアブソルの角はこの洞窟に置かれている。時折、森に住むポケモンがやってきて平和を祈る。人間達が再び暴走しませんようにと。角はとてもじゃないが祀られている格好には見えないが、ポケモン達なりに色々工夫がされていた。隣に置かれている縄は、アブソルが人間を捕らえるときに使っていた縄で、それを引き裂くことにより、運命の束縛から逃れた英雄の姿を表している。
以上がナゾノクサの説明だった。
リュートは食い入るようにこの話を聞いていた。気付けばナゾノクサに顔を至近距離まで近付けていて、ナゾノクサはそんなリュートに少し後退っていた。
こんな事があったなんて知らなかった。
「本当かどうかは分からないよ。あくまでこんなことがあったかもねーってだけで。そもそもどの山が噴火したのかとかも今となっては不明だし」
それでもリュートは、かつて生きていたアブソルが「本能に打ち勝った」という所に釘付けになっていた。そんな事が出来るなんて思ってもみなかった。
(あるいは、もしかしたら自分も)
「っていうか、なんでアブソルである君がこの話初耳で、僕みたいな雑草がこんな良く知ってるの? 親とかから教えてもらったこととかないの」
リュートは、苦々し過ぎる思い出を抑えながら、少し間を置いて答えた。
「自分の親は僕が生まれて直ぐに別れた。だから教えてくれる人なんていなかったんだ」
「両親じゃなくてもさあ、こういう伝承を教えてくれる物知りのおじいちゃんとかってどの種族でも一匹はいるじゃん」
「どうだったかな。いなかったと思う」
「……噂には聞いていたけど、アブソルって本当に連帯感がないんだね。後世に伝えていくという発想もないのかい?」
「一匹狼だから、アブソルは」
「ふーん。みんな仲悪いんだ」
「仲は悪くないよ。仲間が死んだらみんな悲しむ。でもみんなで協力して何かを成し遂げはしない。それぞれが独立して暮らしているんだ」
「すれ違うときとかに挨拶ってする?」
「しない」
「それは仲が悪いんだよ」
「違うと思う。個人個人が自分と自分の家族のことだけ責任を持って、好きなように生きてるだけ」
「ああ、でも自由なのは羨ましいね」
リュートはナゾノクサと少し話した後、そろそろ帰ることにした。もう夕焼けもとっくに過ぎていた。貴重な一日が終わってしまったが、彼は悲願していなかった。
「今日会ったばかりの自分なんかに色々教えてくれてありがとう」
「どういたしまして。部外者の僕が言うのもアレだけど、残り少ない余生、思いっきり楽しんでね」
「僕は死なないよ」
「え?」
「僕は死なない」
リュートはまるで自分に言い聞かせているかのように言った。その目には明らかに決意の炎が揺らめいていた。
伝承。
言葉を話せる生き物が会話や書物を通じて他者から他者へと話を伝えていくこと。往々にして伝えられる話は自分達に都合の良いものが多い。皆信じたい者を信じるから、都合の悪い話は広まっていくことはない。
アブソルが災いを運んでくるという伝承は真っ平な嘘。では、アブソルが本能に打ち勝ちみんなを救ったという伝承は? こちらだって嘘かもしれない。
それでもああいう風に具体的なエピソードが残され、角という遺品が残されているのを見ると、どうしても信用したくなってしまう。
その伝承が微かでも希望を抱かせるものであるとすれば尚更である。
リュートは考えていた。かつて本能に打ち勝ったアブソルがいるのなら、自分だって同じようにできる可能性があるのではないかと。
それは傲慢な発想かもしれない。アブソルのみならずポケモン達を救った英雄と自分は並べると思っているのだ。
だがリュートは「自分は選ばれた存在だ」という自信があった。
自分はこれまで特に凄い事を成した事はない。見かけも同年齢のアブソルと変わりない。角が他のアブソルよりも大きいとか、角にいかがわしい模様が付いているとかなら「選ばれし者」という印象を抱かせるが、そんな特徴も持っていない。
けれども彼には唯一の自負があった。
それが、人間に対する恨みの感情の強さだった。
あのアブソルがなぜ本能に打ち勝てたのかは分からない。しかし恐らく人間を恨んでいたからなのではないかと思う。恨みの感情が本能を掻き消したのだ。
(僕も同じように恨みの感情を武器にして戦えるはずだ!)
災害を知らせに行かなければ、人間達に報いることができる。それだけでなく災いがアブソルのせいだという言い伝えに少しは疑問を持ってくれるかもしれない。そうなればアブソルは殺されなくなる。
この日の夜中、リュートは自信に満ちあふれていた。自分こそが仲間を救う英雄だとうぬぼれた。仲間に称賛されている自分の姿を想像して一瞬だけニヤけた。
だが朝目が覚めるとその自信は火に水を掛けられたようにくすぶっていた。うぬぼれていた夜中の自分を恥じた。何が英雄だ。下らない妄想に縋るな。
その日の昼過ぎになるとまた自信が溢れてきた。そんなことを繰り返していた。彼の気持ちは両極端で揺れていた。
1 week ago.
そんな揺れの中で、また一週間が経過した。
この日リュートはとても不思議な体験をした。恨むべき存在だった人間に命を助けられた。あの家族は、一体何だったのだろう。
助けられたと言えども、彼にとっては、悪夢のような出来事だった。
今までは全人類を恨んでいたのに「人間にも良い人も悪い人もいる」という柔軟な考えを急に持つようになってしまった。
こうなると「災いを知らせに行かないように自分を制する」という選択の善悪が、非常に難解なことになってしまった。
あの家族のように良い人間もいるのに見捨ててしまって良いのだろうか。命を救われたのに恩を仇で返すようなことをしても良いのだろうか。
かと言ってあの家族を救うために、自分の命と仲間達の命を犠牲にするのもおかしい話だ。
「リュート、お前はもう既に本能に侵食されている」
相談してきたリュートにそう返したのはアブサだった。アブサは両親を喪い、狂ってしまったリュートが正気を取り戻せるまで、そして自立出来るようになるまで深く面倒を見てくれたアブソルだった。
アブソルという種族は基本的に個人主義であり、自分は自分、他人は他人という行き方を皆がしている。だから身寄りのなくなった仲間をどうにかしてあげようという気持ちが起こらない者が多かった。そんな中、アブサのみが名乗りを上げた。積極性に動こうとしない周囲に悪態をつきながら、リュートの面倒を見る責任を引き受けたのだ。
アブサは、この近辺に住むアブソルの中で種族の連帯を意識する唯一のアブソルと言っても良かった。
アブサは前脚を巧みに使い、切り裂いた袋から乾パンを取り出して食べていた。
「それどこで手に入れたんですか」
「そんなもん決まっているだろう。キノコ狩りにきた連中から掻っ払ってきたんだよ」
「また盗んだんですか。よくやりますねえ」
通常、アブソルという種族は人間を自分から襲ったりはしない。だがアブサだけは人間に対して積極的に爪を立て、食べ物を盗んだりしていた。襲った人間は証拠隠滅の為に地面に埋めていた。
「俺からしてみれば人間を襲ったりしない時点でもう本能に洗脳されてるんだよ」
「でも、キノコ狩りに来た人間はアブソルを殺したりはしないでしょう。何の罪もない相手ですよ」
「構わねえ。同じ人間だ。連帯責任。自業自得」
「…………」
「誰かの失態や誤ちに対しては種族みんなで責任を負っていくべきなんだ。アブソルだろうと人間だろうと同じことだ。大体、人間だって災いを運んだアブソル以外だろうとバンバン殺してんだろ」
「ま、まあ確かにそうですけど」
「それにだ。お前だって見て来たんだろ。例の家族の、災害に対する意識の低さを」
全く貯めていない非常食。ちょっと大きい地震でも来たらすぐに壊れてしまいそうな家。壁に固定されていない家具。リュートは確かにあの家族の意識の低さ、だらしなさを見てきた。
でもだからこそ助けないと駄目だと思うのだけど。それに、災害対策ができないのは貧しさゆえなのかもしれない。生活に余裕のない状況では「もし」のことなんてとても考えられない。
「そういう奴らはすっかり安心しちゃってんだよ。俺らが知らせに行くから逃げ遅れる心配はないなって。でもそれって良くないことだよな。俺達に依存しちまっている。だからさ、一度ここらで痛い目に合わせてしまった方が良いんだよ」
「でもアブソルを殺そうとしている人間なんてほんの一部なんですよ。他の人達は善良かもしれないんです」
「いやだから、逆なんだよ。俺達を殺そうとしてない奴らこそ、見捨ててやるべきなんだ。積極的に自分から動こうともせず、適当にのほほんと生活している奴らにこそ、災害の怖さを教えてやるべきだ」
「…………」
「そうそう、向こうの崖から丁度村の学校が見えんじゃん」
「はい」
「あそこの学校で避難訓練やってたのを見たんだけどさ、酷かったぞ」
「児童達が半笑いで逃げてたんでしょ」
「そんなんじゃねぇ。もう根本から異常だあれは。先生がさ、アブソルの絵が描かれたお面被ってんだよ」
「え?」
「そしてその先生が校舎に向かって『地震が来たぞー!』ってメガホン使って叫ぶんだ。そしたら生徒達は校庭に防災頭巾被って避難するっていう流れ」
「僕達がいること前提になってるじゃないですか」
「そうなんだよ! おかしいだろ。学校ですらそんなことになってんだ。だからさあ、一回ここらで一発かましてやればいいんだよ」
段々、アブサの考えにも一理あるとリュートは思えてきた。
人間はアブソルの本質を見ようとしない。だったら自分だって人間の本質から目を背けても良いんじゃないか。連帯責任だった開き直っても良いんじゃないか。災害を恐れない人間のためにも、一度被害を被って貰うのもありなんじゃないか。
「まあそもそも出来るかどうか分からないんですけどね」
「いやできるさ、お前ならきっと。憎しみの力は誰よりも強いのは俺だって認めてる」
(人間に対して容赦のないアブサさんの方が適任かもしれないけどね……)
そんな言葉をリュートは飲み込んだ。アブサの力強い言葉によって元気づけられたのは確かだった。
「分かりました。当日は頑張って、本能に打ち勝ってみせます!」
「やってみろ! 俺は信じて待ってるからな!」
the day.
そしてついに、『災害』の日が訪れる。
リュートはこの日、何もしなかった。いや、何一つとしてやる余裕なんてなかった。食事は全く喉を通らなかった。ただただ住居でじっと目を瞑っていた。
自分を、アブソルを象徴する、頭から生えるこの曲刀のような角が災害をキャッチしたら、何がどうあろうとも村へと降りていってしまう。
それを喰い止めようと、恐らくアブサが立ち塞がってくる。アブサにはくれぐれも何もしないで下さいと念を押しておいたが、それでもやって来るだろう。
本能に支配されたアブソルは、周りの仲間、そして肉親をも薙ぎ倒してでも先へ進もうとする。どこかへと消えたアブソルも虚ろな目をして戻って来て、その日の前に発狂したアブソルも憑りつかれたように動き出して、例外なく本能に支配されて先へ進んだ。アブサが立ち塞がった場合、本能の赴くままに殺してしまうことになってしまう。それだけは絶対に避けないといけない。アブサに言わなければ良かったと彼は後悔した。そのアブサに相談したおかげでリュートは本日戦えるようになった訳だが。
ふいに雨が降ってきた。ただしそれは、さらさらと優しい音を響かせるだけの小雨だった。だがリュートには分かっていた。この小雨は引き金なのだという事を。
リュートはもうそろそろ『スタート』の合図がくると確信していた。
そして、やはりその通りになった。
……。
雨音が、次第に激しくなっていく。
…………。
雨の一粒一粒がおおきくなっていた。住居の木の洞でじっと目を閉じていたリュートの足を、腹を、流れる水が濡らしていった。
………………。
あ…………だめ……。
……うん…………。
…………そう……だ……。
…………あ……れ……。
……あれ……うん。
……いや、あれ……なんで僕はまだ…………ここにいるのだろう……。
…………そうだ、早くしないと駄目じゃないか。間に合わなくなるぞ。もうすぐ村中が洪水になってしまう。
人間達はこの豪雨を軽視しているはずだ。それじゃ駄目だ! 大変なことになるんだ。一刻も早くそのことを伝えにいかないとみんな死んでしまう!
みんなを救える『英雄』になれるのは僕しかいないんだ!
ついこの前だって、僕の命を助けてくれた家族達がいたんだ。あの人達もちゃんと助けないと、このままじゃあ恩を返せないことになってしまう。
とにかく急がないと。ぬかるみで転んだ。駄目だ駄目だ、こんな事に足を取られてちゃ。しっかり走らないと。岩の足場が見えた。迂回している暇は無い。慎重に、でも早く、なんとか転ばないように。
越えた、よし。
まだまだ先は長いぞ。
走らなきゃ、僕しかいないんだから! 木の根を飛び越えて、草を掻き分けて!
ん、誰かいる。
「――ト、お前は――――になるんじゃ―――」
何か喚いている。
でも脚を止めている暇はない。
「――ッ!! ――を殺され―――出せッ!!」
何か変なことを喚いているが、何を言っているのかさっぱり理解できない。ただ、それは僕の前に立ちはだかった。どうしてだろう。僕はこれから『英雄』になりに行くというのに。遊んでいる暇なんかないのに。
仕方がない。殺してしまおう。みんなを救わないといけないときに邪魔をするなんてとんでもない悪だから、殺しても構わない。いや、殺すべきだ。
かまいたち。
「ッ!! リュート! 目を覚ませ!」
かまいたち。
「あぐっ!! う、駄目だ、リュート、リュート!」
辻斬り。
「ぎゃあ!! ちくしょう、駄目だ、リュート、駄目だ、お前は、お前は、」
でもそれはどかなかった。何でか攻撃してこないけれど、でもどいてくれない。
「いぐっ! リューヴドおおおああああっ! 目を覚ませえええええええええええええ」
かまいたち。
「おべぇっ! だめ゛だっ!! お゛まえ゛ばっ!」
かみつく。
「い゛い゛い゛い゛い゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛っ!!!! リ゛ュ゛ゥ゛ドオ゛オ゛オ゛オ゛ッ」
辻斬り。
「ぎぃっ!! ……だ、め、だあ゛あ゛っ!」
かまいたち。
「ヴぅ!! …………う゛……リュー、」
かまいたち。
「ぎゃっ! ……………………。
……………………」
やっとそいつは動かなくなった。僕は屍を飛び越えて先へと進んでいく。
村が見えてきた。なんとか間に合いそうだ。どうにか僕は、みんなを救えそうだ。
あれ?
みんなを救う?
みんなって誰のこと? いや分かる人間のこと。当たり前じゃない、か?
あれ、いや、ちょっと待って。僕が本当に救わないといけないのって……人間? 本当に人間?
僕は、誰にとっての英雄になろうとしていた?
「リュート、お前は英雄になるんじゃなかったのか!」
誰かの声が耳に響いた。誰だったっけ、いや、でも、そうだ。僕はアブソル達の英雄になろうとしていたんだ。
なんで英雄になろうとしていたんだっけ。そうだ人間が憎かったからだ。僕は母親と父親を殺されて、そして仲間も何匹も殺されて、そして。
「リュートッ!! 母親を殺された恨みを思い出せッ!!」
ああ、ああ! そうだ、人間が憎くて憎くて、たまらなくて、他のみんなも同じ気持ちで、そんな現状に耐えきれなくなったんだ! だから、僕は、革命を起こそうとしていたんだ。
……。うん?
あ、あ、あ、あ、あああああああああ!! あああああああああああ!! ああああああああああああああああああああああああああ!!!!
僕はさっきなんてことをやってしまったんだ!! アブサは僕を止めようと命懸けで必死にやってくれたのに! そんなアブサを僕は邪魔者扱いして惨たらしく攻撃してしまった! 何度も何度も! 最低だ僕は、なんて最低なんだ!
リュートは気付けば足を止めていた。
雨は横殴りに全てを叩きつけていた。しとしと、さらさら等という形容がまるで当てはまらない激しい滝のような雨が降り注ぐ。植物達にとっては恵みであるはずの水に、今や哀れな程厳しく痛めつけられている。外に出ていた天気の読めないポケモン達は急ぎ足でそれぞれの住居へと帰っていく。
夕立、と呼ぶには激し過ぎる雨。今ではゲリラ豪雨と呼ばれるもので、大気の不安定により突発的に降る。予測することが大変難しい雨だ。
リュートは息を切らしながらその場に倒れた。頭の中がまだ気持ち悪い。頭の中に虫が潜んでいてあちこち動き回っている感覚がしていた。
危なかった。後もう少しで、本能に完璧に支配されてしまう所だった。
リュートはまだ呼吸が落ち着いていなかったが、立ち上がってすぐにアブサの所へと足を翻した。彼は生きているだろうか。僕が殺してしまっていたらなんて謝れば良いのだろう。
足は、次第に早くなり、そして不安の大きさを表すようにまた全力で走った。
近付くに連れて濃い血の臭いがこの豪雨の中でも鼻に届いて、足元を流れる水に赤が混じっていた。
しかしながら、幸いにしてアブサは生きていた。
だが、もう手遅れかもしれなかった。目を逸らしたくなるほどに外傷は酷く、こひゅー、こひゅー、と掠れた音を出しながら、痛みに耐えるようにじっと体を動かさなかった。
「ごめん、僕のせいで、こんな目に」
「気に……するな。それ、より……良かったじゃ……ないか。おめ……でとう、お前は……勝ったん、だ」
「でも、アブサさんが」
「俺は……死な、ない、ぞ」
「いや……この状態じゃ……もう」
「リュート……俺の……背の方向、だ。木の傍……」
喋れる事自体が奇跡のようなアブサの訴える声に、リュートは泣きながら示された場所を見た。そこには少し前にも見たことのある草があった。
「これって……」
「口に……はや、く」
リュートはすぐさま、アブサにふっかつそうを食べさせた。みるみるうちにアブサの傷が治っていく。さっきまで本当に死ぬ寸前の状態だったのにもう起き上がれるようになった。
それから、リュートはアブサに丁重に謝罪を繰り返した。
アブサは、殺されかけたというのに、朗らかにリュートを許した。
ひとまず落ち着いてから、リュートは次第に喜びが湧き上がってくるのを感じた。
アブサを傷つけてしまったことはまだ胸が痛むが、これでもう完全に目的は達成された。自分は本能に打ち勝った。災害を知らせなかった。とうとうやった。
これで、人間達に報復できた。
だが。
リュートはチラチラと村の方角を見ていた。
「あ、いや」
気にならないと言い切ることは出来なかった。
「まだか。本能による支配は完全には抜けてないようだな」
「はい……」
「気になるなら、見てくるだけ見てくればいいんじゃないか」
「え? でもそんなことしたら、つい向かっちゃうかもしれないし」
「大丈夫だ。今更伝えに行った所で無駄なんだから、無意識のうちに向かってしまうなんてことはないだろう」
豪雨は未だに止む気配が無かった。
アブサと一旦別れ。リュートはゆっくりと山を降りていった。そして、村全体を一望できる崖に立った。
下を向いていたリュートは恐る恐る顔を上げてみた。
「あ……」
村の惨劇が、そこにはあった。
この村にあるダムは川の下流よりの方に建設されていた。上流で広範囲に降り注いだ豪雨は一斉にダムの貯水池へ押し寄せた。
更には、おびただしい流木までもが貯水池へ流れてきてしまった。森林環境の劣化が原因だった。
その結果、最悪の結末を向かえた。
流木はダム中央部のゲートに引っ掛かった。こうしてダムは放流機能を喪失し、水が貯水池から更に下流へ流せなくなった。
貯水池に水が溜まっていくばかりで、吐き出すことを知らなくなったダムはいよいよ容量が足りなくなった。洪水はダムの上を越えて流れていく。
そしてついに水圧に耐えきれなくなったダムは決壊した。ダム湖の水は濁流となって水しぶきを上げながら一気に村へと押し寄せた。
家々が次々と水の勢いに敗北して崩れていく。日陰にひっそりと建つボロ家であろうが、広々とした庭を構えた代々受け継がれた立派な家だろうが、水勢には敵わずただの瓦礫となった。
山に避難しようと必死に逃げる人々も、濁流の勢いに追いつかれ、飲み込まれてしまった。頑丈な建物の屋根の上に避難した人もいたが、嵩を増し続ける水流に飲み込まれて消えていった。
やがて村は完全に水に支配された。これまで水の恵みを受け続けてきたこの村は、かつてない大規模な水害に見舞われた。
今も絶えず流れ続ける濁流を見ながらリュートは唖然としていた。
(なんてことを自分はしてしまったんだ!)
リュートは激しく自分を責めた。英雄になれるだとか革命を起こすだとか悦に浸ってばかりでいた自分を恥じた。特にあのとき夜中に一瞬でもニヤけていた自分の姿が酷く滑稽で、馬鹿野郎で、自分が悪であると証明する決定的なものだと思った。
最善の選択はアブソルも人間も救う方法を考えることだった。今更それに気付いた。片方しか救えないものだと考えて行動した自分は間違いなく問題だった。どっちも救う方法なんてない? いや捻り出せよ頑張って。
こんなことしたって仕方がなかった。復讐は何も生まない。心優しいあの父親と少女もこの濁流に飲み込まれてしまったのだ。あのボロ家も勿論、もう何も見えなくなっていた。体をざくざくと抉るような罪悪感だけがいつまでも胸に叩きつけられるだけで、一滴の達成感すらない。
そもそも自分が復讐したかったのはごくごく一部の人間のみだった。だってそもそも大半の庶民はアブソルを殺そうなんて考えていない。自分を痛めつけた、母親を惨殺した、気狂いだけだった。自分を見て目を逸らすような、そして勿論あの心の優しい父娘のような、ただ災害に怯えているだけの弱くて貧しい立場の人間まで巻き込むことはなかった。
終わった後はもっともっと気持ち良くなれるものだと思っていた。災害が起きた村に対して「ざまあみろ」ってとても嫌味な顔で言ったり出来ると思っていたし、密かにそれを楽しみにしていた。
リュートは自分を責めて責めて続けた。自分を責めることでしか、詫びる手段はないと思った。しかしどんなに自己嫌悪したって誰も生き返らないから、この行為は単なる自己満足に過ぎないのだ。けれど今となっては、それ以外の方法も見つからなかった。
リュートは今自分が自己満足行為をやっている、ということを更に責め立てた。けれど、詫びるしか、謝るしか出来なかった。そして責め立て、謝り、責め立て、詫びた。それを延々と繰り返した。
自分の行いが誰かの人生に多大な影響を与えてしまう、ということがこれほどまでに辛いとは。
自分に対する嫌悪感と罪悪感で彼は死にたくなった。なんども岩に頭の角を叩きつけた。相変わらず全く折れる気配はしなかった。すると四肢を殴りつけた。すぐに前足から血が出た。その血が少しだけ罪悪感を薄めてくれたように思えたが、気休めでしかなかった。もう自分も、あの濁流の海に飛び込んでしまおうか。リュートはそんな事まで考えてしまっていた。
だがそんな時、背後からものすごい数の気配を感じた。
振り向くと大勢のアブソル達がこっちまで来ていた。遠くからだとまるで雪崩でも押し寄せてきたのかと思う程の数だった。アブサもその中には混じっていた。
アブソル達はみんな崖の縁に立った。リュートは呆然としながらその様子を眺めていた。
「どうだ! 俺達の痛みってもんがこれで分かったか!」
「ふはははは。結局俺たちが知らせに行かなかったら、てめぇら何も出来ねえじゃねーか」
「ざまあみろとした言いようがないな!」
「俺達を散々殺して回ったバチがようやく当たったな!」
「自業自得だ!」
「むしろ良かったな人間! これからは災害対策を怠らないように気をつけろよ!」
長年の悔しさから開放されたアブソル達は、本当に嬉しそうな表情をしていた。心の底から、何の曇りもない歓喜の表情で村に向かって罵倒を繰り返していた。
ひとしきり叫んだ後リュートの周りに集まった。
「良くやったな」
「ありがとう」
「君は英雄だ」
「君のおかげで胸がすいたよ。本当に感謝しかない」
リュートがアブソル達にとっての英雄になった事も、事実だった。
その、称える言葉も彼の涙を誘うにはあまりにも十分過ぎた。リュートは泣きながらみんなの言葉にうんうんと頷いていた。その様子をアブサは遠くから静かに笑みを浮かべながら見ていた。
罪悪感で胸が押し潰されそうになっていたのが、ずっと過去の事であるような気がした。すっかり気持ちは晴れてしまった。あの家族のことなんて完全に記憶から忘れ去られてしまっていた。
リュートは、自分のやったことは何一つ間違っていなかったと確信した。そうだ、これで良かったのだ。これで……。
ずきん、と頭が痛んだ。
*****
新聞紙が敷かれているだけで何も入っていな倉庫が置かれて家には、四人の家族が暮らしていた。
祖母は相変わらず映りの悪いテレビを叩いていた。
「もうこのテレビ駄目ね。新しいの買いましょうか」
「いいよ、買うの面倒くさいし、色々設定すんのも面倒だ」
晩ごはんの支度をしている母親が呆れて溜息をつく。父親は最近機嫌が悪くて動きたくなくなってしまっていた。隣の家の男にこっぴどく怒られ、一発蹴りまで入れられたのだ。
一方で百合はベランダから山の方をじっと眺めていた。最後の一本になってしまったオレンジジュースを飲み干して、溜息を付いた。みんなで遊んでいた秘密基地が誰かにめちゃくちゃに荒らされて、気持ちがブルーになっていた。
「あのアブソル、今どうしてるかなあ」
外へ向かって百合はそう呟いた。この前避難訓練で先生がアブソル役をやっていたから、つい思い出してしまった。
外では雨が、しとしと降っている。
*****
later.
他のアブソル達が去った後もリュートは独り静かに村を眺めている。
足がブルブルと震え出し、顔はニヤけている。突然地面を転がりながらぶつぶつと「やったぞ、やったぞ」と呟き出した。更にはゲラゲラと笑い声を上げ始める。尻尾が遊んでいるときのように揺れている。
今度は立ち上がって何度もジャンプを始めた。途中着地に失敗して足を捻って転ぶ。体が泥に塗れて、それでもリュートは大声で嗤っていた。足も痛んだままだったが、今はそれすらも楽しかった。
誰の目も気にせずに感情を体全体で思いっきり吐露した。
興奮は際限を知らずに昂り続けていた。永遠に膨れ上がる達成感に耐えきれず、笑いながら地面をリズムカルに叩いた。びちゃんびちゃん、どちゃ、びちゃとのたうち回りながら、ぐちゃぐちゃなリズムを全身で演奏した。
「ははははははははは、あーっはっはっはっはっはっはっはっは!!!! いーっひっひっひ!! あははははははは!! はははははははははは、あは、あは、あは、いひ、あは、あは、あはあはははははははふふふふふっうふふふふふふふふっ! あーっはっはっはっはっは!!!! あーーっはっはっは!」
今の自分の姿があまりにも滑稽なことに気がついて、最後にプっと噴き出した。
息が苦しくなって、流石に笑い疲れて、リュートはのっそりと立ち上がった。一度痛みで足が滑って、どちゃ、と泥が跳ねた。しかし、リュートの体はもうとっくに泥塗れだった。そしてそんな事は全く気にする事ではなかった。
立ち上がると、リュートは崖の縁に歩いて「ざまあみろ!」って思い切り叫んだ。その声はやまびことなって耳に跳ね返ってくるものだから、心地よくて仕方がなかった。
「ざまあみろ! ざまあみろ! ざまあみろ!! ははははははははは! あはははははははは!!」
笑っている最中、突然、リュートの角が、あっけないような、そして悲鳴のような音を立てて根本から折れた。折れた角は崖から落ちていき、やがては濁流の中へと消えていった。
雨は未だに降り続いている。
濁流は人の営みをこれでもかと言う程に洗い流し、そしてどこかへと運び続けている。
その中で一つの笑い声が、ずっと、ずっと響いていた。
-------------
あとがき
こんにちは、逆行です。
このお話は私とまーむるさんの合作となっております。
私が要所要所飛ばしつつ一先ず書き上げ、その後まーむるさんがエピソードの追加及び加筆を行なっていくことで完成させました。
まーむるさんは容赦のないグロテスクな描写や異常な精神状態の描写を得意とする物書きさんですので、そちらはまーむるさんにお任せしました。「この部分はまーむるさんが書いてそう……こっちは逆行が書いてそう……」等と考えながら読んで頂くのも面白いかと思われます。
当初は短めのお話にする予定でしたが、だんだん熱が入ってしまったのと、大規模な水害が実際に発生して安易に書けなくなったこともあり、自分の担当部分だけで1万5千字を超えてしまいました。結果、まーむるさんの担当箇所が少なくなってしまいました。まーむるさんにはこの場を借りてお詫び申し上げます。それでもまーむるさんは少ない文字数でインパクトのある描写を重ねており、流石だなと思いました。
最後になりましたが『制約のない』をお読み頂きありがとうございます。またどこかでお会いしましょう。それでは!
※ポケ庭に匿名で投稿したものです。
仄暗い。
チカ、チカと電灯が切れかけている音がする。
目は閉じたままでも、それは分かる。
体は、未だにあるみたいだった。まだ、生きているみたいだった。
「……なんで」
目を閉じたまま、頭を長い胴に埋めたまま、草蛇はそう呟いた。
「俺が助けたんだ」
声は、すぐ近くから聞こえた。少しの間が経ってから、草蛇は首を持ち上げてその方向を振り向く。
四つ足で座る、青い体。頭と腕には貝殻で出来たような兜と小手を自らの体そのものに備えていた。
細い目と、少しだけやつれたような、それでも大きな口ひげ。そして、その肉体の至る所には血がこびりついていた。固まり、黒ずみ、爪で削れば簡単に落ちそうなそれは、しかしもう削るのが面倒というほどに、様々な場所にこびりついていた。
最終進化後に、とうとう貝から刀を扱うようになった、血の匂いを濃く漂わせる海獣。
「…………ありがとうございます」
その海獣に助けられた事に対して草蛇は、けれどそう嬉しくなさそうに、そして物怖じもせずに答えた。
そこは船の一室。赤い絨毯の上には、様々な調度品が脆さを示すように、破片となって地に転がっている。湿り気に覆われ、シーツなどの布類は気だるく固まっている。しかし、それら全てよりも異常な事は、部屋自体が傾いていたまま、動かない事だった。
そしてガラスの外は、完全な暗闇だった。
それは、深海の暗さだった。しかし、この船は潜水艦ではなかった。煌びやかで頑丈で、そして沈んだ豪華客船の、奇跡的に水が入らずに済んだ僅かな一画だった。
海獣も、そして長い眠りから目を覚ました草蛇も、それを知っていた。
助けが来る事をずっと、ぼんやりと祈りながらその脳裏に浮かぶのは、この手で殺した人間、獣達。
海に住処を持つ獣とは言え、深海の圧力に耐えられる獣はそう多くはない。この海獣も、そうだった。海辺で暮らす種族であり、海を常に泳ぐのではなく、地に足を置いて生きる種族だ。
沈み、それまでに脱出出来なかった海獣は、壁を破壊して出ると言う手段を取れなかった。
そして、まず殺したのは、僅かに居た、深海でも問題なく生きる事が出来る獣達。極度の混乱の中、唯一無二の人間の相棒をも捨てて壁を壊そうと外へ出ようとした獣達。
破壊の光線を今にも撃とうとしたその獣の背後から頭に剣を突き立て、引き抜く。隣でその状況を飲み込めていなかった、同じ深海でも生きられる者を次いで喉元から切り上げ、首をぼとりと落とした。
次に殺したのは、炎を身に宿し、そして自然と生きているだけで炎を身から放っている獣達。
助けが来るまでの間、より長く生きなければいけない。しかし、空気は有限となり、その炎が奪う空気を補えるほど、光合成が出来る獣もそう多くはなかった。
止めてと叫ぶ人間諸共、剣を薙いだ。必死に逃げ惑う炎猿を、体を捩じらせ、狙いを定め、必殺の投擲は胸を貫ぬき、そして壁へと磔にした。
そして、向けられた恨みは全て切り裂いた。
混乱は、長く続いた。殺したのは自分だけではない。殺されたのは自分が殺した以上の何倍にも及ぶ。
漸く落ち着いてきた頃に生き残っていたのは、三分の一以下だった。
それからどれだけの時間が過ぎたのか、考える事は早々止めた。
とぐろを巻き、起きた後も頭を埋めている。体はとても気怠い。この仄暗い場所に閉じ込められてから、全く光合成は出来ていない。その脳裏に浮かぶのは、黒い感情。もう戻らない日常。そして、胸に強く刻んだ決意。
自ずと湧き上がる感情は、堪えなければ慟哭として弾けそうだった。けれど、堪えなければいけなかった。
後悔が、何度も沸き起こる。
何でこんな船に乗ったのだろうというところからそれは始まる。人間が積み上げてきた知恵と獣の様々な力によって作られたこの巨大な船は、金を持たずとも、それに相当する何かを渡せば、そして秩序を守る事が出来ると認められれば、獣だけでも乗る事が出来た。
だからこそ、こんな事になってしまったのだ。
獣だけの王国からやってきた自らと友は、長い永い旅へ出ようとこの船に乗った。
長く暮らしてきた王国を友と離れ、大海原へと船が出る。大地がどこにも見えなくなり、不安を抱える自分を友は優しく宥めてくれた。
人間の道具を使えば、遠くの景色を見る事も叶った。岩礁で歌う獣、空から海へと飛び込み獲物を捕まえる鳥、悠然と泳ぐ超巨大な獣。
何もかもが初めてだった。独特な、ずっと続く揺れに気持ち悪くなったり、食べ物が塩辛かったり、そんな少し辛い事もあったけれど、楽しかった。不安は段々と薄れていった。水平線しか見えなくとも、明るい未来が見えていた。
寝ている間、唐突に激しい衝撃が身を襲うまでは。
―――
暫くして、海獣は立ち上がった。
それに気付いた草蛇は埋めていた頭を持ち上げた。
「……もう、食えるものに碌なものは無い」
それは即ち。
「……食べますよ。碌じゃないものなら、まだまだあるんでしょう?」
「…………ああ」
死肉しかない、という事だった。
海獣は暫くの間、壁に耳を当てて外の音を感じた。誰も居ない事が分かると扉を塞いでいた本棚をどけ、脚から剣をするりと抜いた。それは、血に汚れた肉体とは対照的に、今でも輝きを保っていた。
数多の獣を斬り殺してきたというのに、その血の痕跡は一片たりともなく、刃毀れも、目を幾ら凝らそうが見当たらない。
扉の鍵は壊れていた。いや、きっと海獣が壊したのだろうと草蛇は思った。
ここは人間向けの部屋だった。
海獣が扉に前足を掛けると、ギィ、とこの部屋の豪華さには合わない音が響く。
「本棚で塞いでおけ」
そう呟くように小さく言うと、すぐに外に出て、扉を閉めた。
閉められた後も、草蛇は暫くの間じっと、その扉を見ていた。足音は、全く聞こえてこなかった。
信頼出来るもの同士が各々固まり、いつ壊れるか分からないこの沈没船の中で助けを待っている。
助けが来ると、それだけを信じ、生を繋いでいる。
神経を尖らせながら、海獣はゆっくりと歩いた。混乱は収まり、今はもう物音すら余り立たないとは言え、誰が襲ってくるとは分からない。
血の痕跡は至るところにあった。死体は、食べられない毒を持つような者を除くと全ていつの間にか電気によって焼き焦がされていた。
誰もが信じられなくなるような混乱の後でも、皆で生き残ろうと必死に足掻く者は居るらしい。
信用できなくとも、食料の問題は、とりあえずは問題が無さそうだ。
剣先で突き、そしてほんの僅かだけ切り取り口に含む。
……問題はない。本当に、本当のお人好しが居るらしい。
心の中で強く感謝を述べながら、海獣は一部を切り取り、取って帰った。
脇に焦げた肉を抱えながら、戻り歩く。
その目は、半ば虚ろになりながらもまだ、しっかりと芯を保っていた。
非常灯がぼんやりと今でも点いている。これも、お人好しが何かやっているのだろうか、と思う。電気というものに関して詳しくは全く知らないが、明かりというエネルギーを供給する為には何かしらが必要だとは思っていた。
混乱が収まってきた頃、この一画が助けが来るまでの間までに壊れるような要因を全て殺した後、海獣は部屋の一画に陣取った。殺した獣を引きずり込み、それを糧として外に神経を尖らせながらひっそりと時間を過ごした。
隣の部屋からは、侵入者を凍らせて殺し、食べ漁る声が聞こえた。
もう片方の部屋からは、虚ろな声と、それを必死に励ます声が聞こえた。
通路からは、自分を仇とし、血眼に探す者達の声が聞こえ、それは後でひっそりと殺した。
だから、食料に困る事はなかった。けれど、精神は削れていった。出来る限りまともでいる為に、極力何も考えないようにして、耳に入ってくる音だけを感じながら。
どうしてこんな事に、いつになったら助けは来るの、本当に助けは来るの、誰か助けて。弱気になる声が両方から聞こえてくる。
自分もそう思った。けれど、自分は、その弱音を口に出して吐く訳にはいかなかった。自分は、自分だけなのだから。孤独に弱音を吐いてしまったら、一気に崩れてしまう気がした。
けれど、この焼け焦げた肉からは、焼け焦がした誰かからは、皆が滅入っているこの中で、強い希望を感じた。
羨ましかった。
本棚で扉を開けられなくする事もせずにまた草蛇は、とぐろを巻いて頭を埋めていた。
混乱の中の後悔は、激しかった。
混乱の中、一番最初の一番大きい後悔は、何故、人の物になる事を選ばなかったのか、という事だった。この船には、救助用の道具は色々とあった。けれどそれは人間用の物が主だった。ましてや、巨大な肉体を持つ獣に対してのそれはそう多くはなかった。
人の物になれば、小さく便利な球体に肉体を、重さも鑑みずに納められる。人と共に脱出出来る。それを懇願すれば良かった、と思う。
プライドがそれを邪魔した。船が沈み始めるまでの僅かなその時間、自分も友も、それを躊躇してしまった。
そして植物の体を持つ自分にとって、海水は毒だった。沈みゆく船の船頭に出て、泳ぎながら助けを待つとかそういう事も出来なかった。
友は泳げる体を持っていたのに、自分の為に、沈む船に残った。それも、とても強い後悔だった。
追い出せば良かった。追い出せば良かった。
…………友は、死んだ。死体は確認していない、けれど多分死んだ。
あの海獣の手によって。
そして多分……。
海獣が戻ってきた。腕には焼け焦げた肉を抱え、そして本棚で扉を塞がなかった自分に対して、少し怒った。
多分……その理由は、自分を守る為。
―――
焼け焦げた肉が剣によって綺麗に二分され、付いた血と脂の汚れをベットのシーツで拭い、腕にそれは戻された。
「……ありがとうございます」
草蛇に分けられた量は、海獣の量よりやや多かった。
草蛇は少しだけ時間を置いた後、それに口をつけ、ごくりと飲み込んだ。
蛇は基本的に空腹には強い。しかし、助けを待つだけのこの状況で空腹まで襲ってきてしまえば、体は植物なのにこんな仄暗い海底に長時間閉じ込められてしまえば、それに強い事は余り関係がなかった。
草蛇は、襲い掛かる多重のストレスを、久々に満たされる喜びで自覚した。
胃酸が急激に分泌されていくのが分かる。涙が自ずと出てきた。
堪えようとしていた感情が、表に出ようとしてきた。起きた瞬間、自分の胸に刻んだ決意が、落ち着いた思考によって癒されていく。
海獣も静かに肉を食べていた。
その姿は、初めて目にした時から落ち着いていて。自分が起きた時も、混乱に陥ったこの船の中で誰かを殺している時も、まだ落ち着いていた船で見た時も、船に乗る前にその乗船する人の町で見かけた時も、獣だけの王国で見かけた時も、落ち着いていて。
過去の断片的な記憶は、この海獣を見ていた。
落ち着くに連れて、その海獣がどういう立場の者なのか、分かってきた。
分かってきてしまった。
草蛇は、尋ねた。
「…………貴方は、私達を陰から護衛していたのでしょう? 王国から出たその時から」
海獣は、そう、事実を言い当てられても、静かなままだった。
海獣は、あの瞬間、諦めたのだった。
二匹を両方、陰から守る事を。海獣自身ももう、限界だったのだ。幾ら兵士として鍛えられようとも。幾ら命令だと言えども。
こんな状況でも心の底から平然としていられる程、海獣は特別ではなかった。特別にはなれなかった。
「……ああ」
海獣は、静かなまま答えた。
「……そもそも、泳げる種族の貴方が、他に連れも居なさそうな貴方が、こんな場所に居る事自体おかしい事」
海獣はじっと、聞いた。
草蛇の話す推測は全て当たっていた。
混乱の中、淡々と邪魔者を殺す所を見たと。それは、友に恐怖を植え付ける為だったのではないか。深海でも泳げる友にその気を起こさせないようにする為だったのではないか。
私達が部屋に籠った時、その隣に居たのではないか。
食べ物を取りに行ったとき、都合のいい場所に新鮮な死体があったのも。
だから。だから……。でも、どうして……。
草蛇の口が、そこで止まる。
何から草蛇を助けたのか。
海獣は、口を開く。
「段々追い詰められていくあんた達の会話を、ずっと聞いてたよ」
その気になれば、皆を犠牲にして脱出出来るその友。
体は植物なのに、太陽の光を全く浴びる事が出来ずに心身共に消耗が激しい草蛇。
どちらも、身に受けるストレスは強かった。友は段々と、自分に当たるようになった。その度に謝り、そしてまた堪え切れなくなった様に自分に当たり。
草蛇の方に限界が先に来た。
だったら、もう出ちゃえば良いのに。
草蛇は、そう叫んだ。海獣は、その時、隣で立ち上がった。
友は固まった。友の躊躇いは、欲望に押し潰された。
草蛇の生きたいという欲求は、身に受けるストレスで押し潰された。
草蛇は、続けて、ぽつぽつと続けた。
でもね。出るなら、私を先に殺してね。溺れて、苦しんで死にたくないの。
友は、それを、承諾した。
海獣がその部屋の扉を壊したのと、その友が草蛇に冷気の光線をぶつけたのは、同時だった。
海獣はもう、陰から支えるという任務を続けられないと判断した。そして、出る欲求を抑えられなくなり、決意した目で友を凍らせたその世界一美しいと呼ばれる蛇と、たった今氷漬けにされた草蛇、その両方を助ける事は出来ないとも。
そして海獣は、自分の命も惜しかった。命を捨てる覚悟をしてまで任務を全うする、海獣はそんな特別では、なかった。
海獣は、その世界一美しい蛇の首を、斬り落とした。
「俺を恨むか?」
海獣は、聞いてきた。
草蛇は、今はもう、どうでも良いと答えた。
「でも……殺した姿を見ておきたい」
海獣は、暫し悩んだ後、草蛇の強い目を見て渋々と言ったように承諾した。
―――
海獣は音を立てずに歩く。後ろには、ずり、ずり、と時に血に湿った地面を這う草蛇。
殺意は、感じなかった。別の部屋へ引きずっていき、必死に介抱をし、そして目が覚めた時、草蛇が自分に僅かながら殺意が向けたのを、海獣は知っていた。
今は、感じなかった。
そう遠くはない、その部屋に辿り着くまでそう時間は掛からなかった。壊れている扉のすぐ近く。そこで海獣が後ろを振り向くと、通路にあった焼け焦げた一つの死体を草蛇は見ていた。
「誰が、焼き焦がしたのでしょうね」
「少なくとも、俺じゃない。俺は電気技なんて持っていない」
それは、弁明のようにも草蛇には聞こえた。
壊れた扉の先を海獣が先に見た。
その直後に、草蛇がその先を見た。
焼け焦げた、美しさなど完全に消えた、その世界一美しかった蛇の死体が、今は食料としてあった。
切り取られた跡が至る所にあった。
沈黙の時間が過ぎた。長い間。
草蛇は、聞いた。
「本当に、助けは来るのですか?」
海獣は言った。
「可能性は、かなり高い」
獣だけではなく、人も取り残された事。そして、この草蛇は、獣の王国の中でも、かなり位が高い家の出だった。もう一つ言えば、海獣が殺した美しい蛇も同じく。
「絶対、ではないのですね」
「……ああ」
それでも、絶対とは言い切れなかった。人との関係がそう多くない王国が、今どこまで知っているのか、海獣は知らなかった。人の命がどの位重いものなのかも、知らなかった。
その時、ずん、と船が揺れた。
海獣は驚き、咄嗟に抜いていた剣を地面に突き立て、足腰を踏ん張った。
そこに、草蛇はするすると絡みついた。
ギギ、ギギ、と音がする。それは助けが来たのか、それともこの船が壊れようとしているのか、分からなかった。
ちょろちょろと水が流れ出る音がした。それは、時間がそう経たない内に激しく襲い掛かるだろう。
海獣の心臓は、一気に強く音を立てた。ぎゅ、と肉体を締め付けられていた。その四肢を持たない生物の、四肢の全てを補う胴の筋肉は、海獣の抵抗を一切許さなかった。
「私……分かりません」
草蛇は、海獣の頭の隣で、弱弱しく言った。
「……何がだ」
「この先、助けられたとして、それからどう生きていけばいいのか」
「……何故」
「私はこんな事になってしまったのを、もうきっと一生後悔します。その後悔を背負ったまま、生きられる気がしないのです」
「……だから、ここで死のうと思うのか?」
「ええ」
草蛇は、限界に来ている、と海獣は再度思った。その限界は、自分が美しい蛇を殺した時のそれより一つ更に下だった。
肉を食べて少しだけ回復したところに、首を切り落とされ、そして焼き焦がされた死体を見せつけられ。持ち上げられたところに、突き落とされたのだ。突き落としたのは、自分だ。
「この振動は、助けが来たからかもしれない。目の前に手が差し伸べられていても、お前は死を選ぼうと思うのか?」
通路を走ってくる様々な獣や人間達。右往左往する中、海獣と草蛇は、固まったままだった。
「……貴方には、分からないでしょうね。私の今の気持ちが」
「……だろうな。俺には、お前の友ほどに親しかった存在なんてそもそも居なかった。俺の今までは、兵士として育て上げられ、そして今、陰からの護衛が失敗に終わろうとしているところだ。
哀れだよ、俺は。そしてお前も」
最後、海獣は吐き捨てるように言った。
ギィィィ、と、音がした。遠くから、助けが来たという喜びの声が聞こえた。
「……生き残ったとして、これからどうなるんでしょうね」
「お前は、俺よりかは良い生活が待っているだろうな。俺は、この良家のお嬢様達の片方しか救えなかった、片方は殺したなんて知られたら、多分、処刑されるんじゃねえかな。
その前に逃げなきゃいけねえ」
「……意外と、適当なのですね」
草蛇は、口調の変わりように少しばかり驚いていた。冷徹に障害を殺して回っていた姿とは、起きた時の物静かな姿とは、全く別だった。
遠くから、もう持たない、早くこっちへ、と叫ぶ声が聞こえる。
海獣は走りたかった。草蛇を振りほどいて逃げたかった。
海獣は、特別ではなかった。特別になるようメッキを塗られただけだった。教育によって完璧に塗られたと思われたメッキは、沈没という事故によって、削られ、剥がれていた。
草蛇は、言った。
「私は……どうしたら良いのでしょう」
海獣は、叫んだ。
「そんなの助かってから考えろ! 死んだら何もかもお終いなんだよ!」
「貴方は、私の友を殺したのに。貴方は、沢山の者達を殺してきたというのに。そんな事を言うのですか」
草蛇は冷酷に言った。
ばきばき、とどこかが強く音を立てた。振動が激しくなった。背後からガラスが割れる音がした。水が流れてくる音が強くなった。
海獣は、この草蛇をどう説得出来るか、幾ら考えても分からなかった。
「こんな暗闇で、死にたくない……」
海獣は、泣き出しそうな声で言った。
草蛇は、体をびく、と動かした。
「暗闇……」
力が緩んだ。
「そうだ、暗闇だ。ここで死んだら、真っ暗闇で誰に弔われる事すらないんだ」
「……それは、駄目です」
そういうと、草蛇は離れた。
海獣は、一度倒れ、それから起き上がり、草蛇を正面から見た。
「時間は無いぞ」
草蛇は、蔦を出して美しかった蛇の死体を引き寄せた。
道連れにまでされようとした海獣に、付き合う義理は無かった。けれど、先の事を考えて手伝った。
深海のどす黒い海水がすぐ後ろまで迫ってきている。急いで這い、急いで走った。
途中、人が見え、ボールを出された。
それが意味するところは分かった。ボールに入れば、後はもう何もしなくていいだろう。
草蛇は死体を抱えて、素直にボールに入る事を受け入れた。草蛇はボールに入り、そして海獣の方のボールは、真っ二つに切り裂かれた。
海獣はボールに入る訳にはいかなかった。このままボールに入ってしまえば、自分は王国戻るまで何も出来なくなるだろう。
草蛇のボールを手に取り、海獣は走った。
唖然とする人を傍目に、海獣は走った。人は、後から慌てるように付いてきた。
―――
水上へと出て、別の船へと移ったところで翼の音が聞こえた。
その方を振り向くと、王国の鳥が降りてきていた。巨躯の、鮮やかな色をした猛禽だ。猛禽は、その鋭い目で、海獣の持っているボールの中身を見た。
「……貴様が居てこの様か」
「……」
海獣は、虚ろな目で猛禽を見た。
何も答えずにいると、猛禽は、冷徹な声で答えた。
「罰を覚悟しておけ」
そう言って飛び立とうとした所に、海獣は剣を抜いた。
「もう沢山だ」
そう言って跳躍して高く振りかぶられたその剣は、余りにも唐突だった。
飛び上がった直後の猛禽はそれを眺めるしか出来ず、今は太陽の下で光輝くその刃は、さっくりと猛禽を二つに分けた。
そうすれば、もう何も言わず、動かなかった。
後ろで悲鳴が上がる。
「さて」
刃を地面に突き立て、二足でしっかりと立ち。
すっかり落ち着いた海獣は小さなボールの中に目を向けた。
「お嬢様。私の逃避行に付き合ってもらいましょう」
そして刃を引き抜き、血を払った。
「あっ、あのっ、……すみません、担当者をお呼びいたしますっ!!」
「え!? あ、はい……」
一瞬戸惑った顔をして、でもすぐに頷いたお客様が首を傾げる。高校生だろうか、白いシャツと黒いズボンという制服に身を包んだお客様がポケモンと一緒にここ、フレンドリィショップに入ってきてから私に話しかけてくるまでに、そう時間はかからなかった。アルバイトとは言っても、お客様から見れば私だって店員の一人。わからないことがあったら尋ねるのは普通のことである。
まだドキドキしている胸を押さえながら、休憩室へと繋がる無機質な扉を開く。中で休んでいる同僚さんが、膝の上のヤンチャムを撫でる手を止めてこちらを振り向いた。
「コチョウさん? どうかしましたか?」
「あ、えと、すみません……またお願いしても……」
「ああ、わかりました。すぐに行ってきます」
かじりかけの菓子パンを机の上に置いて、パイプ椅子から彼が立ち上がる。隣の椅子に座っていたタブンネが、ペットボトルの蓋を閉める手を止めて目をぱちぱちさせた。
「本当に申し訳ないです……この前だってイオンさんが休憩中だったのに代わってもらっちゃって……」
「いいですよ。そんな恐縮しないでください、誰だって苦手なものの一つや二つあるもんですから……あ、そいつら頼みますね」
そう言って、彼が扉を閉める。バタン、という音の後に残されたのは私と、同僚であるイオンさんのポケモン、タブンネとヤンチャムだけだ。置いていかれたヤンチャムが、遊びを中断されたことに怒るようにして私を睨みつける。ぎろりとこちらを向く大きな目に「ごめんね」と呟くも、ぽつりと響くその声はヤンチャムへと伝わらない。慌てて駆け寄ったタブンネが彼に代わってヤンチャムを宥める。
やっぱり、ダメだった。
お客様のポケモンを前にして、固まってしまった身体と思考に溜息をつく。高校生らしい明るい笑顔で、こいつに合うフーズとおやつってどれですかね、と尋ねてきたお客様が連れていたポケモン。それを見た途端、私は動けなくなってしまったのだ。
俯いた私の腰のあたりを、イオンさんのタブンネがぽんと叩く。にこにこと優しいその顔に私は少しの間だけ元気を取り戻したけれど、視界の端、監視カメラの映像を流すテレビの中を見た途端にその気持ちはしぼんでしまった。
『お待たせいたしました! ええと、そちらのガバイト様のご相談ですね。フーズでしょうか? それとも、キズぐすりなど薬品関係でしょうか?』
慣れたように接客を始めたイオンさんに、高校生の彼も安心したように声を返す。その様子に申し訳なさとふがいなさで胸が痛み出して、次こそは自分で何とかしなければと決意が湧いた。
だけどその気持ちすら、画面に映った蒼のドラゴンポケモンを見ると瞬く間に消え失せて、足を動かなくしてしまう。きゅう、と鳴きながらカメラを向いたその黄色い瞳が私を見た気がして、そんなはずは無いのだとわかっていても、ぞくりとした感覚が全身に走っていった。
私が生まれ育ったカゴメタウンには、一つの言い伝えがある。
町のそばにあるジャイアントホールという洞窟に、遠い昔に宇宙から隕石が降ってきた。その中にはとても怖い、オバケのようなポケモンが入っていた。そのポケモンは夜になると冷たい風と共に現れて、人やポケモンをさらって食べてしまうのだ。
だから、夜には外に出てはいけない。そういう教えが町にはあって、住民たちはそれを守っていた。オバケの存在など誰も信じなくなった現代でも、町の住民はみんな心のどこかでオバケに対する恐怖と、ある種の信心深さのようなものがあったのかもしれない。
……と、思っていたのは五年前までだ。
なんであの時、よりにもよってジャイアントホールなんかに行ってしまったのだろうかと今でも後悔している。当時私は十五歳で、まだ小さかった弟が夕方になっても帰ってこなかったから慌てて探しに行ったのだ。
弟が十三番道路にいるのを見た、という町の人の言葉にいてもたってもいられなくなったのは今でもよく覚えている。もしも弟がジャイアントホールに行ってしまっていたら、と考えるだけで身体が凍り付くような思いだった。
既に傾いている太陽の下を走り、木々をかき分けて進む。いくら弟の名を叫んでも返事は無くて、気がついたら十三番道路を通り抜けていた私はジャイアントホールの草むらに入り込んでしまっていた。
いけない、と思った時には既に遅いのが世の常というものである。町では感じたことの無いような薄ら寒い風に鳥肌が立った私は、どうにかして早く出なければいけないという思いと、もっと奥に弟がいるかもしれないという思いを交錯させて草を掻き分けた。時折じっとこちらを見つめるようにして浮かんでいるルナトーンやソルロックは、本やテレビで見た時にはミステリアスで素敵に思えたのに、何を考えているのかわからない瞳には不気味さしか感じられなかった。
モンジャラやピッピを避けながら草むらを走るうち、もう方角すらも見失っていた。弟を探すことも十三番道路に戻ることも出来ず、私は洞窟を前にして立ち竦んだ。
どうしよう、そう思った時、後ろから鋭い声がかかった。
「おいお前、そこで何してる?」
振り返った私は、一瞬で全身を固まらせることになる。
私に声をかけたのは紫色の分厚いコートに身を包んだ老人で、白髪を覗かせる大きな帽子の下の顔は、私を咎めるように険しかった。その一歩後ろには黒いマントを纏った長髪の男性と、変わった髪型をした科学者風の男の人もいて、長髪の方は忌々しげな目で、科学者っぽい方はさしたる興味も無さそうに、私のことをそれぞれ見ていた。
勿論、その人たちも不気味だとは思った。町で見かけることなんか、いや、恐らくどこに行ったってそうそうお目にかかれないような怪しさを醸し出している彼らを、怖いと思う気持ちは当然あった。
しかしそれ以上に、彼らに追従しているポケモンたちの威圧感は凄まじいものだった。マニューラの眼が、金色に光って私を射抜く。サザンドラの三つの首が、鋭い牙をがちがちと鳴らす。ギギギアルの歯車が、無機質な金属音を響かせた。
こんな強そうなポケモンは、見たことがなかった。もし攻撃されたらひとたまりも無いだろうと、頭の中に警報が発せられる。
「答えられないのか! もう一度聞くぞ、お前はここで何をしてる?」
苛ついたように老人が言う。しかしそれでも、私の喉は動いてくれなかった。弟を探してるんです、小さい男の子を見かけませんでしたか。それだけ言えば良いはずなのに、その一言すらも出てこなかった。
黙ったままの私に、老人と黒マントはさらに苛立ったみたいだった。キン、と耳をつんざくような音がして、それを耳が認識した時には、私の首筋にマニューラの爪が突きつけられていた。
気絶しそうなほどの恐怖を覚え、目を見開いた私に黒マントが言う。
「ワタクシは、貴方くらいの年頃の子供が嫌いなのですよ……嫌な記憶を思い出しますからね。痛い目を見たくないというのなら、何をしていたのか早く言いなさい」
「我々も暇では無いんだ。かと言って、こんなところに一人でやってくるような奴には少々心当たりがあってだな……奴の仲間という可能性を考えると、黙って見過ごすわけにもいかぬ」
ぐ、と突きつけられた爪が肌に食い込んだ。サザンドラの三つの口が、今にも私を噛みちぎりそうに歯を打ち鳴らす。ギギギアルの歯車が、一層早く回転する。逃げなきゃ、言わなきゃ、と思っているのに身体はちっとも動かない。冷たい風が頬を打ち、身体の震えは恐怖によるものなのか寒さによるものなのかわからなくなってきた。
何も言わないままの私に舌打ちしたのは、老人と黒マントのどちらだろう。マニューラに何かを命じるように口を開いた老人に、もうダメだ、と思った私は思わず目を瞑った。
「――――――――」
その時だった。身の毛もよだつような何かの鳴き声が、草木と空気を震わせた。その声は、それまでに吹いていた風など比べものにならないくらい冷たいもので、この世のどんなものでもたちまち凍らせてしまうような、そんな力を持っているように思えた。
びくりと反応したのは私だけでは無い。苛ついていた老人と黒マントも、そして我関せずというように始終そっぽを向いていた科学者風の男もはっと顔をあげる。マニューラも声のした方を向いたために爪の位置が変わり、私はその場にへなへなと腰を抜かした。
ぎゅっと表情を引き締めた科学者風の男が、草を踏みしめて歩き出す。そして数歩進んだところで、まだ私を睨みつけていた二人をせき立てるように言った。
「そんな子供に構っている場合ではありません! 我々の存在に気がついているということです、一刻も早く行くべきでしょう!」
「しかし、……」
「アレが目覚めている今、その子一人に何が出来ると? 見た感じ、ちっとも戦えそうにないじゃないですか! 捨て置いても問題ないでしょう、行きますよ!」
老人と黒マントはまだ何か言いたそうな様子だったが、科学者風の彼の言葉に渋々といった感じでついていく。後に残された私は腰を抜かしたまま、木の幹にもたれかかってしばらく呆然とするしか無かった。がくがくと震えてへたり込んでいる私を、草むらに住むポケモンたちは遠巻きに観察していた。
あれからどうやって家に帰ったのか、今でも全く思い出せない。ほうぼうの体で帰路を辿った私は、どうやら入れ違いになっていたらしい弟と母がいる家の扉をくぐり抜けた瞬間、玄関に倒れ込んだのである。それから数日間高熱にうなされて、毎晩のようにあの場面を再現した悪夢を見ていた。
その後、ソウリュウシティは嘘みたいな大寒波に襲われて、街全体が凍り付いた。同時にプラズマ団という組織がイッシュのあちこちに現れて、威圧的な態度をとるようになった。それより二年前にいたような、ポケモンの解放を訴える組織と同じ名前を冠しているのに服装も雰囲気も全く違う彼らは、イッシュ中を騒がせた。
しかしそれも短い間のこと。詳しくは明るみに出なかったが、イッシュの平和は一人の女の子によって取り戻されたのだ。プラズマ団の姿はすっかり掻き消え、異常なほどの寒さはまるでそれが夢だったかのようにあっけなく過ぎ去った。
その後のカゴメタウンで変わったことと言えば、『オバケ』はキュレムというポケモンだったとわかったこと、それとそのキュレムは少女がどこかへ連れていったため、夜に出歩いても大丈夫になったことくらいである。得体の知れない不安感に縛られず、行動が自由になったカゴメタウンの住民は喜んだ。出張の多い私の父も、夜に戻ってくるのを避けるべく仕事先に泊まる必要が無くなったと笑顔で言ったし、母親も嬉しそうな笑みを返していた。夜は危ないから旅に行ってはいけない、という風習も意味を成さないものとなって、旅立てることを知った弟の喜びようといったらなかった。
カゴメタウンは、夜の恐怖から解放されたのだ。オバケにも凍てつく風にも怯えることなく、月の下を歩けるようになったのだ。
だけど、私は違った。私は夜どころか、朝も昼も夕方も、いつだって怯えるようになってしまった。
あの時、ジャイアントホールで私が見た人たちのポケモン。睨みつけてきた六つの瞳。ぎゅんぎゅんと勢いよく回る歯車。喉笛に突きつけられた、長くて鋭い爪。
そして、全身を凍らすような寒風を引き起こした、あの咆哮。
何度も何度も夢に出てきたそれは、私の心をどんどん巣食っていった。侵食された心はトラウマというものに変わっていって、私を強く締め付けた。彼らとは違う、あの時見たポケモンとは違うんだ。そう言い聞かせても、彼らに似たポケモンを前にするだけで、私は心臓を吐き出してしまいそうなほどの恐怖に苛まれるようになったのだ。
ポケモンが、怖い。
とりわけ、あの時目にしたような強いポケモンや、ドラゴンポケモンが、怖くてたまらない。
イッシュが寒くなったあの日を境にして、私はポケモンに恐怖を抱くようになってしまった。
「なんとか、しなくちゃ……」
バイトのシフトが終わって、信号を待つ私はポツリと呟いた。その声に反応したのか、隣のお兄さんが手にするリードに繋がれたポチエナが幾度か吠える。一瞬びくりと身体を震わせて、私は思わず逃げ出しそうになった足をどうにか踏みとどまった。
「あっ、すみません……こいつ、吠え癖がいつまで経ってもなくならなくって」
「いえ……こちらこそ、びっくりしちゃって申し訳ないです」
謝ってきたお兄さんに急いで返し、足下のポチエナにしゃがんで視線を合わせる。単に吠えただけのようだ、敵意の欠片も無い瞳がこちらを向く。はっはっ、と舌を出して私を見るポチエナはかわいいと思えた。毛並みの良い頭を少し撫でさせてもらったところで信号が変わり、私はお兄さんに会釈をして向こう側へと渡る。
どうにかしなくては、と思って五年間。ポケモンに対するトラウマは、徐々に克服出来ているはずだ。
あの日から間もない頃は、どんなポケモンでも見るなり発狂しそうになった。たとえそれがいかにも無害そうなルリリやププリンだろうと、はねるしか使えないコイキングだろうと、見た目も中身も優しさで溢れているミルタンクだろうと同じだった。ポケモンというただそれだけのことでも、私の恐怖を引き起こすのに十分だったのだ。
それでも、カウンセラーやセラピー、通院を重ねてトラウマは少しずつ薄れていった。ポケモンを見ても心を乱さなくなったし、大人しいものなら触れるようになった。大学に上がる頃には自分のポケモンを持つという目標を達成し、今はミネズミと一緒に暮らしている。そこまで変わることが出来た。
だけど、まだダメなのだ。あの出来事、あの恐怖を想起させるような怖くて強いポケモンと、私はちゃんと向き合うことが出来ないままなのだ。
どんなポケモンとも接することが出来るように、と始めたフレンドリィショップでのアルバイトでも、さっきみたいに結局逃げてしまうことばっかりで、同僚の方々や店長には迷惑をかけっぱなしである。ドラゴンタイプや強そうなポケモンが来る度にあんな調子なのだ、これでは本末転倒も甚だしいだろう。
「やっぱり、このままじゃいけない」
もう一度、そっと呟いた。私の右手には一つのモンスターボールが握られていて、傷のほとんどない表面は光沢を放っている。中にどんなポケモンが入っているかは、まだわからない。このボールに入っているポケモンは先ほど、バイト先に併設しているポケモンセンターの交換サービスでもらってきたばかりなのだ。
グローバルトレードステーション、通称GTS。世界中誰とでもポケモン交換を可能にするそのシステムの一つに、ミラクル交換というものがある。
交換相手は指定出来ず、交換希望ポケモンの特定も不可。誰とどのポケモンを交換したのかは、ボールを開いてのお楽しみというわけだ。ポケモンセンターのパソコンを使ってボールの中身を確認することも出来たのだけれども、私はあえてそうしなかった。
どんなポケモンが来ても、その子を受け入れる。
それが私の決意だった。何タイプのポケモンでも、どんな姿を持っていても、どれくらいの大きさでも関係ない。旅の途中に私の家へ立ち寄った弟が、「こいつ交換に出そうと思ってるんだよね」と一つのボールを示したのが三日前。その時にミラクル交換の話を聞いた私は弟に、自分に交換をさせてくれないかと頼んだのである。
「ま、どーしても無理だったら俺が引き取るよ」
何が来るかわかんねえんだぜ、と不安気に念を押してきた弟は最終的に折れてくれて、そんな言葉を残して旅の続きへと向かった。ふがいない姉でごめん、と心の中で言う。言葉にも顔にも出さなかったけれど、弟はパートナであるオノノクスを、私の部屋で一度たりとも出さなかったのだ。
次にあなたが来る時には、ちゃんとお出迎えするから。頭の中の弟にそう言って、私は手のモンスターボールにもう一度目を落とした。大丈夫。どんなポケモンでも、ちゃんと、向き合う。
あれこれと考えているうちに、下宿先であるアパートに辿り着いた。学校からもほど近いこのアパートは学生や若者の一人暮らしを対象としていて、ポケモンの規則もかなり緩い。あまりにも臭いが強かったり高温だったりする場合は手続きが必要だけれども、持ってはいけないという決まりは無いのだ。
だから、どのポケモンが来ても問題無い。改めて確認して、私はドアに刺した鍵を回す。ガチャリという音を立てて開いたドアの中に入ると、お留守番をしていたミネズミが駆け寄ってきた。
「ただいま、ナッツ」
抱き上げて頭を撫でる。大学に連れていくことは勿論出来るのだけれども、どうやら悪い意味でトレーナーに似てしまったらしい。ナッツと名付けたこのミネズミは私と一緒に過ごすにつれて、引っ込み思案の人見知りになってしまったのだ。外、取り分け人の多い所に行くことが苦手な彼女を無理に連れ出すのもどうかと思い、基本的にはこうして留守を頼むことにしている。
みはりポケモンなだけあってお留守番は得意らしいけれども、他のポケモンとも仲良くなれればいいと思っていた。だから今回のこれは私だけでなく、ナッツにとってもチャレンジなのだ。
そう思うと勇気が湧いてくる。大きな目をくりくりさせて私の方を見ているナッツに、「がんばろうね」と声をかける。ナッツはわかっているのかわかっていないのか、小さな耳をぴくぴくと動かして、片手で私の頬を軽くつついた。
「よ、よし。いくよ、ナッツ」
手洗いとうがいを済ませ、荷物を軽く整理した私は早速ポケモンを出してみることにする。私の緊張感をナッツも察したのか、半ば私の背中に隠れるようにしてボールをじっと観察していた。ごくり、と同じタイミングで私たちの喉が鳴る。
一旦深呼吸をして心を落ち着かせる。どんどん速まっていく呼吸はちっとも収まってくれなかったけれど、これ以上ドキドキしたって仕方ない。ふん、と覚悟を決めて、私はボールのボタンを押した。
ボールからポケモンが出る時特有の、赤い光が部屋に走る。鋭く眩しいその光に、私は思わず目を瞑ってしまった。
瞼の裏に見える明るさが弱まってきた頃を見計らって、私はゆっくりと目を開ける。光が形作っていった像は実体化を始めていて、徐々にはっきりと姿を現していった。
「………………え?」
クリアになっていくフォルムに、私の喉から声が漏れた。
ボールから飛び出した、新しい、私のポケモン。
このポケモンを、私は知っている。
忘れたくて、忘れられなくて、どうしようもなかった、そのポケモン。
半分以上が凍った、巨大な体躯。
部屋を埋め尽くすほどの影を落とす、氷の翼。
灰色の手足から伸びた鋭い爪と、口から覗く長い牙。
空洞のような隙間に光る、二つの瞳が、私の身体を一瞬で突き刺した。
あの日、私がポケモンに近づけなくなった日。あの時聞いた声の主の姿は見えなかったけれど、騒ぎが収束した後、イッシュに大寒波を起こした存在として姿形が公開された。三番目の竜は本当にいたのだと、世間では研究者を中心として大ニュースになっていたようだが、当時の私はそれどころでは無かった。テレビやインターネット、新聞などで見るその姿にジャイアントホールでの出来事を思いだし、震えるだけだったのだ。
それ以降も、幾度もそれを見ることとなった。ポケモンに慣れてきてからも、その姿は見る度にあの日の恐怖を想起させた。だから、なるべく見ないようにしてきたのだ。あの日のことを忘れようと努めるように、悪い記憶は一掃してしまおうと。
それなのに。
その、姿が、私の目に映っている。
私の部屋で、息をしている。
「……キュレム、」
あの日の咆哮でイッシュを凍りつかせ、拭いきれない恐怖を私の心に植え付けたそのポケモンは、私の目の前で、氷の身体を誇示していた。
「…………っ!!」
一瞬固まった思考が動き出す。逃げなくては。私とナッツ程度じゃどうにか出来るわけ無いし、このポケモンにおいてはもはや、バトルが強い弱いの問題じゃあ片づけられないだろう。とりあえず、少しでも早く離れることが何よりだ。
だけどそれは叶わなかった。ベッドを背にしてボールを開けた私とナッツに逃げ道など無くて、外へ続く扉も、小さなベランダも、トイレとお風呂のドアでさえ、その道は全てキュレムの大きな身体で遮られていたのだ。ただでさえ狭い、一人暮らし用のワンルーム。家具や天井を上手いこと避けてキュレムが出てきたのはラッキーだな、と場違いな考えが頭に浮かぶ。
七月の蒸し暑い部屋が、目を見張るスピードで冷えきっていく。それは恐怖によるものだけじゃない、本当に気温が下がっているのだ。瞬く間に下がった室温に、私は氷漬けになりそうなほどの寒さを感じる。この前夏毛に生え変わったナッツも、ガタガタと身体を震わせた。
キュレムの目が、ぎろりとこちらを睨む。氷で出来た頭部の中、闇のように深い黒に浮かんだ光は、見たもの全ての身の竦ませる輝きを放っていた。
終わりだ。頭の中で、そんな言葉が明滅する。
もう駄目だ、どうすることも出来ない。私はここで、死んでしまうのだろう。いつか感じた恐怖が、何倍にも膨れ上がってリフレインする。
克服した、はずなのに。せっかく、大丈夫になってきたのに。
それなのに。
「!! ナッツ、だめっ!!」
絶望のあまりベッドに座り込んでしまった私は、思わず叫び声を上げてしまった。まるで私を守るようにして、私の前に躍り出たナッツはキュレムを睨み返していた。私の制止の声も聞かないで、小さな身体を震わせたナッツが、全身の毛を総立ててキュレムへと飛びかかる。だめ、私の口からもう一度その言葉がこぼれ出る。
長い尻尾までピンと張り、ナッツはキュレムの頭にかじりついた。勿論、キュレムにとってはかすり傷にもならないだろう。だめだ。すぐ、ナッツは。
ナッツを助けなくちゃいけないのに、私の身体は力が抜けてしまって動かない。なんて情けないんだろう。あまりの恐怖で涙すら流せず、私は、これから起こる悲惨な光景を見たくなくて目を閉じてしまう。そうだ。せめて、これ以上の怖さを感じずに終わらせて欲しい。
「………………?」
しかしいつまで経っても終わりはこなかった。ナッツの悲鳴も聞こえなかった。部屋は依然として寒さに満ちていたけれど、それ以外は静かなままである。窓の外から聞こえてくるハトーボーたちの鳴き声は、のどかに響きわたっていた。
あまりに何も起きないので、私は少しずつ目を開ける。そして開いた先に見えたものを、無意識のうちに二度見してしまった。
キュレムは怒っている様子すらなかった。自分の鼻先に噛みついているナッツを引き剥がそうとすることもなく、ナッツが離れるのを待っているようだった。時折、困ったような動きで首が小さく私の方を向く。
まるで、これ取ってください、とでも言っていそうなキュレムに、ゆるゆると私は立ち上がった。目の前の巨体はまだ怖いままだったが、どうにか足の力は復活していた。震える手をゆっくり動かして、果敢にもまだくっついているナッツを抱き戻す。
ナッツを腕に収めた私を、キュレムの鋭い眼光が射抜いた。やっぱり怒っているのではなかろうか、と私はびくりと震えてしまう。だけど、キュレムのとった行動は攻撃的なものじゃ無かった。
「……えっ」
ぺこり、と大きな頭が下げられる。私やナッツ、部屋にあるものに当たらない程度の角度で動かされた首は、お礼を述べていると思って良さそうだった。
キュレムの目と、私の目とがまた合う。その瞳だけでも、もしかしたら私の頭くらいはあるのではなかろうか。この大きな顎でガブリとやられたらひとたまりも無いだろう、そんな考えが頭をよぎる。
でも、震えは先ほどより弱まっていた。部屋の寒さにも慣れてきた。私をじっと見つめているキュレムが、四肢を折り畳んでちんまりとしゃがみ込む。ちんまりと、なんて言葉がそぐわない大きさであるが、そんな言葉を使いたくなるくらいに穏やかな動作だった。
「…………………」
そっと手を伸ばす。触れた頭があまりにも冷たくて、私の心臓が跳ね上がった。
だけどそれは、怖さを生むものじゃ無かった。キュレムとはこういう身体なのだろう、怖がる必要は無い。そう思って、私は伸ばした手をゆっくりと動かしてみた。
「…………はは、」
キュレムが、気持ちよさそうに目を細める。その様子はまるで人間の子供のようで、小さなポケモンのようで。肩によじのぼってくるナッツの頭をもう片手で撫でてあげながら、私は思わず笑ってしまった。
「それにしても、なんで、こんな……」
こんなポケモンが、GTSに。その疑問は声にならないで、溜息として私の口から抜けていく。
何のポケモンが来ても受け入れる、とは言ったものの、まさかキュレムがやってくるだなんて思ってもいなかった。ほんの五年前までは存在自体が疑われていたのだ、希少価値だなんてものじゃない。『オバケ』だなんて言われてしまうくらいには、幻想上のポケモンだったのである。
ランダム交換に出されている以前に、誰かのポケモンとなっていることにも驚きだ。ジャイアントホールからはいなくなったようだ、と何の根拠も無く思ってはいたけれど、よもや捕獲されていたとは。もしかしたら私は夢を見ているのかもしれない、と思って頬を抓ってみる。痛い。
「ポケモンセンターに行けば、あなたのトレーナーは調べられると思うけれど……」
夢ではないようなので思案に戻る。GTSの係員に頼めば、『おや』など交換された時の情報を教えてもらうことは可能だが、それはやめておいた方がいいように思えた。何しろキュレムレベルのポケモンだ、もしかしたら悪い人が捕まえていたのかもしれない。そんな人のところにわざわざ返すのはイッシュのためにも、そしてキュレムのためにもならないだろう。
調べようとするなら、ポケモンを窓口に出さなければいけないこともある。「このキュレムのトレーナーを探したいのですが」だなんて言ったところで異常者と思われるのが目に見えているし、それが本当のことだとわかってもらえた時こそ大惨事だ。平凡で地味で目立たない、一大学生としての私の日常は一瞬で終わりを迎えるに違いない。
「………………」
それに。
大きな頭をじっとさせ、うなだれているキュレムを見る。ひんやりとした空気を放つキュレムは、その冷気によるものだけじゃない、寂しそうにしているように捉えられた。
もしも、キュレムのトレーナーが悪い人ではなかったとして。キュレムにとっては、それはまるで捨てられたという風に思ってもおかしくないのではないだろうか。交換に出されて、知らないところに行かされて。それを考えても、今は様子を見た方が良さそうだった。
幸い、キュレムは私の部屋にギリギリ収まっている。ちゃんとポケモンとして分類されている以上、ごはんはポケモンフーズなどで大丈夫だろう。この冷たさは冬だと困ってしまいそうだけれど、今は夏。ポジティブな考えをするのなら、むしろ冷房がいらなくて助かるかもしれない。
どうにかなる。
キュレムさえ良いのなら、このポケモンと一緒に過ごしてみたい。そう思った。
「ええと、これからよろしくお願いします……、えと」
ベッドから立ち上がって頭を下げた私は、そこまで言って言葉に詰まる。俯いていたキュレムが顔を少し上げて、どうしたんだというように首を捻った。ベッドの隅で様子を伺っていたナッツも不思議そうに私の顔をのぞき込んで、大きな目玉をきょろきょろとさせた。
私が黙った理由は、キュレムの呼び名である。もしかするとニックネームをつけられていたのかもしれないが、それを私が知ることは出来ない。知るためにはGTSまで行かないといけないのだ。それに、もしキュレムが前のトレーナーに手放されたポケモンなのだとしたら、その名前をひきずるようなことをするのも気が引ける。
かと言って、キュレム、と呼ぶのもどうなのか。しかし新しい名前をつける気にも、なんとなくなれなかった。
「ええと、…………キュレム、ちゃん」
しばらく考え込んだ末、私が呟いたのはそんな言葉だった。それは自分のことかというように、キュレムが私の顔をまじまじと見る。ぎらりと光る目が私を睨み、思わずびくりと飛び上がってしまった。気に入らなかったのだろうか、との不安が胸の奥でぐるぐると回り出す。
だけど、それはどうやら杞憂だったらしい。ひゅら、と短く鳴いたキュレムは、私のことをじっと見ているだけだった。本日二度目の脱力を迎えた私は、ほうっと息を吐きながら氷の頬に手で触れる。キュレムちゃん、ともう一度呼んでみると、空洞の中に見える瞳がほんの少しだけ、しかし確かに細まった。
ちょこちょこと足を動かして、ナッツが近寄ってくる。そのままキュレムに接近したナッツは鼻先でつん、と反対側の頬をつついた。自分の片足ほども無いナッツをちらりと見やったキュレムは、まるで委ねるように目を閉じる。二匹の様子を見ながら無意識のうちに口元を緩ませた私は、最大の難点であったはずの『怖いポケモンに対する恐怖心』が消えていることに気がついた。
人間、ボーダーラインを軽く超えた出来事に見舞われると、一周回って落ち着くものなのかもしれない。
「コチョウさん、なんかそわそわしてるねぇ」
バイトのシフトを終え、帰り支度をしている私に先輩が声をかけてきた。彼は私と違う学校に通っている一つ上の人で、ここでのバイトも長いらしい。常に調子良い感じでぺらぺらと喋っているこの様子を、世間では『チャラい』と言うのだろう。悪い人では無いとは思うけれど、引っ込み思案の私は少し苦手である。どことなくサンダースを彷彿させる髪の毛にそんなことを考えた。
「もしかして、コレ?」
からかうような笑みと共に先輩が小指を立てる。その意味するところは勿論違う、私は慌てて首を横に振った。それでも先輩はまだニヤニヤと「えー、絶対そうだと思ってたのに」などと、わざとらしく腕を組みながら言う。
違いますって、と否定を重ねる一方で、そんなに顔に出ていたのだろうかと内心で首を傾げた。なるべく平素と変わらないよう、自然体を努めていたというのに、これでは何の成果も無さそうだ。彼氏じゃなくってもさー、絶対何かあったでしょ、と金色のピアスを光らせた先輩の目は確信に満ちている。私が浮ついていることがバレているのは明らかだった。
違いますお疲れさまです、と強引に話を打ち切って会釈する。お疲れー、と軽いノリの声を背中に感じつつ、休憩室の扉を閉めた。
自分のポーカーフェイスを過信していたらしい、結構上手くいっていると思っていたけれども間違いだったようだ。よく『わかりやすい』と言われる原因の一つはこれだろう、隠しているつもりでいた気持ちや心が、あっさり顔に出ていただなんて恥ずかしいにもほどがある。
人生この先長い、もしかしたら私だってポケモンバトルに手を出すこともあるかもしれない。バトルは相手の手の内の読み合いだという、それなのにこんなわかりやすい性質をしていたらお話にならなそうだ。いつか始めるかもしれぬバトルのため、そしてそれ以前に今の日常のため。ポーカーフェイスに磨きをかけなければならない。
とりあえず今日は学校もバイトも終わり、後は家に帰るだけ。よし、と心の中で気合いを固めて表情を引き締めた。
きりりとした顔を作りながらショップ裏にある従業員通用口を出かかったところで、シャツの襟元をパタパタさせて暑そうにしている同僚のイオンさんが見え、お互いの存在に気がつく。これからシフトが入っているのであろう彼は挨拶の言葉を口にして、頭に乗っけたヤンチャムをそのままに、小さく首を傾げた。
「何か、いいことでもありました?」
ポケモンバトルは、始めないでおこう。
店長機嫌いいといーなー、と呑気に言った彼と、ぶんぶんと首を振って顔を赤くする私を不思議そうに見てくる、同僚のタブンネから逃げるように歩きながら、私は心からそう思った。
そわそわしている原因とは、言うまでもなくキュレムのことである。キュレムが私の家に来て三日間経ったけれど、今のところ何の問題も無く、部屋が手狭になったこと以外は平凡な毎日と言っても良いだろう。むしろ何も無さすぎて少し不安になるくらいだ。
キュレムはかなり大人しかった。それこそ、ソウリュウを氷漬けにしたとは思えないくらいに。しかしそれでも、あの子がキュレムであり、かつてのオバケであり、第三の竜であることは紛れもない現実なのだ。その証拠に、インターネットに溢れる情報も大学の図書室にある論文も、本屋に並んでいる学術書も、みんなあの子の姿に『キュレム』という説明を添えている。
しかし、それ以上私が考えたところでどうしようも無い。ビニール袋に入ったポケモンフーズの缶が、私が歩くのに合わせて音を立てる。伝説と謳われたポケモンでも味覚は存外庶民派らしい、アレコレ与えてみて一番気に入ったと思えたのは最安レベルのフーズだった。袋の中で揺れている缶は、うちのショップでは安価の王者と呼ばれているものである。
いいのかなあ、と思いつつ信号を渡る。横断歩道を半分ほど進んだところで、お散歩中らしいおばあさんとすれ違った。彼女の足下に寄り添うようにしているのは一匹のレパルダス。綺麗な紫色の尻尾が、一歩を踏み出すごとに緩やかな曲線を描く。
しなやかな身体に斑点を散らしたこのポケモンが、前はすこぶる苦手だった。別に見かけは怖くないし、ちょっと狡猾っぽいところもある種族と言えばそうだけれども、危険というわけでは無い。ただ、プラズマ団なる人たちがよく連れているのを見て、プラズマ団に対する恐怖とない交ぜになっていたのだろう。紫とピンクとクリーム色のカラーリングをした彼らはプラズマ団を想起させ、ペルシアンとかブニャットとか、似た系統のポケモンが平気になってもレパルダスだけは例外であったのだ。
それが平気になったのは、一体いつ頃だっただろうか。よく覚えていないけれど、遊びに行った友人の家にいたレバルダスがえらく人懐っこくって、じゃれつかれた拍子に気がついたら触れるようになっていたのがきっかけだったと思う。ゴロゴロと喉を鳴らして毛並みを擦り寄せてくるレパルダスを、私は確かに「かわいい」と感じた。そこに恐怖は、なくなっていた。
あんな簡単に、あれっぽっちのことで怖くなくなったのだ。私という人間は何とも単純だなあ、と思いながらマンションのエレベーターに乗り込む。微かに聞こえる機械音を耳に受けつつ数秒待つと、私の部屋がある階に辿り着いた。こつんこつん、と足音を響かせて扉の前まで進む。
「ただいまー」
鍵を回して扉を開くと、ちょこちょことナッツが玄関まで駆け寄ってきてくれた。その向こう、ワンルームの中央にうずくまっているキュレムが、氷の頭を少しだけ動かしてこちらを向く。それをちょっと傾けてみせたキュレムに、ナッツを抱きかかえた私はもう一度「ただいま」と言った。
夏用に買ってきた、綿生地のパジャマがちょっと肌寒い。随分と涼しさを漂わせている部屋で、私は衣替えの際にクローゼットの奥へとしまい込んだカーディガンを引っ張りだして羽織ることにした。お風呂上がりでほかほかしていた肌はあっという間に冷めきって、濡れた髪には冷たさすらも感じられる。
バスタオルにくるまっているナッツはいいが、キュレムをお風呂に入れるわけにはとてもじゃないけれどいかない。考えた末にタオルで身体を拭くことにした。こおりタイプだから溶けないように冷たい方がいいのかな、と思ったのだけれども、キュレムが好んだのは意外にも温かな濡れタオルだった。一説によるとキュレムは自身の冷気で自分を凍らせてしまっているらしい、元々が氷で無いなら人肌くらいがちょうど良いのかもしれない。
闇の中の目を気持ちよさそうに細めるキュレムの頬を仕上げにもう一拭きして、電子レンジの中のホットミルクを取り出す。まさか七月にこんなものを飲むことになろうとは、と思ったけれどもそれはそれ。早くも私のベッドで眠そうにしているナッツのバスタオルを毛布に変えて、私はその隣に腰を下ろした。
「……ん、あのね。今日は大好きなドラマがあるの」
普段、私はお風呂からあがったら割とすぐに寝てしまう。そんな私の生活リズムを覚えたのだろう、まだ寝ないのか、という視線をこちらに向けてきたキュレムを見上げて私はそう言った。
リモコンを操作してテレビをつける。ぴ、という電子音に、キュレムも画面の方へ首を動かした。透き通った羽の一部が液晶にかかっていてちょっと見えづらい、キュレムにバレないようにして私は苦笑する。それでも画面のほとんどは見えるので、温かなマグカップを手に持った私は意識をテレビへと移した。
程良い温度の牛乳がそっと唇に触れる。切ないバラード調のオープニングが流れ、タイトル文字が画面に浮かんで始まりを告げた。すぐさま提供のテロップに切り替わり、大手ボールメーカーやミュージカルアイテム会社の名前が次々に映される。
今期一番人気であろうこのドラマは、家族愛を描いたもので幅広い年齢層に受けている。主人公である若者は代々エリートトレーナーを輩出している家の生まれで、本人もトレーナー免許を取得した十歳の頃からエリート教育を受けてきた。が、大学に入り、色々な人やポケモンと接するうちに価値観に変化が訪れる。そのままエリートトレーナーに、ゆくゆくはベテラントレーナーへと続く階段を昇るはずだった彼は、他者と戦うのでは無く他者を助けるポケモンレンジャーになりたいと思うようになったのだ。
当然、家族は反対する。だから主人公はポケモンレンジャーを目指し始めたのをひた隠しにしていたのだが、そうそう上手くいくものじゃない。レンジャー養成スクールに密かに通っていた彼が教室から出てくるのを、現役エリートの姉に見つかってしまったのだ。
……というわけで、今週はその話を父親にリークされるところからスタートである。姉に見つかった時からそうなることを察していた主人公は家に帰るのを渋るが、相棒であるゾロアークの促しと、自分の覚悟を示すために父親と向き合うことにした。
『お前をそんな奴に育てた覚えは無いッ!!』
父親の怒号が主人公を撃つ。厳しい性格をしているとはいえ、自分をずっと育ててくれた実の父に向けられた言葉に口を噛んだ主人公の表情に、私は思わず鼻の奥を熱くしてしまった。ただでさえ涙腺は緩い方な上、こういうのに滅法弱いのだ。急いでマグカップを置き、脇のティッシュに手を伸ばす。
『隠してたのは悪かったよ……だけど俺は本気なんだ! 誰かのためになりたい、誰かを助けるポケモンレンジャーになりたいんだ!』
『この家がエリートトレーナーの血筋であることはお前も知っているだろう! 我が一家に生まれた以上、エリートトレーナーとして生きるのがお前の一番の幸せなんだ! それがどうしてわからない!? 私も母さんも、そのためにお前を育ててきたのではないか!!』
『それはわかってる。俺をこんなに強いトレーナーにしてくれたことには、感謝しようとしてもしきれない。だけど……だけど、バトルだけじゃ駄目なんだ! 自分の強さのために戦うんじゃなくて、他の誰かのために……』
『うるさい!! まだ何のトレーナー種でも無い癖に、知った風な口を聞くな!!』
ナッツはすっかり夢の中だが、鼻をすする私の隣でじっとしているキュレムは画面を見つめていた。ドラマを観ているのだろうか、人間の言葉がわかるのならばテレビの内容だって理解出来てもおかしくは無い。しかし先週まで観ていないであろうキュレムに、ストーリーの全貌はわかるのだろうか。
そんな疑問が頭をよぎる。テレビの中では未だ親子のぶつかり合いが続いていて、互いに譲る様子は無い。父親の方は一見暴論を振りかざしているように見えるけれど、彼にだって事情があった。前々回での回想シーンで明らかになった過去。遅咲きタイプだったため、エリートになるまで物凄い苦難を経た父親。息子である主人公にはそんな思いをして欲しくないと、主人公が幼い頃から才能を開花させられるような教育を試行錯誤でしてきたのである。
父親には、父親の事情がある。エリートになって欲しいというのは父親の切なる願いであり、主人公の幸せを心から思っていることに間違いは無い。だからこそ、主人公が慣れない道に踏み出して失敗することなどあって欲しくない、そう思う一心で反対をしているのだ。
堪えきれない涙をティッシュで拭う私はそれを知っているが、当然ながら主人公は知らない。白熱する口論はどんどん激化し、悲鳴のような声で主人公が『父さん!!』と叫ぶ。
『父さんなどと呼ぶな!!』
売り言葉に買い言葉、父親も激昂を隠さない言葉を返す。怒りの中に悲痛さがにじみ出た声で、父親は息子を睨みつけた。ああ、と私は胸が締め付けられる。
『お前みたいな親不孝は、俺の息子じゃない!!』
そう、父親が言った時だった。涙で歪んだ視界の端に、私は一つの変化を捉えた。
「…………キュレム、ちゃん?」
画面に目を向けたままのキュレムは、ひどく寂しそうな様子をしていた。凍りついた頭部からは何の表情も、そして感情も読み取れない。
しかしそこには、確かに寂しさがあった。寂しくて、悲しくて、冷たいものがあった。
「……どうしたの?」
父親の言葉に部屋を飛び出した主人公は、その勢いで家を出てしまう。だけどそんなことはどうでもよかった。あれほど楽しみにしていたドラマが、今は頭に入らない。ただ、隣で固まっているキュレムのことだけが気になった。
私はこの子のことを何も知らない。強い氷の力を持っていて、五年前に何か悪用されたらしいことぐらいしかわからない。どんな風に過ごしてきたのか、どんな人と関わってきたのか、どんなポケモンに出会ったのか。それは、何一つ私の知るところでは無いのだ。
「…………キュレムちゃん」
なんでそんな、寂しそうなの。
尋ねようとした私の声は言葉にならなかった。聞いたところでキュレムが答えてくれるわけもないし、それ以上に、もしもキュレムが答えを告げてくれたとしても私が理解することは不可能だ。
何か嫌なことでも思い出したのだろうか。仮にこの子が本当にトレーナーに手放されたのだとしたら、まるで父親に見限られたかのような息子である主人公にそのことが重なったのかもしれない。考えても正答は出ないとわかっていても、私の頭に色々な想像が浮かんでは消えていく。
それでも、結局何も出来ない。私に出来ることなんて、臆病者でポケモンを怖がっているような私に、キュレムが来る前はドラゴンポケモンに近づけもしなかった……いや、今だって、キュレム以外のドラゴンタイプや、強い感じのポケモンは駄目なままだ。今日だってバイトの時に、ジバコイルを連れたお客様が話しかけてきませんようにと内心で願ってしまった。ギギギアルを思い出す、光沢を放った身体に照明が反射するたびに震えていた。何も買わずに出ていったことに安心してしまったのだ。
それに、キュレムだってまだ怖い。大きさとか形とか、鋭い爪と牙とか。絶えず放っている冷気だって、少しでも敵意を帯びたら恐ろしいものにとって変わる。「想像よりも大丈夫そう」というだけで安堵の材料ではあるものの、ふとした瞬間に接するのを躊躇ってしまっていた。
何も、変われていない。GTSでキュレムを受け取った時から、私は何も成長していない。
こんな私に、出来ることなんか。何一つ。
「………………?」
ふと、片頬に当たる冷気が強くなったのを感じた。俯いていた顔を上げる。と、キュレムが長い首を伸ばして、私を覗き込んでいるのがわかった。
相変わらず何を考えているのかわからない、目とも呼べない目である光が空洞の中に宿っている。真相こそ謎であるが、ゆらゆらと揺れるそれはまるで、私を心配しているように闇を漂っていた。
「キュレムちゃん……」
なんで、私なんかに、そんな。そう尋ねる代わりに、私はキュレムの顔に手を伸ばす。気がついたら伸ばしていたのだ。
ひんやりとした感触に続いて、突き刺すような冷たさが皮膚を刺す。氷に直接触れているのだから当然だ、だけどそれでも、私は手を離さなかった。
手から腕へ、腕から全身へと冷気が這い上がる。鳥肌が立ったが気にしない。固い頬にあてた手をさらに動かして、私はキュレムの首に腕を回した。
寒くて、冷たい。
でも。
「ありがとう、キュレムちゃん」
口をついて出たその言葉は、『キュレム』じゃなくて『キュレムちゃん』に向けたと思う。オバケと呼ばれるような氷の竜じゃなくって、今私と一緒に暮らしている、このポケモンに。『キュレムちゃん』の冷たさは心まで凍りつかせるようなものなんかじゃなかったし、鋭い牙や爪はこの部屋の空気までもを引き裂いてしまうものでも無かった。
キュレムだって、ただ一匹のポケモンなのだ。化け物でも怪物でも無い、ポケモンとして生きているのだ。
テレビではCMを挟みながら、ドラマがまだまだ続いている。どこまでストーリーが進んだのかもうわからない、リモコンの電源ボタンを押すことすら惜しかった。今は、この子のことだけ考えていたかった。
主人公と、彼の友達の声がスピーカーから響いている。それを耳に滑らせて、寒い寒い七月の部屋で、私はキュレムの冷たい身体を抱き締めていた。
ぶる、と私は身震いする。冷房もそこまで効いていないのに何故、とでも思われたのだろう、数席を挟んだ場所に座っていた生徒がちらりとこちらを見た。
昨日、あのままキュレムにくっついて寝てしまったから風邪気味なのかもしれない。身体の中から湧き起こる寒気に、持ってきておいたカーディガンを羽織ることにした。鳥肌の立っていた腕を袖に滑り込ませる。
本当ならば安静にして、早めに治した方が良いのだろうけれど、今日はそういうわけにもいかない。とある講義のゲストスピーカーとして、シキミさんが来ることになっているのだ。四天王の一人を務める彼女は同時に若い作家でもあり、人間とポケモンの関係を巧みに表現していると人気を集めている。
「これは、アタシたちのところに挑戦しにきてくれたトレーナーさんに言っていることなんですけれど」
講堂のステージでシキミさんが話す。眼鏡の向こうの丸い瞳はいたずらっぽく、にこにこ笑顔と相まって愛らしさがあった。四天王にして人気作家という大物だけれども、見た目にも言葉にも、どこか親しみやすい雰囲気を感じる。
なんでこんな著名人が呼べるのか、と生徒の間で様々な憶測が飛び交っていたが、どうやら今年度ホドモエ大の文学部講師に就任した人にシキミさんの知り合いがいたらしい。今日は私のような学部生だけでなく、一目見てみたいという他学部の生徒や他校の人たちも来ているようだ。講堂はほぼ満員である。
「人には人の、ポケモンにはポケモンの物語があるんです。世界には人もポケモンも数え切れないほどいますけれど……だけど、その分だけ、その数だけ。この世界には『物語』があるんですよ」
明るい声で、シキミさんは語る。人には人の物語。ポケモンにはポケモンの物語。なるほど、キュレムのようなポケモンは確かに物語を持っていそうである。それも、壮大な大長編といった感じの。
「その『物語』の中の主人公は、その人、そのポケモンです。アタシの物語の主人公はアタシですし、この子、アタシのシャンデラの物語では、シャンデラが主人公。カトレアちゃんやギーマさん、レンブさんの物語ではあの三人がそれぞれ主人公です……あ、ちなみに。アタシが不在のため今日はリーグがお休みなんですけど、それをいいことに三人は用もないのにホドモエまでついてきました」
今頃アタシそっちのけでマーケットで遊んでるんじゃないでしょうかね、とわざと拗ねた口調で言ったシキミさんに、講堂に笑いが巻き起こる。
笑い声が響く中、私はシキミさんの隣で揺れているシャンデラの蒼い炎を見てぼんやり思う。シキミさんの物語では、シキミさんが主人公。シキミさんのポケモンも、四天王の皆さんも同じ。
キュレムやシキミさんたちまでいかなくとも、確かにみんな、物語を持っているだろう。例えば右斜め前に見える青髪の男子生徒。彼はエリートトレーナーとして学内で有名な四年生だ、きっと胸の躍るような物語の主人公であるに違いない。
或いは、通路を挟んだところにいる女子生徒。講義の始まる前の休み時間に聞こえてきた彼女とその友人らしき人の会話は、なかなかに波瀾万丈と言える恋愛の話だった。結構エグい話になりそうだけれども、それでも主人公たり得る人だと思う。
それ以外の人たちも。休み時間、ポケモンと一緒に過ごしている他の生徒たちを思い出す。みんな自分のポケモンと楽しそうな時間を送っていた、彼らも彼らのポケモンも、それぞれの物語があるのだと思える光景だった。
じゃあ、私は。
ポケモンを怖いと思うようになったあの日から、恐怖の気持ちは抜けないまま。決して足を止めているつもりは無いけれど、確実に迷惑をかけている。
もしも私が、物語の読者だとしたら。
こんな主人公を、果たして好きになれただろうか。
「えー、話を戻します。そしてですね、人の物語やポケモンの物語、そうやって単独のものも勿論素敵なものです。 ですが! もっともっと、素敵なものがあると、アタシは思うんですよ!」
具合があまり良くないせいか、思考が後ろ向きになっていく私に関係なく講演は続く。少しだけ声のトーンが高くなったシキミさんは、「それはですね」と数秒勿体ぶって言った。
「人とポケモンの物語です! 人だけでもポケモンだけでも無い、人とポケモンが助け合う物語。それこそが、アタシが書きたいと思うもので……そして同時に、読みたいと思うものなのですよ」
さっきまで笑っていた聴衆が静まり返る。そんな講堂を一度ゆっくり見渡して、シキミさんは最後にシャンデラに目を向けた。穏やかな笑顔を浮かべた彼女は、相棒であるというそのゴーストポケモンと視線を交わし合う。
「人はポケモンと一緒にいることで、自分の物語をより良いものに出来る。ポケモンは人と一緒にいることで、より素晴らしい主人公になれる。私はそう思っていますし……それを裏付けてくれた、素敵な挑戦者たちも、沢山いました」
彼らはとても魅力的な主人公たちでしたね、とシキミさんは思い出すような口調で言う。彼女の言葉に、話を聞いていた生徒のほとんどが鞄の中や机の上にあったボールをそっと手にとった。前の席の男子生徒が、黒地に黄色いラインの走ったボールを優しく撫でる。
きっと、みんな自分たちの『物語』を思い描いているのだろう。今まで紡いできた話と、これから紡いでいくであろうそれが、ここにいる生徒の頭に浮かんでいるはずだ。『主人公』の入っている、『主人公』である誰かのボールがかつんと音を響かせる。
ここには、シキミさんが言うところの『素敵な物語』が沢山ある。ここだけじゃない、世界中に溢れているのだ。人とポケモンが力を合わせて生み出していく、人とポケモンの物語が。
じゃあ、私は。熱を持ってきたように思える頭の中に、そんな文字列が再び現れる。
恐怖に苛まれて、その物語を紡ぐことすらもやめてしまった私はどうなのだろう。それではいけないと思って努力はしてきた、だけど、それはちゃんと物語になっているのだろうか。一度やめたものを取り戻そうとして、それは果たして間に合っているのだろうか。
キュレムの姿が浮かぶ。ナッツの姿や、お客様のポケモンの姿。弟のオノノクスだって。
私は彼らとの『物語』を、刻んでいると言えるのか。
「あ、いけない……ついつい喋りすぎちゃいましたね。今日の本題に移らないと」
翳ってきた私の思考を打ち止めるように、シキミさんがぱちんと手を打った。ステージから離れたこの席からでもわかる、白い両手が何枚かの資料をめくる。これこれ、と言った彼女は「では、今日のメインテーマです!」と告げてから、資料の内容を目で追った。
「これはイッシュの正史にはおろか、神話としても消えかけていた話なのですが……最近、ダイビング技術の発達と研究者たちの奮闘によって浮かび上がってきた一つのストーリーです。遠い昔にいたという、王様の話なんですよ」
古典を勉強されている生徒さんたちにとっては特に面白い話かもしれません、と前置きしたシキミさんの優しい声が読み上げるその物語が、マイクを通したスピーカーから響きだした。
キュレムが私の家の住民となって、早十日。
ゆっくり寝たら、風邪はすぐに治った。キュレムは相変わらず大人しく、ナッツは相変わらず外に出たがらない。私も相変わらず、ドラゴンポケモンが苦手である。
キュレムがキュレムという種族である以外は、特別感の無い日々だ。何の変哲も無い、穏やかで平和な毎日。一定の涼しさを保った部屋で、私たちはのんびりと過ごしていた。
日曜日である。外はじめじめと蒸し暑く、夏の雨が窓ガラスを叩いていた。開ければさぞかし鬱陶しい湿気がこの部屋に満ちることになるのだろうけれど、キュレムのおかげでひんやりとした室内は外の様子に関係なく快適だった。役目を失ったエアコンが部屋の上部でそっと眠っている。
バイトの無いせっかくの休日だしどこかへお出かけしたら良いのかもしれないけれど外出嫌いのナッツは元より、キュレムを連れてのこのこ行ける場所など無い。私もあまり外に出るのは好きじゃないし、家でゆっくり過ごすことにした。
昨日の夜からずっと聞こえる雨の音が窓越に響く。一緒に過ごすうちにわかったのだけれど、キュレムは意外にも熱いものが好きだった。冷凍庫にあったヒウンアイスよりもきのみスープを好むこの子は、温かいタオルを気に入っていたからそれも当然なのかもしれない。
今も、キュレムの前には空になった皿が置いてある。その中に入っていたのは昨日の残り物のシチューで、電子レンジから取り出した時には湯気をたてていた。顔の氷が溶けないか少し心配になったけれど、とても固いそれはシチューごときじゃ変わらなかった。
ゆっくり起きて、遅い昼食をとって。時計の針は四時を回った辺りだけれど、ガラスの向こうに見える灰色の空は目が覚めた時とあまり変化が無いように思えた。さして強くも弱くもない、勢いを変えない雨は降り続く。
キュレムの羽を滑り台のようにしていたナッツは、遊び疲れたのか寝てしまった。食事を済ませた私たちの間には当たり前ながら会話は無く、しんとした沈黙が部屋を包んでいる。テレビでもつければ良いのかもしれないけれど、観たい番組があるわけでもない。雨の音だけが聞こえる部屋は、変わらず涼しかった。
「昨日ね」
呟くように口を開く。私の声に、キュレムはひゅら、と短く鳴いて返事をしてくれた。身体が凍り付いているせいで一見無機質に見えるキュレムだけれど、体内から出ているその声は、普通のドラゴンポケモンのように生々しさを伴っている。とはいえ、私に対してするこの鳴き方は恐ろしいものではない。軽い相槌のような響きを持つ、耳にすんなり入ってくる音だ。
「バイト先に、マニューラを連れたお客様が来たの」
キュレムが聞いてくれているようなので、私は話を続ける。コップの底に残った紅茶は冷めきっていて、沈んでいた茶葉のせいで色濃かった。
「私、マニューラが苦手なんだ。五年前……あのポケモンの、長い爪を向けられちゃってから、どうしても」
喉元に突きつけられた切っ先の感触が蘇る。思い出すだけで体温を下げるその記憶は、あの金色に光る両眼と一緒になって浮かび上がった。
あれ以来、私は苦手とするポケモンの中でも、マニューラに近づけないでいた。もしかしたらドラゴンポケモンよりも避けていたかもしれない。直接殺意を向けられたことは、今でも深い影となって私の中に残っている。
黙った私に、キュレムが視線を向ける。呼吸に混じって低い唸り声が聞こえた。それに首を振って、私は口を開く。
「でも、昨日お店に来たマニューラは……ちっとも、怖くなかったんだ」
友達の家にいたレパルダスの可愛さに、私は、プラズマ団に植え付けられていたレパルダスへの恐怖心を失った。それと同じだったのだ。お客様の背中に抱きつき、ポフレをねだるその姿は、あの時私を刺そうとしたのと同じポケモンだとは到底思えなかった。
しかし同時に、同じポケモンなのだということもちゃんとわかった。あれは『マニューラ』という同じ種族であり、個体が違うだけなのだと。私がずっと、怯えてきたポケモンなのだと。そう、思った。
「なんでなんだろうね」
ふっと、息を吐くような小ささで私は言ってみた。首を傾げたキュレムに笑いかけ、冷えた空気に目を閉じる。
「私が怖いと思ったのはあのマニューラだけで、他のマニューラは何も怖くない。そのくらい、頭では理解出来てたんだよ。ずっと前から……それこそ、あの日から、わかっていたつもりだった」
だけど、実感を伴ったのは昨日だった。
全てのマニューラを、全てのギギギアルやサザンドラを……全てのポケモンを、怖がる必要などどこにも無いのだと。
そんなこと、飽きるくらいに言い聞かせてきた。理論的にならば理解していた。でも、胸に落ちてきた、頭の中の方まで染み入ったのは、昨日が初めてのことだった。
「どうして、今まで気がつかなかったんだろうね」
私の疑問に、キュレムは答えない。もしも答えを持っていたところで、この子の言語を私がわかるはずもない。
「……明日は雨、止むといいね。キュレムちゃん」
話を変えた私に、キュレムはもう一度「ひゅら」と鳴き返す。相も変わらず降り続く雨は小さなベランダをひっきりなしに叩いていて、私たちの呼吸音を掻き消した。
キュレムがうちに来て、二週間が経過した。あの子が私の部屋にいるのも、私の部屋が常に涼しいのも、もはや当たり前のことになっていた。
今日はバイトが休みである。学校の授業が終わった私は帰り道に本屋に寄って、旅行雑誌を何冊か買った。大自然の絶景を表紙に謳ったシンオウ地方のガイドブックが、紙袋の中で音を立てている。
いつまでも私の部屋だけにキュレムをいさせるのはいかがなものかと思ったが、しかしキュレムというポケモンである以上どこかにホイホイ連れていくことは出来ない。野生のポケモンはともかくとして、他の人間がいるところには行けないだろう。うっかり写真でも撮られてネットで拡散されたら、収集がつかなくなるどころの話じゃ済まない。
それならば人目の無い場所が前提となるけれど、ジャイアントホールにわざわざ連れて行くというのも考えものだ。トレーナーすらも立ち入らない場所と言えばあそこくらいしか無いけれど、それがダメならイッシュ以外の地方を当たった方が早い。シンオウは自然が豊かで、かつ人口も少ないから良いかもしれない、と思った私は雑誌を買ってきたのである。
いつも渡る信号で、大きなオコリザルとすれ違う。大変気性の荒い種族として知られているオコリザルは、力も強いため扱うにはある程度の腕力がトレーナーにも求められることで有名だ。下手をしたら、血管の浮き出る拳に骨を折られるくらいの話では済まないという。野生の群れには絶対に近づいてはいけないとは、よく知られた話である。
だけど、私とすれ違ったそのポケモンは、自慢の拳を振るう素振りもなかった。固い毛並みに覆われた身体の真ん中あたりから伸びている腕は確かに猛々しかったけれど、その先の手は殴ることは無く、人間の手と繋がれていた。
オコリザルよりもずっと小さな男の子は、何があったのかぐずっている。そんな男の子の手を引くオコリザルは顔こそ仏頂面なものの、そこからは怒りの欠片も感じられない。歩くスピードを男の子に合わせ、何度も何度も顔を覗き込んでは背中を叩いたりしている様子は、まるで優しい兄のようだった。
オコリザルと手を繋いで、少年が歩いていく。彼らの様子に数秒目を奪われていた私も、点滅し始めた信号に気がついて反対側へと進み出した。手に持った紙袋の中身がガサリと揺れる。
早く帰ろう、と思った。無性に、ナッツとキュレムに会いたかった。ナッツとキュレムと一緒の部屋に戻りたかった。
それに、キュレムに伝えたいことがあった。早く行かなくては、と私は歩幅を早めて家路を急ぐ。いくつかの曲がり道の先、住んでいるマンションの入り口を抜けるなり、私はエレベーターに飛び乗った。階数ボタンを押して扉が閉まり、何秒かの静けさを経て狭い個室から足早に出る。
「…………?」
ふと、私は一瞬足を止めた。私の部屋の前に、一人の女の子が立っていたのだ。
Tシャツとミニスカートに合わせたスニーカーという動きやすい服装、暑い中履いているレギンスはスカートの中を見えないようにするためか、それとも草などから素肌を防ぐためか。カジュアルなデザインのキャップも相まって、恐らく旅トレーナーさんなのであろうという印象を受けた。頭の上でお団子にした長い髪は、ツインテールとなって腰の辺りまで垂れている。私よりも少し年下、学校に行っていたら高校生くらいだろう。細い身体つきはしかし同時に健康的で、活発なイメージを抱かせていた。
こんな女の子を、私はどこかで見たことがある気がする。テレビかインターネットか、それとも新聞か。必死に記憶の糸を手繰り寄せてみるが、もやもやと霞んだ情報は思い出せなかった。まあ、旅トレーナーならばバトル大会に出たりもするであろう、そこで上位入賞して、その報道の模様を見たのかもしれない。
そんな風に結論づけて、でも、なんで私の家にこんな人がと思う。旅をしているトレーナーは弟以外に知らないのだ、カゴメタウンで育った私の友人たちは、町の伝承によって旅をしなかったのだから。弟の世代あたりからは旅に出る人もぐんと増えたけれど、そのあたりの子たちに知っている人はいない。
誰だろう、エレベーターを降りられないまま私は頸を捻る。もしかしたら弟の知り合いで、弟がここに来るよう連絡したのかもしれない。私は何も聞いていないけれど、言い忘れという可能性もあるだろう。それならば失礼の無いようにしなくては、と思って足を踏み出した。
「……あっ!! あのっ!!」
背にしたエレベーターの扉が閉まる。それと同じタイミングで、女の子が私の存在に気がついた。
大きな瞳が見開かれ、私を直視する。桃色に染まった頬は可愛らしさを感じさせたが、その表情はかなり切羽詰まったものに見えた。ツインテールが空中に綺麗な弧を描く。
「えっ……?」
急に大声で話しかけられた私は、何と返すべきなのかわからず立ち往生してしまう。そんな私に駆け寄った女の子は息を切らしていて、困惑と期待と不安と、そして明確な焦りが浮かんだ両目は瞬きすることすらも忘れていた。
お互い何も言わず、しばしの沈黙がマンションの廊下に訪れる。口をぱくぱくさせていた女の子は、すぅ、はぁ、と何度かの呼吸を繰り返した。
「あの、突然来て、すみません」
「は、はい……」
「私、ヒオウギシティのメイっていいます」
曖昧に頷いて、私は彼女が口にした言葉を胸の中で反芻する。メイ。どこかで聞いたことがある気がするけれど、少なくとも知り合いの名前では無い。じゃあ改めてこの子は誰だろう、と脳味噌をフル回転させる私に、メイと名乗った彼女は隠しきれない焦燥の滲んだ声で言った。
「えと、いきなり本題で申し訳ないのですが」
彼女の視線はさっきから、私を離さない。それから逃れることも出来ずに立ち尽くすしか無い私を見たまま、メイさんは「あの」と前置きしてから言葉を発した。
「あなたの家にいるキュレム、あの子、私の友達なんです」
「キュレム!!」
玄関の扉を開けるなり、メイさんは飛ぶようにして部屋に入っていった。鍵の音を聞きつけていつものように出迎えようとしてくれたナッツが、自分の横を猛スピードで通り過ぎる彼女に驚いている。恐らくナッツに気がついてもいないであろう、長い髪を揺らしたメイさんはほぼ叫ぶようにしてその名を呼んだ。
「キュレム……!!」
呼ばれたその存在も、彼女の声に大きな反応を見せた。部屋のものを崩したり壊したりするのを考慮しているらしく、立ち上がることはおろか動くこともほとんど無かったキュレムが、メイさんの声と同時に四つの足を動かしたのだ。羽の先が壁にぶつかって、すぐに元の姿勢に戻ったけれども顔はメイさんの方に向いたままである。
メイさんは、そんなキュレムに飛びついた。氷の頭に腕を回した彼女は、ごめんね、という言葉を何度も何度も繰り返しキュレムに言った。
「ごめんね……私が悪いの、私がドジだから……ごめんね、キュレム」
手放される思いなんて、二度とさせないって約束したのに。涙まじりのメイさんの声に、キュレムは静かに目を閉じていた。光の消えた闇を内包する頭部が、そっとメイさんの身体に預けられる。
メイさんの泣き声が響く部屋に、私は近づくことも出来ずぼんやりと立ちすくんでいた。動かないままの私を不思議に思ったのだろう、ナッツがちょこちょこと近寄ってきてスカートの裾を引っ張る。その感覚で、私はようやく意識を取り戻した。とりあえず玄関の扉を閉める。丸い瞳を未だこちらに向けているナッツを、一度しゃがみ込んで抱き上げた。
キュレムを抱き締めたまま、メイさんはしばらく泣いていた。腕に収めたナッツの温かさと一緒になって、私の胸に安堵が満ちていく。
あの子のトレーナーは悪い人なんかじゃなかった、あの子を悪用する人ではなかったんだ。ようやくそんな思いが湧いてきて、私はほう、と溜息をついた。何を笑っているのか、という風に見上げてくるナッツに頬ずりをする。
「ちょっと寂しいけれど……でも、ね」
メイさんに抱かれ、キュレムは幸せそうだった。そこに表情なんか無いはずなのに、何故だかキュレムが笑っているように見えた。それは多分私の見間違いなんかじゃなくて、本当のことだと思う。
キュレム、キュレム、と名前を呼ぶメイさんの声が、涼しい部屋に満ちる。安心と嬉しさと、そしてほんの少しの寂しさが一緒になった気持ちに、私は目の奥が熱を帯びていくのを感じた。
「本当に、本当にお世話になりました」
玄関に立ったメイさんが、深々と頭を下げる。恐縮しきってしまった私は慌てて首を横に振った。
「いいんですよ! 仕方ないです、間違っちゃうことくらい誰でもありますって」
メイさんは落ち着いた後、なんでキュレムというポケモンがGTSに出回ってしまったかを説明してくれた。驚いたことにメイさんは、イッシュを揺るがしたソウリュウ凍結事件を解決し、プラズマ団を壊滅に導いた一人らしい。そしてようやく思い出したのだけれども、メイさんはポケモンリーグのチャンピオンを倒したトレーナーだ。道理で、顔や名前を知っているはずである。
さて、イッシュの英雄となったメイさんはチャンピオンの座につき続けることは望まず、そのまま旅を続けることとなった。細かい話は聞けなかったけれど、殿堂入りを果たした少し後にキュレムはメイさんのポケモンとなったのだという。プラズマ団に利用されていたキュレムは解放され、ジャイアントホールに戻っていたらしい。
オバケと忌み嫌われ、やっと自分の元に来てくれた者は自分の力を目当てとしていた。それが必要なくなったからあっけなく捨てられ、キュレムはどんな気持ちであの洞穴に帰ったのだろう。
ぐ、と私の手に力が入る。メイさんも目を伏せて、唇を噛みしめるようにして言った。
「この子とトモダチになろうと思ってジャイアントホールに行った時、とても冷たい目をしていたんです。だから、もうずっと、寂しい思いなんかさせないって誓ったのに……」
「………………」
「それに……あんなやり取り、目の前で見ているから……尚更……」
呟くみたいに紡がれたメイさんの言葉の意味はわからなかった。聞かない方が良いように思われたので、私は黙っていた。テレビの親子喧嘩を見るキュレムの様子が脳裏に浮かぶ。
メイさんの気持ちが通じて、キュレムはメイさんと共に行くことを選んだ。しばらく一緒に旅をしていたのだけれど、ある日事故は起きてしまった。
バトルサブウェイにチャレンジするため、メイさんはキュレムを一度ボックスに預けたという。そのままGTSを使おうとしたところまでは良いのだが、ランダム交換に出すはずだったポケモンと間違って、隣にいたキュレムを選択してしまったらしい。
とんでもないミスですよね、と、もの凄く申し訳なさそうな顔をしてメイさんは重ね重ね謝ってきた。メイさんが間違いに気がついた時には既に遅く、キュレムはGTSの海に放り出されてしまったらしい。しかもどこの誰と交換がなされるのかもわからないシステムだ、パソコンを前にして、メイさんはしばらく動けなかったと言うが同感である。
交換相手がホドモエのセンターを使った、ということまでは割と早い段階でわかったみたいだが、その先が長かった。ある程度の手続きを踏めば交換相手をセンターに教えてもらえるといえばそうなのだが、何せ交換に出したのがキュレムなのだ。正規の手続きを踏むわけにもいかず、人脈を駆使したメイさんが私に辿り着いたのは、交換から二週間が経った今日というわけである。
「でも、交換相手があなたで本当に良かったです。もうおしまいだと思いましたから……キュレムの力を使えばイッシュを征服することだって出来るかもしれない。そう考える人がいてもおかしくないから、もう、キュレムは無事じゃいられないと……」
それどころか、ちゃんと受け入れてくれる人で。本当に良かった、とメイさんはもう一度繰り返した。その言葉が恥ずかしくて、私は思わずはにかんでしまう。こちらこそキュレムと暮らす日が来るなんて思ってもなかったけれど、楽しかったと答えると、彼女は驚いたように目を見開いた。
「……でも、怖くなかったんですか?」
メイさんが首を傾げる。二つに結わえた長い髪が動きに合わせてふわりと揺れた。当たり前の感覚、当たり前の質問。投げかけられたそれに対して、私は正直な答えを返す。
「はい。勿論……とても怖かったです。それどころか、私はドラゴンポケモンや強そうな見た目のポケモンだけでも、すこぶる苦手なんですよ」
「えっ、じゃあキュレムは……」
不安気な顔になったメイさんに、私は黙って頷く。
今でも、あの咆哮を忘れたわけじゃない。あの日の恐怖は薄れることはあれど、私の中からずっと消えないのだろう。三匹のポケモンに向けられた敵意も視線も、そして突き刺さるような寒さだって、ありありと思い出すことが出来る。怖い記憶は、なくなってなどいない。
それでも。怖いことに、変わりはなくても。
「だけど、大丈夫なんです」
きっぱりと言い切った。こんなこと、少し前の私には言えなかったし、考えもつかなかったと思う。
そう思えるようになったのは何故か。答えなんて簡単だ。
「全てのポケモンは、人間の隣にいることが出来るし……同じように、人間だって、どんなポケモンの隣にもいられるんですから」
キュレムが、そう教えてくれた。
キュレムだけじゃない。ずっと、私は教わりっぱなしだったのだ。ナッツだってそうだし、弟もそうだ。バイトの同僚さんとタブンネたちも、お客様とそのポケモンも、学校の友人やカゴメの人々も、街ですれ違うポケモンも、ドラマの中の登場人物も。あの、やたらと人懐っこいレパルダスだって。私が今まで見た人とポケモン、その全てが教えてくれていた。
そして、あの日に見た三人の男と、彼らの連れたポケモンたちもそうである。私にとって「怖い」ものでしか無い三匹のポケモン、しかし彼らは少なくとも、自分のトレーナーの隣にいた。人間である、男たちの隣にいたのだ。どんな怖い存在であっても、彼らだってポケモンで、人間と一緒に生きる存在だったのだ。
今になって、ようやく気がつけた。いや、今だから気づけたのだろう。
キュレムという、恐怖そのものであった存在と隣合うことで。
「それは……どんなポケモンでも、どんな人でも。トモダチになることが出来る、ということでしょうか」
「友達……?」
私の言葉に目を丸くしていたメイさんが、ふとそんなことを言った。友達という唐突な言葉に、私は少しの間考え込んでしまう。
メイさんが口にしたその言葉は、何か特別な響きを持っているように感じられた。メイさんが、どんな思いでその言葉を発したのかは私の知るところでは無い。きっと彼女にとって、大きな意味のある言葉なのであろうことだけはなんとなく理解出来た。
私には深くわからない。だけど、それはきっと、素敵なものなのだと思った。
「そうですね。友達……トモダチに、なれると思います」
そんな返事をした私に、メイさんはにっこりと微笑んだ。その笑顔はイッシュの英雄のそれでも、チャンピオンを倒した強者のそれでも、ましてやどこかで聞いた王者のようなものでもなく――ポケモンを「トモダチ」と呼ぶ、一人の人間の少女の明るい笑顔だった。
「そろそろ、私たちはおいとまいたします」
改めてありがとうございました、とメイさんが再度頭を垂れる。今度ちゃんとお礼に伺いますので、と形式ばった言葉に、私も再度首を横に振った。
キュレム、とメイさんが私の後ろに声をかける。まだボールに戻されずにいたキュレムは、ほんの数十分前までそうしていたように、狭いワンルームに座ってナッツと遊んでいた。長い首がこちらを振り返る。
もう少しゆっくりしていけばどうかと申し出たのだが、メイさんは急ぎの用事があるからと断りの返事を述べた。キュレムを探すのを手伝ってくれた人たちのところに行かなくてはいけないそうだ、そういうことなら引き留めるわけにもいかないだろう。
メイさんとは連絡先を交換した。お互いの都合が合う時にまた会いましょうと、年相応の屈託のない表情で彼女は言う。
だからいつでも会えるのだ。今生の別れだなんてものとは程遠い。メイさんとも、キュレムとも。
「メイさん、」
「はい?」
だけど、もうちょっとだけ。
私は、キュレムと話したいことがあった。
「少しだけ……いいでしょうか?」
キュレムの方を見ながらそう尋ねた私に、勿論です! とメイさんが頷く。気遣ってくれたのであろう彼女は、私に会釈をすると玄関の扉から外へと出ていった。本当にいい子なのだなあと感心してしまう。
バタン、と扉の閉まる音がして、私とキュレムとナッツが部屋に取り残された。ここ二週間の、いつもの光景。この涼しい部屋で私たちは、静かだけれども心地よい時間を過ごしていた。
「キュレムちゃん」
私の声が静かに響く。ナッツを背中に乗せたまま、キュレムはじっと私を見た。
その状態で、私たちの時間はしばし止まる。まるで世界から切り取られたような、永遠に続きそうにも思えるこの時間。氷に囲まれた闇の中に蠢く、キュレムの目の光だけが動いているみたいだった。
「キュレムちゃんがうちに来た時、私、すごいびっくりしたよ」
私の話を、キュレムは少しも動かずに聞いている。なんでそんなに静かなのか、という風にナッツが目をきょろきょろとさせた。
「あまりにびっくりして、逆に冷静だったかもしれない……どうしようとか、どういうことだとか、そんなことが頭の中に広がってた。これからどうすればいいのかな、ってぼんやり思ってたんだよ」
ボールを開けて、赤い光が霧散した時の衝撃を思い出す。私にとっての、恐怖の象徴。それがよりにもよって、私のポケモンとして現れたのだ。あの時の驚きは計り知れないと思う。
「そのぼんやりがちゃんと晴れないまま、なんとなく、キュレムちゃんと過ごして。そうしたら、意外と普通に過ごせたんだよね。私の部屋が狭いことは問題だけど……でも、キュレムちゃんとの毎日は思っていたよりも普通で、平凡で、穏やかで……」
そして、楽しかった。
あの咆哮の主、氷の竜と、こんな幸せな日々が送れるだなんて。神の気まぐれか何かの運命かわからないが、ランダム交換の偶然が起こり得なければ一生知らずにいたに違いない。
「キュレムちゃんは、キュレムちゃんだった。オバケなんかじゃない、怖いだけのポケモンじゃない。あなたは、私にとって、キュレムちゃんなんだよ」
人には人の。
ポケモンにはポケモンの。
それだけの数の物語があるのだと、シキミさんは語っていた。
その物語の一部しか知らない癖に、その一部が嫌なものだったからという理由で続きを読むのをやめてしまうのは、どれほど愚かなことなのか。キュレムとの出会いは、それを教えてくれた。
『オバケ』としてのキュレムと、『イッシュに寒波を呼んだ氷の竜』しか知らず、それを怖いと思った私はキュレムという物語から目を逸らしかけていた。怖くて冷たいキュレムの物語を、もう読み解こうとは思っていなかった。
それでも、キュレムが私の家に来て、私の中でキュレムの物語は動き出した。それは今までのストーリーとは違い、『キュレムちゃん』としてのキュレムの物語だった。
私の知らない、キュレムの物語。
優しくて温かくて、幸せの物語。
それを読むことが出来たのは、どれほどの幸福だというのだろう。
「キュレムちゃんは、私の思っていた『キュレム』とは違っていた。そのことを知るはずは無かった私だけど。知ることが出来て、嬉しいよ」
そして、私の物語も今までとは違う展開を始めた。シキミさんが素晴らしいものだと言う、ずっと面白いものだという、『人とポケモンの物語』。キュレムと私の間に、出会うはずのなかった私たちの間に、新たな物語が息づいたのだ。
キュレムの物語も、私の物語も。そして、キュレムと私の物語も。世界中の物語は私が知っているよりもずっと複雑で、ずっと鮮やかで、ずっと深くて。
そして、ずっと尊いものなんだと思う。
「キュレムちゃん、あのね」
ひんやりとした頬に手を当てた。こちらを見ている二つの瞳、表情という表情の無いその場所から感情を読みとれるようになったのはいつだったか。
五年前のあの日、肌に感じた寒風よりも、今手から伝わっている冷たさの方がよほど激しいはずだ。だけど何故だろうか、それは全然気にならなかった。
「昔々、イッシュに王様がいたんだって」
キュレムが首を傾ける。シキミさんの講演で聞いた話を思い出しつつ、私は「マイナーな神話だけどね」と付け加えた。
「王様はとっても強くて、ポケモンと人間を仲間にした人なんだよ」
遠い遠い昔、イッシュにいたかもしれない王様。正史に残ることも無く、神話としても掻き消されていた王様の話の真偽を確かめる術はない。今だってどこかに王の末裔がいるのかもしれませんよ! とシキミさんは興奮気味に話していたが、そんな王様がいたのかどうか、そんな出来事があったのかすらわからないのだ。
戦いを嫌って平等を謳い、感謝の気持ちを抱く王様は人々の希望で、理想だった。全てのものを愛する力を持った王様は、全てのものと言葉を通じ合わせることが出来た。生きとし生ける全てのものと、王様は会話し得たのだ。そんな王様は人の姿をしていたけれど、ある時、ポケモンとも話すことが出来ることを知った。
生きとし生けるもの。ポケモンは、人間と同じだったのだ。
「それでね、王様は……ポケモンたちのことを『生き物』と呼んだんだって」
人もポケモンも、みんな生きている。この世界に生きる、相隣者なのだ。
人と、ポケモンは、同じだった。
遙か昔に生きていたかもしれない王様は、人と、ポケモンを、仲間だと。そう、語った。
「この前までの私だったら、その話の意味もわからずにいたと思う。でも、……」
言葉を切った私の顔を、キュレムは優しく見つめていた。その目をちゃんと見つめ返して、私は「でもね」と笑ってみせる。
「本当に、その通りだ、って思えたの」
それは、キュレムのおかげ。この世界の、全ての人とポケモンのおかげ。数え切れない『物語』の主人公たちのおかげだ。
その全員にお礼を直接言うことは出来ない。けれど、一番私の近くにいるあなたには、どうしてもこの言葉を伝えなくちゃいけないし、この言葉を伝えたかった。
すっ、と一度深呼吸。綺麗な氷の身体を目にしっかりと収めて、私はとびっきりの笑顔を作る。
「だからね、」
キュレムちゃん。すっかり呼び慣れたその名前は、よくよく考えてみれば随分と気の抜けるものだ。しかし舌によく馴染んでいるのは否定出来ない。キュレムという種族名と愛称が混ざって、なんともカオスで間抜けな感じなのが私たちの『物語』らしくていいかもしれない、ということにしておいた。
氷の頬をそっと撫でる。少しだけ細くなったように見える二つの光に、私はそっと囁いた。
「ありがとう」
ひゅら、と小さく鳴いたキュレムのその声は、涼しさの漂う部屋に優しく溶けていった。
「すごいキズぐすりが十点、やけどなおしが五点、ねむけざましとこおりなおしが三点ずつ、なんでもなおしが六点……こちら三割引になりますね。で、……クーポンご利用で、合計一万五千八百円になります」
「えっと、カードでお願いします」
受け取ったクレジットカードをレジに滑らせて、籠の中の商品を袋に詰める。大量の回復アイテムを買い込んだお客様は、夏休みの旅行中のバトルに備えるのだと教えてくれた。強いトレーナーがいっぱいいるところだから準備を整えておかなくちゃ、とカードを財布にしまいながらお客様が意気込む。
そのお客様は、よもやモデルかと思うくらいの美人さんだった。綺麗な金の髪を空調の風に揺らした彼女のスカートから覗く、長い脚の白さが窓から差し込む日光に映える。スタイルまで良い上に恐らくバトルもかなりの腕なのだろう、私はこっそり溜息をついてしまう。
お客様の頭には一匹のモルフォンが止まっている。大きな目玉をぎょろぎょろさせたモルフォンは、袋詰めをしている私の手元をじっと見ていた。きらきらと光る鱗粉がいつどくのこなに変わるかちょっと不安だったけれど、そんなことは無いと思おう。
モルフォンの少し下には、シュバルゴとアギルダーがお客様を挟むようにして浮いている。シュバルゴは槍、アギルダーは目をそれぞれ鋭く光らせて、主に仕える騎士と忍者のようにお客様に付き添っていた。さらに足下ではアリアドスが八本の脚で辺りを伺っている。涼しげなサンダルにぴたりとくっついたその様子は、まるで甘えているようにも見えた。
ちょっと前までの私なら、彼らの種族だけで判断し、「怖い」という思考から動けなかったのだろう。ドラゴンタイプでは無いため流石に逃げ出すまでは至らずとも、強い力を持ったポケモンはみんな怖く思えたのだ。
でも、今はその先に進めるようになった。私にとっては怖く感じる彼らも、お客様にとっては大切なポケモンである。彼らはお客様のことを慕い、そして隣にいるのだ。そんな考えが、出来るようになった。
「ありがとうございました、またのご利用をお待ちしています。バトル、頑張ってくださいね」
「はい!! ありがとうございます!!」
元気良く頷いたお客様は、四匹のむしポケモンと共に意気揚々と自動ドアの外へ出ていった。仲睦まじいお客様たちに、私の口元が無意識のうちに綻ぶ。が、一度閉まってから大した間も置かずに開いたドアに顔を引き締めた。
「いらっしゃ……」
思わず、言葉が止まる。しかし入ってきた新たなお客様は私の挨拶なんて気にもしない様子で、目当ての商品を籠にいくつか放り込み始めていた。ベテラントレーナーらしき風格を漂わせる、背筋のいい初老の男性は、キズぐすりをいくつか籠に入れるとこちらに向かってくる。
その隣にいるポケモンに、私は身体を固まらせていた。三つ首のドラゴンポケモン。あの日、六つの瞳で睨みつけてきたのと同じ、大変凶暴とされるその種族。
男性はきっと、このままレジに来るだろう。そうなれば当然私が対応することになる。ドラゴンポケモンを連れたそのお客様と、私は話さなくてはならない。
どうしよう。バックヤードにいる先輩に代わってもらおうか。私の事情を知っている彼は、からかいながらも出てきてくれるはずだ。
そう、するべきだろうか。
ひゅら、と聞こえるはずのない鳴き声が、その時耳の奥に響いた。
それはあの咆哮と同じ声で、あの、とてつもなく怖いものと同じものだ。
だけど、だからこそ。その声は、バックヤードに向かいかけた私の足を止める。
「……いらっしゃいませ! 毎度ご利用ありがとうございます」
すう、と息を吸ってから、私は言いなれた接客文句を口にした。ちょっとつんのめった言い方になってしまったけれども、そこは気にしないでおこう。片眉を上げたお客様から微妙に目を逸らし、私はレジを打つのに専念する。
ぴ、ぴ、と短い電子音が店内に響く。代金を告げた私にお客様が支払いをし、私はお釣りを手渡した。
大丈夫だ。ちゃんと、出来ている。
「ありがとうございました! またのお越しを、お待ちしております!」
頭を下げた私に、お客様が微笑んだ。そして、その横。
お客様に寄り添っていたサザンドラの三つの首が、私に向かって笑いかけた。幾本もの牙が覗く口はにっこりと弧を描いていて、あの日に感じたような恐怖は存在していなかった。
さて、シフトはあと一時間。今はボールに隠れてしまっているけれど、今日はバイトにナッツがついてきているのだ。キュレムがいなくなって寂しいらしいナッツもまた、ちょっとだけ変わり出した。少しずつ外に出るようになっていて、いつかメイさんとキュレムと一緒に、どこかへ出かけられる日も近いかもしれない。
物語は進んでいる。私の物語も、ナッツの物語も。今どこにいるかはわからないけれど、キュレムやメイさんの物語も。あの日に見た三人の男の人たちと、彼らのポケモンの物語だって進行中のはずだ。その全部が、素敵なハッピーエンドを迎えられるといい。
ビニール袋を手に提げて、お客様はサザンドラと隣合ってフレンドリィショップを出ていく。その背中に、もう一度「ありがとうございました」を言った。その言葉はお客様とサザンドラに向けたものであり、同時に、全ての『物語』の主人公へのものだった。
キュレムちゃん。ありがとうね。
最後に、二週間、私たちの物語の主人公だったあの子に向けてそう告げて、私は背筋をピンと伸ばす。
「いらっしゃいませ!」
| タグ: | 【ハワイティ杯】 |
続き
砂糖水@進行:次はGPSさんどうぞ!(22:42)
GPS:はいASPEARさんにれいかいのぬの一枚?(22:42)
砂糖水@進行:(まーむるさんはもう一回やってるので飛んで見えますが問題ありません)(22:42)
GPS:じゃあいかせていただきます!!39番!「エーテル」!!(22:42)
ASPEAR:ぐはっ(22:42)
(ω・ミэ )Э:うわあ(22:43)
砂糖水@進行:39「エーテル」Playerさん http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/039.html(22:43)
フィッターR:そこきたか(22:43)
砂糖水@進行:大きさミスった(22:43)
砂糖水@進行:39「エーテル」Playerさん http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/039.html(22:43)
GPS:エーテルパラダイスはパラダイスじゃない、楽園じゃないけど楽園じゃないからっていって地獄だというわけじゃない、誰かの生きる居場所なんですよ!!!!(22:43)
フィッターR:なぜにこのコンテストのラブストーリーはそろいもそろって物騒なのか(22:43)
砂糖水@進行:ずっと推してましたよね(22:43)
浮線綾:ルザミーネさんとザオボーさんがかっこよくて好きです。(22:43)
円山翔:これもまたプレイヤーでないと分からないかもしれない……でも、私としては素直に楽しめたと思います。知ってたら感じ方はまた違ったでしょうが……(22:44)
GPS:主人公たちの、自分の生きる意味も誰かを生かす意味もわかってなかった人たちが、誰かを守りたい何かを守りたいこの場所を!ここにいる人を!守りたいって!!思えるようになったのはエーテルパラダイスだったからだって!!(22:44)
円山翔:エーテルパラダイスでない場所にいたなら、もしかしたらそうは思えなかったのかもしれない……(22:45)
まーむる:全ての作品の中で、一番重みがある話だったかなー(22:45)
円山翔:居場所って、大事だなぁって(22:45)
お知らせ:(ω・ミэ )Э(Android/Chrome)さんは行方不明になりました。(22:45)
フィッターR:ラストシーンがね……ここで死ぬのは「今日ではない」って言うのがね……(22:45)
お知らせ:No.017(Win/Chrome)さんが入室しました。(22:46)
にっか:こんばんは(22:46)
GPS:リーリエがルザミーネを切り捨てることができなかったみたいに、ルザミーネにも悪人と狂人とは別に、救世主だったり母親だったりって面もあるし、ザオボーもあそこにいた人たちにとっては守ってくれる心強い上司で、エーテルパラダイスも、なかったら救われなかったポケモンもたくさんいるんだろうなって……思わせてくれる!!最高!!(22:46)
あきはばら博士:GPSさんが好きそうな話だなぁと思っていた(22:46)
門森 ぬる:こんばんはです。(22:46)
Ryo:密猟者パーン!!したい(22:46)
砂糖水@進行:ふええええ、鳩さんだああああああ(22:46)
浮線綾:No,017さんこんばんはー(22:46)
円山翔:No.017さん、こんばんは。(22:46)
あきはばら博士:こんばんは(22:46)
Ryo:こんばんは(22:46)
フィッターR:こんばんはー(22:46)
GPS:大好き!!最高!!!!!!(22:46)
GPS:こんばんは!(22:46)
くろみ:こんばんは(22:46)
まーむる:こんばんはー(22:46)
砂糖水@進行:エーテル、今読んでますけど、面白いですね……(22:46)
No.017:すいません、彼氏と焼肉食ってました(22:47)
ASPEAR:わっ、こんばんはー(22:47)
くろみ:アローラ未プレイなんですけど、エーテルパラダイスっていう公式でひどい施設があるっていうのはわかりました(22:47)
円山翔:作中で幾度となく登場する「人はいつか死ぬ」って言葉が何とも言えない味を出しているのではないかなぁなんて(22:47)
Ryo:二度目読んでて改めて面白いなと思った(22:47)
GPS:最後の、「ここは、エーテルパラダイス。」の反復が、自分のいるところを噛みしめている感があって、本当にああああぁぁぁ!!!!!って思うんですよ!(22:47)
砂糖水@進行:お、表向きはちゃんとしてるから…(((22:47)
No.017:誰か突っ込んでくれ((22:47)
円山翔:飯テロ……(22:47)
No.017:ありがとう(22:47)
砂糖水@進行:鳩さんの金で焼き肉が食いたい(22:47)
ASPEAR:こんな時間に……(22:47)
くろみ:彼氏とは誰ですかっていうところですか(どこがつっこみどころかわからない(22:48)
まーむる:鳩の肉をたべたい(22:48)
円山翔:焼肉……いいなぁ焼肉……(22:48)
あきはばら博士:鳩肉…(22:48)
ASPEAR:羽休めと合わせて無限焼肉(22:48)
浮線綾:鳩肉は新鮮でないと不味い(22:48)
まーむる:君の膵臓を食べたい(22:48)
にっか:神絵師の肉(22:48)
くろみ:表向きはちゃんとした地獄の施設エーテルパラダイス(22:48)
Ryo:労働(22:48)
GPS:そう!!ここはエーテルパラダイスなんですよ!彼らの生きる場所で、あの世界の誰かが生きるためになきゃいけない場所なんですよ!今日死なないために、なくてはならない場所だったんです!!(22:48)
くろみ:ドラクエ6の幸せの国を思い出しますね(22:48)
Ryo:間違えた(22:48)
円山翔:エーテルって聞くと構造式が浮かんでしまう理系脳(だった。もう忘れかけてる)(22:48)
砂糖水@進行:まあた、家庭環境悪い話ですよねえ…ホワイティ……(22:48)
砂糖水@進行:C−O−C>エーテル(22:48)
円山翔:3番と合わせて考えると色々すごいことになりそうで……(22:49)
No.017:たしかゲーム上で実際にコモルー使ってくる職員居たよね>エーテル(22:49)
あきはばら博士:エーテル財団は……どれも人を殺しまくってる(22:49)
GPS:地獄じゃないの!!天国でも楽園でもないけど!!エーテルなんですよ!!あそこはエーテル!!あれ以上のタイトルないですよ!!何もかもが最高だった!(22:49)
Ryo:あー密猟者パーンしたいなぁ いいなぁ(22:49)
円山翔:そう、実際にあの作品に出てくるキャラクターが、ゲーム内で出てくるんじゃないかってちょっと思ってみたんです。(22:49)
まーむる:不条理に流されて、なんとかしがみ付いて、ほっとしたけど流され続けているのは変わらなくて、今度はしがみ続けているしかなくて、そこで幸せを見つけて、しがみ続けようともう決めている、みたいな(22:50)
くろみ:そんな、しあわせのくにみたいな話がポケモンに出てくるなんて(22:50)
No.017:いやあれゲーム上の職員がモデルでしょ 少なくとも女の方はいたと思うし ぶっつぶすとか言ってた気がする…気のせいか?(22:50)
GPS:ゲームの中にいてもおかしくないなっていつ絶妙な匙加減なのもすごかった、ぶっつぶすはいます(22:50)
Ryo:労働、しなきゃいけない つらい(22:51)
あきはばら博士:実際にゲーム上に出てきたトレーナーであるか、調べてみたいな(22:51)
まーむる:密猟者はパーンするよりガブリアスに喉笛食らいつかせて血を噴き出させたい(22:51)
フィッターR:ゲーム内に出てくるモブキャラに焦点を当てるとは……(22:51)
Ryo:生活…(22:51)
Ryo:(語彙がどっかいく)(22:52)
No.017:生活…はいたね(22:52)
砂糖水@進行:まだ四分の一くらいですけど、しんどい……この話しんどい……(22:52)
No.017:ゲーム内に焦点ていえば昔くーいさんが投稿してたじゃん「俺だっておまえくらいの歳からポケモンをやってれば…」ってやつ(22:52)
お知らせ:(ω・ミэ )Э(Android/Chrome)さんが入室しました。(22:52)
GPS:人はいつか死ぬって繰り返してた主人公が、でもそれは今日じゃないって言えたこと!(22:52)
砂糖水@進行:おかおか(22:53)
くろみ:おかえり(22:53)
円山翔:αkuroさんおかえりなさいませ。(22:53)
にっか:おかえりなさいませ(22:53)
フィッターR:おかえりなさい(22:53)
(ω・ミэ )Э:ダムでおよいできました(22:53)
ASPEAR:おかえりなさい(22:53)
フィッターR:そろそろ10分ですが、新しく入ってきた方が三名いるのでここらで既出の作品を今一度掲示したほうがよいかと(22:53)
ASPEAR:ロケット団員でしたっけ>俺だっておまえくらいの〜(22:53)
砂糖水@進行:だれかたのむ(22:53)
円山翔:RT(人はいつか死ぬって繰り返してた主人公が、でもそれは今日じゃないって言えたこと!)(22:53)
No.017:そそ(22:53)
砂糖水@進行:時間なんで一回切りますかね(22:54)
No.017:ログが欲しい…(22:54)
GPS:最高の話だった……ありがとう作者さん……(直接脳内に)(22:54)
No.017:この時間だと採取できなかった気がする(22:54)
円山翔:16、17、21、23、25、36、38、49、59、(22:54)
No.017:一回探してみるか(22:55)
円山翔:忘れてたらすみません(22:55)
お知らせ:久方(Win/IE11)さんが入室しました。(22:55)
円山翔:39、(22:55)
久方:よんだ?(22:55)
砂糖水@進行:司書さまあああああああ(22:55)
No.017:仕事人きた(22:55)
Ryo:オフロスキー(22:55)
ASPEAR:13もですよ>円山さん(22:55)
久方:ここまでのログ っ 添付ファイル(text/plain, 65.1KB)(22:55)
まーむる:+50(22:55)
No.017:神(22:55)
にっか:ありがとうございます!!(22:55)
円山翔:13、16、17、21、23、25、36、38、39、49、59、(22:55)
Ryo:さっすがー!(22:55)
砂糖水@進行:神ってる(22:56)
円山翔:久方さんありがとうございます!(22:56)
久方:ノシ(22:56)
お知らせ:久方(Win/IE11)さんが退室しました。(22:56)
フィッターR:50番抜けてますね(22:56)
No.017:久方大名神様をあがめよ(22:56)
砂糖水@進行:あがめよー(22:56)
ASPEAR:ありがとうございます!!!!111!!1!!(22:56)
Ryo:agmy(22:56)
No.017:供物を備えるのだ つ〇(22:56)
円山翔:13、16、17、21、23、25、36、38、39、49、50、59(22:56)
フィッターR:二礼二拍手一礼(22:56)
ASPEAR:88888888888(22:56)
にっか:五体投地!!(22:57)
くろみ:ホワイティにされる(22:57)
砂糖水@進行:うーん、まもなく23時になりますけど、もうちょいやりましょう。あと3人(22:57)
GPS:ゴーストポケモンを供えればいいかな(22:57)
砂糖水@進行:次いってOKです?(22:58)
Ryo:はーい(22:58)
フィッターR:いいですよー(22:58)
円山翔:大丈夫です。(22:58)
くろみ:うぃっす(22:58)
ASPEAR:はい(22:58)
砂糖水@進行:次はあきはばら博士さんどうぞ!(22:58)
あきはばら博士:正直、どれを推すかどうか未だに悩んでいますが たぶん、あまり注目されていない「とても長い」話 「Axis」 で(22:59)
砂糖水@進行:ちなみにあきはばら博士さんは四月に感想会やってくれるらしいぞい(22:59)
円山翔:時空がねじれて繋がるお話。(22:59)
浮線綾:アローラとシンオウ(22:59)
Ryo:私はバトルが全然書けないので素直にすごいと思った(22:59)
砂糖水@進行:28「Axis」アクシス アークスさん http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/028.html(22:59)
円山翔:最初からクライマックスだ……!という感じのお話でしたね。(23:00)
GPS:大正義クロスオーバー(23:00)
砂糖水@進行:あそうそう、クロスオーバーしゅごい(23:00)
あきはばら博士:今回の、とても長い話はすべて最高。(23:00)
ASPEAR:お、私も読んだ話です(23:00)
Ryo:ぼくのかんがえたさいこうのルザミーネ戦を書き切った感があるね(23:00)
ASPEAR:やぶれた世界とウルトラスペースを関連付ける発想力(23:01)
あきはばら博士:ククイ博士の話を、これぞポケモン二次創作の王道と言ってましたが こっちも負けていない 二次創作の王道だと思う。(23:01)
砂糖水@進行:こういうのが見たかったんですよねえ、ルザミーネ戦(23:01)
フィッターR:10年目と20年目の夢の共演(23:01)
あきはばら博士:懐かしいです。この、「20年前に見たポケモン二次創作作品」感(23:01)
砂糖水@進行:王道、かなあ。クロスオーバーはなれてない人にはレベル高くないです?(23:01)
砂糖水@進行:ああーそういう(23:01)
あきはばら博士:まさに、20周年というような懐かしさを感じました(23:01)
ASPEAR:ああまあ登場人物多すぎたような気はします(23:02)
No.017:ルミザーネ戦はあそこまで大変身してなぜルミザーネ本人が戦ってくれなかったのかと(23:02)
GPS:2次創作じゃなきゃできないからこその威力(23:02)
No.017:(脱線失礼)(23:02)
砂糖水@進行:視点が動きまくるので、今の主語は誰やねん、がたまにあったのが玉に瑕(23:02)
まーむる:流石に自分にはごちゃごちゃしてた(23:02)
砂糖水@進行:わかる>鳩さん(23:02)
Ryo:こういうの書くよねー一度は書くよねー!っていうのを高いレベルでやってくる(23:02)
GPS:でも正直クロスオーバーは地雷持ちも多いから好き嫌いが分かれそうな感じもある…(23:02)
あきはばら博士:黎明期のポケモン小説って大体あんな感じ ゲーム中の演出にいろいろと自己解釈を付けて、アレンジしていく(23:02)
浮線綾:9人でバトルは私にはちょっと荷が重かったです……(23:03)
お知らせ:(ω・ミэ )Э(Android/Chrome)さんは行方不明になりました。(23:03)
くろみ:フリーザ様みたいになるのか(23:03)
Ryo:ルザミーネに火傷やマヒを負わせたい(何か脱線している)(23:03)
No.017:わかる>こういうの書くよねー一度は書くよねー!っていうのを高いレベルでやってくる(23:03)
円山翔:帰ってきてVジャンプでルザミーネ最終形態見たんですが、本当にあのまま戦ってもよさそうな姿でしたね……(23:03)
あきはばら博士:わかる >こういうの書くよねー一度は書くよねー!(23:03)
砂糖水@進行:おもしろいのは確かだけど、やはり少々ごちゃごちゃしてしまったのがなあ、っていう漢字(23:03)
くろみ:いつからドラゴンボールになったの(23:03)
砂糖水@進行:感じ(23:03)
フィッターR:ちょっと登場人物が多くて、地の文挟まず大勢で会話しているシーンがあるのがちょっとわかりにくかったですけど、バトルシーンは圧巻ですね(23:03)
No.017:クロスオーバーの何が地雷かっていうと ようするに書く人が下手だったからってのも多分にあるんじゃないか(23:03)
フィッターR:シルヴァディを目にしたアカギの動揺がいい(23:04)
あきはばら博士:そんなにごっちゃになっているかな 割と分かりやすい感じはしましたが(23:04)
砂糖水@進行:ですねー、アカギの同様(23:04)
あきはばら博士:まさかのアカギラスボスという転換が好き(23:04)
砂糖水@進行:いや、明らかに主語を省略しているせいで読んでて??ってなった箇所があった(23:04)
お知らせ:(ω・ミэ )Э(Android/Chrome)さんが入室しました。(23:05)
Ryo:今回の「凄く長い」は三万字の威力を思い知らされる(23:05)
砂糖水@進行:いや、おもしろいしバトルしゅごい、なのは確かなので、まあ難癖です((23:05)
フィッターR:アカギVSリーリエのやり取りもいいなあ(23:06)
あきはばら博士:連載でじっくりと読んでいきたい話。 それが短編で読めてお得(23:07)
円山翔:神ではない、シルヴァディだ(23:07)
ASPEAR:最後らへんの「友達と呼べる存在、かつてはいたのかもしれない。電子空間の中に、ただ一匹だけ。」って何のことでしょう(23:07)
お知らせ:GPS(iPhone/Safari)さんは行方不明になりました。(23:07)
あきはばら博士:「今、この瞬間から――おまえを、白銀の相棒〈シルヴァディ〉と呼ぼう」(23:07)
あきはばら博士:この厨二ネーミングも素敵。(23:08)
円山翔:シヴァルディだと思ってたから、意味を知った時になるほどって思ったのです。(23:08)
砂糖水@進行:厨二かよ〜(好き(23:08)
ASPEAR:タイプ:フルの正式名称決定の瞬間ですか(23:08)
お知らせ:(ω・ミэ )Э(Android/Chrome)さんは行方不明になりました。(23:08)
ASPEAR:silverが由来ならヴが付くのも納得(23:09)
あきはばら博士:語彙が死んで来たので、以上で(23:09)
円山翔:ロトムのことかと(友達)(23:09)
ASPEAR:ん、どういうことです?>円山さん(23:09)
ASPEAR:ロトムは今作の図鑑で第4世代初出ですが(23:10)
円山翔:ギンガ団のどこかのビルで配布アイテム使って入れる秘密の部屋があって、(23:10)
砂糖水@進行:アカギとロトムの関係がほのめかされていたはず(23:10)
円山翔:そこにアカギとロトムの関係が記された書物があったはずです……(23:10)
ASPEAR:部屋の日記の主って名前分かってたんですか? 日記内に記載はなかったはず(23:10)
円山翔:ギンガ団のビルだったからアカギのものなのかなぁって思ってただけなのかもしれません。そんな感じの考察がどこかにあった気もして(23:11)
ASPEAR:日記の文はここで読めますね>http://s2web.sokowonantoka.com/fromblog/pokemon01.html#4(23:11)
円山翔:ポケスペでも触れられていた気がするけど、アカギと関係があったかどうかまでは覚えていないのです。(23:12)
砂糖水@進行:ええと、たしかどっかのモブの話とを統合すると、的な(23:12)
砂糖水@進行:ていうかじかーん(23:12)
あきはばら博士:アカギはナギサシティで引き籠りオタクをしてずっと機械いじりをしていましたからね ロトムと仲良くなっていてもおかしくない(23:12)
円山翔:手元に漫画がないもどかしさよ……(23:12)
砂糖水@進行:次いってOKです?(23:12)
フィッターR:行きましょうか(23:13)
浮線綾:大丈夫です(23:13)
ASPEAR:ナギサって森の洋館から相当離れてるじゃないですか(23:13)
Ryo:どうぞ(23:13)
円山翔:大丈夫です。(23:13)
砂糖水@進行:次はくろみさんどうぞ!(23:13)
円山翔:森の洋館ではなかった気が……(23:13)
お知らせ:GPS(iPhone/Safari)さんが入室しました。(23:13)
円山翔:(違う、ロトムの出現場所が森の洋館なんだ……)(23:13)
ASPEAR:ナギサでロトムの話が聞けたのですか?(23:13)
あきはばら博士:アカギがナギサシティ出身で、家がそこにある(23:14)
円山翔:ごめんなさい、ちゃんと覚えていないです……(23:14)
お知らせ:No.017(Win/Chrome)さんは行方不明になりました。(23:14)
ASPEAR:機械と戯れている話は以前聞きました(23:14)
まーむる:kuromi(23:15)
まーむる:くろみさん居るのかな(23:15)
くろみ:います(23:15)
くろみ:いますすみません(23:15)
砂糖水@進行:おなしゃーす(23:15)
あきはばら博士:確かなことは言えませんが、ロトムと関係がありそうな人物はアカギしかいないので、彼で間違いは無さそうかと…(23:16)
くろみ:あの、私、アローラ未プレイなんですね、そこを踏まえていいですか(23:16)
くろみ:カルテット大好きです(23:16)
まーむる:来た問題作(23:16)
浮線綾:これまだ読めてません(23:16)
フィッターR:きたあ……(23:16)
砂糖水@進行:2「カルテット」1300円さん http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/002.html(23:16)
砂糖水@進行:そこかー(23:16)
Ryo:わーい(23:16)
ASPEAR:ありそうって何なんですか いやまあ時間ですしこの辺にしますか(23:16)
Ryo:一時期毎朝読んでた(23:16)
円山翔:狂気の沙汰……(23:17)
フィッターR:読んだら鬱になること間違いなし(23:17)
GPS:黄色推しかな?黄色のサイリウム振らなきゃ(23:17)
くろみ:オドリドリってのがわからんのです。調べてもいません。けれどなんか種類と色の違う鳥ポケモンっぽいのが命つきるまで踊り続ける感じがすごい好きなんですね(23:17)
Ryo:とてもしんどかった時期に読んでた(23:17)
フィッターR:オドリドリは公式サイトでも解説付きで見れますよ(23:17)
ASPEAR:http://www.pokemon.co.jp/ex/sun_moon/pokemon/160801_01.html(23:17)
まーむる:ルガルガンに食い殺され、包丁で叩き切られ(チキンステーキ)、発狂して死に、ジュナイパーに射殺される(鳥と蟹のシチュー)(23:18)
ASPEAR:島によってタイプと色が変わるポケモンです(23:18)
砂糖水@進行:二番目の話なのに飛ばしすぎでしょう……って思いました!(23:18)
砂糖水@進行:よく知らない人にも刺さる作品(23:18)
浮線綾:これ一番に掲載されることも覚悟してのこのタイミングの投稿ですよね……(23:18)
円山翔:区切りごとにつけられたタイトルがそれぞれの死に際を表しているという……(23:18)
くろみ:よく知らないから刺さったのかよくわかりませんけれど、ポケモンを知らない人がこの子たちどうなっていくのかというのを見せてくれました(23:18)
砂糖水@進行:一番じゃなくて良かったけどあんま変わらんかw(23:19)
門森 ぬる:まだ読めてないけど好きそうな香り……(23:19)
まーむる:多分ドストライク(23:19)
砂糖水@進行:読もう、もーりー(23:19)
あきはばら博士:しおさいが一番で良かった(23:19)
くろみ:赤が悪いのよ、っていうのも好き(23:19)
Ryo:章立てサブタイ付きのやつはニヤニヤします(23:19)
フィッターR:3番目にサブタイがない理由が気になる(23:19)
くろみ:ぜひムーンかったらオドリドリを探しに行こうと思います(23:19)
お知らせ:斬撃の作者(iPhone/Safari)さんが入室しました。(23:20)
砂糖水@進行:わあお、こんばんはですー(23:20)
Ryo:おしごとたのしいぴっぴ(発狂)(23:20)
斬撃の作者:こんばんは(23:20)
浮線綾:斬撃の作者さんこんばんはー(23:20)
フィッターR:こんばんは(23:20)
ASPEAR:こんばんは(23:20)
Ryo:こんばんは〜(23:20)
まーむる:こんばんは(23:20)
くろみ:こんばんは(23:20)
門森 ぬる:こんばんはです。(23:20)
あきはばら博士:こんばんは(23:20)
にっか:こんばんは(23:20)
円山翔:斬撃の作者さん、こんばんは。(23:20)
斬撃の作者:カルテットとても好みでしたのでつい(23:20)
砂糖水@進行:懺悔期の作者さんを釣るカルテット(23:21)
浮線綾:三番も一番に掲載されるのを覚悟してのタイミングでの投稿ですよね……(23:21)
砂糖水@進行:誤字すみませn(23:21)
ASPEAR:3番ですかね(23:21)
Ryo:しゅごい…(23:21)
お知らせ:No.017(Win/Chrome)さんが入室しました。(23:21)
くろみ:アローラはホワイティ地方じゃないんだけどな!って思った(23:21)
斬撃の作者:とりあえず炎のチキンステーキと出所不明の缶詰をどうぞ(23:21)
斬撃の作者:では(23:21)
お知らせ:斬撃の作者(iPhone/Safari)さんが退室しました。(23:22)
あきはばら博士:?! >出所不明の缶詰(23:22)
円山翔:お疲れ様です。(23:22)
No.017:貴様が!!!!!あの!!!!鬼畜小説を!!!!!!!!!!(23:22)
お知らせ:カルテットの作者(iPhone/Chrome)さんが入室しました。(23:22)
砂糖水@進行:あらーお疲れ様です(23:22)
Ryo:私は勘弁しておきます。(別ゲー)(23:22)
円山翔:カルテットの作者さん、こんばんは。(23:22)
浮線綾:カルテットの作者さんこんばんはー(23:22)
門森 ぬる:こんばんはです。(23:22)
砂糖水@進行:あらー作者さん降臨(23:22)
GPS:問題の人が次々に現れている 世紀末だ(23:22)
Ryo:こんばんは〜〜(23:22)
ASPEAR:お疲れ様です。 そしてこんばんは。(23:22)
フィッターR:なんということでしょう(23:22)
砂糖水@進行:世紀末www(23:22)
No.017:よくも!!!!!!!あんな!!!!!!!!鬼畜小説を!!!!!!!!!(23:22)
あきはばら博士:これから、ここはどうなってしますのか(23:22)
GPS:金!!暴力!!食人!!(23:23)
Ryo:これはもうそれはそれとしてアローラをダムに沈めるしか…(23:23)
砂糖水@進行:それダムはいいぞ(23:23)
カルテットの作者:正直斬撃には負けているなと思っているのです(23:23)
No.017:結果発表は大荒れですな!(23:23)
くろみ:別人なのか!!!!!(23:23)
Ryo:そこに39番エーテルの人達が突入してパーン!!(23:23)
砂糖水@進行:方向性が違うんで……(23:23)
GPS:39番の方きたらプロポーズしなきゃ……(23:23)
砂糖水@進行:はい、時間です!!!(23:24)
円山翔:カルテットはじわじわと迫りくる恐ろしさ。(23:24)
まーむる:え、もう(23:24)
カルテットの作者:1300円はチキンステーキの値段ですよ(23:24)
円山翔:斬撃はそれまでの雰囲気を裏切って突き落とす恐ろしさ。(23:24)
No.017:斬撃喰らった後にカルテット読んで2月の繁忙期に心がしたんだアカウントがこちらです(23:24)
Ryo:しれっと!!(23:24)
カルテットの作者:さようなら(23:24)
砂糖水@進行:延長希望ですね?いいですよ!(23:24)
お知らせ:カルテットの作者(iPhone/Chrome)さんが退室しました。(23:24)
Ryo:繁忙期が発情期に見えた!末期だ!(23:24)
くろみ:チキンステーキのねだん!(23:24)
円山翔:チキンステーキ……誰かが考察していた通りでしたね……(23:24)
あきはばら博士:Pさんさすが!(23:24)
浮線綾:ステージではなくステーキのほうでしたか。(23:24)
No.017:そう 鳩はチキンステーキになったのです(23:25)
砂糖水@進行:カルテット、こわい(23:25)
砂糖水@進行:次いってOKです?(23:25)
まーむる:良いのかなあ(23:25)
砂糖水@進行:どうします?(23:25)
Ryo:まさかの作者降臨でみんながこんらんしている(23:25)
円山翔:私は大丈夫ですが……(23:25)
フィッターR:僕は構いません(23:25)
まーむる:自分もー(23:25)
浮線綾:私も大丈夫です。(23:25)
Ryo:問題ありません(23:26)
円山翔:さくしゃこうりん 効果:敵味方問わず使用者以外を混乱させる(23:26)
砂糖水@進行:ではー(23:26)
砂糖水@進行:次は No.017さんどうぞ!(23:26)
ASPEAR:ふらふらダンスですか 私はOKです(23:26)
No.017:えっ(23:26)
砂糖水@進行:鳩だけにトリ(23:26)
No.017:アローラ、ぼくのふるさとは 出ちゃったしな(23:26)
砂糖水@進行:ああまあ、ないならないで閉会で(23:26)
No.017:カプとケッコンはもう出た?(23:26)
円山翔:まだです(23:26)
まーむる:鳩さんが推してたので残ってるのニャーくん位、ってそれもあったか(23:26)
ASPEAR:まだです(23:26)
フィッターR:出てないです(23:26)
砂糖水@進行:まだですねー(23:27)
No.017:じゃあそれで(23:27)
砂糖水@進行:27「カプ・とケッコン」ちなみに私はアシレーヌと結婚したいさん http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/027.html(23:27)
円山翔:現時点で2、13、16、17、21、23、25、27、36、38、39、49、50、59(23:27)
まーむる:御三家で選ぶとしたら、アシレーヌよりはガオガエンかなー(23:27)
Ryo:エンニュートのイヤラシ(23:27)
No.017:もう作者名がずるいよね(23:27)
フィッターR:貴重なコメディ枠(23:28)
あきはばら博士:斬撃を読んだ後で、このマスクネームを見ると どんな結婚生活があるのか(23:28)
まーむる:唐突に出るマッシブーン(23:28)
No.017:それなwwww >エンニュートのイヤラシ(23:28)
Ryo:デンジュモクのデングズマさん(23:28)
GPS:ギャグだけど筋が通っててすごいなって思った(23:28)
円山翔:ニックネームがツッコミどころ多すぎる……(23:28)
Ryo:ニックネームでさり気なく腹筋殴ってくるの止めてください(23:28)
No.017:バクガメハ大王(23:28)
円山翔:緊迫したバトルからのギャグ路線。手のひらを返すような展開。素敵。(23:28)
No.017:これはハワイのカメハメハ大王という元ネタがちゃんんとあって(23:29)
円山翔:カメハメハ大王⇒バクガメハ大王……これは吹いてしまいました。(23:29)
くろみ:いろんな要素がまざって素直によめないマスクネーム(23:29)
ASPEAR:何気に真ん中の調べ物パートも好きです(23:29)
浮線綾:アローラのみんながミヅキさんとカプを祝福してくれて幸せでした。村八分にされずに済んでよかったです。(23:29)
あきはばら博士:後半部分に全部持ってかれているけど、 前半部分のバトルシーンの完成度はすごく高く、ここだけで作品にしてもいいと思う。(23:30)
No.017:作者すっげーふざけてるんだけど かなりハワイの歴史調べた上で フォルクローレっぽい考察や妄想をいれこみつつ、笑わせてくるのが非常に好感を持ちまして(23:30)
まーむる:探偵にされ、結婚相手にされ、伝統の破壊の象徴にされ、カプ・コケコは大忙しですな(23:31)
お知らせ:浮線綾(Win/Chrome)さんは行方不明になりました。(23:31)
Ryo:ゴシュジン…オレ、キンニクデゴシュジン イワウ(23:31)
あきはばら博士:「あら、カプ・コケコ。私は貴方の前では常にしびれっぱなし、常時エレキフィールドだから、眠るなんて出来やしないわ」(23:31)
Ryo:ダムがあったら沈めたくなるレベルだ(何を)(23:31)
No.017:あと夢オチかと思いつつ正夢でしたってのがよくあるけどだがそれがいい(23:32)
お知らせ:GPS(iPhone/Safari)さんは行方不明になりました。(23:32)
門森 ぬる:ダム・コケコ(23:32)
砂糖水@進行:それダムはいいぞ(23:32)
Ryo:フィールドがダムになる特性を持っていそうだ…(23:32)
No.017:なんつーかお約束とまじめにやるところとふざけるところが絶妙というか 計算されてるというか(23:33)
円山翔:待って……ダム・コケコて……(23:33)
砂糖水@進行:わかるー>鳩さん(23:33)
ASPEAR:タイプ:水・電気・フェアリー(23:33)
まーむる:読み返してると、色々絡めてるのが分かって来る(23:33)
円山翔:お笑いの人って凄く頭がいいんだって、明石家さんまを例に挙げて誰かが言ってました。(23:34)
ASPEAR:何気に歴史とか生態とか考察されてますね(23:34)
No.017:こっちは笑いながら読んでるわけなんだけど、作者…かなりの技量やで…ガクガクブルブル…などと思ったわけです(23:34)
円山翔:まさにそんな感じなのではないかなぁ、なんて。(23:34)
あきはばら博士:ネタが多すぎて反応に困る作品(23:34)
Ryo:頭いい人ができるギャグって感じだ(23:34)
No.017:この路線で単行本化してくれたら買うわ(23:35)
Ryo:人を笑わすのって難しいんよなぁ(23:35)
まーむる:単行本化って、この後どうすんのよ(23:35)
フィッターR:改めて見てみると確かにそんな感じだ>ネタが多すぎて反応に困る作品(23:35)
No.017:カプ4種が主人公をめぐって争う(23:35)
ASPEAR:他のカプも捕まえるとか?>今後 ハーレムか(23:35)
あきはばら博士:ギャグパートだけじゃなくて、シリアスパートの完成度が高いですよね。(23:35)
円山翔:安産祈願の儀式って、孵化作業のことですか……(23:35)
お知らせ:浮線綾(Win/Chrome)さんが入室しました。(23:36)
砂糖水@進行:おかえりなさいまし(23:36)
ASPEAR:おかえりなさい(23:36)
浮線綾:たろいもです(23:36)
まーむる:花よりカプ(23:36)
円山翔:お帰りなさいませ。(23:36)
No.017:ネタ出しなら誰にでもできんだよ こういう形にもっていくのが難しい(23:36)
まーむる:おかえり(23:36)
No.017:それをやったのはえらいと思う(23:36)
円山翔:レヒレ、テテフは男性を、コケコ、ブルルは女性を好む、みたいな記述があったから、最大三角関係までじゃないかと……(23:37)
Ryo:おかえりなさい(23:37)
Ryo:タロイモはハワイの主食(23:37)
ASPEAR:ああまあストーリーの後なら平時ですか……(23:37)
No.017:あくまで好む傾向の話なので…(23:37)
あきはばら博士:円山さん、世界には百合という言葉があってだな(23:37)
円山翔:知らない世界……(23:37)
砂糖水@進行:百合……(ガタッ(23:38)
まーむる:知らない方が良い世界かもしれない(23:38)
ASPEAR:両性具有なのでどうにかなる!(23:38)
くろみ:神様の傾向なんて傾向なだけで、気に入ったものは全部さらっていくんだ。ひどいやつらなんだ(23:38)
No.017:まぁとにかく好感度が高かった マッシブーン(23:38)
ASPEAR:伝説のポケモンとか、ゲーム上で「性別不明」とひとくくりにされていても実際には両性具有とか単性生殖とか繁殖自体しないとかいろいろありそう(23:38)
円山翔:確かに、同性結婚認めてる国もありますし……そもそも守り神性別ないのでは……(23:38)
まーむる:というよりそもそも異種姦(23:38)
Ryo:ゼウスも少年少女関係なくさらってますしね(リアルを持ち出す)(23:38)
砂糖水@進行:さりげなく出てきたマッシブーンに腹筋もってかれた(23:38)
円山翔:ギリシャ神話の人間くささよ……(23:38)
円山翔:マッシブーンは完全にネタ枠になってる……(23:39)
Ryo:筋肉!!!!!(23:39)
あきはばら博士:アセロラちゃんの先祖はそうやった家系という、実例(23:39)
まーむる:夜のルガルガン♂(23:39)
にっか:マッスル!!(23:39)
砂糖水@進行:http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/041.html(23:39)
ASPEAR:発売前の印象からがらりと変わって……>マッシブーン(23:39)
No.017:物語の構成の話ばかりしてしまってあれなんだけど 読んでる間は終始wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwな感じだったので(23:39)
No.017:でも終始wwwwwwwwwwwwwwwwwwwってなるのってすごくね とこう思うわけであります。(23:40)
くろみ:なぜ筋肉から突然のダム(23:40)
ASPEAR:筋肉でダムをぶち割ってしまったのでしょうか(23:40)
くろみ:ダムの底に穴あければ水圧でめっちゃ飛ばされますね(23:41)
円山翔:終始人を笑わせることの難しさ……(でも終始wwwwwwwwwwwwwwwwwwwってなるのってすごくね とこう思うわけであります。)(23:41)
Ryo:ダム>>>>>>>>>>筋肉(23:41)
まーむる:コナンでそんな事件あったな(23:42)
No.017:私アローラ、ぼくのふるさと 大好きなんですけど 世界観的にはこっち推しですね(23:42)
No.017:こう、南国のおおらかさがいいじゃないですか(23:43)
ASPEAR:そうですね 平和はいいことです(23:43)
お知らせ:(ω・ミэ )Э(Android/Chrome)さんが入室しました。(23:43)
円山翔:アロハシャツが礼服の一つとして認められているのです。(おおらかさ)(23:43)
まーむる:平和は誰かの犠牲の上に成り立つものですし(23:43)
あきはばら博士:南国のおおらかさとは一体… な作品が多いことは気にしない(23:43)
くろみ:そして明日は遠出するのでおやすみです(23:44)
(ω・ミэ )Э:なんごくのあざらし(23:44)
くろみ:アローラ!(23:44)
お知らせ:くろみ(Mac/Chrome)さんが退室しました。(23:44)
Ryo:おやすみなさい〜(23:44)
ASPEAR:おやすみなさーい(23:44)
(ω・ミэ )Э:あろーら(23:44)
No.017:カプを捕まえちゃって大丈夫なのかにも一個の答えが出つつ、平和なのがいいなぁと思いました まる(23:44)
まーむる:おやすー(23:44)
円山翔:おつかれさまです。(23:44)
フィッターR:おやすみなさいー(23:44)
浮線綾:くろみさんおやすみなさいー(23:44)
にっか:おやすみなさいませ(23:44)
砂糖水@進行:はわーお疲れ様でしたー(23:44)
あきはばら博士:お疲れ様でした(23:44)
No.017:オツカレー(23:44)
砂糖水@進行:ふいー、そろそろいいですかね?(23:44)
No.017:うむ(23:44)
まーむる:全員終了ですかー(23:45)
フィッターR:もう出た人は一通り作品指定しましたし、よいのでは(23:45)
ASPEAR:はい(23:45)
Ryo:うい(23:45)
砂糖水@進行:やはし一巡が限界だったか(23:45)
あきはばら博士:あとは、パスした人が やっぱり語りたい と言うかどうかか(23:45)
砂糖水@進行:どうしますー。日付変わるくらいまでなら(23:45)
にっか:わたしは、まだ読めてないので大丈夫です(23:46)
浮線綾:私は別に結構ですよ。そろそろ眠いですし(23:46)
まーむる:プラス1ならやっぱり進行役の砂糖水さんがもうひと押しすればいいんじゃないかな(23:46)
砂糖水@進行:今日仕事だったんで体力の限界です(23:46)
(ω・ミэ )Э:もふごきゅ(23:46)
円山翔:お疲れ様です……(23:46)
まーむる:あれま(23:46)
Ryo:お疲れ様です(23:46)
あきはばら博士:お疲れ様でした……(23:47)
砂糖水@進行:とりあえず、読んでも読んでも終わんないの、おかしいよ!!!!!!!!1(23:47)
にっか:お疲れ様です(23:47)
砂糖水@進行:あ、あれです(23:47)
Ryo:60作品ともなるとなぁ(23:47)
にっか:www(23:47)
ASPEAR:皆さまお疲れ様です(23:47)
No.017:それな!!!!!!!!!(23:47)
フィッターR:秋葉さん主催の感想会もあるというので、そちらに回してもいいかと。そしておつかれさまです(23:47)
まーむる:終わりは必ずある(23:47)
Ryo:全部読んだ人ってどれくらいるんだろうか(23:47)
砂糖水@進行:それダムはいいぞ!!!(23:47)
砂糖水@進行:他はない(23:47)
まーむる:3/1には全部読んだかな(23:47)
あきはばら博士:私が考えていたのは、感想会ではなく考察会で(23:48)
No.017:明日はこまさんとシンゴジロケ地めぐりをするんだ(23:48)
円山翔:改稿後はまだ全部じゃないですが、改稿前なら全部拝読しました。(23:48)
円山翔:個人的には34番がなくなったのが残念だったり……(23:48)
フィッターR:全部一回は読んでます。最初のほうに投稿されたお話は改稿版は読んでないですけど(23:48)
まーむる:34番結局誰だったか分からないのかなー(23:48)
(ω・ミэ )Э:いつ頃予定ですか博士ー(23:48)
浮線綾:一通りは読んでおります。考察会気になります。(23:48)
No.017:辞退したってことは発表もしないっしょ(23:48)
砂糖水@進行:ご本人が名乗り出てくれない限り難しいでしょうねえ(23:48)
あきはばら博士:みんな、ネタをたくさん放り込んでいるのですが、それをちゃんと拾えているか不安なので、それらの情報を共有したいなーと思ってました(23:49)
Ryo:考察会いいっすね(23:49)
(ω・ミэ )Э:好きなのにな(23:49)
No.017:少なくとも主催からは言わないでしょうね(23:49)
砂糖水@進行:解説ないとたぶんわかんないから、ありがてえ、ありがてえ(23:49)
円山翔:作者本人が語る、みたいなのがあったらなぁ……(ネタ)(23:49)
あきはばら博士:でも、感想会でもいいかもしれないな(23:49)
Ryo:本人が語るのは順位発表後でないと厳しい(23:49)
あきはばら博士:マスクネームネタとか、知りたいですよね(23:49)
まーむる:楽しめれば良い派だから、考察はそこまで、って感じだなー(23:50)
円山翔:考察会って、発表前にやる感じなのですか?(23:50)
あきはばら博士:例えば、061 「死神の棲む空」 のマスクネーム 10万ボルト(23:50)
あきはばら博士:10万ボルトの英語名は「サンダーボルト」(23:50)
あきはばら博士:とか(23:50)
砂糖水@進行:たどり着けてない(23:51)
あきはばら博士:ネタをちゃんと知っておかないと、失礼な感想を書いちゃいそうで怖い。(23:51)
まーむる:名前はド直球なネタが多い(23:51)
あきはばら博士:考察会があるときには、Pさんにも来てほしいな…… と儚く思っています。(23:52)
砂糖水@進行:直接声をかけるしかないのでは(23:52)
(ω・ミэ )Э:それはいつ開催ですか?(23:53)
No.017:Pさんの考察はうなるよなぁ(23:53)
ASPEAR:Pさん案件コンペでもほとんどの作品にちゃんと感想付けててすごかったですもんね(23:53)
あきはばら博士:直接声を掛ける… というのも恐れ多い。忙しいでしょうし(23:54)
No.017:かけたらええやん(23:54)
Ryo:Pさんの感想いつもいい(23:54)
(ω・ミэ )Э:Pさんには悪いことしたなあと思ってます(23:54)
お知らせ:P(Win/Firefox)さんが入室しました。(23:54)
あきはばら博士:う、うむ では、覚悟決めて話してみようと思います(23:54)
あきはばら博士:あああ!!(23:54)
浮線綾:Pさんこんばんはー(23:54)
(ω・ミэ )Э:わっ(23:54)
あきはばら博士:こんばんは(23:54)
P:|・)読めたところまででよろしければ!(23:54)
Ryo:こんばんはー(23:54)
門森 ぬる:こんばんはです。(23:54)
フィッターR:こ、こんばんは(23:54)
ASPEAR:こんばんは(23:54)
砂糖水@進行:人間はエスパーじゃねえんだよ!!!!言おう!!!!!11っていたんかーい!(23:55)
にっか:こんばんは(23:55)
円山翔:Pさんこんばんは。(23:55)
(ω・ミэ )Э:こんばんは(23:55)
P:こんばんは、突然すみません。(23:55)
砂糖水@進行:コントか(23:55)
砂糖水@進行:こんばんはですー!(23:55)
No.017:きたこれ(23:55)
砂糖水@進行:え、Pさんの推し作品聞く流れ?(23:55)
No.017:それだ(23:56)
Ryo:あ、聞いてみたい(23:56)
No.017:聞こう(23:56)
まーむる:どうなる(23:56)
P:今のペースで読んでいると本当に全作読了が投票〆切り寸前に って えっ。(23:56)
砂糖水@進行:じゃあ、Pさんさえよろしければ(23:56)
No.017:君の(推しの作品)名は。(23:56)
砂糖水@進行:wwwwwwwwwwww(23:56)
あきはばら博士:あ、考察会は4月に考えています。 投票まで半分切った以降、そのタイミングが間延びを防ぐににはいいと思いまして(23:56)
まーむる:最悪簡易投票で済ませましょう(23:56)
P:009「エピソード4 アローラ」!!(23:56)
円山翔:おお!明るい!(23:57)
あきはばら博士:渋いところきた!!(23:57)
浮線綾:ピカーーーーーー(23:57)
Ryo:超短い(23:57)
砂糖水@進行:9「エピソード4 アローラ」小麦粉がないならパンケー(以下略さん http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/009.html(23:57)
No.017:くっまだ読んでない(23:57)
(ω・ミэ )Э:ぴかー(23:57)
フィッターR:壮大に何も始まらない(23:57)
まーむる:何故エピソード4なのだろう スターウォーズ形式でしょうか(23:57)
砂糖水@進行:そこかー(23:57)
P:あの発想はなかった。一番ストレートに騙されて大笑いしました。(23:57)
Ryo:1〜3はどこへ(23:57)
No.017:じゃなかった(23:57)
No.017:読んでたwwww(23:57)
No.017:これかwwwwwww(23:57)
フィッターR:1〜3はダムの底に沈みました(23:57)
P:RT:壮大に何も始まらない(23:57)
円山翔:どこかまでやってから1〜3も放出する感じ……?(23:58)
砂糖水@進行:文字数の目安で若干あれ(23:58)
P:前半の硬い文から王達の集う物々しい雰囲気 これは何かあるな! → おお! 明るい!!(23:58)
No.017:感想「これじゃあ独立は無理だなぁ…」(23:58)
あきはばら博士:最高ですよね(23:58)
Ryo:ほうら あかるくなつただらう(23:58)
円山翔:素直に、騙されました。(23:58)
P:独立は無理だけど傍観者としては最高に面白いです。(23:58)
No.017:だが嫌いじゃない(23:58)
砂糖水@進行:>アローラに最初の電気の光が灯った瞬間である。(23:59)
まーむる:なんか拍子抜けだったのです(23:59)
砂糖水@進行:くっそwww(23:59)
円山翔:最初、ライトバルブがイメージできなくて、どんな武器だろうって想像してたんです。それがまさかの電球って……(23:59)
あきはばら博士:ちなみに、ダブルダムの次に短い 781文字です(23:59)
(ω・ミэ )Э:そこから!?みたいな脱力感(00:00)
(ω・ミэ )Э:そこから!?みたいな脱力感(00:00)
円山翔:ダブルダム……(00:00)
(ω・ミэ )Э:あう、すみませ(00:00)
No.017:でもさ、敵を研究することのはじめって案外こんなものかもしれないとも思うんですよね(00:00)
044 「ダムを埋める話」 586文字(00:00)
あきはばら博士:041 「夏の終わりに次元を超えて」 611文字
P:最後の一言でひっくり返すパターン、「この記述は疑っておいた方がいいな、引っ掛けピースだな」って思って読むことがいっぱいあるんですが、まったく気付けなかった。普通にあの部屋が吹っ飛ぶとかだと思っていた。(00:01)
フィッターR:わかる>敵を研究することのはじめ(00:01)
No.017:彼らは一歩を踏み出したのだ… 敵は電球を使える…(00:01)
円山翔:相手が何を持っているか分からないからこそ、試してみないといけない。試す前には考察をする。考察が間違って入れば当然こうなる。(00:01)
あきはばら博士:叙述トリックの極みを見た(00:01)
(ω・ミэ )Э:しゃじゅつ?(00:02)
円山翔:じょじゅつ(00:02)
(ω・ミэ )Э:じょじゅつ(00:02)
円山翔:です。(00:02)
にっか:トリックとは?(00:02)
円山翔:項だと思わせて実は違った、みたいな感じのことかと……(00:02)
円山翔:項⇒こう(00:02)
にっか:ああ(00:02)
P:叙述トリックとしては008が秀逸なんですよね あれは全部計算してまったく嘘をつかずに書いているのが読んでる途中からでもわかる。(00:03)
円山翔:完全に兵器と思わせてたじゃないですか。それがまさか電球だったって(00:03)
No.017:こう後の歴史を知ってる者から見ればお笑いエピソードですけど 彼らいたって大まじめですよ(00:03)
(ω・ミэ )Э:ミスリードってやつですな(00:03)
砂糖水@進行: http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/008.html(00:03)
あきはばら博士:あれだけの文字数でこうも読者を騙せるのはすごいな(00:04)
P:ちがう8じゃない 4。(00:05)
砂糖水@進行: http://fesix.sakura.ne.jp/contest/2017/alola/004.html(00:05)
P:大変失礼しました。あの辺り短文ミスリード系続きだったなって思い返しています。(00:05)
砂糖水@進行:4「僕のほとんど完璧な彼女について」やまおとこの試練さん(00:05)
あきはばら博士:8も見事なトリックでしたね(00:05)
まーむる:4は割と序盤から何となく察した(00:05)
円山翔:4.騙された。(00:05)
P:それ<察した(00:05)
Ryo:4はメレシー連れてるからガバイトだと思っていた(00:05)
円山翔:今回いろんな作品に騙されてるのです……(00:06)
(ω・ミэ )Э:おなじく察した(00:06)
あきはばら博士:8は、きのみ云々で察することができた(00:06)
砂糖水@進行:4は察せた(00:06)
あきはばら博士:間違えた 4番(00:06)
円山翔:と、日を跨いだのでそろそろ失礼します。今日はありがとうございました。(00:06)
まーむる:何だろうな、迷路で分岐の先の行き止まりがはっきり分かってるような感じ(00:06)
(ω・ミэ )Э:そういや25も最後の一説がわりと(00:06)
浮線綾:円山さんお疲れさまでしたー(00:06)
円山翔:Good night and have a nice dream!(00:06)
お知らせ:円山翔(Win/Edge)さんが退室しました。(00:06)
まーむる:おやすー(00:06)
フィッターR:おつですー(00:06)
Ryo:おやすみなさい(00:06)
P:お疲れ様でした。(00:06)
(ω・ミэ )Э:お疲れさまでしたー(00:06)
門森 ぬる:お疲れ様でしたー! ありがとうございました!(00:07)
(ω・ミэ )Э:一節か(00:07)
砂糖水@進行:おっとーお疲れ様でしたー(00:07)
ASPEAR:お疲れ様でした(00:07)
まーむる:日付跨いだし、そろそろ終わりかな?(00:07)
砂糖水@進行:日付も変わったし、時間も時間なので一回締めまーす。そのあとはフリートークで(00:07)
(ω・ミэ )Э:はーい(00:07)
Ryo:お疲れ様でした…!(00:07)
にっか:了解しました。お疲れ様です(00:07)
浮線綾:どうもありがとうございました、楽しかったです。(00:08)
砂糖水@進行:待って挨拶させて(00:08)
P:皆様大変お疲れ様でした、終わり際にすいません。(00:08)
砂糖水@進行:本日はこんな時間までおつきあいいただき誠にありがとうございました!(00:08)
ASPEAR:お疲れ様でした。 本日はありがとうございました。(00:08)
まーむる:お疲れ様でしたー(00:08)
砂糖水@進行:後半作品全然読めてなくてほんとすみません!いやでもこんな急な日付でGOが出るとは思ってなかったんだ……これをきっかけにやばい読まねばと思ってぎりぎりで泣きを見ないようにしていただければ、感想会やった甲斐があるというものです。わたしも読みますー(00:08)
Ryo:楽しかったです!(00:08)
砂糖水@進行:一人一作品でも結構時間かかりましたね……おそらく消化不良の方もいるかもしれませんが、その辺はツイッターなり、投票と一緒に感想書くなりしていただければ。(00:08)
砂糖水@進行:あと四月にあきはばら博士さんがまた感想会もとい考察会やってくれるんですね!博士よろしく(00:08)
No.017:おつかれー(00:08)
砂糖水@進行:たくさんの方に集まっていただき感謝の念にたえません。ありがとうございました。(00:08)
あきはばら博士:人がいなくなる前に、告知 考察会(もしくは感想会)はおそらく4月8日あたりにやる予定です。(00:09)
砂糖水@進行:これにて閉会します。(00:09)
ASPEAR:私が読んだ作品は全部語れて満足です。(00:09)
砂糖水@進行:ごめんぶっちゃけしんどい!!!!お疲れ様でした!!!!!!!!(00:09)
Ryo:私も残りの紹介文書かないといけないんですよね(00:09)
にっか:砂糖水さん。お疲れ様です(00:09)
フィッターR:おつかれさまでしたー(00:09)
お知らせ:久方(Win/IE11)さんが入室しました。(00:09)
(ω・ミэ )Э:888888(00:09)
砂糖水@進行:おーわーりー(00:09)
Ryo:マジおつでした!(00:09)
砂糖水@進行:挨拶320字もあってすまんな(00:09)
終わり
※本文中では作者の死生観が語られます。
『生きとし生けるすべての皆様へ
ヨノワールとサマヨールの幽霊レイディオ』
「さ、やってまいりました幽霊レイディオ、略して霊レイのお時間です。
メインパーソナリティは私、任せて安心ヨノワールと」
「アシスタントをつとめます、至って健全サマヨールです」
「当番組は生きている皆様や幽霊の皆様に、ほんの一時でも生活を愉快に感じていただければと思い配信しております。
お聞きの皆様方、30分程度の予定ですがどうかお付き合いくださいませ」
「よろしくお願いします。
……といっても放送してる現在時刻、ご存じでしょうが深夜です。おまけに……今何時?」
「2時10分ぐらいだね」
「前回は1時50分ぐらいにやってましたよね?
この不定期ぶりです。正直なところこの番組、リスナーさんがどれだけいるんでしょうか」
「というかリスナーさんに届いているかどうか、配信機器を担当するロトムの気まぐれによるところがあります。
今回お聞きいただけてる方は案外幸運ですよ」
「狙って聞けるものじゃないですからね。
っていうかリスナーさん、人間の方だったら信じてくれないんじゃないでしょうか。
ヨノワールとサマヨール、つまりポケモンが人間にわかる言葉でラジオまでやってるって」
「ポケモン相手に何を疑ってるんだかねー。わざマシンひとつでサイコキネシスが使えるようになっちゃうんだよ? エスパーだよ」
「いや、誰でもできるってわけじゃないですよね、それ」
「確かにできるできないは種族によるけどさ、それだけエスパーの素質をいろんなポケモンが持ってるってことだよ。
サイコキネシスじゃないけど、テレパシーを届けるぐらい、ある程度の通力を得たポケモンならだいたいできるって、ねぇ」
「その『ある程度』が難しいですよ。通力の修行って説明できるポケモンがどれだけいるんだか」
「いやー、これだ、て決まったやり方が未だに確立されてないんだもん。だから無闇に時間がかかる。
みんな信じないのも、やりとげたポケモンがあまりに少ないからじゃないかな」
「それだけじゃないでしょう。一応、これラジオですよ? 放送機器越しにテレパシーって、普通は通じるとは思いませんって」
「そこはあれだよ、ヨノワールの霊界アンテナ。通訳は機器に取り付いたロトムくんの不思議パワーで」
「うまく説明できないってことですね」
「あー、っと。ディレクターさんから、ゲストが焦れてるってさ」
「流しますね!? って、ぁ……ごめんなさい、前置きが伸びすぎました。最初のコーナー、いきましょう」
『生きてるって素晴らしい』
「はい、『生きてるって素晴らしい』のコーナーです。
このコーナーではゲストにゴーストタイプの方をお呼びして、幽霊なりの苦労をお話しいただいております」
「生きてる苦労に悩むリスナーさんも多いと思います。そんな苦労してる皆様に、死んでも苦労は絶えないよ、と伝えていくのがこのコーナーです。
生きてても死んでても変わんないよ、だったら急いで死ななくても、と。
毎度思うけどこのコーナー、名前変えない?」
「いや、こんな名前で始めちゃったんですから、引っ込みつかなくなっちゃったんでしょう。
俺だってこんな、前向きなんだか後ろ向きなんだかわかんない名前は……」
「平たく言って諦めろってんだからねぇ。行く末を絶望させてるんだもん」
「うらめしいなぁ。呼んどいてやらせることはそれかい? アタシそんな暗い感情は食べてないよ?」
「ちょっ……えー、ゲストさん早いです。また前置きが伸びちゃって……」
「いやま、いいじゃないか。コーナー始まってマイクの前に来たのに、まだ黙っててってのはー、ねぇ」
「無理あるよねー」
「というわけで今回お呼びしましたのは、ユキメノコさんです」
「はーい、やっとね。呼ばれてきました、氷タイプのユキメノコです。どうぞよろしく」
「ありがとう。それではコーナーの目的として、あなたしか知らないような苦労をひとつ、皆様に伝えていただこうと思います」
「ゴーストポケモンの中には生まれた時から幽霊、てのも多いです。生き物としても幽霊としても中途半端、それが俺たちです。
そこでユキメノコさん」
「はい」
「ユキメノコさんは先天的にゴーストタイプってわけじゃないんでしたね」
「そうなんですよ、昔は普通にユキワラシの女の子でした」
「そう、氷タイプだけだった。
というわけで、ゴーストになってからどうだったか。それをちょっと話していただけないでしょうか」
「なってから、てねぇ……やっぱり大騒ぎだったのはユキメノコになった直後だなー。進化するほど強くもなかったんに、オニゴーリでなくこれだもん」
「ある日、出かけた娘が声まで変わって戻ってきたとか、どこのエステティックだよ、てねー」
「なんということでしょう。ご家族の驚きは察するに余りあります」
「あっはっは、あんたらねぇ……。ま、確かに急な進化にも程があったから、父ちゃん母ちゃん大騒ぎよ」
「それはそうでしょう。
あ、そうだ。リスナーの方は進化の事、ご存じと思いますが、一応。
ユキメノコさんは『めざめ石』という進化の石の影響でユキワラシから進化します。別に経験とか実力とか高めなくっても」
「極端な話、生まれた直後でも進化できる可能性はある。
これは自身の能力に依らない、外的要因のみでの進化。言ってみれば不自然なんです、この姿」
「不自然な姿ってちっと引っかかるわね。
前置きでも似たようなこと言ったっしょ? そうなる素質があったからこうなれたの」
「いやいやいや、すみません、不自然ってのは言い間違えた。希少な進化だったから、みんな予想外で騒いじゃった」
「そう! そうなんよ。いつか大人になったらみんなと同じオニゴーリになるとは思っとったん。
でも友達と山に石掘りに行ったときにな、きれーなピカピカ石めっけてぇ。持ち帰ろうって触ったらこれだわ」
「あー、それが『めざめ石』だったんだ」
「周りからは不良扱いだよ。とーちゃん、うちの娘がこんなんなるなんてって怖い顔するし、かーちゃんは育て方間違えたって泣くし。
なりたくてなったでねーがに、だっも信じんがで、なんも良いことなかったよ、こっちは!」
「訛ってる訛ってる。恨めしいのはわかるけど落ち着いて」
「その辺、人間とかは良いわ。ただ大きくなるだけだもん。進化して手足なくなったり、ガラッと姿変わるポケモンって面倒くさいんだから、これ」
「あ、わかりますよ、それ。俺だってサマヨールですもの。ヨマワルだった頃は浮遊してたんです。それが2本足になりまして……なんて言われてると思います?」
「のろまー」
「わ、すっごいムカつく言い方!」
「大当たりですよ、ヨノワールさん……!!」
「ごめんね、サマヨール君。でも私が吹聴してるんじゃないよ? 陰口を聞いたことあるだけだから」
「サマヨール君、そんな言われてるんだ。一気に怒っちゃってまー。氷あるけど、頭冷やす?」
「いりません。ったく!
とにかく、俺みたいに形の変わる進化でも、成長に伴った順当なものなら、大人になった証拠みたいで分かりやすいし、群の中でも当たり前のことと受け入れやすいものです」
「それがちょっと逸れたら不良扱いだもんねー。一応、可能性のある進化なんだけど」
「逆にイーブイみたいな、枝分かれが当然の進化なら、何になっても騒がれにくいもんです。
しかし、珍しいってだけなら私のようなヨノワールも、進化できるのは割と少数なんだよね」
「そー……? 成長じゃないんで?」
「“れいかいのぬの”っていう代物がありまして。強い霊の力が宿っている、と言われるこの道具がないとヨノワールにはなれないんです」
「自身では生涯かかっても集めきれない力を、その布を介して集める、て感じ……と、俺は聞いています。
で、その布がまた出回らないものでして」
「へぇー……じゃ、なれた時どんな感じだった、ヨノワールさん?」
「私はー、行くところまで行っちゃった、て感じだったけど、まー、周りはすごかったね。
喜ばれる、誉められる。妬まれる、恨まれる」
「あの時はすごかったですねー。俺が覚えてるのは、『ヨノワールの血で染めた布が霊界の布になるんだ』ってヤツが……」
「キツかったよ、あれ。死にはしないけど気持ち悪いのがずっと続いて、なかなか快復しなくってさ」
「やられちゃったんだ……」
「今でも襲ってくる人間、いるよ? 迂闊に人前にでるとさ」
「人間に!?」
「そう。ヨノワールに憧れるのはサマヨールだけじゃないんだ。
サマヨールのトレーナーがね、霊界の布を欲しがるんだよ。で、欲しがる人には高値でも売れるってわけで」
「本当に霊界の布が作れるのかも定かじゃないんですけど、それでも信じてる人は多いみたいです。血液の神秘性ってヤツでしょうか」
「ドラゴンの血とか、よく話題にあがるもんねぇ。
ユキメノコさんは、そういう人間に襲われたとか、ありません?」
「アタシはまー……ないかなー」
「あれま。ユキメノコっていったらトレーナーに結構人気なんですけどね。強いとかめんこいとかで」
「そんな人間に好かれたって知らないわよ。
ん……多分だけども、住む場所が場所だから?」
「あー、雪山」
「そりゃ確かに人は来ませんなぁ。
でもその分、出会ったトレーナーとか、血眼で追ってきません? 苦労した以上、珍しいポケモンの1匹でも捕まえないと勘定が合わないとか」
「それがそうでもなくって。
この間、トレーナーの坊ちゃんがね、雪ん中に頭埋めてたんで、引っ張りだして助けたのよ。そしたら悲鳴上げて、『氷漬けはイヤだ』って逃げてって」
「ありゃー」
「ははー、雪解けの頃に発見されるとか思っちゃったのかなー」
「ホンっト失礼しちゃう。そんな人を捕まえて、なんてやったことないのに」
「やったヤツがいたんでしょう、昔に。それに、ゴーストってだけでも変な目で見られますし」
「夜道で出会った人に逃げられたこと、ホント多いよね。ヨマワルの頃は、誘拐される、て言われてさ。
今じゃこっちが誘拐されそうで、夜道でもなきゃ出歩けないけど……」
「苦労するねー、レアなポケモンは」
「ヨノワールさん、しっかり……!」
「しっかりってね、サマヨール君、私はちょっと君が羨ましいよ。
この中で、表を出歩いても特に騒がれないのは君ぐらいじゃないか?」
「それは、えっ……」
「強くなって、能力も増えて、可愛い後輩もできたけども。私も、ユキメノコさんも普通に出歩いたら、悪いヤツに狙われかねないんだ。
その点サマヨールはどうだい? ちょっとは珍しいかもしれないけど、そこまで話題にはならないだろう」
「そう言われましても……。というかヨノワールさん、いくらサマヨールでも……いやヨマワルでも、白昼出歩いていたら変な目で見られますよ、ゴーストですもの。
それに珍しさなら、ヨノワールさんは★でヨマワルが●、サマヨールでも◆ぐらいはあります。捕まえてやる、てトレーナーはいるんですよ、たまに。
もしバトルを挑まれでもしたら、もう泥沼です。負ければ捕まる、撃退したら『こんな強いなら』ってますます狙われる。ヨノワールさんならどうです? 『勝てない相手だ』って恐れられませんか?」
「えー……サマヨール君?」
「サマヨールなら押し切れば勝てる、て微妙に舐められるんですよ。足遅いから逃げられないし。
助けてもらうまでに、いったい何人のトレーナー、相手にしたっけなー……」
「サマヨール君!? 君こそしっかりして!? いや、変なこと言い始めたのは私だけどさ!」
「いやーもう、みんな苦労したのね、うん。
どうよ、ヨノワールさん、コーナーの趣旨には沿ってるんじゃない?」
「そって……確かに沿ってるけど、別にイヤな思い出に浸ろうってコーナーじゃないから!
ほら、サマヨール君も沈まないで。こう言う時は……柏手2つ!」
パン! パン!
『空気を変えよう!!』
「というわけで次のコーナーに移ります!」
『お便りコーナー 教えて、ゴーストさん』
「えー、ちょっと強引に進めましたが、お便りのコーナー『教えて、ゴーストさん』です」
「世間の評価で揃って沈むとは、俺も反省です。
というわけで、このコーナーはさっきと違って、生きているからこそ抱くお悩みや質問に答えるコーナーです」
「こんな番組ですからお便りもそんなに多くないですが、0でもないんですよ。今回取り上げますのはこちら、ラジオネーム:風前のトモシビさんからのお便りです。
えーと、ヨノワールさん、サマヨールさん、ゲストの方、初めまして、風前のトモシビと言います」
「はい、初めまして、トモシビさん」
「こんなラジオ番組がありますことを前回の放送で初めて知りました。幽霊への質問を募集しているとのことでしたので、普段から気になっていることを質問として投稿してみました。
不躾で申し訳ありませんが、早速お伝えします…………」
『死んでからなる幽霊はもう死なないと言われます。
しかしいつか幽霊にも変化や寿命に近いものはあると、私は思います。
そこで質問です。幽霊は月日の経過でどんな風に死ぬか消えるかするのでしょうか』
「……お答えください、と」
「どんな風に、かー。俺はあんまり……ユキメノコさんは?」
「アタシも知らないなー。っていうか、アタシのところじゃ基本的に氷タイプのポケモンとして死ぬんだもん。ゴーストタイプはそんなに……」
「あ、そうですよね。ヨノワールさんは? 何か……」
「私は割と」
「えっ?」
「何か知ってる!?」
「実際に誰かの死に目にあった、てことはないけど、聞いた話でよければ。
とりあえず、このトモシビさんの予想はあってるね。
幽霊も月日の経過で消失する。寿命がある、て言った方がわかりやすいかな。
生き物のように老化して死ぬ、てわけじゃないけど」
「確かに、昔からいる幽霊に会ったことありますけど、ヨボヨボの老人って感じはしなかったですね」
「輪廻という概念があるように、死んだ命はいずれ新たな形に生まれ変わり、新たな命が世に生まれ出る、らしいから。
もし命が増えるばかりで幽霊が消失しないなら、世の中は幽霊で溢れかえっているはず。
と、こんな前置きの上で質問にお答えしようじゃないか」
「……そうだった。質問は寿命の有る無しじゃなかったですね。どんな風に、と」
「どう死んでいくか、だよね。これは、ある長寿のゴーストタイプの方から聞いた話ですが」
「ある長寿の、ですか」
「誰とは言わないよ。さて。
幽霊は基本的に未練で動いてる。未練とは記憶の一部で、それを無くすことがつまり死ぬこと……に、近い」
「未練を忘れると、死ぬ、というか消える? いきなりポンと忘れる訳じゃないですよね?」
「まぁ、事故とかが起きない限り、そうだね。少しずつ、消失するまでに記憶が薄れていくんだ」
「思い出せなくなる……痴呆、に近いんでしょうか」
「近いね。ただ、順序があるんだな。
まず自分が生前に何をしてたか忘れる。
この辺りはまだ軽い。けど見た目が老けないから進行がわかりにくい」
「あ、俺も見たことあります、そういう方」
「まだ軽い方だからね、結構いるんだ。だからか、そのまま長いこといる幽霊もいる。
ただこの先は進みが早い。次は物忘れが自分の名前にまで至る」
「名前、思い出せなくなるんですか」
「特にゴーストポケモンになったのなら、ポケモンとしての名前で呼ばれるから、むしろ忘れやすい。私らとしては軽い方なんだけどね。
普通の幽霊なら、これは割と重い方だ」
「それ、ヨノワールさんも……?」
「いや、私は覚えているさ。まだまだね。
で、名前の次は自分の姿。
自分がどんな顔をしているか、どんな格好をしているか。それを忘れる」
「姿って、水とか氷で見ません?」
「いやー、それがわからない」
「え」
「というのも、なんと姿が朧気になって誰だかわからなくなるんだ。人間の幽霊だったら、人型の何か、て感じに。
この段階から見た目でわかるようになる」
「朧気に……え、まさか心霊写真とかの?」
「あんな感じだよ。個人を判別できない程度に姿がぼやける」
「うわ、俺も見たことある! あれが成れの果て!?」
「そういうことさ。
続いて忘れるのは、自分の種族、というか形を。
ここまで忘れちゃうといよいよ種族もわからなくなる。いったい何者なのか、と」
「さっきは人間なら人間の、ってわかる程度でしたけど、それがさらに?」
「そう、さらにわからなくなるんだ。ほとんど霧みたいな漠然とした形になっちゃってさ」
「そこまでいくと、じゃあ次はいよいよ……?」
「いよいよね、未練を忘れる。
これで幽霊としては、ほぼ体をなさなくなる」
「ただの霧みたいになっちゃう……」
「あれが……」
「意外と身近にあるだろう、サマヨール君。
でも、実はそれが最後じゃない」
「まだ忘れるものが!?」
「もう一声あるんだな。もう、一声。
幽霊は最後に、自分の声を忘れるんだ」
「声ですか?」
「そうだよ。未練を忘れても声や言葉だけは伝えることができる。それが一般には空耳とかお告げとかに感じられる。
しかし声も言葉も忘れてしまえば、いよいよ命の残滓のような霧だけが残る」
「それが、幽霊の消失と……」
「そういうこと。質問への回答は、幽霊を記憶を無くしていき、やがて何者でもない霧に姿を変えるのです、と。
しかし霧になっても幽霊は幽霊。普通の生き物の目には見えず、霧は世界中に漂い続ける。
と! ここで前置きの輪廻の話がでてくる」
「前置きの、ってことはその霧が、新たな命の素に?」
「そうなるわけさ。
ご理解いただけたかなー、風前のトモシビさん。お便りありがとう」
「ありがとうございました。
そういえば、ヨノワールさん。俺、幽霊の霧というとゴースってポケモンを思い浮かべますけど、関連あるって思うのは無理がありますかね?」
「いや、関連ありだよ」
「え、なんかあっさりと?」
「実際あるからには、ねぇ。
……そうだ、ここで問題」
「え゛」
「あっさりじゃつまらないんだろう?
さて、今さっき幽霊が忘れていくものを挙げていったわけだけど、1つだけ、霧の中に残るものがある。
それは、何が残るかな」
「何って……えーと、記憶に、姿、声……」
「アタシらの中にもあるもの?」
「そりゃそうだよ。ヒントは、記憶に関連したもの」
「じゃぁ、記憶を無くした時点でほとんど?」
「だいぶん薄れちゃうねー。じゃ、次のヒントは、なぜ未練を感じるか、ということかな」
「未練を……やり残し?」
「あ、感情!?」
「心ですか?」
「はーい、ふたりともだいたい正解!
霧に残るのは、ほんの少しの心だ。記憶を無くした以上、本能的な感情ばかりだけどね」
「あー……確かに、記憶に関連してて、心に残ってるから未練になる」
「でも、経験とかの記憶が無いから、漠然としてる?」
「そうそう。声が残っているうちはそれを伝えることもできるんだけど、ね。
というところで、霧のポケモン・ゴースとの関連性だ」
「はー、待ってました」
「お待たせしました。
まず、幽霊が記憶をなくして霧になっても、ほんの少しだけ心は残る。
次に、その霧なんだけども、霧と呼ばれるだけあって風に流れるし、空気が淀む場所には溜まる。
そしてだ。溜まった霧の中に悪意や恨めしく思う心が多かった場合……」
「そこにゴースが生まれる、と」
「空気の淀んだところに幽霊がいる、っていうのは、そういうことだったんですね。いるっていうか、生まれる」
「まぁね。さらに言えば、そのゴースがより多くの幽霊の霧を集めたり、力を高めることで記憶や意識がハッキリしていくと、その姿もやがてハッキリしていく。
手があり、頭がある。自分の姿に気付いたとき、ゴーストに進化する」
「じゃあ、ゲンガーはさらに姿形を意識できるようになったから? だからより生き物に近いシルエットになるんだ……」
「なんていうか、ゴーストのアタシたちも勉強になったわ……」
「私も結構、長生きしてるし、それ以上に長生きの方から聞いたものだし。
……と、ここでネタばらし。
今の話、実は全部“らしい”ってこと。不確かなんだ」
「は!?」
「調べようとして調べたって話はひとつもないんだよ。
最初に言った通り、私も聞いただけの話だし、幽霊が霧になるまでをじっくり記録・観察した例は、時間がかかることもあって、どこにもない。それこそ、あの『長寿の方』が見てきたって話だけでね」
「ぇえ!? なんですか、それ。筋が通ってるだけホントっぽいけど、つまり子供だましじゃないですか!」
「そうは言っても、だ。
幽霊が霧になるのを見てきた者はいるわけだし、ゴースの進化も実際にゴーストになる前後に話を聞いたことがあるから、今回話せたんだよ。口伝てでもちょっとは信じてほしいなぁ」
「はー……見事に納得させられた。
でも、古い伝説とかって全部そんなもんよね」
「た、確かに証拠自体が怪しい伝説とか、口伝てしかないとか、有りますけども……。
でも、ヨノワールさん、そうやって俺を何度も騙してきたじゃないですか。俺がヨマワルの頃に適当な嘘いろいろ吹き込んでさ」
「子供を納得させるってのはそういうものだよ。
ややこしい真実を教えるより分かり良い嘘を、てね。子供だましも悪いばかりじゃないさ」
「まぁ、わかりますけど」
「ちなみに、その嘘ってのは?」
「聞きますか!?」
「私からお伝えしましょう!
幼い頃のサマヨール君……いやあの頃はヨマワルちゃんだったな……いろいろ私に聞いてきてねぇ。
まず『なんでヨマワルには足がないの?』と」
「ほうほう、それは?」
「それはね、足下に関係なく、どこへでも行くためだよ。
そう答えると、今度は『じゃなんでサマヨールになったら足ができるの?』と来た。
それは足跡を残すことで、ここは歩いたことのある場所だ、て記憶するためだよ」
「おぉ、じゃ次はヨノワール?」
「当たり。『ヨノワールになったらまた足がなくなっちゃうのは?』と聞かれたよ。
それは足跡で歩いたことを覚えなくても良くなったから。自分の居場所を決めて、どこへも行かなくなったからだよ……とね」
「はぁー……なるほど、そういう見方がー」
「全部うそっぱち! 信じ込まされて、俺は恥ずかしいよ」
「だーれも知らないことだからねー。私も、口から出任せでよくこれだけ言えたもんだ」
「ヨノワールさんのバカ! その才能だけは尊敬に値しますけどね!
ディレクターさん、笑ってないで!」
「あっはっは! サマヨール君、そっちをつっついちゃダメよ」
「目を向けたくなるのはわかるけどねー。
って、え? お便りもう1通! はー、珍しいこともあるねぇ」
「へ!? あー、お便り! まだあった!」
「そうだよ、サマヨール君、気を取り直して。
なになに? ラジオネーム:フランケン・シュタインの被造物さんから」
『私は自然に生まれた命ではありません。様々な生き物の破片から作られた継ぎ接ぎの化け物です。
このような私でも死んだときは、他の皆様と同じように幽霊となるのでしょうか。
おそらく前例のないことでしょうが、お答えください』
「……と」
「人造の命とかいうのですか。近年、てほど新しくもないですけど、人造のポケモンっていましたね。カントーの方に」
「まー、個体数がとにかく少ないからかな。生きてるのも死んだのも見たことはないね、私は」
「ヨノワールさんもですかー。確かにこの、フラン……えーと、被造物さんの言うとおり前例がない」
「でも答えは出せるよ。あってるかどうか、当分は分からないけど、とりあえずでよければ答えようか」
「ですね。では被造物さん、『人造の命でも死んだら幽霊になれるか』という質問ですが」
「なれると思いますよ、あなたも普通の幽霊に」
「ですよね」
「はっきり答えたねー」
「そうさ。幽霊になるだけなら誰だってなれる。たとえ被造物さんが自然に生まれた命でないとしても、命である以上、死んだからには他の命の素になる」
「植物で言うなら、枯れ葉が腐葉土になるまでの状態、てところでしょうか」
「うん、命が人の手によって作られた、という事自体は幽霊になれるかどうかにそんな影響しないはずだから」
「ヨノワールさん、それはなんか根拠があって?」
「まぁね。その……」
「な、なんです? こっち見て」
「新しい命って、ほら、男と女が揃って、アレすることで生まれるでしょう?」
「…………」
「目を背けないでよ、サマヨール君。誕生ってそういうものさ。
ともかく、命が生まれるには必ず誰かが何かをしたって原因があるんだ。
交わらないようなものを混ぜ合わせたのだとしても、命を作る行いがあった以上、生まれたものは命だよ」
「……サマヨール君、性教育って苦手?」
「余所の話ですッ……!
とにかく! ヨノワールさんはこう言いたい? 人造と不自然はイコールじゃないし、不自然でも行く末は同じ、と」
「そうだね。それに、前の回答の時にも関係していること、言っているし」
「え? な、何かありました?」
「未練・記憶が幽霊を動かす、とね。
さて被造物さん、幽霊になれるかどうかは、あなたの出自よりも経験が重要です。
生きている間に多く、強く記憶を残せば、それだけ強い幽霊になれます。ご安心ください!」
「ご安心……なのかしら。ん、この場合は……」
「心配事は死んだ後どうなるか、だからね。ここは、そういうことで」
「で、すね。俺たちも結構 強い記憶……っていうか、思い出、たくさんありますし」
「あ、サマヨール君、それはキレイな言い方だ。
思い出をたくさん残して、あなたも強い幽霊になろう! どうかな?」
「どうかな、て……ギャグですか、ヨノワールさん」
「……まじめなんだけどね」
「ちょっと恥ずかしいわね。でも良いんじゃないかしら。
大した思い出がないまま死んでもロクな幽霊にはならない。それって生きる事への励ましにならない?」
「おお、良いまとめだ! 番組の趣旨に沿ってる!」
「まるで締めみたいですね。
……あ、そう言えば今、何分ぐらいですか?」
「えー……40分超?」
「あれ!?」
「あ、時間オーバー。長引いちゃったわ!」
「キレイにまとまったんだ。サマヨール君、締めよ、締めよ!」
「締める、はい!
ユキメノコさん、今回はゲストとして楽しいお話を、ありがとうございました!」
「いえいえこちらこそ。みんなそれぞれ苦労があるだなーって、アタシも楽しかったから。
ヨノワールさんも、面白い話をしてくれましたし」
「どこまで信じられるかは別だけどね。でも気に入ってもらえたなら、私も覚えていた甲斐があったというものさ」
「うん、童話とか噂話とか、その程度で覚えておくわ」
「それがいいですよ、ユキメノコさん。この人、結構 信用なりませんから」
「はっはっはぁ、そりゃもう人じゃないからねー! 後で見てろ?
それじゃ、サマヨール君、いよいよエンディングが流れてきちゃった」
「よ、よし!
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました! 本番組では皆様からのお便りを募集しています!
生きることに疲れた方、死んだらどうなるのか気になってる方、お悩み相談から疑問質問まで、俺たちがお答えいたします!」
「また、幽霊やゴーストポケモンの皆様からもお便り募集しております。
普段の悩み、気になること、ございましたらどしどしご応募ください。ゴーストポケモンの先達がお答えしますよー」
「というわけで!
生きとし生けるすべての皆様へ、ヨノワールとサマヨールの幽霊レイディオ」
「メインパーソナリティは私、任せて安心ヨノワールと」
「アシスタントをつとめました、至って健全サマヨール」
「そしてゲストで呼ばれました、鮮度長持ちユキメノコ」
「以上のメンバーでお送りいたしました!
では、この番組が、皆様の生きる気力となりますように!」
「たくさん思い出 作って、強い幽霊になっちゃいましょう!」
「それでは、またの機会にお会いしましょう!
最後に締めの一言、いきます。せーのッ!」
『人生、死んでも終わりじゃないッ!!』
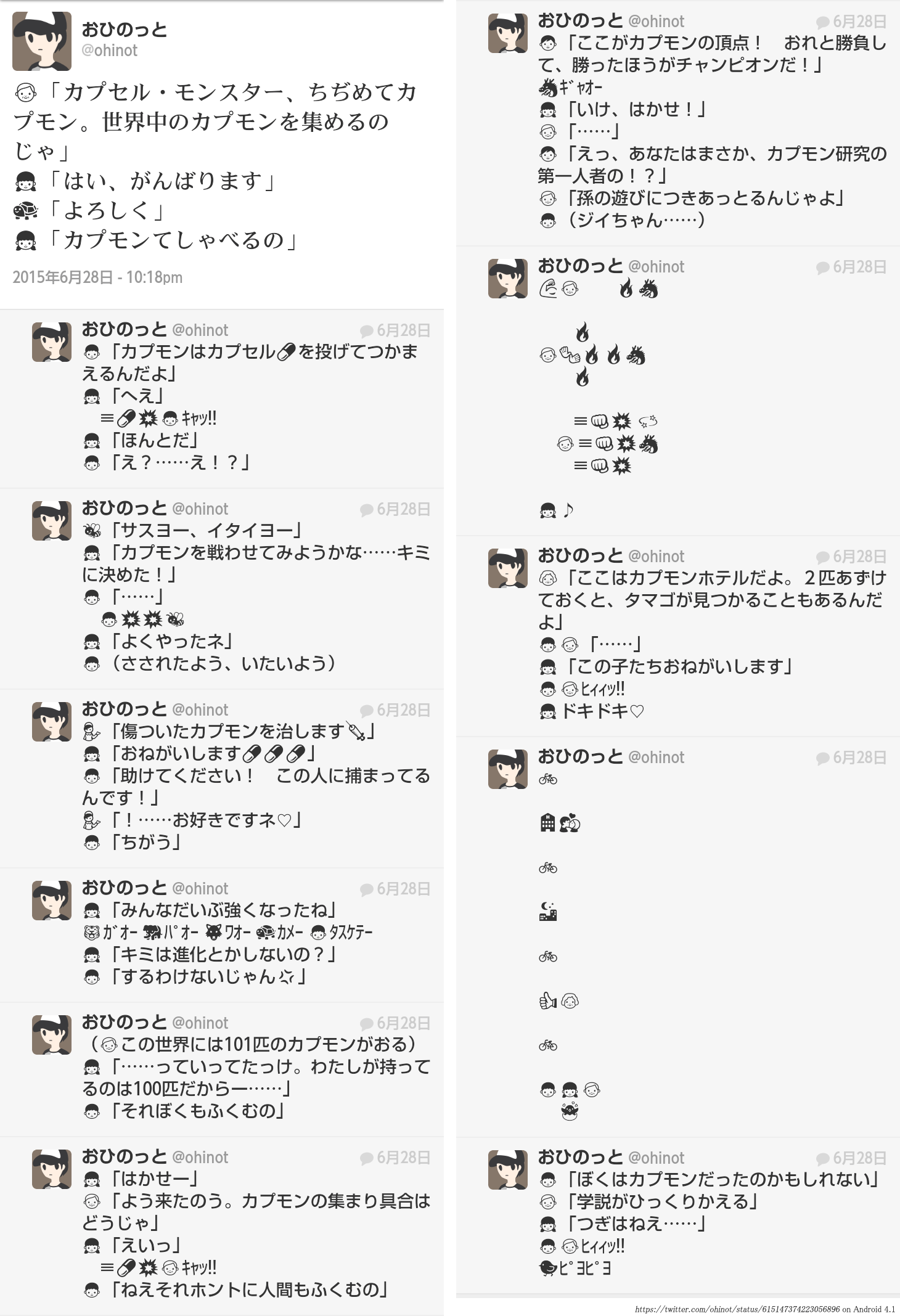
初出は2015年6月28日 https://twitter.com/ohinot/status/615147374223056896 以下です。 |
カイリューは何をする事も無かった。
あれから、休日を除く日は仕事に行こうが付いて来る事も無ければ、俺とウインディ、それとムシャーナにちょっかいを掛ける事も無かった。
俺から貰うポケモンフーズをぽりぽりと食べ、俺が居ない時は外をぶらぶらと回って近所を騒がせ、俺が居る時は俺とウインディと一緒にテレビを見たり。
正に居候そのものだった。
ここに来てからは俺にとって害になる事もしなかったし(食費やら近所への説明やらはあったが)、かと言ってこれと言って益になる事もしなかった。
ドラゴンタイプの生命力、それは近付けば慣れた今でも少し畏怖を感じる程にあるのだが、このカイリューには活気が無かった。
生命力を持て余しているような、そんな気もした。
そんなカイリューは、くぁ、と俺の近くで欠伸をする。長く、大きく口を開けて。口の割りには小さな歯が並んでいるのが見える。
そしてむずむずと鼻を動かして、体を丸めて大きくくしゃみをした。
居眠りをしていたウインディが跳ね上がる。慣れた今でも、俺も少しびびる程の反応をしてしまう。
そのままガラスに向けてやられたら、ガラスがはじけ飛ぶ気がした。
そんな事がありながらも、俺の日常はそこまで変わっていなかった。
朝起きて、ウインディを連れて仕事に行く。カイリューがぶらぶらと外を散歩する。
仕事を終えて、ウインディと一緒に帰って来る。カイリューが庭で待っている。
テレビを見ながら二匹と一緒に夜飯を食べる。シャワーを浴びて寝る。
大して変わらない日常だった。
同僚に話すと、とても珍しがられた。
俺もそう思う。
その一番の理由は、カイリューも俺も、互いに大して何も要求していないからだと思えた。
……と言うよりかは、俺はカイリューに対して大それた事を要求出来なく、そしてカイリューは俺に対して、ここで暮らす事以外を要求していない、と言った方が正しいか。
カイリューが暴れたら、俺とウインディには為す術も無い。ただ居るムシャーナも、戦う姿を見た事は無いが一緒だろう。
それを恐れずには居られなかった。ここに居るなら俺のものになれとボールに入れる事すら出来ない。そんなでもお人よしにカイリューに飯を与えているのだが。
けれども、それでも別に良かった。
ただ隣に居るだけ。それだけで俺はカイリューが居ない時より満たされていた。きっと、カイリューも同じだった。
それ以上、カイリューも俺も、今は望んでいなかった。
休日、起きるとムシャーナが居なくなっていた。
妻は、どう思うのだろうか。きっと、カイリューが居る事も伝わる筈だ。
とは言え、どうなる事でも無いだろう。俺が曲がらない限り、きっと帰って来ない。そして、曲がるつもりは無い。
それだけの事がきっとずっと続くのだろう。
互いに曲がらずに、子も為さずに、離婚も再婚もせずに、そのまま終わるのも有り得ると思う。
目覚ましを掛けなかった今日の朝、いつもより遅めに起きる。ウインディは器用に自分でドアを開けて外にもう既に出ている。カイリューも居なかった。
欠伸をして、目を擦って、起き上がった。でも、二度寝する事にした。少し疲れている。
暫くして、ウインディが俺を起こしに来る足音が聞こえた。圧し掛かってべろべろ舐められる前に起き上がる。
頭を掻きながら、ドアを開けられるならポケモンフーズも自分で取って食えよと言いたくなる。それはそれで困るが。
寝室にウインディが入って来て、跳び掛かられる前にベッドから降り、そして跳び掛かって来たので横に避けた。
まともに跳び掛かられて、蝉ドンされ、そのままウインディが壁に爪を立てながらずるずる床に落ちた日何て、本当に何とも言えない気持ちが一日中続く羽目になった。
躱すとカイリューが入って来て、壁からずり落ちるウインディを不思議そうに眺めた。
「……飯にするか」
とは言え、休日だろうと食う物は大して変わらないのだが。
飯を食い終え今日はどうするか少し悩む。
ただぼうっとしているのも、ここにずっといるのも余りしたくはなかった。
また魚釣りにでも行くか、と思うが、カイリューを連れて行く事になると、傍にいるだけで釣れなくなりそうな気がした。
「……町にでも、行くか」
ただ居候しているだけ。きっと俺やウインディを害する事は無いだろう。そうは思えても、保険は欲しかった。
外へ出る。カイリューも今日が俺にとっての休日だと分かっているらしく、ラフな格好の俺に付いて来た。
ウインディの背に乗って、「町に行くぞ」と言うと、意気揚々と走り出す。
後ろを振り返ると、カイリューも空を飛んで追って来ていた。小さな翼なのに、余裕のある飛び方だった。
ウインディもそれを見て、負けじと足を速める。カイリューが付いて来る。
足を速める。カイリューがそれを追う。
やめてくれ、と言おうとした時にはもう遅かった。俺は下手に走る車何かよりとても速く走るウインディの背中にしがみつくのが精いっぱいだった。
吐くかもしれないと思った。
タブンネを倒すと、経験値が多く得られる。だから一部のトレーナーは、飽くことなくタブンネを倒す。延々と流血を強いる。
勿論、僕も頻繁に倒された。夥しい程の攻撃を受けた。意識が途切れる際の、朦朧とした感覚には慣れた。だから僕は、人間を憎んだ。それは至極、当たり前のことだ。
六番道路には、他にも沢山のポケモンが住む。だが人間がなぎ倒すのは、タブンネのみ。その他は眼中に全くない。
この、こっちが不幸になる情報が広まったのは、割とつい最近のことだった。何故か人間はやたらと、知識の伝達が早い。一人知れば、数時間後には千人が知る。コラッタが増えるより早いペースで、彼らはデータを拡散させていく。
僕は、他のタブンネから、良くこう称される。自己中心的だ、と。けれども、僕はこう思う。僕以外が、他人を思いやり過ぎなのだ、と。
あるタブンネは、人間に襲われたとき、ボールから出てきたポケモンが既に傷だらけで、だから可哀想に感じて、癒しの波動を使ってしまった。彼はその後、彼が癒やした獣に突進された。
またあるタブンネは、人間が傷薬を岩の上に忘れたから、それを教えてあげたくなって、忘れ物を掴んで正面に立った。彼もその後、悲劇に見舞われた。
どう考えても、その行動は異常だ。彼らの思考回路が、さっぱり理解できない。何故憎むべき相手に、優しくするのか。攻撃する者を助けるのか。
僕は仲間から、利己的という欠点を責められた。一部からは、完全に避けられた。タブンネは、基本的に優しい。誰かを批難するなんてしない。けれども、他人に優しくしない者には、頗る彼らは厳しくなる。
確かに僕は、人間から食べ物を盗む。だが、それぐらいだ。何度も、瀕死状態にしてくる奴らだ。その程度の被害なら、賜ってやってもいいだろう。
それは、突然のことだった。
タブンネ達に大きな、とても大きな転機が訪れた。
条例か、法律か、はたまた憲法だったか、良く分からない。とにかく、タブンネを倒してはいけない、という決まりごとができた。タブンネを見かけたら、無視して逃げろ。危害を加えては駄目だ。ほぼ全ての人間は、その命令にしぶしぶ従った。
何故このような、決まりごとが作られたか。理由は、だいたい想像がつく。一部の人間が、幾度となく攻撃され続けるタブンネを憂いだ。そして、抗議をしたのだろう。
こうして僕らは、地獄の日々から逃れられた。実にあっさりだった。こちらからは、何もしなくても済んだ。
僕も仲間も、当然の如く喜んだ。喜ばないタブンネなどいなかった。木の実を集めて宴をした。しかも、その宴は三日も続いた。
ただ僕は、人間を恨むことを止めなかった。これまで、酷い仕打ちを受けた。だから、一生恨んでも許される。自分は人間から、食べ物を盗み続けた。何の罪悪感も抱かずに、悪事ではない悪事を働いた。
六番道路にはもう、人間は来ない。誰もがそう、考えていた。僕は、もう食べ物は盗めなくなるけど、まあ別にいいかと思っていた。
ところが、その予想は見事に覆された。
人間は、今もなおやってきた。そして彼らは、タブンネ以外のポケモンを倒していった。多種多様な悲鳴が、六番道路に響き渡った。人間が去った後には、多種多様なポケモンが、傷だらけで横たわっている光景が広がった。
習慣。人間は、この場所で手持ちを育成するということが、日常の一部となっていた。習慣とは、急に変えることのできないもの。だから彼らは、未だに訪れる。そして、タブンネ以外のポケモンを傷つけていく。
誰かが幸せになれば、その分誰かが不幸になる。タブンネが人間から狙われなくなれば、他のポケモンが狙われるようになる。
こうなったことに、罪悪感を抱いている者が、タブンネの中にはいた。自分らさえいじめられていれば、みんな幸せだったのに、等とぶつぶつ呟いていた。いや、それで己を責めるのは筋違いだろう。こうなったのは、タブンネのせいではなく、紛れもなく人間のせいなのだから。
多くのタブンネは、地面に横たわるポケモンを見かけては、癒しの波動で立ち上がらせた。自分は、やらなかった。他のタブンネがやっているなら、自分はやらなくて良いと思っていた。
そうして、三日が経過した。
この日僕は、目撃した。草むらに、堂々と放置されたリュックがあった。そして、そのリュックのチャックを、必死になって開けようとしている、一匹のシキジカがいた。
自分はそのシキジカに、とても親近感が沸いた。憎むべき相手から、盗もうとしている。僕と同じように。
けれどもそのシキジカは、非常に不慣れであった。歯でチャックを開けるのに、かなりもたついていた。
そして、予想通り悲劇に見舞われた。やっとのことでチャックを開け、中を漁っていたちょうどそのとき、持ち主であるトレーナーがやってきたのだ。
人間の顔は、怒りに満ちていた。ボールからポケモンを出した。経験値を貰う。盗みを働いた罰を与える。この二つを、同時に行おうとしているのだ。
シキジカは、咥えていた木の実を即放り投げる。まだ三日目。やられ慣れていないシキジカの足は震えていた。
数分後、酷い傷を負ったシキジカが、眼前に横たわっていた。怒りを買った分、余計に痛めつけられた。
ボロボロの体でシキジカは、必死に立とうとしていた。さすがに僕は、胸がちくちくと痛んだ。周囲に、仲間がいないか確認した。けれども、こんなときに限ってどこにもいない。
僕は自然と、体が動いていた。
「ありがとうございます。おかげで助かりました」
癒しの波動を二回使ったことにより、シキジカは全回復した。
投げ飛ばしたモモンの実を見つけ、シキジカはそれを運んでいった。僕は後ろからこっそりついていった。運んでいった先には、息も絶え絶えのシキジカがいた。毒状態であった。このシキジカは、仲間のために、危険な行為を遂げようとしていたことが、発覚した。
シキジカはモモンの実を仲間に喰わせた。しかし、それだけでは体力は回復しない。ここは僕の出番か。と、思ったら。
シキジカはなんと、宿り木の種を使い始めた。仲間に向かって、幾多の種を飛ばした。それは、体力を余計に減らす愚行だ。
しかし、倒れているシキジカは、少しずつながらも元気になっていった。そしていつの間にやら、立てるくらいに元気になった。一方で、宿り木の種を使った者は、少々足がふらついていた。
宿り木の種の使い方は、本来逆である。どういう原理か知らないが、こんなこともできるポケモンが存在した。思いやりの心があるシキジカだからできるのか、と想像した。
シキジカは、自分の体力を犠牲にしてまで仲間を回復させた。本当に絶対に、自己中心的なんかではない。
それに引き換え、自分は。
自分と同極だと思っていた存在は、むしろ対極に位置していた。自分はだんだんと、今までの自分が、自己中心的であったことを自覚してきた。
ああ、なんて自分は、愚かだったのだろう。
僕は、自分か利己的であったことを認めた。タブンネ達がおかしいんじゃない。僕がおかしかったのだ。
シキジカの行動に浄化され、考えを改めた僕はそれ以降、倒れているポケモンを見かけたら、すかさず助けるようにした。助けると必ず、お礼を言われた。お礼を言われるのは気持ちが良かった。
そうなってから、周りのタブンネの視線も変わった。僕を避けていたヒト達も、寄ってくるようになった。
誰かを助ける行為は、嬉しいという感情以外を生み出さなかった。
そうして、またときが経過した。
やってくる人間は、半分に減った。それに伴い、被害も減ってきた。
しかし、この日は違った。
一人の人間が、やってきた。その人間は、酷かった。醜かった。人間は、ただ只管にポケモンを倒しまくった。本当に、これはいつまで続けるつもりだろうというくらい倒し続けた。人間は六匹のポケモンを持っていた。その全てを、大きく成長させようとしていた。
ようやく、人間は作業を終えた。被害は膨大だ。草むらの至る所に、ポケモンが倒れている。僕はすぐに体が動いた。彼らを回復させてやらねば。
いつもの通り一匹ずつ、癒しの波動で回復させていく。ボケモンの数が膨大で、PPが切れないか心配だった。
一匹に、癒しの波動を二回使ってやることはできなかった。PPは後二つ余ってはいるが、二匹だけ特別扱いするわけにもいかない。だからこれでいい。後は全員自然回復する。
さあ、これで安心。僕はここから去ろうとした。
けれども、そのときだった。僕の正面に、先程倒れていたポケモン達が表れた。
「なんで全回復してくれないんだ」
彼らの中のハトーボーが、このように言ってきた。
「PPが足りなかったんだ。済まない」
「それは君の問題だろう。俺達が悪いんじゃない」
タマゲタケが、強い口調で言ってくる。彼らの怒りの形相の意味が、僕には分からなかった。僕は、彼らを回復させた。良いことをしたのだ。だから本来は、お礼を言われるべき立場だ。
「仕方がないじゃないか。半回復でもさせて貰えるだけ、ありがたいと思えよ」
「ふざけるな。誰のせいでこうなったと思っているんだ」
誰のせい? 勿論人間だろう。
いつの間にか、囲まれていた。
「お前意外のタブンネに同じことを言ったら、申し訳ない顔をして謝ってきたぞ。謝るってことは、タブンネ達が悪いって認めるってことじゃないか。だから回復して貰うのは、当然のことなんだよ」
ふざけるな。そんなの、利己的すぎる。
あまりに理不尽な言い分。僕はあっけにとらわれて、反論ができなくなった。黙っている僕を見たポケモンたちは次の瞬間、とんでもない行動を取った。僕に襲い掛かってきたのだ。
逃げ場はなかった。完全に袋叩きにされた。怒りのこもった攻撃が、僕の体を何度も抉った。
倒れてもなお、攻撃を止めなかった。助けを呼ぼうと、辺りを見回す。どこにも仲間はいない。なんでいつも、肝心なときに。
ようやく、彼らは満足していなくなった。
辛うじて、意識はあった。しかし、このままではいずれ終わってしまうことが、感覚で分かった。
僕は、自分で自分を回復できないか試みた。奇跡に賭けた。常識を覆せと自分を念じた。けれども、傷はいつまでも癒えない。やはり無理なのだ。癒しの波動は、他人のみを回復させる、思いやりに溢れた技だから。
死にたくなかった。ようやく地獄の日々から逃れて、これからってときだ。もう一度仲間がいないか探す。激しく痛む首を無理やり回す。木の後ろにいた一匹の、シキジカを発見した。
そのシキジカは、僕がこの間助けたシキジカだった。これは、明らかなチャンス。
「おい聞こえるか! 死にそうなんだ助けてくれ! 仲間を呼んできてくれ!」
できる限りの大声を発した。絶対に聞こえている筈だった。それなのに、シキジカは動かない。
「早くしてくれ! 一刻を争う!」
ようやく、シキジカは走った。自分はほっと安堵する。仲間の到着をじっと待った。
けれども、待てど待てども、仲間はやってこなかった。
シキジカは、恐らく仲間を呼んでいない。僕は、裏切られたのだ。同種族はすごく思いやるが、関係のない者は助けない。そういう奴なのだろう。僕の視点から見れば、シキジカは自己中心的だった。
シキジカに対して、怒りは感じなかった。不思議と、シキジカを許せた。良く考えれば、仕方がないことだ。僕を助けたら、僕を痛めつけた連中に何をされるか。仲間になんて思われるか。ハイリスクな上に、見返りがない。だから、仕方がないのだ。自己中心的だけど、仕方がないのだ。
シキジカを許すと同時に僕は、全てを許した。恩を仇で返してきた、あの連中も許した。そして、長らく僕を苦しめてきた、人間達も許した。
薄れていく意識の中、一人僕は考える。
僕は、間違っていた。自己中心的でいることを、むしろ肯定すべきだったのだ。ぶれてはいけなかった。自己中心的でいるのなら、徹底的にそうであるべきだった。誰も助けてはいけなかった。誰も回復させてはいけなかった。経験値を得るためにポケモンを倒す人間も自己中心的で、そのストレスを発散しようとした野生のポケモン達も自己中心的で、僕を助けなかったシキジカもそうで。みんな自己中心的で、正しかったのだ。なのに僕だけが、タブンネだけが優しくて、他人のことばかり考えてても、バランスを崩すだけなのだ。
このまま死ぬのか。諦めるしかないのか。
僕はとうとう、来世のことを考え始めた、何に生まれ変わるのだろう。何になろうとも僕は、自己中心的でありたい。そう、思った。
「今度は絶対に、自分のことだけを考えて生きてやる!」
最後の力を振り絞り、空に向かってそう叫ぶ。
そして、最後の足掻き。もう一度、癒しの波動を使ってみる。
何も、起こらない。
そう、思っていた。
ところが、数秒経ってから。右手の傷跡が、だんだんと薄くなっていくのが確認できた。そして、体が楽になってきた。
成功したのだ。自身を回復させることに。
僕は、シキジカが宿り木の種を使って、他人を回復させていたことを思い出した。僕が今やったのは、その逆だ。
ポケモンの技は、時折本来とは、違う効果を発揮する。
タブンネのくせに、自己中心的な思考だった僕は、これが可能だったのだろうか。
もう一度、癒しの波動を使った。またしても成功。僕は全回復した。あの連中は、半回復だけど。
僕はこれで、生命の危機から逃れることができた。
僕はもう、他のポケモンを回復させるのを止めた。
これで再び、他のタブンネから嫌われる。そう思っていたが、そうではなかった。あの一件を知ったタブンネの中には、僕に対して、同情する者も多くいた。中には、自分もこれからは利己的で生きてみるよ、と僕に向かって言ってくるタブンネもいた。他のポケモンを救うタブンネの数も減った。
人間達はまだ、ここにいるポケモンを狙っていた。けれども、それもあと少しで終わる。
やがて人間は、タブンネに次ぐ、あるいは同率程度の、能率の良い経験値マシーンを、発見するのだろう。そして、そのポケモンのみが犠牲になるのだ。
その後人間は、そのポケモンを倒してはいけない、という決まりごとを作るかもしれない。そしたら、また別のポケモンが標的になって。それが、いつまでも終わらない。いつまでも終わらないことに気がついた人間は、そんな決まりごとは意味がないことを悟る。そうすると、タブンネを倒してはいけないという決まりも撤廃される。そうすれば、またタブンネが狙われることになる。
その流れを予想している、仲間は多かった。
今だけなのだ。こうして、体に傷をつけずに暮らしていけるのは。
「この間、ハブネークが吐き出した毒の塊が、僕にかかっちゃって。強い毒だったから、すごく苦しかった。でも、癒しの心を使って、毒を取り除けたんだ。すごいでしょ。癒しの波動は、まだ覚えてもいないけど。でも、覚えたらきっと、お兄ちゃんみたいに、自分を回復させられると思うよ」
そう言った後、まだ幼いタブンネが、僕に向かって笑顔を見せて駆けていく。僕も笑顔で手を振った。自己中心的になったタブンネは、癒しの波動や癒しの心を、自分のために使うことができる。どうやらそれは真実のようだ。
誰かが不幸になれば、誰かが幸せになる。その循環は、終わることはない。だから、自分が幸せなときは、遠慮なく、その幸せを味わっていこうと思った。
思えば夏に葬式をやってばかりだ、とぼやいた父の声を、僕は暑さに揺らぐ視界の中で聞いていた。
夏の葬式とは体力を削るものだと初めて知った、大学三年生の夏のことである。
冬に厳寒に襲われるこのシンオウの土地も夏の猛暑には音をあげたようで、カントーほどでは無いにしろ、全身に纏わりつくような暑さがひたすらに重たかった。残暑と呼ぶにはまだまだ少しも収まる様子の無い熱気に、第一ボタンまで締めた首筋に汗が伝う。夕刻の空はまだ青く、西方の太陽は明るかった。
「タタラ製鉄所の方までお願いします」
ハクタイジム前で捕まえたタクシーに乗り込んで運転手に告げる。空調の効いた車内は少し寒かった。ハンドルを切り始めた男の二の腕が覗く、半袖のワイシャツの白が眩しかった。
車窓の向こうに見える景色が流れ出す。訪れる毎に整備されていくように感じる街並は、西陽を反射してぎらぎらと輝いていた。最後にこの街を見たのはいつだっただろうかと思った僕のことを垣間見て、窓硝子越しにムックルが飛んでいった。
祖父の訃報を父から受けたのは今日の朝だった。タマムシゲームコーナーの帰り、大学の友人宅に集まっていつものように無為な時間を過ごしていたら、見慣れぬ電話番号から着信が入った。酒の抜けない起き抜けの頭で夢現に取った電話口で、父は平坦な声で話していた。
友人達に事情を告げ、リザードの入ったモンスターボールをその中の一人に預けて帰った自宅は静まり返っていた。危篤の知らせに父は二日前からカントーを発っていたし、母も先に家を出たようだった。食卓の椅子に、成人式以来袖を通していないスーツと、数日分の着替えが入りそうな大きさの鞄と、黒のネクタイが置いてあった。母が用意してくれたものだと思われた。
数時間の航空を終えて飛行機から降りると、乗り込む前よりも些か冷たい空気が漂っていた。それは風土の違いだけでなく、僕自身の内部から湧き上がる寒気であったのかもしれない。電車に揺られてハクタイに着く頃には消えてしまったその感覚は、祖父の家で感じるそれとよく似ているようにも捉えられた。
「森を越えた辺りにある住宅街に向かって進んでください」
交通の便を良くするためにと、ハクタイの森を抜ける道路が整備されたのは、もはや私が生まれるよりも前のことであろう。これが出来るよりも前は案内人を雇って森を抜けるか大回りして電車に乗るかしか無かったのだから大変だったと、かつてはそうしていた父に度々聞かされたことがある。
森に住むポケモンの生活を出来る限り守るために多少の迂回がされた道路であるが、そういった考え方は一体いつからなされていたのだろうか。考え自体は遥か昔にあっただろうけれど、そちらの方が尊重され、まかり通るのになったのは恐らくそう古い日のことでも無いだろう。
汗を掻いた身体が冷房によって冷たくなる。下がった体温に肌が粟立った。空調の臭いと煙草とエンジンの臭い、消臭剤の芳香に混じって鼻腔を突くものは獣臭さだった。
「すみませんね、先程お乗せした方がビーダルを連れていまして。当社はポケモンをボールに入れずに乗れるタクシーを売りにしてるんですよ」
まるで僕の思考を読み取ったかのように運転手がいい、車窓がするすると下りていく。流れ込むのは冷房よりも穏やかな涼風と、森の木々が茂る葉の臭いだった。
この臭いを嗅ぐと、僕は帰省を実感する。傾いた日に目を細めながら見やった空には回る風車のシルエットが浮かび上がり、フワンテと思しき球体がいくつか漂っていた。
◆
ソノオとハクタイの中間部に位置する住宅街に差し掛かった辺りでタクシーを降りた。製鉄所などの連なる工場地帯で働く人の多く住むここから少し奥まった所に、祖父の屋敷は建っている。去っていく黒の車を見送ると、東の空には折れそうな月が浮かんでいた。
家並みを抜けて屋敷へ向かう。どこかの家庭が夕飯の匂いを漂わせていた。電柱に貼られた求人案内のポスターは剥がれかけていて、連絡先と書かれた電話番号を読むことが出来ない。そのポスターよりも上方で無機質な柱に張り付いたテッカニンが数匹、ジワジワと弱い鳴き声を響かせていた。
幾人かの住民とすれ違いながら歩くと、やがて鳴き声が話し声に変わっていった。声を顰めたざわめきの方へ進んで角を曲がると、長い塀の周りに弔問客が集まっているのが見て取れた。
軽く頭を下げながら黒の群を縫っていく。冠木門の向こうに顔を覗かせると、誂えられた受付で見知った顔の女性が客達を出迎えていた。父の姉にあたる鏡子伯母だった。前を通り際にこちらも礼をすると、彼女は年齢よりも若々しい口元を緩めて「久しぶり」と言った。僕は小さく頷いて、屋敷の奥へと足を踏み入れた。
やたらと広い屋敷は既に葬式の準備を粗方済まされているようで、行き来する弔問客の声や足音が夏風に混じって響いている。喪服に身を包んだ彼らは祖父の会社の人たちや近所の住人だと思われ、親戚の姿はなかなか見当たらなかった。通夜という場に遠慮しているのかそれとも祖父の生前の様子がそうさせるのかはわからないが、ポケモンを出している人はおらず、ただ庭に訪れる野生ポケモンの声だけが長閑であった。
うっすら暗くなってきた屋敷に置かれた照明が、弔問客達を浮かび上がらせている。行き交う影と喪服の黒が混ざり合い、どこか異世界めいた風情を醸し出していた。黒が動く度に漂う汗の臭いと、彼らに出された茶の香りが屋内の湿気に蒸されて強くなる。
盆に乗せた茶を運ぶ母の姿を前方に見つけたが、あくせくと忙しそうであったため声をかけるのは躊躇われた。話すのは後回しにしてそのまま進む。何度目かの障子を横切ると、この屋敷で恐らく最も広いであろう座敷の前に辿り着いた。
祖父の祭壇はそこに設えられていた。葬式など幼児期に一度行ったきりである僕にとって、それは今ひとつ現実味に欠けるものであった。シートの敷かれた畳に鎮座する棺に祖父が入っているというのも想像がつかなかった。
「明久君」
弔問客の密やかな会話をぼんやりと聞きながら佇んでいた僕の名を呼ぶ人がいた。声の方を見やると、祭壇前に並べられたパイプ椅子に座る女性が控えめに手を上げるのが視界に映った。
彼女は鏡子伯母の姉で、名を桜子という。平素の彼女は品の良い夫人を絵に描いたような人であったが、流石に今は全体的に窶れ、弱っている風な印象を受けた。
「お正月以来ね」首だけを動かして伯母が言う。
「はい」
「鏡子達が手伝ってくれたから助かったわ。最近どうも腰が痛くて、あまり動けないものだから。千穂さんにもよろしく言っておいてね」
千穂とは僕の母親の名である。
「はい」
「覚悟はしてたけど、急だったから慌ただしくて。この家も広いし、会社の方々もいらっしゃるから色々手間取ったわ」
「お疲れ様です」
「遺影も碌に探せなくてね」
そう言った伯母の横に腰掛けて祖父の遺影と向き合うと、写真のくせに鋭い眼光がまるでこちらを射抜かんとしているように思えた。深い怒りに何かを睨み付けるかの如き祖父の遺影は、他にもっと別の写真があっただろうと思わせる一方で、これ以上無いほどに祖父という人間を表しているようにも感じられた。
「あんな写真しか無かったのよね。もっとも、お父さんはいつもあんな顔だったから当然なのだけど」
半ば独り言のように伯母が呟いた。くっきりとした紅に彩られた、半開きの唇が微かに歪む。黒い着物から覗く首元に刻まれた皺に、うっすらと汗が滲んでいた。
庭の木に止まりに来たと思しきホーホーの声が、僕たちの間を滑っていった。額の中の祖父は微動だにせず、ただただこちらを睨んでいた。
◆
祖父は近くの工場地帯で、食品加工の工場を経営していた。若い頃の祖父はイッシュで炭鉱をやっていたと聞くので、起業したのはおおよそ五十年ほど前のことだと思われる。
屋敷を建てたのは祖父の祖父、僕にとっては高祖父にあたる江角総次郎だった。江角家初代とも言われる総次郎はカントーの武士の出であったが次男坊であることと維新の風に流され、シンオウの開拓に身を乗り出したという。当時のシンオウは今程までに人の手が入っておらず、自然とポケモンが大きを占める土地であった。
そこで総次郎が如何にして開拓を成功させたのか、それを詳しく知る者は誰一人としていない。祖父は知っているのかもしれないが、それが父達に語られることは遂に無かった。先住民との衝突や行く手を塞ぐ森に歯向かい、誰もが辛酸を舐めたシンオウ開拓を身一つで成し遂げた高祖父の活躍は、ある種伝説となって語り継がれている。
開拓の成功によって得た資産により、総次郎は製鉄業を立ち上げ、同時にこの屋敷を建てた。製鉄工場は祖父の起業に伴い売り払われ、現在は江角でない者達によって経営されている。祖父の屋敷に来る道中に見える、灰色の煙を空へと吐き出す煙突が連なる中のいずれかが、その製鉄工場のものだ。
祖父はこの屋敷に一人きりで暮らしていた。父の母で祖父の妻たる巴さんは父が子供の時に亡くなってしまったから、父達子供が家を出てからは祖父と共に屋敷に住む者はいなかったのだ。一年半前に脳梗塞で倒れたのを機に僕の姉が住み込んで身の回りの世話をしていたのだが、それでも何十年かの間、祖父はこの広い屋敷に一人だった。
大学に上がる折、祖父に挨拶へ出向いたことがある。前年の夏にシンオウの大学を勧められていたのだが、結局僕は自宅から通える大学を選択した。
入学式の季節であった。まだ寒い空気が満ちる屋敷で、僕は祖父と二人で向き合っていた。庭に吹く風が木々を揺らす音と、池の水面が揺蕩う音、時たま野生のポケモンが鳴く声の他には何も聞こえなかった。祖父の部屋は庭へと面していて、いつでも葉の匂いと濡れた土の匂いが充満していた。
屋敷は穏やかに時を刻み、入学を報告する僕の声を響かせた。祖父が終始黙っているのが気まずかったが、それ以上に唯々僕の話を聞くだけの祖父の瞳が怖かった。何か後ろめたいことも怒られる理由もある訳でないのに、何故だか針の筵に座らせている心地であった。
祖父が傾ける杯の縁で、透明の酒がゆらゆらと揺れていた。そこに映る祖父の顔が、幾つにも砕かれ割れていた。自分の声に混ざるハトーボーの鳴き声が、恐ろしく遠くのものに感じられた。
祖父は酒を舐めながら、静かにこちらを睨み付けていた。未だ冷たい春風に散らされた木の葉が何枚か座敷に吹き込んでも、その視線が揺らぐことは決して無かった。
◆
そして、あの時と何ら変わらない視線は今も遺影の中から僕を射抜く。
世間話などを交わしていた桜子伯母は、寺の方が来たという呼び声に席を立って座敷を出ていった。儀式が始まるまでまだ時間があるようだったが、一人で祖父の睨み顔を眺めているのも気が進まない。伯母の足音が消えて数分後、僕もパイプ椅子から腰を上げた。
「ああ、明久」
廊下や中庭で何某かを話している弔問客の中を歩いていると、向かいからやってきた人影が僕を呼んだ。祖父の世話をしていた姉の小春だった。
「姉ちゃん」
「お父さんに会った?」
「まだ会えてない。母さんには会ったけど」
姉は日頃から明るく活発な性格をしており、気難しい祖父の世話も上手くこなしていたのだが、今は流石に顔を曇らせていた。それは祖父が亡くなったという事実と葬式の準備に追われた忙しさだけが理由では無いように思われた。
長い髪を一つに結わえた姉は腰に手を当て、「この暑い中、ねぇ」と中庭を見やって溜息をついた。この屋敷は今時いくつも残っていないであろう日本家屋だが、広々とした中庭を囲うようにして建てられているのが特徴的だった。
一本の大樹と、トサキントなどを泳がせた池を中心に緑の葉が多く生い繁る庭が暮れてきた空の下にぼんやり広がる様子は、まるで小さな森が屋敷に閉じ込められたようである。
「大往生だったんだけど」
「そりゃ、八十七年も生きれば」
「それはそうなんだけどね」姉は声を落とした。
「最期が苦しそうだったから」
庭には勝手に入ってきた野生ポケモンが彷徨いており、弔問客が愛でたり指差して話したりしていた。ブタクサの上で転がるスボミーに、近隣の住民と見える初老の女性が手を伸ばして軽く撫でる。「毒を持ってるから気をつけてほしいな」話題を変えるように姉が言う。「ま、スボミー程度なら大したこともないか」
玄関の方が若干騒がしくなってきた。先ほど伯母が迎えにいった、寺の者が入ってきたのだと思われた。そろそろ始まるのであろう、客達もその気配を感じて庭から動き始めた。
何か手伝えることは無いかと一応問うてみると、これと言った仕事は粗方終わってしまったという答えが返ってきた。白粉を塗った姉の横顔に、風に吹かれた細い髪が一房かかった。
「相変わらずじめじめしてるね」
姉がそれを手で払いながら鼻を小さく鳴らした。
「この家はいつも湿気が酷い」
◆
平坦な声の読経が屋敷に響く間も、祖父の死を実感するということは無かった。
木魚を叩く僧侶を睨み付ける祖父の遺影は今に動き出し、心経を聞く我々を蹴散らして座敷に立ちはだかるかのように思われた。或いは畳でじっと横たわっている棺の中から、痩せ細った身体が怒気を滲み出して這い出てくるのではないかと感じられた。暑苦しい背広とワイシャツに覆われた背中が、薄い底冷えに数度震えた。
入れ代わり立ち代わり、弔問客が焼香するために座敷中に線香の匂いが漂っていた。庭から流れてくる緑臭さと充満する湿気とが混ざり合う臭いは、盆にここを訪れるたびに嗅覚を刺激するものであった。そのため僕の中ではこの臭いは盆のものであり、夏休みのものであり、同時に何時まで経っても慣れない畏怖を感じる祖父の元で過ごすことを実感させるものだった。
読経に被せるようにして、庭でホーホーが一つ鳴いた。横目で見遣った庭は薄暗く、座敷から漏れ出た光が木々や草を照らしていた。
庭寄りの端に置かれたパイプ椅子に腰かけた僕の蟀谷を、庭からの風がのっそりと撫でていった。植物の生臭さを運ぶそれはしかし、湿った空気の満ちる座敷に居ては渇きのものとして捉えられた。視界の不明瞭な庭をずっと眺めるのも気が滅入り、視線を祖父の遺影に戻した。隣に座る姉の向こうに、母、そして父の姿が僅かに見える。
大学で教鞭を揮う父は歳の割に姿勢が良く、伸びた背筋は平時と変わりないものであったが、顔色は悪く青白いものとして僕の目に映った。この屋敷に訪れると、父はいつも顔色を悪くしていた。
◆
「どうにも蒸し暑いな」
読経が終わり、弔問客が帰り出してからようやく父と口を聞いた。母と姉は食堂で夕食の支度をしている。黒のネクタイを緩めながら、父は薄い唇を少しだけ舐めた。
「いつ来たの」
「昨日の夜中だ。ホウエンに近づいている台風のせいで、飛行機が少し遅れていた」
「僕の時はそんなことなかったけど」
「台風が逸れたんだな。さっきニュースでやっていたよ」
父との会話に割り込んできたのは哲人叔父であった。哲人叔父は父の弟で、件のホウエンからここまで来たはずである。垂れ目がちの童顔と日焼けした肌が相俟って、ジグザグマをどこか彷彿とさせた。
「こっちに来ている間に上陸して、家が倒壊したりしないか不安だったが杞憂だった。今向こうは晴天そのものらしい」
「結構なことだ、ぱっとしない空よりずっといい」
縁側に出た父が視線を上へと向けて言った。濃紺の空に浮かぶ星は一つとして無く、まるで朦朧とした灰色の雲が天球の全てを薄く覆っていた。折れそうな月だけが鈍い光をひたすらに放っており、蒸されるような中庭を見下ろしているようであった。
頰と首筋に吹き出る汗を同じように湿り気を帯びた手で拭おうとすると、傍からタオルを差し出された。
振り向いた先にいたのは鏡子伯母で「姉さん」僕よりも先に叔父が声をかけた。何となく口を開くタイミングを失った僕は黙ってタオルを受け取り汗を拭く。冷たく乾いたタオルは母や姉が外へ行く時には匂わせているのに程近い、化粧品の香りがした。
「お寺さんは帰ったの」
「今ね。ご近所の方と話してたんだけど、やっと」
「ああ、この辺に住んでる人なのか」
「お父さんのことも知っていたらしいわよ」
「そりゃあこんなに大きい家に住んでれば有名人にもなるものよね」
僧侶の見送りから座敷に戻ってきた桜子伯母が会話に入ってきた。縁側に祖父の子が四人揃った。
「姉さん、今夜はどうするの」
「まあ、寝ずの番をやっておかないと」
「不安だな、そこまで保つかどうか」
寝ながらの番になってしまいそうだ、と冗談めかして言った叔父に、鏡子伯母が「お父さんが怒って出てくるかもよ」と混ぜ返した。
「洒落にならん」父が言う。
「でも、親父はそんなことで怒る器でもないか」
続けられた言葉に、父の姉たちと弟は一様に頷いた。庭で眠るブイゼルを見つけた桜子伯母がそれを指差し皆で笑っている彼らが背にする、彼らの父の遺影は誰が見ても怒りの表情であった。しかし、滅多なことでは怒らぬ祖父が何に対して忿怒の感情を向けているのか、それは恐らく子供たちの知るところですらも無いのだろう。
◆
父は後妻の子であった。
祖父には元々、正代さんという妻がいて、その人が桜子伯母と鏡子伯母の母である。しかし正代さんは伯母たちが小学生の頃に家を出てしまった。二人の姉妹は父と共に屋敷に取り残され、そして今まで実母の顔を再び見たことは無いという。
それから暫くして屋敷の門を潜ったのが父と、父の母であった。父は私の祖母にあたる巴さんの連れ子で、江角という苗字を得た時にはまだ三つか四つという幼子だった。父にはこの屋敷に来る以前の記憶がほとんど欠落しており、それまでどこに住んでいたのか、実父がどのような人であるのか、どういう経緯でここに来ることになったのかなどをまるで知らない。ただ母の柔い手を握り締めて、草木の薫りが満ちる門の向こう側へと足を踏み入れたことだけが鮮明に残っている。
巴さんが祖父の妻となり、二年が経とうとした頃に哲人叔父が生まれた。伯母は二人揃って、頻りに父や叔父の面倒を見た。十幾つも歳の離れた弟たちが可愛かったのと、近寄り難い雰囲気を醸し出す祖父の姿が幼心には怖く見えることを知っていたからである。事実、身体が弱く早くに亡くなった実の母たる巴さんよりも、父や叔父は姉たちに世話を焼かれていた。
やがて桜子伯母はジョウトへ嫁に行き、次いで鏡子伯母が大学を中退して遅まきのトレーナー修行に旅立った。彼女がエリートトレーナーとして名を馳せる頃、父も大学進学を機にカントーに発ちそのまま学校に残り続け、そして哲人叔父もホウエンの大学に入ることになった。姉弟の分散は桜子伯母の所在が夫の転勤によりイッシュへ移った今も変わることなく、四人の子は祖父を一人屋敷に残してそれぞれの土地で生きている。
父たちは仲の良い姉弟であった。それは今でも同じだろう。
ただ、その彼らが屋敷から散るようにして居なくなったのは何やら父たちにもわからない理由があったのだろうか。次々に門の外へと出ていく子供たちを見送る時も尚、祖父の瞳が放つ光の鋭さが弱まることは一度も無かった。
◆
村佐という、祖父の会社の後継者が挨拶に来たため僕は父たちから離れて座敷を出た。村佐は恰幅が良く如何にも企業の取締役という風情で、祖父の体格とはまるで正反対であった。神妙な顔で頭を下げていた彼だが、祖父に後釜と認められるまでに一体どれだけの辛苦を積んできたのかということは計り知れなかった。
「今日は皆様、朝まで起きていらっしゃるのですか」
「ええ、まあ。通夜と呼ぶものですから」
「明日のこともありますし、あまり無理はなさらずに」
桜子伯母は村佐と面識があるようであった。部屋の連なる家屋を繋ぐ長い廊下を歩くと、母らの作っている夕食の匂いが漂ってきた。
この屋敷には中庭と別に、渡り廊下と家屋に挟まれた小さなスペースがあった。祖父はそこで、オドシシとメブキジカを一匹ずつ育てていた。メブキジカは昔、祖父が巴さんとイッシュへ旅行に行った時に連れて帰ってきたもので、当時はまだシキジカだったらしいが今ではオドシシに負けず立派な角を備えていた。
中庭を背に渡り廊下に立つと、彼らの様子を見ることが出来た。大きなポケモンと遊べるのが楽しくて、ここに来ると僕は決まって彼らを構っていた。しかし今では二匹の鹿は揃って寝ているらしく、草に覆われた薄暗い空間にはこんもりした塊が二つ、丸くなっているのが影として見て取れた。
祖父と同じく、彼らもまた高齢である。どちらも雄であるため、子を成すことはなくここでひっそりと過ごしていた。動かぬ二つの影の向こうには家屋、さらに向こうの塀を越えたところにある林地から葉擦れの音が流れてきた。
廊下を渡り終え、幾つ目かの部屋に入る。改築された食堂や便所などを除けば、ここは屋敷で唯一の洋間であった。茶と紫のどちらともつかぬ真紅の絨毯が敷かれたこの部屋を作ったのは、旧き佳き和の建築を好んだ高祖父でも機能美を愛した祖父でもなく、華美と豪奢に惹かれた曽祖父の伸之介だ。
伸之介は派手好きで、芸術を分かりもしないのに遍く手を出していた。
祖父があまり足を踏み入れないせいで何時でも埃っぽい絨毯に一歩を進めると、靴下越しのふかふかとした感触と共に鼻の奥がむず痒さを訴えた。特にここの部屋に用も無いだろうから、姉も滅多に掃除などしていないのであろう。大理石の机や、本棚に詰まった本の頁には細かな塵が積もっていた。
絨毯を踏みしめ幾らか歩くと、棚に置かれた洋燈が目に留まった。カロスの舶来だというそれには、虹色の角を持つ鹿と色鮮やかな花々がステンドグラスで描かれており、僕は父や伯母、叔父などにこの洋燈を灯してもらうのが好きであった。煌びやかな絵が内側から照らし出される様子をまた見たい気もしたが、洋燈の隣にある古いマッチはとうに湿気っていて、洋間に火を灯すことは不可能だと思われた。
ただ光源は引き戸の隙間から漏れ出る廊下の灯のみである、視界のきかない洋間をぐるりと見渡す。小説や学術書、何やら読めない文字の並ぶ背表紙が敷き詰められて僕を睨みつける。壁に掛けられたファイアローの群れが躍る絵の入れられた額は、端に黴が生えていた。数えきれぬ金の瞳を描いた絵の具だけがひたすら鮮やかに、薄汚れたガラスの向こうで輝いている。
しっとりと茶色い、四角のピアノの蓋に指を走らせると指紋いっぱいに埃が張り付いた。曽祖父が果たして音楽に精通していたのか、また楽器を奏でる腕があったのかは不明であるが、そんなことなど我々子孫たちには関係の無いことであった。幼い頃、この屋敷に親戚一同が集まると好き勝手にピアノを叩いて遊んだものである。曽祖父は既にいないし祖父は洋間に無関心であったから、我々を叱る者は存在しなかった。
重い蓋を開けてみると、つんと黴臭さが鼻をついた。黄ばんだ白鍵を右の人差し指で押さえてみると、篭った音が濁った空気を微かに震わせた。この湿気にやられたのであろう、昔に姉が軽やかなワルツを披露した鍵盤は、今ではその命を尽かせかけたかのように白と黒を黙って並ばせていた。
ピアノの蓋を元に戻して、僕は絨毯に腰を下ろした。足をだらしなく投げ出して天井を見上げる。瀟洒だが実用性に欠けるシャンデリアが取り付けられたそこには、幾何学模様が描かれている。
何ともつかないこの模様は、幼心にはどうにも不気味に見えてならなかった。こうして床に寝そべって天井を見ると、さながら自分が深い水底に沈められて揺れる水面を眺めているような、或いは巨大な生物の腹の中で自らの運命が決まるのを待っているような、はたまた逃げることの出来ない巧妙な罠に捕らえられて途方に暮れているような、そんな気分になったものだ。さっさと起きて部屋を出てしまえばよい話なのだが、言い知れぬ不安は身体を洋間に縛り付けてしまうらしく、僕はいつでも姉や両親などが呼びにきてくれるのを待っていた。
今は流石にそのようなことは無いけれど、不規則な曲線や図形の並ぶ天井は変わらず気味が悪かった。まるで蠢いているような、その癖時を止めているかのようなその模様に覆い尽くされそうになるのを、引き戸からの光とのか細い夜鳴きが繋ぎ止めていた。
◆
洋間を出て父たちの元へ戻ると、村佐はもういなかった。桜子伯母の姿が見えないのは、村佐の見送り際に、祖父のかかりつけであった井上医師が尋ねてきたからだという。井上医師は、診察が立て込んで読経に間に合わず、今になってようやくここを訪れることが出来たらしかった。
「明兄ちゃん! どこ行ってたんだよ、さっき話しかけられなかったから探してたんだ」
村佐と入れ替わりで座敷にいた、従兄弟にあたる大貴が縁側の障子から顔を覗かせて手を振ってきた。父である哲人叔父と似た垂れ気味の目が、くりくりと丸かった。今年十五になるという彼は、半年ほど前に顔を合わせた時よりも更に背が伸びていた。
「悪いね、ピアノの部屋に行ってたんだ」
持主の成長に追いつけない黒のズボンから垣間見える、硬そうな踝を視界の片隅に捉えながら言うと、大貴は大して興味も無さそうに「ふうん」とだけ答えた。幼さの残る、日によく焼けた顔は既に庭のポケモンなどに移っており、興味を失われた僕は苦笑した。
「またあの部屋に行ってたの?」
大貴の代わりに会話を引き継いだのは、それまで彼の隣で笑っているばかりであった少女だった。
「明久君はあそこが好きだよね」
彼女は大貴の姉で、名を菜美子といった。菜美子は僕よりも歳が一つ下で、今は大学に通う傍、ポケモン研究員である哲人叔父の仕事を手伝っていると聞いている。黒のワンピースに身を包んだ彼女の、緩くパーマをかけたような癖っ毛が緑めいた夜風に吹かれて揺れていた。
僕が曖昧な頷きを返すと、菜美子はふっくらとした頬を緩ませた。赤い唇が綻ぶ様子に何となく視線を逸らす。僕はこの、柔らかな笑みを浮かべる従姉妹がどうにも苦手である。彼女に明久君、と呼ばれると、今も昔も耳の奥がくすぐったくなる心地に陥るのだ。
「お父さんたちは今夜ずっと起きてるみたい」僕らそっちのけで明日のことなどを話している父たちの方を見て菜美子が言う。
「ああ、さっき聞いた。寝ずの番をするらしいね」
「お酒の用意とかしてたよ、いいな。俺も混ざりたい」
「別に楽しいものじゃないだろうよ。明日もずっと何かしらあるんだから、僕たちは早く寝ておくべきだろう」
年長者ぶってそんなことを言ってみると大貴は口を尖らせて、わかってるよ、と軽くぼやいた。弟の年相応そのものな素振りに菜美子が笑う。
廊下から漂ってくる、腹の中を刺激する匂いが一層強まった。縁側へと目を向けると、父の吐き出した煙草の煙が夜の空へと溶けていくのが障子の間から見え隠れした。
空に流れる灰色の雲と紫煙との区別がつかなくなる。夕食が出来た旨を姉が知らせに来たのは、それから間もなくのことであった。
◆
夢に魘されて目を覚ますと、木張りの天井がやっと見えるくらいの明るさしか屋敷には残っていなかった。
あの後親戚一同で夕食を取り、夜食の準備をする母や姉、通夜の支度に追われる父とその姉弟を横目に風呂に入った。特にすることも無くそのまま眠りに就いたのだが、気味の悪い夢によって僕は起きてしまったのだ。
寝巻きの下の皮膚は、脂汗でじっとりと湿っていた。ただでさえ湿気の中で寝ているせいで蒸されている感覚が絶えないのに、その上汗まで掻いては耐えがたい。湿り気を帯びたTシャツを脱ぎ捨て、僕は鞄から取り出した予備のそれに腕を通した。
寝起きついでに便所へ行くことにしたが、どうやら目が冴えてしまったようである。襖を開いて廊下に出ると、夜露に濡れた土の匂いがした。隣の部屋の母や姉は元より、親戚の誰もがよく眠っているらしく屋敷は静まり返っていた。飽きもせず鳴いているのはホーホーやヨルノズクだけである。
タイル張りの便所はひんやりと冷たかった。空の色に濃厚な墨を落としたような蒼のタイルが、白熱灯の光にてらてらと照らし出されていた。目を凝らすとその一つ一つに無数の自分が映し出されるのを見て取れたが、冴えぬ顔を沢山見たところで得るものも無く、僕は水が流れ落ちる音を背にして便所を後にした。
すぐに部屋へと戻れば良いのだが、ふと父たちのことが気になった。寝ないで夜を明かすと話していたが、屋敷の静まりようから考えるにその志は果たされなかったと推し量られた。道中、渡り廊下から降りて睡眠中の鹿たちを撫でてそんなことを考える。草と獣の臭いをした二つの塊を覆う毛は細く硬く、僕の手の動きに合わせて低い呻き声を上げた。
微かに軋む音を立てる縁側を歩き、祖父の遺影がある部屋に入ってみると、大方予想していた通りの光景が薄明るい部屋に広がっていた。藺草の匂いに酒や煙草の強いそれが重なって、一瞬奇怪な息苦しさに囚われた。ほぼ空になった何瓶かの酒瓶の側に置かれた、夜食の皿には何も残っていなかった。
「父さん、起きて」
煮染が盛られていたと思しき皿の隣に転がる父に声をかける。軽く肩などを叩いてみると、父は「うう」と唸って身体を起こした。
「俺は何を」
「寝てたんだよ。叔父さんも伯母さんもみんな酔い潰れてる」
「今は何時だ」
「12時過ぎたあたりかな」
「そうか。思ったよりもたなかったんだな」
俺たちももう歳だ、父はそう言って頭を押さえた。流石に酔いは醒めたようであるが、目元は明らかに眠そうな上に呂律も覚束ない。「おい起きろ、姉さん。哲人」父が叩き起こして回った他三人の様子を見ても、このまま通夜を続けるのは困難だと思われた。
「ああ、寝てしまってたのね。いつの間に」
「やはり父さんのようにはいかないな。僕たちはいつまで経っても酒に弱い」
「ともかく、みんなもう寝た方がいいですよ。後は僕が片付けておきますから」
「じゃあ、悪いけれどお言葉に甘えさせてもらおうかしら。もうこれ以上続けられる気はしないわ」
瞼を擦る桜子伯母の言葉に父たちは頷く。「まあ、それで親父が怒ることもないだろう」父は大きく伸びをしながら遺影に向かって呟いた。「親父の一番嫌うのは酒に弱い奴が無理してする酒盛りだから」
足をふらつかせた大人たちが自室へ去っていく。欠伸をする鏡子伯母の細い首筋に浮かぶ、青の血管がやけに目立って見えた。むにゃむにゃと夢現に何事かを言っている哲人叔父の背中を押して歩く父が「そういえば明久」と座敷を出て生きざま、思い出したように振り向いた。
「さっき俺を呼んだか。恭介、と。俺の名を」
「父さんのことは、父さんとしか呼んでないはずだけど。何時頃の話なの」
「俺が寝ている間だ。俺を、起こす前に」
一言一言噛み締めるような父の言葉には、思い当たる節が全く無いため正直に首を横に振った。そうか、と父は緩く頷き、哲人叔父と共に部屋を出ていった。乱れ気味の足音がしばらく響き、遠ざかってやがては聞こえなくなる。
食堂と座敷を往復して、夜食の皿だの空の酒瓶などを片付けてしまうと、祖父の遺体を前にして自分が一人であることを強く思い知らされた。もう幼い子供でもあるまいし、不機嫌な遺影や黒塗りの棺が怖いわけでは無いけれど、むしろ生きている祖父と独り対面しているような緊張感に襲われた。物言わぬ祖父は死して尚僕を睨みつけ、生前と同じ無言を以て自分以外の者を気圧している。
何となく居た堪れなくなり、手近にあった線香を焚いてみた。慣れない手つきと湿気に火がつかぬことを案じたが、それは杞憂に終わった。香に灯された小さな火は、蛍光灯に照らされた部屋の中で音も立てずに燃えていた。
薄ら寂しい匂いに手を合わせ、うろ覚えのお経を心中で唱えていると、背後で軽い音がした。父か親戚が戻ってきたのかと振り向いたが、そこにいたのは僕の予想していたどの人物でもなかった。
「水を飲もうと思って食堂に行ったのだけれども、物音がしたから」
「菜美子」
涼しげな寝巻き姿の菜美子は、「ここまできたらどうにも目が冴えてしまったようで」と廊下側の下桟を踏み越えて言う。白い裸足が微かに押され、仕切の凹凸の形に潰れるのがどうにも艶かしかった。
「明久君も、そうなの」
「大体は、うん。父さんたち、寝ずの番出来そうにないって」
「そう」
菜美子が畳を踏むだけの微小な音が鼓膜を擽った。祖父の遺影と向き合う僕の横に彼女が座ると、床が幽かに軋む音がした。
「どうせ眠れそうにないし。お父さんたちの続きでもしようかな」
独り言のように呟きながら菜美子が線香に火を点ける。僕よりも慣れているように見えるその手つきに、灯された線香がか細い煙を吐き出した。度重なる焼香によって酒や煙草や畳、また庭からの土の臭いは香のそれに取って代わった。どこか非日常的なその香りが強く鼻腔を突くせいで噎せ返るようである。
僕は何も言わなかったし、菜美子も敢えて何かを言うことをしなかった。しかし僕が自分の寝床に戻らなかったように、菜美子もまたこの座敷から動く様子を見せなかった。
隣では菜美子が手を合わせているし、眼前には祖父の祭壇が鎮座している。奇妙なことになったな、と二重の緊張を覚えながら、僕はじっとりという湿気の中にふうと息を吐いた。
◆
昔、こうして菜美子と共に縁側で庭を眺めていた記憶がある。
夏の夜だった。夕飯が出来るのを待っていたのか、或いは食後の夕涼みをしていたのかは定かではないが、僕たちは縁側に腰掛け生温い風に吹かれていた。
桜子伯母が、自分や弟妹の過去に着ていた浴衣を出してくれて、僕と菜美子はそれに身を包んでいた。白地に朝顔を描いた菜美子の浴衣の裾に、一対のメガヤンマが舞っていた。麻の生地越しに感じられる木目が少し痛かった。
当時、屋敷では家政婦を雇っていたのだが、交代で派遣されてくる彼女らの誰かが気を利かせてくれたらしく、僕たちに甘露を作ってくれた。ミツハニーの蜜とカイスの汁を水と混ぜ合わせたそれを縁側に置いておくと、バルビートやイルミーゼが何処からともなく集まってくるのだ。
甘やかな匂いがする皿を間に挟み、僕と菜美子は蛍たちが飛び交う中庭を眺めていた。彼らの光は不規則な軌道を描いて行き来し、僕は時折その柔らかな輝きが眩しくて目を細めた。暗い庭のせいで彼らの身体は見えず尻の光だけが浮かび上がっているのが少し怖くて、膝を隠す浴衣の布をぎゅうと握り締めていた記憶がある。自分の太腿に拳を押し付けていると、子供特有の柔らかな肉を感じることが出来た。
「綺麗だね」
そんな僕とは対照的に、菜美子は頻りに喜んでいた。蛍の舞を表現する豊かな語彙も、何も言わない選択肢も知らぬ時分の彼女は繰り返し、その言葉を繰り返した。曖昧な頷きだけを返す僕の首筋に汗が垂れていたのは、もしかすると蛍のせいだけでは無かったのかもしれない。庭の中央に位置する大樹の葉が風に騒めく度、幾何匹の蛍たちはその周りをぐるぐると回った。
◆
それから十年以上の月日が経った今、中庭に飛ぶ蛍はいない。祖父が倒れたことを皮切りにして家政婦を雇うことはなくなったし、夏の夜に甘露を作る者もいなくなった。僕と菜美子の間に挟まれているのは薄ら甘い水ではなく、父たちが残していった何本かの酒瓶である。
我々も育ち、あの頃着ていた浴衣などとうに着れなくなっているだろう。あの頃は縁側からぶらつかせていた両足も今や地面につき、むしろ縁の高さが足りないようにすら思えた。土を踏む裸足の皮膚が、湿り気を帯びた冷たさを訴える。茶黒の土は濡れていた。
「大学はどうなの」
「それなりに。むしろお父さんの手伝いの方が忙しいかも。明久君は」
「毎日を不毛に過ごしてるよ」
戯けて言うと、菜美子が息だけで笑ったのが鼓膜に伝わった。半袖の寝間着から覗く彼女の二の腕は白く、闇夜に照らし出されたそれはふっくらという印象が見受けられた。記憶の中の幼い菜美子もお饅頭のような子供であり、僕は菜美子に会う度に内心、チョウジの銘菓が口恋しくなったものだ。
縁側に出たため、座敷の灯りは消してしまった。視界を助ける光源は塀の向こうの街灯と、ハクタイが近いせいかやたらと明るい夜の空と、叢雲に覆われた細い月だけである。奇妙に薄暗い空の下で、あの日から変わることのない大樹が風に葉を揺らしていた。巨大な影が中庭に浮かび、その様子はまるで何か大きな化物が体躯を震わせているかのようにも感じられた。
何くれとなく大樹を眺めながら、菜美子と取り留めのない話をしていたのだが、やがて話は彼女の弟である大貴のことに差し掛かった。「旅は順調なのかな」トレーナー修行のために数年前から旅を続けている彼の笑顔を脳裏に描いて僕は問う。この質問は菜美子と言葉を交わす毎にしているし、先程見た彼の逞しく元気な姿から考えるに聞くまでも無いのだろうけど、それでも僕は飽きもせずに毎度毎度尋ねていた。
「うん。三月からアルミア地方に行ってるみたい。今日は飛行機で駆けつけたみたいだけど」
「すごいなぁ、レンジャー志望かな」「どうだろう。そんなことも言ってたけど、すぐに興味が変わる子だから」
ついこの前はドラゴン使いになるって張り切ってたのにね、と菜美子はそう言って肩を竦めた。頭の中に、ボーマンダに乗って空を飛び回る大貴の姿が現れる。想像上の従兄弟は、晴れ渡った空を背にして眩しい笑みをこちらに向けていた。
ひとたび現実に戻ればしかし、はっきりとしない空が我々の上に広がっている。手に収めた猪口に映り込む空は、流れるような灰色の雲をひたすらに浮かべていた。猪口の底には墨絵のハンテールが描かれており、注いだ酒が揺れるのと一緒になってゆらゆらと揺蕩った。
細長い身体が揺らめいて、雲の藻に幾つもの斑点が見え隠れする。「でもねぇ」菜美子が酒に口をつけて言った。彼女の使う猪口にはサクラビスが描かれているはずだった。
「ああして、ここで元気にしてるのが、まだ信じられないことがあるんだよねぇ」
ここに来るといつもそう思う。この屋敷で大貴が普通に笑ってるのを見るとね。
大樹やその他の木々が起こす葉擦れの音が、菜美子の声に被さった。濡れた空気を吸い込むと、深緑が肺の奥まで流れ込んできた。猪口を摘む右手の指が、薄く汗を掻いている。
大貴は昔、この屋敷で生死を彷徨ったことがあった。
◆
僕が十になった頃のことであった。
盆のために屋敷へ僕の家族と菜美子の家族が集っており、まだ四つになるかならないかという幼さの大貴もここに訪れていた。
その時、僕はあの洋間で菜美子と共に、姉に本を読んでもらっていた。無論洋間にあるような読めない文字で書かれた本ではなく、前日に祖父が本屋で買ってくれた子供向けの冒険小説だった。ホエルオーに呑み込まれた主人公が胃の中から巨大な鯨を攻撃し、脱出を試みるシーンであったと記憶している。
母が持ってきてくれたジュースを飲みながら、僕たちは洋間で緩い時間を過ごしていた。よく晴れた午後で、けたたましいテッカニンの鳴き声に姉の朗読が重なるのが心地良かった。湿気はやはり満ちていたが、廊下から吹く風は涼しかった。
菜美子や大貴の母親の悲鳴が聞こえたのはそんな折だった。言葉にならない言葉をただ音として表したような叫び声は、長い廊下を渡って僕たちの元まで届いてきた。
最初に反応したのは姉で、次いで菜美子が弾かれたように立ち上がった。それからのことは怒涛のようで、詳しいところまで把握することは不可能だった。父や母、叔父の叫ぶ声や怒号が飛び交い、菜美子や彼女の母親が泣く音もした。僕はどうすることも出来ず、一人洋間に取り残されて呆けたように座り込んでいた。ジュースの入っていたコップが空になって床に倒れていた。姉や菜美子が立った衝撃でそうなったのかと思い、絨毯に染み込んでいないかを霞んだ頭で心配した僕は足元の天鵞絨を指でなぞってみたが、酷い湿り気のせいで僕の指も絨毯も、元から濡れていたようなものであった。毒々しいほどに鮮やかな紫の、香料がきつい液体は一滴も残っていなかった。
ふらつく足でようやく廊下に出た。洋間の外は湿気が一層酷かった。救急車のサイレンが聞こえて、運ばれていく従兄弟の姿が一瞬だけ見えた。柔らかで健康的な小さい手足はぐったりと投げ出されていて、噴き出た汗のせいかぬらぬらと光っていた。
一つ、はっきり記憶に残っていることがある。
救急車への同乗を許可されたのは大貴の母親だけで、自分もついていくと強く訴えた父や菜美子は屋敷に残るよう命じられた。
そうしたのは他ならぬ祖父であった。救急隊員に縋りつく菜美子たちを引き剥がし、祖父は酷く恐ろしい声で、自分の部屋に戻ること、そして中庭には絶対に近づかないようにすることを怒鳴っていた。後にも先にも、祖父があれだけ激しく感情を露にしていたのはあの時だけである。
「水を飲め」
祖父はそんなことも強く言い聞かせていた。濃厚な湿気と水の臭いが充満する廊下で、僕はぼんやりと中庭に目を向けた。
陽炎の揺れるそこに鎮座する大樹は我々の騒ぎなど御構い無しに翠の葉を繁らせていた。隆々とした幹の根元、大樹の隣に位置する池の水がすっかり干上がって、中を泳ぐトサキントとアズマオウが美麗な腹を仰向けにしてごろごろと転がっていた。
◆
大貴は脱水症状を引き起こしていた。
暑い夏の昼間であったからそれ自体は何ら不思議なことではない。幼い子供は熱中症にもなりやすいのだから、目を離した少しの間に大貴がそうなってしまったのも無理のない話である。
不可解なのは、大貴がどうして、一人で中庭へ向かったのかということだった。当時の彼は今と違って大人しく、また母親に甘え盛りであったためにそばを離れて何処かへ行ってしまうなどということは滅多に無かった。その上、彼がいたのは渡り廊下の向こう側の家屋であり、縁側から中庭へすぐに行けるということも無い。彼が中庭に行くのなら、屋敷にいる誰かしらが気がついても良さそうだった。
大貴は、大樹の根元に倒れていたという。小さい身体からは水分が失われ、丸い目は全くもって閉じられていた。
「あの時、大貴が死んだのだと思った」
薄明るくぼやけた空を見上げて菜実子は言った。
「もう大貴は、ここにいないんだって考えたの。救急車が運んでいったあれは大貴の抜け殻で、本物の大貴は、この庭に閉じ込められてしまったんじゃないかって」
「でも、大貴は戻ってきたじゃないか」
「そう。戻ってきた。信じられなかった」
生死の境を彷徨うこと数日、大貴は無事に回復した。後遺症なども特段無くて、まるで何事も無かったかのようでった。むしろ歳を重ねるにつれて彼は活発になり、命の危機を垣間見たとは感じさせないほどに健康そのものである。しかし菜実子は、また彼らの父や母は、ふとした瞬間に彼がまた死に向かってしまうのではないかと不安になるという。それは単なる過去への恐怖というよりは、この屋敷に訪れると無条件に襲いくるものだと菜実子は述べた。露に濡れてぬらぬらと光る、大樹の葉を見る毎に、自分の弟がどこか違う世界へ連れて行かれる思いに駆られるのだ。水気の満ちる空気に、大貴が溶けてしまうかのような錯覚を覚えるのだ。
「それでも、大貴がここに踏み入ることは流石に無いのだけれどね」
「そりゃそうだ。いくら小さい頃といっても、何と無く覚えているのだろう。自分が死にかけた場所になんて、入りたくないに違いない」
菜実子の言葉に頷きながら、僕は杯に揺れる酒を舐めた。眼前の中庭に生える大樹は、あの日と何も変わらずに青々という葉を只管に繁らせている。
大貴が病院へ運ばれた後、祖父があの下に立っているのを見た覚えがある。何をしているのかはわからなかった。炎天下の中、大樹を強く睨みつけている祖父は、汗の一つも掻かずに太い幹の前で仁王立ちをしていた。少しも鳴り止まぬテッカニンの声が、警鐘のように何処か遠くから聞こえてきた。
「そう、庭に入らないといえば、明久君が怒られたことがあったね」
その祖父も今はもういない。話題を逸らした菜実子に、僕は苦笑と軽い溜息を返した。自分の口から吐き出された酒精の匂いが夜風に運ばれる。
「怒られたというほどではないだろう」
「まあね。おじいちゃんはいつもああいう顔だから、怒っているのかどうかもわからないし」
でも、あれは怖かったよと菜実子が笑った。首肯を以てそれに応えながら、僕は友人の家に置いてきた相棒のことを考えていた。
◆
僕が初めてポケモンを持ったのは、トレーナー免許を取れる最低年齢から三年遅れた中学一年生の時だった。
友人の中には旅に出る者もいたし、そうでなくとも自分のポケモンを持つ者もそれなりにいたが、ポケモンといるよりかは本を読んだりゲームをしたりという方が好きだった僕は、取り立ててポケモンが欲しいとも思っていなかった。祖父の家に来ればオドシシやメブキジカと遊べるし、平素は友人や学校のポケモンを見たりするだけで十分だったのだ。家にいたポリゴンは姉のものであったが、ほぼ共同のポケモンであるようにしていたのも一因と言える。
その僕がポケモンを持つ機会となったのは、菜実子の中学進学であった。進学祝いにポケモンを欲しがった菜実子は、研究者である哲人叔父のツテで初心者向きのポケモンを用意してもらえることになったのだが、もしよければ一緒に来ないかという誘いが僕にもきたのだ。その頃はまだ大貴も幼くポケモンを持てる年齢では無かったため、菜実子が一人でポケモンと対面するのは心細いと叔父に訴えたらしかった。
父も母も、そして僕もポケモンを持つのに反対する理由は特に無かったため、菜実子の家へ遊びに行くのも兼ねて申し出に甘えることにした。カントー地方から菜実子たちのいるホウエンまで、生まれて初めて自分だけで飛行機に乗った。着替えを詰めた鞄がこれほどまでに重いのかと思ったのも、機内の無機質な空気がやけに重苦しかったのも、あの時が最もそうだった。
空港で待っていてくれた哲人叔父一家に迎えられた僕は早速、菜実子と共に研究所へ向かった。駆け出しのトレーナーに適しているようなポケモンが何種類か、リノリウム張りの床で好き勝手に走り回っていた。僕は一番大人しそうな、柱の陰で退屈そうに丸まっていたヒトカゲを抱き上げた。これといって抵抗もせず、かといって喜びを見せるわけでもない橙色の柔らかい物体と顔を付き合わせている僕の後ろで、菜実子が頬をぷくりと膨らませ、小さなアチャモを追いかけまわしていた。
そうして僕はヒトカゲを連れて家に帰り、特段問題も無い日々を過ごしていた。ヒトカゲは予想以上に怠惰な性格であった。炎を司る種族であるくせに暑いのが苦手なようで、夏が近づくにつれて丸々とした腹を天井に向けて我が部屋で転がっているのをよく見た。
やがて盆の季節になり、祖父の屋敷に行く時期が来た。ポケモンを持ったことを祖父に報告しなさいと父が言ったため、ヒトカゲも連れて行くことにした。ボールに入れられた彼はいつも通りにぼんやりとしていて、眠たげに身体を丸まらせていた。
屋敷に着き、僕はヒトカゲをボールから出して祖父の元に向かった。ヒトカゲは自分で歩くことを面倒臭がるため、僕が抱きかかえて運んでやった。激しい湿気と夏の暑さに加え、腕の中にいる高体温の生き物が汗腺を執拗に刺激した。
「そいつを今すぐに戻せ」
ヒトカゲを見た、祖父の第一声はそれだった。
「その火を持ち込むな」
座敷に胡座をかいた祖父は微動だにせずそう言った。怒鳴っているわけではないし、激昂されたというわけでもない。ただ、有無を言わせぬ声で、僕は立ち退きを命じられた。
呆然と立ち竦み、戸惑う僕の後ろで、同じようにアチャモを見せようとしていた菜実子が赤い雛をそそくさと後ろに隠しているのが視界の端に見えた。菜実子は存外ちゃっかりした性格であった。抱きかかえたヒトカゲの爪が、腕を回された首筋に食い込むのが微弱な痛みとなった。鱗に覆われた尻尾の先で燃える炎が揺らめき、無言で我々を見ている祖父の姿を、まるで陽炎のように溶かしていた。
僕は何も言えずに祖父の部屋の扉を閉め、菜実子と共にポケモンたちをボールに戻した。悲しみや怒りといった感情は、唐突な驚きにすっかり掻き消されてしまっていた。廊下から見える中庭だけが変わらぬ様子で、大樹に繁る葉がばさばさと音を立てていた。
あれからずっと、屋敷にヒトカゲを連れて行っていない。それは彼がリザードになってからも同じだし、菜実子もまたそうだった。もう怒られるのは御免であるという理由も勿論あるが、それ以上にボールを握った我々の手が屋敷の門を越えるのを押しとどめているのは、あの時の祖父が放った声であった。
低く告げられた、地の底から響くような声。水気の多い空気を静かに揺らしたそれは、祖父の身体の奥深くから発せられたように思えたものだったと記憶している。
◆
ヒトカゲに限らず祖父は、中庭に誰かが立ち入ることにあまり良い顔をしなかった。
野生のポケモンが勝手に入ってくるのには何も干渉しないのに、我々が敢えて連れ込んだりすることは祖父の気に入らない部類であるようだった。
父に聞いた話である。
父が中学に上がる頃には既に桜子伯母は嫁に行ってしまったし、鏡子伯母もトレーナーとして各地を回っていたため、屋敷に残されたのは父と、小学生であった哲人叔父だけだった。家政婦が通っているとはいえ祖父は日中家を空けているし、二人の母親は幼い頃に亡くなっていたため、取り残された兄弟は必然的に揃って行動するようになっていた。
哲人叔父は昔から兄たる父によく懐き、憧れている部分があったから、二人の趣味嗜好は似通っていた。父と叔父は夏休みになると、午前中に図書室へ出かけ、昼になると帰ってきて食事をとり、あとは一日借りてきた本を読み耽るという生活を送っていたという。余談であるが、今現在の叔父が研究者であることと、父が大学教授という職に就いたことはその頃の過ごし方が深く関係しているのだろう。ともかく、父たち兄弟の生活は夏休み中変わることが無く、彼らは障子を開け放した座敷に本をいっぱいに広げて時間が過ぎるのを待っていた。部屋に寝転がる兄弟は蒸し暑くも穏やかな夏に包まれており、中庭を臨む縁側からは緑臭い風が時折涼しさを流してきた。桜子伯母が帰郷した際に持ってきた、薄い硝子にぽってりというラブカスを描いた風鈴がその度に、水粒を転がしたような音を立てた。薔薇の花弁にも見える海水魚達が、陽光を乱反射させてゆらゆら泳ぐ。
その日、祖父は珍しく一日屋敷にいた。仕事がひと段落ついて休みを取っていたのか、或いは家ですべき業務があったのか、誰かをもてなしていたのかは定かで無い。それに祖父がいたからといって父たちと共に遊ぶというわけではなかったため、父も叔父もいつも通りに二人で過ごしていた。
父はカントーの生態系変化について書かれた本を読んでいた。生物学に興味を持っていた父の真似をし、叔父は分厚い植物図鑑の頁をせっせと捲っては並ぶ草花の写真をに指をなぞらせていた。図鑑は古く、日に焼けて黄ばんだ頁を一枚捲る毎に乾いた音がか細く聞こえた。紙の酸化した臭いが少年の鼻をつく。
そうして写真を見ているうちに、幼い叔父は見覚えのある植物を本の中に見つけた。それはついぞ先日、縁側から見た中庭の光景にあったものだった。叔父は、汗で畳と張り付いてしまった膝を起こして中庭の方へと向かった。真っ白のタンクトップから露出する腕には、畳の目の跡がびっしり走っていた。
「どうしたんだ」活字が犇めき合う本から少し顔を上げて父が問うた。「あれを探しに行くの」叔父は答えながら開いたままの図鑑を指差したが、幾種類かの植物が載った中のどれを言っているのか、父に見当がつくはずもなかった。「ふうん」父は緩く頷き、細かな文字の海へと意識を戻してしまった。
物静かな兄の反応が芳しくないのはいつものことであるため、叔父は特段不満に思うこともなく中庭へと降り立った。覆うもののない足の裏が土を踏む。地下から伝わる冷たさと、炎天に焼かれた熱さが同時に皮膚を襲った。叔父は跳ねるようにして中庭の奥へ進んでいった。紺青の空は眩しかったが、大樹の落とす広い影は中庭を程良い明るさにしていた。
図鑑の写真と似通ったものを目指し、叔父が一歩を踏み出した時だった。叔父の左腕を掴み、強く引っ張る者がいた。
「何をしている」
それは祖父であった。いつの間に近づいていたのか、縁側に立った家着姿の祖父は小さな息子の腕を掴んでただ問いかけた。「何をしているんだ」
「あの葉っぱを探すの」
叔父は素直に答えた。彼の指が先ほど兄へとそうしたように、座敷の図鑑を指差した。図鑑の近くでは、祖父が急に現れたことに驚く父が頁を捲る手を止めて身体を硬直させていた。
答えた叔父に、祖父は怒るでもなく笑うでもなく、そうか、とだけ返した。しかし細っこい手首を握る、骨張った手が離されることはなかった。縁側から叔父を見下ろしたまま、祖父は淡々と言った。
「あまりこの庭に出ない方がいい。毒に触れると危ないから」
「毒のある葉っぱがあるの」
「葉っぱだけじゃないから危ないんだ」
障子の向こうで交わされる会話は、聞いていた父からすると微妙に噛み合っていないものに思えたという。玻璃の如き青空を背にした親子の姿を見ていると目が霞み、眼下の文字列が得体の知れぬ微小な生物が蠢いている様子に感じられた。座敷に満ちた湿気に蒸された頭は、藺草の臭いだけを執拗に捉えて少年の意識を朦朧とさせた。
◆
玄関へ続く廊下に置かれた柱時計が、深く低い音を一度鳴らした。屋敷の床を伝って響くその音は、今我々の後ろで棺に収まっている祖父の声を思わせた。
薄暗い中庭で、どこから来たのか、コロボーシの鳴く声がし始めた。彼らが震わせる夜の空気は冷えていたが、それを凌ぐ蒸し暑さが全身を覆うように漂っていた。
「おじいちゃんはいつも怒っていたようで怖かったけど」
菜実子が違う酒瓶に手を伸ばしながら言う。
「でも、一度おじいちゃんと二人だけでお祭に行ったことがあるの」
杯に注がれたのはどうやら果実酒だったようで、甘さと酸っぱさの混じり合う匂いがつんと鼻腔を突いてきた。緋色の曇りのある透明な瓶には筆絵のヒメリが描かれている。菜実子の杯で、黄金色の液体が小さく波打ちちゃぷんと音を立てた。水底のサクラビスが身体を翻す。
「そんなことあったっけ」
「八歳の頃。明久君たちはその次の日にくる予定で、本当は私たちの家族とおじいちゃんで行くつもりだったんだけど、大貴の準備が手間取ったから。私と、おじいちゃんだけで先に行ってなさいって」
「なるほど」
「自分で言うのも何だけど、その時のことはよく覚えているの」
菜実子の白い喉が、酒を飲んでこくりと音を立てた。金の水が流れる動きに合わせ、首の皮膚が盛り上がったり元に戻ったりした。
それがどうにもグロテスクで、僕は庭へと視線を戻す。杯に残っていた酒を飲み干し、枝を広げる大樹の葉の隙間から、無理くりに夜空を見ようなどと無意味な試みを徒にした。熱を持った目元は霞んで、視界に捉えた青墨色が単に木の葉がぼやけたものなのか、それとも本当に夜の雲居であるのか、決めることは出来なかった。
◆
ソノオの神社で毎年行われる夏休みへ、祖父に手を引かれた菜実子は向かっていた。
祖父の歩くスピードは速く、菜実子の小さな歩幅ではついていくのが精一杯だった。慣れない浴衣も足を開きにくい一因となり、裾に描かれたシャワーズの見返りの絵柄も着た当初に比べて色褪せたものに感じられた。腰に締められた赤い金魚帯がどんどんきつくなった。
自分の腕を掴んで先へ先へと進んでいってしまう祖父は、菜実子にとって恐怖の対象であった。怒られているわけでも叱られているわけでもなく、むしろ祭に連れて行ってくれているということは理解しているのだが、それでも仏頂面で終始無言の祖父はその気が無くても高圧的な印象を与えざるを得なかった。年の割に背が低く、祖父を見上げるためには首を痛くなるほどに傾けなくてはならなかったのもその一因かもしれない。
祭に浮き足立つ参拝客の間を縫いながら、菜実子は今頃家で準備をしているだろう両親や弟のことを考えていた。本当ならば今自分の手を引いているのは祖父ではなく、人好きのする優しげな丸顔の父であったろうし、或いは勝気だけども笑顔を絶やさぬ母であったであろう。そうでなくても、サンダースを描いた紺の浴衣に身を包んだ、やわやわとした弟の片手を自分が引っ張っていたかもしれなかったのだ。人ごみの中に弟ほどの年頃である幼児を見つける度、菜実子の心はどっしりと重くなった。
早歩きをしたせいで、小さい菜実子はすっかり疲れ果ててしまっていた。この日のために父が買ってくれた下駄の鼻緒は指の付け根を幾度となく擦り、薄い皮膚は裂けて滲んだ血が黄色の鼻緒にこびりついた。人波に熱された空気は息苦しく、階段を上りきる頃には肺が悲鳴を上げていた。がやがやと絶えることのない参拝客らの話し声や行き来するポケモンたちの鳴き声、屋台から放たれる呼び声が一緒くたになって鼓膜を揺さぶった。本殿から聞こえてくるお囃子の、篠笛の甲高さは浴衣の下の肌を粟立たせた。お好み焼きや焼きそばの屋台から漂ってくるソースの匂いは例年ならば食欲を引き起こすものであったが、滅入った気分をさらに悪くするだけだった。
ただ、そんな菜実子の心中を祖父も察していたようで、険しい表情こそ崩さないものの、立ち並ぶ屋台に近寄ってはあれやこれやと買い与えて孫の機嫌をとったらしい。甘ったるい水飴を舐め、粉末ソースと砂塵とが混じったお好み焼きで腹が膨らむと、菜実子の緊張も幾らか和らいだ。ビニールのプールに浮かんだスーパーボウルを赤と緑と白地に金筋、そしてマルマインの顔を描かれたそれを祖父が見事掬い上げたので菜実子は歓声を上げた。
サーナイトのお面を買ってもらい、側頭部にそれをつけて菜実子は上機嫌であった。相変わらず祖父が菜実子の歩く速さを待ってくれることは無かったが、靴擦れの痛みも帯の苦しさもいつの間にか忘れていた。すれ違った、桃色の浴衣の少女が掌に弾かせる水ヨーヨーが鈍い音を響かせる。かき氷屋の暖簾の下で、グレイシアが熱気を凌ぐようにして地面に伸びていた。
「なんだ、怖いのか」
不意に菜実子が祖父の手を強く握った。それはお面屋に並んだ面に混じって舌を出している、悪戯なゴースを見つけて驚いたことによるものだったが、祖父にそれは伝わらなかったようだった。祖父は、お面屋の向こうにある本殿を見て菜実子が怯えているのだと思ったらしかった。
朱塗りの本殿では軽やかなお囃子に合わせて舞が披露されていた。緋色の袴と純白の舞衣に身を包んだ巫女が四人、透けた般若の面を着けた男と赤帯の女を挟み込むようにして舞っていた。当時の菜実子にわかるところでは無かったが、毎年披露されるその舞は神社が出来た由縁、ソノオの花畑を氷雪に包み込み人々を苦しめていた邪神たるオニゴーリとユキメノコが術師に封じられた末、二度とそのようなことの無いように祀られたという様子を表すものである。
祖父はそのことを知っていたのであろう。邪神を封じた焔に見立てた真赤の鶏頭が大きく振られて靡く本殿を見やり、握った手の先にいる菜実子にこう言った。
「怖がる必要は無い。遥か昔に奴等の力は潰えたのだし、それに」
祖父の空いた片手が、本殿と逆方向にある鳥居を指す。「それに」
「あれがある限り、どうせ出ることなど出来るまい」
声や演奏などの騒音の中で、祖父の声は妙に響いていたように菜実子の耳に届いた。木で組まれた鳥居はどっしりと、暮れかけた空を背にして聳え立っていた。組み木の間から一番星の弱々しい輝きと、紫色の空に溶けるようにして飛んでいくムウマの姿が見て取れる。闇色をした小さな魔物はふわりふわりと浮遊して、橙の西空へと消えていった。
祖父の言葉の意味を、菜実子は理解することが出来なかった。手にしていた綿飴が参拝客の熱気で蕩け出し、幼い片手と薄青の袖をべたつかせた。溶けたそれよりも大分重そうな鈍色の雲が、本殿の遥か上空に浮かんでいた。
射撃ィ、という禿頭の呼び声がどこか遠くに聞こえたような気がした。同時に鳥居の向こう側に見つけたのは、ようやくやってきた両親と弟の姿であった。支度時にぐずったままに泣き跡を残した弟の顔を見るなり、菜実子は祖父の手を離して勢いよく駆け出した。
その拍子に落としてしまった精霊の面を、祖父が拾い上げる音を背中に聞いた。
◆
「結局、あの時振り払ったっきり、おじいちゃんと手を繋いでないんだ」
それで、あれっきり。果実酒で喉を潤す菜実子は微かに息をついた。視界に映る天空の半分を覆い隠す軒は殺風景で、いつかあったような風鈴などは外されたままであった。透き通る器を打ち鳴らす音の代わりに今聞こえるのは、鈴の音の如き蟲の鳴き声である。不規則に思えてその実規則的な声は、まるで耳元のすぐ近くで小さな銀の鈴を只管鳴らされているかのような心地にさせた。
「今思うと、おじいちゃんがあんなことを言うのも珍しかったかもしれない」
「あんなって」
「出てこれないだとか、怖がる必要は無いだとか。おじいちゃん、そういうの信じなそうだもの」
杯を両の手に乗せた菜実子の顔がこちらを向く。白く膨らんだ頰に月の灯りが当たって、柔らかな肉がどこか青白く映し出されていた。僕は少しだけ豆大福のことを思い出したが、そういうと菜実子は決まって僕を叱りつけるために黙っておくことにした。
丸い頰から視線を外して下方へ移す。「それでも、あのくらいの歳の人なら普通のことか」一人で納得する菜実子の手首の先、頰と同じ程の白さをした手は昔ほどでは無いにしろ、強く握れば蕩けて消えてしまいそうな心持ちを抱いた。この手を握り、引き、そうしてするりと抜けだされたしまった時の祖父は一体どのように思っていたのだろうか。「シンオウの人だしね、そういうの大切にしてるのかも」濡れた綿菓子が瞬く間に、ほんの少しの名残だけを後に消し去られてしまうような心地に襲われたりは、しなかっただろうか。
神社の雑踏。不気味さを伴う祭囃子。鳥居の中に祀られるは、遠い昔に封じられた邪神。
自分の手から、繋いだ手が抜け出てしまった祖父はその時も、あの珍重とした態度を崩さずに在ったのだろうか。
「信仰心とか、そういうやつなのかな。それなら、ひいおじいちゃんの方があった気がするけど」
菜実子の言葉に合わせて漂動する甘酸っぱい匂いに、足元の草の臭いが被さって奇妙な感覚を嗅覚に与える。池の中でアズマオウが跳ねる音がした。「あれは信仰といっていいのかな」半ば呟くように返した僕に、菜実子は一言「そうだね」と鈴の音程度の小さな声で言った。
◆
曽祖父、つまり祖父の父たる伸之助には総之助という兄がいた。
しかし生まれつき身体が強くなかった総之助は、二十を目前としたところで早い死を迎えたため、総次郎の後を継いだのは次男たる伸之介だった。
江角家初代総次郎は商売に関して俊豪であったが、伸之助にその能力が受け継がれることは無かったようである。総次郎の商才が血と共に流れ出て総之助の脆弱な身体を巡っていたのか、或いは彼らの妹でジョウトの宿屋の女将になった養女に継承されていたのか、それかはたまた、広い屋敷の湿気となって空虚に溶けてしまったのかは依然わからない。ともかく総次郎亡き後、伸之助は父の工場を継いだは良いが父のように切廻すことは出来ず、シンオウ指折りとも呼ばれた江角の名は、緩やかな坂を転がり落ちるように少しずつその輝きを鈍らせていった。
父の持つ商才は全く以て受け継がなかった伸之助だが、しかし強情で牢固たる性格の方はそっくりそのまま写し絵をしたかのように似通っていた。伸之助の危うい経営に周囲の者は度々口を挟もうとしたが、荒い気性と狷介ぶりはそれらを全て跳ね除けた。
結果的に工場の経営は破綻し、伸之助は限界まで膨れ上がった借金を抱えることになる。それらを処理して回ったのが、それこそ総之助の生まれ変わりかとも囁かれる鬼才であった江角家三代目、僕の祖父たる重雄であった。
◆
総次郎の死は、質素で堅実と言えども栄光たる人生を歩んできた男に似つかわしく無い、呆気ないものだった。
彼は息を引き取るその日も工場で采配を揮っていた。その頃の総次郎は優秀な部下に囲まれ、また慕われてはいたものの、いまいち光るところの無い息子の教育に始終頭を痛めていたという。総次郎とて他の者を後釜にする選択肢くらい思い浮かべたであろうが、世襲が当たり前であった時分、差しあたって心身共に健康である実子を却下してまでわざわざ別の後継者を探す理由も無かった。伸之助自身に後継ぎの意志があったのも、彼が江角を継ぐことになった原因の一つである。そのため総次郎は不安を抱えつつも、伸之助が自分の座に就けるように刻苦していた。
長いことそのような生活を続けてきたように、総次郎はその日も工場から帰り、風呂に入り、夕食を摂り、毎夜の習慣だった一杯の酒を飲んで床に就いた。それが彼の最期であった。夏の夜で、蒸した屋敷はさながら熱帯夜とでも呼ぶべき暑さであった。
夏用の掛布団にくるまれ、総次郎が動かなくなっているのを最初に見つけたのは洗濯のため部屋に出入りしていた使用人であった。普段ならばとうに総次郎の起きている時間であったから、使用人はいつも通りに彼の部屋に入ったのだが、いざ布団を持ち上げようとしたらその中にいたのは硬くなった主人であった。
まさに眠るようにして亡くなった総次郎だったが、一つだけ不可解なことがあった。総次郎は酒盛りを好む他には極めて健康的な生活を送っていたにも関わらず、死後に調べた結果内臓や消化器官、骨など体内の隅々に渡るまで、まるで酷使されたかのように壊滅的だったという。何物かに食い荒らされたかとも思えるその様子は異常であったが、その原因に思い当たる者は誰もいなかった。
果たして総次郎の死は謎のまま、江角の名を伸之助が継いだのである。
◆
「ひいおじいちゃんのことは、あの場所でしか知らないからなぁ」
白い頬を薄紅に染めた菜実子が言う。
あの場所、というのは中庭の向こうにある家屋を隔てたさらに向こう側、塀との間に設えられた蔵のことである。
石造りの蔵はかなりの古さを感じ取れるものの非常に丈夫であり、雨に打たれても雪に降られても壊れる兆しを見せずに建っていた。所々が罅割れて不規則な溝を作っているその蔵には、曽祖父伸之助が集めた品の数々が収められていた。もっとも、本当に芸術的価値があったりまたありそうなものは、屋敷を立て直す際に祖父の手によって粗方売り払われているのだから、今現在あそこにあるのは眉唾ものか贋作、そうでなければ路傍の石とも呼ぶべき無名の代物で、単なるがらくた部屋に過ぎないであろう。
「あの物置か。どうだろう、昔は何度か入ったこともあるけれど、よく覚えてないな」
「暗くてよく見えないしね。私、あそこ苦手だったんだ。なんだか怖いから」
「父さんたちは悪いことをすると、決まってあそこに閉じ込められたらしい」
僕の言葉に、菜実子は呼吸だけで笑ってみせた。弦楽器をはじいたように鳴く、コロトックが揺らす空気に菜実子の息が溶けていった。首を少し動かして座敷の方を見てみると、未だ線香の匂いが僅かに残る部屋は薄暗く、祖父が只々眠っていた。
蔵の中は洋間と同じ空気をしていた。埃と黴が鬩ぎ合う、太陽の光から遮断された狭い密室は、世界の外側へ放り出された箱庭の如き静寂さを帯びていた。しかしその癖限りなく小さく寂しいはずの無人の世界では絶えず何者かの呼び声が聞こえ、無数の瞳が自分のことを見張っており、壁を越えればどこかも知らぬ場所へと行けるようにすら思えることもあった。
蔵の中に何があるか、僕はほとんど覚えていない。大体の印象は洋間のような空間だったと記憶している。奇妙な凹凸をした壺、紙魚が酷くて読めない書物、襤褸といった方が適切であろうほどに劣化した羽織。かと思えば、やけに綺麗で美しい状態を保っているグラエナの剥製などが、蔵の片隅で硝子玉の眼を眈々と光らせており、どうにも不気味な場所であったことは確かであった。
「あそこに入った時に見たもので、一つすごい覚えてるものがあるの」視線を杯に落とした菜実子が言う。揺れる酒に映った菜実子の顔はほろほろと崩れては元に戻り、そうしてまたその形を幾つかの破片に変わるのであった。
「何を?」
「巻物。いつのものかわからないけど、とても古かった」
どんな、と尋ねた僕の方へ菜実子が顔の向きを変えた。丸い瞳が僕を見る。その中に映り込む自分の姿は、以前同じ場所で同じように彼女の瞳に入った時同様に、どうにも間の抜けた顔をしていた。
「酒呑童子の」
菜実子はそこまで言って一度口を閉じ、少しだけ俯いて「酒呑童子のお話だった」思い出しながら話し始めた。「昔の絵本みたいなものなんだと思う」
「鬼を酔わせて退治する話だったっけ」
「そう、それがあった」
「何でそれだけあるんだろう」
「わからないよ」
菜実子が困ったように口を尖らせる。特別薄くも厚くも無い唇は酒に濡れていて、彼女が何かを言う毎に合わせて光った。
酒呑童子の絵巻とやらに見覚えは無いが、かといってそんなものは絶対に無かったとも言い切れない。何が収められているのかすらも把握出来ないあの蔵に、それがあっても不思議なことではなかった。
「おじいちゃんがお酒好きだったからかな」
小首を傾げた菜実子が、人差し指と中指で杯の縁をついとなぞった。陶器の擦れる幽かな音が響く。自分の噂をされていることなど露知らず、後方に眠る祖父は唯々静かなままである。
「酒が好きだった割には、あの口癖はどうかと思うけど」
「そうね。でも、それこそ酒呑童子っぽいし」
「なるほど、確かに鬼っぽい。仲間が酒でやられたから戒めとして言い続けてた、か」
「ちょっと、怒られるよ。鬼だなんて」
けらけらと笑う菜実子が、僕の肩を軽く叩きながら目だけで祖父の方を指す。薄い布越しに弱く感じる体温はしかし確かに熱く、湿気に汗ばんだ肌の温度を殊更に上げた。
庭の草の根を視線で掻き分けると、勝手に住み着いたらしい、フローゼルの母が影に丸くなっているのが見えた。柔らかな毛に覆われた腹に守られてめいめい寝息を立てているのは、一見毛玉かと見紛うブイゼルの子供たちだった。明るい茶色の毛がくっつき合って並ぶ様子はまるで鞠のようであった。
「あの口癖。私は、数える程しか聞いたことのないのだけど」
「僕もそうだ。しかし父さんは何度も言われたらしい」
獣の親子が眠る上空には、葉を繁らせた大樹の姿がある。
天高く伸びるその幹は太く隆々としており、あたかも鬼の剛腕の如き風体を醸し出していた。
◆
酒は毒だ。
それが祖父の口癖だった。その癖祖父はかなりの酒豪で、夜毎に酒瓶を一本は空けるかというほど酒を飲んだ。酒に強いのは父親譲りで、その伸之助も父総次郎から受け継いだ数少ないものとして、酒精への不敗を徹底していた。
親譲りの酒豪たる祖父はとにかくよく飲んだ。どれだけ飲んでも顔を赤くする素振りすら見せることなく、涼しい風体で盃を傾け続けていた。その様子を見て、まるで水を飲んでいるようだと揶揄する者もあったけれども、水とてあんなにすいすいと飲むことは困難であろう。
食べ物に好き嫌いが無い祖父は、酒にもとやかく言う性分では無かったが、しかし贔屓にしていた酒はあった。その酒は薄紫をした硝子瓶に入っていて、凹凸の少ない素朴なデザインの容器は陽に当たると菫の花弁の如き光影を地面に落とすのだった。透き通った硝子瓶はそれほど大きくなく、酒が入っている状態でも片手で持ち上げられるほどであった。
その酒の銘柄を僕は知らない。僕だけでなく、菜実子や、父たち祖父の子供も同様である。一般的に売られている酒とは違い、その酒瓶には何のラベルも貼られていなかったし、何かが書かれていることもなかった。祖父は知っていたのかもしれないが、結局誰にもそれを言わないまま死んでしまったのだから、あの酒が如何なるものだったのかは謎のままである。逢魔ヶ刻と呼ばれるような黄昏の空を流し込んだような、青とも黒ともつかぬ紫色の瓶の中で揺れる液体がどんな名を持っているのか、何で出来ているのか、誰によって造られているものなのか、今となっては果たして迷宮入りだ。
その秘密を知ってか知らずか、祖父は兎角その酒を好んで飲んだ。桜子伯母が物心つく頃には既にそうであったし、僕の姉が屋敷に住み込んでから禁酒を医者に命じられる直前まで、祖父は紫の硝子瓶に揺蕩う酒を飲み続けた。
◆
座敷に転がっていた箱から煙草を取り出し火をつける。羽を広げたウォーグルが一羽、濃紺の背景に描かれたその箱は哲人叔父の忘れ物だと見受けられた。祖父は火事を案じていたため屋敷内での喫煙を嫌ったが、この湿度ではたとえ庭の草木に火が燃え移ったとしても、膨れ上がる前に立ち消えてしまうのでは無いかと思われた。肌に貼りつく湿気の中、一緒にあったライターで数回の失敗を経て点火する。
「煙草は普段から吸うの」
「いや。友達からたまにもらうくらいかな」
「高いものね」
最近、また値上がりしたし、という菜実子の言葉に頷きながら息を吸い込むと、肺の奥で熱と芳香が渦巻くのを脳が認識した。身体の中で何か別のものが生成されるこの感覚にいつまで経っても慣れることが出来ず、僕はこの、薬草を乾かしただけのこの物体を咥える度に、飽くことも無く鼓動を速めているのだった。熱くなった胸の内が加速する。自分の半身が奇妙な熱に侵されていく心地は、僕が自分自身でない何者かに乗っ取られ、それに作り変えられていくようにさえ思えるのだ。
胸中で作られた煙をほうと吐き出す。独特の匂いが闇に解け、庭に生える植物の臭みにぶつかった。我が口から漂うその匂いは湿気によって強められ、いつも同じものを纏っている叔父がすぐそこにいるという錯覚を僅かに引き起こした。
「煙草の味の違いなど、僕にはわからないからなぁ」
そもそも美味しさ自体がわからない。そのことを菜実子に告げると、彼女は「それならどうして吸うの」と呆れたように口を開けた。ごもっともなその意見に頷いて、僕はもう一度煙を吐いた。環状の気体が浮かび上がる。
「酒豪の血も流れてないから、酒の審美も出来やしない」
「それはどの道、お父さんたちの誰も受け継いでいないじゃないの」
「その通りだ」
一晩飲み明かすと言った癖して、日が変わるまでが精々であった父たち姉弟を思い出した僕は苦笑した。けらけらと笑いつつも杯に紅い口をつける、隣に座った菜実子の方がまだ彼らよりも酒に強い部類であろう。祖父まで続いた三代の酒豪の血は、誰にも譲られないまま何処かに流れ出てしまったらしい。
指の間に光る小さな炎は赤かった。その先から上がる煙と、先程自分が吐き出した煙が揃って天へと向かっており、月と我が目を隔てる雲と重なり合って両者の見分けをつかなくしていた。
◆
鏡子伯母が初めて酒を飲んだのは、彼女が十六の時だった。
今でこそ活発に各地を飛び回り、老いを知らぬ盛んな血気を評判としているが、昔の鏡子伯母は大変生真面目な性格をしていたらしい。よく言えば淑やかで清廉な症状であったが、はっきり言って愚直な世間知らずである、とは今の鏡子伯母本人の言葉である。
人一倍能天気で天真爛漫とした姉の桜子伯母と一緒にいると、その真面目さはより一層際立った。社交的で好奇心が強く、何事にも積極的に介入していく奔放な姉と、内気で保守的なところがあるが、与えられた課題を黙々とこなす実直な妹を比べ、二人を知る近所の者などは度々その様子を、それぞれ攻撃と防御に特化する、化石から復元された二種の龍に擬えていた。
当時女学生だった鏡子は、学業と嫁入り修行、そして幼少の砌より続けていた薙刀の稽古に打ち込んでいた。手を抜くということを知らない彼女はそのどれもに心血を注いでおり、一瞬たりとも気を休ませることのない日々を送っていた。母はとうの昔に家を出てしまっていたし、父も仕事で日夜多忙であるから、呑気な姉に代わって自分がしっかりしなくてはという自負もあったのかもしれない。長い黒髪を三つ編みにひっつめた鏡子は両眼をきっと吊り上げて、朝は机で書物と睨み合い、昼が過ぎると汗を流して薙刀を振るい、夜が更けるまで己の中の女を磨き上げるのだった。
しかし彼女の気概も無限では無く、秋めいた風の吹く頃に、鏡子は緊張の糸がぷつりと切れたように寝込むこととなる。
迫る女学校の試験に向け根を詰めていたのが原因か、或いは薙刀の大会出場を目指して鍛錬に入れ込みすぎたのが祟ったのかはわからないが、疲労よりくる熱に三日三晩魘された鏡子は呆けたように布団で横たわっていた。あれほど忙しなく動かしていた両手両足も力を失い、絶えず燃える火の如く奮い立たせ続けてきた気勢もすっかり萎んでしまったようであった。広くも質実な自室の天井をじっと見上げ、鏡子はただぼんやりと現に暮れていた。寝続けているせいで日の匂いを失い、部屋の湿り気と微かな体臭を帯びた布団に埋れていれば、何もかもが自分を忘れて進んでいくようにさえ感じられた。
庭に面した障子が開いて、冷たい風がすいと畳を滑っていった。枕に乗せた頭だけを動かしてそちらを見ると、彼女の父の立ち姿が若干の逆光となっているのが視界に入った。秋風よりも静かに現れた父に、平素の彼女ならば何らかの言葉をかけていたのかもしれないが、その時の鏡子は口を動かすことすらも億劫であった。表情というべき表情の無い親子は無言で向き合い、塵一つない部屋の空気を風が揺らす音に耳を澄ませていた。
「来い」
先に言葉を発したのは父の方だった。仏頂面のままそう言った彼は鏡子が何か返事をするよりも先に踵を返し、障子の向こうへと歩き出してしまった。
身勝手な父の行動に鏡子は全く不満を抱かなかったわけではないが、怒るよりも大人しく従った方が楽であると彼女は推測した。薄い掛け布団を剥いで、寝間着の鏡子は起き上がった。自分の身体が鉛のようであるなどと感じるのはこれが初めてのことだった。汗ばんだ肌に、使用人の用意してくれた濡れた布を這わせると、思考を霞ませる熱から少しは解放されるようで心地良かった。
重い足を引きずり、先を歩く父についていく。連れてこられたのは父の部屋だった。
小さな箪笥が一竿と、鎮座する文机。人のことが言えた筋合いでも無いが、いつ訪れても殺風景な部屋だと鏡子は思った。自分の部屋がいつでも片付いているのは几帳面な性質がそうさせているのだと彼女は自負していたが、祖父の部屋がきっちりと整頓されている光景はそういった気性の問題というよりも、生活感と呼ぶべきものが存在していないような印象を与えた。
鏡子は畳に正座し、文机の向こうの祖父と対面していた。障子の外に広がる中庭は緑と茶、赤や黄色が混在して妙な様相を呈していた。部屋に訪れる道中に見えたメブキジカの角に黄金色の葉が茂っていたのを思い出す。焦げたように色付く木々の上空には、細かく千切られた綿によく似た雲が幾つも浮かんでいた。
文机の上には薄紫の酒瓶と杯が二つ置かれていた。素焼きの杯の底にはそれぞれ満ちた月と、そこに目掛けて羽ばたくカイリューが描かれていた。父は口を閉じたまま、カイリューの杯に酒瓶の中身を注ぎ始めた。水が流れて打ち付け合う音が鏡子の鼓膜を弱く揺さぶる。霞みがかった頭に目を閉じると、文机の上に現れた小さな滝がこんこんと清水を落としているようであった。
杯になみなみ酒が注がれると、父は鏡子の方へそれを押し出した。鼠色の器をどうするべきかと戸惑う鏡子に、父は「飲みなさい」と告げた。酒を飲むなどそれまで考えたことも無かった鏡子は驚き、そして渋るように父親から視線を逸らしたが、彼はそれでもじっと動かないままだった。
「飲みなさい」
繰り返される言葉に、鏡子は苦々しい顔をしつつも杯に手を伸ばした。音も立てずに揺れる液体は甘い匂いがした。食欲の無さと、大樹が庭から流す青臭さのせいで、鏡子の気分は少々悪くなった。
父の方を睨みつけても何も言わないため、鏡子は諦めて杯に口をつけた。一思いに傾けてしまうと喉の奥に流れ込んできたのは体内を灼きつくすかのような熱と、苦いほどの甘ったるさであった。朝から白湯しか含んでいなかった胃が弱々しげな悲鳴をあげた。
全身を駆け巡る熱さに目を白黒させ、鏡子は身体を丸めて軽く噎せた。その様子を見、父はやはり何も言わずに酒瓶を手にし、満月の描かれた杯へとその中身を注いでいつものように飲み始めた。
鏡子の咳が収まると、彼は再度龍の杯に酒を注いだ。鏡子もそれ以上何も言わなかった。落ち着いて口に含んだその甘露は先程よりも熱くはなく、また舌に心地良い控えめな甘さであった。今まで体感したことの無い味をしている、と鏡子は思った。
細い喉を鳴らして酒を飲み込んだ鏡子と向き合い、父は淡々と杯を傾けていた。薄紫の瓶の中身はみるみるうちに空になっていった。つい数刻前とは別な類に浮かされている頭で、父はこの酒を一体どこから調達しているのだろうと鏡子は疑問を抱いた。
鏡子の具合はその日のうちに回復した。それから何度か彼女は父と共に杯を交わし、時にはその酒を飲むこともあったけれど、いつか抱いた疑問を口にすることは終ぞ無かった。
◆
底冷えの激しい冬の早朝、若き頃の桜子伯母は虚ろな両眼で縁側に座っていた。
ジョウトへ嫁に行った彼女は腹に子を授かり、旦那方の家の勧めもあって出産のため帰郷していた。生まれ育った地の方が心休まるだろう、と口を揃えて言う夫やその両親たちの心遣いは確かに桜子にとって嬉しいものではあったが、何時でも無表情を貫く父親の居る屋敷がそれほどまでに落ち着く場所かと問われると、実際のところそうでもなかった。どんな心変わりか、可愛がっていた内気な妹がトレーナー修行に出てしまったため家を空けているのも寂しいことだった。それでも、一年半ほど前に出来た小さな弟と優しくて美しいその母親、そして新たに誕生した哲人という次弟に会いたさもあったため、桜子は郷里についたのだった。
しかし元来身体が丈夫な方では無かった桜子の出産は難儀なものだった。どうにか桜子の命は無事だったものの、宿った子は産声を響かせるよりも前に、十月の生に幕を引いてしまった。
体調が回復しても、桜子は全身の力を抜かれたように部屋から動けずにいた。螺子の回りきった人形のように部屋で動かず、彼女はただただ障子の外を見つめていた。連日酷い寒さが続いており、中庭は解けぬ雪で覆われていたが、極寒にも関わらず屋敷の中には奇妙な生暖かさで満ち溢れてもいた。
障子を開け放して中庭を見遣る、桜子の佇まいは異常なほどに存在感に欠けていた。特別痩せているというわけでは無いが身体は一回りも二回りも細いものに感じさせ、艶のあった髪は乱れ、紅色の頰はすっかり痩けてしまった。天真爛漫な笑顔を振りまき、誰にでも好かれる彼女の愛らしさは何処かに消え失せたようであった。
少し目を離せば、降り積もった雪の白銀に溶け込んでしまいそうな桜子の様子を皆心配した。巴さんや弟も、報せを受けて飛んで帰ってきた鏡子も、見舞いにきた旦那家族や使用人たちも、揃って同じような不安を抱いた。
その時の桜子は余りに儚げで、そして何もかもが希薄であった。産道を通るままに三途の川の向こう岸へと旅立った子のように、彼女もまた、縁側から立ち上がると同時に彼岸に消え去ってしまいそうだった。陰を落とした桜子の両眼に映るのは、枯れた葉を数枚残して寒さに耐えている大樹の筈なのに、まるで自らの妄執から成る閻魔大王の裁きに頭を垂れているかのように思われた。
「桜子」
そんな彼女に声をかけたのは父であった。桜子は聞こえているのかいないのか、或いは音としてそれを捉えてはいるものの脳が処理することを拒んでいるのか、庭を眺める姿勢のまま動かなかった。
「桜子」
しかしそれでも父は動じることなく、娘の名を繰り返して呼んだ。揺れの無い、落ち着き払った声であった。今回の件で動揺を見せなかったのは、生まれて間もない哲人を除けば、この父だけだった。
ゆるゆると力の無い動きで、桜子は首だけを回して父を見た。丸い瞳は濁りきって、氷を孕んで天空に広がる薄鼠の雲とよく似ていた。視線の先こそ父に向いているけれど、本当に桜子が見ているものが何であるのかは不明瞭であった。
「来なさい」
が、やはり父は御構い無しで、淡々とそう口を動かした。有無を言わせぬ声だった。桜子の返事を聞くよりも前に廊下を歩き出してしまった父に、経験上何かを言っても仕方ないと知っていたからか、それかそうするという選択肢まで頭が回らなかったか、彼女は至極生気に欠けた動作で腰を上げた。
父の後についていくと、辿り着いたのは父の部屋であった。何度来ても極限まで片付けられている、と桜子は暈けた頭の片隅で感じた。整えられた部屋にいると自然と落ち着くものであるが、父の部屋は整頓されすぎているため、むしろ妙な居心地の悪さを桜子はいつも抱かなくてはならなかった。
部屋に置かれた数少ない家具である文机を挟み、父は黙って桜子と対面していた。彼の前には薄紫色の酒瓶と、硝子で出来た二つのグラスが置かれていた。光に当てると色とりどりの破片を落とすそのグラスにはそれぞれ、朱色の翅を広げる太陽に似た巨大な蛾と、艶かしげな緑色の鱗を持つ長い胴の蛇が描かれていたが、桜子にはそれが何であるのかはわからなかった。父が酒を注ぎ入れると、硝子が描いた蛾と蛇は乱反射してその色を僅かに変えた。
寒風が吹くのも構わず、父は中庭と座敷を隔てる障子を開け放していた。庭から届くぼんやりした光によって輝く蛾のグラスを、父は桜子の方へと押しやった。
だが、桜子はそれを受け取りも拒みもせずにただ座敷に正座していた。グラスの中で揺れる酒の揺れる音もやがて収まり、二人の耳に届くものは冬にも負けないらしいハトーボーの鳴き声だけだった。桜子はまさに心此処に在らずといった様相で、真正面に座る父の顔を見つめ返していた。
「桜子」
父が娘の名を呼んだ。桜子はそこでようやく、二重瞼の下の眼を動かした。「飲むんだ」父が視線だけで指したグラスを、桜子は緩慢な手つきで持った。力の抜けた手は震えており、彼女の右手に収められたグラスの中で酒が危なっかしく揺れた。小刻みに震える水面で、死人とも見紛う桜子の顔が無数に分断されていた。
「飲むんだ」
父はもう一度言った。桜子がその刹那に何を考えたのかを知る者はいない。当の桜子でさえも、一瞬のうちに駆け巡った思考の全てを把握しているはずも無いだろう。
彼女は目を閉じ、グラスの中身を一気に煽った。冬の寒気に冷やされたグラスは氷で出来ているようだった。その中に注がれた酒もまた、遥か北にある氷海を飲み干したように感じられたのに、その実地獄の業火の如き熱を以て桜子の身体を激しく焼いた。
桜子は薄紫の瓶に入ったこの液体を何度か飲んだことはあったが、これほどまでに体内を揺さぶられるのは未知のことであった。燃えるような熱水に口許を押さえながら、桜子は涙を流していた。その涙は次から次へと溢れてきて、やがて嗚咽へと移り変わっていった。産後、彼女は初めて泣いた。
滂沱する桜子の正面で、父は何も言わずに蛇のグラスを傾けていた。慰めることも、言葉をかけることも無かった。彼はただ、甘くて苦い、薄紫色の酒瓶の中身を喉の奥へと流し込んでいた。
桜子の咽び泣く声が響いていく。緑を失った真冬の庭は枯れた草木の匂いで満ちていた。張り詰めた空気は凍りついていたがその一方で、消えることの無い湿り気が、地に落ちた白の塊をだんだんと侵食しているようだった。
◆
カントーでは桜の開花が報じられたが、屋敷にはまだ冷たい空気が満ちていた。
哲人はホウエンの大学に進むため、屋敷を出て一人で暮らすことが決まっていた。高校の卒業式も終わり卯月へ月日が刻々と進む頃、哲人の出発もあと数日というところに迫った。
あれはいらないこれは持ってく、と哲人は連日荷造りに追われていた。捨てられない性分の弟の尻を叩くため、帰省した兄の恭介も彼の仕度を手伝っていた。子供の頃によく読んだ絵本などを逐一持っていくと哲人が宣うため、恭介はその度に弟を宥めなくてはならなかった。
それもようやくひと段落つき、あとは引越し業者に荷物を預けるだけという段階に差し掛かった時だった。すっかり綺麗になった哲人の部屋に父が現れ、自室に来るよう伝えてきた。哲人は戸惑い、忙しいからと一度は断ってみたものの父は折れず、またやるべき片付けなどは恭介が請け負ってしまったがために父を拒む理由もなくなってしまった。哲人は仕方無く、父に言われるままに障子の外に出たのだった。
廊下はとても冷たく、哲人は氷の上を歩いているような気分になっていた。父と話すのは久方ぶりであった。ここ数ヶ月の間父は仕事が忙しいようで、家へ帰ってくるのは毎晩遅くなってからだった。また哲人の方も受験勉強に苦しめられていたり度重なる試験や予備校のため外出が続いていたものだから、顔を突き合わせることすら長いことしていなかったかもしれなかった。とはいえ以前ならば頻繁に話していたというわけでもなく、父との間にいつも訪れる沈黙を想像して哲人は重い気持ちになった。渡り廊下を歩く際に目に入った、長い角に新芽を宿した鹿の片割れにその不安を訴えてみたが、四季折々に移ろう角を持つ鹿は無視を決め込み、足元に群れる雑草を食していた。
父の部屋は幼い頃からの印象そのままに静寂に包まれていた。いや、記憶の奥底に潜ってみると、この静寂はある時を境により深まっているようにも思える。それは哲人がまだ幼い頃に迎えた母の死であったように考えられたが、如何せん薄い記憶では判断のしようも無かった。
哲人はこの部屋をあまり好んではいなかった。一見整頓されており、必要最低限のものすらも無いように感じられるほどに殺風景なのだが、反面、ここに来るとどうにも圧迫される心地がしたのだ。目には見えない何かが部屋一杯を占拠しているようで、哲人はここで父と向き合う度に、恐ろしい怪物に首や腹を締め付けられる幻覚に襲われた。それは部屋の至る所から生まれてくるようにも思えたし、対峙する父そのものが怪物であるようにも思えた。
それは大学進学を控えた今になっても変わることなく、文机の向こう側の父を前にして哲人は身体を縮こまらせていた。せめて兄についてきてもらえば良かった、などと情けない後悔に駆られたが既に遅く、哲人は父親と二人、居心地の悪い湿気が蔓延する部屋に座っていた。
父は哲人の苦悩など知らぬ顔で、薄紫色の酒瓶の蓋を開けていた。酒瓶の隣にちんと並べられている朱塗りの盃は、チェリムの姿が描かれていた。はらはらと散る桜の花弁は金箔によるもので、注がれた酒の中でも尚可愛らしい輝きを放っているのだった。
庭から差し込む光に合わせて瞬く金の花弁に、哲人が満開になった想像上の桜に溺れていると、片方の盃が自分の方に押しやられた。意味が飲み込めずに次の行動を決めかねる哲人を、器の中に踊る桜の精霊が笑って見上げていた。愛嬌のあるその顔に首を捻っていると、やっと父が「飲め」と口を開いた。
「入学祝いだ」
成る程そういうことか、と哲人は恭しく盃を手に取った。酒を飲むのはこれが初めてだったが、不安よりも好奇心の方が余程先立っていた。鼻に近づけると優しい風が鼻腔を突いた。哲人は警戒するように数秒考えていたが、やがてほんの一口、舐めるように盃の中身を咥内に含んだ。
途端、春の訪れに香る花の芽のような、夏に感じる茹る程の熱のような、秋の夜更けに在る酩酊感のような、冬の極寒が孕む棘のような、かといってそれらの何れともつかない感覚が哲人を襲った。それはとても衝撃的なものだったが、同時に彼は何か幸せ夢を見ている気分にもなった。
盃を手に収め、ほやほやと目元を赤くしている哲人の向かいで、父は無表情を崩さぬままに自分の器を空にしていた。身体と頭が温かくなった哲人は、父の前に置かれた薄紫色の酒瓶が酷く美しいものだと思ってやまなかった。奇妙に美味である酒をその身に収め、鎮座しているその瓶は、どこか遠くにある異世界の空を溶かし込んでいるように感じられた。
「酒にはくれぐれも気をつけるように」
たった盃一杯で惚けている哲人に、父も思うところがあったのだろう。厳しい声でそう言い含めたという。加えてもう一言、父は息子に何かを伝えたらしいが、既に意識の幾分かを幻惑の中に旅立たせていた哲人の記憶には残らなかったようである。
そうして家を出た哲人は、その後何度か酔いの所為であらぬ揉め事を引き起こしたり引き起こされたり、巻き込んだりしたのであるが、それらの出来事の原点にあるのが、父と交わした朱塗りの一杯だった。雪解けも大分進み、中庭の草木にはちらほらと緑色が現れ始めた頃だった。寒いくせに奇妙な蒸し暑さの漂うそこで、せっかちなハネッコやポポッコがどこに向かうでも無く浮かんでいた。薄く広がる青空に点在する桃色や黄色に、酔いにうかされた哲人叔父は楽園を見た。
◆
「そのお酒を、明久君が見たことはあるの」
「さぁ。それらしいものは何度か目にしたことがある気もするけれど、本当にそうなのかはわからない。それに、父さんは飲んだことが無いんだ」
鏡子伯母が、桜子伯母が、哲人叔父が彼らの父親と酒を酌み交わしながら眺めた中庭を、今は僕と菜実子が眺めている。それぞれの抱える事情に関係無くいつでも杯を傾けていた祖父と同じように、翠の葉をいっぱいに繁らせた大樹もまた、変わることのない風格で庭の中央に聳えていた。コロボーシの奏でる鈴の音に重なるホーホーの声は朧な月のせいかどこか物哀しげで、何かに啜り泣いているように聞こえた。
「父さんはその酒の味を知らない」
祖父は、僕の父に薄紫の瓶の中身を飲ませることは無かった。酒を飲むこと自体を禁じていたわけではない。むしろ父と杯を交わすのを祖父は好んでいた節すらあり、長期休暇にタマムシの大学から父が帰郷すると、決まって酒を飲ませていたようである。
しかしその酒だけは別だった。父と同席すら際に自分だけ口にすることはあっても、それを父の杯に注ぐことは決して無かった。父とて好奇心というものを人並みに持ち合わせているから、一口味わわせてもらえないかと何くれと無く尋ねてみたものの、祖父の返事はにべもなかった。「お前にこれを飲ませるわけにはいかん」という断定的な口調に父もそれ以上言及する道理を見出せず、花とも果実とも付かない甘やかな香りを放つそれを飲み干す祖父の姿を見ながら、自分は別の酒を飲むというのが親子の決まった図式となっていった。
「菜実子は、無いの」
「無いよ。お父さんから少し聞いたことはあるけど」
「そもそも僕たちが酒を飲む歳になったのも最近のことか」
「私は一緒に飲んだことすら無いもの」
その祖父も晩年には酒を飲むこと叶わず、医者に禁酒を命じられたまま死んでいった。姉の話によると祖父は、「酒が飲みたい」と最期まで訴えていたらしい。水が入った器を姉が渡すと、これじゃないと激昂するため姉はほとほと困り果てていたという。
「巴さんがいれば、また違ったのかもしれないけど」
僕は言いながら杯に酒を注ぐ。底に描かれたハンテールは芳香の中でゆらゆらと泳いでいた。池のアズマオウが跳ねる音がする。墨絵のハンテールが跳躍したのかと酔った頭が早合点をしたが、少々不気味な斑模様の深海魚は未だ酒の海に沈んだままであった。
口に流し込むこの液体を、慣れた味だと感じるようになったのは一体いつのことであっただろう。「おばあちゃんの話」語尾が上がり気味の菜実子の言葉に軽く頷く。酔いに温まられた身体を外側から熱するのは未だかつて消えたことのない屋敷の湿気であり、大樹が屹立する中庭の空気が纏った水っぽさだ。
◆
巴さんは父の母親で、また哲人叔父の母でもある。
祖父が再婚相手の巴さんを連れてきたのは、桜子伯母が十九と十七の時だった。幼い頃に実母が家を出ていったきり、使用人を除けば顔をよく知る肉親は祖父だけであった二人は、どちらかと言えば母となる人というよりも自分たちの友人のような若さであった巴さんを見て、飛び上がるほど驚いた。しかしそれ以上に娘たちを仰天させたのは、実に幼い、新しく弟となった幼児であった。
それが父である。父は巴さんの連れ子で、母親と共に海の向こうからやってきた。巴さんはルネの出身ということだったが、海峡を渡る際に自らの過去を置いてきたらしい彼女の半生は、実の息子である父にすら語られないままであった。祖父は何か知っていたのかもしれないが、祖父とて語らないのだから同じことである。この屋敷に来る以前の父の記憶はほぼ欠落しており、系譜を辿った先にある最も古い情報は、屋敷の門をくぐった時の蒸した空気と繋いだ母の手の柔らかさだった。
巴さんについては、父や叔父よりも二人の伯母の方がよく知っている。僕は彼女を写真で見たことしか無いが、ほっそりと美しい女性という印象を抱いた。それは概ね合っているらしく、伯母たちの言葉によると巴さんはその見た目通り、優しくて儚げな人だったらしい。
巴さんは、穏やかな微笑を常に失わなずに屋敷に在った。気難しい祖父の妻など苦労が絶えないだろうと伯母たちは揃って気を揉んだが、それは杞憂に終わった。新しい伴侶が来たからといって祖父が変わることは無かったが、巴さんはその隣で、いつでも柔らかな笑みを浮かべていた。桜子伯母と鏡子伯母はこの綺麗で優しい母親を好いたし、歳の離れた弟をよく可愛がった。
やがて桜子伯母は嫁に行き、鏡子伯母が旅に出て暫く経ったところで、巴さんは男児を産んだ。その名は言うまでも無く、哲人である。
◆
「姉さんは巴さんに似ているらしい。勿論顔だけで、性格や振る舞いは全然違うのだろうけど」
竹を割ったような性格で表情のよく変わる姉と、写真の中の見果てぬ祖母を重ね合わせて僕は言う。同じことをしたのであろう、菜実子がくすりと口許を緩ませた。
「巴さんのこと、お父さんもよく覚えていないの。何かしてもらったっていうとすぐに伯父さんか、お手伝いさんか、そうじゃなかったらおじいちゃん。だからおばあちゃんって感じがしないんだ、どうにも」
「僕もだ。巴さんは、いつまでも巴さんのままだ」
灰皿に押し付けられ、火の潰えた煙草はぐにゃりと曲がって転がっている。浅い銀の器の中で丸まったその様子はまるで何かの死骸のようで、微かに飛び散った灰は、何か取り返しのつかないことをしてしまった時の感覚を呼び起こした。
それ以上見ている気も起きず、僕は庭へと視線を向けた。大樹を中心に様々な草木が群生するこの中庭は、短い間だけれども巴さんによって整えられていた。というより、今のように多種の植物が持ち込まれたのも巴さんが来てからである。それまでは外側の庭に植木屋を呼ぶことはあっても中庭はほぼ手付かずの状態で、池の魚たちに各人が餌をやる程度だったのだ。
白くて細い体躯の巴さんに庭仕事など務まるだろうか、気分を崩して倒れやしまいかと伯母二人や使用人たちは心配したが、巴さんは存外体力のある者だったようで、その身体のどこからそこまでの精気が湧いて出るのかという勢いで働いた。
巴さんが手入れを始めてから、中庭はそれなりに見るに堪えるものに変わった。雑草が好き勝手に群れるだけだった地面にも色々な草花が持ち込まれ、緑一色の庭に黄色や桃色などの花が咲くようになった。時には祖父に談判し、秋に葉を綺麗に染め上げる木を新しく植えることまでした。しかし彼女の方針として、植物の育成を助けるような薬品を使うことは滅多に無かった。そのため訪れ、棲み着く野生ポケモンが減るということも無く、中庭は大分立派なものになった。
「植物は、心を込めて育てれば必ず応えてくれる」
「何、それ」
「巴さんの口癖だったらしい」
そうして彼女はその言葉の通り、丹精込めて庭の世話を続けていた。今でこそまた雑草も増えてきたが、それでも巴さんが来る前に比べれば、多様な草葉を見ることが出来る。それらの王の如く鎮座する中央の大樹も、雑草で荒れ果てた庭から脱却出来て嬉しいだろう。夜風に揺れる葉が落とす影は広く大きく、幾種類もの草花に闇を乗せていた。
しかしその巴さんも、この庭と関わるようになってそう長くは無いうちに亡くなってしまう。
◆
巴さんが奇妙な死を迎えたのは、哲人叔父がまだ三つになるかならない頃のことだった。
夏日で、数日間雨の降らない状態が続けていた。青い空はどこまでも高く晴れ渡り、欠片ほどの雲もそこには存在していなかった。屋敷はいつにも増して蒸し暑く、また刺すような射光を容赦無く放つ太陽によって着々と燻されていた。
その日、父と叔父は近所に住む親子と共に市民プールへと遊びに行っていた。父の通う幼稚園で同じ組になった少年は活発な性分で、どういうわけか気の合ったらしい、おとなしい子供だった父を連れ回すことを好んだ。彼の母親も気の良いもので、忙しい祖父と屋敷から滅多に出ない巴さんに代わって父兄弟を外に連れ出してくれた。
母の死に関して、父は全てが終わってから知らされた。母親の命日と聞いて僕の父が思い出す記憶は激しい塩素の臭いの充満する市民プールの人混みである。泳ぐ水は客の体温と日光で生ぬるく、プールサイドを歩くとぬるぬると気色の悪い感触が足の裏にあった。友達の母親が着ていたチーゴ柄の水着、彼女が抱えていたのは確か、目一杯の空気を入れられてパンパンに膨らんだラプラス型の浮き袋だ。赤い浮き輪に嵌った弟が流れていくのを、友達は笑いながら追いかけていた。歓声と水の跳ねる音で賑わう中、打ち寄せる人口波に揉まれて空を見上げると、ケンホロウが悠々と飛んでいくのが見えた。弟が自分を呼んでいる。友達親子も。しかしどうしてか父は空を見たままの姿勢から動くことが出来ず、薬品臭いプールの中に立ち尽くしていた。
旱天に飛翔する大鳥の姿に父が何を見たのかは父自身にもわからない。
巴さんは、屋敷からやや離れた所にある水路で死んでいた。水死ということだったが柵の中へ故意に入らなければ落ちることも無いそこに、何故巴さんがいたのかは不明である。揉み合った痕跡も無く、自殺するような理由も見当たらない。日頃屋敷を空けない巴さんが、その日にどうして水路へ向かったのかも謎であった。
苔が生える、湿った水辺に倒れていた巴さんの周りには、数匹のベトベターが群れていた。平素水路の周りで見ることのないそのポケモンたちの所為か、辺りは鼻を摘みたくなるような悪臭に包まれていた。ベトベターは軟体の身体を這わすようにして、びっしりと生い茂った苔の上を行き来していた。腐臭をいち早く察知したのではないかという声が警察の一人から上がったが、その正否は誰にも判別つかなかった。
巴さんは青白い身体を横たえ、眠るように亡くなっていた。猛暑の中行われた母親の葬式で、父は暑さに眩む目を開けているのが精一杯だった。涙は出なかった。母の死への実感が湧かなかったという。そうしてそれは今でも変わっていない。
泣いている姉二人と、退屈してぐずりだした弟に挟まれ、父は黒の半ズボンから覗く足を無作法に揺り動かしていた。汗で湿った膝から顔を上げ、彼は父親の姿を見た。いつもと変わらぬ仏頂面には汗の一つも無く、ただ、睨むようにして、巴さんの遺影と正対しているのだった。
◆
柱時計の鐘が二度鳴った。地響きのようなそれに満ちる屋敷は物音一つせず、誰もが深い夢の中に落ちてしまっていることを暗に示していた。気づけばホーホーやコロボーシたちの鳴き声すらも消えていて、僕と菜実子を包むのは僅かな鐘の残響を除けば静寂のみだった。
草木も眠る丑三つ刻というが、中庭のそれらも確かに寝ているように見えた。しかし反面、風に葉擦れの音を立てる大樹だけはまだ意識を残したままで、我々のことを眈々と見張っているかのようだ。それはまるで今は亡きはずの祖父の威風にも酷似していて、知らず識らずのうちに後方の祭壇から目の前の大樹へと移り変わったのではないかと錯覚に陥った。
「そういえば、彩音さんは来なかったね」
言葉と共に吐かれた菜実子の息は、酒の甘い匂いを含んでいた。
彩音さんとは僕たちの従姉妹で、桜子伯母の娘である。血は繋がっておらず、伯母がこの屋敷で流産を経て六年後、ジョウトの養護施設から引き取ったと聞いている。桜子伯母と父たち兄弟の歳が離れているため、僕や菜実子と彩音さんもまた歳に開きがあった。
彩音さんには久しく会っていない。彼女は何時からか、ここに訪れることをやめてしまったのだ。そもそも菜実子や大樹、親戚たちと会う機会など祖父の屋敷に集まる以外で滅多に無いのだから、ここに来ないのならば態々僕が年上の従姉妹と会う理由も存在しなかった。
「ポケウッドの衣装だっけ、仕事。忙しいのかな」
「そりゃあ、僕みたいな暇な大学生と彩音さんは違うだろうけど。でも、多分」
「多分?」
「彩音さんはここが嫌いなんだ」
「嫌いって」
「気味の悪い夢を見るから」
桜子伯母によると、彩音さんは昔から、この場所を怖がっていた。いつ見ても怒っているような祖父や、古風な家の感じがそう思わせている面もあったのだろうが、それ以上に彼女の足を遠のかせたのは、ここで見る夢であった。
彩音さんは屋敷を訪れると、いつも同じ夢を見るという。特段悪夢というわけではないが、毎度必ず見ることと、どうにも不安になる雰囲気をその夢が持っていたことから、次第に恐怖心を抱くようになったのだ。結果彼女はトレーナー修行の旅に出たのをきっかけに、ここに来るのをやめてしまった。
「何、夢って」
「知らないの」
「知らないよ」
「ここに来ると決まってみる夢がある」
「そんなもの無いもの」
「僕はさっきも見たんだ」
彩音さんの話に、僕は思い当たる節があった。この屋敷に来ると見る夢。それと同じものを屋敷の外で見たことは無い。夜に布団で寝ている時、ささくれた畳に転がって惰眠を貪っている時、何をするでも無く天井の木目を無為に数えている時。屋敷で眠ると僕は必ずその夢を見た。そうして夢から覚めると、有無を言わせぬ倦怠感と疲労感、また全身を纏う脂汗に襲われる。どこもかしかも汗だくのその状態は、まるで水の中から這い上がってきたばかりのようであった。
毎度毎度、欠けることのない瞼の裏に広がる情景。不安を与える空気。それと恐らく同じものを、僕もまた味わっていた。
そうわかった時、僕はどこか安堵した。奇妙な夢を見るのが自分だけでないというのなら、きっと悪戯なポケモンでも棲み着いているのだろうと思うことが出来たからだ。エスパータイプやゴーストタイプのポケモンの中には、他者に悪夢を見させる技を操る者もいる。フローゼルの親子のように、ここに住んでいるポケモンたちの仕業であろうと考えたのだ。
しかし、そうでは無いと菜実子は言った。
「菜実子は、見ないの」
「見ないし、知らない。夢だなんて」
「いつも見るんだ」
「どんな夢」
そう、菜実子が尋ねた時だった。赤らんだ唇から漏れたその問いに、僕は乾いた口を開きかけた。しかし僕の声が菜実子の鼓膜を揺らすよりも先に、僕たちの後ろ、祖父の祭壇の方で、何かが動く気配と物音があった。
僕と菜実子は飛び上がらんばかりに驚き、一瞬の間を置いてそちらを振り返った。
座敷の暗闇に目を鳴らす僕たちに、気配の主が声を発した。
「御免下さい。酒を届けに参りました」
◆
夢の中の僕は薄暗い道を歩いている。その道が何処なのか、また何処から歩いてきたのか、そして何処へ向かっているのかは全く以てわからない。かなり長い距離を進んできたようにも思えるし、今しがた出発したばかりのようにも思える。ひどく疲れているようにも感じられるし、疲労を知らずに永遠に歩き続けられるようにも感じられる。どのくらい続いているのかも不明な道を、僕は唯々歩いているのだ。
その道は堅い壁に覆われている。壁の向こうがどうなっているのかは知らない。何で出来ているのかわからないが、つるりと平らな壁は三百六十度を囲っており、道と外界を隔てている。とてもじゃないがその壁は破れそうになく、パイプ状の道に閉じ込められた僕は土管の中にいるような錯覚にしばしば陥る。
道の先は見えない。通ってきたはずの後方も見えない。光が存在しない暗闇というよりは、僕の視力が働いていないのだと思う。ともすれば、歩いている自分の姿さえも見失ってしまいそうだ。
僕の足音に混じって聞こえる音がある。何の音なのだろう。何かが迫っているような音だ。地面の下で何者かが這うように動いたならば、こういう音がするかもしれない。轟音と呼ぶには余りに遠すぎるが、恐らく近くで聞けばかなりのものなのだろう。何かが勢いよく動き続けるその音は、静寂の中で僕の耳に流れ込む。
道の中は奇妙な涼しさを常に浮かべている。空気に多分の水が含まれているのはわかったが、どういうことか蒸し暑さは感じない。居心地の良い川辺などを歩いている気分だ。ひんやりとした冷たさは全身に纏わりつき、目を瞑るとまるで水底に身体を沈めているようである。
僕は歩き続けている。右足と左足をひたすら交互に動かしている。何故そうしているのか、その理由を僕は忘れてしまった。誰かに会いにいくのだと、そして誰かに何かを届けにいくという目的があったように思う。しかしそれも定かでない。ただ、海の中を漂い続ける難破船の如く、僕は道を進むのである。
壁の向こう側から、或いは道の終着点から、誰かが呼ぶ声がする。
おい。
おおい。
声のする方に進み続けても、僕は一向にそこへ辿り着けない。どれだけ歩いたところで道はずっと続くのだから、僕は声の主に会うことは叶わない。
声は呼び続けている。
おおい。おおい。おおい、と。
壁に覆われた道に深く響き渡る低い声は、身の毛がよだつほどの恐ろしさを持っているくせに、どこか哀しげである。何か僕には想像することも不可能である、巨大な存在の慟哭のようだ。
声は誰かを呼んでいる。それは僕の名では無いと思う。知っている誰かの名前だった気がするが、それが誰かはわからない。
それでも、この言葉だけはわかるのだ。
声は言う。
声は叫ぶ。
先の見えない道の終わりで、声はこうやって呼んでいる。
江角、と。
◆
酒屋であると名乗ったその人は、何故だか顔を白い布で覆い隠していた。風で微にはためくその布には、円の中に点を一つ、眼玉を模したような記号が描かれていた。墨をつけた筆で描かれたそれは何だか動いている風に見えて、アンノーンを一匹布の中に閉じ込めているようであった。
たった今来たところであるという酒屋は、暗闇に物も言わず佇んでいた。足袋に包まれた両足から黒い影が伸びていることがむしろ不自然で、化物の類であると説明された方がよっぽど納得出来たかもしれない。
「重雄様のことは、誠にご愁傷様でございます」
仰々しく礼をする酒屋の、紺色の着物から覗く骨張った手は男のものと見て取れた。しかし夜の空気によく溶ける、耳障りの良い声は女らしかった。布越しの顔を見ることは出来ず、どこか機械めいた振る舞いと妖怪じみた雰囲気を持つその姿に、僕と菜実子はどう接して良いかわからず顔を見合わせた。
「本日は御注文いただきました品をお届けに参りまして」
「ま、待ってくださいよ。急に言われてもわかりませんし、そもそもこの時間ですよ」
手から提げていた冷却箱を畳に降ろした酒屋に慌てて言葉を発する。単に僕たちが聞いていないだけである可能性も低くないが、しかし真夜中に宅配にくる酒屋というのは素直に受け入れられるものではなかった。また、姉などが買い出しに行っていたのだから、わざわざ宅配を頼むというのもおかしな話であった。
狼狽える僕と菜実子から十歩ほど離れた場所にいる酒屋は、不可解そうに首を傾げた。「そう言われましても」何かを喋る度に白の布がひらひらと揺れる。揺れが作る凹凸は須臾にして作り変えられ、アンノーンの如き眼玉が絶えず動いているようである。
しかしその文字の表すところを僕は知り得ない。
「お電話をいただいたのですが」
「何時の話ですか」
「今日の朝方ですよ。この時間にいつものものを持ってこい、と」
「いつもの、とは」
「重雄様には昔から懇意にしていただいておりまして。多様な酒をお買い上げいただいていたのですが、その中でも決まって御注文なさるものがあったのです」
「祖父がですか」
「ええ。この頃体調を崩されたということで、此方の門をくぐることもめっきり無くなったのですが。お医者様に禁酒でも命じられたのかと勘繰っていたのですが、朝方に訃報の御連絡をいただきまして」
「何故、屋敷の中にいたのです」
「重雄様は私に鍵をお預けになったのですよ。勿論最初は私も驚いて、お返ししようと思ったのですが、届ける毎に玄関までいかなくてはならないのが不便だとおっしゃったものですから、もう暫くのことそうしておりました」
「直接持ってこいと祖父が言ったのですか」
「ええ。何時もこの部屋に伺ってお渡しいたしました」
酒屋が懐から取り出した銀の鍵が、塀の向こうの街灯の光を反射して鋭く輝いた。この者が嘘をついているとは思えなかったが、腹の底どころか表情すら見て取れない事実は、喉元をひやりとさせるような不安を僕に与えた。
祖父が酒屋に酒の宅配を頼んでいたなど、況してや鍵まで渡していたなどという話は未だ嘗て聞いたこともない。もっとも僕の姉が屋敷に住み込むようになった時点では既に、祖父の飲酒は禁じられていたのだから、雇っていた家政婦の誰かが伝えなくては知る由も無いと言えばそうである。買い物になど繰り出さない祖父が、どうやって酒を常備していたのかも酒屋の宅配があったからというなら説明がつく。鍵を渡していたのも合理的ではあるし、防犯意識等の問題があるといってもこの酒屋がそのような、俗世間めいた事をするとは良くも悪くも思えなかった。
蒸した座敷でようやく冷えてきた頭でそんなことを考えると、背中を一筋、冷たい汗が伝っていくのがわかった。僕の隣では菜実子が困惑と疑惑を丸顔に浮かべ、すべやかな指を無意味に組み合わせたりしていた。
「その電話というのは、誰からのものでしたか」
「さぁ、お名前を伺おうとしたら切れてしまったのですよ」
「声の感じは」
「何とも言えませんな。何分電話ですから、成人した男性の声であったのは確かでしたが」
背にした中庭から葉の匂いがする。いくらシンオウ夜とはいえ夏の道を、しかも冷却箱を抱えてきたというのに、酒屋は汗の一つも掻いていなかった。袖口から伸びる手首は陶器のように白く滑らかで、よく出来た機巧人形かとも思えた。首の後ろで束ねられた黒髪は背中ほどに長く、穏やかに流れる小川を連想させた。
僕はそれ以上の質問が言葉とならず、菜実子と共に立ち尽くす他無かった。恐らく待ってくれていたのであろう酒屋は、僕たちのそんな様子に「それでは御注文のお品ですが」と今度こそ箱の蓋に手をかけた。
開いた箱の中から白の煙がもくもくと立ち昇る。無機質な銀の冷却箱には細かな氷が詰められていた。
「いつものを、一本。よく冷やしてくるようにとのことでしたので」
「あの、お代は」
「結構ですよ」
以前にまとめてお支払いいただきましたから。やや高めである酒屋の声が、布の向こうから僕の耳元を擽った。
酒屋が箱から取り出した酒を見て、僕たちは言葉を失った。
氷に埋れていたその酒は、薄紫色の小瓶に入っていた。それは様々な話の中に登場する、祖父が好んで飲んでいたという酒であった。酒屋の白い手はまるで赤ん坊を抱きかかえる時のように、優しく、酒瓶を扱っていた。
「では、私はこれで失礼致します」
酒瓶に目を奪われていた僕の意識を酒屋の声が引き戻した。ぴんと伸びた背筋を曲げて一礼し、立ち去ろうとする酒屋を引き留めなくてはならない気もしたが、何を言えばよいのか判別がつかなかった。
そのまま酒屋は障子の向こうに行ってしまいそうであったが、「おや」と不意に呟いて僕と菜実子を振り返った。
「ひとつ、お聞きしてよろしいでしょうか」
「何ですか」
「重雄様が体調を崩されてから、何か新しいポケモンを住まわせ始めましたか」
その質問に僕は答えることが出来なかった。野生ポケモンは勝手に出入りしているし、祖父の行動はほとんどわからない。姉は何も言っていないはずだが、敢えて言うことでも無かったのかもしれない。
口籠った僕に、酒屋は数秒動かず考え込んでいたようだが、やがて「いや、私の気のせいでしょう」と話を打ち切った。「以前は聞こえなかった鳴き声がしたようでしたから」
その意味を問い返そうと口を開きかけた時には既に、酒屋の姿はそこに無かった。風が吹くよりも気づかぬうちに帰ったらしい酒屋がいた場所には薄闇と湿気、そしてほんの僅かな残り気配しか存在していない。頭の中で、白の布に浮かぶ大きな一つ目がぎょろりとこちらを睨みつけた。
縁側に取り残されたのは立ち尽くす僕と菜実子、そして間に置かれた薄紫の酒瓶だった。畳にそっと置かれたその酒瓶は、何も無い世界に一輪咲いた菫のようであり、また、祖父の隣に寄り添う写真の中の巴さんのようでもあった。
僕も菜実子も、佇んだまま動かない。背中に感じるのは中庭の大樹が揺れる音と、生温く空気を掻き回す風だった。
◆
祖父の元妻が屋敷を出ていった時の話である。
彼女は祖父がイッシュの鉱山開発に出稼ぎへ赴いていた際に出会った女で、貿易商の父を持つハイカラな娘であった。二人の間にどのような経緯があったのかは不明だが、ともかく二人は結婚し、桜子と鏡子という娘を授かった。娘たちが生まれて間もなく祖父が伸之助の工場を売って事業を始めることとなり、その際家族揃ってシンオウに移り住んだ。
シンオウの屋敷に住むようになってからというもの、彼女は気掛かりなことがあった。それは祖父の飲酒に関する問題であり、また謎でもあった。
自分の旦那が元来酒好きな方で、出会った当初よりよく飲んでいたことは知っていたが、屋敷に来てからの祖父は酒の飲み方が少し変わったのだ。何か粗相を起こしたり、厄介ごとを招くといったことではない。ただ、彼女の知らぬ酒を一人で飲むようになった。
その酒は薄紫色の瓶に入っていた。好奇心に駆られた彼女はその中身を飲ませてくれるよう頼んだが、祖父は断固として認めなかった。そんなことが何度か続いたある時、彼女が祖父の目を盗んでその酒を飲もうとしたところを祖父が見つけてしまい大喧嘩となった。
何日にも渡った悶着の末、彼女は屋敷を去ってしまった。取り残された祖父は何も言わなかったし、幼い二人の娘も今ひとつ事態を飲み込めずにいた。そのまま時間は流れ、彼女の面影は屋敷にほとんど残っていない。祖父は彼女の話題を出すことも無かったし、桜子伯母や鏡子伯母も記憶に薄い実母に対しての思慕は驚く程に欠落している。
何が彼女をそれほどまでに掻き立てたのか、彼女の天性の性格がそうさせたか、或いはそうではないのか、それはわからないままだ。
◆
その酒が、今、僕の目の前にある。
酒屋が置いていったそれは冷却箱と外気との温度差で、薄紫の瓶の表面には丸い水滴がびっしりと張り付いていた。結露の一部は既に流れ落ち、歪んだ筋を描いて畳を濡らして輪染みを作った。針金で固定された陶製の栓は、何やら重大な秘密を守っているかのように閉じられていた。
まさに話題としていたものの突如なる登場に、僕も菜実子もどうするべきかを図りかねた。僕たちの間で、一本の酒瓶は静かに座作している。薄暗闇に浮かぶ透き通った紫の中で、無色透明の液体がごく僅かに揺れていた。
伝聞した酒は想像よりも呆気のない見た目だった。謎多き祖父にまつわる話に頻出する存在であるこの酒に、僕は知らず識らずに幻想的なイメージを抱いていたのかもしれないが、実際蓋を開けてしまえばなんてことの無いただの小さな瓶であった。黄昏に暮れる空を溶かし込んだような色は確かに美しかったが、祖父が毎晩のように飲み、そして時には人に分けるのを惜しむほどのものとは思えなかった。
「どうしようか、これ」
ようやく菜実子が口を開いた。内股気味の素足が、戸惑うように畳を擦る。丸っこい指はケムッソの腹を連想させた。「誰かが注文したのかな」
「でも誰が。そんな話は聞いてないよ」
「お父さんとか叔父さんとか。伯母さんかもしれないし。酔って忘れちゃったんじゃないかな」
「それにしても、『いつもの』を父さんたちが知ってるとも思えない」
どれだけ考えたところで、酒屋に電話をかけた者を特定することは不可能であるように思われた。屋敷に寝ている全員を叩き起こして問い詰め、また祖父の関係者や弔問客を片端から当たるなど、現実に行動を起こせば、もしかしたら見つかるのかもしれない。しかしそのようなことをしたところでわかるとは思えなかったし、それにこの瓶を目にしてから、根拠の無い不安が頭の中に渦巻いていた。詮索してはいけないのだと思った。知ってはならないことなのかもしれない、という感覚が胸の奥底から湧き上がった。
どうすれば良いのかわからなかった。そもそもこの中身が、祖父の好んだ酒であるという保証もない。瓶の見た目がよく似ているだけで他の酒なのかもしれないし、単なる水であるかもしれないのだ。それに考えてみれば、薄紫色の瓶というのも僕にとっては人から伝え聞いた話でしかなく、これぞ何であるという確証などどこにも存在していなかった。
普通に考えるのならば余計な干渉をせず、明朝目を覚ましてくる伯母たちに尋ねるのが最も現実的な選択であろう。事実僕はそうするつもりであり、それ以外の選択肢など思いつかなかった。
しかし菜実子は違ったようである。彼女の言葉に反対しなかった僕も本心ではそうでなかったのかもしれない。蒸すような暑さか酔った頭か、はたまたこの薄紫を纏った小さな海か、何が僕たちにそうさせたのかは不明である。ともかく菜実子は、足元の酒瓶に暫く視線を落とした後、ぽつりと唇を動かしたのだった。
「ねえ明久君」
「なに」
「飲んでみようか」
僕は返事らしい返事は何一つしなかったが、しゃがみ込んで酒瓶を手に取る菜実子を止めることもしなかった。丸い背中が屈められて、寝間着の薄い生地越しに肩甲骨の膨らみが現れた。彼女のうなじに、肩ほどの長さである黒髪がかかって覚束ない動きをした。
菜実子の手の中で酒瓶が鈍く光る。結露に濡れた薄紫はぬらぬらという輝きを幽かに放っており、僕は何となくその光景が夢で見た何某かに似ているような心地になった。
僕たちは縁側に戻り、先ほどの位置に腰掛けた。酒屋が来て、そして帰ってからも変わることなく中庭は湿った緑の臭いを漂わせていたし、大樹は重々しい風格を醸し出していた。更けた夜の草木の間にはゴーストポケモンすらも現れず、ただただ風のみが通り過ぎていく。菜実子が栓を開ける、小気味の良い音が僕たちの周囲にある湿気を少しばかり軽くした。
菜実子が瓶を鼻に近づけ数度呼吸を繰り返した。目をぱちぱちさせて何とも言えぬ表情になった彼女は首を捻りながら僕にも近づけてきたが、同じように臭いを嗅いだ僕もまた、眉間に皺を寄せてしまった。
栓の抜かれた硝子の穴から漏れるそれが良い匂いなのか、不快なものなのか、今ひとつの判断がつかなかった。似ているというわけではないが香水のようなもので、好いものにも臭いものにも受け取れるあの感覚を思い出させた。香り立つ花のそれにも似ていたし、甘ったるい果実のそれにも近いようだった。高校の頃付き合っていた彼女のポケモンだった、ロゼリアの振りまく匂いはこんな印象だったかもしれない。長らく頭の奥から引き出されることのなかったその存在を、持ち主であった癖毛の少女と共に、僕は薄紫色の瓶に幻視した。
しかしどちらにせよ、酒らしい臭いには思えなかった。菜実子もそう感じたらしく「何で出来てるんだろう」と訝しむように呟いたが、思い当たる節は全く無かった。僕たちは数秒、知らぬ世界の風を閉じ込めているかのような瓶を挟んで向かい合っていた。
腰かけた縁側は湿り気を帯びていた。そっと瓶を傾けた菜実子が杯に酒を注ぐと、澄んだ液体がとくとくと流れ落ちた。先程嗅いだ臭いが一気に広がり、むせ返るような思いだった。それはソノオの花畑に降り立った時の感覚に似通っていたが、中庭の湿気の所為で、ノモセの湿原に放り出されたかの如き不快感も存在していた。そのどちらにも、祖父と共に行ったことを想起した。大湿原にある広葉樹に樹液が溜まっており、その湿気た臭いと甘ったるさに思わず顔をしかめた僕に、祖父は呆れたような視線を向けていた。
菜実子から杯を受け取った。注がれた酒はやはり色味も濁りも無く、底を泳ぐハンテールの姿がよく見えた。横目で菜実子の手の中を見ると、白く柔らかな右手に乗せられた杯の深海に、桃色の魚が潜んでいるのを捉えることが出来た。
二匹の深海魚をそれぞれ掌中に収め、僕と菜実子はしばし無言でいた。水底に沈んだまま動かぬ魚たちは嵐の通過を待っているようであり、また、何か恐ろしい敵から身を隠しているようでもあった。海は彼らを包み込み、畏怖すべき存在に怯える者たちを守っている。その海の外にいる僕は、自分を取り巻くものが蒸した空気のみである現状がひどく頼りなく思った。
聞こえるはずの無い、粒子の流れる音を聞いている錯覚に陥った。菜実子がこちらを見た。僕は杯に視線を落とした。口元まで持ち上げると酒が揺らめいて、グロテスクな形状を刹那に成して零れそうになった。名状し難い幽香がより一層の激しさを持ち、鼻腔の奥底まで絡みついた。
杯の縁に口をつける。陶器のすべすべした感触が唇に貼りついた。「いただきます」菜実子の囁きが耳を掠った。いただきます。
一口飲み込んだ途端、喉を内側から抉られるような嫌悪感に襲われた。口の中が焼かれたようであった。胃や食道ごと噴き出したくなる嘔吐感と、全身の血液が心臓に押し寄せてくる圧迫感を一度に味わった。何が起こったのかわからない僕の視界で、白と黒の明滅を只管繰り返していた。
怒濤のような気持ちの悪さに咳き込む僕を、菜実子が「どうしたの」と不安げに見つめた。彼女は火照った頬を除けばごく普通の様子であり、中身が半分ほど減った杯を持つ手にも何ら変化は見当たらなかった。無意識のうちに杯を握り締めていたらしい僕の手から零れた酒が安物の寝間着を濡らしていた。
「大丈夫、明久君」
「いや。気管に入ったのかもしれない」
「おいしいまずいのか、よくわからない味がするよ」
言いながら、菜実子は杯を斜めにしている。白い喉が形を変えて、あの液体が彼女の身体へ流れ込んでいく。
「口を漱いでくる」僕は縁側から立ち上がった。見上げる菜実子の太腿の隣に、ハンテールの杯が乱雑に置かれて転がった。僕が中身を零してしまった所為で空になった器から優しい海はすっかり失われ、外界に打ち捨てられたハンテールは干からびて死んでしまった水棲生物そのものであった。
「足元に気を付けてね」という、菜実子の声は酔いからか少し上擦っていた。右手と手首と足の付け根、酒を零した箇所が炙られるような痛みを訴えた。
◆
父と祖父が向かい合っている。
夏の午後だった。入道雲が巨人の腹のように膨らんでいた。その遥か上空で太陽が輝いていた。中庭の草木はどこからか集まってきた露に濡れており、丸い雫は日光に当たる度に眩い輝きを放っていた。
祖父の部屋は不思議な涼しさに満ちていた。屋敷のどこにいても感じる蒸し暑さを、ここでは覚えないのが父にとって違和感だった。同年の正月にもこの部屋には訪れたはずだが、その時にどうであったかは思い出すことが出来なかった。
テッカニンのじわじわという声が庭から響いていた。幾重もの混声になったそれは鳴り止むこと無く、汗の引いて冷たくなった父の耳を煩わせるのだった。平素タマムシの大学で聞く声とは違っていた。こちらの方がより夏という監獄に押し込められている心地になると父は思った。
祖父は父の真向かいに鎮座していた。二人を隔てる文机が、父にとっては刑務所の外壁よりも堅牢なものに感じられた。血の繋がらない父親と馴れ合った記憶など存在しないが、しかしこれ程までに彼と自分が遠いものに思えたこともまた初めてであった。
父は大学院に進みたいという旨を伝えに来ていた。博士課程は教授からも強く勧められていたし、そうするだけの意欲を父は持っていた。研究したいことは山ほどあった。
背筋を伸ばして話す父の言葉を、祖父は黙って聞いていた。その表情からは是も、また非も読み取ることが不可能で、息子の申し出を彼がどう考えているかを推し量ることは誰に出来る芸当でもなかった。
父が話し終えても尚、祖父は声を発しなかった。庭からの音が反響するため、父は四方八方からテッカニンの声に取り囲まれていた。じわじわというその声は果たして本当に蝉たちの鳴き声なのか、本当は自分を見張っている怪物の息遣いなのではないか、或いは逃れられぬ暗殺者が今まさに忍び寄ってきている気配なのではないか、などという非現実的な妄想が彼の頭に浮かんでは消えた。
文机には、色の無い硝子で出来たグラスが二つ並べられていた。その隣に置かれていたのは、やはり二つの酒瓶だった。
片方の酒瓶は大吟醸酒のそれであり、相当な上物であることが見て取れた。達筆な墨汁が躍る付紙には雲を突き破って翔るギャラドスが描かれていた。獰猛な紅は鬼の血よりも地獄の釜の炎よりも濃く、向かう先にいるであろう天照神すらをも喰らい尽くすかの如き凄烈さであった。
その陰に隠れるように立っているのは、薄紫色をした酒瓶だった。
祖父は大吟醸を片方のグラスに注ぎ、もう片方には薄紫の中身を注いだ。無色透明の器に入れられたそれは一見見分けがつかず、どちらがどちらなのか判別し難かった。
「飲むといい」
しかし父は、祖父のその言葉と共に自分の側へと押しやられたグラスの中身が、どちらの酒なのかを理解していた。
グラスの水面に映る父の顔は青く、自らが何に恐怖しているのかわからぬことが恐怖だった。
◆
何度か嗽をしても、口から喉にかけての違和感は拭いきれなかった。手足に酒を零したところも水で軽く濯いでみたのだが鼻に纏わりつくような芳香はとれないし、皮膚を弱く焦がす熱っぽさも未だ残っているように感じられた。口の中がぴりぴりと痺れる心地だった。
洗面所の空気はひんやりとしていて、蛍光灯の白い光が無機質な清潔さを演出している。消毒薬の匂いがした。隣接する風呂場から漂ってくるものだと思われた。
蛇口から水が漏れていた。限界までハンドルを回してもそれは収まらず、白のシンクに一定の間隔で水滴が打ちつけられては音を立てた。落ちた雫は傾斜を流れ、排水口へと消えていった。パッキンの不調ならば今はどうすることも出来ないので、明日誰かに伝えることにした。
暗さに覆われた視界で進んだ廊下には、僕の足音しか響いていなかった。暑さで起きてしまうような夜であるけれど、誰もが深く眠っているようだった。渡り廊下を歩きながらオドシシたちの様子を見遣ったが、薄闇の中からは草木の陰と幾つかの塊しか見出せず、寝息の一つも聞こえてこない。それ以上目を凝らす気も起きず、僕は祭壇のある座敷へと戻る足を再び動かした。
「菜実子か」
座敷と廊下の間にある縁を踏んだ途端、祭壇の前に佇む影が目に入った。それが何であるかを一瞬図りかねたのと、鈍い動きで揺らめいたのとで、僕の心臓は一瞬高く跳ね上がった。しかしすぐにそれは菜実子であるとわかった僕は肩の力を抜き、座敷の中に踏み入った。
一歩進むと、先程までよりも一層激しくなった湿気がある種の熱量を持って襲いかかってくるように感じた。絡みつく蒸し暑さに吐き気がした。「明久君」祭壇を見つめていた菜実子が首を動かしてこちらを向く。「おかえり」
「どうしたの。こんなところに立って」
「何か聞こえる気がして」
「聞こえるって」
「明久君は聞こえないの」
菜実子は訝しむような眼で僕を見た。何が聞こえるの、と尋ねると「何かが通る音」そんな答えが返ってきた。
「ざーっ、って。あと、さらさら、っていうのも。それと、何かが落ちていく感じの音もした」
菜実子の説明は正鵠を得ないものであったが、僕はそれに覚えがあるような気がした。彼女が聞こえるという音はわからないけれど、それをどこか別の場所で聞いたことがある風な感覚に囚われた。別の場所ですら無いようにも思った。
何かが通る音。落ちていく感じの音。
通り過ぎていくものは、果たして何であるのか。
「今は聞こえないや。明久君が来るまでしてたんだけど」
「どこから聞こえてたの」
そう聞くと、菜実子は黙って前方を指差した。祖父の祭壇であった。
「なるほど。きっと僕たちが酒盛りしてるのが羨ましくなったに違いない」
酒の味もわからないくせに、自分を差し置いて何をやってるんだ、ってさ。戯けて言うと、菜実子はくすりと微笑んだ。形の良い耳にかかる黒の髪が、彼女の笑みに合わせて頼りなげに揺れた。
「じゃあ、おじいちゃんも一緒に飲もうか」
「コップが無い。父さんたちが持っていったかな」
「台所から取ってこようか」
「いや。僕の使ってたのでいいだろう。せっかく届けてくれたんだから、あの酒にすべきなのだろうし」
「それはそうね」
言いながら菜実子が身体の向きを変えて縁側に足を踏み出した。酒瓶と杯を取りに行った彼女の後ろ髪を見、僕は祭壇に視線を向けた。暗がりの中の祖父の遺影はやはり顰めっ面で、手持ち無沙汰に佇むだけの僕を強く睨みつけていた。
「ひッ」
すると、障子の外に出た菜実子の悲鳴が聞こえた。慌ててそちらに目を戻すと、菜実子がやや丸い身体をよろめかせ、柱にしがみ付いているのが見えた。
「どうした」
「池、池が」
声を震わせてそう言った菜実子の指がさす方に僕は顔を向ける。中庭の池を指していることはわかったが、何しろ暗いのと、大樹の影になっているせいでよく見えなかった。しかし細めた眼で暫く凝視してみると、池の中が何やら蠢動しているような光景がそこにあった。
腰を抜かしたらしく、崩れ落ちた菜実子を背中に僕は庭に出た。縁側から降りると土の冷たさが足の裏に伝わった。しかしそれ以外はじっとりと暑く、前髪の下にある額が汗を掻いた。
静寂であったはずの庭に、ぐちゃぐちゃという音が低く響いていた。むっとするような生臭さが立ち込めていた。飲んだ酒が腹の底からせり上がってきそうになるのを押さえつけながら、その臭いの元へと歩を進めると、大樹と隣り合う池へと着いた。
「水が無い」
思わず呟いた僕の後ろで、菜実子が息を呑む音がした。
平素冷たい水が揺蕩うそこは干上がっており、水底の岩肌を露わにしていた。トサキントとアズマオウが球体のような腹を仰向けにして、びちびちという音と共にのたうちまわっていた。まだ湿り気を帯びている鱗が不気味に輝いている。青白い血管が浮かぶ腹に緋色の斑点を散らした金魚は、厚い唇を開けたり閉じたりと苦しげであった。
鮮麗の象徴たる彼らが、鰭を振り乱して辛苦を訴える様子はとても醜く、また見るに堪えないものだった。あたかも地獄絵図であるようなこの状況をどうしたものか、と途方に暮れた頭の中に思い描かれるものがあった。それを僕は実際に目にしたことが無いくせに、ひどく鮮明に夢想出来る。まるで今まさに目の前で体現されているかの如きその一齣は、吐き気を催すこの臭いと共に僕を包み込むのだ。
◆
伸之助の蒐集癖は昔からのものであったが、父総次郎の死後、それは益々激しくなって歯止めが利かなくなっていった。その悪化が何をきっかけとするものなのかははっきりとはわからないが、慕っていた父親の死と折り重なるように彼を襲った、彼の妻の病死であったと言われている。一人息子であった祖父重雄が家を出たきり戻る気配も無く、何処か遠い場所に行ってしまったことも関係しているのかもしれない。屋敷に一人取り残された伸之助は、まるでその淋しさを蒐集によって埋めるかのように、泥沼の中へと潜り込んでいった。
彼の集めたものは多様である。壺や皿、根付などの骨董品から始まり、楽器や絵画などにも手を出した。伸之助に見る目など無かったものだからそれらの価値は天上から地の底までに差があり、何もかもが入り乱れている有様であった。伸之助は奇妙な逸話のある品を好んだものだから、やれ額縁の中のレントラーが夜な夜な抜け出して人を喰らうだとか、やれ皮を剥がれたニャースの霊が三味線で恨み節を奏でるだとか、やれ海の向こうから買い取った洋燈に憑いた悪霊の蒼い炎は人の寿命を燃やし尽くすのだとか、そんな噂が使用人を中心に流れていた。
人々を君悪がらせたのは何も骨董品だけでなく、同じく伸之助の蒐集の対象であったポケモンたちもそうだった。伸之助は珍しいポケモンを集めていたのだが、それらもまた、ただのポケモンでは無いのだと実しやかに囁かれていた。冥府へと繋がる結い紐を持つニンフィア、人骨を被り人語を話すガラガラ、百面相のナッシー。天を泳ぐホエルオーは満天の海に蕩けて誰にも見えない。屋敷に響くピジョットの咆哮は、頭がエテボース、四肢がウィンディ、ヒヒダルマの胴を持ち、ミロカロスの尾を轟かせるという鵺だと言われた。
伸之助の転落を決定的なものとなったのは、彼が妙なものたちを集め出してから五年ほどが経過した時であった。伸之助は日頃より様々な者を座敷に出入りさせており、骨董屋や古本屋といった商人は勿論のこと、画家や楽師や書生、奇術師や僧侶、猛獣使いなど伸之助を尋ねる者は多岐に渡った。中には霊能力者を名乗る者や王家の末裔を自称する者もいて、得体の知れない人影も次々と屋敷の門をくぐっていた。
そのような者たちを集め、伸之助は大掛かりな樽俎を開催した。誰が参加したのかという明確な情報は無く、何をしていたのかもわからない。酒宴であったとも言われ、旋律の歌姫を招いた大規模な音楽祭が開かれたのだとも言われた。或いは人とポケモンが入り乱れた殺し合いが繰り広げられたとも伝えられて、血飛沫を上げながら揉み合う来客たちの様子を、伸之助は呵呵大笑して見物していたとも言われている。
その日、屋敷は渾沌と混迷の限りが尽くされた。赤や紫や黄色など色とりどりの提灯に火が灯され、座敷も、廊下も、中庭でさえも艶めかしげな光に照らされていた。廊下には怪しげな形状の壺が並べられ、その中には鈍く光るパールルが一匹ずつ収められていた。軒下にはカゲボウズがずらりと並び、抉られたように巨大な眼玉をひっきりなしに動かしては、灰色の襤褸を裂いた口で嘲るように嗤うのだった。天井付近には桃色のハクリューが舞い踊り、長い渡り廊下を腐臭を撒き散らすダストダスが這い蹲って移動した。石壁にびっしりと貼りつくバチュルは互いに蠕きあっており、硝子玉のような無数の碧い瞳が血の池に泳ぐ亡者たちのそれであるかの如くぎらぎらと哀しげであった。
泡沫の光が泳ぐ屋敷へと、無秩序な者たちが吸い込まれていった。ある者はネイティオの面で顔を覆った着流しの男であったし、ある者は黒のドレスに身を包んだ青髪の美女だった。またある者は異臭を放つ巨大な花を頭に飾った踊り子に猿轡を噛ませた幼い少女であり、またある者は惜しみなく身に着けた煌びやかな宝石を牙の覗く口に放り込んで噛み砕いている若者でもあった。
そんな彼らを招き入れ、伸之助は何をしていたのか。狂気の渦に飲み込まれた屋敷でその晩、何があったのかを語る者は誰もいない。
樽俎の催された夜が明けた後、伸之助の人生はもはや引き返せない闇の中へと踏み込んでいた。正体不明の恐怖を抱かせた屋敷へは誰も寄り付かなくなり、江角の工場と手を組んでいた者たちも次々と退いた。工場にいた労働者の中には逃げ出す者もいた始末で、またそうしなかったものや出来なかった者も、勤務先で伸之助の姿を見ると、苦々しげに目を逸らしたり指の先を震えさせたりした。屋敷にいた使用人たちも辞めてしまい、いよいよ伸之助と江角の屋敷は怪奇と化物の支配する、暗澹たる世界であるかのように思われた。
そんな伸之助から実権を奪い、祖父は江角を立て直した。工場を同業者に売る傍らで、出稼ぎ時代に出来た交友関係を利用し事業を始めた。伸之助を良いようにしていた骨董屋や霊媒師などを屋敷から徹底的に追い払い、蒐集された品も片端より売り払ったため、今現在は伸之助のコレクションはほとんど残っていない。屋敷に棲んでいる怪物と称されたポケモンたちは皆、祖父がぼんぐりに詰めて遠く離れた海の底に沈めてしまったらしく、噂の真偽を知ることは不可能となった。
伸之助は屋敷の一室に閉じ込められ、そこで生涯を終えることになる。晩年の彼は口をきくことも自ら歩くこともなく、日がな一日暗い部屋の中でじっと動かなかった。その顔は髑髏のように瘦せこけており、怒りも絶望も哀しみも浮かべられず、感情を抱くという機能が失われているのだと思わせた。死神を生き写したかの如き伸之助を幼い伯母姉妹は怖がり、また祖父の元妻は気味悪がったために近寄らず、伸之助はただただ孤独に生きていた。しかし自分が孤独であるという認識すらも無かったかもしれない。新たに雇われた使用人の出入りも禁止され、彼と接する時間があったのは、食事を運び入れる祖父のみであった。
祖父は実父へと、簡素な飯と一本の酒瓶を毎日運んでいた。その酒瓶は薄紫色をしていた。伸之助が押し込められた四畳半は狭苦しく、大樹の落とす影のせいで日中でも暗闇に覆われていた。
一切の光を奪われたその部屋で、伸之助は闇と同化するように亡くなった。伸之助が横たわっていた黴臭い畳には、空になった酒瓶が無造作に転がっていた。
◆
「とりあえず一回、バケツか何かに水を汲んでこよう」
水の枯れた池で苦しげにしているトサキントたちだが幸いまだ息はあるようで、すぐに処置をとればまだ間に合うように思えた。池が駄目になっているのならばここに水をまた入れるよりも、浴槽などに移した方がよいかもしれない。水を運ぶ手間が惜しく感じられ、直接手で抱えて持っていこうかと、僕はやけに冷静になった頭で考えた。
池は広く、そこに棲まわされた金魚たちの数はおよそ十匹弱と見えた。とてもじゃないが一人で運べる数ではなく、池に屈みこんでいた僕は立ち上がって縁側へと戻った。菜実子に手伝ってもらうか、誰かを呼んできてもらおうと口を開いた。
「菜実子」
しかし、その依頼は言葉にならず、代わりに弱い溜息が自分の口から吐き出されたのを感じた。
縁側にへたり込んだ菜実子の顔には、玉のような汗が一面に張り付いていた。平素は白くとも健康的な丸顔は朧の月光に照らされて青白く見える反面、赤黒く染まっているようにも捉えられた。どちらにせよ気分が悪いことは明白であり、菜実子は顔を覆う汗を拭う素振りも見せず、半開きの口で小刻みに呼吸を繰り返していた。
ぬちゃぬちゃという音が未だに聞こえる池を中心に中庭は生臭く、息の詰まるような湿気が充満している。あの残酷な光景も相まって、精神面の衝撃が体調の不調となり現れているのだと思われた。
「休んだ方がいい。叔母さんたちの部屋に行こう」
そう言って手を差し伸べると、菜実子はこくりと頷いて僕の手を取った。その手はやはり汗に濡れており、掴まれた瞬間に互いの掌がぬらりと滑った。
汗ばんだ肩を支えるようにして縁側に立つ。洗髪剤の香りと酒の匂い、そして微かな体臭が鼻をついた。よろめく菜実子の横顔は中庭の影になって見えなかったが、伏せられた目に黒の睫毛が乗っているのだけはわかった。
「ん」
座敷に足を踏み入れた刹那、僕は小さく声を上げた。出した一歩が妙に冷たく感じられた。言い知れぬ不気味さを覚えながらもう一歩を踏み出す。「え」今度は菜実子が息を呑んだ。
「濡れてる」
独り言のように彼女が言った。僕らの裸足と接している畳は湿っているを通り越してもはや濡れており、歩く度にぴしゃ、と弱々しげな水音が耳をついた。雨上がりの地面を歩いた時の感覚に似たそれは、プールサイドを小走りになった時のものに近いかもしれない。ぴしゃり、ぴしゃり、とごく僅かな水飛沫をあげ、濡れた畳は水辺のように薄く光っていた。
一体どういうことだ、と僕は首筋に汗を伝わせた。どこからか、下水などが壊れて水が漏れているのだろうと考えることは勿論出来たのだが、心の中にいる沢山の自分のうち、一人が否定の意を示していた、大多数の自分で彼を押さえつけ、黙らせてしまうことは容易であるはずなのに何故だか出来ず、僕は菜実子を支えたまま足を止めてしまった。
足の裏に冷たさを感じたまま立ち竦んでいると、土付随に微弱な、しかし確かに何かが押し付けられる感覚がした。畳の含んだ水は飽和状態を超えたらしく、日に焼けた藺草を表面張力のように薄く覆っていた。
その水には流れがあった。屋敷が傾いているなどとも思いたくないが、畳を滑る水は確実な動きを持って僕たちの足元でぴしゃぴしゃと波打っていた。流れの元に視線を這わせると、祖父の祭壇に行き当たった。仏頂面の遺影が飾られたその場所から、この水は流れているのだった。
「ねえ、聞こえるでしょ」
心臓を跳ねさせた僕が何か言うよりも先に、菜実子の震えた声が鼓膜に響いた。彼女の指が僕の寝間着の袖を掴んで引っ張った。一刻も早くここから立ち去るべきだという思いと、もう何処へも行けないのだという思いが交差する中で、僕は菜実子の体温を感じながら目を閉じた。視界に暗闇が訪れる。水の臭いに満ちた暗闇だ。
音がする、と先ほど菜実子は言った。何が聞こえるのか、そう問いたかったが口が動かなかった。じっとりと重い空気の中、水気に耳を澄ましていると、何かが移動していくような、地響にも似た音がした気がした。かなり地下深くを通っているらしいように聞こえるそれは、誰にも気付かれないままに、陰乍に進んでいるのであった。何の影一つも見えぬ暗闇の底を、刻々と、流れていくのだ。
ざあー、という落下音がした。ぽつ、ぽつ、という、何かを打ち付けるような音もした。びちゃ、と叩きつけられるような音、ばしゃり、とひっくり返る音。さあ、と降り注ぐ音も聞こえた。そして、その影には常に、あの轟くような振動が響いている。
この音は、一体何であろうか。どこかで聞いたことがあると思ったが、やはりそれがどこであるのかを思い出せない。想起しようとすると頭が酷く痛み、胃を握り締められるような不快感に襲われた。思い出さなくてはならない、思い出してはいけない、その二者に板挟みになり、意識が揺さぶられているように感じた。
「明久君ッ」
途端、菜実子の鋭い声が名を呼んだ。袖口を激しく引かれる感覚に目を開ける。若干の時間をかけて夜眼を取り戻した僕は、呆然とするあまり呼吸を忘れた。
祖父の祭壇がぐらぐらと揺れていた。火の消えた線香が床に落ち、香る薬草を水に浸らせた。献花が次々に落下しては花弁を広げて転がり、遊惰の権化となって散らばった。激化する振動に終に遺影が落ちる。額が悲鳴のような音を立てて割れた。
孵化したばかりの怪物のように、祭壇は数度、震えるみたいに揺れ動いた。そして、最後に小さな振動を残し、祭壇の下から水が噴出した。それと同時に足元の水嵩が増した。天井から俄雨のように水が激しく滴り落ちた。鉄砲弾のような乾いた音が何発かして、壁を破った鋭い水が吹き込んできた。
縺れる手足で菜実子を抱きかかえ、僕は縁側に出てまた絶句した。両隣から水流が押し寄せてきていた。水分を吸って重くなった寝間着はひどく冷たくて、どうすることも出来ない寒気を覚えた。
菜実子と寄り添い、僕は早鐘のような鼓動を鳴らしていた。フローゼルの親子が毛玉が転がるように駆け出して、スボミーの群れが甲高い声を出しながらひたすら逃げ惑ってはまた鳴いた。木々にとまっていたホーホーやヤミカラスたちが一斉に飛び立ち、全てを掻き消すほどの羽音が響く。混迷に満ちた中庭において、四方八方を取り囲むこの水の流れが向かう先にある大樹だけが動かずにいた。
◆
祖父が死ぬ一月前から、いよいよ病状は思わしくないものへと変わっていった。それまでは体調は常に優れないものの起きたり横になったりを繰り返していたのだが、ついにそれもままならなくなり、何をするにも姉の手を借りるようになっていた。
とある日のことである。喉が渇いた、と訴える祖父に姉は水を持っていった。透明のコップに注いだ水を姉は手渡したが、しかし祖父は勢いよくそれをはたき落した。
「水なんか飲めるか」
そして祖父は「酒を持ってこい」と激昂したように叫ぶのだった。聞き分けの悪い子供のようにそう言い続ける祖父に姉は辟易したが、医者に禁じられている手前、酒を与えるわけにもいかず、無理であることを懇々と言い聞かせる以外の道はなかった。
姉がいくら説得しても、祖父は酒が飲みたいと譫言のように訴え続けていた。唸り声すら上げて強請るその顔は悪鬼のようであり、修羅のようであり、そのくせ涙を流す亡霊のようであり、姉は只管、咳き込む祖父の背中を摩ることしか出来なかった。
「酒を」
死ぬ間際まで、祖父はそのままであった。
蒲団の中から天井を睨みつけ、何かを呪うかの如き眼光を放っている祖父の姿は、ひどく恐ろしくて哀しい生き物のようであったと姉は記憶している。
◆
祖父の葬式から半年ほどが過ぎたあたりで、菜実子の一家がカントーへと遊びに来た。
お互いの家族で時間を合わせて食事でもしようということになったのだが、菜実子と菜実子の母親、そして母と姉は買い物に行ったまま戻ってこないため、僕と父と哲人叔父は適当な喫茶店でひたすら待ち惚けを食らっているのだった。ガラス窓から見える空はどんよりと曇っていたが、大貴の旅先に広がる空は今頃どうなのであろうなどという、妙な感傷が心中を過った。
何杯目かになる珈琲の香りが内側と外側、どちらからも鼻腔を刺激する。紙のカップに描かれた、このチェーンのトレードマークであるジュゴンはこちらを目指して泳いでいた。無意味に口にする話題も早々に尽き、我々はめいめい身体を凝り固まらせながら時間をやり過ごしているのだった。
「親父のことなんだけれども」
窓の外の通りを、リードをつけたラクライの散歩をしている初老の女性が歩いていく。沈黙に耐えかねて口を開くのはいつも哲人叔父であった。僕と父は何か返事こそしなかったが、携帯電話だの本だのに落としていた視線を上げて叔父の方を見た。
「いや、親父というか母さんのことだ」
叔父は「もっとも僕が幼い頃で朧気な記憶だから単なる妄言に過ぎないかもしれないが」と前置きして話し始めた。
それは巴さんが亡くなる前の晩の記憶であった。幼い叔父は夜中に目を覚まし、隣に母親が寝ていないことに気がつき不安に駆られた。逆隣の蒲団にいる兄を起こそうにもぐっすり眠っていてとても目覚めてくれそうになく、叔父は巴さんを探しに廊下に出た。
暗い廊下の中に唯一、灯りの漏れる部屋があった。祖父の部屋であり、叔父にとっては父の部屋だった。普段入ることは滅多に無い場所であったが、その時は叔父をほっとさせた。
こっそり部屋に近づいていくと、巴さんと祖父が文机を挟んで何かを話していた。その内容は叔父の知るところではない。ただ、二人の間にある薄紫色の酒瓶が美しかったことだけが目に焼きついた。
祖父が巴さんに紫の玉が連なったものを手渡した。受け取った巴さんの手の中で、それはぽろぽろと音を立てていた。その綺麗な何かが数珠であるとわかったのは、叔父がもっと大きくなってからのことだった。
「そういえば、母さんが死んだ時に、その数珠をつけていたなあ」
黙って話を聞いていた父がぽつりと言った。叔父が「そうだったのか」と頷きを返す。カップに半分ほど残った珈琲は冷めきっていた。
「あの数珠の色が、ずっとあの酒瓶の色と重なるんだ」
◆
凄まじい量の水が、大樹へ向かって流れていく。この水がどこから来ているのか、それを知る術は恐らく無い。轟音を立てて辺りを埋め尽くしていく水に負けないよう、立っているのが精一杯であった。
庭の草木が薙ぎ倒されていく。祭壇が押し流されていくのが見えた。背後に聞こえるめきめきという音は、屋敷の柱が水圧によって折れていくものなのだと直感で理解した。僕と菜実子は障子が剥がれてしまった柱にしがみついていたが、これも何時までもってくれるかわかったものではなかった。
水に濡れ、揺らぐ視界の中で祖父の棺を探す。せめて遺体だけは流されないようにしなくてはならないと思った。飛沫が頰に飛ぶ。冷たさと生臭さに吐きそうになる。既に胸ほどの高さまである水は大きく揺れ動き、何を見るにもままならない。
菜実子が短い悲鳴をあげた。反射で掴んだ彼女の腕に、翠色の蔓が巻きついていた。腕だけでなく、首や腹、水中に捥がく脚にも同じものが見える。愕然として蔓の根元を辿ると、水に流れていく祖父の棺があった。
菜実子が蔓に引っ張られる。彼女の根元と頰を濡らす雫が涙なのか水なのか、そのどちらであるのか僕にはわからない。目を見開いて叫ぶ菜実子の声は奔流の轟く音に掻き消される。悴んだ手で蔓を解こうとしたが固く絡みついたそれは菜実子から離れず、より一層絡みを強めるだけであった。
菜実子の腕を掴み、大樹に近寄らせないようにするのが限界だった。渦巻く水の中で菜実子は俯き、息を荒くして堪えている。気管に水が入ったらしく、鼻の奥から頭にかけてがつんと痛くなった。耳にも水が入ってきたのか、それともあまりの轟音なのか、僕たちは低い唸り声のような音の中に飲み込まれていた。
押し寄せる水流と共に、無数の記憶と誰かの想起と聞いた話と妄想が、一緒くたになって脳裏を駆け巡っていく。
屋敷を常に包み込んでいた湿気。広い中庭。祖父と歩く祭囃子。朱塗りの鳥居。幼い大貴の青い顔。入れなかったリザード。桜子伯母の流産。洋間に飾られた絵画と蔵に詰められた蒐集品。酒呑童子の絵巻。伸之助が育てていたという化物と、正体不明の催事。夢の中で通るあの暗く涼しい道。酒屋の影。巴さんの死。薄紫色の酒瓶が傾けられる。父はそれを飲むことが出来ない。「酒は毒だ」祖父が言った。
草木が育つための必要条件とは何であったか。
頭の中に水底がある。水面は遠く、遥か上にあった外の様子を見ることは出来ない。柔らかな陽が差し込んで、水と共にゆらゆらと揺蕩う様子は穏やかであった。
その中に、裸体の女が沈んでいる。身体を丸まらせて蹲っている女は、水底の近くをゆっくりと漂っている。それは菜実子であるように見え、巴さんであるように見える。
水底を囲うのは、薄紫色の透き通った壁であった。
奔流に乗って、あの酒瓶が流れてきた。
三分の二ほどの中身が残ったそれを掴み取った僕は無我夢中で、酒瓶を大樹に向かって放り投げた。
◆
「会社を継ぐ気はないのか」
夏の座敷で祖父が問う。祖父と父は文机を挟んで向かい合っている。文机の上には二本の酒瓶と二つのグラスが置かれている。グラスの片方は手付かずであり、もう片方は半分ほど減っている。
「いいえ」
若き日の父はそう答える。「勉強を続けたいのです」
「そうか」
祖父は怒りもせず、かと言って表情を和らげることもせずに、ただそう言うだけであった。父は祖父の顔を見れずに俯いている。グラスの表面に現れた結露が滴り落ちて、木製の文机を濡らしている。中庭では相変わらずテッカニンが鳴いており、室内に反響しては万華鏡のように幾重の声となる。
「父さん」
父は顔を上げる。祖父と視線が合い、父の背中を冷たい汗が伝う。喉の奥で変な音がした。
薄紫の瓶が、光を浴びて美しく輝いている。
「何故、その酒を俺は飲めないのですが」
父は尋ねた。祖父は黙っている。じわじわという鳴き声だけが響いている。どれほどの時間が流れているのか父にはわからない。祖父の部屋だけが時間の流れから取り残されたようである。祖父が時を止めているようでもある。この須臾は永遠であった。
「酒は毒だ」
祖父はそう答えた。それだけであった。他には何も言わなかった。
毎度聞かされるその口癖に、父は「そうですか」と呟いた。差し出された方のグラスには口を付けていない大吟醸がなみなみと注がれている。手を伸ばそうとしたが動かなかった。祖父の手にしたグラスの中で揺蕩う、無色透明の海がゆらりゆらりと揺れて、父はそこにもう亡き母親の面影を見た気がした。
◆
酒瓶は放物線を描き、渦巻く水流の中へと吸い込まれていった。濡れた前髪が額に貼り付いて気持ちが悪い。夢と現も判別付かない頭の中に、哀しげな慟哭が響いた気がした。ひどく重くなった身体はもはや自分のもので無いように感じられ、感覚の無くなった片手で菜実子を掴んでいることだけが唯一現実味を伴っていた。
その片手が不意に軽くなった。勢い余って蹌踉た菜実子を抱き止めて、僕は目の前の光景に息を潜めていた。
あれほど轟いていた水があっという間に引いていった。どこに消えていくのかはわからない。庭の土に吸い取られるようにして、或いは塀の下を通って屋敷の外へと逃げるようにして、中庭に集まっていた洪水は瞬く間に無くなってしまった。
腕の中の菜実子が息を飲み、小さく身体を震えさせる。彼女の目線の先には祖父の棺が、濡れた状態で打ち捨てられていた。流水によって蓋は外れてしまっており、祖父の遺体が転がり出ている。
全てを跳ね除けるような、不屈という言葉を具現化したかの如き表情は死んでいても変わらない。その事実はある種の安堵ともなり得たのかもしれないが、今はそれすらも絶句の理由でしかなかった。
祖父の身体を突き抜けて、幾本もの蔓が長く伸びていた。菜実子を水流の中へと引き込もうとしたそれは今でこそだらりと垂れ下がっているが、青々という鮮やかさを今も尚、朧月の光に湛えていた。突き破られた皮膚は表面こそ水に濡れてしまったものの乾いているように見え、痛そうなどと感じないのが不思議であった。その様子は、まるで祖父とこの蔓が初めから一体であったかのような、馬鹿げた妄想を引き起こした。
しかしそれ以上に我々の目を惹いたものがあった。水浸しになった中庭は泥濘んでおり、まだ残っている水が足を微かに叩くのが奇妙に心地良かった。彼方此方に流されたトサキントやアズマオウが再び水を失い、散らばった先で各々のたうち回っていた。彼らが持つ、美しい鰭が地面に打ち付けられる度に、びちびちと濡れた音が強く響いた。
その中庭の、中央に位置していた大樹が大きく傾いている。一杯に生い茂らせた葉は僕たちの知るままの姿であったが、筋骨のような幹から繋がる、猛々しい根元の先が月明かりの下に晒されていた。
奔流によって大地が抉られたからか、それとも故意にそうしたのかは知る由も無い。半壊した屋敷に囲まれるようにして、恐ろしいほどに巨大なドダイトスが、大樹諸共中庭を背負ってその身を投げ出していた。
ドダイトスは冷たい水に浸され、ぎらぎらと輝いているように見えた。切株程もある四肢は力を失って、苔に覆われた両眼は固く閉じられていた。額に寄せられた皺は苦しげであったけれど、巨躯は驚くほど綺麗なままであり、畏怖すべき美しさが眼前に顕現していた。
僕も菜実子も、無言で佇んでいた。濡れた土の匂いと、噎せ返りそうになるほどの深緑の薫りが満ちていた。何処かでドンカラスが鳴いた気がした。父や母、姉、親戚たちが僕たちを呼ぶ声が聞こえてきた。
◆
屋敷から三十分ほど車に揺られた先にある火葬場はこじんまりと静かであった。周りに広がる草原が穏やかで、暑くも心地良い空気が漂っていた。大きな尻尾を揺らして駆けていくパチリスの上空を、夏型のアゲハントがひらりひらりと舞う。雲の無い空は青く、今にも落ちてしまいそうに綺麗だった。
あの後、崩れ掛かった屋敷は大騒ぎになったが、皆必要以上に慌てたり騒いだりすることは無かった。地面を割って現れたドダイトスが何故そこにいたのか、どうしてあれほどまでに大きいのか、また、何を思って今日この日に出てきたのかということも、誰も触れなかった。大貴でさえも黙っていた。蔓に裂かれた祖父の遺体の不気味さがそうさせるのか、埋まっていたはずのドダイトスの身体がつい先ほどまで生きていたかのような美しさであったことが原因なのか、或いはもっと、深いところに理由があるのかはわからない。蒸し暑さの消え失せた屋敷は祖父の葬式当日であるはずなのに、祖父の話をする者は誰もいなかった。
葬式の食事は豪華な寿司が出たが味など分からず、粘土を頬張っているような心地であった。夜、菜実子と過ごしたあの時間は夢の延長だったのではないかと僕は考えていた。しかし、薄紫の酒瓶の中身を飲んだ時の痺れも、干上がった池の生臭さも、押し寄せる水流の圧も棺から伸びる蔓も菜実子の横顔も、夢というには実に鮮明に、僕の脳裏に刻まれていた。
やや離れた席では、村佐さんと哲人叔父が寿司をつつきながら話していた。村佐さんはこの辺りに昔から住む血筋らしく、過去の話などを叔父に聞かせていた。
江角家初代、総次郎が若い頃の話だというそれは、シンオウの開拓時代だという前置きから始まった。カントーから訪れた開拓団によりシンオウは切り開かれていったのだが、とある場所の住民たちがいつになっても了承しないため、開拓団は手を焼いていた。
が、ある時住民たちは、一つの話を開拓団の一人に持ちかける。この近くには邪神がいる、自分たちはそいつを鎮めなくてはいけないからここから動けない、森を広げる邪神の機嫌を損ねると祟られるから怖くて出ていけない、と彼らは嘆いた。そして、その邪神をどうにかしてくれさえすればすぐにでも立ち退こう、とも。それより間も無く住民たちはそこを去り、開拓は滞りなく推し進められた。開拓に多大な貢献をした一人の男にはかなりの対価が支払われたらしいが、その男がそれを何に使ったのか、開拓団を抜けた後にどうしたのか、そして如何にして開拓を成功させたのかは杳として知れない。
村佐さんはそんな話をした。哲人叔父は黙って頷いていた。茶と共に飲み込んだ寿司に塗りたくられた山葵が、喉の奥でつんと香った。
二人と別の一角では、桜子伯母と鏡子伯母が、遺産相続の手続きについて話していた。屋敷の崩れた土地は売り払い、得た金はシンオウの自然保護に取り組む団体に全額寄付するなどという会話が聞こえた。ドダイトスの亡骸は丁重に供養した後、かつて森があった処へ帰してやろうなどと伯母たちは言った。
彼女たちが持っていた屋敷の間取り図を覗き込み、僕は思わず言葉を失った。妙な部屋の並びをしていると思っていた屋敷の形を図式化したそれは、歴とした鳥居の形を成していた。
「どうせ、出てこれまい」菜実子が聞いた祖父の声が頭に反響する。地面に作られた大きな鳥居は、地下深くという社にいる神を封じているかのようだった。
食後に運ばれてきたロメは熟し過ぎているように思った。苦いほどの甘さを持つそれを口内へと押し込みつつ、僕は斜め前に座る菜実子を盗み見た。喪服姿の彼女は白い頬に薄く紅を塗っていた。スプーンで掬われた緑の果肉が小さな口へ運ばれる。前髪に隠れた菜実子の、あまり手を入れられていない眉が微かに見える度、僕は現と夢の区別がより一層つかなくなるのだった。
祖父が焼かれているのを待つ間、我々は手持ち無沙汰に草原に立っていた。母が手洗いに行ってしまったため、僕は父と姉と並んで何くれとなく空を見上げていた。
わざとそうしようとしているのか、僕たちは取り留めもない話を口にして母を待っていた。父は僕の大学のことを聞きたがり、姉は友人のポケモンがコンテストに出たことなどを話した。
姉の話が、不意に「そういえば、変な夢を見たの」という内容に差し掛かった。
「水道の中を歩いてる夢なのよ」
「水道?」
聞き返した僕に姉は頷いて、片手を頬に当てながら考え込んだ。細い手首に骨が浮かんでいる。手の触れた顳顬を汗が一筋伝っていた。
「なんだか、水道の中みたいなところ歩いてるのよ。ぐるりと壁に覆われて、水が流れていく音が聞こえるから、水道」
水が流れてる菅ってだけでそう決めるのは安直かしら。汗を拭う姉は言った。「でも、それしか例えようもないしね」
「でも、毎晩同じ夢を見てたのよ。ここに住み込んでから、いえ、もっと前から、ずっと」
「小さい時から、ずっと、か」
呟くような姉の言葉に父が口を挟んだ。普段父はあまり喋らない性分だったし、こうして誰かの話を遮るような真似をしなかったから、僕は少々驚いた。意外であると感じたのは姉も同じだったようで、目を数回開けたり閉じたりしてから返事をした。
「そうだけど。お母さんに言っても信じてもらえなくて。でも、何でわかったのよ」
もしかしてお父さんもそうだったとかじゃないでしょうね、という姉の言葉に父は返事をしなかった。ただ少しだけ口許を緩めた父は、汗の浮かんだ瞼を数秒閉じた。
「道の向こうに、親父が歩いていった。俺はそれを追いかけるんだが、どれだけ急いでも、親父との距離は開くばかりなんだ。親父の向かう先に、親父に似ている男が二人歩いていた。俺は親父に手を伸ばした。だが、」
父が話し出した。それは僕たちに話しているというよりも独り言のようであり、またここにいない誰かに語りかけているかのようにも感じられた。
「後ろから引っ張られて、親父の方へは行けなかった。振り解こうとすると地面が揺れて足が縺れた。ずっと聞こえていた音が、轟々と鳴り響いていた」
それは果たして、昨日にだけ見た夢なのだろうか。父の話を聞いていた僕の頭の中で、ふとそんな疑問が首を擡げた。
しかしそれを確かめる術はもうあるまい。いや、最初から無いだろう。父の見た夢の意味するところは、父にすら永劫にわからない。
「引っ張ってくれたのは、母親だったように思う」
父はそこで目を覚ましたという。夢から引き戻された父を待っていたのは屋敷が崩れる現実の震動と、蒲団から出た自分の妻が慌ただしげに障子の外を覗く姿であった。血相を変えた姉が廊下を走ってきて、その後を追った父が中庭の惨状を見るのはその数刻後である。
水が流れてるから水道だと姉は言った。水の通り道となる管に、またそれと隣り合っている道に、僕は思い出すものがあったが、今となっては全て終わったことであるため黙っていた。
「声は呼んでいた。何度も聞こえた」
僕も姉も、父の話に何かを言うことをしなかった。その夢は僕もよく知っているようであり、また全くの未知であるようでもあった。姉もきっと同様であろう。僕たちは黙りこくったまま、父の声だけが頭の奥に溶けていった。
その声が何を言っていたのか、僕は昔から知っている。姉も、そして父もだ。何を訴えているのか、何を読んでいるのか、僕たちは皆、その声を長く聞いていた。
「江角、と」
しねしねしね。テッカニンの鳴き声が響いてくる。この鳴き方を聞くのは久方ぶりであった。以前に聞いたのはずっと昔のことで、やはり屋敷に訪れた際だったのは覚えているが、その時隣に誰がいたのかは記憶に残っていない。ただ、夏という監獄の檻となって自分を責め立てるようなものに感じられたことだけが、今も尚はっきりと思い出せる。死ね、という慟哭となって。
煙突からは白い煙が細く上がっている。終わっちゃったねぇ、と姉が気の抜けた声で言う。父が小さく頷き、取り出したハンカチで汗を拭う。青一色の空を突き進む煙は、祖父らしからぬ緩慢さで天へと向かう。
首筋を伝った汗がワイシャツの襟に染み込んだ。火葬場を囲う木々の緑が、鮮やかな色をして風に揺れていた。
江角が殺し、江角を呪った神を、江角の血をひかない僕が葬ったのだと、そう思った。
雨はさらさらと音を立てて降り始めていた。
ボンネットの上から聞こえる雨音は、いつもより小さい。
ただ付いて来ただけ。だからか、車を運転しながら色々悩む羽目になる。
レジャーシート程度のものならある。雨避けでも渡そうか。いや、そもそも湖で暮らしていたなら雨何て避けるものじゃないのか?
それに、もうそろそろ家に着く頃だった。
そんな事やってる暇があればさっさと車をかっ飛ばして家に戻る方が良さげだろう。
家に着く。二階建て、庭有り。そして俺一人とウインディ、妻が残していったポケモン一匹。
ローンはまだ残っている。
車から出て、その郊外に建てた家を眺める。いつもの事だ。
この家は未だに物理的には心地いい空間ではあったが、俺にとってはもう精神的に心地いい空間ではない。
魚釣りはこの頃再開した趣味だったが、それの原因が別れた妻にある事は内心分かっていた。
ウインディのボールを引っ掴み、荷物を肩に背負い、ドアから出る。
常人ならボンネットの上に乗っていても安心していられないような普通な運転だったが、カイリューは未だにそこに居た。
カイリューはゆっくりとした動作でボンネットから降りる。
僅かに、凹んでいた。舌打ちをしたくなるのを堪えた。
とは言え、追い返す事は出来ないし、付いて来る事を拒む事も出来ない。ボールに入れる事も出来ない。
だが、誰かに連絡を取って何とかして貰おうとも不思議と思わなかった。
何故だかは、分からない。その表情からは何も読み取れなかったし、ここに居候するとなったらポケモンの食費が増える事やら手間が増える事やら良い事は決してないのに。ボンネットも凹まされたのに。
ただ、悪い事はしないだろうとは思えた。暴れたりはしない。そして、こいつにとって俺に付いて来た事は何らかのプラスがある事だ。
それだけは何となく分かっていた。
「……来いよ」
雨の中、ぼうっと突っ立っている訳にもいかない。それに、ただ付いて来ただけにせよ、俺は雨の中にこいつを突っ立たせておける程割り切れる人間でも無かった。
ボールが少し、震えた。
ウインディは反対のようだった。
玄関を潜り抜けるようにしてカイリューは家の中に入った。
ウインディを出して「バスタオル持ってきてくれ」と言う。渋々ながらウインディは従った。
反対しようとも、俺が受け入れてしまった事を分かっているのだろう。
こいつが卵だった頃からの、そして俺が学生だった頃からの付き合いだ。互いの事は良く知っている。
ウインディがバスタオルを持って来て、俺は濡れたカイリューの体を拭いた。精神的に居心地の良い場所ではないが、物理的にも居心地の悪い場所になっても困る。
カイリューは大して邪魔をせず、俺が体を拭うのにじっとしていた。
聞き分けは良さそうだった。こうやって付いて来た位だ、我が強いのはあるだろうが。
カップ麺に湯を入れ、ポケモンフーズを出す。
バスラオを食って満腹だったウインディも、何故か欲しそうにしていたのでまあ、いつもより少なくだが皿に入れた。カイリューにも皿を出してポケモンフーズを入れた。
ウインディが食べているのを見て、ぽり、ぽりと少しずつ食べ始める。遠慮しているような素振りを見せながらも残しはしなさそうだった。
テレビを付けて、適当にチャンネルを回す。カイリューは驚きはしたが、特にそれと言って何もする事は無くただぽりぽりと食べながら眺めていた。
テレビでは見慣れた芸人がクイズに答えていたり、視聴率が並そうなドラマをやっていたり。
ニュースでは肉に関する新たな規制に対しての議論をしていた。
明日の天気を知りたかったが、気が重くなり、チャンネルを回した。
軽くシャワーを浴びて、明日の仕事の為に少し早く寝る事にする。今日はいつも以上に疲れた。
明日から会社なのにこいつをどうしようかという不安はある。何とかなりそうな感覚はあるのだが。
居候はもう一匹居る事だし。
寝室へ行く。ツインベッドの片方は、今はウインディが占拠している。毛だらけになっているが、いつから放置しっぱなしだったか。コロコロで拭ってもキリが無いし。
そして窓が開いているその寝室には、ムシャーナ、妻が置いて行ったポケモンがふわふわと漂っている。
時々ここから居なくなるこいつは、きっと俺の夢を盗み見て妻にでも届けているのだろうと思う。
今でもある、妻との唯一の繋がりだった。
ムシャーナは、俺の後ろから二匹目、カイリューが来た事に対しても特に何も反応せずにふわふわと浮き続けているだけだった。
予備の布団を適当に広げて、カイリューの為の寝床にする。
ウインディはその布団の上で丸まるカイリューを心配そうに眺めながらも、俺の隣で目を閉じた。
電気を消し、俺も目を閉じる事にした。
夢うつつになる中、カイリューの目的が何であれ、ただ居候する程度なら歓迎している自分に気付いた。
そういう関係なら、何も考えずにコミュニケート出来る、一緒に居られる、と思っている自分が居た。
Pokezine 20XX年9月13日 19時45分32秒
おとなしく可愛らしいイメージの電気ポケモン、プラスルがマイナンと協力して群れを作り、ペリッパーを捕食するシーンが撮影され、日本ポケモン学会に衝撃が走っています。
プラスルは最大体長0.4メートルの小型草食ポケモンで、数匹で群れを作り、木の実や草を食べて生活するおとなしく平和的な性格のポケモンです。近似種のマイナンも交えた群れを作ることもありますが、お互い喧嘩をすることもなく、家族のように一緒に仲良く暮らすほどです。今回撮影された写真では、そのプラスルとマイナンがポチエナの群れのように協力して大型ポケモンの「狩り」を行っており、本来の生態からも大きく逸脱した行動にポケモン生物学者達は動揺を見せています。
写真を撮影したのはカイナシティに住むポケモン写真家のカミヤ・コウイチロウ氏。「101番道路でロゼリアの写真を撮っていたら、近くの草むらで騒がしい鳴き声と火花の弾けるような音がしたので近づいてみたら、プラスルとマイナンがペリッパーを襲っていたんです。本当に驚きました」とのこと。彼が撮影した写真には、数匹のマイナンが電気の網を張ってペリッパーを道路の隅に追い込み、体に電気を纏ったプラスルがペリッパーの頭部にたいあたりを食らわせる、非常に息の合った狩りの様子がありありと写しだされています。
プラスルやマイナンは小型の虫ポケモンやタマゴなどから動物性タンパク質を摂取することもありますが、積極的に狩りをし、肉食を行うことはこれまで報告されていませんでした。写真を見たポケモン生物学者のハコベ・ケンゾウ氏は「写真を見る限り、プラスルとマイナンの肉食行動は非常に新しい習性のように見えます。例えばルクシオのように普段から肉食を行うポケモンであれば、獲物を追い詰めた際にはまずとどめを刺すために喉元に食らいつきます。それから腹などの柔らかい部位から食べ始めるわけです。ところが写真を見る限りプラスル達は、電気で痺れさせた獲物がまだ飛び立とうとするうちから捕食行動に入っていますし、自分たちが飛びついた部位から闇雲に食べ始めています。狩りのルールが確立されていないのです」と話しています。
穏やかなはずの彼らを狩りに駆り立てたトリガーは何だったのか。今後地元のポケモン生物学者によって詳しい調査が行われる予定です。
お騒がせトリオとの共同生活、三日目。
ふと目覚まし時計を見ると、設定時刻を一時間も過ぎていた。うっひゃあ寝坊だーーっ!
慌てて飛び起きたら布団の上に乗っかっていたらしい小猿たちが「ぷきゃ!」と悲鳴を上げて床へ転がった。我に返る。
「ああ…お店行かなくていいんだった…」
私に振り落とされてぷりぷり、もとい、おぷおぷ怒っているバオップ。しくしく、もとい、やぷやぷ泣いているヒヤップ。それから一匹転落を免れたらしいヤナップを順繰りに見渡して、息を吐く。
目覚まし時計にもお騒がせ三重奏にも気がつかないほど熟睡していたらしい。昨日なかなか寝付けなかった所為かな。なんとなく頭がぼーっとする。
三匹(正しくはバオップとヒヤップ)を宥めすかしながらリビングへ向かう。ちょうど両親が出勤の支度をしている所だった。キッチンテーブルに私の分の朝食が用意されており、お昼ご飯は冷蔵庫にあるから、と母が言った。
「行ってらっしゃーい」
二人が仲良く家を出るのを見送る。それから朝食を済ませ服を着替え、私たちも我が家を後にした。
アパートの階段を下りて北へ、通い慣れた道筋を辿る足。交差点の横断歩道を渡れば、三日前まで毎朝通っていた三ツ星は目と鼻の先だ。
あそこへ行かなくなってからたったの三日。なのに、もう何週間も行っていないような感覚だ。ずうっと続いていた習慣を突然断絶すると、こんなにも心がそわそわして落ち着かなくなるのね。
渡ろうとしていた横断歩道の信号が赤に変わったので、立ち止まる。待つ間、ぼんやりと慣れ親しんだお店を眺めた。
窓にはカーテンが引かれ、中の様子は判然としない。開店まではまだ時間があるし、スタッフも集まり切っていないんだろう。正面玄関も堅く閉ざされている。
「……行こうかな」
三ツ星に。
「追い出されることはまず無いだろうし」
アパートを出るやいなや無意識にあそこを目指していた体に対して、そんな風に言い聞かせる。気になるなら行っちゃいなよ私。うん。
「みんな、お店では静かにしててね!」
そう言って振り返れば、そこには「分かった!」とでも言うように私を見上げて来る三匹の小猿が……
「いなーーい!!」
いなかった。
「アレッ、どこ行ったの? ヤナップ? バオップ? ヒヤップーー?」
朝っぱらから大通りで大音声を張り上げる私に通行人が驚愕の表情を向けてきたが、構っていられない。
一気に冴えた頭をぶんぶん振り振り辺りを見回す。西へ続く別の横断歩道の向こう側に、緑赤青のカラフルな影が走って行くのを発見した。待ってェーーー!
「やぷっ!」
「おぷー!」
「なぷぅ!」
加速するお騒がせトリオ、追跡する私。必然的に三ツ星からはどんどんどんどん遠ざかる……。
行き先を鑑みて、公園でまた遊びたいのかと思いきや、どうも違うようで。三匹は公園内の通路を次は北へと突っ切る。木香薔薇が絡まった木製のアーチをくぐると、隣町シッポウシティへと繋がる三番道路に出た。
丘に建つ幼稚園と育て屋の前を通り過ぎ、前方と左方とに分かれた道をかくんと左折。木立を抜けるとやがて池が見えて来た。向こう岸との間に架けられた小さな橋に差し掛かった所で、三匹の暴走はようやく終止符を打つ。
「やっ、やっと、止まった…!」
ぜーぜーと肩で息をする私の真ん前で平然と、どころかすごく嬉しそうに跳ねているヤナップバオップヒヤップ。もう怒る気力が湧かないわ……。
ひとまず切れ切れになった息を整えようと、深呼吸していると。
「我々への挨拶も無しに旅に出るつもりですか? メイ」
聞き慣れた涼しい声が背中に投げかけられ、私は勢いづいて振り向いた。
「コーンさん! 違いますよ…旅になんか出ません。この子たちを追いかけて来ただけです」
背後には予測通りコーンさんの姿。腰掛けた自転車を左足で支え、立っていた。少々困り顔で。
「一緒に行こうと、あなたを誘っているのでしょう」
「そんな。私にはお店のお手伝いがあるし……」
そのように返しつつ三匹の様子を窺うと、期待に満ちたキラッキラの眼差しに迎えられた。……そんな顔されましてもねえ。
「コーンさんはどうしてここに?」
訊けばシッポウシティに用事がある、とのこと。
それとこれとは関係無いけど、自転車での外出だと言うのにコーンさんも前日の二人と同様のウエーター姿だ。むしろこれが彼らの普段着と言っても差し支えない着用率。まぁ、私もいつもならエプロンと三角布を着けたままその辺を歩き回るから、人のことを言えない(今は休みだから私服だ)。
「はあ。店の手伝い、ね…」
先の私の返答に首を傾げたコーンさんは、自転車を降りて傍らに停めると、私の目を真っ直ぐに見、口を開く。
「それは本当に、メイが心から追い求めた願望なんですか?」
「え…」
「彼らを見ている内に気づいたんじゃありませんか? あなたの願いや望みが、あの場所には無いことに」
不意の問い掛けでとっさに返す言葉を見つけられず、私は茫然としてしまう。
あの場所って三ツ星のこと…よね。
「まだ余裕があります。一つ、為になる話をして差し上げましょうか」
左の袖口を捲り腕時計を確認したコーンさんは、私のぼんやりした態度に構わず話を進める。
「メイ。あなたはコーンたち三人が、この先もずっと共に、あの場所にいるものだと思っていますか?」
またしても唐突な質問。とりあえず頷いてみると、コーンさんは少しだけ悲しそうに頭を振り、足下の小猿たちへと目線を落とす。
「我々は決して運命共同体ではありません。デントはイッシュ各地の色、味、香りを追究し味わうため、自由気ままな一人旅がしたいと願っていますし、ポッドは一般トレーナーと同じようにジムバッジを集め、いつかはイッシュリーグへ挑戦することを望んでいるんですよ」
コーンさんは三匹の前に膝をつき、彼らの頭を撫でながら、続ける。
「このコーンも、いずれは修行の旅に出向こうと考えています。もちろん一人でね。ポケモンもそうですが、コーン自身のレベルも上げることが出来るでしょう。それが、コーンの夢なんです」
「…………」
「デントもポッドもコーンも目指す夢は違い、向かう道は異なります。三つ子だからと言って、いつまでも三人、一つ所には留まっていませんよ」
お騒がせトリオが私たちの周りを跳ね回っている。とても楽しそうなその姿に、コーンさんはふっと口角を上げた。
「夢……」
アイドル。美容師。教師。イラストレーター。パティシエール。
友達はみんな確かな未来像を持っている。将来はどうしたいと問われれば、彼女たちは迷わず即答するだろう。それは、彼女たちが自分にとって最も素晴らしいと考える毎日を形作る、土台となるものだから。
私の両親も子供の頃に料理人になりたいと願い、望み――今は、ずっと夢見ていた毎日を送っている。
そしてコーンさんたちも。今は一緒に仕事をしているけれど、いつかはそれぞれに思い描く素敵な日々を送るために、三ツ星から…サンヨウから、旅立つんだ。
コーンさんはそこですっくと立ち上がり、私を見た。
「あなたのご両親もコーンらも。あなたの才能がより強く美しく開花し、それを存分に奮うことの叶う未来を求めるならば、それがどんな旅になるとしても、全力であなたを応援する心積もりですよ」
「……でも」
戸惑い。躊躇い。迷い。恐れ。心の中に入り乱れ、靄のように蟠るそれらの感情に抗えず、目を伏せる。
ひゅうと吹いた強い風が、私とコーンさんの髪や服を揺らし、木々の葉をざわめかせ、水面を波立たせる。けれど私の胸にかかった靄までは、払い除けてくれそうもない。
「ポッドがあなたを夢の跡地へ行かせる、と言い出した時には驚きましたが……しかしメイならもしかしたらと、このコーンも思ったんです。そしてあなたは我々の期待を裏切らず、見事チョロネコと打ち解けてみせた」
コーンさんは再度足下にいる小猿たちに視線を転じ、左手全体で三匹を指し示す。
「彼らが何故あなたの採取した果物を盗ったのか、解りますよね? 林の奥にはそれこそ、至る所に果物が生っているにも関わらず。何故、あなたの持っている物を奪ったのか」
それは、チョロネコたちが自分では果物を採らず、私が譲る物を手にするのと同じ。あの子たちは私が選んだ果物が必ず美味しいことを、知っていた。この子たちにもそれが判ったんだ。
「生まれ持った才能を、成り行き任せに組み立てられた退屈な暮らしの中に埋没させるなんて、勿体ない。さして好ましくもない行為に、限りある体力を心血を、未来を費やすなんて、これほど味気ないことは無いとは思いませんか?」
ポッドさんに、私は言った。
私はトレーナーに興味が無い。そう好きでもないことをやるなんて、おかしくはないか、と。
「退屈だなんて私…」
三ツ星での仕事が好きじゃない、合っていない、とは感じない。探してみても一つも不満は無い。
だけど……ただ一つ、あの場所に何か足りない物があるとしたら、それはたぶん、
充実感。
「…………」
私は前から漠然とそれを感じていた。明確な言葉にする機会が無かっただけで。真っ向から自分の気持ちを見つめようとしなかっただけで。
だって、“平凡だけれど安定した生活”から脱するには、新しい一歩を踏み出すには、勇気が要る。覚悟を強いられるから……。
「惰性であの場所に居続けるのは、コーンはあまりお勧めしませんね」
デントさんは、私に言った。
自分のことは自分が一番よく解っていると、殆どの人間は考えているけど、周りの人間の方がその人を理解している時もある、と。
みんな、そう思うんだ。
私は外へ出た方がいいんだ、って。
「ま。周りがどうこう言っても結論はメイ、あなたが出すんです。あなたがこの先どういう日々を送りたいのか、それはあなたにしか解らないし、あなたにしか決められないことなんですよ」
直立不動で黙りこくる私を、小猿たちが静かに静かに見つめていた。
「いけない。そろそろ行かなければ」
私が発言するのを待っていたんだろうか。
声も無くそっぽを向いていたコーンさんが、ふと時計に目をやるや呟いた。スタンドを蹴って解除しサドルに腰を降ろすと、視線を私へ移す。
「それではまた。はしゃいで池に落ちないよう、気をつけて帰るんですよ」
この辺りには凶暴なバスラオが沢山棲息していますからね。
そう言い残し、一路シッポウシティへ向けて、コーンさんは自転車を走らせて行った。
「………………。」
いくらはしゃいだって、十五にもなって池ポチャする訳が無いのに…あの青鬼…子供扱いして…!
しかし、可能性が全く無いとも言い切れない(私はともかくお騒がせトリオは何を為出来すか判らない)。余計なことを始められる前に、ここから離れなきゃ。
*
「なぷぷぷっ!」
バニラビーンズを煮出し終え、色とりどりの果物をカットする作業に移る。
「おぷおぷー!」
片手鍋に注いだ水が沸騰したら、そこへミントを入れて。
「やっぷぅ〜!」
隣で火にかけられている大きめの鍋では、ミネストローネがふつふつと煮立ち始めた。
「ぁいたっ。向こうで遊んでよ、もう」
キッチンテーブルの周りを追いかけっこしている三匹に、時折ぶつかられ小言を溢しながら、私は調理を続ける。
今日は両親が早く帰って来る日なので、私が夕食を用意することになっていた。メインはたっぷりの野菜とハーブを効かせた特製ミネストローネ。煮込み終わるまでの間、小猿たちの食後のおやつとしてフルーツゼリーを作ることにした。
バニラとミントで香り付けしたお湯に、グラニュー糖とゼラチンを加え泡立て器で撹拌。火を止めたらオレンジリキュールを少々。粗熱を取ったら平らなカップに流し入れて、とろみがついたら細かく切っておいた果物を沈める。あとはラップをかけて冷蔵庫に入れ、固まるのを待つだけ、っと。
「ハイハイ、もう少しあっちで遊んでてね」
作業が一段落したのを感知し、まとわりついて来る三匹をリビングへ追い払う。
次はサラダを作ろう。
胡瓜とプチトマト、サニーレタスを洗って水を切る。プチトマトはへたを取って、胡瓜は薄く斜め切り。レタスは手で一口サイズに千切っていく。
「…………」
そんな単純作業の傍ら。
私はコーンさんの言葉を思い出していた。
才能を存分に奮うことが出来る未来を求めるなら、それがどんな旅になるとしても――。
「旅…か…」
仮に私が旅に出るとして。
私は旅から何を得ようとする?
何を得るために、私は旅に出ればいい?
キッチンの椅子に座り、リビングに敷かれたラグの上でポケモンフーズを食べるヤナップたちを眺める。その間にも思考は巡っていた。
あの子たちはサンヨウへ来るまでの間、色々な人やポケモンを見て来ただろう。
その人たち、ポケモンたちは、みんな生まれた場所も育った環境も違っていて、そして物の考え方や味の好みも違うんだろう。
私はイッシュ生まれのイッシュ育ち。
だけど私が知っている範囲は、イッシュのほんの一部分に過ぎない。
サンヨウの外には、一体どんな人やポケモンが住んでいるんだろう。
そこに住む人たちは、ポケモンたちは、どんな料理が好きなんだろう?
そこまで考えた所で、はたと気づく。
私はそれを知りたい。
見てみたい。探してみたいのだと。
「………………そっか。」
答えは思いの外呆気なく導き出され、私の胸にすとんと落ちた。
洗い物をしていると、冷蔵庫に付属したタイマーが鳴った。と、小猿たちが食後とは思えない素早さを以て駆け寄って来る。
「そこどいてー!」
占拠される足下に用心しつつ冷蔵庫からカップを取り出し、ラップを外す。それぞれの小皿にひっくり返し、ローテーブルに置く。
「はい、どうぞ!」
瞬間、待ってましたとばかりにゼリーに食らいつく三匹。
「…………。」
うーん…もうちょっと落ち着いて食べられないものか。メンタルハーブでも盛りつければ良かったかな。
しかし、つくづくこの子たちは凄い。
ああいや、食べっぷりのことじゃなくて。
その幼さで、ここまで三匹きりで旅をしてきたという、事実が。
「勇気あるよね。あなたたち」
感嘆の声に反応し、三匹が皿から顔を上げる。直向きで無邪気な三対の瞳が、私の姿を捕らえる。
「私も、覚悟を決めなきゃいけないけど……」
ここから旅立とうとしているのは私だけじゃない。デントさんたちも同じ。それには確かに勇気づけられる。
でも。
「やっぱり不安になる。ちゃんとやっていけるかって考えると……どうしても、怯んじゃうわ」
三匹はゼリーの残りを平らげると、こちらへ歩み寄って来た。そして私をじい、と見つめると。
「なぷぷっ!」
「おぷおぷ!」
「やぷぷぅ!」
そう言って、ニコッと笑った。
「……………………」
勇気は、ほんのちょっとでいいんだ。
覚悟は、何度だって決められるんだ。
要はやるか、やらないか、なんだよ。
彼らの目はまるで、そう言っているようだった。
「……………………うん。」
少しの沈黙の後、一つ頷いて。
つられて、私もにっこり頬笑んだ。
「そうね…………ありがと!」
背中を押してくれて。
ガチャ、と扉が開く音がして、ただいま、と二人分の声が聞こえた。
私は勢いに身を任せ、玄関へと直走る。そしておかえりを言う代わりに、力強い宣言で二人を出迎えた。
「お父さん、お母さん! 私、決めた。旅に出るっ!!」
突然過ぎる宣誓に二人はしばらくぽかんとしていたけれど――やがて揃って破顔し、大きく頷いた。
次の日の昼下がり。
三人に会いにお店へ顔を出すと、私が声をかけるよりも先にカラフルヘアートリオがやって来た。大体予想はしてたけど、両親は出勤早々、いの一番に彼らに報告したらしい。そんなに嬉しかったんですかお父様お母様……。
私は三人(と言うかポッドさんとコーンさん)にせびられ、事の顛末を簡潔に伝えた。ヤナップたちのお陰で決心がついた、と。
「彼らがメイちゃんに、将来について考えるきっかけと勇気をくれたんだね」
デントさんの台詞に頷きながらも、私は心の中でううん、と頭を振る。
この子たちだけじゃない。デントさんとポッドさんとコーンさんが、平凡な場所に逃げ込もうとした私を引き留めてくれたんです。
……なあんて、照れ臭くて本人たち(と言うかデントさん以外)には言えないけどね。
その後、私たちは夢の跡地へと向かった。
この子たちに、ある話をするために。
*
夕暮れ時、鮮やかな橙色に全身を包まれてアパートへ戻ると、我が家の扉の前に人影が佇んでいた。
燃え盛る炎のような形状の髪型。間違えようも無い。赤鬼だ。
「ポッドさん?」
呼びかけると少しの間、そして怒声が返って来た。
「おまえおっせーぞ! 何分待たせんだよッ」
「は、はい?」
聞くところによると、三十分ほど前から私たちが帰って来るのをずうーっとここで待っていたんだとか。ポッドさんの割には気の長いことで。
「用件はなんですか?」
事務的に問うと、あーだのうーだのと言いながら視線を彷徨わせ始めた。
挙動不審だ。怪訝に凝視する私とお騒がせトリオ。
一分くらいそんなことを続け、ポッドさんは苦々しい顔つきでようやく開口する。
「チョロネコの件……わ、悪かったな」
刹那、数日前この人が見せた腹立たしい言動の数々がフラッシュバックした。
「ほんとですよっ!!」
勢いで憤慨してみせたら予想外に大声が出た。柄にもなくビクッと肩を震わせたポッドさんがちょっぴり可哀想になり(ついでにヤナップたちも驚いて飛び跳ねた)、「でも良い経験になったので今は感謝してます」と続けると、怖じ気づいたまま「お、おう…」と返事をした。
「あと、コレ」
小脇に抱えていたクラフト紙の封書から何やら取り出し、こちらに差し出す。どうやら本のようだ。薄い…………本?
ピュアでイノセントな心の空が脳裏をよぎった。
「なっ、なんでそんな本を私に寄越すんですかっ!!」
「はー!? おまえが旅に出るって言うからわざわざ持って来てやったんだろ! ポケモン取扱免許持たずに旅するつもりかよッ!?」
「え。ポケモン取扱免許?」
ポッドさんの台詞に違和感を覚え、よくよく本を見てみれば。
あれよりも大分小さくて、表紙に『ポケモン取扱免許取得の手引き』と書かれていた。
「な、なぁ〜んだ……すみません。電波な例のあの本かと思って。ありがとうございます」
非礼を詫び、お礼を言って本を受け取る。
「ああ、アレ…。アレはデントの私物に昇格したから安心しろ」
果たしてそれは安心していいものなのやら。
ポッドさんの声を聞きながら、早速頁を捲る。
「特別勝負がしたくなくっても、旅するってんならポケモンと一緒の方が断然ラクだし、楽しいかんな。前にも言ったけど、おまえかなり素質あると思う。いっそトレーナーとして旅に出ちゃえよ」
手引き書を一通り流し読みすると、サンヨウシティに在住している人の場合、トレーナーズスクールに申し込めば、いつでも希望者の好きな時に講習を受けられることが解った。
「こいつら、おまえと旅したがってんだろ? こいつらのことだったら、オレらが色々教えてやれっしさ」
「あ…えっと、ポッドさん」
三匹の前にしゃがみこんで、両手使いで彼らの頭をわしわし撫でまくっているポッドさん。上機嫌な様子で、私は少し申し訳なく思いながら話しかける。
「そのこと、なんですけど。実は、私……」
遠慮がちに切り出す私に、ポッドさんは案の定、訝しむように眉根を寄せた。
――昨日、三ツ星へ顔を出した後のこと。
夢の跡地をのんびり歩きながら、私は三匹に、自分の心からの願望を話して聞かせた。
「旅をするには、トレーナーになるのが一番いいみたい。無料でポケモンセンターに宿泊出来たり、色々と特典があるらしくて」
香草園へ続く轍の道に差し掛かってすぐ、木陰からチョロネコやムンナが現われて、私を取り巻いた。会わない日が続いていたから気にしてくれていたのかもしれない。
「でも私、勝負には疎いから、ポケモンのことを一からしっかり勉強したいの。勉強不足でポケモンを傷つけることにならないように、ね」
チョロネコたちにちょっかいを出したり出されたりしつつも、三匹はしっかり私の声に耳を傾けてくれている。
草むらに点々と姿を見せ始めるハーブ。その香りを楽しみながら進んで行くと、頭上からマメパトの鳴き声が降って来て、目の前を数匹のミネズミが横切った。
「その間、あなたたちを待たせたくない。あなたたちと行けたら最高なんだけどね、早く旅を再開したいでしょ? だから、私が責任を持って、あなたたちと色々な場所へ行ってくれる人を探すわ」
香草園の入口に辿り着いて私は、後ろを歩いていた三匹に振り返った。
「私の目利きよ? 素敵なトレーナーを見つけるから、期待して!」
私の言葉が、意図した通りに彼らに伝わったかは、判らない。
「…なぷっ」
「おぷー!」
「やぷぅ〜」
でも、三匹がこくんと頷いて、にこにこと笑ったから。
「良かった。解ってくれて。」
ありがとう、と言って、笑顔で飛びついてきた三匹を力いっぱい抱きしめた。
*
三匹とのお別れ。そして彼らの、新たな旅立ちの日。
朝の陽射しを受けるサンヨウの街並み。その間を歩いて行く私の後ろには、小猿は一匹だけ。他の二匹は、さっき出会った二人のポケモントレーナーの元へ、送り出して来たところだ。
最初に見つけたのは、眼鏡をかけた、真面目そうな黒髪の男の子。ミジュマルを連れていたから、そのミジュマルが苦手な草タイプに対抗出来る、バオップを託した。彼なら、怒りっぽいバオップ相手でも冷静に対応出来るだろう。
次に見つけたのは、ツタージャと追いかけっこをしていた、緑の帽子の、眼差しが優しい女の子。草タイプのツタージャの弱点、炎タイプに有利なヒヤップを託した。彼女なら、ヒヤップの一挙一動に、一喜一憂してくれるだろう。
三匹離れ離れになるのは嫌がるかなと思っていたけど、そんなことは全く無かった。むしろ、誰が一番楽しい旅が出来るか勝負、という感じのノリで、別れ際、バチバチ火花を散らしていたように私には見えた。
「おぷおぷー!」
「やっぷぷぅ!」
バオップもヒヤップも、私が見込んだトレーナーを気に入ったみたいで、とっても嬉しそうな顔で歩いて行って。
残るヤナップは心なしか、だんだんとそわそわし始めた。
「大丈夫。あなたにも、きっといいトレーナーを見つけてみせるから!」
「なぷー」
そんな会話をしながら、私とヤナップは再び夢の跡地を訪れた。ここならトレーナーが修行に来ることも多いから、ヤナップを託すのに見合うトレーナーとも出会える気がして。
そうしたら、やっぱり居た。ヤナップと同じように、好奇心に満ちた面差しをした女の子が。それも狙ったかのように、炎タイプのポケモンと一緒だ。
この子だ。この子しかいない。
運命のようにも感じる出会いに胸を高鳴らせつつ、女の子に声をかけた。
「ねえねえ、あなた。このヤナップが欲しい?」
私の台詞に、えっ、と言って振り返ったその子。服装もそうだけど、目ぱっちり歯真っ白で、とても健康的だ。何故かきょっとーんとした顔してるけども。
……あ、私の所為か。
「ごめん、唐突過ぎたよね」
仕切り直し。女の子に謝り、順を追って説明する。
「あなたポケモントレーナーでしょ? 私はサンヨウのカフェレストで働いているんだけど……このヤナップをね、あなたの旅に連れて行ってもらえないかな、と思って声をかけたの」
「なぷー!」
後ろに控えていたヤナップが、待ち切れないとばかりに女の子の前に進み出る。すると女の子よりも先に、彼女の足下にいたポカブがぱっとヤナップに近づいて来て、挨拶するみたいに一声鳴いた。
「私は事情があってポケモンを持てないの。あなたが良ければ、このヤナップを仲間にしてあげてほしいんだけど……どうかしら?」
いいんですか、と女の子が驚き半分喜び半分といった体で私に訊ねる。
「うん! この子、あなたを気に入ったみたいよ。それにポカブも、かな?」
私の発言にふと視線を落とし、ポカブとヤナップがすっかり打ち解けてじゃれ合っているのを見た女の子は、ははは、と男の子みたいに白い歯を覗かせて笑った。私もつられてくすくす笑う。
「この子は草タイプだから、あなたのポカブが苦手な水タイプに相性がいいわよ」
エプロンのポケットに一つ残った紅白色の球体、モンスターボールを、「はい、どうぞ!」と差し出す。私の意図を汲み取り、女の子は私の手からボールを取ると、よろしくね、と言って、ヤナップの頭上にそれをかざした。
「なぷ!!」
光に包まれた緑色の小猿は、彼女が持つボールの中に瞬く間に吸い込まれる。
これで、ヤナップの親トレーナーの登録は完了だ。
直後、女の子はボールからヤナップを解放したかと思うと、うーんと頭を垂れて考え込んで……しばらくして、ぱぁっと表情を明るくさせた。どうやら、彼に付ける名前を閃いたらしい。
満開の笑顔でヤナップを抱き上げ、彼女は思いついたばかりの真新しいニックネームで、何度も彼を呼んでいた。
「…あっ! 大切なこと忘れてたわ!」
私に礼をして背を向けた女の子に、一番重要なことを話し忘れていたのを思い出して、慌てて呼び止める。
女の子は私のその言葉に神妙な表情で振り返り――そして。
「あのね、その子ものすっごく食いしん坊だから、ご飯の時は他の子の分を取らないように、しっかり見張ってね!!」
大口を開け、笑った。
焦茶色のポニータテールを楽しげに振って、女の子が去って行く。彼女の足下をポカブ、そしてヤナップが歩いて行く。
意気揚々と歩き出したヤナップに、彼と同じように旅立ったバオップとヒヤップの面影を重ね、その前途が希望に満ちたものであるように願う。
空っぽな日々を送っていた私に、歩みたい道を見出すきっかけを贈ってくれた、あなたたちへ。
今度は私が、あなたたちに最高の旅をプレゼントしてくれるトレーナーたちとの出会いを、贈る。
次に会う時には、あなたたちが心から願い、望んだ日々を送ることが出来ていますように。
「私も、そんな日々の中にいますように。」
私はまだ『やりたいこと』を見つけただけで、目標と言えるほど明確な形をした物は手に入れていないけれど。
旅をしていく内に、この漠然とした願望の中から「これが私の夢だ」と即答出来る物を、必ず見つけられると、そのことだけは確信していた。
「いつかどこかで、また会おうね」
あの、小さくも勇ましい三匹の小猿の背中を、私は祈りを込めて、見送った。
――それから、数日後。
カフェレスト『三ツ星』兼『サンヨウシティポケモンジム』にて、新人トレーナートリオ&お騒がせトリオに早々に再会することになるのは……
また別の、おはなし!
――――――――――――――――――――――
二度目の投稿がまさかの三年後…だと…?
……気を取り直してもう一度。
初めまして! メルボウヤと申します。
冒頭にある通り、超個人的な理由でBW2はまだプレイしていません。と言うかBW以降、ポケモン関連に全く手を出していません(サイトは畳み、アニメもBW2からは見なくなり…あまり関わるとゲームをやりたくなってしまうので´`)。
今後何本かBWの話を投稿するのが当面の目標です。求ム…プレッシャー…!
この話は13年3月21日に、(三)の小猿トリオが旅に出た理由を話すシーン(〜〜勿論三匹は、同時にコクン! と頷いた。)までを故サイトに載せていました。切りが悪過ぎる。
実はポケスコ第三回のお題が発表された直後に書き始めた代物だったりします(始めから応募しない方向で。何故って絶対一万字内に収まり切らないんですTT)。完成するのが遅過ぎる。
絵もこれまた年代物ですが(11年10月30日作)折角なので一緒に。ええいもう、チミは何もかもが遅過ぎるんじゃっ(一人芝居)。
とにもかくにも…ここまで読んで下さり、ありがとうございました!*´∀`*
おまけ
・メイの名前は三つ子に倣い、イギリス英語でトウモロコシの『メイズ』から。私は三つ子ではコーンが一番好きです(何
・三猿がギフトパスを覚えられないなんて口惜しや…
・チェレンとベルが連れているお猿はヒウンジム突破後に初登場することから、それぞれ野生をヤグルマの森で捕まえた設定なのでしょうが、私の中ではあの通りです。これくらいの俺設定ですとまだまだ序の口レベルです←
・それよりデントがプラーズマーされてることに対する謝罪は無いのか(無いです)。
追記
この記事を間違えて(三)に返信してしまいました…以後気をつけます…!
怖いぞ。そんな作品でした。1個目の話からしてなんだなんだどうなるんだとなって、最後まで一気に読んでしまいました。語りが可愛いのもまたホラーですね。短めでさらっと読めるのにひたすらに恐ろしい話でした。
進化の石を三つの未来と表現しているのも好きです。
色違いであるポケモンはステータス画面で姿を確認したり戦闘に出したりした際に光るエフェクトが出るため、「光るポケモン」とも呼ばれる事がある。
ゲームでは第二世代から出現。
アニメでは無印編第21話から出現。
よく勘違いされるが、データ上では全てのポケモンに色違いが設定されている。
ただし配布ポケモンなど、野生で存在せず、卵を生まないポケモンの場合ステータスなどの値が固定されている場合があり、事実上色違いが入手不可能なポケモンもいる(例:セレビィ、アルセウス等)。
また、第五世代には色違いブロックルーチンによって色違いの入手が意図的に不可能にされているものもある。
色違いは、野生ポケモン以外にも卵から生まれたポケモン、かせきから復活させたポケモンでも出現する。
御三家の3匹や伝説のポケモンも例外ではない。色違いポケモンは進化しても色違いポケモンのままで、進化する事で色違いになったり、色違いで無くなったりする事は無く、これはメガシンカやゲンシカイキの場合も同様。
ゲーム中NPCが色違いポケモンを使用する事はほとんど無いが、トレーナータワーの一部トレーナーが使用する。また、バトルファクトリー等でレンタルするポケモンが色違いである事もある。
色違いである事自体は遺伝しないが、第二世代のみ親のどちらかが色違いの場合、色違いの判定に個体値を用いている関係から、1/64(1.5625%)という高確率でそのタマゴから孵るポケモンが色違いになる。
<色違いの概要。ポケモンWikiより抜粋>
+オッドアイは色違いになるか+
「そのウインディ、貴女の手持ち?」
ハニーブラウンのボサッとした長髪と、反対にしわ一つないパリっとした白衣。
首元の聴診器を見て、彼女がすぐに医者だとわかった。
「……そうだけど。」
「そう。綺麗な目ね。オッドアイか……珍しい。」
これも色違いのうちに入るのかしら、などと呟きながら、突然現れた女医者は、ウインディの顔をジロジロと見る。
これが金銭目的の連中や、単に見栄やら名誉やらで欲しがる輩だったら、ゴーリキーのばくれつパンチを問答無用で叩き込んでやったのだが、彼女にはただただ純粋に、子どものように興味を持ち、見つめるだけ。
久々に良心のある人物に出会ったと思いながら、横においてあった杖を手にとって、それを支えに立ち上がる。
横にいたゴーリキーが片腕で支えようと腕を伸ばしたのを手で制して、ゆっくりと彼女に近付いた。
「あなた、名前は?」
「え?私?クルミ。そこの医療センターで働いてんの。」
「ヘェ。医者なの、おねーさん。」
「おねーさんって……年変わんないでしょ?」
「これでもまだ21才なもんでしてね。私のこと、何才くらいだと思いました?」
くすくすと笑いながら、身分証明代わりにトレーナーカードを差し出した。
クルミと名乗った女医者は驚いた顔をして、失礼したわ、と素直に謝る。
気にしてませんよ、と返しながら、近づいてきたウインディの首元を撫であげた。
色違い。わかりやすく言えばアルビノ。
一部の人間には「光るポケモン」と言われる稀有な存在で、遭遇率はほぼ0に等しい
けれど、それより珍しいのが、このウインディ。
通常色のウインディと、色違いのウインディの間に生まれた女の子。
ジョウト地方のポケモンは、親のどちらかが色違いだと、子どもにも色違いが遺伝しやすいというデータがあり、実際にそのデータは常識化しつつある。
だけどこの子は"特殊"だった。
この子の両親のうち、母親の方のウインディが色違いで、体の色もさることながら、目の色も綺麗な金色だ。
そしてそんな母親と通常の父親との間に生まれたこの子。
タマゴから孵ってすぐに、母親の方のトレーナーさんが気づいた。
「体は通常色、一般的だ。でも目が左右で違う。」と。
そしてそれは、この子が孵ってすぐ、世間様に注目されて大ニュースになりかけた。
そして母親側のトレーナーさんは、疲れかけのこの子や親が大事に至る前に、オッドアイとして生まれたこの子を私に預けてきた
「"色違い"としても"通常"としても中途半端なこの子を"普通に育てられるトレーナー"は、きっとあなただけよ。」
と、大見得切って言われた日は、1人の人間として惚れかけた。
恋愛的な意味ではなく、懐の深さ的な意味で、だ。
そんなことがあり、私の元にやってきたこのウインディ。
オッドアイと大きな体躯を除けばとても女の子らしいむじゃきな子だ。
足を悪くする前は、よくこの子といろんな場所を駆け回って遊び、足を悪くしてからはその背中に乗っていろんな場所を旅してる。
そしてそのたびに、このオッドアイを珍しがられている。
今はアサギシティで落ち着いて生活をしているが、また少ししたら、旅に出てもいいかもしれない
「綺麗な色ね。ジョウト生まれ?」
「はい、この子の母親は色違いですよ。」
「そう、遺伝なの。しかも特殊中の特殊じゃない。」
今、目の前にいる彼女もまた、この子の目を珍しがっていた。
そして医者だといったその人は、慣れた手つきでこの子が一番、喜ぶところをすぐに見抜いて撫でつつほのおタイプならではのその暖かさを噛み締めている。
「あなたのその目は親譲りの大切でとても綺麗で、そして素敵な目よ。
大事に大事にしなさい。ね?ウィンディ。」
「さすがドクター。この子が喜ぶ場所をすぐ当てるなんてね。」
「あら、ありがとう。そっちのゴーリキーもなかなか強そうね。
片腕なのが惜しいわ。義手でもつける?」
「あぁ……こいつはそのままでいいんですよ。
何度言っても聞きやしないんで。
それより仕事はいいんですか?」
「え?……あぁっ!?」
だいぶここでゆっくりし過ぎたのか、彼女は慌ててなにやら名刺を差し出した。
彼女の名前と連絡先のようだ。
何かあったらここに連絡してということだろうか
それじゃあまたね!と言い残し、クルミと名乗った女医は大慌てで去って行った。
こっそり抜け出していたらしいマニューラが、やれやれとでも言っているのか、ため息をついているようにも見えた。
「なんというか……突風みたいな人だな………。」
突然来たと思ったら、突然いなくなっちゃったね。
その一言に、ウィンディとゴーリキーも、それぞれらしい反応を示すだけで、それ以上特に何もなかった。
「ノアー、宅配頼むわー。」
「あ、はーい。」
店長に呼ばれて店の奥へ入る。
店長は荷物をゴーリキーに渡して、届け先のメモを私に渡してきた。場所はエンジュシティ。
場所を確認して、店先で待っていたウインディの背中に腰を下ろした。
「エンジュまで、ゆっくりお願いね。」
「ガウ!」
元気よく返事をして、ウインディは歩き出す。
ゴーリキーが荷物を抱えながら着いて来るのを確認しながら空を見上げた。
アサギの空は、今日も快晴です。
.
11月23日で行きます。
ほかの方、ご予定はいかがですかー?
| タグ: | 【鳥居の向こう】 |
●全体
【No.017】
さて鳥居の作戦会議だが
本は「春コミくいらいに出せればいいなーと
で、大幅に改稿を予定してるのが災い様と冬を探しての二つ
某月某日午前二時七分、とある山中の道にて は少し 言い回しというか 別冊を意識して変える程度
残りはまあ気になる表現を各自変えていく程度でいいでしょう
手伝ってほしいのは 誤字脱字発見ですね
ただこれは原稿できないと意味がないw
後参考に読んでる本があれば教えてください できるだけ私も読みます
【久方】
図解雑学シリーズのこんなに面白い民俗学
境界の発生
【No.017】
特に希望がなければこっちから改稿方針を打ち出してそれに従って直してもらうか
ただ意に沿わないのは言ってね
【砂糖水】
新田次郎の強力伝途中で挫折(
【No.017】
じゃあ砂糖水さんそれ読み終わって(
あと たかひなさんは 体裁ととのえな
●災い様の編集方針
【No.017】
結構前の発言なので掘り返さないといけないんだが
災い様の場合はちょうど日本が近代化して言って神様どうこうの意識が薄れていくような背景がほしいとか言った気がする
でないと くーうぃさんの言うように山伏がボコられる(
ただ日本って戦後すぐなんかはまだ 狐憑きがどうこうとか言ってたくらいだから どういう設定がいいか
電気が通った とか 電話が通った 街灯がついた なんてエピソードを織り交ぜたいよね
主人公のうちは割と金持ちで電話がとおったのかもしれぬ
後はとなりの村で土砂崩れがあったとかあるいは何らかの公害とかそういうことがあって周辺住人が不安だといいよね
そのタイミングでこいつのせいだ!って話になったらみんな信じるかもね
【音色】
もっと主人公の周りの環境(舞台設定なり風習なり)をゴリゴリ書いた方がええ感じなんですかね
周りのフラストレーションが一気に爆発
【No.017】
ただゴリゴリ書いた結果、本来のシンプルな良さが失われる可能性もあるんだよね。
なのでやってみて違和感あれば元に戻すことも視野に入れたほうがいいかもしれぬ
【音色】
シンプルっつーか、中の人がその辺全く調べずにただ勢いだけで捻りだした結果があれなんですけどね
(かき集めた資料羅列するだけになるようなら削ると
【No.017】
イメージとしては しずまりたまえー だったのが 俺らには文明がある災いなんかやっつけてしまえ!
みたいな変化が出せるといいかなーって
【音色】
あー成程…科学の勝利!!っていう空気創る感じが良いのかな
【No.017】
そんな感じにもっていければとおもっている
【音色】
ウィッス了解
【No.017】
とりあえずプロット見たいのを考えてみるのでできたら渡すね。
【音色】さんもこんなエピソードがあるといいんじゃないかっていうの何か上げておいて。
【音色】
了解です ちと何か捻りだしてみましょう
【No.017】
あれだな 日本における電話と電気の普及ってどんな感じだったのか
ネットレベルでいいから調べておいて
【音色】
了解しました
どっかやることメモっとこ
【No.017】
あるいは医療の普及もあるのかもな 結核が治せるようになったりとかな
じゃあ災い様はそんな具合で
●冬を探してのネタ出し、アイディアなど
【No.017】
問題は冬を探して
砂糖水さんの中では今どういう流れになってるの?
【砂糖水】
リョースケとコハルちゃん出会う
湖観光する
山に登ろう(その前にコハルちゃんちで装備整える)
登山
一晩お泊り
冬の神さま現る
負ける
【No.017】
リュースケめ。。。。コハルちゃんちに侵入したのかよ
【砂糖水】
お母さんがパートでいない間に!!(((
登山であれやこれやと二人が離す内容と順番どうしようか迷ってるのが一番進まない原因ですかね
おじいちゃんの装備をかっぱら…もとい拝借
【No.017】
リュースケエエエエエ!!!
【砂糖水】
リョースケでし…
【No.017】
俺はリュースケを許さない
ちなみにおばあちゃんって どういうシチュエーションで神様を見たのかね
【砂糖水】
ええと鳩さんから言われておばあちゃんからおじいちゃんになりました
おじいちゃんは狩りをしているときに見たそうです
【No.017】
伝説のマタギか
【砂糖水】
伝説wwwwwww
【No.017】
ちなみに狩りって何を狩るの?
【砂糖水】
さらっと流してしまったのでまだ考えてなかったです
【No.017】
リングマでも撃ちに行ったのかな…
穴もたずのリングマかな… 身体が大きすぎて冬眠できない熊は凶暴らしいよ
お供に猟犬くらいいたかもねえ
【砂糖水】
お供はマニューラさんでもいいかなーとふわっと
でもそうか、匂い追うならわんこか…
【焼き肉】
雪ってことでオドシシなんかも合いそうな気も>獲物
【砂糖水】
おじいちゃんのポケモンは人に預けられてて連れて行けないという設定(まだそこまで書けてない
【No.017】
寿命で死んでる可能性もあるわな
猟犬が死んじゃってからおじいちゃん元気ない 、とか
【砂糖水】ああああああああああああそれいいですね!
がっくりきたところに病気で入院
なるほど!!!!!!!!!
【焼き肉】
ガーディなんかは暖もとれて猟犬にもできて一石二鳥そう
【No.017】
後ふと思ったんだが
お年寄りってさ、やっぱみんなで集まって昔の武勇伝話すやん?
その時にフリーザー様の話振ったらさ、 おじいちゃん以外見たことないもんだからみんな信じてくれなくてがっくりくるやん
しかも一緒に見たポケモンが死んだとなったら…
で孫にぐちると
【砂糖水】
うおおお
ああああ
んなあああああ
【No.017】
これで動機は十分ですね
【砂糖水】
ありがとうございます!!!!!!!!!!!
【No.017】
あともしかしたらコハルちゃんは何度かトライしてる可能性あるんじゃないかな
ところで今グーグルマップ見てるんだけど エイチこ ってどの湖なんだろうなぁ
【森羅】
クッチャロ湖だそうですよ。>はとさん
【No.017】
把握>食っちゃろ湖
【砂糖水】
ひい
【No.017】
というと リョウスケ達が登った山は
サマシキリ山とかそのへんかもなぁサマシキリ山 トキタイ山
おじいさんはどういう状況で冬の神に会ったんだろう?
【砂糖水】
未定です!(
【あきはばら博士】
人が踏み入れない奥地に行ったら、たまたま冬の神に会ったのでは
博士冬の神様はあの場所を守っているのですから、パトロールとかしているだろうし
【No.017】
まず コハルちゃんは山の歩き方に関してはおじいさんから習っててある程度わかっている
で 冬の神さまに会ったシチュエーションも結構くわしく聞いている
ただ出会った地点についてはじーさんも迷っていたから曖昧 もしくは場所を勘違いしている
コハルちゃんは冬の神様が見たくて過去に何度か挑戦しているが会えていない
リュースケが参加した事でなんらかの条件が満たされるか コハルが気づいていないことにリュースケが気づく
【門森 ぬる】
未だにリュースケと呼ばれるリョースケ
【砂糖水】
まあ一応、部外者であるリョースケがいることの意味はあるようなないような
【No.017】
で かつての仲間も猟犬も死んじゃってもう語り合える人がいない
少しボケも入ってきてもしかしたらあれは夢だったんじゃないのかなんて言い出したのかも
一人死んで 一匹死んで 最後の一人も忘れようとしている。
コハルちゃんが「みんな忘れてしまったから」というのもそうなると結構悲壮感が出るよね。
コハルちゃんは直接見てないけど最後の1人になりつつあるんだわ。
爺さんがじゃなくてコハルちゃんがだよ。
おじいちゃんを元気づけたいのももちろんだけど、根底はそういうことなのかもね〜
山小屋でさ リョウスケと泊まる時「私わかったの。
おじいちゃんを元気づけたいのは本当だけど、本当はひとりになりたくなかったの」とか言わせると私的には燃えます
【new】
割と山のぼりだと、ひとりぼっちとかひとりきりみたいな心境になるシチュエーションとか作りやすそうですね(涙)
【No.017】
まとめると
・おじいさんは 人〜人の仲間と自分のポケモンとで冬の神様を見ている
・コハルちゃんに山のぼりを仕込みながらよくその話をしていた
・おじいさん「冬の神の伝説」自体は自分のお母さんあたりから聞いていてそれも含めて話している(アイヌの末裔か何かなのかもしれない)
・やがてじいさんは骨折か何かして山登りは引退
・かつての仲間と冬の神の事を語ったりもしていたが、仲間も老衰で死に、相棒のポケモンも先立ってしまった。
・仲間もポケモンも死んだ今、冬の神の事を話してもコハル以外は誰も信じてくれない。
・そのうち自身もボケが入ってきてあの頃の事は夢だったんじゃないかと言い出す。
ただボケに関してはむしろ過去の記憶がリピートされるみたいなので、再考の余地あり。むしろその中からヒントが出るかもなぁ。
このへんの感覚はペコロスの母へ会いに行く を読んだほうがいいかも
おじいさんは昔の記憶の中で遊んでいて、何度も冬の神様や自分の友人に会ってるのかもしれぬ
そうなると直接見てないコハルは置いてきぼりなので、ある意味仲間外れという事ですね。
そして爺さんがしねば冬の神を知るたった一人になる。
【あきはばら博士】
私としては冬の神に会うための特別な何かは用意しなくていいと思います
すぐそばにいるけど見えない神という感じで
あまり、おじいさん関連を掘り下げてしまうと、コハルとリョースケの話じゃなくておじいさんの話になってしまうだろうし
博士野生のポケモンが凶暴かつ年中豪雪で、人間が立ち入ると生きて帰って来れないエリアがあると思う。
そこに遭難などで立ち入った時に、冬の神が「帰れ、ここはお前達の来る場所ではない!」と追い返したとか
【No.017】
今は考察してるだけなのでこれを全部盛り込めとは行ってませんよ
【砂糖水】
書いた話は一つなのに読む人によって解釈とか違うのってすごい(小並感
【殻】
おじいさん掘り下げるなら、冬の神っていうあくまで神話、伝承が失われつつあるって部分と、
昔話ではなくておじいさんがそれらしいものと接触したらしい、
本当にいたかもしれないっていう部分とは混同できないような
【砂糖水】
冬の神はあくまで伝承であれはただのフリーザーですよ
【No.017】
ああ、つまりただの昔話じゃないもん!本当にいるんだもん!てなかんじか
【森羅】
ふと思ったんですけど、リョースケ自身が冬の神の出現条件になってもいいんじゃないでしょうか。
フォルクローレの記事的に「部外者排除」の感じで
【No.017】
あああああいいねそれ!
つまり朝廷からの侵略者なんだ
【砂糖水】
りょーすけはキッサキから見たらまれびとなんですよね…
【No.017】
じいさん、シンオウの外の人と行動していた?
いや今私陣割と侵略者そうでないを見分ける何かがあって・・・みたいなのかんがえてたから
こううおおおってなったわ
リョウスケが山に入ったらなんか吹雪すごいぞ! でも抜けたら…みたいな
【砂糖水】
あーまいがー
おーまい
フリーザーはただのフリーザーです…何も特殊能力ないつもり…
【森羅】
じゃあ縄張りに偶然入り込んでしまった感じが一番正しいんでしょうか。
【砂糖水】
私のイメージでは
【No.017】
小説的にしっくり説明できる法を採用すればいい
【砂糖水】
はあい
【No.017】
縄張りに入り込んだだけだと山に入ってたコハルと爺さん一回くらいあってそうだから、
リュースケが加わったことで何かがあったと考えるのが自然ではないか
たとえば サクラがおいしそうだった とか。そんなん
【砂糖水】
サクラああああああああああああ
【あきはばら博士】
リョースケ君がシンオウに生息していないポケモンを連れているならばいいんだろうけどなぁ
ギャロップはいるものね
【殻】
冬の神さまは若い男の子が大好きなのでリョウスケくんをつれていこうとするのだ
【No.017】
そっちwwwwww
ポケモン「フリーザー様 あなたごのみの若い男がきました」
【No.017】
あるいは鈴かビードロか
【砂糖水】
あんな低温下でビードロ吹いたら割れそうな気しかしなかったので鈴にしましt(
【あきはばら博士】
ポケモンを近寄りにくくなる【音色】ってどういうものかは知らないけど、
そんなものを鳴らしながら一日中歩いたのだから、野生のポケモン達の報告か何かで、
部外者が来たのだと気づいたのだろう。不審な者が踏み込んできたのだから
始末する
【殻】
組織化する冬山
【No.017】
ポケモンよけだけどフリーザー様はよんじゃうのかも。あるいはあまりに不快だからとめにきた、とか
【new】
リアル山登りだと、熊よけのスズを持ち歩いて登山するっていう話きいたことあるので
【あきはばら博士】
ビードロはシンオウには存在しないもんね ホウエンにしかないし
【new】
他の地方だとその鈴は役に立つけど、ここでは逆効果、みたいな?
「山菜採り山歩き用熊ベル」なんというものが売ってるのか(涙)
【ピッチ】
どうもこんばんは、失礼します。シンオウの冬山と聞いて。
効くかどうかは実際クマ次第です。<熊ベル
臆病なクマだと変な音がするので逃げ出しますが、好奇心旺盛なクマだと変な音に嬉々として近付いてくるとのこと。
【きとかげ】
最近のクマは熊よけに慣れちゃって、空のペットボトルべこべこした方がきくとかなんとか
【殻】
くま「きょ、きょうのところは勘弁してやるよ……」
【あきはばら博士】
「まさか本当に、会えるとは思いませんでした。なんで私たちの前に現れてくれたのでしょうか?」
「さっき、ふと気づいたのだけど。もしかして、これじゃないかな」 リョースケが指し示したのは黒い鈴だった。 「鈴?」
「ああ、ポケモンを近寄りにくくなる【音色】ってどういうものかは知らないけど、そんなものを鳴らしながら一日中歩いたのだから、野生のポケモン達の報告か何かで、部外者が来たのだと気づいたのだろう。不審な者が踏み込んできたのだから、ここのキッサキの地を護る者として、追い返そうとしたのかな」
「あっ…… そうか」
たとえ人が忘れてしまっても、冬の神様はいつでもどんな時でも、このキッサキの地を守っている。キッサキの人間だけじゃない、このキッサキのポケモン達や、大地すべてを守っているのだ。
【森羅】
おじいさんやコハルちゃんが入らないような雪深い時期
(そんな風習があるのかわからないですけど風習的に入れない時期など)に
そのとき初めて入った設定にするとか。
●禍津水神と皆殺し
【あきはばら博士】
そういえば、鳥居の作戦会議とは聞いたものの、なかまづくりに関しては加筆などは無いのでしょうか
私は文章力も表現力も底が浅い者なので、推敲していただけるならば甘えたいところですが
【森羅】
あ、禍津水神の方は
【No.017】
優先度的に 冬と災いが最大の課題なので
もちろん改めて読んでみておかしいところは言いますけどね
【あきはばら博士】
博士禍津神というのは、ポケモンで言うとギラティナレベルの神様のはず。
キュウコンさんはきっとそれを知っているでしょうから、
進んで自分をギラティナだと名乗るのは恐れ多いでしょうね
【森羅】
ちょっといろいろ調べてるんですけど、どうも禍津神って一人の神様じゃないらしいんですよ。
というか神様じゃないみたいで。
【あきはばら博士】
たしか アマテラスやスサノオが生まれる時に出てきた、影の部分ですよね 闇スサノオみたいな
キュウコンとかを表す単語としては「鬼」と呼ぶのが適切かな
鬼は”人間の手で退治できる”存在ですし
【森羅】
八十八禍津日神だったですかね。これ自体がもう「たくさんの神様」を指すようでして。
ただ、鬼としちゃうとまた雰囲気かわってしまうのでどうかなと。
ただ、「禍津神」という表現を普通名詞として使用している部分があったりもしますから、そのあたりも微妙でして。
---閲覧中のケンタ(Win/Chrome)さんが入室しました。---
【あきはばら博士】
キュウコンさんとしては自分を「禍津神」と呼んだり自称することに対してかなり複雑で、抵抗があるのだと思う
閲覧中のケンタ
どっちが正しいとは言えないけど、雰囲気でいいと思う。
現実の世界と同じような神話を持った、別世界の物語だから。それがフィクションの醍醐味。
【森羅】
はい。だからキュウコンは自分を「禍津神」とは呼んでいません。
あくまで「お前がそういうなら」の前提付です。
【閲覧中のケンタ】
Trick or trick!(菓子なんかいるか! 皆殺しだ!)
皆殺しにされたので会議終了。
当分の目標
●冬を探して 編集方針まとめ
●災い様 編集方針まとめ
課題図書
●強力伝(優先)
●図解雑学シリーズのこんなに面白い民俗学(できれば)
●境界の発生(できれば)
●ペコロスの母に会いに行く(砂糖水さんに読ませたい)
調べること
●電気の普及、電話の普及
語彙力があって羨ましいです。
ギャロップの描写すごいっすね。
ライカは勇敢ですね。
人間たち意見が対立して捕まえるの失敗しそう……
硬派な文体なので書き上げるのが大変かもしれませんが、続きを期待してます!
どうも、こんにちは。
読ませていただきました。
輪廻転生が本当にあるとしても、やっぱり人間の姿で生まれてくる確率は低いですよね。
ポケモンだったらまだいいですが、ポケルスとかだったら最悪ですねw
転生を題材にした小説は、なろうの一次小説なんかでは良く見られますが、ポケモンでは(ポケダン以外で)あまり見ないので、どうなるか楽しみであります。
トキワタウンの老人は前世何のポケモンだったのか、気になる所です。
「よし、今日もいい感じ」
いっぱいに並んだ鉢植えの様子をチェックして、私は思わずガッツポーズを作る。
私の仕事はメンタルハーブの育成だ。最近はこの植物に優しい天気が続いていて、とてもよく育ってくれている。小さな庭での副業とはいえ、それなりの数を育てているためこうして成果が出るとやっぱり嬉しい。
「おはようございます。おお、綺麗に育っていますね」
隣の庭から、お隣さんが顔を出して挨拶してくれた。私も笑顔で返す。
「ありがとうございます、先月は気温が不安定でしたからどうなるか心配でしたけど、無事に育って安心しましたよ」
「この家に越してきてから、僕のポケモンたちもみんな穏やかなんですよ。前は怒りやすかった子も、とても優しい雰囲気になって。バトルの間に使わなくても効果ってあるんですかね」
「そうなんですか! それは聞いたことありませんでしたけど……確かに、そういうのもありそうですよね」
「やっぱりいい匂いですから。さて、僕もみんなを散歩に連れて行かないと」
それでは、とお隣さんが家の中に戻っていく。ポケモンブリーダーのお隣さんは少し前に引っ越してきた方で、いつも沢山のポケモンたちを散歩させているのだ。
と思った矢先に早速、10匹くらいのポケモンを連れてお隣さんが門から出てくる。わちゃわちゃと群れているラルトスの可愛さに目を細めた。よく見てみると、二匹ずつでくっついているようにも見える。
「こんなちっちゃいのに、もうラブラブなんですねえ」
その様子が微笑ましくて、私の家の前を通ろうとしたお隣さんに声をかける。すると彼は苦笑して、「やだなあ」と手を振った。
「こいつらみんなオスですよ。ホウエンでメガエルレイドも確認されたから頑張って育てないと」
いずれは綺麗なメスとお見合いさせることになるし、と言い残してお隣さんが散歩に出て行く。そうだったのか、恥ずかしいことを言ってしまった。ポケモンの見た目には疎いもので、オスメスの違いなんてニドランかケンホロウか、カエンジシあたりしかわからないのだ。
まあもう過ぎたことだし、と気を取り直して、ジョウロの水を足した。落ち込まないのが私の取り柄だ。ふう、と息をついて見上げた空は、青く澄み渡っていた。
今日もいい天気、メンタルハーブはよく育つ。
| タグ: | 【一粒万倍日】 |
お知らせ
今月の一粒万倍日は以下の通りです。
17(水)22(月)29(月)
今回を逃した方は是非次の機会にどうぞ!
もちろん来月でもいいのよ?
ここは酷く煩かった。そして、かなり不穏だった。
酷く煩いこの音は、ここにある機械が放っている。一つではない。たくさんの機械が音を出す。指揮者なんていないから、それぞれ思い思いのままに、ひたすら大声で歌っている。
機械の前には椅子がある。必ず丸い椅子がある。人間達はそれに座る。彼らの目線は機械だけ。この機械はスロットと呼ばれる。スロットにはリールがある。三つのリールはぐるぐる回り、ボタンを押すとぴたっと止まる。
ここに通う人達は、誰に話す訳でもなく、個々の作業に熱中する。ごく平凡な言い回しだが、何かに取り憑かれるように。彼らはここに来るときに、いくらかのお金を持ってくる。たくさん持ってくる者もいる。オニスズメの涙ほどしか持ってこない者もいる。彼らは端にあるカウンターに行き、予め所持金をコインに替える。
人間はコインを何枚か、投入口に入れていく。投入口は小さくて、一枚ずつしか入れられない。入れたコインを"BET"すると、リールを回すことができる。一枚ずつBETするのではなく、三枚同時にBETする人の方が、遥かに多いと思われる。人々は、ハイリスク・ハイリターンを求めている。
ここには集まる人々は、だいたい常連客が多い。一度ここへ来た人は、やがて顔をまた見せにくる。十代半ばの男の子が多い。いや、比率で言ったら中年の男性が一番多いが、こんな不穏な場所にしては、若い人が多いという感じだ。そして、今のような平日の昼間に至っては、圧倒的に少年の方が比率が高い。
現在この席に座っているのも、まだ将来長そうな若い人間であった。腰には赤色のボール四つ、青色のボール二つがある。スーパーボールを持っていた。平均よりは上のトレーナーであると推測できる。
ここに来るような人々は、大抵顔がやつれている。彼はそうでもない。少々疲れている感じはするが。どうやら、スロットは初心者のようだ。コインを一枚ずつBETしている。
スロットに装着されている、黄色いスタートレバーを下げた。するとぐるぐるとリールが回る。リールには、数個の絵柄が描かれてある。(通常これは"目"と呼ばれる)これが横、あるいは斜めに揃うと、コインが貰える。貰える数は、揃った目によって異なる。
彼は左から順番に、三つの赤いボタンを押していく。
いよいよ、"僕達の"賭けが始まる。
彼は特定の目を狙わない。適当に素早く押すだけだ。初心者ならば仕方がない。全てのボタンを押し終えたとき、絵柄が整列していることはなかった。
何も呟かない。黙って、次のコインを投入。先ほどと全く同じ。適当にボタンを押していく。そしてやっぱり揃わない。
五十回は繰り返した。手持ちのコインが減ってきた。果たして何回か目は揃った。しかしチェリーやルリリのような、あまりコインが貰えないものばかり揃った。徐々に彼の顔に、苛立ちが見えてきた。
彼はまたコインを投入。リールを回す。
揃わない。
そのときであった。彼は小さい声で、一独り言を言った。
「はあ」
更に何回かリールを回す。しかし揃わない揃わない。チェリーすらも揃わない。あるとき、彼は再度独り言を放つ。
「ああ」
更にリールを回す回す。コインは残り一枚となった。名残惜しそうにBETする。彼は今までと異なった。ゆっくりとボタンを押している。しかし、初心者はリールの回転についていけない。結果は同じであった。
「なんだもう」
最後の独り言。彼は椅子から立ち上がる。そして建物から出て行ってしまった。トレーナーであるならば、帰る場所などどこにもない。椅子から立ち上がる瞬間、彼は実に悔しそうな顔をしていた。こぶしを固く握っていた。この様子だと、またここにくる。悔しさは人を、再びこの場所に引き寄せる。
「また僕の負けですね」
僕は、思わず苦笑いを浮かべた。
「惜しかったね。でも大丈夫、次があるよ」
セブンさんは僕を励ました。数字の"7"である体を、ピンと張ってみせた。心なしか、その赤い体は、日に日に輝きを増しているような気がする。
「僕も、まだまだなんですかね」
「確かに、そうかもしれない。でもね、君は才能がある。何度も言っているだろ。ハスボーは目の輝きが他とは違うって」
ネガティブな発言をする度に、セブンさんはこのように、暖かみのある言葉で励ましてくれる。才能があると。そのうち報われると。そんな言葉で撫でられると、少し照れてしまうと共に、天にも昇る気持ちになる。だから、また頑張ろうと思える
一ヶ月前に僕は、スロットの絵柄になった。そして僕はこのように、セブンさんと毎日賭け事を行っている。賭け事のルールはとても単純。このスロットの席に座った人間の、独り言の種類で勝ち負けが決まる。まず、複数ある独り言が書かれたカードの中から、好きなものを選ぶ。カードに書かれたものと、同じ独り言を人間が放てば、得点が入る。「はあ」、「ああ」、「ふう」。独り言が、この三つの内のどれかであると、セブンさんに一点入る。「しゃらっつふうううう」、「せっらにっわあ」、「ラペス」、「さふぁいん」、「のだっすう」。この五つの内のどれかであると、僕に一点入る。一点入ると、相手から百円貰えることになる。例えば今の場合だと、「はあ」と「ああ」が当たったから、僕はセブンさんに、二百円を支払わなくてはいけない。僕の方がカードの数が多いのは、いわゆるハンデである。ハンデを与えてくれる、セブンさんは親切だ。けれども、僕に得点が入ったことは、一度もない。
それでも。
「最初のうちはね、みんな全然駄目だったんだよ。だけどあるとき突然、ぐいーんと伸びる時期があってね。そこからはもう私はお手上げだ。負けっぱなしだよ」
そう。僕はまだ一ヶ月目。未だピカピカのルーキーだ。僕意外にも、この賭け事をセブンさんと行っていた者は、結構いるらしい。そしてみんな、途中から勝ち続けていったみたいだ。だから僕だっていつか、きっとそうなる。
それに僕は、一生懸命賭けで勝とうと、頑張っている。努力は必ず報われると、僕の主人も繰り返し言っていた。
「どうする? 今日はもう終わりにする?」
この賭けは結構疲れる。"スロットの目"として、ぐるぐる回っているだけでも、疲労が溜まっていく。そこに更に、人間が何を発するかに神経を注ぐという作業を付加させるのは、肉体的も精神的にも体力を消耗する。にもかかわらず、僕はまたやりたいと思ってしまう。次こそは当たるのではないか、そんな期待があるのだ。
「後もう一回だけ、付き合って貰ってもよろしいでしょうか」
すると突然、セブンさんが高らかに笑った。その笑いに、嫌味は感じない。むしろさわやかである。
「もしかして駄目ってことですか……?」
「違うよ。ハズボーもいよいよ、根性がついてきたなあって」
「根性、ですか」
「君は私が思っている以上に、大きく成長していた。陽の目を見るのも、近々かもしれないね」
こんなに嬉しい気分になったのは、初めてだ。陽の目を見るのも近い。いよいよ僕が、報われるときが来るのか。
「それじゃあ次のお客がくるまで、カードをどれに入れ替えるのか、決めようか」
そうだ。言い忘れていた。挑戦者である僕は、ゲームとゲームの合間に、手持ちのカードを、自由に替えることができる。
「これを選びます」
僕は「せっらにっわあ」のカードを捨てた。代わりに「ノベスノベスノベス」を選んだ。「せっらにっわあ」は、人間が無意識に発する言葉としては、少し言い辛い気がするから、今後も当たらない気がする。一方で、「ノベスノベスノベス」は言いやすい。加えて、"ノベス"を三回繰り返すことにより、力強い雰囲気を感じさせる。これから僕は陽の目を見る。そのためのラストスパートで、この力強さというものは最も重要であるだろう。そんな思いから、僕はこれを選んだ。
「おい何してるんだ! 早くこっちへ来いや!」
突然、セブンさんが怒鳴り声をあげた。反射的に、僕はびくってしてしまった。セブンさんが体を向けた先には、果実が二つくっついた一つのチェリーがいた。チェリーは何やら、体を少々傾けながら、一方の果実を地面から浮かせ、こっちへ向かって走ってくる。
「すいません。床を舐めながら歩くのが、難しくて」
「もたもたすんなよ! だいたい、床だってちゃんと舐めてねえだろ! 分かるんだぞ舐めた跡で。ほら見ろ! あのへんで一旦サボっただろ」
「すいません」
「すいませんじゃねえよ! 許してください言うこと聞きますからって、お前がそう言ったんじゃねえか!」
「だってこれ以上舐めて走ると果肉が」
「言い訳をするな!」
「……はい」
「もういい。肩揉んででもらおうかと思ったけど、今それやられても困るから帰れ。今ね、新人君と賭けやってるの。邪魔だから。ちゃんと床舐めながら帰れよ」
言われた通りチェリーは、先ほどと同じように体を傾けて行ってしまった。
「ごめんね、何回も怖がらせちゃって」
セブンさんは、再びこっちを向いた。優しい声に戻って、僕は心底ほっとした。セブンさんはなぜか、チェリーにはやたらと厳しく当たる。
「おっと次のお客が来たようだ。よっし、所定の位置に戻ろう」
僕達スロットの目は、自由にスロットの内部をうろつける。もちろん、目の前に人間が座っていない間だけだが。こんなふうに、セブンさんと賭けもできる。次のお客が来る前に速やかに、所定の位置に戻るのは少々大変。ちなみに、別のリールに移動はできない。"7"の目は三人いる訳だけれど、そのうちの一人としか、僕は合ったことがない。
次のお客が椅子に座る。また若い男性だ。しかし、さきほどの人間とは違い、明らかに顔がやつれている。しかもこの顔には見覚えがある。この人は、何回かこの席に座っている。
彼はコインを投入。BETを始める。やはり、この人は初心者ではない。三枚同時にBETした。しかし、彼はスロットの目をよく見てボタンを押す、などと言うことはしなかった。まだそこまでの、段階ではないのか。
そして、やっぱり揃わない。もう一度、彼はコインを投入する。それでも駄目。あっと、早くも彼の口が、開こうとしていた。流石、やつれている人は違う。
「ああ」
その後も、何回もリールを回す。二十回目くらいだろうか、彼は大当たりを引いた。"7"を揃えたのだ。"7"には、セブンさんのように赤いものと、青いものがある。赤色、もしくは青色のみで三つ揃えると、コインを三百枚貰える。赤青混合で揃えると、九十枚貰える。彼は、青一色を斜めに揃えたから、三百枚のコインを手に入れられた。彼の表情はご満悦である。
しかし、その後は全く調子が悪い。せっかく三百枚当てたのに、その分は全て消えてしまった。彼の顔に、徐々に苛立ちが舞い戻ってきた。そして、このように呟いた。
「ああ」
更に数回リールを回す。今度は、赤青混合で横に揃えた。しかし、九十枚のコインでは、大当たりとは言えないだろう。そこからはさっぱりだ。彼はもう一度呟いた。
「ああ」
どんどん不調になっていく。もはやチェリーすら当たらない。幸運の女神はどこへやら。彼は再び独り言。
「はあ」
もう、リールから手を離した。投入したコインを戻すボタンを押した。彼は椅子から立ち上がった。僕達の賭けはここで終了だ。
今回も、駄目だった。いや、今回は輪をかけて酷い。四回とも、セブンさんが当てた。こんなのは初めてだ。一方で、当然僕は一つも当たらない。
もう、駄目なのかもしれない。
不思議なものだ。さっきまであんなにやる気だった。一回でも、えげつないほど打ちのめされる。それだけで、僕はこんなに落ち込むのか。心変わりしてしまうのか。
「どうした? 元気ないな。一回負けただけじゃないか」
「すいません、もう、いいです」
「え」
「もうやめます」
「これ以上続けても、意味がないと思います」
「そっか。じゃあ止めよっか」
「……」
心のどこかで、止めてくれることを期待していた。セブンさんに、前のように暖かく励ましてくれることを、待ち望んでいた。けれど、セブンさんの口から出たのは、そんな都合の良い言葉じゃなかった。
「薄々気がついていたよ。もうハスボーはいくらやっても伸びないって」
「でも、さっきは才能があるって」
「ハスボーのやる気を引き出すために、今までおだてていただけだ。そんなことにも気がつかないなんで、お前は愚かだねえ」
おだてていた。そうだったのか。なんとなく、そんな気もしていたのだ。僕は褒められると伸びるタイプだと、自分で評価している。だからセブンさんは、思ってもないようなお世辞を、僕に繰り返し唱えていたのだ。
「もう止めだ止め、止めよう。やる気ないんだったら帰れ」
ぴしゃり、という音がした。セブンさんに表情などない。けれど、口調と体の傾け具合で、本気で怒っていると分かった。
もう駄目だろうか。せっかくここまでやってきたのに。こうやって全てを、無駄にしてしまう。なんと愚かなことか。そうだ、セブンさんの言う通り、僕は愚かだ。
「残念だったな。主人を救ってやるというお前の夢も、どうやら敵わなかったようだ」
セブンさんが、こっちに背を向けながら、小さく呟いた。それを聞いて僕は、何故こんな賭けをやっているのか、その理由を思い出した。
僕は、堕ちた主人を救うために、賭け事をやっていたのだ。
主人は、トレーナーとして旅をしていた。キンセツシティから旅立った。
しかし主人は、全然バトルで勝つことができなかった。バトルは負けると、相手にお金を払わなくてはいけない。所持金の半分も。お金がないと、ポケモンを捕まえるための道具が買えない他、食料だって買い揃えられない。所詮この世は、お金が全てである。お金がないと、生きていけない。弱肉強食の世界であり、勝ち続ける人しか生き残れない世界。負けた人は、後悔の渦に飲み込まれ、やがてどこかへ去っていく。
主人が勝てない理由は、至極単純なことだった。
ポケモンジムは本来、トレーナーにとって鬼門になるはずである。しかし主人にとって、そこは難しくなかった。むしろ、一般トレーナーや野生のポケモンの方が、遥かに苦戦した。
ジムリーダは、挑戦者のレベルに、自分のポケモンのレベルを合わせてくれる。バッジ一つしか持ってないなら、弱いポケモン。全て持っているなら、一番強いポケモン。使い分けてくれる。それは、そういう決まりだからである。どの町から旅立った人にも、平等になるように、決して高すぎる壁にならないように、そう決められている。
しかしながら、野生のポケモンは別だ。トレーナーのレベルに合わせたポケモンのみが、草むらから飛び出してくるなんて、そんなご都合主義なことはない。
基本的に、一つの草むらに、同じ程度の強さのポケモンが集まる。その草むらの中に、強さの格差があるならば、強いポケモンが弱いポケモンを、追い出してしまうからである。
主人が旅立つ、スタート地点であったキンセツの周りには、初心者トレーナーでは勝つことが難しいレベルの、野生のポケモンがわんさか生息していた。ヒワマキシティ周辺等と比べれば、たいしたことはないらしいが、それでも、かなり厳しい。そもそも、ヒワマキシティの人間は、この理由でトレーナーになる人が少ない。キンセツシティあたりは、中途半端にトレーナーになる数が多く、そして厳しい状況に迫られている。
更に、強いポケモンがいる草むらには、当然、腕の立つトレーナーが集まる。これではいくらなんでも、乗り越えるのが難しすぎる。一応、乗り越えられる人も、少しはいるらしいが。
弱いポケモンはどうやら、ミシロシティ付近等の草むらに、生息しているらしい。その町からスタートした人が、圧倒的に有利なのは、言うまでもないだろう。おまけに、ミシロ出身のトレーナーは、何やらポケモンのことを精密に調べられる機械を貰えるらしく、更にはそこの人達は、何やら才能を持っている人が多いらしく、どうしてもそれ意外のトレーナーは、彼らに勝利することができない。もはや勝てる人は、すでに決まっているも同然だった。
更に悪いことに、バトルで得た賞金の十パーセントを、税金として持っていかれる制度が、主人が旅だった前の年から開始された。塵も積もれば山となる。たった十パーセントでも、積み重ねれば膨大な金額になる。しかもこの制度は途中で、取られる金額が十五パーセントに上がった。来年には、更に二十パーセントに上がるらしい。
主人は勝てない日が続きお金を取られ、たまに勝利して得た賞金も幾分か減らされ、直ぐにお金に困る生活を強いられることとなった。もちろん勝つために一生懸命努力した。しかし、ポケモンを育てられる日は限られていた。たまに町に弱いトレーナーがいて、その人とバトルしていくしかなかった。
そんな主人が拠り所にしたのが、この"ゲームコーナー"だった。
主人は、大金を集めようと、意気込んでいた。ゲームコーナーでは、集めたコインを景品に交換できる。景品は、別の店でお金と交換できる。すなわち、コインはお金と交換できる。
主人は、口癖のように日々自分に言い聞かせてきた。努力は報われる。やってきた分だけ返ってくる。だから、このスロットに情熱を注げば、注いだ分必ず返ってくる。それも、トレーナーをやって報われなかった分も、同時に返ってくる。コインの量として。お金として。
けれども、全然コインは溜まらない。所持金は更に減っていき、財布の中は惨めな状態になっていった。
主人の目は、もはや怖くてちゃんと見ていられなかった。ギャラドスのような、赤い目をしていたのだけは覚えている。主人は、最後の一枚で、リールを回した。結果は、あえなく敗北。主人はがっくりとうなだれた。所持金も後僅かだ。
しかしそのとき、非現実的な事態が発生した。スロットが突然光り始めた。その光は、僕が入ったボールへ向けられた。あっと思った次の瞬間、ハスボーである僕は、スロットの絵柄になっていた。このときの衝撃は、今も忘れることはない。最初は夢だと疑った。頬を一生懸命抓った。痛みを感じた。これは現実だと知った。どういうことだ。スロットの絵柄になったのか。けれども、自分はこうして動いている。パニックになって、それからは覚えていない。いつの間にか気絶していた。セブンさんに起こされた。これが、セブンさんとの出会いだ。
そしていつしか、セブンさんとこのような賭け事を、するようになっていた。
スロットの中から脱出する。それは、実は難しくない。けれども、僕はまだまだそれはしない。今出てしまうと、膨大な借金を抱えてしまう。その借金は、主人の所へ流れてしまう。これから借金を0にして、いくらかお金を得られなければ。
そうすれば、主人はまた立ち上がれる。お金さえあれば、なんでもできる。傷薬を買いまくって使いまくれば、強いポケモンも大概倒せる。ボールだっていくつでも買え、手当たり次第に捕まえられる。
思い出した。僕がやるべきこと。やらなくてはいけないこと。それを自覚した。
今、終わらせてはいけない。膨大な量の借金が、主人の元へ課せられてしまう。それだけは、絶対に合ってはならない。
「すいません、まだ止めません」
聞こえているのか否か。どちらにせよ、セブンさんは、振り向きもしてくれない。
「まだ止めません!」
大声を出しても反応がない。つまり、わざと聞こえないふりをしている。
諦めては駄目だ!
僕は走って駆け寄った。セブンさんの元へ駆け寄った。必死になって叫んだ。
「お願いします!僕と賭けを やって下さい! 主人をなんとしてでも救いたいんです! 今の状態ではいけないんです。僕がお金を手に入れて、主人をまた立ち上がらせる。主人は本当は、堕ちてはいけない人間だった。頑張っている人間が堕ちるなんて、不条理にも程がある。そんな不条理、僕が壊してやる! 僕が主人を、不条理から助けてやるんだ!」
感情を吐き出した僕に対して、セブンさんはようやく振り向いてくれた。表情なんてないけれど、ニッコリと笑っているような気がする。
「合格だよ」
「ごう、かく?」
僕は思わず、怪訝な表情を浮かべる。
「試したんだよお前のこと。よく折れなかった。えらい!」
「じゃあ、僕が本気がどうか調べるために、わざと冷たい態度を……」
「そうだ。途中ちょっと笑いそうになったけどな。名演技だっただろ」
「そうだったんですか……。びっくりした」
僕の顔から、今後は自然と笑みがこぼれる。真実を知った僕の胸には、絶望という名の二文字はなかった。セブンさんは、見捨ててなどいなかった。良かった。これで僕は。
「お前はやっぱり本物だ。この私が保証する。きっといつか、当てられるときがくる。借金返済なんてあっと言う間だ。お前の目の輝きは、まだちっとも死んじゃいない。前とおんなじだ。だから、大丈夫だ」
「はい!」
「じゃあやるか、もう一戦!」
「次こそは必ず当ててみせます!」
報われる。
次のお客がやってきた。この人間はもはや、生気を失っていた。顔面蒼白。この四字熟語がピタリと当てはまる。しかし、顔面蒼白とは、何かショックなことが起こったときになるもの。まだこれから、ショックを受ける恐れがあるのに。腰にいつくかのボールがある。彼はトレーナーだろう。髪の毛はほとんど白髪で、四十歳以上にも思えた。しかし服装を見る限り、若者である可能性もある。
もう何回も、ここに通っているのだろう。非常に慣れた手つきで、コインを投入していく。しかし、途中激しく咳き込む。体をふらっとさせる。口を押さえた右手は、真っ赤に染まっていた。彼は大丈夫か。
とにかく僕は、この一回に全てを賭ける。今度こそ、絶対に当たってほしい。いや、絶対に当たれ。主人が頑張っても報われなかった。これは不条理なことだった。ここで僕がお金を得られれば、その不条理が消えてなくなる。普通の状態となる。
三つのリールが、回転を始める。
この人は、なかなかボタンを押さない。目に火花を散らして、絶対に絵柄を揃えようとしている。ようやく三つ押し終えた。だが、揃わない。そして彼は、呟かない。これは長期戦になりそうだ。
二百回は繰り返しただろうか。大当たりを二回も引いたのは、流石ベテランだ。しかしだんだん、調子が悪くなってきた。そして彼はいよいよ、独り言を放つ。
「ああ」
その後も、全く当たらない。前の人よりも、調子が悪くなってきた。さきほどの大当たり二回が、実力なのか運なのか、もう分からなくなってきた。彼の口からまた独り言。
「×××××」
と、思ったら違った。彼は思いっきり、真っ赤なものを吐き散らした。正直、こんなになるまでスロットに熱中するなんて、どうかしていると思う。
メタモンといえば「へんしん」の技ですが、あれって「他の姿に変わる」ものじゃないですか。
ということは、若いポケモンや幼いポケモン、少なくとも死ぬ間際で無ければ、変身をし続ければほぼ不老不死の状態なのかな、と思いまして。
もし致命傷を負っても、変身の技が使えるなら元気な姿に変われば生き延びることも可能では無いかと。
しかし、メタモンがとれるのはあくまでも「へんしん」を使った時の姿でしかなかったら。
進化も出来ず、老いることも出来ず、時間の経過によって姿を変えることも出来なかったら。
それはとても、寂しいことだと思います。
「へんしん」が得意でも、メタモンはメタモンの姿であってこそ、幸せになれるのではないでしょうか。
そんなことを思って、この話を書きました。
読んでいただき、ありがとうございました。
あるところに、「へんしん」の技に大変優れたメタモンがいました。
木、花、石、珊瑚、人間……。そのメタモンは、どんなものにもとても上手く変わりました。
中でも、ポケモンに変身するのが得意でした。
しかし、そのメタモンはとある大嵐に巻き込まれ、元いた住処から飛ばされてしまいました。
他のメタモンたちと離れ離れになり、行き着いた先では同じ種族を見つけることが出来ずに知らない土地で途方に暮れていました。
一匹だけで毎日を過ごし、寂しさを抱いて、自分と同じ姿をした者を探して辺りを彷徨っていたメタモンは、やがて森に辿り付きました。
その森にはピカチュウがたくさん住んでいました。ピカチュウたちの様子を影から伺っていたメタモンは、姿を変えれば一人ぼっちにならなくてすむだろうか、と、試しに一匹のオスのピカチュウへと変身してみました。
突然現れた同族に、他のピカチュウたちは最初こそ警戒していたもののメタモンの変身は完璧だったのですぐに群れへと迎え入れてくれました。
木の実を食べ、池で遊び、ポッポを追いかけ、ゴローンから逃げ回り、メタモンは毎日を楽しく過ごしていました。
そのうち、ピカチュウの姿をしたメタモンの隣にはいつも、一匹の可愛らしいピカチュウが寄り添うようになりました。
花が咲いて、緑が茂って、そして葉が色づく頃には多くのピチューが二匹を取り囲んでいました。
メタモンは、今や伴侶となったピカチュウと、子どものピチューたちと、群れの仲間たちがいて幸せでした。
しかし、時は流れ、愛していたメスのピカチュウは静かに息を引き取りました。
メタモンは悲しみ、来る日も来る日も涙を流しました。
それだけではありません。さらに季節が巡り、メタモンが最初に出会ったピカチュウたちは皆この世を去り、そればかりかメタモンの子どもたちも少しずつ命を落としました。
いつまで経っても、群れにやってきた時の姿を保っているメタモンは、徐々に気味悪がられるようになっていきました。
とある静かな夜、メタモンは他のピカチュウたちが寝静まった頃にそっと森を立ち去りました。
行くあても無く進み続けたメタモンは、野原に着きました。
そこに住んでいるのは、夏の翠葉をその身に宿らせた、シキジカとメブキジカでした。
メタモンは寂しい気持ちを抑えきれず、一匹のメブキジカへと変身しました。
群れの者たちに負けず、メタモンが変わった姿も立派な深緑を持っていました。
より素晴らしい角と葉を持つ者が評価される群れの中で、メタモンはあっという間にトップになりました。
暑い日差しの下、群れを率いるメタモンの周りにはたくさんのシキジカとメブキジカが存在し、いなくなることはありませんでした。
いつも誰かと共にいることが出来て、メタモンの寂しさはなくなりました。
しかし、夏が終わって、秋になって鹿たちはその姿を変えていきました。
「なつ」のメブキジカに変身したメタモンは、緑の葉を彩ることは出来ません。
赤、黄、茶の中で取り残された緑の鹿はすぐにリーダーの座を奪われ、異物扱いされ、誰も近寄ることはありませんでした。
シキジカとメブキジカの身体が雪に染まる前に、メタモンはその姿を眩ませました。
次にメタモンが辿り着いたのは、荒れた大地でした。
岩が立ち並び、雑草が繁ったその土地ではザングースとハブネークが長年争いを続けていました。
メタモンは少し迷いましたが、結局ザングースのメスに変身することにしました。
ハブネークとの戦いに備え、少しでも多くの同種族を求めていたザングースの群れは喜んでメタモンを迎え入れました。
その中でも、群れのルールやメンバーを教えてくれた若いオスのザングースとメタモンの仲はどんどん深くなりました。
しかし、そのオスは、メタモンが生まれたてのタマゴを暖めている間に起こった全面戦闘によって命を落としました。
彼だけではありません、群れのザングースのほとんどが、そして、敵対していたハブネークたちの多くも相討ちで地に伏しました。
メタモンが大事にしていたタマゴさえもが、戦火に飲まれて新たな命を生み出す前に壊されました。
幸か不幸か、傷を負ってもまた元の姿に変身し直すことによってダメージを回復していたメタモンは生き残りました。
静かになった大地を一度だけ振り返り、メタモンは一人歩き出しました。
メタモンは、旅をし続けました。
メタモンは、変身を繰り返しました。
ある時、メタモンは一匹のコイキングでした。
濁った川の中で、鳥ポケモンたちの来襲をかわしながら、他のコイキングと共に滝壺に向かって泳ぎ続けました。
やがてコイキングの群れは、文字通り登竜門である大きな滝に辿り付きました。
一匹、また一匹と、コイキングは滝を登り、紅の鱗を輝かせて威厳に満ち溢れた龍へとその姿を変えていきました。
メタモンも負けじと滝を登りました。
そして、とうとう滝を登り終えた時、そこに残ったのは上流を泳ぐ一匹のコイキングでした。
メタモンが変身したのは、あくまでもコイキング。
ギャラドスへと進化を遂げることは出来ませんでした。
その事実を悟ったメタモンは、流れに逆らってがむしゃらに泳ぎながら川上へと姿を消しました。
ある時、メタモンは一匹のネイティオでした。
過去と未来を見せるネイティオは、他のポケモンと交流することはありません。
全ての時間を見ることが出来るので、コミュニケーションを必要としないのです。
ずっと変わるものを見続けられたら寂しい気持ちにはならないだろう、そう思ったメタモンはネイティオに変身したのです。
しかし、あくまでも姿を変えただけに過ぎないメタモンは、その能力までも真似ることは叶いませんでした。
物言わぬ仲間たちに一度だけトゥートゥー、と鳴いてから、メタモンはネイティオの姿をやめました。
ある時、メタモンは一匹のイーブイでした。
立派な毛並みを持ったイーブイへと変身したメタモンは、ポケモンブリーダーの手に渡りました。
メスのイーブイの姿のメタモンと、イーブイの進化系であるオスのそれぞれとでタマゴをたくさん作るためです。
サンダース、シャワーズ、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、そしてニンフィア。
色とりどりのオスたちはいずれも器量が良く、また強さも兼ね備えた粒ぞろいでした。
暖かい寝床と栄養のとれた食事も確保されていて、メタモンはやっと居場所を見つけられたと喜びました。
しかし、ここでの生活は大変味気ないものでした。
言われたままにタマゴを作り、後は狭い檻の中。
オスの進化系たちがそうであったように、メタモンの表情も徐々に冷え切ったものに変わっていきました。
とある晩に、メタモンはクレッフィに変身し、全ての鍵を開けてオスたちと共に逃げ出しました。
久しぶりの外に、オスは皆、メタモンを一度も見ることなく方々へと散っていきました。
メタモンはその様子を見届けたあと、ブリーダーの施設を後にしました。
メタモンは、色々な場所へと行きました。
メタモンは、その姿を変え続けました。
ある時、メタモンは一匹のマンタインでした。
海に沈んだメタモンは、常にテッポウオを引き連れて深海を泳ぐマンタインを見て、いつも一緒テッポウオがいるならば寂しくないだろうと思いました。
メタモンは、マンタインの姿を完全に再現しました。
しかし、テッポウオも含めて変身してしまいました。
他のマンタインとは違い、メタモンに寄り添うテッポウオはメタモン自身の一部であり、共にいる存在とは言えませんでした。
形だけのテッポウオはもの言うことなく、ひれにくっついているだけでした。
暗い海の底で、メタモンはテッポウオの偶像を隣にして一人泣きました。
ある時、メタモンは一匹のアンノーンでした。
遺跡に刻まれた文字であるアンノーンたちは、様々な形をしていました。
その中の一種類に姿を変え、メタモンは古代の城跡に住みました。
ある時、もの好きな人間が遺跡にやってきました。
人間は好奇心で訪れただけでアンノーンを攻撃するつもりは無かったのですが、警戒したアンノーンたちは人間から隠れるために文字へと戻りました。
もともと文字では無いメタモンだけが取り残されました。
完成された文章には、メタモンが入る隙などありませんでした。
一匹だけで浮いているアンノーンを見て人間は不思議に思い、もっと調べるために近づきました。
捕まる、と思ったメタモンは、その姿をゴローニャに変えて人間を追い払いました。
メタモンの放った岩雪崩は、それはそれは強力でした。
人間が去り、文字から元に戻ったアンノーンたちは、自分たちの住まいである遺跡を壊したメタモンを攻撃しました。
全てのタイプの目覚めるパワーに襲われ、メタモンは遺跡から逃げ出しました。
ある時、メタモンは一匹のヒトモシでした。
ヒトモシは、人の魂をその身に吸い込むことで炎を作ります。
たくさんの魂を得れば得るほど、炎は美しい青白に変わるのです。
メタモンが出会った他のヒトモシたちは、次々に人の命を取り入れ、そして炎を輝かせていきました。
メタモンの姿は、どれだけ魂を吸い込んでも変わることはありません。
初めのうちは同じだけの輝きだった青白い炎は、周りのヒトモシのそれがどんどん美しくなっていくのに比べ、メタモンは未だみすぼらしい、今にも消えそうな燃え方でした。
そんなメタモンが惨めに見えたのでしょう、そのうちにヒトモシたちはメタモンを遠ざけるようになりました。
炎が本当に消えてしまう前に、メタモンはヒトモシでいることをやめました。
メタモンは、世界中を渡りました。
メタモンは、世界中のポケモンに変身しました。
ある時、メタモンは一匹のバルキーでした。
険しい山では、たくさんのバルキーが修行を積んでいました。
より強靭に、より俊敏に、より正確に、より機敏に。
ある者は腕力を鍛え、ある者は脚力を鍛え、またある者は反射力を鍛えました。
バルキーたちは、攻撃に特化した者、防御に特化した者、素早さに特化した者にわかれました。
そして、それぞれはその能力に応じて姿を変えました。
メタモンは、バルキーのままでした。
それでも諦めず、様々な修行を続けました。
やがて、メタモンはバルキーにして、山のどんな者よりも強い存在になりました。
皆が毎日、メタモンに稽古を求め、勝負を挑んできました。
自分の元に絶えず誰かが訪れる日々を、メタモンは嬉しく思いました。
しかし、最強と崇められ、敬われるということは裏を返せば、敬遠と、畏敬と、恐怖されるということになり得ました。
誰も隣にはいてくれないと気がついたメタモンは、鍛え抜いた足を使って、一晩で山を下りました。
ある時、メタモンは一匹のフラージェスでした。
とても美しい花畑で、メタモンは他のフラージェスやフラべべ、フラエッタと優雅な暮らしをしていました。
花畑に咲き乱れる花々に負けず、その力を受けたフラージェスたちも美しい姿をしていました。
しかし、花畑を急な日照りが襲いました。
強い日光は、花々をみるみるうちに枯らしていきました。
フラージェス、フラべべ、フラエッタも、身体の花をしおれさせてしまいました。
ただ一人、メタモンだけが変身した時のままの美しさを保っていました。
唯一綺麗なままのメタモンを、他の花は妬み、嫉み、恨みました。
渾身の花吹雪を受け、メタモンは傷つき、花畑にいることが出来なくなってしまいました。
どこへ行っても、メタモンは独りになりました。
どれだけ愛しても、メタモンと添い遂げる者はありませんでした。
どんなに愛されても、メタモンが共に眠ることは叶いませんでした。
独りぼっちのメタモンは、幸せを求めるたびにその姿を変え、悲しくなるたびにその姿を変えました。
どんな姿でもいい、自分が寂しくなくなるなら、全ての存在に変身してみせる。
メタモンはそう思いましたが、何度変身しても、寂しさが消えることはありませんでした。
それに気がついていたのか、それともいないのか。メタモンは、もはや悪あがきのように変身を続けました。
沼魚になり、蝶になり、鳩になり、狐になり、鯨になり、ゴミ袋になり、南瓜になり。
メタモンは、あらゆるポケモンの姿になり、何度も涙を流しました。
メタモンは、自分の本当の姿を忘れていました。
ある日、エアームドに変身して空を飛んでいたメタモンは、地面に紫色の点を見つけました。
何だろうと思って近づいてみると、それは一匹のメタモンでした。
ふよふよとした定まらない形と、落書きのような表情。
その姿にどこか懐かしいものを感じたメタモンは、すぐにそのポケモンへと変身しました。
そのメタモンは、何も言いませんでした。何もしませんでした。
何もすること無く、ずっと空を見上げていました。
メタモンは、そのメタモンの隣に陣取り、一緒に空を見ることにしました。
雲が横切り、鳥が飛び、花びらが舞いました。雷が光り、雨が滴り、風神が暴れました。星が瞬き、雪が降り、龍が流れました。
空は毎日、その姿を変えました。今までのメタモンのようでした。
それに対し、隣にいるメタモンは、全く姿を変えませんでした。へんしんポケモンのはずなのに、変身することなく、黙って空を眺め続けていました。
不思議と、そんなメタモンと一緒にいると、寂しさを覚えることはありませんでした。
変わりゆく空を共に見て、メタモンは今まで感じることが無かったような気持ちで心が満たされていくのがわかりました。
何度も季節が巡った後、メタモンは、流星群の夜が終わり、明るくなった空を見ることなく眠りにつきました。
隣のメタモンに寄りかかり、幸せなまま、永遠に目を閉じました。
そんなメタモンを見て、隣にいたメタモンが小さく動きました。
同じ姿をした、長く生きたへんしんポケモンを、そっと撫でました。
何かを告げるように口許が動き、そしてその動きが止まった後、そのメタモンの姿はもうありませんでした。
動かなくなったメタモンの上空を、桃色の猫のような一匹のポケモンが軽やかに飛んで行きました。
あるところに、「へんしん」の技に大変優れたメタモンがいました。
そのメタモンは、たくさんのポケモンに変身しました。
たくさんのポケモンを愛し、たくさんのポケモンに愛されました。
今は、もういません。
ずっと欲しかった、おやすみの言葉をもらえたそのメタモンは、もう二度と、目を覚ますことはありませんでした。
記事用
・熱砂の国の蛇神譚
【蛇といえば、世間一般には「細長くてくねくね動く気持ちの悪い生き物」「猛毒を持っていて危険」「ロケット団などのアングラ組織が手持ちに入れている」等、あまり良くないイメージを持たれているのではないだろうか。確かに、四肢を持たず滑るように地を這い、獲物に食らいついて丸呑みしてしまうその姿は異様である。また表情を表さない顔や、際限なく開く(少なくともそのように見える)顎、長くて鋭い牙は畏怖と嫌悪の対象にされやすい。世界中に広がる某宗教間では、人の始祖が楽園から追放される原因を作った生き物として忌み嫌われている。神の罰を受けてあのような気味の悪い姿になってしまったのだ、という説がある程に。
身近で親しみやすい獣型や獣人型、人型など人々の支持を集めやすいポケモンと違い、彼らは大抵日陰の身扱いである。
しかし、そんな彼らも一部地域では神の使いとして、あるいは神そのものとして崇められていることをご存じだろうか。】
ここまでで挫折。世界の蛇話と蛇ポケモンとを絡めつつ、メインはイッシュの砂漠の城(都市)を古代エジプトに見立てて、アーボックが墓守の女神だったと紹介する予定でした。結局、予定は未定でした!
・ヨツクニ地方の狸譚
四国のタヌキ伝説をかき集めて方言バリバリダーで書き、それを記者が標準訳したという二段構えで……と考えつつ、うやむやのままに保留。
山奥に住む爺さんが語る伝聞、という形にしたかったんですけどね。
小説用
・嘆きの湖の伝説
第一次の記事の元ネタ。いまだ仕上がらず。
・タイトル未定
熱砂の記事の小説版。古代エジプトの神々をポケモンに当てはめて、どうこうするつもりでした。煮詰まりきらず断念。
【熱砂の国には、古い古い信仰があった。今はもう人々の記憶から抜け落ちてしまった神々が、遠い昔に生きていた。】こんな感じ。
以上、鳥居ボツネタでした。いつかまたどこかで、形にできたらいいなあ。
1番の18時からを希望します。
21時から別件が入っておりまして・・・
チャットなら問題ないかもしれませんが、確実に時間作れるタイミングをば。
1の18時からを希望します。
早いほうが、次の日に響かない…と思いまして。
おそらくどの時間帯でも21時前後に離席するかと思いますが、20:00だと比較的都合がいいです。
18時開始希望します
早く終わると寝れる!
ツイッターで開始時間を早めにして欲しいとの要望をいただいたのでアンケートをとります。
以下、三択から選んで下さい。
1.18:00〜
2.19:00〜
3.20:00〜
回答期限:今週木曜日いっぱいまで
ボツネタの宝庫だよ!
・竜を呼んだ師匠
旅芸人の師匠と付き人の話。
明治より昔らへんを意識
現在のフスベシティらへんを通った時、興味持った新しい領主にやれと言われて、削ったばかりの横笛で師匠が演じる
が、弟子はその笛はやたら高く、竜の声(雲を呼ぶ風の音)に似ていてあまり好きではなかった
フスベシティでは笛を吹いてはならぬと言われていたが、新しい領主はそんなの迷信とばかり。
しかし師匠が奏で始めるとだんだと雲行きが怪しくなり、大量の雨が振り、雷が鳴る
師匠の身の回りの世話と、台無しになってしまった笛のために、フスベの山へいい木を探しにいく弟子。
猟犬(デルビル、ヘルガー)を連れた地元住民に、ここは昔、シロガネ山に住む竜(カイリュー)が仲間を失って探しに来たはいいが、結局みつからずに終わってしまったこと、それ以降、笛の音を聞くと仲間だと思って大雨を連れてやってくることを聞く
元々表を歩けない身、黙々と笛を作り、二人は旅立つ。
・主任の炭坑
シンオウは石炭や金銀などが取れるため、たくさんの炭坑があった。
ポケモンを使い、どんどん掘り進めシンオウ地方から取れる資源は人々の生活を豊かにした。
炭坑で働くものは取れれば取れるほど自分にまわってくる利潤が多くなるため、どんどん掘り進んだ。
事故も多かった。しかし会社は遺族にたくさんの金をおけるほどだった。
そんな時、作業員が何人か戻らないことがあった。確かに一緒に作業し、直前まで話していたはずなのに
探したが崩落などはなく、また明日探そうと解散。
次の日も探すが永遠に戻ることはなかった。
そのかわり、炭坑でイワークの変種が見つかる。金属の体にシャベルのような顎を持っていた。
作業員が見てるまえで壁を堀り、金属を見つけるような動作をした。そいつは作業員を見つけると勢いよくやってきた。驚いた作業員は逃走するが、途中で何人かいなくなる。
そして作業員が何人かいなくなった。ついに主任者が現場に入るが戻ってこなかった。それに比例してイワークの変種の目撃談が多くなる。
噂では山に取り憑かれた炭坑夫の成れの果てだとされ、炭坑は閉じられた。
今では調査のため、開かれているが、決してハガネールだけには攻撃していけないと言われている。
それがもしかしたらあの時の作業員かもしれないのだから
(モンハン、ウラガンキンネタより)
・妖狐はいかにしてシンオウから姿を消したのか
今ではシンオウでロコンは見られない。
元はたくさんいたのだが、人に退治された。
シンオウの開拓や炭坑で働く人はケガも多く、この男も全身に火傷を負って看護されていた。
だいぶ治ってきたころ、家に人が来た。妻が対応すると会社のものだという。しかし男も女も子供まで混じっていた。
おかしいなと思いつつも、仕事のことを相談したいから少し部屋を閉じてくれと頼まれてその通りにした。
何時間たっても出て来ないので様子を伺うと、男は既に息絶えていて、そのまわりをキュウコンとロコンが争うように男の肉片を食べていた。
火傷の治りかけの皮膚はロコンキュウコンのたぐいの好物である。炎でやいた相手を生きたまま放置し、治ってきたころに食べることもする。
妻が叫ぶと、一目散に逃げていった。
同じようなことが相次ぎ、狐をこの世から抹殺すべきだと残された開拓民は炎に強い猟犬ヘルガーと共に山に入り、一匹残らず仕留めた。
最後のキュウコンが絶滅したのはその事件から7年後だったとされている
今でもシンオウでロコンは見かけない。むしろ見ない方がいいのかもしれない
(北海道の炭坑記録から)
どれも、文章にするとだるくなっていく
道祖神の詩(うた)です。
道祖神とはミクリの言う通りに正しい道に導いてくれる神様と言われていますが、旅の神様でもあるんですね。
また、境界線を示す神様でもあり、神様の住む世界と人間の住む世界をわけていると言います。鳥居と性質は似ています。
大人のトレーナーにしか思えないこと、それが本当に今の人生でよかったのか、今までの事はよかったのか、今は正しいのかという反省です。
彼らにも突っ走ってポケモンに夢中だった時があったはず。でもその結果は本当によかったのか。正しかったのか。
本当に正しいならなぜ今の位置にしたのか。
ポケモンで最も神秘的な街だと思ってるルネシティ。音楽もホウエン地方の他の街と比べてジャズワルツになっています。グラードンカイオーガが目覚める祠もありますし、ルネの住民が全ての生命はおくりび山で終わり、目覚めの祠から出て行くというセリフ、そして飛ぶか潜るかしないと行けない地形などから、ルネシティは独自の自然信仰がありそうだなと思い、このような形にしました
そしてなぜミクダイなのか。
手にしたミクダイにとても感動し、こういう形で彼らが生活している基盤をかけないかとかきだしていたら自然とまとまりました。
最後に。
詳しい方はすぐ解ると思いますが、道祖神は男女の性交も司ってるんですよね。だけどダイゴはそうじゃない。だからどうしてこの道(ミクリが好きだという現状)に行かせたのかと恨みを抱き、どうにもならない心を必死で隠そうとします。
(ミクリの対戦相手がカチヌキ一家の長男。彼もまたここまで後悔も振り返りもせず突っ走って来たんだろうなあ)
| タグ: | 【ポケモンXY】 【ヤヤコマ一進化が萌える】 |
No.017でございます。
みなさま、ポケモンXYはお楽しみでしょうか?
すでに殿堂入りされた方も多いかもしれませんね。
企画もお休みにしたので、全力で入り浸ってる最中でございます!
さて、本題です。
せっかくポケモンファンサイトがあるのでフレコ交換をしませんか?
とりあえず私の載せておきます。
No.017
3609-1222-6407
プレイヤー名:セレナ(主人公♀)
返信があった方のは登録させていただきますねー。
どうぞよろしくです!
読み専門の方とかもこれを機会にぜひどうぞ!
時よ止まれ、貴女は美しい。
〜
栓を捻る。リングが割れて、炭酸の弾ける小気味良い音が瓶の中から吹き出した。パシパシ弾ける泡の液体を、一気に喉に流し込む。瓶を傾けた拍子に見える、底抜けに青い空。暑いくらいの天気には、冷たいコーラが丁度良い。
「美味いな」
青井は気分良く、腹に溜まった炭酸を吐き出した。これで、山道の途中の、この休憩所の景色が綺麗なら、言うことなしだったのだが。青井は小汚いトイレや、塗装が剥がれるままに放置されているベンチや、日除けや、自動販売機を見た。作ったはいいが、管理まで考えていなかったのがよく分かる。だが、友達四人で旅行なんて、中々出来ないことが出来た時に、この快晴だ。文句は言うまい。青井は景気付けに、もう一度コーラを呷った。
「コーラか。村に着くまでに抜けちまうぞ?」
そんな良い気分に水を差すように、友人が言う。
「そんなこと言うなよ、真壁。まあ、ここで飲み切るさ」
言葉の最後にゲップが出た。コーラはまだ、半分程残っている。真壁は「がんばれ」と気怠げに言って、笑う。
真壁は猛禽のように鋭い一瞥を今しがた登ってきた道の方へやると、再び青井の方を向いて愉快そうに笑った。
「どうした、真壁」
「いや。面倒なことになるな、と思って」
そう言って真壁は一瞥を、今度は三人目の方へ向けた。青井は道を見て、「ああ」と合点の声を上げた。
間もなく、がやがやとかしましい声が下から聞こえてきた。休憩所に現れたのは、女性の三人組。年は二十歳ぐらいだろうか。青井たちとそう変わらない。彼女らは小汚い休憩所を見て、途中まで素通りするペースで足を進めていたが、青井、真壁、と休憩所にいる人間を見、それから三人目に目を移したところで、揃って足を止めた。女性三人組は、互いに小突き合い、小声で何かを話し合う。その顔が少しにやけている。青井と真壁は「やっぱりな」と呟いた。
やがて、三人組は足並みを揃えて青井たちの方へ向かってきた。しかし、青井と真壁には目もくれない。目標は、少し離れて座っている三人目の彼である。
「あの、すいません」
三人目、海原は話しかけられて初めて気付いた様子で、顔を上げた。女性たちは顔を見合わせて笑うと、
「写真、撮ってもらえませんか?」
そう言ってインスタントカメラを差し出した。
海原が青井と真壁を見た。しかし、彼らは意地悪く笑っているだけ。海原は仕方なさそうに女性からカメラを受け取った。
「写真ねえ。撮りたい景色なんてないだろうに」
小声で言いながら、青井は周囲を見回す。休憩所は勿論写真に残せるような代物ではない。山の向こうを拝んでみても、なだらかとも険しいとも言えない微妙な角度の稜線と、微妙に紅葉した森が広がっているだけで、とりたてて観光客に売り込める景色はない。
真壁は、女性三人と少し見晴らしのいい所へ行った海原を指差した。
「海原を撮りたいんだよ」
「なるほどな」
青井はコーラの瓶に手を伸ばして、休憩所のトイレの方を申し訳なさそうに見る。
「しかし、アキちゃん、遅いな」
「女性は色々と時間が掛かるんだよ。海原がパパラッチを振り切るのと、どっちが早いかな」
真壁の軽口に笑いながら、青井はコーラを口に運ぶ。しかし、一口飲んですぐに異変に気付いた。
「真壁。お前、振ったな」
「油断するからだ」
青井は真壁を一睨みしてから、ただの甘ったるい液と化したコーラを飲み干した。
「おまたせ!」
明るい声がした。小柄なショートボブの女性が、手を振りながら青井たちに走り寄った。友達の四人目で紅一点の晶子だ。
「ごめんなさい、時間が掛かっちゃって。私はいつでも出発できるから」
青井は口の横に手を当てると、大声で海原を呼んだ。海原の周囲に群がっていた女性三人が、晶子を見て残念そうな顔をする。やっぱり振り切れなかったか、と真壁が楽しそうに呟いた。
〜
それからしばらく時間を潰して、青井、真壁、海原、晶子の四人は休憩所を出発した。海原に写真を撮ってとねだっていた女性三人組は、先に出発していた。こちらは彼女らに会わないように、わざとゆっくり進んでいる。人のいない山道だ。各々ポケモンを出したりしながら、のんびり、登っていた。真壁はポケモンを持っていないので、三人のポケモンを眺めているだけだが、それでも心は踊った。
「たまにはこうやって森林浴もいい」
これから向かう村の観光案内を読みながら、真壁が言った。
「今回の目的は、森林浴じゃなくてセレビィの村の観光でしょ」
真壁に反抗するように、晶子が言った。しかし、作ったようなしかめっ面も一瞬で、彼女はすぐに破顔する。
「でも良かった。皆の休暇が合って」
「俺のは療養休暇だけどな」海原がボソリと呟いた。
「こんな機会は滅多にないだろうな」
真壁はパンフレットを閉じて、感慨深げに言った。他の三名も頷く。真壁はジャーナリスト、彼以外の三人は警察官だ。こんな風に休暇が合うことなど、もうないかもしれない。
巨木の多い山道は、これまで歩いてきた町中や休憩所よりも、ぐっと涼しかった。風は、ごくわずかにあった。木の葉がさやさや頷く音がする。晶子は自分のエーフィの喉元を撫でてやっていた。ヘルガーは眠たげに欠伸をし、その周りをメタモンとストライクがくるくる回っていた。ガーディが泥を跳ね上げ、煽りを食ったシャワーズは海原の元へ走って行って、泥を落としてもらっていた。姿が見えなかったベロリンガが、リグレーと山菜を抱えてやってくる。
この時間が、ずっと続けばいいのに。多かれ少なかれ同じようなことを、四人皆が思っていたはずだ。
時よ止まれ、貴女は美しい、か。真壁は心の中で呟いて、観光案内のパンフレットに目を戻した。パンフレットの表紙には、クスノキを元にした村章が描かれている。村の木がクスノキなのだそうだ。おそらく、村に大きなクスノキがあるのだろう。
「そういや、セレビィの村って、どういう所なんだ?」
今回の旅行先について、何も予習してこなかったらしい青井が言った。晶子が諸手を上げて「それはね」とはしゃいだ調子で説明を始める。今回の旅行のプランを決めたのは、晶子だった。
「セレビィが祀られてるのよ。昔、悪いことをしようとしたけどやっつけられて、それ以降は村の守り神になったの。運が良ければ、姿も見られるんですって」
「へえ、いいな」
シャワーズの泥を払いながら、海原が呟いた。セレビィが見られるかもしれない、なんて、晶子が喜びそうな売り文句である。もっとも、セレビィは幻とさえ言われるポケモンだ。余程運が良くなければ見られないだろう。
「その悪いことってのは?」
青井が聞く。今度は真壁が答えた。
「昔、まだ森が広がっていたこの場所を、村に作り替える為に多くの木が切り倒された。それで、セレビィが弱ってしまったんだ。森ってのはセレビィの力の源だからな。
そうして村は出来たが、セレビィはすっかり弱ってしまった。そのセレビィを人間の女性が助けた。セレビィの力が戻るまで親身に世話をしたその女性に、セレビィは恋をした。そして、彼女とずっと一緒にいたいと願ったセレビィは、村ごと、彼女の時間を止めてしまう。
しかし、そんな蛮行が許されるはずもない。ある男が聖剣でセレビィを調伏し、村の時は再び流れ始めた。男と女は結ばれ、セレビィは彼らを見守る為に、村の守り神になったそうだ」
「調伏?」
「叩きのめして従えたってことだろ」
青井の疑問に答えたのは海原だ。青井は「モンスターボールで捕まえるようなもんか」と納得した。
「それでね」と再び晶子が喋りだす。
「その村には時の巫女という女性が一人、時の勇士という男性が一人いてね。年に一度のお祭りでは、その人たちが当時のことを再現してお祭りをするの。女性はセレビィを助け、男性はセレビィを調伏する。セレビィは他の草ポケモンが演じるらしいけど、それでも見たかったな。時期が合わなくって」
「仕方ないだろ」
真壁が言った。
「そうね。こうやって皆で遊びに来れただけでも、感謝しなくっちゃ」
晶子は笑顔を浮かべた。花が咲いたようだ、と男たちは思う。セレビィのやり方は駄目だろうが、そうしてしまいたいと願う気持ちは、三人には分かる。彼らがそう思っていることを、晶子一人だけが知らない。
「ちょっと」
第三者の声が、四人の間に割って入った。剣呑な雰囲気に、四人は振り返った。村人だろうか。山菜の入った籠を脇に抱えた老人が、四人とポケモンたちを睨みつけていた。ベロリンガが山菜を飲み込んだ。
「こんな道の真ん中でポケモンを出すなんて、非常識じゃないか」
すいません、と口々に謝って、それぞれのポケモンをボールに戻す。手持ちのいない真壁は、手持ち無沙汰にその様子を眺めていた。別に、道でポケモンを出してはいけないという法律はないし、周囲の迷惑になるような、例えばバンギラスやカビゴンみたいなポケモンも出していない。それでも、いちゃもんを付ける人というのはいるものだ。そんな時は、大人しくポケモンをボールに戻すに限る。わざわざ諍いをすることはないし、それに、老人の方だって、実は何かのポケモンアレルギーで苦しんでいるのかもしれない。真壁はそう考えて溜飲を下げることにした。
「偏屈老人だな。ああいうのにはなりたくない」
老人が去った後を見て、青井が苛ついたように言う。
「でも、私たちも、ちょっとはしゃぎすぎたわよ。真壁さんは違うけど」
「いや、俺はたまたまポケモン連れてなかっただけだし」
言いながら、真壁は海原の方を見る。彼は先程からキョロキョロと、辺りを見回している。
「どうした、海原?」
「ミームがいない」
言葉少なに答え、また見回す。
「ちょっと道外れただけだろ。バルキリーも見当たらねえけど、大丈夫だよ」
まだ苛々が収まらない様子で、青井が言った。
「ほら、戻ってきた」
上空からポッポを追いかけて、ストライクが降りてきた。ポッポは海原の上空に行くと、ドロリと溶けてメタモンの形に戻った。そして、素早く海原の鞄に入り込む。ストライクは逃げるメタモンに向けて、シャアッと鳴いた。海原が大きく身を引いた。
「バルキリー」
トレーナーが呼ぶと、ストライクは大人しく青井の元に戻った。
「悪い」
「別にいい」
青井の謝罪を介せず、海原はふいと背を向けた。
微妙な雰囲気のまま、四人は村へと向かった。さっきの今でポケモンを出す気にはならないが、出しっぱなしのメタモンやストライクをわざわざ戻す気にもなれない。ストライクは、今は大人しく青井の後ろを歩いている。メタモンも鞄の中に収まったきり、うんともすんとも言わない。四人もそれぞれ黙ったまま、村を目指した。
そうして、ようやく村の入り口が見えてきた時。
「思ったより、時間が掛かったな」
青井がポツリと呟く。
日はすっかり落ちていた。都会から離れた村は眠るのも早いのか、静まり返っている。
「まだ七時過ぎだってのに」
青井が腕時計を確かめて言った。
「とりあえず、宿屋を探そう」
真壁の一声で、四人は村を進み出す。有名な観光地ではないし、祭りの時期も外れているので、宿は予約していない。四人はそれぞれに道の両側を眺めて、宿屋の看板を探した。しかし、月明かりを頼りに探してみても、一向にそれらしい物が見当たらない。
「いくら過疎った観光地だからって、宿屋がなさすぎじゃないか?」
青井が腕組みをした。彼のストライクも、トレーナーそっくりの渋面でカマを合わせた。「あの」と晶子が言い難そうに口を開く。
「私が調べた宿屋も、ないみたい」
「潰れたんじゃねえの」
にべもなく言い放った青井に、真壁が反論を出す。
「だとしても、この静けさは異常だろ」
その時、三人から離れて立っていた海原が、何かを言いかけて口を閉じた。
「何だ? そういう態度が一番気になるんだよ、言ってくれ」
いい加減疲れが出てきたのか、青井が投げやりに言った。海原は青い目をす、と空へ逸らすとこう呟いた。
「月」
三人は夜空を見上げた。田舎らしい、落ちてきそうな程に星屑の詰まった紺色の空に、丸い盆のような月が一つ。
「今夜は満月じゃない」
海原はそう言うと、村の入り口に戻り始めた。三人は慌てて、彼を追った。
〜
背中から近付く足音を聞きながら、海原はため息をついた。三人が立ち止まったのを聞くと、振り向いて、黙って村の入り口の方角を示した。
「入り口がない」
青井が唸った。村の入り口があったはずの場所は、ぬっぺりとした岩壁に変わっていた。海原は黙ったまま村の中へ戻る。その腕を、青井が掴んだ。
「おい、戻ってどうすんだよ。明らかに変だってのに」
「でも、帰れもしない」
淡々とそう言うと、鞄の中にいるメタモンを肩に乗せる。そして、一番近くにあった家の戸を乱暴に叩いた。「誰かいますか」返事はない。戸板が揺れただけだ。
「いないな。明かりも点ってない」
海原が戸に手を掛けた。しかし、晶子が「ちょっと待って」と声を上げて遮った。
「ねえ、モンスターボールが開かないみたい」
そう言って、自分のモンスターボールの開閉スイッチを押し込んでみせた。スイッチは彼女の指の動きに従って押し込まれ、離されれば元に戻るが、いつものように、ボールが開いて中からポケモンが飛び出してくる気配がない。
青井と海原も、自分のモンスターボールを改めた。開閉スイッチを押してみるが、中のバネが空しく戻る音がするだけで、一向にボールは開かない。
「どうなってんだ」と青井が声を上げた。
「青井、今何時だ?」
皆がボールを確かめる間、ずっと黙っていた真壁が口を開いた。青井は怪訝そうにしながらも、自分の腕時計を確かめ、そして、顔を歪めた。
「七時過ぎで止まってる。でも時計が壊れたのかもしれない」
「俺の腕時計まで、同時刻にか?」
真壁が左手をゆるゆると振った。
「私のも止まってる」
晶子が言った。
「どうやら、時の止まった世界に迷い込んだらしいな」
真壁が言った。その手には村のパンフレットが握られていた。表紙に付いたクスノキの村章を指で弾く。青井が「信じられない」と声を荒げた。
「だが、そう考えた方が辻褄が合う」
真壁はクスノキの村章を再び指で弾いた。そして、少し考え込んでから、口を開いた。
「人がいない。建物の配置も、このパンフレットとは少々違う。それにあの月だ。俺たちは、セレビィの作った異界に迷い込んだ」
「でもなあ。それだと、俺たちが元々目指してた村はどうなるんだ?」
青井が腕組みをした。次に答えたのは海原だった。
「ここは、時の流れから取り残されてるんじゃないか。俺たちが元いた世界と、そもそも別の時間軸にある」
「分からん!」
青井が音を上げた。
「とにかく、セレビィが原因なんだろう? ならそのパンフレット通り、セレビィを調伏すればいい。それで、俺たちを元の世界に戻させるんだ」
「聖剣の話は?」
海原が水を差した。青井は五月蝿そうに手を振った。
「セレビィもポケモンだ。こっちにはバルキリーがいる。聖剣なんてなくても、ポケモンバトルで伸してやりゃあいい」
「それに、聖剣という言葉自体、何かのポケモンの比喩かもしれない」
青井に加勢するように真壁が口出しして、海原はまたふいと背を向けた。
「じゃあ早速、セレビィを祀ってる社へ行こう。いいな、海原?」
「ああ」
海原の返事を聞いて、青井が頷く。真壁も頷く。三人は晶子を見た。
晶子は三人の顔を順々に見ると、いつもそうするように、物柔らかな、陽だまりのような笑みを浮かべた。
「……大変なことになったけど、セレビィと会えるんだって思うことにしましょ」
そして声のトーンを落とすと、「ごめんなさいね、私の所為で」と言った。
「晶子の所為じゃない」
海原がボソリと呟いた。
〜
パンフレットによると、この村は大きく上層、中層、下層に分かれているのだそうだ。山の斜面にあるこの村は、俯瞰すると、山を削って大きな三段の棚田を作ったような形をしている。棚田の下層には田畑が多く、中層に村の主要施設があり、上層に社があるらしい。自分たちが用があるのはセレビィだから、階段を探して、上層を目指せばいい。
「あった。階段だ」
最初に見つけたのは真壁だった。社や、それに続く階段の位置は、時が移ろってもそう変わらないということだろう。山肌にそってやや右曲がりの道を進む。上層へ続く階段はすぐにそれと分かった。少なくとも百段はありそうな石段。その中程に鳥居があった。青井は上方を仰いだ。しかし、暗くて見えない。
誰が言うでもなく、青井とストライクが先頭に立って石段を登り始めた。晶子が後ろに続き、その次に真壁、しんがりはメタモンを連れた海原が務めた。四人は黙って階段を登る。もうそろそろ半分というところで、青井のストライクが唐突に止まった。
「どうした、バルキリー?」
青井が先に立ってストライクを呼ぶものの、ストライクは困ったように首を横に振るばかりで、それ以上前に踏み出そうとしない。「ちょっと失礼」海原が石段を登る。そして、メタモンを肩に乗せたままストライクの横を通りすぎて、そのまま青井の上に登った。
「虫ポケモン除けになってるのかもな」
海原が指差した先を見ると、鳥居があった。海原は再び段を降りる。
「セレビィっていうのは草・エスパータイプのポケモンらしい。だとしたら、天敵になる虫ポケモンが入れないようにしてても、不思議じゃない」
「じゃあ海原、お前が行けばいい」
「だめよ」
晶子が口を出した。
「皆で行かなきゃ」
四人はしばしの間、石段の途中で固まった。青井はストライクをボールに戻そうかとも考えたが、やめた。モンスターボールからポケモンを出せない今、ストライクをボールに戻しても鳥居をくぐれないとなったら、戻し損だ。四人はこれといった打開策が出ないことを悟ると、今度は真壁を先頭にして石段を降り始めた。
「さて、どうする?」
一番に中層に戻った真壁が言った。その次に晶子がトン、と石段を数段飛ばして降りる。青井はその次だ。
「聖剣を探す?」晶子が困った様子で言った。
「だとよ。いい気分だな、海原」
「何が?」
最後に石段を降りた海原に青井が嫌味を飛ばすが、海原は気が付かなかったようだ。真壁の方を見て、「他に、ここを出る方法はないか」と尋ねた。真壁はパンフレットを振る。
「つっても、ここに書いてあるのは、時の勇士がセレビィを調伏した話だけだぜ?」
「それ以外でも。例えば、似たような話で……異界に迷い込む話で、そういう話の主人公は、どうやって元の世界に戻ったんだろうか」
「似たような話ねえ。急に言われるとなあ」
言いながら、真壁は近くの塀にもたれる。そういえば、時間感覚がないが、疲れが溜まっている。他の三人もそれに気付いたらしく、晶子が「どこかで休めないかしら」と声に出した。
「適当に近くの家で休もう。どうせ、誰もいないだろ」
青井の言葉に他の三人も頷いて、石段から程近い場所にある平屋に投宿することになった。「ごめんください、一晩ここに泊まります」とは言ったものの、案の定中には誰もいない。一晩というのも、一体どれくらいの時間になるのか分からない。時間が止まるなんてなあ、と青井はため息を吐いた。
四人は、家に入ってすぐのところに囲炉裏の部屋に集まっていた。板敷きの中央には囲炉裏が切られており、そこには鍋が吊り下げられてあったのだが、今は外されて、青井の懐中電灯が代わりに結わえ付けられている。乾電池二本分の光が、囲炉裏とその周りをぼうっと照らしている。ポケモンを出すことも出来ないのが、なんとも気詰まりだった。
障子を開けて、家の探索に出ていた真壁が戻ってきた。
「飯はなかった。風呂も台所もあったが、水が出ないからどうしようもないな。でも便所は使える」
何故か、とは誰も聞かなかった。
「とりあえず、夕食にするか」
青井は自分の荷物から、缶詰とカップ麺を出した。トレーナーの修行の旅をしていた時の癖で、つい色々持ってきてしまっていた。それがこうして役に立つとは、なんだか複雑な気分だ。
缶詰を適当に四つ選び、三つを他の人に投げた。ポケモン用のドライフードも投げる。この時も海原だけ何故か離れた場所に座っていて、一々名前を呼ばなければならなかった。なんなんだあいつは、と心の中で悪態をつきつつ、今度はカップ麺を配る。しかし、囲炉裏に鍋を掛け直そうとした時に、真壁に止められた。
「これで煮炊きはしない方がいい」
「なんで?」
「よもつへぐい」
海原が分かったように口を聞いた。
「何だよその、よもつぐへい、ってのは?」
青井の質問に、今度は真壁が答える。
「よもつへぐい、な。あの世の物を食べたり、あの世の竈で煮炊きした物を口にすると、この世には帰れなくなる、という話だ。ところで、色々考えてみたんだが」
真壁は缶詰を開けると、割り箸を割った。
「この世とは思えない所に迷い込む話って、帰ろうとしたら帰れました、ってパターンが多いんだよなあ。迷い家とかさ。あるいは、異界の主に招かれて、歓待されて、帰りますと言ったらお土産までくれるパターン。竜宮城みたいなやつな。でも、そういう雰囲気でもないし。こう、帰ろうとしても帰れないっていうのは……」
「お菓子の家みたい」晶子がポツリと呟いた。
「セレビィは魔女ってとこか」真壁が言った。
「やっぱり、セレビィを叩きのめすしかないんじゃないか」
青井が食べ終えた缶詰をリュックに放り込み、「なあバルキリー」とストライクの方を向いた。ところがどうだ。ストライクは海原に頻りに寄って行っている。
「こら、お前のトレーナーはこっちだぞ。戻ってこい」
青井の言葉に渋々、ストライクは向きを変えた。戻ってくる途中、何度か名残惜しそうに海原の方を見た。
全くどいつもこいつも、と言いかけて、言葉を呑み込んだ。海原に寄っていくのは、今のところ、一見さんの女性たちと青井のストライクだけだ。青井が気になっている彼女は、まだ誰のことが好きだとか、何も明言していない。今はまだ。
わびしい夕食が終わった。青井は板敷きの上にゴロリと横になった。晶子も自分の上着を掛けて横になった。
「隣に畳部屋があったぞ。そっちで寝たらどうだ?」
家を一通り見ていた真壁が晶子に言った。
「うーん、でも」
「男共と同じ部屋ってのも具合悪いだろ」
「それより、皆と離れちゃう方が不安だわ。大丈夫よ、固いところで寝るのは慣れてるし」
そう言って笑うと、リュックサックを抱き枕代わりに引き寄せる。そして、目を閉じた。
「俺はしばらく見張りをしとく」
海原がメタモンを撫でながら言った。ストライクが自分もやる、と言うように鳴き声を上げたが、「お前はいいよ」と青井が止めた。
横にはなったものの、青井はよく眠れなかった。時々変な夢を見ては、夢から醒めて暗い天井を見上げる。夢の内容は思い出せなかった。ただ、恐ろしく夢見の悪い夢だという感覚だけ。
ストライクはまた海原の近くにいた。小さな鳴き声が聞こえる。メタモンとストライクが話しているのだろう。青井はまたうとうとし始めた。メタモンとストライクの話し声が、夢の中を行ったり、来たりする。夢の中で、ガシャンと卵が割れた。暖めれば金銀財宝が孵ったのに、なんて勿体ない……いや、割れて良かったのだ……
「ミーム、落ち着けって! 海原、おい、どうした!」
真壁の声がして、青井は跳ね起きた。真っ先に目に入ったのは、鍋を叩き付けられて、気を失っているストライクだった。鍋は二つに割れていたが、すぐに囲炉裏に掛かっていた物だと気付いた。青井が懐中電灯を取り付ける時、外して囲炉裏の横に置いたのが、どうしてこんなことに。青井は部屋の中央を見た。冷気をダダ漏れにしたマニューラが、鋭い爪を床に突き刺している。
マニューラが口を開いた。口元に冷気が収束していく。
「ミーム、やめ」
海原の声がした。マニューラは目を見開くと、ブルリと体を震わせた。その途端、マニューラの体が溶けてメタモンの姿に戻る。メタモンは怒気の籠り籠った目で、倒れたストライクを睨み続けている。
青井はストライクの容態を見た。気を失っているだけのようだ。目を覚ましてから、オレンの実をやれば大丈夫だろう。そして、海原の方へ向かう。囲炉裏の近くにいるメタモンは、遠回りして避けた。
海原は壁に背中を預けて、座り込んでいた。真壁が自分の荷物から救急箱を引きずり出した。
「傷、見せろ」
海原が首を振った。「見せろと言ったら見せろ」二度目で、ようやく海原は右腕を出した。真壁が袖を破る。現れた傷口を見て、青井は顔をしかめた。切り傷だ。肉まで切れているが、動脈は切れていない。しかし、まだ血が流れ出している。
「浅いよ」
「そら、普段死体を見てる人間には浅い傷だろうさ」
言いながら、真壁は手早く包帯を巻いた。巻き終えると海原は腕を引っ込めて、再び傷口を押さえた。
青井はまだ気絶しているストライクを見た。真壁が騒々しく荷物を片付けている。まとめた荷物を蹴って壁際にやったところで、青井はやっとこさ、口を開いた。
「俺のバルキリーの所為だな。悪かった」
いくら青井だって、自分のポケモンが付けた傷くらい、分かる。本当は頭を下げて「申し訳ありませんでした」とでも言うべきところだが、今の青井には、それだけ絞り出すのが精一杯だった。
海原は顔を背けた。「ミーム」メタモンを呼び戻す。そして、「別にいい」と言った。
「良くない。これは立派な業務上過失傷害だ」
「この程度では立件されない」
「そういうことを言ってるんじゃねえよ」
海原は怪我をしていない方の手で、メタモンを持ち上げた。
「どうせミームが怒らせるようなこと言ったんだよ」
「お前なあ!」
青井は大声を出した。海原が寸の間驚いたように青井を見上げた。真壁は素知らぬ顔で、自分の荷物を転がしていた。青井は構わず続けた。
「そういう態度が腹立つんだ。こっちが悪いっつってんのに、やたらと庇われんのも癪に障るんだよ。俺にだってポケモントレーナーとしてのプライドはある。自分のポケモンの不始末の責任を取るくらいはな!」
「でも今回は青井の責任じゃない。バルキリーをミームが怒らせたから鎌を振ったんだ。ミームを止めなかった俺の責任だろ」
青井は近くの壁を殴りつけた。
「ふざけんな!」
「ふざけてない。俺なりに公平に判断してるつもりだ。ところで」
「話を逸らすな!」
「もうそのくらいにしとけよ」
真壁がどちらに言うともなく、言った。
「で、何だ? 海原」
「晶子がいない」
その言葉で、二人ははじめて晶子が姿を消していることに気が付いた。リュックサックと上着は残っている。真壁が言った。
「厠じゃないか?」
「さっきまではいたんだ。俺が斬られた時はまだ寝てた」
青井は唸った。晶子はあの騒ぎを放っておくような、薄情な女ではない。
「探してくる」
青井は真壁から懐中電灯を受け取ると、ストライクを起こして、隣の部屋に移った。海原も見張りだといったって、眠くて意識が飛んで、その間に晶子がどっか行ったんだろう。そう思いながら、青井は真っ暗な廊下を進んでいった。
〜
「さて」
青井が行ったのを確認すると、真壁は海原の近くに腰を下ろした。荷物から毛布を引っ張り出して、海原に投げる。
「ちょっと寝とけ。厄介なことになりそうだしな」
「じゃあ、青井が戻るまで。お言葉に甘えるよ」
海原は毛布を被って横になりつつ、「しかし、お前はなんでこんな物持ってきたんだ? たかが旅行なのに」と問うた。
「面倒くせえから、トレーナー修行してた時のをそのまま持ってきたんだよ」
「なるほど」
真壁は囲炉裏の近くに座った。そして、パンフレットを広げると、懐中電灯の明かりで読み始めた。海原はピクリとも動かない。疲れていたのだろう。真壁はパンフレットの一字一句も見逃さないよう、目を皿のようにして読み続けた。
時を止めた村。
セレビィは自分を助けた女性に恋をした。
女性の時を止めたいと願い、事実その通りにした。
そして、ある男性に聖剣で調伏された。
真壁の頭にある可能性が閃いた。悪い可能性だ。もしかすると、晶子は……
「いない。家のどこにもだ」
青井が騒々しく戻ってきた。寝ていた海原が身を起こす。「なんだ、寝てたのか?」「ああ」「それよりだ」
青井が懐中電灯を真壁に投げた。真壁は受け損ねて落とした。
「アキちゃんが見つからねえ。トイレにも行ったし、屋根裏も探してみたんだが」
「もしかすると」
真壁は今しがた思い付いた可能性を話した。
「セレビィに連れていかれたんじゃないか。セレビィに惚れられて、さ」
「何?」
青井が狼狽えた声を出した。
「ってことは何だ。アキちゃんはその、昔語りの時の巫女みたいに?」
「可能性の話だがな」
青井は腕を組んで考え込んだ。後ろでストライクも同じポーズを取っている。真壁はもう一度パンフレットに目を落とした。聖剣についての記述はない。外部に漏らしてはならない、という約束があるのかもしれない。セレビィは災厄をもたらした悪神だったが、村の守り神でもあるのだ。それを調伏させる力の正体を、村の敵に悟られてはまずい、というところか。
「行こう」
青井が立ち上がった。
「どこに? 手がかりなんて何もないんだぞ」
「黙って座って考えてるのは性に合わない。それにまあ」
青井は後ろのストライクを見やった。
「いざとなったらこいつをボールに入れるなり、鳥居の前で座って待ってるなりするさ。アキちゃんも今一人で心細いだろうしな。それを考えると苦にはならん」
彼女のことだから今頃セレビィと談笑しているだろう、と真壁は思ったが、口には出さなかった。
青井は海原の方を向くと、やや言い難そうに、
「海原、行けるか」と口にした。
海原は頷くと、毛布を丸めて真壁に寄越した。
まずは社に続く階段に行ってみたが、やはり途中からストライクが進めなくなった。
「こうなったら」
青井がストライクにモンスターボールを向ける。しかし、横から海原に止められた。
「貴重な戦力を減らそうとするのはやめてくれ」
海原が苦言を呈した。青井の腕を押さえた手が、今度は怪我をした右腕に添えられる。
「それと、虫除けがなされてるくらいだから、相手も虫ポケモンが苦手なんだろう。バルキリーがいるだけでも、セレビィの手出しを避けられるかもしれない」
「分かったよ、やめるよ」
青井は五月蝿そうに手を振った。真壁が海原の右腕を指差した。
「海原、腕、大丈夫か?」
「ああ」
海原が腕を下ろした。
「悪かったな」青井が小さな声で呟く。
ふいと海原が背を向けた。そして、そのまま歩き出す。真壁は慌てて海原を呼び止めようとした。
「おい、どうしたんだ」
「下層に降りてみる」
海原はこちらを振り向かず、淡々とした調子で答えた。
「そっちは中層を調べといてくれ」
真壁はパンフレットを広げて、地図を確かめた。上層に社、中層に主要施設、下層に田畑。村の大きな構造は昔から変わっていないはずだ。
「下層には多分、何にもないぞ」
「刑事の性だよ。虱潰しにやらないと気が済まないんだ。それと、念の為に行くだけだから、俺一人でいい。じゃあ、青井は真壁を頼む」
そう口早に言って、海原は月明かりの届かない向こうへと姿を消した。
「ほっとけ」
海原を追い掛けようと一歩踏み出した真壁を、青井が止めた。
「強情な奴だから。それより、こっちもこっちで調べちまおうぜ」
真壁は海原が消えた方向を一瞥したが、結局諦めて、青井に付いていった。海原は強情だが、道理の通らないことをやる人間じゃない。それにあの言い方、まるで、自分が既にセレビィの攻撃を受けていたみたいじゃないか?
「ああ、さっさと片付けよう」
真壁は青井にそう、声を掛けた。こちらにはストライクがいる。海原よりかはいくらか安全だろうが、さっさと調べるに越したことはない。時間は無限にあるが、どうも、猶予はなさそうだ。
三軒目の民家を調べたところで、新聞を見つけた。今から二十年前の四月と記されている。捲って読んでみると、真ん中程の面の端に、太陰暦で十五日と書かれていた。この世界は、二十年前の満月の夜で、止まっているらしい。新聞も捲りやすいことに、真壁は気が付いた。物質も、二十年前の状態のまま、保存されているのだろうか。
それから四軒、五軒、六軒と調べ、途中で数えるのを放棄したが、これといった成果は得られなかった。「捜査はこういうもんだ」と言って、青井は気にする様子がない。疲れも感じさせない。流石本職の刑事だな、と真壁は思った。
「人がいないのは、何故なんだろうな」
間取りも変わらない民家を、既に十軒は調べた後で、真壁はポツリと疑問を口にした。時を止めただけなら、人がいても良さそうなものだ。
「疲れるくらいだから、死んだのかもしれん」
「だがそれだと、セレビィが時の巫女の時間を止めたという話に反する。あるいは、村の時間を丸ごと止めても、人間の時間は一人分しか止まらないのか。そうか、あるいは」
真壁は言いかけて、やめた。あまりに悪趣味だ。しかし案の定、青井に言われた。
「何だよ? 途中でやめられたら気になる」
真壁は「ああ、いや」と少し言い淀んで、結局、白状した。
「発狂したのかと」
「なるほどなあ」
青井はしかめっ面で、一寸だって動きそうもない満月を見上げた。
「いくら綺麗な月だって、そればっかじゃなあ」
そうして、またしばらく歩いた先に、今まで見てきた民家より、少し大きくて、心持ち豪勢な家を見つけた。
「村長の家かもしれないな」
青井が進んで、観音開きの扉に手を掛ける。扉は難なく開いた。
「鍵を掛ける習慣がなくて助かるな」
真壁の台詞に、青井は頷いた。
青井が警戒しながら家に踏み込む。その次にストライクが入り込んで、間を空けずに真壁が滑り込んだ。
「多分、旅人なんかをここに呼んだんだろうな」
応接間らしい。木製の椅子に机が並べてある。壁や棚にクスノキのシンボルを織り込んだ布が掛けられてあった。
「クスノキか」
青井が慣れた手付きでタンスの引き出しを調べていくのを見ながら、真壁は椅子に腰掛けた。手伝おうとしたら怒るので、勝手にやらせておく方がい、
「うわっ」
真壁の口から悲鳴が出た。座面が抜けた。
青井の手を借りて立ち上がると、真壁は椅子を調べた。
「座面と椅子の足を繋ぐネジが外れたんだよ。ネジ穴が腐ってたみたいだ」
ため息をつく真壁の横で、青井がもう一つの椅子の座面を押した。一度押しても崩れなかったが、力を込めて叩くと座面が落ちた。机の方は叩いてもびくともしない。
「多分、元から腐ってたんだろ」
とりあえず、家の探索を続けることにした。しかし、目ぼしい物は見当たらない。三つ、四つと部屋を調べている折に、不意に青井が「あいつは」と口にした。
「なんで俺にだけああいう態度なんだろうな」
「へえ、どういう態度だ?」
相槌を打ちつつ、誰のことだろうと真壁は考えた。ややあって、海原のことか、と気付く。
「他の奴は絶対庇ったりしないのにな」
「そうなのか」
「ああ」
青井は頷いた。
「出来のいい同期で友人だよ。その上庇われて、こっちは劣等感ばっかりだ」
「大変だな」
青井は頷く。そして、投げやりに言った。
「女もああいうのが好きなんだろうな」
それから、部屋の引き出しを乱暴に開け始めた。
真壁たち三人の中で、ある文脈で“女”といえば、特定の一人のことを指した。彼女については、当たり障りのない話題でしか触れない。抜け駆けもしない。それが三人の不文律となっていた。
彼女と誰かが付き合い始めることで、彼女を含めた四人の関係が変わってしまうのが恐ろしいのだと、真壁は分かっていた。真壁も、青井も、そして海原も、彼女に恋心を抱いているのは分かり切っているのに、誰もその先に進めない。
「俺たちの時も止まってんだな」
真壁はごく小さな声で自嘲した。
部屋を虱潰しに調べて、最奥まで来た。文机にタンスが一つという、質素な部屋だ。青井が早速、タンスを調べ始める。真壁は文机の方を見た。机に置かれた紙に、『お守り』とだけ書かれている。メモ書きのようだ。
「おい、真壁、これ」
青井が大声を出した。真壁は青井が持っている物を見た。カセットテープだ。
「ほら早く」と急かされて、真壁はいつも持ち歩いているテープレコーダーを出した。一度停止ボタンを押して止めてから、カセットテープを入れ替える。巻き戻す時間がもどかしかった。テープが全て巻き終わってから、真壁は再生ボタンを押し込んだ。静かにリールが回り出す。「えっと」ここにいない、女性の声が聞こえた。
「ちょっと間が開きました。ごめんなさい。えっと、ほら、もうすぐお祭りだから忙しくて」
女性は喋り慣れていないのか、「えっと」や「あの」を繰り返す。しかしそれは、すぐに恥ずかしさからくるものだと知れる。
「時の巫女の私が時の勇士の貴方に……貴方を好きになるなんて、なんか、不思議ですよね。あ、今回はこういう話をしたかったわけでは。あの、貴方が送ってきた前のテープ」
無音。
「あのですね」
女性は咳払いした。
「今回駆け落ちをするにあたりまして、私なりに色々考えて、調べてみました」
青井と真壁は顔を見合わせた。しかし、すぐに続きを傾聴する姿勢になる。
「道は貴方が言ってた道でいいと思います。ちょっと湿気が気になりますけど。冗談ですよ。で、決行の日ですが、出来れば明後日に。禊ぎの時ならお付きの目も少なくなりますし。その日が確か町に市の立つ日でしたよね。
それでですね、貴方には何とかして、聖剣を持ち出してきてほしいんです。その、大丈夫だと思いますけど、セレビィ様に見つかった時の為に、念の為。お祭りの前に練習したいとか一目見たいとか言って。出来ればでいいですが、お願いします」
二人は随分長い間、耳を澄ませていた。しかし、それ以上カセットテープは音を出さなかった。
カセットテープが終わりまで巻かれる。真壁は黙ってカセットテープをひっくり返すと、再生ボタンを押した。古臭い歌が流れてきた。ラジオの放送を録音したものらしかった。
「こっちはダミーっぽいな」と青井が肩の力を抜いた。
カセットテープを取り出しながら、真壁が言った。
「音で恋文か。ロマンチックだが、危ないとは思わなかったんだろうか。隣の部屋に誰かいて、聞かれるかもしれないのに」
「普通に手紙に書いて、盗み見されるのと変わんねえよ。でも確かに、妙だよなあ」
それからもう少し部屋を探してみたが、ボロボロになった木製のアクセサリーぐらいしか見つからなかった。
この家に、これ以上目ぼしい物はなさそうだと判断して、真壁と青井は家の玄関へ戻りながら話す。
「何代目か分からないが、時の巫女が時の勇士と駆け落ちしようとしていた」
「駆け落ちというからには、本当は結ばれない運命だったんだろうな」
運命、という似合わない言葉が青井から出てきたので、真壁の思考が一瞬停止した。
「とにかく」と言って持ち直す。
「セレビィが祀られている村で、時の巫女と勇士が駆け落ちしようとした。セレビィに見つかった時に備えて、聖剣を準備しようとしていた」
「セレビィが時の巫女に惚れてた、とか」
「なるほど」
判断材料が少ないが、それで辻褄は合いそうだと真壁は考えた。
「セレビィに惚れられた時の巫女は、時の勇士と愛の逃避行に出ようと考えた。時の勇士は聖剣を持っていたとして。駆け落ちは」
真壁は頭の中で仮設を組み立てた。
「成功したんだ。セレビィは逃げてしまった時の巫女の面影を感じて、晶子を攫った」
これで辻褄は合いそうだ、と手を打つ。「いや、でも」と青井が反意を唱えた。
「それだと、なんでこの村の時が止まってるんだ?」
「ああ、そうか」
真壁はもう一度考えた。今度は青井が先に答えを出す。
「駆け落ちは失敗した。セレビィは時の巫女を囲い込む為、村の時を止めた」
「すると、どうして晶子を攫ったのかが分からなくなる」
青井は腕を組んで唸った。
「この問題は後にしよう」真壁は言った。
「巫女と勇士が恋仲だった。セレビィに見つかるとまずかった。今はこれだけ分かればいい」
「お前、刑事に向いてるかもな」
青井が感心したように言った。
二人は表に出た。「あれ」同時に声が出た。そして、二人同時に立ち止まる。この家に入る時にはいなかった者が、道の中央に鎮座していた。
「くるっぽ」
「ポッポだよな?」
真壁は懐中電灯の光をその物体に向けた。毛羽立ち、汚れているが、どうやらポッポのようだ。
「迷い込んだのか?」
真壁は背を低くすると、ポッポにゆっくりと近付いた。汚れたポッポは座り込んだまま、逃げる気配も見せない。「疲れてるんじゃないか」と青井が言った。
真壁はポッポに距離を詰めていく。ポッポは真壁の手が触れる所まで来ても逃げ出さず、それどころか、自分から近付いてきたではないか。真壁は腕を地面に下ろす。ポッポはごく自然に、真壁の腕に乗っかった。
真壁は立ち上がった。ポッポは真壁の腕に掴まっている。
「似合ってるぞ」と青井が言った。
「オレンの実とか、ないか? こいつ、体力なくなってるみたいだ」
真壁はポッポを撫でながら言った。羽繕いをする元気もないようだ。茶色と白の境目が分からないくらい、汚れている。
青井からオレンの実を一つ受け取って、ポッポに差し出した。ポッポは凄まじい勢いでオレンの実を食べ尽くして、真壁の指まで齧りそうになった。「こら、こいつ」と言いつつポッポと戯れている真壁を、青井がニヤニヤしながら眺めている。
「なんだよ、ったく」
「いや、仲が良いなと思って。ゲットしてやったらどうだ?」
「そうだな。ポッポ、俺がゲットしてもいいか?」
ポッポはくるっぽ、と鳴くと、真壁の肩に飛び移り、そこから頭の上に飛び移った。正直、痛いし重いが、これがこのポッポなりのオーケーの出し方なのだと真壁は受け取った。
「じゃ、よろしく、ポッポ」
真壁が腕を出すと、ポッポは躊躇いなくそこに飛び移った。
「こいつをゲットする為にも、この村を出なきゃな」
「そうだな」
ポッポを撫でながら、真壁は自分の口元が綻んでいることに気が付いた。
自分のポケモンを持つのは久しぶりだった。トレーナーをしていた頃のポケモンたちは、就職する時に全て他人に譲ってしまっている。仕事とポケモンの世話の両立に自信が持てなかった所為だが、今は仕事にも慣れてきたし、このポッポと暮らし始めるのはいいかもしれない。
さて、ポッポの世話には何が要るだろうか。考え事をしながらポッポを撫でていると、指に奇妙な物が当たった。
おやと思い、ポッポをひっくり返す。ポッポの足に、紙が括りつけられていた。
「伝書ポッポか」
青井が紙を外そうとすると、今までの脳天気ぶりはどこへやら、電光石火の速さで首を伸ばして、青井の指を突いた。青井が慌てて指を引っ込める。
「痛かったぞ」
「はは、ごめんごめん。でも、宛先以外には手紙を渡さないなんて、伝書ポッポの鑑じゃないか」
言いながら、真壁はおかしなことに気付いた。こいつは誰に手紙を届けに来たんだ?
二人と一匹にさらにもう一匹加わって、一行は村のさらに奥へと進んだ。
「おお」と青井が感嘆の声を漏らした。
「ここが村の中心部か」
「だろうな」
真壁も青井の隣に並ぶと、上方を仰いで言った。巨大なクスノキ。幹には注連縄が巻かれている。
「これが村のシンボルなんだろうな」
青井はクスノキの周りを回って、注意深く調べている。真壁は今しがた懐いたポッポを指先で撫でてやっていた。
「おい、真壁!」
青井が大声を出した。手招きしている。真壁は急いで戻った。
「どうした?」
「これ見ろよ」
青井が懐中電灯で照らしたものを見る。『エリナ』『マイコ』『カヨ』と、クスノキの肌に彫りつけてあった。
「どこの世界にも、こういう傷を付ける馬鹿はいるらしい」
「でもってこれだよ」
青井が懐中電灯を動かした先には、エリナマイコカヨがこの村を訪れた年月日らしきものが彫られていた。
「昨日の日付だ。いや、この世界じゃ時間の流れが分かんねえな。とにかく、俺たちがこの村に来た時の日付だ」
青井は立ち上がる。「どういうことかな」
ポッポは飛び上がると、真壁の上空をくるくると飛び回って、くるっぽーと鳴いた。
真壁は木に付けられた落書きを見る。
「ここだけ時空を越えた、ってことか?」
この村は一体、どうなってるんだ。
〜
中層と下層を繋ぐ階段は短かった。海原はさっさと石段を降りると、右腕の包帯を外し始めた。包帯は真っ赤に染まっていた。右腕も、血がべったりと貼り付いている。
「困ったな」
「何が?」
海原のものではない、変声期前の少年のような声がした。声の主は、海原の肩から顔を出す。メタモンのミームだ。
「うわあ、酷い。あのバカマキリ」
「人のポケモンを悪く言うもんじゃない」
海原はメタモンが喋り出したことは気にせず、自分の右腕を押さえた。「やっぱり、血が止まらない」
「じゃ、僕が止血するよ」
メタモンが言った。そして、自分の体を平べったくして、くるりと海原の腕に巻き付く。しばらく巻き方を模索していたが、やがて動きを落ち着かせると、紫の一反木綿のような格好のまま、こう言った。
「変だね。自然治癒力が働いてないみたい。仕方ないから、管で太い静脈を繋いどくよ」
「ありがとな」
「こんな芸当できるメタモンって僕だけだと思うから、もっと感謝してね」
「その減らず口を治したら考えてやる」
それからメタモンは体を伸ばすと、その一部分を懐中電灯に変化させた。懐中電灯部分を海原が持つ。そして、周囲を照らした。
「明かりがあると、違うな」
「同時に包帯にも懐中電灯になれる、そんな素敵な僕に掛ける言葉ってもっと他にない?」
「この状態でも喋り続けるお前に吃驚するよ」
軽口を叩きながら、海原は残りの変身回数のことを考えていた。行きに一回、空き家で一回、ここで二回、あと六回だ。
村の下層部分を、懐中電灯の光で照らす。真壁が言っていた通り、田畑が主らしい。農作業に従事する人の住居か、あるいは作業小屋か、家らしき物もいくつか見える。海原は農道を歩き出した。田畑に光を当てる。
「うわあ、酷い。枯れてるよ」
メタモンが声を上げた。
海原は田んぼだか畑だかに降りて、しゃがみ込んだ。規則正しく、同じ種類の植物が植えられている。何かの苗だろうか。どれも瑞々しく、枯れている状態とは程遠い。
「これ、何だ? ネギ?」
「稲だよ」
海原の質問に、メタモンが答えた。そして、「ああ」と合点したように声を上げて、こう言った。
「水が枯れてるんだよ。ここ、田んぼなのに」
海原は立ち上がると、先へ進んだ。今度は海原にも一目で畑と分かる区画に出た。規則正しく立てた支柱に、何かの植物が絡み付いていた。これも触ってみるが、瑞々しい。しかし、実は付けていなかった。
「時間が止まってるから、成長もしないし、実も付けないんだろうな」
「そうだね」
メタモンが頷く。水が枯れたのは、時間が止まって、水が流れなくなった為だろうか。
「人間はどうするのかな」お喋りなメタモンがまた口を開いた。
「この状況を見る限り、成長や老化はしないだろうね。その為のエネルギーも必要ない。でも、運動した時に消費するエネルギーはどうしようもないからね。僕らポケモンは小さくなってボングリの中とかに逃げ込めばいいんだけど。エネルギーが賄えないから、出られなくなるけど、死ぬよりマシ」
そこまで一息に言った後、メタモンはまたもや喋り出した。
「ああ、だからさっき傷が治らなかったんだね。傷が出来た状態で、時が止まってたんだ。出来れば、傷が出来る前の状態で時に止まってほしかったね」
海原は黙って頷いた。田んぼや畑の傍に建っていた小屋の中も調べてみたが、ごく普通に農作業の道具が置かれていた他は、何もなかった。海原が小屋を調べている間も、メタモンはずっと喋り続けていた。その大半を聞き流す。外に出ると、先程と変わらない景色が立ち現れる。枯れることはないが、実ることもない植物の群落。そして晶子のことを考えた。例えば彼女がずっと美しいままでいるからといって、好きになれるだろうか。海原はかぶりを振る。それはない。海原は、草花が枯れ、実る度に、悲しみ、喜ぶ彼女のことが。そこまで考えて、海原は「手がかりらしいのはないな」と口に出す。さっさと今しがた考えたことを振り払って歩き出した。
「あ、あれ、見て」
メタモンが懐中電灯を海原の手から奪い取って、別方向に向けた。
「井戸だ」
「水が枯れてるから、何か見つかるかも」
海原は頷くと、井戸に歩み寄った。メタモンが懐中電灯を井戸の中に向けるが、深すぎてよく見えない。
井戸の中に足場があった。梯子の段のように作られたそれを使い、井戸の底に下りる。枯れ井戸にかつて水を運んでいた道が、ぽっかりと口を開けていた。海原にも楽々通れそうだ。海原は井戸の中の道を少し見た後、井戸の底に落ちた物を改めた。しかし、誰かの食べ残しや、落としたハンカチに煙草の吸殻くらいしか見つからなかった。海原は懐中電灯を持ち直して、井戸の道を進み出す。
水は枯れているが、やはり井戸らしい。じめじめした感じが、肌にまとわりつく。
井戸から差し込んでいた月の光は間もなく見えなくなって、頼れるのは懐中電灯の光だけになった。引き伸ばされた楕円状の光を見つめて、歩く。後ろには闇ばかりが残る。重苦しい道をひたすら進むと、唐突にそれが現れた。
「紙?」
それも、一枚や二枚ではない。
地面から拾い上げようとしたが、紙がふやけていて、触るだけで破れてしまう。拾うことは諦めて、紙に書いてある内容を読むことにした。海原が来た方向からでは逆さまで読み辛いので、一度飛び越えて、それから読み始めた。
「死ね、出てけ、間男」
「一々音読しなくていい」
それから、海原は地面に散らばった紙を、出来る限り解読してみることにした。
ほとんどが単純な罵詈雑言だ。死ね、出てけ、殺すぞが多い。間男、ふしだら、阿婆擦れという言葉もあった。浮気に気付いた誰かが、浮気した伴侶とその浮気相手をひたすらに罵りながら、出て行けと喚いている。そんな印象を持った。
海原はさらに懐中電灯の光を動かす。他のより細かい字がびっしりならんだ紙を発見した。その冒頭を読んで、海原は眉を顰める。
「時の巫女は私にだけ仕えていればいい。他の男に心を寄せるなど言語道断」
「音読はしなくていいんじゃなかったの?」
軽口を叩くメタモンを無視して、海原はその細かく書かれた紙の方に一歩踏み出した。その時に、懐中電灯が紙以外の異質なものを照らしだした。
海原は指先でその物体を突いた。茶色く朽ち果てているが、どうやら木片のようだ。今度は手を伸ばして持ち上げてみる。木の繊維の走り方が、途中で交錯している。木でパーツを作って、後で組み合わせた物らしい。長い間ここに置かれて、腐ってしまったようだ。そう考えて、すぐにおかしなことに気付く。この村で、物が朽ち果てることなどないはずだ。その証拠に、目の前の紙は濡れているものの、きちんと原型を保っている。
海原は木片を叩いた。叩いた場所から、ボロボロと破片になって崩れていく。
「クスノキだね」
メタモンが言った。
「クスノキ?」
「そう。その木片」
海原は木片をしばらく眺めた後、紙の解読に戻った。しかし、せっかく見つけた細かい字の書かれた紙も、同じようなことが延々書かれているだけで、大した収獲はなかった。
しかし、セレビィが時の巫女に思いを寄せ、その巫女が男と逃げようとした為、激しく怒ったというのだけは分かった。そして、この道を使って出奔しようとしたところを取り押さえたのだろう。
また別の紙が見つかった。『私とずっと一緒にいましょう』『老いも死も恐れることはありません、ずっと一緒』
「うへえ」
メタモンが身震いした。
「今まで見た中で、最悪の口説き文句だよ」
「そうだな」
巫女の方は連れ戻されたのだろう。
これ以上、ここにいても収獲はなさそうだ。そう判断して、海原は立ち上がる。少し目眩がした。紙を飛び越えて進む。その刹那、バン、と音がして、目の前に白い紙が現れた。立ち竦む間に、白い紙に、文字が浮かび上がる。
『今度もまた引き裂く気ですか』
真っ赤な字。
紙は水平に傾くと、海原の喉目掛けて真っ直ぐ飛んできた。横道の壁に、体ごとぶつかるようにして紙の進路から逃げた。赤い文字で染まった紙は海原を通り過ぎると、失速して地面に落ちる。
紙が飛んできた方向に懐中電灯を向ける。挿絵でしか見たことがない、幻のポケモンがそこにいた。
「なんだよ、今度もまたって。今まで引き裂かれたのもお前が悪いんだろうが!」
メタモンが高い声で騒いだ。
『黙れ。お前たちの言葉を聞く耳はありません』
再び赤い文字の浮かんだ紙が現れ、海原に飛びかかる。メタモンは懐中電灯の部位を、素早くブラッキーの頭に入れ替えた。そして、サイコキネシスで紙を撃ち落とす。フラッシュで明かりも絶えず、便利だが、極めて気持ち悪い。
『化け物め。だがここでお前たちの道を断つ』
「お前の行動の方がよっぽど化け物じみてるだろ!」
再び紙を撃ち落とす。
「晶子をどうして連れてった」
海原が聞く。
『殺すぞ』
その紙も撃ち落とされた。反動でブラッキーの頭がふらつく。海原が手を差し出して、メタモンを支えた。それを見たセレビィが、まるで口が裂けているかのように、ニタリと笑った。
何が起きたのか、全く分からなかった。気付いたら、セレビィが二匹向かい合っていた。片方はメタモンが変身したものだろう。
『思ったより厄介でした。私はここで一旦退きます』
『だが、お前たちの道は断つ』
セレビィは紙を残して、姿を消した。二枚の紙はセレビィが消えると同時に、地面に落ちた。
さっきのは何だったのだろう。右腕の傷を押さえて、今はセレビィの姿をしたメタモンの方へ、一歩進む。何かを踏みつけた。海原はそれを拾い上げて、ポケットに入れた。
「まずい、走って!」
メタモンが叫んだ。海原はその場から前に飛んだ。遅れてメタモンも海原の隣に滑り込む。その直後、鈍い振動が地面を走った。後ろを振り返ると、木の根ががっちりと組み合わさって、井戸の道を塞いでいた。
「危なかった」
メタモンが呟く。それからセレビィの変身を解くと、包帯と懐中電灯の姿に変身した。あと二回。海原は呟いた。
「さっき、あのセレビィ、時間を止めたよ、一瞬」
メタモンは戻る道すがら、さっきのセレビィとの戦闘について喋っていた。
「僕がブラッキーだったからかな。効くのが遅かったから、咄嗟にセレビィに変身してあいつを攻撃したんだ」
井戸に戻ると、梯子の段が全て落とされていた。メタモンがフワンテに変身して井戸を出る。月明かりを頼りにして歩く。あと一回。
中層と下層を繋ぐ石段に戻ると、石段が通れなくなっていた。
変身しようとしたメタモンを、海原が止めた。
「なんで?」
「もう一つ、変身してほしいものがある。今はいい」
「って言っても。登れないよ?」
メタモンの言葉で、海原は石段の方向を見た。石段の入り口が、木の根のバリケードで塞がれていた。そのバリケードが、かなり高い。横の斜面もほぼ崖みたいなものだ。道具がないと登れない。石段はその崖に切り込むように作ってあるので、石段を登りたければ、まず、木の根のバリケードを何とかして越えるしかない。
手を掛けてみる。取っ掛かりになる部分が全くと言っていい程なかった。
「ねえ、僕が変身した方が」
くるっぽ、と鳴き声がした。
くるっぽ、くるっぽ。月明かりではっきりと見えないが、どうやらポッポのようだ。ポッポは頻りにくるっぽと鳴くと、バリケードの向こうへ飛んでいった。そしてすぐに戻ってきた。ロープを持って。
「くるっぽ」
ポッポはバリケードの上に降り、ロープの一方を海原の方へ落とすと、もう一方をバリケードの向こう側に垂らした。海原はロープを手に取り、離す。ロープに結び目が作ってある。これなら、なんとか登れそうだ。
「あのポッポ、自分の鳴き声で位置把握して、月明かりでもぶつからないように飛んでるんだね。器用だね」
海原がメタモンの口を塞いだ。
「おい、海原、そこにいるのか?」
バリケードの向こうから、声が聞こえてきた。この声は青井だ。
「ああ」
「そっちは虱潰しに調べられたか」
真壁の声だ。
「ああ。そっちの首尾は」
「調べられる所は全部調べた」
再び、青井が答えた。
「そっちも調べたんならロープ使って戻ってこい」
「そうする」
海原は近くの木にロープを結び付けると、結び目に足を掛けて登った。バリケードを登り切ると、今度は滑り落ちるようにして向こうに降りた。
「ったく、危ねえよ!」
ロープを支えていた青井が、手を離して飛び退いた。
「ま、今回は許してやる。それで、何か分かったか」
「ああ」
バサバサと羽音がした。くるっぽ、と声がして、真壁の肩にポッポが停まった。よく見ると、右足に紙を結び付けてある。伝書ポッポだろう。
「そいつ、捕まえたのか?」
「まだ捕まえてはない。予約済みだ」
真壁がポッポを撫でる。「そうか」海原は口元を緩めた。
「それで、そっちは何か掴めたか?」
「おう、勿論だ」
青井は快活に笑ってみせると、石段を登り始めた。海原も後を追う。真壁が途中で切れたロープを回収して、最後に続いた。
三人は最初に投宿した民家に戻って、晶子の荷物を回収した。そしてそこで、今まで集めた情報を突き合わせる。
海原の話を聞いた真壁が、話をまとめた。
「つまりだ。二十年前、時の巫女と勇士が恋仲になった。ところが、時の巫女はセレビィに惚れられていて、その恋は許されそうもなかった。そこで、巫女と勇士は駆け落ちを企てた。
だが、その駆け落ちの計画がセレビィに知られてしまう。巫女と勇士は抜け道でセレビィに出くわした。勇士は聖剣でセレビィを調伏しようとしたが、返り討ちに合い、村から追放。巫女は連れ戻され、セレビィが時を止めた村に監禁された」
「でも、その後、巫女はこの村からいなくなった。逃げたか、死んだか。だからセレビィは時の巫女の代わりに、晶子を攫った」
海原が後を引き継ぐ。
「きっとそんなところだな」
青井がまとめた。
「聖剣のことは分からず仕舞いか?」
青井が困ったように海原の方を見た。海原はポケモンたちを見ていた。ストライクは相変わらずメタモンにご執心のようだ。海原の右腕をジロジロ見ている。ポッポは真壁の隣に、大人しくチョコンと座っていた。
「心当たりはある」
海原は少し躊躇ってから、そう切り出した。青井は海原の態度を気にせず、身を乗り出した。
「そうか。じゃあ早速聖剣でセレビィを」
「聖剣を持ってるわけじゃない。どういう物か推定しただけだ」
青井の言葉を遮る。ストライクを追い払ってから、海原はポツリと推定を口にした。
「クスノキで出来た剣だと思う」
「木剣ってことか?」
青井の問いに、海原は頷いた。真壁が「そうか」と呟く。
「村の中心にあったクスノキには昨日の日付が彫ってあった。クスノキだけはセレビィの力の影響を受けないんだろう。木のアクセサリーとか、俺が壊した椅子とか」
「壊した椅子?」
海原がオウム返しに尋ねると、真壁は「そんなことはどうでもいい」と言って続けた。
「クスノキで作った物は、年月相応に朽ちていったんだ。だから、クスノキで作った剣を使うと」
そこまで言って、真壁は首を傾げた。
「どうなるんだ」
「さあ。ただ、井戸の底の抜け道に、クスノキの木片が落ちてた」
青井が苛ついたように床を叩いた。
「それが聖剣だって保証は?」
「ない。全部俺の推測だ」
三人の間に、静寂が降りた。
メタモンの変身は、あと一回しか出来ない。その一回で正しい聖剣になれなければ、最悪、この世界で死ぬまで彷徨うことになる。慎重にならざるを得ないのは、当たり前だった。
「文句付けるわけじゃねえけど、失敗した人の剣ではなあ」青井がボソッと言った。
「そうだな」海原は大人しく同意した。
海原は立ち上がると、部屋の端へ行った。そして、今度は壁にもたれるようにして座り込んだ。その拍子に、ポケットの中の物が腰に当たった。
「調子悪いのか?」
「いいや」
真壁に生返事を寄越して、海原は自分のポケットの中にあった物を取り出した。出してから、これはどこで拾った物かと考える。
「それは?」
「確か、井戸の底で拾ったやつだ」
海原はそれを床に置いた。手の平に収まるくらいの、小さな容れ物。丸い瓶のような形で、短い口の部分には固く栓をしてあった。細い筆で、四季折々の風景が描き込まれている。
青井が手を伸ばして、瓶の封印を外そうとした。しかし、全く歯が立たず、真壁に渡した。真壁も挑戦してみるが、一度やって諦めた。真壁は瓶を床に置くと、「これはあれじゃないか」と言った。
「あれ、って何だ?」
青井が聞く。
「ほら、モンスターボールだよ」
真壁はそう言って、説明を始めた。
「モンスターボールって、プラスチック製とボングリ製以外にも、色々あるんだよ。陶器製とかガラス製とか。強いポケモンを捕まえるのに、鉄製のモンスターボールがいいと信じられてた時代もあった。それは迷信だけど。職人が作った陶器製のモンスターボールが貴族の間で流行して、一種のステータスとされてたこともある。これもそういうモンスターボールの一種じゃないか」
「これがモンスターボール」
青井は疑うように小瓶を見た。
「投げたら割れそうだけどな」
「うん、だから、投擲には向かない。そういうのは大体見せびらかす用とか、祭事用だから」
青井はまだ疑うように小瓶を見ていた。海原も、これがにわかにモンスターボールの一種だとは信じられなかった。
「中からポケモンが出てくりゃ、信じられるんだけどな」
青井はもう一度栓を抜こうとして、諦めた。
「時間が止まってるから、ポケモンはモンスターボールの外に出られない」
海原が言った。「ああ、そうだった」と青井が頭を掻いた。
「でも、中にどういうポケモンが入ってるか、気になるなあ」
「それは、確かに」
青井の言葉に、真壁が同意した。
「井戸の抜け道にあったんだろ? 巫女か勇士のポケモンだとしたら、この村の伝承に縁のあるポケモンかもしれないじゃないか」
「俺はそんなに深い意味があって言ったんじゃないけどな」
再び静寂が訪れた。三人とも、小瓶を見つめている。四季折々の景色が、細かく描き込まれた小瓶。
「お守り」ふと海原が呟いた。青井が不可思議そうに海原を見る。
「時の勇士の方の家に、メモ書きみたいにして書いて置いてあったんだよ。それがどうかしたか?」
海原は再び黙り込んだ。そして、ゆっくり、自分の考えを整理するように話し出す。
「どうも俺は、根本的に間違ってたらしい」
そして、青い目で二人を見た。
「村の神様を倒す方法なんて、観光案内に書くはずがなかったんだよ。青井が正しかった」
三人は再び鳥居の前まで来た。
小さな木片を青井が宙に投げ上げた。そして、戻ってきたそれを受け止める。
「本当に、これで大丈夫なのか?」
海原は「多分」と小さな声で答えた。
「何だ、頼りねえなあ」
「だったら、青井はここで待っておけば」
いつものように、淡々とした口調で海原が言う。青井が大仰に顔をしかめた。
「おいおい、お前一人に持ってかれちゃたまんねえぜ」
「死なば諸共だ」と真壁も笑顔で言ってのけた。
「真壁、それは意味が違う……」
「で、バルキリーがここを通る方法だが」
真壁は鳥居を見上げた。
「いざとなったら、バルキリー抜きで挑むしかないな」
青井が渋面を作った。
「出来れば、それは避けたい」
海原が呟く。
その時、真壁の肩に乗っていたポッポがくるっぽ、と鳴いた。
「どうした?」
真壁の問いに答えるように、くるっぽ、くるっぽと鳴きながら、ポッポは鳥居の上に飛び上がった。そして、何かを爪で引き裂いた。
頭上から紙片が降ってくる。
ストライクが前に進んだ。そして、難なく鳥居をくぐる。
「一体、どういう手品だ?」
青井が不思議そうにポッポを見上げた。ポッポは一声鳴くと、大きな紙片を掴んで真壁の所へ飛んで戻った。紙片には、奇妙な模様が描かれている。
「これが虫除けの御札だったってことかな」
ポッポは肯定するように鳴いた。
「ともかく、これで三対一だ。セレビィを懲らしめて、アキちゃんを連れて元の世界に戻ろう」
青井が拳を自分の手の平に打ち付けた。残りの二人も頷いた。
ストライクを先頭に、石段を登る。登り切ると、ごくありふれた神社らしい、拝殿が目に入った。入ってすぐ横には手水舎がある。左右にある建物は、お守りを買ったり、納めたりする所だろうか。狛犬の類はないようだ。
海原は拝殿の前まで進んで、周囲を見回した。晶子はどこにいるだろうか。
「おい、何やってんだよ?」
青井が声を荒げた。
海原が声のした方を見た。真壁が手水舎を覗き込んでいる。
「一応神社だから身を清めようと思ったんだが、肝心の水がない」
「馬鹿かお前。これから退治するってのに」
青井が大仰に肩を竦めた。
「戦の前でも、礼儀は大事だぜ。仕方ないから、賽銭だけで勘弁してもらおう」
そう言って、真壁は海原の隣に立つと、アルミ硬貨を賽銭箱に放り込んだ。鈴を鳴らす。
「どこぞの傍迷惑な神様をはっ倒せますように」
「願い事は口に出すもんじゃない」
「もう知らねえ、お前らは勝手にしろ!」
青井が叫んだ。だが、顔が笑っている。真壁も愉快げにニヤリと笑った。
『おや、随分丁寧ではありませんか』
ふわり、と白い紙が舞った。三人に緊張が走る。紙に書き付けられた文字は、今はまだ黒色だ。
『お相手致しましょう。どうぞ中へ』
二枚目の紙が、拝殿の横を回って奥へと飛んでいく。海原は二人の顔を見た。
「どうした、今更怖くなったんなら、留守番でもいいぜ」
青井が快活に笑った。
「いや、いい」
海原は頷くと、「行こう」と言った。
「言われなくとも」真壁が答えた。
拝殿の向こう側には、思いがけず広い空間が広がっていた。茶色い地面が顕になった四角い庭には、白い縄で四角い線が引かれており、ちょっとしたバトルフィールドになっているようだった。そのバトルフィールドの向こうの本殿に、彼女がいた。
「おおい、アキちゃん!」
青井が早速手を振る。「アキちゃん?」二度目は疑惑に満ちた声音となった。
晶子は青井の声に、全く反応しなかった。それどころか、身動ぎさえしない。晶子は困ったような、寂しそうな笑みを浮かべたまま、止まっていた。
アキちゃん、と叫びながら青井が本殿に向かって走り出した。その道をセレビィが遮った。
『鬱陶しいですよ』
青井の顔スレスレに、紙が飛んだ。
「おい、どういうことだ。彼女に何をした」
青井がセレビィに噛み付く。セレビィはそんな青井には頓着せず、固まったままの晶子にすっと近付くと、その頬に手を添えた。
『あなた方の想い人は、私がお預かり致しました。彼女こそ理想の女性、最初からこうすれば良かった』
真壁が手帳を取り出して、何か書き付けた。そして、そのページをセレビィに見せる。セレビィは晶子の隣から動かず、ただ少し目を細めた。また別の紙が出現する。
『彼女の時を完全に止めさせて貰いました。これで、死に別れることも、老いや空腹を恐れることもありません。前の巫女は耐え難い空腹を味あわせた挙句、手放してしまいましたが』
「手放した?」
青井が叫ぶ。セレビィは青井の方を見ていたが、口の動きで察したらしく、紙に続きを書き出した。
『この村より追放しました。その際、なんらかの形で戻ると約定しました故、こうして待っておりました』
腑に落ちない、と思った。海原は真壁を見た。同じように思っているらしいと見てとれた。
『彼女は戻りませんでしたが、約束は約束。この女性を身代わりとして、私の理想の村の完成とすることに致します。だがしかしそれには』
『あなた方三人が邪魔だ』
字が赤く染まった。
『一度目は聖剣で、二度目は飢餓で引き離されましたが、三度目の今、最早私たちを引き裂くものは存在しません』
セレビィがバトルフィールドに躍り出た。
『クスノキの守りを身に着けているようですが、圧倒的な力の前に、そのような小細工は意味を為さぬもの。あなた方には森の腐葉土と消えて頂きます』
「二度あることは三度あるってな。バルキリー!」
青井が威勢良く叫んだ。ストライクが飛ぶ。セレビィに距離を詰めて、両の鎌を袈裟懸けに振り抜いた。シザークロス。
「やったか?」
「いや、避けられてる」
真壁はポッポを腕に停まらせたまま、上空を注視した。海原は歯を食いしばって、腕を押さえた。
「上だ」
ストライクが上空に向けて威嚇の声を上げた。セレビィは、ストライクが届かない高みから、じっと見下ろしていた。
『かつての聖剣と同じ種のポケモンなら勝てるとでも? 私も敗北から学ぶのですよ』
セレビィの周囲を取り巻くように、純白の結晶体が発生した。水晶のような形のそれは、切っ先をストライクに向けて一直線に飛んだ。
原始の力――ストライクの弱点を突く技だ。食らえば重い。ストライクは両腕の鎌を振るって、原始の力の軌道を逸らした。セレビィが地面まで一気に降下して、地面スレスレで二撃目を放つ。
その技の軌道を追って、海原が叫んだ。
「青井!」
ストライクが上空に飛んで躱そうとして、その場に踏みとどまった。セレビィ、ストライク、青井と一直線に並んでいた。これでは躱せない。
原始の力が容赦なくストライクの体を弾き飛ばした。
「バルキリー、ごめん」
青井がストライクの横に片膝を付く。その顔の横にセレビィが現れた。セレビィが青井のこめかみに手をやった。と思うやいなや、青井がストライクと同じようにドサリと倒れた。
「何しやがった」
セレビィには聞こえていない。そもそも耳が聞こえないのだ。そう分かっていても、海原の思いは声に出た。
『祈り虫は大人しく、私に跪けば良いのです』
セレビィは海原の叫びなど一顧だにしない。そして、再び飛び上がった。
『今度はあなたですよ』
セレビィは真っ直ぐ真壁とポッポの元へ飛んで行った。真壁はポッポを放すと、両手を上げる。
セレビィは真壁の数メートル手前で止まった。
『あなたは物分かりが良いようだ』
そして踵を返すと、今度は海原の方へ向かってきた。
『おや? あの厄介なメタモンはどうしたのですか? いえ、答えなくて構いません』
セレビィは紙にそう書き出しつつ、愉悦の笑みを浮かべる。
『あなた、そのままでは失血死しますよ。それを待つのも心楽しいですが、そう』
『冥土の土産に、一つ、面白い話をしましょう』
セレビィは宙でくるりと回った。いつの間にか、紙の字も赤から黒へと戻っている。
『私の力がクスノキに通じないことは、もうご存知ですね? クスノキは私の力の源、いわば私の母。子が母に逆らえぬように、私の時を操る力はクスノキには掻き消されてしまうのです』
ふわりともう一枚紙がやってきた。
『それはいかなる場合も同じ。私がどんなに強い術を掛けて時を止めたとしても、クスノキの守りの前には無効化されてしまいます。では、どうしても時を止めたい者がいる場合、どうするか』
セレビィが猟奇的な視線を本殿へ向けた。
『その者に触れぬよう、結界を施すのですよ。この表六めが!』
破裂音がして、メタモンが舞い上がった。その手からクスノキの木片が落ちる。メタモンも続けて地面に落ちた。
『さて、舐めくさった真似をしてくれたあなたには、選択肢をあげましょう』
セレビィが再び海原の方を見た。
『今すぐ地獄に落ちるか』
「サイハテ、フリーフォール」
『苦しみ抜いて死ぬか』
海原は動揺を消してセレビィを見た。真壁の奴、何しれっと指示出してるんだ。あと、いつの間にポッポに名前を付けたんだ。
ポッポのサイハテは、突然セレビィの頭上に現れたかのように感じた。細身の鞘入りの剣を持ったまま、セレビィの頭も掴むと、そのまま地面に落下した。そして、剣を海原の方向に飛ばすと、素早く空へと舞い戻った。
セレビィが起き上がって、ポッポを見た。セレビィが飛び出す前に、海原は鞘を払って、セレビィを一打ちした。
『死ね』
赤文字で描かれる。
「やだね」と海原は呟いた。
海原は地面に伸びたままのメタモンを見た。
「おい、ミーム! 起きてるならさっさと変身しろ!」
メタモンはピクリとも動かない。起きているのか、伸びているのか。
海原は剣を右手で持って、右半身をセレビィに向けた。晶子の時間が止まったままなのが悔やまれる。彼女が動いていれば、きっとセレビィだって説得できると思ったのだが。
いや違う、と思った。判断ミスだ。どうしても彼女を助けたかった。
起こらなかった可能性より、今目の前のことだ。海原は剣を構えたまま、後ろに下がった。ストライク抜きで、セレビィを調伏しなければならない。その為に、ポッポ一匹以外に何が必要か。セレビィを確実に倒せるポケモンに、メタモンを変身させなければ。
「サイハテ、エアスラッシュ」
がら空きになっていたセレビィの背を、空気の刃が叩いた。セレビィが怯んだ隙に、間合いを詰めて突いた。その間にポッポが距離を取る。このままヒットアンドアウェイで倒せれば。そう思った矢先に、セレビィの体が光に包まれる。自己再生。僅かに与えたダメージも無に帰した。
「もう一度エアスラッシュ」
真壁の声に従って、ポッポが羽を振り上げる。羽を振り下ろすポッポを見据えて、セレビィは虚空から葉っぱを生み出すと、それにふうと息を吹きかけた。葉っぱはセレビィが手を離すと、ポッポへと飛んだ。向かってくる風の刃をすいすいと躱しながら。セレビィが飛ぶように複雑な動きをする葉っぱ――マジカルリーフは、ポッポの元へ難なく到達し、お守りとポッポを繋ぐ糸を切った。
セレビィが笑った。
『時よ止まれ』
ポッポが空中でピタリと止まる。そして、為す術なくセレビィから念力を食らって落下した。真壁が落下点に滑り込んで受け止めた。セレビィが海原を見た。
剣を左手に持ち替える。血が止まらない。感覚が消える、その前に。メタモンを何に変身させればいい。この状況から、逆転王手を打てるもの。考え出さなければならない。トレーナーなら。
セレビィの目が妖しく光った。念力の発動サイン。そうだ、簡単なことだ。
海原は右手を柄頭に添えると、セレビィ目掛けて一気に振り下ろした。セレビィが体を逸らす。外した。
「ミーム、セレビィに変身しろ!」
直後、肺が詰まったような感覚がして、咳き込む。地面に剣を突いた。
〜
頭が痛いと思ったら気絶していた。先鋒を務めてこれとは情けない。
青井はストライクの頬を叩いた。シュウ、と元気のない返事が返ってくる。戦えないだけで命に別状はなさそうだ。ひとまず胸を撫で下ろした。
しかし、問題は解決していない。セレビィは未だピンピンしている。セレビィが、海原に原始の力で止めを刺そうとしていた。その背後で光が弾ける。セレビィが後ろを向いた。光の中から飛び出した者に、驚愕の目を向ける。宙空から紙を取り出した。
『紛い物め、恥を知れ』
セレビィの殺意の籠った視線を受けて、セレビィは――メタモンは、楽しげに笑って宙空から紙を取り出した。
『その紛い物に今から負けるんだよ』
紙が凶器のように飛び出した。二枚とも、メタモンを狙って飛ぶ。しかし、メタモンは飛行術一つだけで、紙を躱してセレビィにそれを掠らせた。
『二十年も頭が停滞してたんじゃ、僕の動きは革新的すぎて付いてこれないかな?』
『若輩者め。私の真の力を思い知りなさい』
メタモンの動きが、寸の間止まる。しかし、すぐにセレビィの力を振り払って飛び上がった。セレビィの原始の力を見事に躱す。恐らくあれは、躱すことに専念している動き方だ。
ひゅう、と口笛を吹く。青井の目の前に、白い紙が降ってきた。
『天才メタモンの僕でも、セレビィの力をすぐにコピーするのは難しいから、僕が時間稼ぎしてる間に、僕の大事なご主人様の手当てでもしといてください。どうせ暇だろ。ミームより』
青井は紙を握り潰した。手当てはするが、一体どういう育て方をしたらこんな性格の悪いポケモンになるのか後で問い質さねばなるまい。
海原は、朦朧としているものの意識はあるらしかった。握ったままの剣から、手を引き剥がす。その瞬間、剣が地面から抜けて、空へ飛んでいった。危ねえよ、と思わず呟く。海原の右腕に包帯を適当に巻いてから、青井は空を見上げた。
『白熱の攻防戦ってやつだね、これは! と思ったけど、じいさんが一人で勝手に白熱してるだけだった』
メタモンは次々に言葉を叩きつけては、セレビィを怒らせている。放たれた原始の力を、同士討ちに持ち込んで自壊させる。それにセレビィが気を取られている内に、背後から剣を念力で操って強打。大量の紙が念力で巻き上げられ、メタモンに襲いかかる。メタモンは目を細めると、避けに集中した。しかし、周りを取り囲まれる。どうやってこの場を切り抜けるのかと思ったら、念力で強行突破を仕掛けた。
メタモンが本殿に飛び込む。晶子の両肩に手を置いた。目が醒めたみたいに、晶子が顔を上げる。メタモンは再びセレビィと同じ高さまで上昇した。
『さてどうする? 愛しの眠り姫が起きちゃったよ?』
『紛い物の力なんて上塗りしてやりましょう。これ以上邪魔はさせません』
『邪魔だって? 僕が正道だろ』
再び二匹は空中戦に突入した。しかし、この調子では決着が付かないだろう。一体メタモンはどうするつもりだ、と青井が考えていると、突然話しかけられた。
「ねえ、青井さん」
「おお、アキちゃん」
「ポケモン、出せるようになってるわ」
普段よりいくらか暗い表情で、晶子はそう言った。彼女の後ろに、ヘルガーとエーフィが控えている。彼女の意図が読めなくて、青井はただ「良かったな」としか言えなかった。
「青井さん、ちょっとだけフレちゃん貸してくれる?」
晶子の様子に違和感を感じながら、青井は言われた通り、ガーディのボールを晶子に渡した。彼女の意図を知ったのは、ボールを渡した後だ。
「ちょっとお灸を据えるわ」
そう言って彼女はガーディを出すと、テキパキと指示を出した。
「ヘル、大文字。フレちゃん、オーバーヒート。サンはヘルに手助け」
ヘルガーとガーディの二匹が腔内に炎を溜める。エーフィが額の宝玉をヘルガーの首に押し当てる。ヘルガーの火力が目に見えて増した。
「ミーム!」
晶子は上空にいるメタモンの名前を呼ぶと、飛ぶべき道筋を指し示す。メタモンが針路を変え、セレビィもそれを追う。メタモンが三匹の目の前を、垂直に降下する。セレビィがそれを追って降下した。セレビィがピタリと止まる。
「時よ止まれ」メタモンがニヤリと笑う。二匹の炎犬から解き放たれた業火が襲った。
セレビィがポトリと落ちる。晶子はセレビィを抱えると、「じゃ、私が勝ったから言うこと聞いてくれる?」とセレビィに問うた。
セレビィは黙って頷く。なるほど、これが調伏かと青井は思った。晶子はセレビィの耳が聞こえないことを忘れているようだが、セレビィは晶子に完全に気圧されていた。
「まず、私たちを元の世界に返すこと」
セレビィは頷いた。
「それから、こんな風に人を傷付けないで。私の大事な人を傷付けられて、私、すっごく悲しかった」
晶子はセレビィの目を見て話す。セレビィはコクコクと頷いた。そして、ややあって、紙を取り出した。
『不老不死をもたらす力。これで喜んでもらえると思った』
晶子はパチパチと瞬きして紙を見つめた。
「ごめんなさい」
そう言うと、ここまで運ばれてきた自分の荷物の中から、手帳とペンを取り出して、さっき言ったことを書き付けた。それをセレビィに見せてから、続きにこう書き付けた。
『きっと、それは使い方を間違えてる。私は嬉しくなかった』
セレビィは触覚を垂れ下げると、フラフラとバトルフィールドの中央に飛んだ。ポトリと地面に落ち、本殿に手を翳す。すると、本殿から光が溢れてきた。あそこから帰れるのだろう。
青井は海原に肩を貸して、立ち上がらせた。こんなにボロボロになったのに、悪役があんなにしょぼくれてるんじゃ、報われないよなあ、と青井は思った。
青井と海原は本殿に踏み込んだ。床も壁も天井も光っていて、上下左右の境目のない部屋に入り込んだかのようだ。青井は海原を床に下ろした。メタモンの姿に戻ったミームが続けて入り、海原の傍に走り寄った。続いて、青井のガーディとストライクが来る。真壁も来る。晶子のヘルガーとエーフィが来て、それから晶子が本殿に入った。
「さよなら、セレビィ」
晶子が小さく呟いた。その言葉はセレビィには聞こえない。
不意に羽音がした。真壁のポッポが、セレビィの目の前に降り、そして、足に括りつけられた手紙を差し出した。
セレビィは腕を伸ばし、小さな手で不器用に手紙を外した。クシャクシャになったそれを広げ、読み出す。セレビィの大きな目に、みるみる涙が溢れてきた。
ポッポが飛び立って、真壁の胸元に飛び込んだ。光が強くなる。扉が閉まる。閉じかけた扉の隙間から、一枚の紙が飛び込んできた。
『彼女は約束を守ってくれた。心はここに帰ってきてくれた。だから、ごめんなさい。ありがとう。私からあなた方に、時と森の祝福を』
目の前が真っ白になって、見えなくなった。
〜
観音開きの扉を開けて、外に出た。陽の光が、広い庭いっぱいに降り注いでいた。真壁の肩で、ポッポが嬉しそうに鳴いた。
「お日様がありがたく感じるな」
真壁はポッポを撫でる。さて、モンスターボールを買わないと、と呟く。
続いて晶子と青井が出てきた。続いて彼らのポケモンが出てくる。ストライクにメタモンが囁いているのが聞こえてきた。「な。異種間恋愛ってのはうまくいかないんだ」ストライクはそれを聞いて項垂れていた。誰が誰に種族の壁を越えて恋慕していたのだろうか。
最後に本堂から出てきた海原が、ポケットから何かを取り出した。彩色の美しい小瓶。変わり種のモンスターボールだ。時を止めた村から持ってきてしまったらしい。
「どうするんだ、それ?」
真壁が尋ねる。海原は黙って瓶の封印を解いた。時が流れている為か、瓶の蓋は簡単に外れて、中からポケモンが出現する時の光が出てきた。光が地上に触れて、弾ける。
「ストライクか。いい体してんな」
青井が興味ありげに言った。なるほどそれは、青井のよりも体が大きくて全体的にがっしりしたストライクだった。鎌も、白刃のように光っている。
「聖剣か、その子孫かもしれないな」
真壁が言った。
突然現れたストライクに、青井のストライクが反応した。いそいそと鎌を擦りながら近付いて、顔を寄せる。聖剣のストライクはぎょっと身を引くと、素早く羽を広げて飛んで逃げてしまった。
「何やってんだよ、バルキリー」
青井がストライクをボールに戻す。
「現金な奴」メタモンがごく小さな声で呟いた。
青井がガーディを、晶子がヘルガーとエーフィをそれぞれのボールに戻した。それから、二人が海原の方を見て言う。
「海原、大丈夫か?」
「海原くん、大丈夫?」
海原は頷いた。
「少し休めば」
「本当?」
腕の傷以外に外傷らしい外傷はないが、顔色が悪い。
「大体あれだ。真壁が海原に剣なんて渡すからだ」
「いや、サイハテが勝手に」
「真壁さん、そんなことしたの?」
晶子が怒った顔をする。そうなると、真壁も辛い。
「いや、そこに剣があるからといって、ポケモンと生身で戦おうとする奴がいるとは思わなかった、から」
「本当か? 何か証拠残ってねえか」
青井が真壁のリュックを無理矢理漁る。そして、テープレコーダーを引っ張り出してきた。
「証拠の音声が残ってるかもしれない」
そう言って、容赦なく巻き戻し、再生ボタンを押す。そのタイミングで、真壁がテープレコーダーを奪還した。
『なんで俺にだけああいう態度なんだろうな』
カセットテープから、青井の声が流れてきた。声の主が瞠目した。
『へえ、どういう態度だ?』『……他の奴は絶対庇ったりしないのにな』
「おいおい、ちょい待てこれ」
青井の顔が怒りで赤くなった。
「どういうことだ!?」
「あー、多分鞄の中で録音スイッチ入ってた」
『出来のいい同期で友人だよ。その上庇われて』
「だああああああ!!」
青井が叫びながら、真壁の手からテープレコーダーを奪い取った。停止ボタンを押す。
「消しとけ!」
青井がテープレコーダーを突き返す。
「今の、忘れるわ」
晶子が困ったように笑った。
「そうしてくれ」
青井はそう言ってから、海原の方を向いた。
「庇わないように善処する」
「いや、忘れてくれ」
青井が言った。
「あの、すいません」
若い女性の声がした。見ると、巫女装束に身を包んだ女性が、こちらを困ったように見つめていた。
「ここ、関係者以外立入禁止なので」
そう言いながら、彼女の目が海原の上で止まった。またか、と真壁は思った。
「失礼しました。山中で道に迷ってしまいまして」
海原が申し訳なさそうに言って、それから笑みを浮かべた。若い巫女はコロリと騙される。
「そうでしたか。時々あるんですよ。ほら、この神社って周りが森だから。あ、あの小道を下りて小川沿いに進んだら、この村の入り口に出られます。そこから下ればすぐ麓で」
「ありがとうございます。ご親切にどうも」
「旅のトレーナーさんですか?」
「そのようなものです」
あ、これは長引くぞ、と真壁は思った。案の定、若い巫女が話を続けた。
「旅のトレーナーが迷い込むことが多いので。あ、この村では、来月、時の感謝祭という祭事を行います。セレビィ様に会えるかもしれませんので、是非」
「ということは、君はセレビィ様に仕える巫女さん?」
見ていられないので、真壁が助け舟を出した。巫女さんはちょっと名残惜しそうに海原から目を離して、真壁の質問に答えた。
「はい。まだまだ至らぬ身ですが」
「間違ってたらごめん。だけど、巫女さんっていうことは、神様と結婚する、とか、している、ということかな」
巫女は少し考えてから、こう、笑って答えた。
「神社によって違いますが、この神社ではそうです。時の巫女はセレビィ様に身を捧げます」
「時の勇士の話は?」
「それは、セレビィ様が陰の気に当てられた時に、陰陽を正す存在で、婚姻とは関係ないです」
「ああ、なるほど。尋ねてくださってありがとう。最後に一つ、いいかな」
「はい、どうぞ」
「いずれは君は、セレビィ様のお嫁さんになるということ?」
巫女ははにかんで笑った。
「私は修行中ですので。でも、頑張ったらそうなるのかもしれません」
頬にほんのり赤みが差していた。幸せそうに笑うな、と真壁は思った。
「それでは、今度は是非表からいらしてくださいね」
「これは、道を教えてくれたお礼に」
海原が、何を思ったか、ついと進み出て巫女の手に握らせた。あの、四季折々が描き込まれたモンスターボールだった。
「偶然手に入れた品ですが、この地域に縁ある物だと思いますので」
そう、そつなく言う。
「ありがとうございます」巫女は変わり種のモンスターボールをしっかりと握りしめた。
若い時の巫女に見送られて、四人は小道を下りた。
「あのセレビィも、愛されてるんじゃない」
晶子がそう言った。
小川沿いに道を下って、四人は村の入り口を見つけた。そこから改めて村に入る。昼過ぎの村は微妙に見慣れなくて、奇妙な感じがした。まずは晶子が目を付けていた宿に部屋を取って、めいめい荷物を下ろしてから、ロビーに集まって土産物屋を見て回った。
「海原、本当に体、平気か?」
「ああ」
真壁の問いに素っ気なく頷くと、海原は腕を伸ばして木彫りのアクセサリーを手に取った。「村のクスノキで出来たお守り」
「もうクスノキはいいよ」
「あ、これ」
晶子がはしゃいだ声を上げた。海原が取ったのと同じ物を、体を伸ばして取ると、「これ、この村の工芸品なんですって」と言った。
「この村の守り神にあやかって、恋愛成就の効果があるとか」
「なさそうだ」
青井がぼやいた。
しかし、晶子は笑って、「これ、買うわ」と言った。
男三人は、レジに向かう晶子を見送った。彼女はそのお守りで、誰と結ばれたいのだろう。時は流れるのに、誰も前に踏み出せない。彼女の笑顔を見て、進みたいと思いながら、時よ止まれと願ってしまう彼らがいる。
(完)
咲玖という仮面HNのものです。連載板に置いてあるお話のキャラクターで、『鳥居の向こう』の作品を一つ……と思ったら、字数大幅オーバー(35912字)でこちらに投稿となりました。
楽しんでくだされば幸いです。
(七月二十二日 微修正)
| タグ: | 【フォルクローレ】 |
屏風の大唐犬の希望が被っておりましたが、割り振りが決定いたしました。
茉莉さんに第二希望の絵を描いていただくことになりましたので、
一次掲載決定作品 は以下のようになります。
冬の神 砂糖水(絵:碧)
探検の舞台は クーウィ(絵:ヤモリ)
ニドランの結納 No.017(絵:草菜)
鮫の子孫たち No.017(絵:たわし)
盗まれた才能 No.017(絵:発条ひず)
屏風の大唐犬 No.017(絵:のーごく)
ミルホッグ・デー リング(絵:茉莉)
以上、7作品となります。
二次に向けて絵師さんにも更に声掛けして参りますので振るって応募くださいませ!
部屋を掃除していたら、とんでもない代物が出てきた。
と言っても、俗世間様には全く価値が無い物だけど。
「……」
時は十年以上前。私が小学二年生だった時のこと。ポケモンはジョウト編の最後の年。映画はラティアスとラティオス。唯一私が見損ねた映画でもある。
国語の授業で、『のはらうた』をやった。動物や虫の気持ちになって詩を詠むのだ。小二にしてはハードルの高い課題だったと言えよう。
当時私は工藤直子さんの小説『ともだちはみどりのにおい』を読んだばかりだった。馬鹿正直に私はそれを読んだことを詩に書いた。
へったくそな絵まで付けて。
「懐かしいな」
だがそれが先生の目に留まることとなる。しばらく後、私は後ろに貼られているはずの詩が数枚抜けていることに気づく。そしてその中には、私の詩も入っていた。
少し考え、まさかと思い私は教室を飛び出した。向かった場所は一年生が毎回帰る時に集合する場所。校門前。
うちの学校は独特の構造をしていて、入口が三つあった。一つは業者用。あと二つはそれぞれの道から登校してくる生徒用。
私は坂を登った先にある、校舎直通の門から入っていた。
そこには一年から六年までの掲示板があった。
「!」
二年の掲示板に、五枚の詩が展示されていた。
その中に、私の詩があった。
今思えば、それが私の一番始めの創作だった。
幼稚園の頃から何かを書くのは好きだったけど、ここで一区切りがついていた。
その後も時々書いた文章が学年通信に載ったりした。
『ともだちはみどりのにおい
わたしは図書館で かりた本をよんだ
さいしょにライオンがいて、
つぎにかたつむりがいて、
さいごにロバとともだちになる』
その時は、まだ自分がこんな所にその内容を書くなんて思ってもいなかった。
そもそも未来を夢見ることもあまりしなかった。
でも、
大人になれば、何でも出来ると――
それは、思っていた。
こんにちは。NOAHです。
まずは、この小説をここまで読んでいただき
本当にありがとうございます
長編未経験ながら、どこまで書けるか不安ながら
衝動だけで書き始めたこの小説ですが
少しずつ書き足していってるのが現状です。
これを書く前にも書き足したのですが
このような形で更新して大丈夫だろうか?
と、疑問に思いました。
と同時に、このまま書き足すことも、勝手に消してしまうことも
マサポケ管理者のNo.017様を始めとした
たくさんのマサポケノベラー様に、ご迷惑になるのでは?
とも思っています。
そこで皆さんに、お聞きしたいことがあります。
それは、この「アリゲーター・ロンド〜受け継がれる名前〜」を
消した方がいいか、書き終えた方がいいかということです。
私個人では、どうしても決めきれません。
皆さんのご意見を、ぜひお聞かせください。
NOAHより.
『ヘルガーが来たぞ!』
その声を聞いて集落は恐怖に包まれる。
『ヘルガーが来たぞ!』
見張りの少年の声を真似て、ペラップは何度も鳴きながら飛び回る。
その集落はメリープを育てる遊牧民のコロニーだ。そんな場所にヘルガーはやってくる。ヘルガーはその牙や爪、炎を使って人々やメリープを襲う。
大事な物を纏めて、もしくは何一つ運ぶこともできず、メリープと人々はその場から一目散に逃げる。
一人残らずに逃げ切ったところ、前々から決まっていた避難場所で皆が冷静になったところ、最後の一人が現れる。危機を知らせたペラップを肩に乗せ、皆のことを見回しながら少年は満面の笑みを浮かべた。その時だけ少年は笑う。
ヘルガーは来なかった。
少年の両親はヘルガーに食べられてもうこの世にいない。天涯孤独になってしまった少年をある親子が引き取って育てた。同じく妻をヘルガーによって失っていた男も、同い年の少女も、少年を新たな家族として迎え入れて精一杯の愛情を与えたつもりだった。
少年は男の言いつけを守り良く働いた。しかし少年は笑わなかった。幼くして両親を亡くしたのだ。無理もないと思いながら親子は特に変わらずに少年に接した。しかし、集落はそんな少年に最初こそ同情したものの段々と気味悪がるようになった。少年が熱心に働けば働くほど集落の心は離れていくようだった。
ある日、少年の働きが一人前と認められた時、集落はある決定をして少年に仕事を与えた。
見張りだ。
集落の端で放牧を行い、異変が起きればそれを皆に知らせる。重要な役割だ。そしてそれは危険な役割だった。
少年の父親代わりの男は異を唱えた。そんな危険な役を押し付けるのか、一人前に認められたとはいえまだ子どもではないかと。しかし少年は極めて平静に言った。僕がやります、と。
ある日、ペラップが集落を飛んで回った。少年の声で「ヘルガーが来たぞ!」と何度も鳴いて飛び回った。皆は少年がペラップを使って危険を伝えたのだと思い、メリープを連れて一人残らず逃げた。しばらくして少年が姿を現した。幸い、誰一人ヘルガーの餌食にならなかった。
それからしばらくして同じようなことが起きた。また犠牲者は出なかった。しかし集落に戻ったところで誰かがおかしい、と言い出した。ヘルガーを誰一人見ていないというのだ。そしてヘルガーが来た形跡すらないと言ったのだった。ヘルガーはほのおポケモンだ。少年の親が犠牲になった時も、それ以外の時も、集落で火事や焼け焦げた跡があった。しかしこの前も今回もそれが無い。その時はおかしいと思わなかった者達も、再びペラップが『ヘルガーが来たぞ!』と飛び回り、何も起きなかったことに不信を抱いた。そして誰かが少年に聞いた。
「どこも燃えてないのか。ヘルガーはここまで来なかったのか?」
少年は笑った。誰もが始めてみる満面の笑みを浮かべるだけで、何も言わなかった。
平穏が続き、忘れた頃にそれは繰り返された。そんなことが何度か続いた時、誰かが言い出した。
「アイツは我々にヘルガーが来たと嘘をついてからかっているんだ! 嘘をついて逃げ回っている俺達を見て笑っているんだ!」
「アイツは集落の者を恨んでいるんだ! 自分の両親が食われたのは我々の所為だと思っているんだ!」
人々は段々少年に不信感を募らせていった。
「寒くない?」
「うん」
夜風に当たる少年の元に少女がやってきた。頬を押さえる少年を見て彼女は溜息をつく。濡らしたハンカチを手渡して彼女は言う。
「またお父さんに殴られたの」
「うん」
「どうせ『だって』とか言ったんでしょ?」
「『言い訳するんじゃねぇ!』ってさ」
「あなたはペラップとは違って物真似の才能はないわね」
少女が薄暗いながらも彼の腕や脚に痣があるのを見つけた。父の仕業だろうか? いや、きっとそうではないのだろうと思った。少年を良く思っていない連中の仕業で、そのことが原因で口論になったのだろうと推測した。
「ねぇ、ペラップに『ヘルガーが来た』って鳴かせるのは止めなよ」
「どうして?」
「もし、ヘルガーが来なかったらどんな目に遭わされるか――」
「君はヘルガーが来た方がいいって言うのかい?」
「そんなことあるわけないでしょ!」
「じゃあ、僕は止めないよ」
そう言って、彼は家に戻っていった。
少女は、本当は見張りなんて辞めればいいと言いたかった。
でも言えなかった。
少年が見張りを辞めたら誰が見張りをやるのか。辞めろと言ったら「じゃあお前がやれ」と言われるのが怖かったのだ。それは彼女だけではない集落の皆が思っていることだった。だから少年はずっと見張りをさせられている。
我が身の可愛さに何もいえない自分が情けなくて、悲しくて、少女の目から涙が溢れた。
それでも家族である自分だけは少年を信じなければならないのに、人々が逃げ回った後だけ見せる彼の笑顔を見ると、彼女は何にもわからなくなってしまうのだった。
そして、またペラップが集落を飛び回る日が来た。
『ヘルガーが来たぞー!』
ペラップが飛び回りながら叫ぶ。何ども叫ぶ。
だが集落の者は誰一人として慌てる者はいなかった。
「またか」
「全くしょうがないやつだなアイツは」
誰一人として逃げる者はいなかった。皆は少年にどんな言葉をかけてやろうか考える。今度は騙されなかったぞ、と笑いものにしてやろうという者もいれば、今度こそ足腰立たなくなるまでぶん殴ってやると息巻く者もいた。
ヘルガーは現れなかった。そして少年も現れなかった。
夜になっても朝日が昇っても、次の日も、そのまた次の日になっても帰ってくることはなかった。
それから数日して少年が放牧していた場所の近くで、焼け焦げ食い散らかされた少年らしき亡骸が見つかった。近くにペラップが飛んでいて間違いないとされた。集落の皆は新たな見張り役が選ばれることを恐れ、その見張りは同じような目に遭うのだと思い、憂鬱になった。因果応報だと少年の死に悲しまなかった。親子を除いては。
「お父さん、飲み過ぎよ」
「うるさい」
枯れた声で娘が制止しても男は酒を飲むのを止めなかった。男はその日、朝からずっと酒を飲み続けている。
「もう、その辺にしておいてよ。私、水を汲んでくるわね」
娘が出て行くと、男は空になったコップに酒を注ぎながら、テーブルの上で豆をつまむペラップを見た。
「お前の主人は馬鹿なヤツだったよ」
呂律の怪しい男の声を聞き、ペラップは男をじっと見た。それが妙に癪に障り、男は紅い顔をさらに真っ赤に染めてテーブルを叩いた。
「テメェの主人は大馬鹿野郎だっ!」
大きな音と声に驚きペラップは飛び上がった。そして男の頭上を羽ばたいてぐるぐる回ると大きな声で鳴いた。
『ヘルガーが来たぞ!』
少年の声でペラップは何度も言う。
『ヘルガーが来たぞ! ヘルガーが来たぞ!』
「止めろ」
『ヘルガーが来たぞ! ヘルガーが来たぞ!』
「止めろって言ってるだろう!」
男は中身がまだ入っているコップを投げつけました。直撃し、落ちてきた所をさらに男は殴り、ペラップは壁に叩きつけられました。
『ヘルガー……ヘルガー……』
「まだ言うかこの――」
男が再び怒鳴り声を上げようとした時、ペラップは少年の声で言った。
『ペラップ、早く行くんだ』
男は動きを止めた。それは初めて聞く言葉だった。
『早く行って みんなに知らせるんだ』
羽を広げたまま息も絶え絶えにペラップは言う。
『ここは通さない ヘルガーめ 僕の大切な人達に近づけさせるものか』
「おい、何を言ってるんだ――?」
『あっちへいけ 絶対に通すものか おいペラップ何やってる 早くみんなに知らせるんだ早く』
男は知っている。ペラップは聞いたことしか物真似ができないことを。少年が会話しようとどれだけ喋っても、聞いたことをオウム返しに喋ることしかできなかったことを。
『ペラップ 帰ってきたのか でも下手を打ったかな いつもみたいにいかなかった いや いつもが運が良かったのかな? 大丈夫 先に行けよ もう 不思議と痛くないんだ もう少し休んだら行くよ』
それが何なのか想像することはたやすいことだった。
そう、これはペラップが聞いた少年の言葉。
「そんな馬鹿な――」
「どうしたのお父さん? そんなところに突っ立って」
顔を向けると入り口に少女が立っていた。彼女は部屋を見回すと驚き、水の入った桶を乱暴に置くと壁際に伸びているペラップに駆け寄った。
「ちょっとお父さん! ペラップは何も悪くないでしょ! 急いで手当てしないと!」
治療道具を急いで取ってくると娘はペラップの手当て始めた。
「そうだ悪くない」
「え?」
少女は父の呟きが聞こえて思わずその顔を見る。まるで生気の無い表情でどこか遠くを見ていた。
「ペラップも、あいつも悪くないんだ……」
男は気が抜けたように座り、そのままテーブルに突っ伏した。そして両手を握ると、何度も何度もテーブルに打ち付けた。
「ヘルガーが来なかった時俺達がするべきは怒ることじゃなかったんだ! そんなことじゃなかったんだっ!」
肩を震わせ叫ぶ彼に娘は何も言うことはできなかった。ただ、彼女の側でペラップが『馬鹿野郎』と男の声で小さく鳴いた。
その集落でペラップが『ヘルガーが来たぞ』と少年の声で鳴いて飛び回ることは二度と無かったという。
一匹のワルビアルが、突っ立っていた。
砂嵐のひどい、この4番道路のど真ん中で
傷だらけの体に何も手当てをせず、誰かをずっと待っていた。
その傍らには、1つのポケモンのタマゴがあった。
孵るとしたら、おそらく、メグロコ……。
このワルビアルの子が生まれるのだろうと、大体の検討がつく。
「……まだ待つつもりか?」
「がう。」
「お前のトレーナーは……ヤツはもう死んだんだぜ?
お前はもう野生だろう。ヤツの言葉に従うことはねぇだろうが。」
そう。コイツのトレーナーは、相棒であったあの男は死んだ。
コイツの目の前で、幼い少女と、傍らのタマゴを守ろうとして、死んだ。
ヤツが死んだことで、唯一の手持ちであったコイツは野生となった。
だがコイツは、今でも死んだヤツの、最後の言葉を聞いて、今まさに、それが果たされようとしている。
ザッ、ザッ、と、砂を踏む小さな足音が聞こえた。
吹き上げる砂煙の向こう側から現れたのは、12、3才くらいの少年だった。
砂嵐から身を守るための防護用コートで身を包んでいるため確認できなかったが
確実に、わかったことがある。
あの少年は、死んだヤツの子どもだ。
ワルビアルはタマゴを持ち上げると、無言で少年に近寄る。
少年は、ワルビアルとタマゴを交互に見やり、こちらも無言で受け取った。
「……父さんのこと、悔しかったろ。」
「…………。」
「ありがとう、父さんの傍にずっといてくれて。
……本当に、ありがとう。幸せだったと思うよ、きっと。」
少年は、自分より背の高いワルビアルに、臆せず話しかける。
普通のガキなら、そのいかつい見た目を怖がるっつーのに
ヤツの子である少年からは、微塵もその様子はなかった。
「よう、少年。」
「……だれ。」
「てめえの親父を撃った……って、言ったら?」
少年は眉を顰めて、ポケモンが入ったボールを
無言で突き出すように構えた。
ギロリ、と睨みつける目は、ヤツにそっくりだった。
「冗談だ。……俺はヤツの同僚だよ。」
「…………。」
「くくっ……親父そっくりだ……お前、名前は?」
「……『仁科シュロ』。」
「シュロ、な……お前、刑事になる気は無いか?」
その言葉で、シュロと名乗った少年は驚いた表情をする。
隣では、ヤツのワルビアルが、事の成り行きを見守っていた。
「素質はあるぜ、充分にな。」
「……試したの。」
「あたり。……お前なら、コイツと、ヤツの意志を継げるってな。刑事のヤマ勘信じろ。」
「へぇ……子どもに賭け事させるわけ?」
「刑事とその辺のペテン師を一緒にすんなよ。」
この生意気な口調も、親父譲りのようだ。
警戒心はもう解いたのか、ボールは既にしまっており
タマゴを改めて抱え直していた。
「刑事になれ、ね……考えとく。」
「おー、来るの、楽しみにしてるぜ。」
「……それじゃあ。」
シュロはコートをはためかせて、来た道をまた戻っていった。
砂煙の中に消えたシュロを見届けて、隣にいたワルビアルが
ついに事切れたように倒れ込んだ。
「なんだ……てめえも死期が近ぇのかよ。」
「ぐぅ……。」
「は、笑えってか?……そうだな、盛大に嘲笑って見送ってやる。」
にやり、と笑って、倒れ込んだワルビアルを見る。
コイツもにやり、と笑い返した。
「じゃあな、『ヴィッグ』。『仁科レン』の、良き相棒。」
最後まで笑みを浮かべたまま、コイツはその生涯を終えた。
*
-11年後-
「あ"ー!もう!雑務押し付けてどこ行きやがった、あの飲んだ暮れーーッ!!」
人の行き交うヒウンシティに、俺の主の声が響いた。
その横で、穏和な顔付きの、主の先輩にあたる緑の髪の男が笑う。
「あはははは、本当だよねぇ。班長ってば、俺たちほったらかして
昼間っから飲み明かすもんねぇ。……この前なんか、100万もするロマネコンティ飲んでたし。」
「ヒースさん、他人事のように笑わないでください!
俺は、事件のときだけマジメに取り組む
あのおっさんの鼻を明かさないと気が済まないんですッ!!」
「ねぇ『シュロ』君。新作スイーツ販売の度に
班長と同じようなことを仕出かすキミが言えた義理かい?」
「……………。」
主にとっては思いもよらない反撃だったらしく
つい押し黙った主を見て、隣の男がにへら、と
力の無い笑みを浮かべる。
「キミも大変だねぇ、『ヴィッグ』。似た者同士の義理の親子に付き合わされて。」
「ヒースさん、冗談でもそれ以上言わないでください。
有り得ないですから。マジで本当に、無いですから。」
「あーじゃあ…あれだ。キミの亡くなったお父さんと班長が似た者同士で
キミがお父さんの血を濃く引きすぎたから、親子に見えるんだ。」
「ヒースさん……言ってることが半分くらい無茶苦茶ですよ……。」
「そう?的を得てると思うけど。」
適当すぎる推理に突っ込みを入れている主を横目に
ずっと抱きかかえている、俺の子どもがいるタマゴを見つめる。
時々動く程度で、まだ生まれる気配は無い。
……やはり、信頼できるトレーナーに任せた方がいいだろうか。
「あー……何であの人の誘いに乗っちゃったかなぁ……。」
「誘われたんだっけ、子どもの時に。」
「そうですよ、『お前なら、親父と、親父の相棒の意志を継げる。刑事のヤマ勘信じろ。』……と。」
「へぇ、刑事のヤマ勘ねぇ……。」
「あの人のギャンブル運、半端無いっすからね。」
「そうだよねー、それはまあ、あの人のお子さんにも言えることだけど。」
「『あいつら』とあのおっさん、血ぃ繋がってないっすよ?」
「え、そうなの?」
主の言うあいつらとは、2人の上司にあたり、今現在をもって
行方を眩ませている人の元に、養子に入った双子の姉弟のことで
このヒウンシティで、『Jack Pot』という捕獲屋を営んでいる友人だ。
今俺が抱えているこのタマゴも、普段はそこに預けているが
ここ最近は平和なため、俺が親として責任持って抱えている。
「しかし、どこ行ったんだあの飲んだ暮れ……!!」
「何時も行くカフェにも、カジノバーにも居なかったもんね……。」
本格的に頭を悩ませる2人だったが、プライムピアの方が
やけに騒がしいことに気付いた。
何か事件でも起きたのだろうか。
よくよく見るとなんとこの街のジムリーダーがいた。
慌てて彼の近くに寄ると、ベレー帽の女の子がわんわん泣きながら、ポニーテールの女の子と
浅黒い肌の、元気そうな女の子に慰められていた。
「どうした、アーティ。」
「んうん……心強い刑事さんのご登場だ。
シュロ、ヒースさん、ちょっと力を貸してよ。」
「何かあったの?」
「聞いてよ!このお姉ちゃん、プラズマ団にポケモンを奪われたんだって!!」
「「……!!」」
プラズマ団、この状況で一番聞きたくなかった名前だ。
主の表情が、一気に険しいものに変わる。
「ちっ……またヤツらか……。」
「まずは、詳しく話を聞こうかな。キミたち、名前は?」
「私はトウコ。カノコタウンから来ました。この子は幼馴染のベル。」
「私はアイリス!」
聞くと、このベルという少女のムンナが、1人のプラズマ団によって奪われたらしい。
追いかけたが、この辺りで見失い、途方に暮れて泣き喚いていたそうだ。
ふと、こちらを見張るような視線に気付いた。
振り向いた先には、奇天烈な服を着た男。
間違いない。プラズマ団……!!
「ぎゃうっ!!」
「げ、バレた……!!」
「!待てッ!!」
脱兎の如く逃げ出したプラズマ団を、主とジムリーダー
そしてトウコと名乗った少女が追いかけて行った。
向かった先は、ジムの方向のようだった。
「ヴィッグ、タマゴは僕が預かるよ。
キミはシュロ君の相棒でしょ?
彼が無茶しないようにしなきゃ。ね?」
何かがあっては困ると、ココに残ることにしたらしい
ヒースさんにタマゴを預けて、俺は主の後を追いかけた。
*
カノコタウンを旅立った時から、度々目立つ集団がいた。
プラズマ団。ポケモン解放を訴える、奇妙な服装の謎の集団。
けど、実際はポケモンを道具としか見てないヤツらばかりだった。
このヒウンシティに来る数日前も、ジムと共同で動いている
シッポウシティの博物館の、展示品の盗難事件に携わったばかりだ。
あのときは追い詰めた先で、丁寧にも盗んだものを返してくれたが
今回は、物じゃなくてポケモンだ。しかも、幼馴染の、ベルのポケモン。
「絶対に、取り返してやる……!」
「ぎゃう!」
「!」
気付いたら、刑事さんのワルビアルが追い付いていて
私を諭すような目で見ていた。
危ないから下がっていなさい。そう言わんばかりの痛い視線だった。
しかし、その目線に何故だか懐かしさを感じた。
なぜだろう。私はあの刑事さんにも、ワルビアルに会うのも初めてなのに。
「……私、引き下がる気はないから。
このまま指を加えて見てるって云うのは嫌なの。
ましてや被害者は、私の幼馴染だから、余計に。」
「……がう。」
「どうしてもって言ってる?……もちろんよ。」
挑発的な目線を送れば、諦めてくれたのか
これ以上、咎めることはしてこなかった。
「……ありがとう。行こう!」
私の掛け声に彼が応えてくれた。
それが嬉しかったけど、ジムのすぐ近くのビルの前で
プラズマ団とバトルを繰り広げている刑事さんとアーティさんを見つけた。
「全員、携帯獣愛護法違反、強盗、窃盗!
その他諸々の罪で現行犯逮捕だ!!」
「ぎゃうん!!」
「!!」
「!トウコちゃん!!」
「私も戦います。ベルを泣かせた上に
彼女の大切なポケモンを奪ったんです。
絶対許さない……!!行くよ、ジャノビー!!」
*
あれから少しして、ビルの中に入ることが出来た私たちの前に
カラクサタウンで演説をしていた、壮年の男の人がいた。
ゲーチスと名乗った男の話の前に、目を泣きはらしたベルが
アイリスちゃんと、もう1人の刑事さんに隠れながらもやってきた。
彼は何を思ったのか、ベルにムンナを返すように指示し
そのまま煙玉を使い、結局は逃げられてしまった。
ワルビアルのトレーナーである黒髪の刑事さんは
悔しそうな顔で外に出ると、ぐしゃぐしゃに頭を掻き始めた。
それをもう1人の刑事さんが宥めている。
「くそ……また逃げられた……!」
「まぁまぁ。根気良く行こうよ。」
「……そうっすね。」
ハァ……と、ため息を吐く黒髪の刑事さんを見ていると
何だかずっと昔に会ったことがあるような気がした。
黒髪に……ワルビアルを連れたトレーナー……。
「……ぁ。」
「トウコ?どうしたの?」
「ベル……11年前、私が遭遇した事件のこと……覚えてる?」
「え……っと、確か、トウコを守ろうとして
亡くなった人がいるって言ってた、あの?」
「うん……あの黒髪の刑事さん……
たぶんその亡くなった人の、子どもさんだと思う。」
「ぇ……?」
「おー、じゃあキミがあの時の女の子か。」
ぽん、と頭に、男の人の手が置かれた。
……あれ?この人、どこかであったような……。
「あ。ギリア班長ー、どこ行ってたんですか?」
「……墓参りだ。あぁ、そうだ……アーティさんよぉ。」
「んうん?何でしょ?」
「どっか一室、貸してくれねえかなァ。
……11年前のこと、きちんと話してやろうと思ってさ。」
アーティさんは、突然の申し出ながらも
笑顔で承諾してくれた。
「…あの!…私も、お邪魔していいですか?」
「ベル……?」
「トウコを助けた人の話だもん……幼馴染として聞かなきゃ。」
「……ありがとう、ベル。」
「気にしないで!……あ、チェレンも呼ぶ?」
「……うん。」
「わかった。ちょっと待ってて!」
ベルが、ライブキャスターでチェレンを呼んでくれた。
今からジムに挑戦しようと思っていたらしく
すぐに駆け付けてきてくれた。
「んじゃ、話すか。……1999年、6月13日。
20世紀最後の、凶悪事件が発生した日のことを。」
*
-1999年6月13日・イッシュ地方ヒウンシティ-
「いやー、やっぱ向こうと違って、こっちは晴れの日が多いね!」
窓から外を眺める、長身の、黒髪の東洋人の男。
見た目だけなら、まだ人種差別も残っていた当時のイッシュ地方では
ソイツは異質な存在だった。
「そうかー?普通だと思うけど。」
当たり前のように返していたが、俺はこの男―…。
仁科レンが、少し苦手だった。
「ギリアは知らねえだろうけど、俺の故郷の
ホウエン地方はこの季節、どっこも雨ばっか何だよ。
晴れの日なんてホント稀!!」
「へェ……興味ねぇや……つーか声、うるさい。」
「おま……また二日酔いか?いい加減控えろよ……。」
「お前が甘いもん控えたら止めるかもな。」
「………。」
皮肉を込めて返したら押し黙った。ざまぁみろ。
ペットボトルの中の水を飲んで、息をつく。……やっぱ昨日、飲みすぎた……。
「……あ、お前、今日なんかあるんじゃなかったっけ?」
「あ"ぁー!!」
「だからうるさい……。」
「あ、すまん……。」
うるさくなったり静かになったり……。テンションの幅が本当にうざったい……。
このホウエン人の気質である、能天気なとこが苦手だ。
「少し出てくる。」
「おー…そのまま帰れ。」
「ひどっ。」
そしてげらげらと笑うレン。ギロリと睨みつけると
おどけた表情の笑みを浮かべて出て行った。
これが、事件発生1時間前の
俺とヤツの、最後のやり取りだった。
*
始めてこの地方に来たとき、目にする物全てが新鮮だった。
ホウエンの大自然の中で育った身としては、空を貫くような高いビルも
モノクロのタイルのようなレンガ道も、食べる物も、住んでいるポケモンも
何もかも、全てが違う場所。
生まれ故郷のホウエンを離れたのが18才のとき。
……あれから17年が経った。
今は守るべき家族がいて、良き友人がいて、ライバルがいる。
片手間に、途中で買ってきたミックスオレを持ち
ポケモンセンターへと入って行った。
「仁科さん。」
入ってすぐに、ここを取り仕切るジョーイさんが
タブンネと共に話しかけて来た。
「やぁ、ジョーイさん。……アイツは?」
「今日はお元気ですよ。相棒さん。」
「そうか、良かった……会えるかな?」
「わかりました。少しお待ち下さい。」
鳩さん、返信ありがとうございます。
議論が噛み合わないと思っていたら、私の一つ目の書き込みから誤解が生じていたようですね。
おそらく、「私の書いている話と同じネタが投稿されたら困る。書き直さないといけない」と読まれたのかなぁ、と二つ目の書き込みをした後、鳩さんの返信で気が付きました。(もし違ったら、今後のためにも教えてくださるとありがたいです)
誤解を招く表現をしてしまい、申し訳ありませんでした。
お互いに認識の齟齬を正すことができてよかったと思います。
このスレに書き込んでくださった皆様も、活発な議論をありがとうございました。
とても勉強になりました。
カフェラウンジの画像、でかすぎませんか。記事タイトルが前より見えにくいのが気になります。
で、ネタについてですが。
思うに、『予想する』と書くからいかんのです。人の没ネタを拾うのはいいけど、予想して当てられたら負けた気がする。そんなもんです。
私自身は、ネタが被ったりどっかから拾ったりは、それでいいと今は思いますが、そう思えなかった時期があったのも事実。被った即負け。そうではないと気付くまでに色々書きました。
ま、とりあえず書けばいい。
チャット会にご参加のみなさま、そしてご観覧くださったみなさま、大変ありがとうございました。
みなさまのお陰さまでチャット会はほぼ滞りなく進行いたしました。あとは私にもっと司会スキルが必要だと痛感いたしました……結果発表チャットこそは上手くやれるように訓練しておきます。
●概要
(1) コンテストのお題
→ 「数/時」(同数1位:7票)
(選択制、最低でもどちらかひとつを織り込んでください。両方も可です)
(2) 開催期間
→ 提案から変更なし
2012年10月15日〜12月23日(募集:10月15日〜12月1日、投票:12月3日〜12月22日)
(3) 文字数と応募可能作品数
→ 文字数:100〜20000文字、応募可能作品数:ひとり1作品
(4) 募集対象を小説に限定するかどうか
→ 変更あり。小説のほか論文風・ニュース風の作品も募集対象とさせていただきます。
ただし詩については募集対象から除外させていただきます。
(5) コンテストのタイトル
→ 「ポケモンストーリーコンテスト 〜ムウマ編集長のポケバナ大賞」
メインタイトルはマサポケから継承させていただくことに決定いたしました。
サブタイトルは巳佑さんのご考案です。ありがとうございました!
●詳細
(1) お題には次のものが出されました。ひとり5つのお題への投票を行い、合計13人分の65票の有効票がありました。
色 数 光 白 闇 お別れ 空 魂 きかい バチュル おはなし
希望 こころ 過去 未来 はつ(発/初) 時 流れ 化石
このうち、「数/時」が最多得票の7票で、次点は「色/空」の6票でした。決選投票は実施しませんでした。
(2) 文字数カウンタについて
文字数カウンタによって返される文字数が変わることがあります。
ですので、この点に関しては運営側が利用を推奨する文字数カウンタを決めておこうと思っております。
(3) いわゆる「エロ・グロ作品」について
これまで概要ページに掲載していた通り、主催者判断で掲載をお断りすることがあります。
寛容でありますが、評価が割れる可能性があることはあらかじめご承知ください。
(4) 恋愛小説および同性愛を扱ったについて
恋愛小説については全面的にこれを認めます。同性愛を扱った作品についても、これを禁止しません。
ただし上記の「エロ・グロ作品」同様、評価が割れる可能性がありますのでご承知ください。
(5) 作品への批評について
コンテストのコンセプトとして「はじめて小説を書かれる方」も想定をしておりますので、批評はお手柔らかにお願いいたします。
また、批評が中傷になることがないようお願いいたします。
◇
チャットログは後日掲載させていただきますのでもう少々お待ちください。
今回のチャット会をもちまして、ストーリーコンテストを本格的に運営する準備が整いました。
あくまでスタートラインに立てただけのことですので、ここからみなさまにお楽しみいただけるコンテストとすることができますよう、運営として邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたしますm(_ _)m
10月7日 小樽ミオ
イッシュ地方。この地に来るのは何年ぶりになるだろう。男は飛行艇の窓から、久しぶりの光景を見渡した。ヒウンシティは多くの人で相変わらずの賑わいだ。
やがて飛行艇が港に着陸すると、男は船を降りた。すると背後から彼の後を追ってくる足音。男はいい加減うんざりしていた。
「誰も付いてくる必要はないと言っただろう」振り向きざまに、思い切り顔をしかめて言った。
「しかし……この頃のイッシュ地方はプラズマ団とかいう危険な輩が横行しているとの話もありますし、大切な御身に大事があっては……」この真夏でもピッチリとした黒のスーツに身を包み、まるで定規を当てたかのようなみごとな七三ヘアーのこの男は、彼のボディガードをしている。
――何がボディガードだ。
男は彼が、父親の差し金により、自分の見張り役として寄越されていることを知っている。
父上の会社から離れてホウエン地方のチャンピオンリーグマスターになると決めた日、確かにきっぱりと会社を継ぐ意思はないと話したはずだが、未だに僕を放っておいてはくれない。そのせいで、どこへ行くにも、この僕を追いかけて離さないようにプログラムされた“人間ロボット”が付いて回る。
「君は僕を誰だと思っているんだい? 僕は先のホウエン地方チャンピオンリーグマスター、ダイゴだよ。はっきり言って君がいるとむしろ邪魔だ。君を庇ってチンピラ相手に勝負なんて面倒、僕は御免だからね」
男――ダイゴはそう言うと、ボディガードの言葉を待たずにヒウンの雑踏へ駈け出して行った。
彼はすぐに父上から激しい叱責をくらうだろう。もしかしたらこの件が原因でツワブキコーポレーションをクビになるかもしれない。
しかし、ダイゴにとってそんなこと頭の片隅にも残らないほど、どうでもいいことであった。
やっとボディガードを撒いてくると、ダイゴはポケモンセンターに向かうことにした。……が、目の前まで歩いてきてやはりやめた。もし、さっきの男が私を探したら真っ先にやってくるのはこの町のポケモンセンターだと思ったからだ。
仕方なくそこからさらに少し歩くと徐々に人通りは減っていった。ダイゴは「この先モードストリート」と書かれた看板の前でいったん立ち止まると、タウンマップを開いた。
――えーっと……。
目的の施設はすぐに見つかった。ホドモエシティのすぐ南、周りを大きく海に囲まれた半島の中に新しくできた施設PWT(正式名称をポケモンワールドトーナメントという)が、今回僕がこのイッシュ地方に呼ばれた理由だ。
このPWTは全国各地から強力なポケモントレーナーを集めて競い合う、ついこの間までは夢のような、まさしくドリームマッチが繰り広げられる施設だ。
今回このPWTのゲストトレーナーとして今のホウエン地方チャンピオンのミクリと並んで、すでに引退した僕にまで声がかかるのは、少し照れくさいような、よけい期待が大きいような気がして緊張するような、妙な気分だ。
PWTの開催は明後日だ。二日前に来たのは手持ちのポケモンたちをイッシュの空気に慣れさせるため……でもあるが、一番の理由はイッシュ一の鉱山でPWT主催者ヤーコンさんの所有する、ネジ山を見せてもらうためだ。実をいうと、ダイゴにとってネジ山の見学をすることは、密かにPWTに参加することよりも大切な目的であった。
イッシュだけに生息するポケモン、ホウエン地方にもいるポケモンも生息していると聞いている。一ポケモントレーナーとして、ポケモンの生態はとても興味深い。だが、なにより楽しみなのが、ネジ山の鉱物だ。石だ。
ダイゴはまだ見ぬネジ山に眠る石たちを思い浮かべて笑みを浮かべた(はたから見たら、何もないところでニヤついている変な人だ)
この石好きのせいで、ダイゴは一部の人間から変人呼ばわりまでされている。凄腕のトレーナーでありながら、石が好きで年がら年中各地を渡り歩き、彼がホウエン地方のチャンピオンであった時ですらその石さがしの旅は変わらなかった。
ダイゴは目的地を確認すると、タウンマップをバックにしまった。本当はこのヒウンシティから迎えの車に乗ってホドモエシティのホテルまで行くはずだったが、抜け出してきたので、タクシーでも探さないといけないが、その前にこの町をぶらぶら歩いてみることにした。時間はまだまだある。
とりあえず、目の前のモードストリートに入ってみた。さすがはイッシュ一の大都会。大勢の人たちがまるで拳銃の乱れ撃ちのように、行き来している。
「おっと、すみません」
のんびりした町の多いホウエンでは滅多に見られない光景に圧倒されてぼーっとしてたら、サラリーマン風の男にぶつかってしまった。しかし、男はダイゴの謝罪を聞くでもなし、振り向いた時にはすでに雑踏の中へ消えかけていた。
――なんだよ、アレ。
少しばかりむっとして、先へ進むと今度は長い行列ができているのが見えた。アイス屋さんらしい。行列の中にちらりと見覚えのあるブロンドのロングヘアーを見た。
アイスなんて全く欲しくない。行列まであるとなればなおさらだ。それにあの女……。
構わず先へ進もうとすると、
「あら! ダイゴ?」
足早に、逃げるように行列の横を通り過ぎようとしたが見つかってしまった。
ダイゴは気づかないふりをして先へ進もうとしたが、あの女にがっちり腕を掴まれてしまった。
「無視することないじゃない? ちょっと待ちなさいよ」
目一杯腕を伸ばし、行列から半身を乗り出しながらも女は片足だけで器用に順番を保っていた。通行人は道を塞がれてあからさまに嫌な顔をしているし、その不格好な体勢を笑う声も聞こえる。テレビや雑誌で最強の美女と謳われた、シンオウチャンピオンリーグマスターとしての風格は、ここでは微塵も感じられない。
「シロナ、君はもうちょっと周りの目を気にしたらどうだ?」
ダイゴが呆れて言う。
「あら……みなさーん! お気になさらずにー」
気にするも何も通行の邪魔なのは事実だ。ダイゴは一度はぁとため息をつき、シロナの元へ寄って行った。
モードストリートを進んだ先にセントラルエリアと呼ばれる公園がある。噴水の先にあるベンチに二人はやや距離を空けて……、というかダイゴがシロナを避けて座った。
「あなたがここにいるってことは、あなたもPWTに招待されたのね」
そういってアイスを一口、シロナ。
結局ダイゴはアイスを買い終えるまでシロナの元を離してはもらえず、約30分ほど買う気のないアイスの為に待たされた。
「まったく、ミクリだけで十分だろうに……」
そういってアイスを一口、ダイゴ。……待たされたのだからついでだ。ついで!
「ふふふ……美味しいでしょ? ヒウンアイス。この町の名物ですって」
アイスを舐めるダイゴにシロナがにやにや。
「ま、まぁ……」
まるで子供扱いされているような気分で恥ずかしい。……うまい。
「って、今そんな話じゃなかっただろ!」
「あら、ごめんなさい」
悪びれるでもなくシロナは言う。
「私は、あなたも招待されて当然だと思っていたわ。ミクリだけじゃ不十分ってわけじゃないけど、あなたもホウエンを代表する素晴らしいトレーナーだから」
さらりと言って、またアイスを一口。
「あ、ありがとう」
ダイゴもまた一口アイスを舐めて、顔をあげられずにさらにもう一口舐めた。
「ふふふ、ホントあなたって素直じゃないわねぇ……」
「うるさい!」
ダイゴは残りのアイスを一気に食べて、コーンの部分までばりばりたいらげると、席を立ち逃げるように去って行った。
「あなたとの勝負楽しみしてるわよー!」
後ろの方から大きな声がした。
その後は街の北の通りでタクシーを捕まえてまっすぐホドモエシティに向かった。PWTがゲストトレーナーのために用意しているという宿泊施設に泊まる予定だったが、そっちまで行けば確実にあの人間ロボットに見つかるだろうし、あそこにはシロナも泊まるはずだ。シロナと同じ場所で一泊だなんて、例え一日でも嫌だった。そこで、適当な安ホテルに泊まっておこうと思ったのだが……。
――何だ、これ!?
ホドモエシティについたダイゴは、一瞬行き先を言い間違えたのかと思った。それほどまでにホドモエシティの様子は変わっていた。
ダイゴの記憶にあるホドモエシティは地元民とホドモエのマーケットにやってくるまばらな客しかいないものという、イメージがあった。
それが今やあちこちにホテルが立ち並び、人の数もずっと増えて、あのヒウンにも負けない活気のある都市になっている。
安ホテルは無かった。しかもどのホテルも満杯で、ダイゴは唯一空いていたホドモエでも最高級ホテルのスイートを一人で借りることにした。ちょっと痛い出費ではあるが、それでもあいつらに見つかるよりよっぽどましだ。
「よぉ、お前がダイゴか?」
今、目の前で立っている、カウボーイハットを被った一見強面な中年男性がこの街をこれだけ大きくした立役者で、今回このPWTを開催した主催者でもある。
「ヤーコンさんですね。初めまして」
ダイゴが挨拶する。
「あぁ」
ダイゴはホテルにチェックインするとすぐにこの町のポケモンジムにやってきた。もちろん挑戦に来たわけではない。ヤーコンはこの町のジムリーダでもあるのだ。
ダイゴは初対面のこの男にあまりいい印象を持たなかった。町の名士で会社の社長もしているという男だからてっきり、父上のような上品さの漂う紳士かと思いきや、無愛想なうえ妙に土臭いオッサンじゃないか。
「お前なぁ、ウチの宿泊施設に泊まらないなら、先に連絡入れてくれねぇと困るんだよ」
ヤーコンがやれやれという風に言う。
「はい?」
ダイゴはいきなりの苦言と、なぜ自分がPWTの宿泊施設に泊まる気がないことがこの男に知れているのかという疑問で混乱していた。
「ツワブキ家の坊ちゃまには、ウチの宿なんかとても泊まれるもんじゃなかったのかもしれねぇけどよ、他あたる気なら先に連絡入れておいてくれねぇと、向こうのスタッフたちが動けなるだろ」
「は、はぁ……すみません」何か腑に落ちずあいまいな謝罪をしてしまった。
「まったく、金持ちのボンボンはこれだから……人の迷惑ってのをちぃとでも考えたことあんのかねぇ」そういって、これでもかとばかりにため息を吐く。仮にもゲストとして招かれたはずの相手への態度とはとても思えないほどだ。
あんまりの態度にダイゴもむっとした。
「僕はここまでPWTのゲストトレーナーとして着ました。僕の家のことはここでは関係ないでしょう。それに僕がまだ会場に挨拶へ言ってないなんてどうして言えるんです? イライラするのは結構ですけど、憶測でそこまでよくも言えるもんですね。……田舎モンが小金稼いだくらいでエラそうしてんじゃねぇよ」
この世界規模の大会を開いたヤーコンが稼いだ金は決して「小金」程度ではないだろうがもう口が止まらなかった。
――沈黙。
ヤーコンは先ほどまでと打って変わって黙っている。表情からも何も読み取れない。ダイゴは少し後悔していた。本当はこっちが悪いのについついキレてしまった。気まずい。
「ちょっとついてきな」
沈黙を破りヤーコンが言った。表情は相変わらず読めない。
「……はい」
そう言うほかなかった。
ヤーコンに従ってついて行った先は洞窟だった。
「ここは俺の会社が作ったトンネルでネジ山まで続いている。お前の探し物は、ネジ山でもこのトンネルの中でもそこいらじゅうに転がってるだろう。さっきも言った通り、このトンネルもあとネジ山も俺の会社のもんだ。気に入ったのがあったら好きなだけもってけ。遠慮はいらん」
ヤーコンはそれだけ言うと踵を返し、ダイゴを置いて出ていこうとした。
「ま、待ってくださいヤーコンさん! どうして急に……?」
ダイゴにはヤーコンがどういうつもりでいるのか全く分からなかった。彼のスタッフには迷惑をかけ、彼に向かって暴言まで吐いてしまって、それがなぜこんな親切になって返ってくるんだ?
「嫌なら構わん。さっさとホテルにでも帰りな」
嫌なわけがない。願ったり叶ったりだ。
「いえ……決してそういう訳ではないのです。僕は生来の石好きで――」
「知ってる」とヤーコン。
「えっ?」
「お前なんか勘違いしてるんじゃないのか。えっ? ダイゴさんよ。お前は俺にとってもお客様だ。お前を含め、ゲストトレーナーを歓迎するためずっと俺もスタッフも準備してきた。何を用意すれば喜ばれるか下調べもしてる。だから、お前にはこのもてなしが最適だと思って案内した。さっきはつまらねぇこと言ってすまんかった。だがな、俺はダイゴ、お前を歓迎してるんだよ。さっきのは……まぁあれだ、俺はポケモンと自分に正直をモットーにしててな、イライラしてたのをついついクセで言い過ぎちまった。すまんかった」
ずっと無表情だったヤーコンがぎこちない笑みを浮かべていた。照れくささと、慣れなさの混じった、初めて見るオッサンの笑顔だった。
ダイゴは困惑していた。ころころと変わる状況とヤーコンの態度にどう対応したらいいのか分からなかった。
「あ……ありがとうございます」とりあえず感謝を伝えた。それ以外なんと言うべきか思い浮かばなかった。この男は不器用なだけだっただけということなのか。
「ま、楽しんでってくれや」最後にそういうと再びヤーコンはダイゴを置いて出ていこうとした。
「あっそうそう」本日二度目、出ていかないパターン。
「はい?」
「お前さっき、なんで俺が、お前がうちの施設に泊まってないってこと分かったか気になってたろ?」
「えぇ……」気になってはいた。今となってはどうでもいいことだが。
「あれはな、お前の様子をみて分かったんだ。もともとゲストトレーナーが来たら施設からすぐに連絡がくるように指示してあったんだがな、ダイゴがきたという連絡はなかった。なのにお前は手ぶらで荷物を持ってる風ではない。表に車が停まってるのも見えねぇし、それで分かったわけよ。あぁ、こいつはどっか別のホテルに荷物おいてきて、そっから歩いてきたんだなってな。どうだ? 俺の推理? なかなかなもんだろ?」ヤーコンは満面のしたり顔で言った。
言われてみれば当然の流れだ。一つ一つの状況を追って考えてみればすぐにたどり着く結論だ。だが――
「さすがです……」ぼそり言った。我ながらそっけない相槌だった。
だが、この当然の流れを当然にこなせる人間は少ない。人間はそもそも何でもない時に周りの状況にいちいち頓着しない。何でもない時、それら状況は馬耳東風といった具合に頭の中を素通りしていく。
ダイゴはなんだか打ちのめされたような気分だった。ヤーコンは企業の社長でジムリーダもしている男だ。それくらいの観察眼、状況判断能力があるのも不思議なことではない。
――じゃあ、俺は?
俺だって元チャンピオンだ。刻一刻と戦況の変化するポケモンバトルを、ギリギリの試合を何度も勝ち抜いてきた。ヤーコンにも負けない……いやそれ以上の「眼」を、俺は持っているはずだ。
――あなたもホウエンを代表する素晴らしいトレーナーだから。
あの女――シロナならヤーコンのように察することができたろうか? 俺の立場だったら彼の本当の感情や意図に気付くことができただろうか。
――あなたとの勝負楽しみしてるわよ。
「くそっ」
ヤーコンは明日ゲストトレーナー同士の顔合わせをするから朝のうちに会場まで来るように言いこのトンネルから出て行った。ホテルに泊まることは何も問題ではないらしい。
石探しにはピッケルだとかブーツだとかいろいろ準備が必要になる。だからこのトンネルを探索する前にホテルに戻らないといけない。
しかしダイゴは戻らずトンネルの奥へと進んでいった。進んでいくと野生のポケモン(後で調べたらガントルというらしい)が出てきたのでこちらはメタグロスを出して倒した。さらに進んでいくとノズパスやコドラといった別のポケモンも出てきたがすべて倒して進んだ。トンネルの中にはトレーナーもいた。そのトレーナーたちも見かけ次第全員に勝負を挑み倒した。だんだんメタグロスを戻すのがめんどくさくなって、ボールに戻すのをやめた。何匹何人倒してもこちらは無傷だった。もっと進んでいったらトンネルを抜け出た。野生のポケモンもトレーナーも見当たらない。それでもダイゴはまだまだ勝負したりなかった。
これほど悔しい思いをしたのは久しぶりだ。ホウエンリーグであの子供に負けた時以来の悔しさだ。
でも何がそんなに悔しいのかよく分からない。ただ、負けた気がする。誰に? ヤーコン? シロナ? いや、両方かもしれない。ただ、俺は負けた。そんな気がしてものすっごく悔しい。
――ゴツンッ!
「痛っ!!」突然背中のあたりをハンマーのようなもので殴られてふっとんで地面に倒れた。あまりの痛さにうずくまったまま一瞬動けなくなった。
「お前! 急に何すんだよ!」
やっとこその場に座ると、目の前のメタグロスに言った。コイツの思念の頭突きは身構えてても危険な代物というのに、不意打ちでくらって無傷だったのは奇跡だった。
「いてて……」
立ち上がるとさらに腰のあたりに痛みが走った。メタグロスは俺を吹っ飛ばした位置から動かずこっちをじっと見ている。じゃれてたのかどうか知らないが、反省している風では無い。
――コイツ!
一瞬痛みも忘れて俺は怒りのままメタグロスに近寄った。アイツは動かない。俺は頭に血が上って、メタグロスをまっすぐ見据えそのままの勢いで右足を大きく後ろに引き――。
やめた。
「帰ろっか」ポケットからボールを取り出し、メタグロスを戻した。
コイツとの付き合いはもう何年になるだろう。コイツはいつだって俺の最高のパートナーで、そばにいてくれた。だからコイツの考えてることは目を見ればなんとなくわかる。こっちの思い込みかもしれないが、でも、分かるんだ。
「悪かったな、メタグロス」右手のボールにつぶやいた。
別に俺がコイツに何をしたわけでもないが、俺は謝らずにいられなかった。
すーっと深呼吸してみた。イッシュは今秋も終わりかけの季節。山の空気はとても冷たく澄んでいる。ダイゴは頭の中が冷やされていくのを感じていた。
深呼吸を終えると今度は服についた土を払った。さっき地面に転がった分もあるのだが、改めて自分の姿を見てみると酷い有様だった。がむしゃらにトンネルを抜けているあいだに靴は泥だらけズボンや上着にも土が付き転んで擦れた部分は布地が痛んで毛羽立ってしまっている。これじゃあモードストリートで俺を捕まえていたシロナをとてもどうこう言えない。強者の威厳がかけらもない。
ホテルに戻ろう。帰ったらすぐに服を脱いでシャワーを浴びたら、着替えてメタグロスや他のポケモン達とご飯を食べよう。それから……。
ダイゴは右手のボールをポケットに大切にしまった。
――コイツにはあとでまたちゃんと謝っておかないとな。
あんな、悲しい目をさせてしまった、その謝罪をしておかないとな。
怒りのままメタグロスに詰め寄った時、あいつの悲しい目に気付いた。どうしてそんな目をしているのかも、すぐにわかった。
『プライドを忘れるな、自信を取り戻せ。かつての敗北に飲まれるな、次の勝利を目指していけ。王者のプライドを思い出せ!』
メタグロスが思い出させてくれた。王者のプライド。
――俺は強い!
「うわぁ……」
ゲートを抜けた先でダイゴは思わず声が漏れた。話には聞いていたがPWTの会場はそうとうな規模だった。半島が丸ごと施設になっている。
翌日の朝、ダイゴは初めて会場に来ていた。ヤーコンの言っていたゲストトレーナー同士の顔合わせの為だ。
半島の中央に巨大でな建造物がPWTの本会場になる。この建造物は巨大なだけでなく、デザインも凝っていて正面入り口の真上にあるでっかい電光掲示板や左右に設置されたライトがチカチカと光って目が痛いほどだ。
中に入ると、そこもまた巨大な空間だった。二つの大きなモニュメントや観葉植物、ただよう空気まで、何もかもが新品という感じがする。天井まで4,5mはあるだろう。しかし開催前の施設の中には、当たり前だが中にはほとんど人がおらずぽっかり空いた洞穴を思わせた。
「ダイゴ! こっちだこっち!」
左の方から声がした。そっちを向くとヤーコンが手を振って呼んでいた。
ヤーコンの前には六つほど椅子が並び、そこには見知った顔が並んでいた。ダイゴはそれらの左からゆっくり向かていった。
ダイゴから見て一番手前の右の椅子には、ドラゴン使いのカントーチャンピンとして名高いワタルが座っている。真っ黒なマントに身を包み、何か思案にふけっているかのように目をつむっている。いや、眠たいだけだなアレ。
ワタルの正面にはダイゴとも交流の深いホウエンチャンピオンが座っていた。ミクリは横を通るとこっちに向かって軽く笑みを浮かべ、とまたすぐに正面に顔を戻した。
ワタルの右にはあの女が座っていた。シロナは長いブロンドを床ぎりぎりまで垂らし、いつものロングコートに身を包んでいた。歩いていくダイゴをじっと見つめる姿からは嫌でも強者の余裕を感じさせる。
シロナの向かいにはぼさぼさの真っ赤な髪をしてポンチョを着た壮年男性が座っていた。アデクと直接の対面をするのはこれで初めてになる。だがここイッシュにおける彼の強さは他地方まで噂が広まっている。
シロナの右隣りには最年少と思しき少年が座っていた。アデクと同じくグリーンもここで初対面になる。今でこそカントーのジムリーダをしていると聞くが、かつては史上最年初のチャンピオンでもあった天才だ。
「ダイゴ、お前はそこに座りな」グリーンの前の空いた席を指さしヤーコンが言った。
そこに座るとヤーコンが挨拶を始めた。
「あー……その、ここに集まってもらった方々には改めて、はるばる来ていただいて感謝する。こっちでのもてなしもあるから存分に楽しんで行ってもらいたい。それから、これが今日の本題になるが、皆さんの中でも今日これが初対面という人がいることだろう。そりゃ、どの方も有名なトレーナーばかりだから名前くらいは聞いていると思うが、ここは一つこれから先のライバル同士として挨拶していってもらいたい」ヤーコンはそれだけ言うと後ろに控えていたスタッフとともに去って行った。
ヤーコンが去って行って、ダイゴは他の人たちの動きを見ていた。ワタルはさっきから目をつむったまま微動だにしない。……絶対寝てるだろアレ。その前のミクリはどうしたものかと困った様子でもじもじしている。対してシロナはさっそく向かいのアデクと話し始めているし、ダイゴも何か話さないといけない気がして目の前のグリーンに声をかけた。
「君がグリーン君だね。君の話はホウエンでもいろいろ聞いているよ。僕の名前は――」
「ダイゴだろ。知ってるぜ」言い切らないうちにグリーンが答えた。
「ほぉ、それは嬉しいな」
「石好きの変人だろ?」
「……」
初対面の相手に変人呼ばわりされたショックで言葉に詰まってしまった。
「ははっ! 冗談だって、冗談。鋼のチャンピオンダイゴの実力はカントーでも有名だぜ。あんた、相当腕が立つらしいな。ま、お手柔らかに頼むぜ」
このグリーンの態度を幼さと決めつけるのは危険だと、ダイゴは感じた。飄々としてみせてはいるが、この男の実力は間違いない。今、これだけの大物に囲まれても一切物怖じしない態度は、その実力を裏づける証拠と捉えるべきだろう。
「こちらこそ、天才グリーンの胸を借りるつもりでお相手願うよ」
そういうとグリーンは何も言わずにんまりと笑った。
こちらも軽く笑みで返した。しかしその手には汗。
互いに余裕を見せていても、平気なふりをしているだけって分かっている。それでも決して弱みは見せない。これは実力の拮抗した、強者たちの戦いなのだから。
面識のなかった者たちとの挨拶は一通り終わった。といっても、グリーンを除けばアデクだけなのだが。アデクは終始おおらかといか、がさつな男だった。細かいことは気にしない、言い換えればちょっとやそっとのことでは動じない男のように思われた。
一時間ほどして再びヤーコンが戻ってきた。今日はもうこれで解散らしい。ヤーコンに言わせてみれば、「小学生じゃないんですから、あーだこーだ引っ張られるの退屈でしょう?」ということらしい。間違いない。
顔合わせが終わり、宿泊施設へと戻る者、どこか出かけていく者と別れていく中で、ダイゴは座ったままでいた。
彼らは皆強い。ポケモントレーナーとして最高の人たちだ。
だから俺はここで勝たなければならない。誰にも負けない。最強は、俺だ。
「シロナ!」
部屋に戻る途中のシロナがさっとこちらを振り向いた。
ダイゴは足を組んで、両手は肘掛に乗せて深く椅子に座っていた。さながら王様のようだ。虚勢と思われても構わない、虚勢ではないのだから。
「けっきょく僕が一番強くてすごいってこと、君に教えてあげるよ!」
王者の中の王者を決める戦いが始まる。
-------------------------------------------------
ひっさしぶりの投稿。
いつも見ているアニメ番組にちらっと過去キャラが出た時のような、そんなアレが書きたかった。
出来てないかもしれないけど
(
〈書いてもいいのよ〉 〈描いてもいいのよ〉 〈批評してもいいのよ〉 〈ダイゴさんかっこよく書きたかった……〉
イサリさん
感想ありがとうございます。
ポケスト板で感想貰ったの初めてなんですごいドキドキしています。嬉しいですありがとうございます。
誰でも「これだけは許せない」っていうものがあると思うんですよね。
ただこのドーブルの場合、主人が死んだということで、その感情は極端なものになってしまったという。←作中で書けなかったことを、ここで書いて誤魔化そうとしている人
改めて感想ありがとうございました。
では、拙文失礼しました。
こんばんは、逆行さん!
小説読ませていただきました。
表現を趣味とするものとして、非常に身につまされる寓話でした。
絵と文章、表現形態は違っても、自分の好きなものを信じるあまり、盲目的に他者を排除しようとしてしまう心理は痛いほどよくわかります。
自分とは異なるものがもてはやされているところを見ると、自分の創作まで否定されたようで、どうしようもない嫉妬に駆られてしまうものですよね……。
ふと我に帰った瞬間の、ドーブルの言葉にできない後悔と苦々しさが伝わってくるようでした。
それでは、ありがとうございました。
俺のかわいい3匹のグラエナ。俺のことが大好きで、いつも俺の言うことを聞く。今日も俺が仕事から帰って来たらしっぽが千切れるくらい振って俺のところに来て。寂しかっただろ。こんな男には女なんかこねーから世話してくれるやつがいなくて困るよなあ。
一番古い付き合いのグラエナがクロコで、2番目の素直なやつがハイイロで、最近の勇敢な新入りがチョコだ。特に意味はねえ。でもどれも俺の自慢のグラエナだ。強さだってその辺のひよっこなんかに負けん。
餌箱に入れてから待てと待機させてクロコにお手、と命令した。待ちきれない様子で、しっぽを振ってるから尻が浮いてる。それに前足を何回も俺の手に乗せてくるからお手というより俺の手にタッチしている。ハイイロは俺の目をじっとみて早く許可をくれないかと言っていた。チョコはおすわりを命令したのにしゃがんでる。
みんなのふわふわの黒い毛皮をなでてやると、俺はよしと言った。早いが我れ先に餌箱に鼻を突っ込む。対して上手くもないポケモンフードだが俺の安月給だから我慢してくれよ。
飯おわったら夜の散歩行こうなー。おかげで俺は運動不足にもならねーし。もう真っ暗だからお前ら保護色だけどな。
ポケモンの足にはやっぱり舗装してない道路がいいみたいだな。グラエナたちが土の上をはしゃぎながら歩く。歩くというより、飛び跳ねてる。散歩のときくらい落ち着いて前歩けよ。俺が歩けないじゃねえか。
俺の足に体おしつけて歩いてるのはチョコ。俺の足の間に顔を出すのはクロコ。歩けと言えば歩くけどそのうちチョコと反対の足にじゃれついてくるハイイロ。街灯が暗いんだが仕方ない。少し離れるとグラエナだと見えなくなるからな。リードつけてるからどっかいっちまうようなことはないが。
3匹のリードは同じ手で持ってたんだが急に引っ張ってそれぞれ走り出した。俺はその反動で転んだ。いきなり何があったんだ。俺のグラエナが家出の仕方をするとは思えない。
「クロコ! ハイイロ! チョコ!」
遠くでグラエナの息づかいが聞こえる。3匹で何をしてるだ。追いかけないとあいつら野生で生きていけるかもしれねーけど!
道を少し外れると真っ暗で何も見えなかった。名前を呼んでも何の反応もなかった。
なんでいきなりあいつらが俺から離れていったのか解らない。俺は真っ黒な森をぼーっと見ていた。あんなにかわいがっていたのに見捨てやがって。あっさり見捨てやがって。餌も毎日やってたのに裏切りやがって。
個人的なことだけど一週間前に振られたばかりでそれでもお前らの世話してやったじゃねえか。餌餌餌、散歩散歩散歩って毎日いってやったのにこのザマかよ。
ああもう人間もポケモンも信じねえ。どーせお前ら自分のやりたいようにやるんだろうよ。帰って寝てやる。もう明日から何の世話なんかしなくていいんだー。
俺の家の玄関の前に、黒い毛皮が座っていた。
なんだよ、なんでお前ら帰って来てんだよ。しかも一匹増えてるじゃねえか。遅かったじゃないかと言いたげな顔してんじゃねえよ。じゃれつくなよ。しかもハイイロのリード切れてんじゃねえかよ。いくらすると思ってるんだよ。これでも節約してお前らに投資してんだぞ。
しかもチョコ、増えたやつを見てみてと差し出すなよ。ポチエナだし。大きさからいって生まれたばかりか?
「……またか」
だからこいつら走って行ったんだな。お前らもそうだったもんな。
ホウエンでは子供でも小さい時からポケモンに触れさせる教育をしている。個人的に持つ場合もあって、力のあまり強くないジグザグマとかポチエナとかエネコが人気だ。
けれどな、力のあまり強くないということは、強くなったらイラナイんだよ。不要になる。だからクロコはゴミ捨て場に一匹でひたすら主人を待っていた。ハイイロは餌を取ろうとして川で溺れてた。チョコは主人に会って自分より強いポケモンにコテンパンにされていた。
俺にボランティア精神はないが、クロコが俺の弁当の匂いにつられて会社まで追いかけてきたことが発端だ。仕方ないから飼ってやったら次々に捨てグラエナを拾ってきやがる。
俺の経済力を知ってろよ。全部のグラエナは助けられねえよ。あー、そんなこといってもこいつらには解りませんですね。俺がバカだった。生まれたばかりのポチエナとかどうしろって言うんだよ。
頭かかえてしゃがみ込むと、クロコが覗き込んで来る。疲れたのか、元気だせと言ってるのか知らんが、元はといえばお前らのせいだ。
「随分たくさんのグラエナを飼ってるんだな」
知らないおっさんの声がかかる。好きで飼ってるわけじゃねえよおっさん。こいつらみんな俺をよりどころにしてる捨てグラエナだっつーの。なんならこのポチエナおっさんが飼ってやれよ。
「その力をトレーナーとして使わないか」
「はぁ?」
「そんなたくさんのグラエナをそのレベルまで育てるのは、トレーナーとして……」
「これは俺のグラエナじゃねえよ。弱くなって要らなくなったグラエナを引き取っただけで、育てたトレーナーは今頃どっかでエリートトレーナーじゃねえの」
それより俺はもう寝たい。ポチエナのボール買いに行きたい。誰だよこのおっさん。話が止まりそうにないというか、ますますこのおっさんの恐ろしい系のオーラが増えてる気がする。上司に怒られる前の空気と似ていて俺の居心地もよくない。
「それを制御しているのだから、やはりトレーナーの才はある。どうだ? 悪い話ではあるまい。私は才能のあるトレーナーを探している。あるポケモンを探しているのだが、それにはトレーナーの協力が必要なのだ」
「へえ。何の為にポケモン探してるんだ? こいつらの寝床を広くしてくれるのか?」
「……まあそんなところだ。条件はこちらから出そう」
人をほめて引き抜くなんてよくやるじゃねえかこのおっさん。今より貰える金が増えるなら協力してやろうじゃねえの。そうしたらこいつらにもっといいもの食わせてやれる。
「これだ。この計画は秘密にして欲しい。先を越されたくない」
「企業秘密ってやつか。なるほどな」
妖しい匂いはする。しかしこのおっさんの話になぜか興味がある。玄関先でグラエナに囲まれてる男に声をかかけるやつなんていないだろ。何を期待しているんだ。
「この話に乗るなら、君の名前をそこに書いてくれ」
俺は敢えて違う名前を書いた。よく知らないおっさんに全てを吐き出す勇気はないんでね。
「……この話、乗ってやるよウヒョヒョ!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グラエナに囲まれたホムラというツイートがホムラ大好きな人からまわってきました。
グラエナ多頭飼いしてるんだろうなあ。いいよなあ。ワンコに囲まれて幸せそうなホムラ。
わんわんお
【好きにしてください】
ドーブルという種族は、好きなように絵を描く権利があった。野生に生きる者はもちろん、たとえ人間に捕まっても、たまに自分の身体に傷をつけて戦い、ちゃんと言うことを聞いていれば、そんなに悪いトレーナーじゃない限り、自由に絵を書くことができる。それは私達ドーブルが、絵を描くために生まれた存在だからであって、そうじゃなかったら認められない。
私のトレーナーは、とても良い人だった。私のことを無理させず、適度に回復してくれた。私が火傷を負った時は、すぐに薬を塗ってくれた。私に対して、とても優しく接してくれた。だから私は、あの人に良く懐いた。
私は主人を喜ばせたかった。私の描いた絵を見せて、主人を心から喜ばせたかった。それがドーブルとしての、せめてもの恩返しだと思った。
そのために私は、主人の嗜好を徹底的に調べた。明るいものが好きなのか。暗いものが好きなのか。シンプルなものが好きなのか。複雑なものが好きなのか。何を正しいと思っているのか。何を悪だと思っているのか。
長い間の努力の成果もあり、主人の嗜好がだいたい分かった。主人の嗜好に従い、私はたくさんの絵を描いた。主人は必ず喜んでくれた。心が安らぐと言ってくれた。心が安らいで、幸せな気持ちになれると言ってくれた。だから私も嬉しくなって、もっと頑張って描いた。主人が嫌いな思想に対する風刺も、訳が分からないながらも、盛んに取り入れてみた。主人はくすっと笑いながら、良くやったと誉めてくれた。
何時の間にか、主人が喜んでくれる絵が、一番描いてて楽しいものになった。それ以外を描くことに、もはや喜びを見出せなくなっていた。
楽しい日々は、あっという間に過ぎていった。私が絵を描く。主人が喜ぶ。そんな単純な日々が、ずっと続けばいいと思った。
しかし、運命というのは残酷だった。
ある日突然、主人は交通事故で死んだ。
外から大きな音がした。ボールから出てみると、主人が血だらけで横たわっていた。隣には、トラックが止まっていた。私はその光景をただ眺めていた。
何が起こったのか分からず、しばらくの間、主人の親の家でぼーっとしていた。しばらくして、その事実をじわじわと理解して、私は暴れまわった。主人の親が必死で私を止めた。
それから私は、いろいろあって野生に帰った。主人に捕まる前の、草むらへと戻った。戻ってきた私を見て、昔の仲間は喜んでいたが、私の心が晴れることはなかった。
野生に帰った後も、絵は描き続けていた。それは、ドーブルとしてのアイディンティを保つための行為であり、やらなくてはならないものだった。
そして、どのような絵を描いていたかというと、主人が好きな絵を描いていた。前と変わらない絵を描いていた。何時の間にか、主人が好きな絵が、「これが普通」という形に変っていた。絵とはこうゆうものである。これが正しい絵の姿だ。そう思うようになっていた。
仲間達とは、仲良く暮らせていた。主人のことは辛かったけど、仲間がいたから、私は前向きに生きてこれた。
ある時、自分より年下のドーブルが、絵を描いているところを見つけた。私は自分の絵に没頭していたので、他のドーブルの絵をしっかり見ることがなかった。年下のドーブルは、私が見ていることに気づかず、ただひたすら絵を描き続けていた。
描いてる本人には、興味がなかった。ただ、その絵が少し気になっていた。その絵を見ていると、何か、自分の中に、黒い感情が、沸いたような気がした。
その絵は、主人の好きなものとは、全然違うものだった。むしろ、正反対だった。背景の色や絵が複雑な所が。もちろん、正反対じゃない部分もあった。けれど、一部が正反対なせいで、全てが真逆のように見えた。この頃私は、主人が好きな絵が、正しい絵の姿だと思っていた。だからその絵に、違和感を感じた。違和感はすぐに、怒りへと変わっていった。そして怒りはついに、極端な思考を産み出した。
こんなのは絵じゃない。
私は文句を言った。こんな絵は、おかしいと。冗談じゃないと。もっと真面目に描けと。こんなものは全然、心に響かないと。時折暴言を織り交ぜて、私は散々に言いたいことを言った。相手の反論を怒鳴り声で遮って、ひたすら何度も「正しいこと」を伝えた。
言われている方は、とうとう我慢できなくて、ついに私に攻撃してきた。私は非常に呆れ返った眼で相手を見つめた。相手は攻撃を止めなかった。こいつは手を出さないと分からないのか。その思った私は、戦闘態勢に入った。
相手はオスとはいえ年下。簡単に勝てるだろうと思っていた。
しかし、私は甘かった。
相手の力量を知らずに、戦いを挑むのは愚かだった。
自分より遥かに強い技を、相手はたくさん持っていた。「スケッチ」を使って火炎放射やハイドロポンプを覚えていた彼は、あっと言う間に私のHPを0にした。絵を描くことに努力値を振っていた私に、最初から勝ち目などなかったのだ。
相手は去っていた。意識が朦朧としていた私は、彼に何も言うことは出来なかった。
しかし、これで終わりではなかった。痛い思いをして、これで終了とはいかなかった。
彼は、私の仲間に、一連のことを伝えた。あいつが急に偏見を押し付けてきた。挙句の果てには攻撃してきた。恐らく誇張して、話を簡潔にするために嘘も混ぜて、ここらへんにいるドーブル達に話した。そのせいで、私はすぐに、嫌われ者となってしまった。仲良くしていた友達も、次第に離れていった。
そしていつしか、私の味方はいなくなった。私は独りになった。
私が絵を描いていると、みんなが笑ってきた。平気で馬鹿にしてきた。私は構わず無視をしたけど、心の中では悔しくて泣いていた。私の絵を否定されると、主人のことを否定されようが気がして、それが一番辛かった。それが一番悔しかった。誰にも責任はない。ただ、私が自我を失って変なことをしたせいだ。
私は言い聞かせた。主人は良い人だった。良い人が私の絵を誉めてくれた。ということはその絵は、正しい。間違ってなんかいない。
それに、ドーブルという種族は、「自由」に絵を描く権利があるのだから。何を言われたって無視すればいい。
それは、とても立派で、とても愚かな考えだった。
その一言を待っておりました。
こういう話って、現実世界でも具体例はありますよね、きっと。
暇です、暇です、暇、暇、暇、暇、暇、暇、暇、暇、暇!ねー、遊んで、遊んで、遊んで、遊んで!今すぐ遊ばないと、サイコキネシス…【以下略】
誰かこの状況から助けて下さい、1万払ってもいいから。誰にだ、誰でもいいから。コイツ止めてください…
ほら、英雄!出番、出番!チャンピョン、ジュンサーさん、ジムリーダー!1万でいいなら雇いますから。
ー悲鳴じみたことを考えつつも、無粋に思考に割り込んでくるそれ。情け容赦なく飛んでくる念波。
先ほどから、頭がガンガンしている。
エーフィに進化する前から似たようなことしてさ、飽きないの?
遊んで、遊んで、遊べよ!どうせまたくっだらない男に、玉砕しに行くんでしょ。自分の容姿も考えろって!そこらへんのフツメンで妥協しなさいよ。未来見せてあげようか?
やめてください。そんな殺気出しながら、睨まないでください。後、サイコキネシス飛ばすのもダメだから!
下の人から苦情来たら、出ていかなきゃならないんだよ。
イジケルな。
瞳、ウルウルさせても無理!
「せっかくのデートよ、留守番くらい頼んだっていいでしょ?」
ようやくゲットした彼氏の方が、優先度は大きくなるに決まってる。小うるさいエーフィよりは、マシだし。
さみしがり屋でもない癖に、何でいつもデート前になると、こうな訳?邪魔ばっかする。
クールな癖に……。
あーあ、あたしも甘いな。うう、頭痛、ひどいな。
こんなことされても、やっぱね。
「大人しくしてたら、遊んであげるから、ね?」
コクンと頷いたエーフィの瞳に、妖しい光が宿った。そう簡単にいくと思わないことね、ユキ。甘いわよ?
数時間後。
ライモンシティの遊園地に、カゲボウズとジュぺッタ、イーブイの3種が大量発生したのだった。
「エル!出てきなさい、今日という、今日は!許さないから、お風呂入れるわよ!おやつなしよ、ブラッシング1週間なしよ。いいわねー」
こうして、旅のトレーナーは追いかけっこする二人を見るのだった。
こんにちは、お世話になっている小樽ミオです。m(_ _)m
唐突かつ勝手ながら、ストーリーコンテストを開催する運びとなりました(企画ページ:http://yonakitei.yukishigure.com/stcon2012/index.html)。
マサポケでは休止中のストコンに準拠し、できるだけ「ストコンのつづき」といった雰囲気でご参加いただけるように計画しているものです。
以下、
(1) コンテスト概略、準備チャット会開催のお知らせ
(2) コンテストのトップを飾るイラストおよびバナーイラストの募集
(3) 審査員の募集(10月3日21時追加)
の3点についてお話を進めさせていただきます。
◆
【1. コンテスト概略、準備チャット会開催のお知らせ】
開催期間は「年内に完結する」ことを基準に、
2012年10月15日〜12月23日(募集:10月15日〜12月1日、投票:12月3日〜12月22日)
として仮決定しています。
ただ、もっとも重要な「お題」が未決定です。みなさまのご参加を想定する以上、お題はこれまでのストコン同様多数決で決定したいと考えております。また、上述の開催期間も当方が勝手に仮決定したものですので、修正が必要になるかもしれません。
つきましてはチャット会を開催したうえで、お題や開催期間を筆頭に、今回のストコンに関してみなさまのご意見を賜りたく存じます。
チャット会は本年10月7日(日)20時より、マサポケチャットにて行わせていただく予定です。
かなり急な提案ですが、ご参加いただければ嬉しく思います。
●とりわけご意見をお伺いしたい点
・ お題
・ コンテストのタイトル(決まってないんです 苦笑)
・ 開催期間は適切な長さか
・ 募集は「小説」だけに限定するか
・ その他みなさまがお気づきの点
募集期間につきましてはすでに「駆け足気味」というご意見をいただいておりますので、「年内で完結させる必要はあるの?」「年を跨いだっていいじゃん!」というご意見が多ければ、募集期間を中心にもう少し余裕のある開催期間としたいと思っております。
また、「チャットでは聞きづらい/チャットに入りづらい/チャット前に伝えておきたい」という方がいらっしゃりましたら、当方のツイッターアカウントやメールアドレスに直接ご連絡をいただいても構いません。アカウントやアドレスはこちらに掲載しませんので、お手数ですがコンテスト用のウェブページからご確認ください。m(_ _)m
◆
【2. コンテストのトップを飾るイラストおよびバナーイラストの募集】
コンテスト開催にあたりまして、トップ絵およびバナーとなるイラストを募集させていただこうと思っております。チャット会後に本格的に始動したいと思っておりますので、「描いてもいいよー!」という方がいらっしゃいましたらお心づもりをしておいていただけると幸いです。
◆
【3. 審査員の募集】(10月3日21時追加)
当コンテストでも、可能であれば審査員というシステムを継承したいと思っています。
審査員の募集要項は、(1) 全作品を熟読し、 (2) かつ熟考した上で全作品に評価およびコメントを行う ことが可能な方とさせていただきます。
審査員であることに対するお礼はできませんが、ソルロックも裸足どころか全裸で逃げ出すほどにまばゆい笑顔で感謝の気持ちを表させていただきたいと思います(やめい)
※審査員とは
(これまで同様)全作品を読み、全作品にコメントすることを使命とする役職です。
これまでのストコンでは、どの作品に対しても審査員の方々から必ずコメントがつくことが応募特典として挙げられていました。
◆
以上でございます。
では、ご参加を考えてくださっている方がいらっしゃりましたら、チャット会で改めてお会いいたしましょう(*・ω・*)ノ
後味わりい。
でもなんだろう、ポケモンの世界ではよくあることなんだろうな…現実はシビアだ
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |