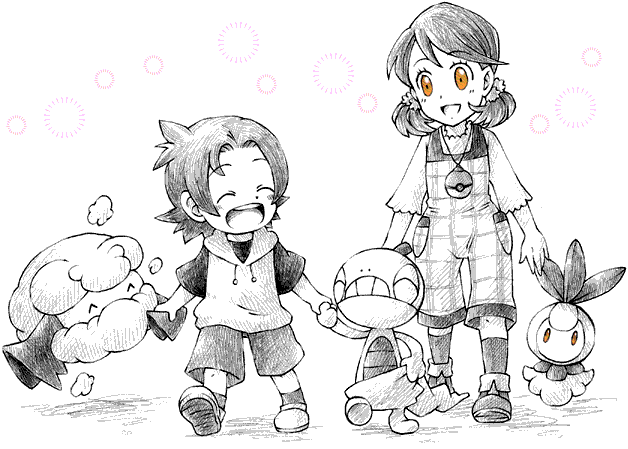
「シュヒくんはどうですか? 出来れば私も一緒にいてあげたかったんですけど」
ブリーディングクラブの研修旅行があって。眉を八の字に歪ませ、そう言い加えた少女にアデクは小さく頷き、問う。
「うむ……わしは勘違いしておったのだが、彼はポケモンに対して恐怖心があるだけで、決して嫌っているのではないんだな?」
「私が見る限りでもそうだと……だってシュヒくんがもっと小さかった頃はテッちゃんとキューちゃん……あ、シュヒくんのご両親のポケモンです。ふたりとも、すっごく仲が良かったもの……」
少女の返事を聞きながら、アデクは先頃まで少年が座っていたアイアンチェアに腰掛けた。ナズナも倣って隣の席に座る。それから面を伏せた。
「あの時からです。シュヒくんがふたりを……ポケモンを、怖がるようになっちゃったのは」
「あの時?」
問い掛けられ、ナズナは言うか言うまいか躊躇するように視線を移ろわせたが、しばしの後ゆるゆると口を開いた。
「シュヒくんが四歳くらいの時だったと思います。私よくシュヒくんたちと一緒に遊んでいて」
そうして彼女は、少年の過去を伏し目がちに語り始めた。
それは今から六年前、シュヒと彼の家で飼われていたポケモンたちと共に郊外で遊んでいた時のこと。ナズナが少し目を離した隙に、少年たちの姿が見えなくなったのだという。
地面に残されていたメイテツ――モンメンの綿を辿って行くと、田畑と林の境にシュヒたちがおり、その目前に巨大な百足のポケモン、ペンドラーがいた。
カナワは森林に取り囲まれた町であるから、野生のポケモンが迷い込むことはままある。シュヒは遠くからこの蟲を見つけ、一緒に遊ぼうと近づいたのだろう。にこにこ見上げている少年の両隣でしかし、連れ合いの二匹は明らかに戦慄いていた。勝手に歩き出した彼を何度も止めようとしていたのかも知れない。
ペンドラーは腹を空かせてでもいたのか、かなり気が立っていた様子で、ナズナがその場に辿り着き「逃げよう」と腕を引くより前にシュヒらに襲いかかった。怯んで一歩も動けない少年、それを瞬間的にモンメンとズルッグが庇い、反撃に出た――そこまでは良かったのだ。
戦わせるために育てられていたのではないモンメンとズルッグの戦い方にはまるで秩序が無かった。今から逃げ出してもすぐに追い付かれてしまうと理解していたのか、必死に追い返そうと、自分たちの何倍もの大きさがある相手に滅茶苦茶にぶつかって行った。
彼らが牽制する間、ナズナはたじろぎながらも、連れていたチュリネに眠り粉を指示した。敵が一瞬気を失った所に、二匹が渾身の力を振り絞って体当たりする。合間に何度かチュリネが敵の体力を吸い取って行った。
巨大百足との相性は芳しくなく、どの攻撃も効果の程は望めなかったが、そこはやはり多勢に無勢。攻撃を続けるうちにペンドラーは苦し気に呻き出し、踵を返して森へと去って行った。
大事に至ること無く追い払えたことに胸を撫で下ろした幼い人間たちに、前線で戦い抜いた二匹が振り返り――思わず息を詰めたナズナの隣で、シュヒが小さく悲鳴を上げた。モンメンとズルッグの体は完膚無きまでに切り傷だらけで、所々血が滲み出ていた。百足は全身に無数の棘を持っており、二匹はぶつかる度に体の至る所を刺されていたのだ。
青い顔をして後退した少年に、二匹はけれど、笑顔で近づいた。今にも卒倒しそうな大怪我を負いながら、両腕を彼に差し伸べて。傷付いた肌が引き攣って上手な笑顔になっていなかった。それでもなんとしてでも、彼を安心させようと二匹は笑っていた。ナズナにはそのように見受けられた。
しかし当のシュヒは、ゆっくりと歩み寄って来るポケモンたちから逃げるように後退りし――ついに彼らに触れられたという瞬間に、大声を発したのだった。紛れも無い、恐怖の叫びを。
「それからシュヒくんはポケモンを避けるようになったんです。ポケモンは怖い生き物なんだって、思い込んでしまったんでしょう……」
じいと少女の双眸を見詰め、その語りに耳を澄ませていたアデクは、眉間に皺を寄せて短く唸る。
「そうか、そんなことが……。年端も満足にゆかぬ子供が見るものではなかったろうな」
内に秘めていた――もしくは、二匹自らが眠らせていた野性。本能を剥き出しにして戦い、見るも無惨に傷ついた姿を見て、次は自分を傷つけるのではないかと、次は自分がこのような姿になるのではないかと、幼子が恐怖を抱くのは不自然なことでは無い。
「私の所為で、シュヒくんたちを危険な目に合わせちゃったから……シュヒくんのご両親に全部お話ししました。でも、ポケモンが戦ったのはシュヒくんを守るための手段だし、それを見てシュヒくんが怖がるのも当然だし……シュヒくんが、ポケモンは時には恐ろしい生き物だって理解した上で、またテッちゃんキューちゃんと解り合いたいって自分から望むまでは、私たちは見守ってやるしかないと言われて」
いつかきっと、彼にも理解出来る日が来る。二人は彼を、本当の弟のように想っていて、だからこそ勝ち目の無さそうな相手にも立ち向かい、ボロボロになっても彼を守ったのだということを。
なるほど、と老翁が無精髭の生えた顎に手を添えて頷く。
「シュヒくんは幼いながらに、自分がポケモンたちを傷つけてしまったとも、思ったのかもな。また、そこまでしてポケモンが自分を守ったのは何故か? それを知らぬが故に反射的にポケモンを恐れ、避けるようになってしまった……。ご両親の判断は正しかったのだろうね。我々がいくら必死に説いたところで逆効果だろう」
「アデクさんもそう思いますか」
ナズナは安心とも不安ともつかない平淡な返答を溢した。直後、膝の辺りに据えていた両の拳を震わせ出す。
「でも……お父さんとお母さんを同時に亡くして、一人じゃ耐えられないくらい悲しいはずなのに。いつも一緒にいたポケモンたちとも、同じ悲しみとか寂しさとか解り合えないなんて……そんなのつら過ぎるって私、思って……!」
妙に実感の篭った台詞だ。彼女も以前に、少年と似た経験をしたのかも知れない。そうアデクは思考した。
途中から次第に涙声になり、話し終えると同時についに零れた一滴が、少女のチェック柄のスカートに小さな染みを作る。握り込んだ両手から肩へと伝染した震えを抑え込もうとすると、余計に視界が滲んでしまい、ナズナは堪らず二粒三粒、涙の粒を腿や手の甲に落とす。
「安心しなさい、ナズナさん。周りの者に手助けが出来ない訳じゃない。ほんの小さなきっかけなら、与えられるはずだよ。わしらはそれを考えようではないか」
見兼ねて、出来る限り優しく、アデクは俯く少女に声をかけた。ナズナはポケットからハンカチを取り出して目元をぎゅっと押さえてから、顔を上げる。
「きみにとっても大切な“弟”を、助けてあげようぞ?」
穏やかでありながら力強い温もりを湛えた二つの青藍に、心が奮い立たされるようだ。涙の筋が残る頬を綻ばせ、ナズナは明るく応えた。
「……はいっ!」
*
「して、メイテツとキューコはどうしておるのかな?」
「私がお世話しています。……どっちかって言うと、私のお父さんの方が張り切ってますけどね」
家に置いて来た二匹をひっきりなしに構っているだろう父親の姿を想像し、ナズナは苦笑いするも、にわかに表情を改める。
「私、お父さんの影響でブリーダーになろうと思ったんです。お父さん、若い頃はトップブリーダーだったって……今は見る影も無いんですけど」
言って、彼女は胸元で揺れていたモンスターボールをネックレスから外し、ボタンを押す。中から現れたのは白い肌に橙色の目を持った、人間の少女のような風貌のポケモンだ。
「この子は、お父さんが昔育てていたドレディアの子供です。ブリーダーになるって決めた次の年に、お父さんがプレゼントしてくれて。私も、お父さんのドレディアに負けないくらいの大きくて綺麗な花を、この子に咲かせてあげたいなぁ〜って思っているんです」
呼び出された花飾りポケモン・ドレディアは、見知らぬ人間に目を留めると、葉っぱのドレスの裾をつまんでぺこりと頭を下げる。感心して問えばナズナが教えたのではなく、研修の際に見学したコンテスト会場で、ドレスを着たトレーナーが同じ仕草をしていたのを見て、自分で修得してしまったとのことだった。
「ドレディアは健康状態が直に見て取れるポケモンだ。育てるのは骨が折れるだろう?」
「はい。とっても」
「ブリーダーもトレーナーも、人間が思い詰めてしまうと、それがポケモンにも伝わってしまう。あまり気負うこと無く、ポケモンといかに毎日を楽しく暮らせるか、どうすればポケモンが笑顔でいてくれるか。それのみを考えておれば、まず悪い方向に転ぶことはない」
そう話すと、アデクは「失敬」と一言置いてドレディアを観察し始めた。顔つきや目の輝き、葉っぱで出来た髪や腕やドレスの張りと艶、そして頭部に咲き誇る、トレードマークの赤い花冠。
「うむ。素人目から見ても瑞々しい花を咲かせておるし、優しい、いい表情をしている」
ブリーダーがどのようにしてポケモンの容態を探り結論を出すのか、アデクもよくは知らない。だが長年のトレーナーとしての直感で推し測れば、そういった見解に落ち着いた。
花飾りポケモンの前から立ち上がり、老翁は若きブリーダーへ語りかける。
「ドレディアはね、ナズナさん」
呼ばれた少女は彼を仰ぎ見て、続く言葉を待つ。
「きみの心を映しているのだ。共にあるポケモンが何を望むか忘れるなよ。さすればきみもドレディアも、もっと成長出来るに違いないぞ」
感極まってナズナは椅子からがばっと立ち上がり、一礼した。
「はい! ありがとうございます」
目指す道とは違えど、この界隈に数ある山頂の一つに立つ男。そんな彼に助言を貰えるというのは、彼女にとって、光栄至福以外の何物でも無かった。
「カルーーーッ!」
と。和やかな空気を突如として、青い甲虫が発破した。
「きゃあ!?」
ボールが開閉する際には光が発されるため、ポケモンの出現に対してある程度心構えは出来るのだが、それでもナズナは中から飛び出して来た彼の勢いに盛大に驚き、仰け反った。
「なんだカブルモ、また勝手に飛び出してきおって」
主人に呆れた顔をされても、幼いカブルモに慎みなど備わる訳も無く、相変わらず活発に跳ねるだけだ。
「この子はまだ子供なんですね? 元気いっぱい!」
「ああ。カナワに着いた時も凄いはしゃぎようだったよ。こいつのやんちゃっぷりには毎日骨を折らされておる」
カブルモは椅子と揃いのアイアンテーブルを見上げて何やらカルカルと訴えている。机の上には主人が屋内から持ち出して来た荷物袋があり、それに目を留めたアデクは即座に合点した。少女との対話に夢中になって失念していたが、庭に出たのは自分のポケモンたちに昼食を摂らせるためだったのだ。
すまんすまんとカブルモに謝り、急かされるまま支度する。昨日と同じプラスチック皿を三つ取り出してフーズを盛り終えると、残る旅の仲間を庭へ放してやる。新たに登場した二匹のポケモンに、ナズナはわぁと息を吐いた。
「バッフロンとクリムガンですよね。実物を見るのは初めてです、迫力ありますねー!」
様々な人が行き交う都会暮らしならいざ知らず、トレーナーの関心を引く場所ではないこの田舎町では、彼らのような“見るからに上級者向き”のポケモンを目にする機会は滅多に無い。ナズナは物珍しげに、尚且つ彼らの機嫌を損なわせぬよう注意しながら凝視する。餌をがつがつと貪る二匹の姿は第一印象通りの荒々しさだが、獰猛さは感じられなかった。
「でも、優しい目をしていますね」
「こやつらとは長い付き合いになる。始めに比べれば随分大人になったものだ。こいつと違ってな」
老翁は腕組みし、カブルモを顎で指した。
「カブ?」
もりもりとフーズを頬張っていた甲虫は一瞬だけ手を止めて二人の方を向いたが、すぐに食事を再開した。
やがて皿の中が空になり、三匹は名残惜しそうにしつつも顔を上げた。食べ終わった皿を片し、庭にある水道へと向かうアデクの後ろで、自分と変わらぬ背丈の竜にナズナが歩み寄る。
「ああ、クリムガンには素手で触ってはならんよ」
「はい! “鮫肌”ですもんね」
アデクが袋から取り出した厚手の軍手を少女に渡す。ありがとうございますと礼を言い、ナズナは受け取った軍手をはめてクリムガンの肩の辺りに触れた。布越しでも地肌の刺々しさが詳細に伝わってくる。
「ブラシをかけても?」
「ありがとう。きっと喜ぶよ」
腰に提げた鞄の側面から幅の広いブラシを抜いて、程々の力を掛けてゆるりと撫で下ろす。慣れない感覚に始めは硬直したクリムガンだったが、肩から腕、背中を辿り、尻尾に差し掛かる頃には目蓋を閉じてリラックスしているようだった。
仲間が心地好さそうにしているのが羨ましかったのだろうか。芝の匂いを嗅いでいたバッフロンが自分も頼む、と言いたげに鼻を鳴らしながら近寄って来た。少女は頬笑み、頷く。
仕上げに両手両足の爪を布でゴシゴシこすってやると、クリムガンの厳つい顔はすっかり緩み切り、傍で見ていた翁が「だらしないなあ」と笑った。
「はい、バッフロンの番よ」
ブラシをハンカチで拭い、軍手を外した手で頭突き牛を招く。竜と入れ替わりで目の前へやって来たバッフロンの頭に、ナズナはおもむろに手を差し入れた。
「わ、頭ふわふわもこもこ。温かくて気持ちいい〜!」
なんなんだ、と批難がましく一瞥する頭突き牛へナズナは誤魔化すように笑い、彼の胴体にブラシを掛け始める。しかし。
「カブー!!」
「わ!」
「カブルモ?」
シュヒ宅の周りを散策していたらしいカブルモが家の影から現われたかと思いきや、何故だかバッフロンの頭部に突進し、体毛に埋もれて見えなくなった。
「ブモウ!!」
邪魔をされたばかりか自慢のアフロの中に侵入された頭突き牛は、鼻息荒く頭を振り回す。青い塊がぼとっ、と地面に落下した。
「さてはカブルモ、おまえもブラッシングしてもらいたいか!」
一昨日同様またもや顔面から倒れ込んだ甲虫を、アデクは片手で拾い上げてテーブルに乗せる。我が意を得たりと言う風に、甲虫はカルカル鳴いて飛び跳ねた。
「うふっ。もう少し待って。まだバッフロンの分が終わってないからね」
ナズナは彼にそう伝えると、不貞腐れたように木陰に横たわってしまったバッフロンの手入れに取り掛かった。
「アデクじーちゃん、ナズナさーん」
カブルモのブラッシングもあと少しで済みそうだというところで、リビングの窓からひょこっとシュヒが顔を覗かせた。
「どうした?」
翁が訊ねると
「お茶いれるから来て!」
との返事。
時刻を確認すれば午後三時十六分。おやつの時間という訳だ。
家に上がり、食卓へ赴くと少年は戸棚の前で茶器を選んでいた。アデクがそれを手伝い、ナズナは自分が持って来た菓子をシュヒから受け取った大きな陶磁器に移す。マフィンやフィナンシェ、バターサンドにラングドシャなど様々な甘味が並んだ。
「あっ、シュヒくん、紅茶を淹れてくれるのね」
少年宅には多数の紅茶の茶葉があった。彼の母親の昔からの趣味で、ナズナも何度か呼ばれたことがある。シュヒは食器棚に並んだ中から、ビリジャンのパッケージの茶葉を取り出していた。銘柄など覚えていないし、まだ紅茶よりジュースが好きな年頃なので適当な選択であったが、奇しくもそれは、父親が好んでいたダージリンだった。
「おいしくないかもしれないけど……」
本人が危ぶんだ通り、注がれた紅茶は渋い口当たりだった。しかし菓子と合わせれば丁度良い案配だったので結果オーライだ。
各自思い思いの菓子をつまみながら話すうち、話題は自然とナズナの研修旅行のこととなった。
ズイと言う草原の町で育て屋や牧場を手伝って勉学する傍ら、近辺の街へ遊びに行った時のことを、少女は話す。ヨスガシティの教会で、シンオウ地方の創世神話を聞かせてもらったこと。トバリシティに向かう途中突然の大雨に見舞われ、慌てて近くの喫茶店に逃げ込み、ホットミルクの温かさに和んだこと……。
「噂には聞いてたけど、ほんとシンオウは寒かったよ〜」
腕を抱えて身震いして見せる少女にアデクが仰々しく相槌を打ち、シュヒが訊ねる。
「じーちゃんも行ったことあるの?」
「おうよ。もう五十年は昔のことだがな!」
「…………」
「五十年……」
翁はそのように言って笑い、少年少女らは彼との年齢差をしみじみ思い知らされた。
三人から離れたソファの上では、ケースの中のタマゴが小刻みに震えては、幽かな光を放っている。
| 