
このフォームからは投稿できません。
[もどる] [新規投稿] [新規順タイトル表示] [ツリー表示] [新着順記事] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
|
|

|
|
一抹の不安。それが起こる事はまだ、無さそうだ。
何事も無く、ひと月が過ぎ、ふた月が過ぎて行く。秋から冬へ、季節も移り始めていた。
そして、そんな短い間でカイリューは言葉を理解し始めていた。ニュースを毎日眺めていたり、俺がウインディに喋りかけていたりをずっと興味深く聞いていたからだ、と思う。
お前は何で俺に付いて来たんだ? まだ、その問いをカイリューに聞いてはいない。
聞いたとしても、言葉を扱えないカイリューが俺にその理由を伝えられるだろうか。
きっと無理だろう。
ココドラに鉄くずを与える。値段はポケモンフーズよりもかなり安い、タダ同然のものだが、錆びてはいない。コドラに進化した時には、こっそり買ってある玉鋼なるものを与えようと決めている。
やはり、質の良い鉄程、こいつは良く食べる。俺の手持ちになる前は廃材の錆びた鉄をばっかりを食っていたのだろうか。
心なしか、見つけた時よりも少し体のツヤが良くなっている気もした。
カラッとした肌寒い風にカイリューは少し寒さを感じていた。
ウインディと距離を縮めているように見えるのはきっと、錯覚じゃないだろう。ウインディは慣れたとは言え、その強さにまで慣れた訳ではない。
こっそり近付いて来たのを見ると、さっと離れた位置に移動する。
見ているとまるで、だるまさんが転んだ、みたいな感じだった。
暖房をそろそろ付けようか。窓を閉めて、エアコンのスイッチをこっそりと入れ、音が出ると、カイリューはびくっと驚いて温風が吹いて来る方を見た。
ココドラは、そんな時でもばりばりと鉄くずを食べ続けていた。
驚かない、というよりも周りに関心が無いと言うか、気付いてないと言うべきか。
その鋼の体に神経は通ってるのか、と聞きたくなる。まだこいつが驚いた所を俺は見ていない。
鉄くずを食い終えると、眼を閉じて眠り始める。食っちゃ寝、それ以外じゃ偶にとことこ庭を歩いたりするだけだ。カビゴンみたいな奴だと良く思う。
ココドラの冷たい鋼の体が、徐々に温まって行く。夏も冬も、こういう体のポケモンって、どう体温の調整をしているんだろうか。金属の体じゃ、熱がすぐに内部に伝わってしまうと思うんだが。
まあ、特に問題なく生きている。それだけで十分ではある。
そして、冬のある日。
とある事が起きた。平日の、仕事がある日だ。
ムシャーナはふわふわと浮いていた。口から出ている煙に、俺の夢が少し映っている気がした。
体を起こして、違和感に気付く。隣にウインディが居ない。カイリューも。ココドラも。
「……あれ?」
部屋のドアも開いている。何が起きているのか分からないまま、俺は寝室から出て、階段を降りる。
肌寒い、外の空気が感じられた。玄関も開けているのか。
体に震えを感じながら、玄関に近付いた。風の音以外、特に何も聞こえない。
靴を履いて、外に出る。さらさらと雪が降り始めている中、ボスゴドラが居た。カイリューと同じ位の巨体には、カイリューと同じ位の威厳が感じられた。
……親、か? ウインディとカイリューはそのボスゴドラの近くで警戒を程々に解いて座っていた。
ココドラはそのボスゴドラの腕の中で、けれどいつも通りのように眠っていた。
ボスゴドラが俺の姿を見止めた。
後退りそうになるのを堪えた。その目は、母親のものだった。そして、そこに怒りは無いように見えた。
確証は全く無いが、試されている気がした。
俺が、このココドラを持つに値する人間かどうか。後退れば、無理矢理にでもココドラが連れて行かれそうな気がした。
このココドラには愛着も湧きはじめているが、今、このココドラが母親に連れて帰られたら、俺はその愛着を失う以上の何かを失う気がしてならなかった。
それは、俺が子供を持ちたがっているという証拠なのだろう。
親で在れる最低限は満たしていたいという証拠なのだろう。
ボスゴドラは、目を未だに眠っている息子に戻した。どれだけの時間、目を合わせていたか、長かった気もしたし、短かった気もした。
ボスゴドラは、手でココドラを何度か撫でた。ココドラが薄らと目を開けて、甘えるかのように母親に向けて前足を動かした。
初めて、俺はそこで、ココドラの感情というものを見た気がした。そして、 羨ましさを感じた。
俺は、そうなるのだろうか、なれるのだろうか。父親として。
羨ましさの直後に、不安も覚えた。
こん、こん、とボスゴドラがココドラの健康を確かめるように、鋼の肉体を軽く叩いて、そして光沢が出るように磨いて行く。
寒さは覚えていたが、その光景に俺は何故か目を離せなかった。
そして、ボスゴドラはココドラを降ろして、もう一度撫でてから、また俺の方を見た。
近付いて来る。ウインディが立ち上がり、俺はそれを手で止めた。カイリューも、その俺の手を見て、立ち上がったまま、動きはしなかった。
強大な存在感は、カイリューとはまた別物だった。そして、慣れた訳でも無い。怖いと言う感情は胸の中をぐるぐると強く渦巻いている。
けれども、俺は後退る事もしなかった。逃げてはいけないと、分かっていた。
ボスゴドラは、俺の前に立つと、しゃがんで俺と顔を合わせた。ただ、俺は視線を合わせた。それ以上もそれ以下も何もしなかった。
観察されているのは、カイリューの時と同じだった。
暫くして、ボスゴドラはどこかからか、球体を取り出して、俺の手に握らせた。
メガストーンではない。
鋼色の球体だった。それは、オーブと呼ばれるようなものの気がした。
ココドラにきっと、持たせるべきものなのだろう。ボスゴドラはそして振り返ってココドラをまた撫でてから、歩いて去って行った。
ずん、ずん、と巨体の音を少し響かせながら、後ろ姿が小さくなって行く。ココドラは、追う事はしなかった。けれども、少し悲しそうな目で、母が去って行くのを眺めていた。
その時、ウインディの情けない声が聞こえた。
カイリューが、ウインディを強く抱きしめていて、ウインディは足掻いているものの、抜け出せそうには無かった。
カイリューは、強く、そして絶対に離さないような感じでウインディを抱き締めていた。
それは、暖を取る目的以外にもあった。
目を強く閉じて、忘れたいような、思い出してしまったような、そんなものをまた記憶の彼方へ飛ばしたい、けれども、ポケモンの温もりが欲しい。そんな感じがした。
ウインディはじたばたと暴れる。俺に助けも求めて来た。
「諦めろ」
俺がそう言うと、絶望したかのような目を向けて来る。
仕方ない、モンスターボールを取って来てやるか。
「ボール取って来てやるから、待ってろ」
出来るだけ早く、と言うように、ウインディは情けなく吼えた。
寝室にあるボールを取りに戻りながら、思う。
カイリューはきっと、あそこから逃げる為に俺に付いて来たのだろう。何か逃げたい思い出があるその場所から逃げる為に。
そしてそれはきっと、子供とかに関する事だ。
俺と似ている、と思った事があったが、本当に似ているかもしれない。
天井を眺めて、ぼうっとする。俺はこのままで本当にいいのだろうか。曲がる必要もあるのだろうか。
ウインディの声で俺は我を取戻し、仕方なく寝室のボールを取る。
ムシャーナの煙が目に入った。そこには、子供が居た。
叫びたい気持ちになった。
空腹に耐えかねて目を覚ますと、いつの間にか日が沈んでいたらしい空は紫色であった。沈んでいた、とわかったのは開け放した窓の外から聞こえてきた豆腐売りのラッパの音のせいである。間の抜けた音色が耳に障る。ヤドンだって、もう少し気合の入った声で鳴くに違いあるまい。
今日も自主休講を決め込んでしまったな、と思った数秒後、大学はとうに夏休みに入っていることを思い出す。わざわざ与えられなくとも日頃から積極的休暇を取っている僕にはいまいち実感がわかないが、今は一部の熱心な研究学生とそれに付き合わされる哀れな教員を除けば概ね、長期休暇の緩い空気に身を任せているということだ。もはや遠くなった記憶を呼び起こせば、なるほど確かに、この世の辛苦を掻き集めたかのような心地で受けた試験の数々が思い出される。後は野となれ山となれ、しかし単位はCでも良いから我が手の中に、などと願ったが最後、記憶から消すよう心がけたものだからすっかり忘れていた。
兎にも角にも夏休み、幾ら惰眠を貪っても誰も咎める者のいない時期である。別に夏休みでなくとも、咎める者がいる時であっても僕は構わず惰眠を貪っているのだが、やはり心持ちというものがあるのだ。とりあえず死なない程度に食事をとらなくては、と汗だくの身体を起こす。幾ら汗臭くとも誰にも咎められないのは素晴らしい。
狭い台所の物入れを漁る。使い終わった食器やら捨て忘れた生ゴミやらが突っ込んである、所々が凹んだシンクで蠢いている紫の軟体についた二つの目玉、ガサゴソと音を立てる僕を迷惑そうに睨んだけれども全く気にしない。この、シンクの汚れなのか区別がつかないベトベターは数ヶ月前から僕の部屋に勝手に住み着いた居候である。日々貧困に喘ぐ僕はポケモンなどという金のかかるものを持っていないし、仮に持つとしてももう少し良い匂いのものを選ぶと思う。マサラの実家にいるウインディを連れてくればもう少し部屋が華やぐのだろうが、タマムシはマサラと違って土地が高く、六畳一間が精一杯の僕がウインディなどと同居した日には圧死も免れないと予想するのは容易であった。
かくして僕は、何を考えているのかようわからん、悪臭スライムマンと今日も蜜月なのだ。どうせ居座られるならばもっといい感じのポケモンが来ないかとも思うのだが、窓から入り込んだニャースは部屋の散らかり具合を一瞥すると再び夜闇に消えていくし、一度は住み着いたイトマルも巣だけ残して去ってしまった。恐らくはベトベターよりも強い我が部屋の臭いなどのせいだと思うが、僕は来るもの拒まず去るもの追わずの精神である。適応出来なかった彼らのことは気にしないことにした。
やっと見つけたカップ焼きそばは賞味期限が三ヶ月ほど過ぎていたがそれも気にしない。お湯を沸かそうにもヤカンがベトベターの枕になっているので、そのまま食べることにした。空腹は最高のスパイスとはよく言ったもので、マサラの母親が見たら激昂しそうなこの食事もなかなかに美味しいものである。バリバリと、微妙に湿気った麺を齧りながら一人の食事を楽しむ。シンクのベトベターが無意味に蠢くから正確には一人では無いのだが、そういうとこには触れない方向で僕は生きているのだ。
「おい三下」
その、孤高にして至高の一人の時間を早速壊す奴がいた。何だコンチクショウ、と乾いた口で麺を飲み込みながら思いながら、邪魔者の選択肢を考える。僕の部屋には鍵をかけていないからきっと勝手に入ってきたのだろうけど、こんな見るからに盗る物ありません、と言っているようなボロアパートに踏み込む強盗などはいないから、大学のアホ共に違いない。
実際、僕のことを馴れ馴れしく三下と呼び、尚且つ部屋にやってくるような仲間内は大体推定出来る。山本は夏休みに入ったらすぐにヒワダに帰ったらしいし、大崎はバイトがあるとか無いとか言っていたから、きっと森田のバカだろう。声もそんな感じがした。僕はカップ麺から顔を上げ、恨み言の一つでも言ってやろうと、乾麺でジャリジャリした口を開いた。
「何者だコンチクショウ」
しかし口から出たのはそんな言葉と、唾液にまみれた麺の欠片であった。無理もないと思う。しわくちゃのTシャツにジーンズ姿の野郎がいると想定したはずの視界に映っていたのは、宙に浮かぶカボチャだったのだ。
「何者だコンチクショウ」
「うるさい、これ以上焼きそばを飛ばすんじゃない」
「これは失敬」
もう一度言ってしまった僕に、空飛ぶカボチャ野郎こと、バケッチャとかいうポケモンは吐き捨てるように呟いた。
憮然とした声の森田が言った。
「とりあえず名を名乗れよ」
阿呆面をぷるぷると振って、顔なんだか身体なんだかわからないが、顔らしきところについた焼きそばを振り払っているバケッチャに尋ねる。僕の名前を知っているのだから、こいつの名前も聞いてやらないと不公平だ。人の言葉を喋るバケッチャ、というかポケモン全般に渡ってそんな話は現実に聞いたことがないが、今こうして存在しているのだから騒ぎ立てても仕方ない。無駄におののきびっくりしたところで、散らかった部屋がさらに散らかり、ついでに僕が打ち身などをするだけである。
「俺だよ俺」
「なんだ、ミックスオレは高くて買えないから勘弁してくれ」
「ふざけるな。おいしいみずすらケチって人にたかるクセして。俺だよ、森田だ」
呆れた口調で、バケッチャはそんなことを言った。名乗られたのは我が友人にしてタマ大文学部の誇る駄目学生である。ちなみに森田は「駄目学生はお前だ」などと僕のことをなじるが、僕はあえてそれを否定しようという気概は無い。要するに五十歩百歩であり、要するに僕は面倒なのである。
「はぁ。それは奇っ怪なこった」
「てめぇ。信じてないな。俺は森田なんだよ、正確にはバケッチャの中に俺の魂が入ってる状態だが、ともかく俺は俺だ。わかれ」
「無茶言いなさんな」
僕は思ったことを正直に告げた。目にうるさいオレンジ色のカボチャ野郎が言うことはちっとも理解出来なかったため、僕はカップ麺を食べる作業に戻ることにする。放っておけば、このわけわからんちんなカボチャくんもおうちか八百屋へ帰るだろう。どうぞ、温かいご家庭の夏野菜カレーにでもなってくれたまえ、といった気持ちである。
「この野郎、こんな非常事態にカップ焼きそばなんぞ食いやがって。というか酷い食い方だな。せめてソースを水で溶くくらいはしろ」
「大きなお世話だ。この食べ方こそが至高なのだ。ほっといてくれ」
「相変わらず貧乏臭い奴め。そんなことはどうでもいい、いいから話を聞け。俺は死んだんだ。死んで、身体から抜けてしまった魂をこいつに運んでもらってるんだ」
「はぁ、はぁ。それは大儀なことであるな」
「真面目に聞こうという気はないのか。親友が死んだんだぞ。もっと悲しめ」
「だっていきなり言われても信じらんないんだもん。つーか死んだだって? この野郎、僕の貸した五千円はどうしてくれる」
「その点につきましては、誠に申し訳ございませぬな」
カップ焼きそばを放り出してバケッチャに掴みかかろうとした僕の腕は、腹立たしいことに機敏な動きをしたカボチャ野郎にかわされた。
「なるほど、この苛立たせる才能に関しては右に出ない感じ、確かに森田の魂だな。よし信じる」
「ふざけんな。お前が遥か右手にいるから安心しろ。一生かかっても敵うまい。死んだし」
「しかしなぁ。本当に森田なのかお前」
正直話がややこしいから面倒だったのだけど、聞かないのも失礼だと思ったので一応聞いてやった。
「なんだ、俺じゃ悪いか」
「良いか悪いかで言ったら、まあ、悪いかな」
「こんちくしょうめ。言わせておけばキリがない。いいから信じろ、このバケッチャは俺の育ててたバケッチャじゃないか」
森田は単位も頭も気遣いも可愛げも、その他諸々必要なものは何ひとつ足りない男であり、同時に色々と足りない部分全てを体毛へ注ぎ込んだと思われる男でもあった。下手すれば教授と見間違われる髭面のこいつがどうしてバケッチャなどという、似つかわしくないポケモンを連れているのかというと理由は明瞭で、かわいいポケモンを連れていればかわいいオンナノコと仲良くなれるのではないかという浅はかな考えからである。
非常に馬鹿らしい考えだが、その結果もまた非常に馬鹿らしいものであった。リングマにも似た剛毛の大男が連れるバケッチャは、愛くるしいポケモンではなく、腹が減った時の非常食としか見えないのだ。実際、僕はこいつを非常食と呼んでやまない。そう見えるのだから仕方ないだろう。バケッチャだって、可憐な乙女の隣にいればプリチーなマスコットキャラとも見えるナリをしているのに、森田なんぞの隣にいるせいで間抜けな非常食と成り果てる羽目になるだなんて哀れなヤツである。
ともあれ、オレンジ色をしたこのマヌケ面は、確かに森田のバケッチャと見て取れた。なるほど、こいつは死んで、近くにいたバケッチャに魂とやらを乗っけてここまで来たというわけか。さっぱりわからない。
「しかし面倒だからわかったことにしておこう。そもそも、死んだからと言ってなんで僕のところに来るんだ。五千円を返してくれるわけでもないのに」
「そればっかりだな。違う、頼みがあるんだ。俺の親だの妹だの親戚だのが来る前にお前、頼む、俺の部屋に行ってアレとかソレとかを回収してきてくれ」
「やだよ。こんなクソ暑い中、お前の家まで何分かかると思ってるのさ」
「十分もかからないだろ。頼むって。俺の部屋にあるやつ全部あげるからさ」
「僕おとなのおねえさんとかOLとか別に好みじゃないし」
「お前ポケモンごっこ派だもんな、マニアックなヤツ!」
「大体、無理だよ。何かの拍子に見つかりでもしたらタダじゃ済まないだろうし、お前の同意が得られないんだから完全にコソ泥じゃん」
「それもそうか。辛いなぁ」
森田はしょげた声で言った。しかしあくまでそこにいるのはマヌケ面のバケッチャであり、スピーカーのようにして森田の耳障りな声が聞こえてくるのだから、気味が悪くて仕方ない。これならば、ベトベターが意味も無く笑いを浮かべながらシンクでねちゃねちゃしてる音の方がまだマシというものである。
せめて掻き消してやれとばかりに焼きそばをバリバリ食ってやったのだが、森田は気にもしない様子で泣き言を口にしている。せめてパソコンは破壊したいだの携帯も爆発させたいだのとうるさいが、カビゴンのいびきみたいな声で涙ぐまれても気色悪いだけなので静かにしてほしかった。
「というか、森田、お前なんで死んじゃったわけ」
聞くに堪えない涙声をやめさせるためにそう聞いてみると、「お前はニュースも把握してないのか」と呆れたような返事をされた。「仕方ないじゃないか、さっき起きたばっかりなんだから」「しょうのないヤツ」などと言い合いながら携帯でツイッターを開く。この部屋は陽当たりと耐震強度と見た目に加えて電波の届きもよろしくないため、読み込みにはかなり時間がかかった。手持ち無沙汰な沈黙がやや続き、やっとこさ画面が動くようになる。
「ああ、あった。すごい話題になってる。ポケモンリーグで飛び降りだと。何、飛び降りなんぞしたのか森田。迷惑な奴だな」
「違う。俺はそんな血気盛んな真似はしない。記事をよく読め」
「なになに、飛び降りした本人は命に別状無し。着地点に偶然いて下敷きになった男が即死。なるほど、これがお前か森田。間抜けな奴だな」
「それは俺もそう思うよ。しかし不運だ。どうしようもあるまい」
「はは、推定四十代だとよ。身元の確認には時間がかかるねこりゃ。ははは」
「笑うんじゃない。見た目がこんなんなのも不運の一種だ。どうしようもあるまい」
「それにしてもお前、なんでポケモンリーグなんぞ行ったんだ。金も無いくせに」
「金が無いからだ。リーグの設営とか屋台とか、日雇いのバイトを渡り歩いてたんだ」
「なる」
「死んだ時もバイト中だったんだ。野外テントを片付けててな、鉄筋抱えてたせいで上から降ってくる野郎から逃げ遅れた。危ない、みたいな叫び声は聞こえたんだけどなぁ」
「なるなる」
適当になるなる言って相槌を打ちながら、関係ツイートをひたすら見ていくと、飛び降りた奴が誰なのかということがもう特定されていた。末恐ろしい世の中である。ツイッターのアカウントも平然と晒されているが、こういうことを出来る人たちにはエスパー能力でも潜在しているのだろうか。
「というか、待て。この飛び降りたって奴、リーグの準優勝者らしい」
「マジかよ。そんな勝ち組がなんで自殺なんかするんだ」
「一回負けたからじゃないかな。ほら、決勝戦終わった後の呟き」
見ているだけで気落ちする反面、どうにも全身がむずがゆくなってくるような、飛び降り男のアカウントをバケッチャの方に向ける。「げげ」と森田が声をあげた。
自他共に対する恨みつらみ、誰に向けているのかすらわからない泣き言、繰り返される『もう死んじゃおう』。負け組どころかゴミ同然、というかゴミと同居しているような僕から言わせれば、なんで決勝で負けたくらいでそんなに落ち込むんだ、と叱咤したくもなるけれど、エリートにはエリートにしかわからぬ苦しみがあるのだろう。そこに口出しする権利は僕には無い。
「にしても、実際死んじゃったのは自分じゃなくて、ゴミと同居してるヒゲ男だからな。運がいいんだか悪いんだかわからん奴だ」
「何を言うか。こいつ、元々死ぬ気なんかなかったに違いないさ」
「でもお前に当たらなかったら普通に死ぬでしょ」
森田がなんだか怒り出したので、僕は生返事をする。
「確かに飛び降りたのは本当だけど、それは気の迷いだろ。頭に血でも昇ってたんだ、こいつ、ただ目立ちたかっただけなんだよ。自殺予告までしてさ」
「うるさいな。静かにしたまえ。なんでそんなに断言するんだ」
「だってこの野郎、わざわざカイリューに空飛ばしてその上から飛び降りたんだぞ」
「ふーん良かったじゃん生き延びて」
掌を返しつつタイムラインを眺めていると、なるほどそんな旨を書いているツイートも多く見つかった。「本当に飛び降りたいんならそんな目立ったマネしないで高いビルでも行きゃよかったんだ」森田がぼやく。彼の言うことはもっともだし、もしかすると飛び降りたのではなく、飛び降りる感を出していたらうっかり足を滑らせたのかもしれないな、とすら僕は思ったが流石にそれは口に出さないでおいた。どちらにせよ、迷惑な話ではある。そのカイリューが決勝戦でボロ負けしたのではなく、大活躍したらしいというのが、また何とも言えないきもちにさせてくるものである。
「良いものか。こいつもう駄目だぞ、死ななかっただけで大怪我だろうし、俺が死んだからかなり叩かれるだろうからな。準優勝レベルまで戻れるかって話だ」
「飛び降りれたのも最後の晴れ舞台かぁ。まったく、お前が死ぬから」
「俺も余計なことをしたものだよなぁ」
「でも、命落としたおかげで単位落とさなくて済んだし」
「こんにゃろう。上手いことでも言ったつもりか。大体、卒業出来ないことには変わりあるまいよ」
「それもそうだ。つくづくどうしようもないやつ」
僕の言葉に、森田は「まったくだ」と吐き捨てるみたいにして言った。飛び降り男の末路については自業自得であるため追及しないとして、森田の単位はそれはそれで自業自得の話である。追及してもしょうがないことばかりだ。硬い面にかじりつく。粉末のままのソースが上顎に張り付いた。
「しかしもう終わったものは終わったんだ。グッド・バイだ」
「何ぞそれ」
「そういう話があるんだよ。いたわるような、あやまるような、甘ったるい囁きでグッド・バイって言うんだ。一度やってみたかった」
「お前に囁かれてもゾッとするだけじゃないか」
ぺっぺっ、と唾を飛ばして僕は森田を追い払う真似をした。それにしても、此の期に及んで『やってみたかった』とはなかなかに前向きな発言である。そのまま前だけ見続けて落とし穴にまんまと引っかかりそうな類の明るさだ。要するに馬鹿である。
「そういうものは、もっともったいぶってもいいんじゃないかと僕は思うよ」
「いいんだよ。別に大したことじゃないんだから。明るく、軽快に。そっちの方がよっぽどいい」
「阿呆らし」
「阿呆で結構。サヨナラは笑顔で言う主義だ」
「単位には未練タラタラだったくせによく言うや」
「それに関してはサヨナラを言う気が無いからな」
得意げに言うことではない。こんなやつにはサヨナラを言われる以前に、付き合いを持ちたくないと単位だって思ってるに違いないだろう。
「そうだ、お前バケッチャの世話頼むぞ」
「何をおっしゃる。なんで僕がお前の非常食の世話なんか焼かないといけないんだ」
「非常食じゃない。よく考えろ、かわいそうなのはこいつだぞ。こんな劣悪な部屋に住まわされることになるだなんて」
「お前の部屋だって似たようなもんじゃん。絶対やだ」
森田の部屋はゴミで出来ていて、多分この世で一番強力な悪臭が常に充満している。その強さたるや、臭いにつられてやってきたドガースやマタドガスが慌てて逃げ帰っていくほどだ。ベトベターが住んでいるだけ僕の部屋の方がまだ許される部類である。
しかしそれはそれ、これはこれであり、なぜ僕がこの浮かれポンチオレンジ野郎を育てなくてはならないのかというのは別の問題だ。床をバンバン叩いて抗議してみたが、森田は気にも留めない様子である。自分勝手な男なのだ。
「文句なら飛び降りた準優勝に言うんだな。あいつがあんなことしなけりゃこんなことにはならなかった」
「お前がリーグのバイトなんかするからダメなんだ。チクショウ」
「まあ落ち着け。所詮そういうものなんだ。俺たちみたいな世界にとっての脇役、エキストラもどきの下々は、ああいう主役級に振り回されるしかないんだよ。諦めろ」
「主役、って言ってやらないところにお前の意地の悪さがよく出ているな。こんな時だけ文学青年ぶるんじゃない。だいたい、どちらかというとお前の立ち位置はスタントマンだったじゃん」
「失敗したがな」
言いながらまた腹が立ってくる。脇役は主役に振り回されるしかない、という森田の言い分は概ね正しく諸手を挙げて賛同出来るところではあるが、しかし、脇役にも脇役の生活というものがある。たとえそれが、ゴミとか古本とか拾ってきた成人雑誌とかにまみれたものであったとしても、一応は立派な部屋である。世界というやつはちっともわかっていない。仕送りはすでに底をついていて、非常食の世話をする余裕など僕にはないのだ。
「かわいそうなバケッチャ。お前、変な病気なんかに罹らず強く生きるんだぞ」
「人が菌を培養してるみたいな言い方はやめるんだ」
「してんじゃん」
「してるかもしれない」
「じゃあいいってことだな」
何がいいのかよくわからないが、きっと何もよくはないと思う。窓の外から吹き込んできた生温い風が、粉末ソースとこぼれた麺のカスを飛ばしていった。飛んでいった粉微塵は、埃と混じってすぐに見えなくなる。なに、乾いているからカビる心配も腐る心配もないだろう。そういうことにしておく。
僕が麺を咀嚼する、バリバリという音だけがしばらく響く。いい加減口が渇いてきたが、水を取りに行くのが面倒だったので我慢してバリバリし続けることにした。ほっぺの内側に麺が刺さる。ムカついたので噛み締めてやった。
「どうせお前暇だろうし」
森田が腹立たしいことを言う。どうせ、とは何たることであろうか。
「僕も色々と忙しいんだよ」
「色々ってなんだ」
「色々は色々だ」
「どうせ寝たり部屋を汚したり酒を飲んだりする程度だろ。お前の色々は。それを暇というんだ」
「間違っちゃいないけど。でも、明日からバイトでも探そうかなとは思ってたんだ。それは本当だよ」
実家に帰る旅費も使い果たしたからね、と付け加えると、やめとけ、死ぬから、と森田が説得力に溢れかえった忠告をしてくれた。素直に聞いておこうと思う。旅費に関しては電話口で謝り倒すしかあるまい。
「しかしなぁ。お前、そんなに適当に生きてて虚しくならんのか」
「森田に言われたくないけどね。でもいいんだ。なるようになるさ」
「何か頑張ろうとは思わないのかい。」
「ポケモンリーグの優勝でも目指せって。ゴメンだね。そんなことしたくないもん」
「どうしようもないやつだ。安心するといえば安心する。それでこそお前だ。つくづくどうしようもないやつ」
「何とでも言え。いいんだよ。僕は適当に、主役級の人たちに振り回されながら生きてくから。誰かの害にはならないし、害になれるほどのやる気もないからね」
「そうだなぁ」
森田はそれ以上何も言わなかった。彼が黙っているので、僕はカップ焼きそばを食べる作業に戻った。口の中の水分はもはや失われ、イッシュにあるという広大な砂漠地帯もかくやという気になったが、それでも空腹は水分よりも焼きそばを求めているのだから仕方がない。バリバリというよりはもそもそという音であったが、僕はひたすら口を動かした。森田が無言なので、バックミュージックはベトベターの粘着音だけである。ベトベターだとわからなければ、美しく艶かしいシャワーズが尻尾を気怠げに揺らしている音に聞こえなくもない。所詮は想像力に帰結するのだ。
「でもねぇ、森田」
無事にカップ焼きそばを食べ終えたので、僕は息をついて声を出す。白の発泡スチロールには、僕の唾液が汗でこびりついた僅かな粉末が残っていた。指でこそぎとってなめていると、「汚いな」森田が自分を棚に上げて言った。
「なんだ」棚上げ野郎が返事をする。
「僕にとっては、この、空から飛び降りたリーグ準優勝よりも、リーグの優勝者よりも、お前の方がずっと主役みたいなヤツだったよ」
「リーグ優勝者が誰だか知ってるのか」
「いや知らんけど」
「適当なヤツだな」
「それでもそういうこと」
「そうか。悲しいヤツだなお前も」
「他でもない僕が一番そう思っているとも」
「しかしなかなか、それはそれで、楽しいものだったんだろ」
「人のト書きをとるんじゃないよ。文学部のクセしてその程度もわからないのか。そんなだから卒業出来ないんだ」
「お前も人のことは言えないだろうが」
「森田こそ、僕のことは言えまい」
「そうだな。悲しいヤツだな、俺も」
「そうとも。どうしようもなく不毛なんだ。僕たちときたら」
「一緒にすんな」
「とりあえず五千円返せ」
「来世はデボンの跡取りに生まれ変わるからそしたら返す」
「ほざけ。そうなったら五千円と言わず五億円くらいよこせ。利子だ」
「やなこった。五千円だ」
「うるせぇ。とりあえず五千円返せよ」
「うるさいのはお前だ。ばか者」
「化け物みたいなツラしてるくせに何を言うんだか。大ばか者」
「まあ、否定はしない」
「何度だって言うさ。大ばか者。この野郎め」
「うむ」
「アホ。たわけ。えーと、バカ。まぬけ。うーん、あとは何があるかな」
「語彙力の少ないヤツだな。こっちが不安になってくるわ」
「勝手に不安になってろ。ばか」
「ばかはお前だ」
「ばか。おおばか。すごいばか」
「それしか言えないのか、お前は」
「悪いか」
「いいや」
「そうだろ」
「そうだな」
「じゃあどんどん言うとも」
「そうしとけ」
「ばか野郎め」
「うるせえ」
「そうしとけと言ったのはお前だ」
「そうだったな」
「そうだったろ」
そこで森田の声が聞こえなくなった。バケッチャは何が起こったのかもわかっていないのだろう、相変わらずのアホ面を晒して浮遊している。わかっていたとしてもこのアホ面だ、そこに大差などきっとない。「このアホ面を見ているとお前をたびたび思い出す。非常に不快だ」森田はよくそんなことをのたまった。失礼な男とはあいつを指すための言葉であるに違いない。しかしアホ面であることを否定するだけの器量が僕に無いのも、悲しいことに事実であった。
アホ面が二つ、汚いシンクの汚いベトベターモ入れるならば三つ、取り残された六畳一間はやけに広いものであるとなと僕は思った。バケッチャが浮いていて、場所を取らないことを抜きにしても、この汚い部屋は僕にとっては広すぎる。精一杯散らかしてみているのだけれど、それでも尚、僕の部屋はまだまだ広い。
やはり、世界にとっての僕など無意味で無害な存在であるのだ。こんな狭い部屋一つ持て余す僕が、世界の隅っこを少しばかり占拠したところで誰が困る道理もあるまい。そうだ、誰も困らない。誰の迷惑にもならないなれないなりやしない、僕たちとはそういう存在なのだ。所詮はエキストラ以下、誰に怒られるはずも無いというのに。
バケッチャの二つの目には欠片ほどの知性も無い。ずっと見ていると阿呆が移りそう、これ以上移る阿呆も無いかもしれぬが念のため、僕はカボチャ野郎から視線を外して携帯を見てみることにする。ツイッターでは先ほど以上にリーグ飛び降り事件がホットなトレンドで、ご丁寧に現場の写真を撮って上げている猛者もいる。僕とは違って、エネルギーが有り余っている連中なのだろう。一生かけても分かり合えないと思う。
ニュースサイトでは続報を伝えていて、被害者男性の身元が確認されたと報じられていた。代理で出席票を書いてやるなど、何度か綴った文字列を目がなぞる。予想していたよりも早かった、あいつは学生証かトレーナー免許でも持っていたのだろうか。現役の学生だと判明した時の捜査員の驚きたるや計り知れ無い。
ツイッターのアプリを閉じて、代わりにあいつのラインのトーク画面を開く。一週間前に交わしたやりとりが表示された。『シンオウ神話学概論落とした』『とれる前提で話してるのおかしい』『出席しないで単位取れたら俺が神話になれたのに』『アルセウスに謝ってろ』『アルセウスの時間の無駄』『ごもっとも』まことにくだらない会話である。
ここはひとつ、僕が気の利いた言葉でも添えてくだらなさを払拭してやろうと思ったのだが、そもそも、気の利いた言葉を思いつこうとして思いつければ苦労しまい。そうだ、思いつけるはずなどないのだ。あいつはああやって言ったけれど、そうそう出来ることでもない。やはりあいつは稀代の馬鹿だ。あんな風に無責任なことを言いやがって、だから単位も取れずに人相ばかり老けていくのだ。そうだ。そうに違いない。大体、自分だって結局出来なかったクセして。
明るく、軽快に、阿呆らしく。
大したことなど無いのだから。
笑顔でさようならを。
無茶言いなさんな。
そんなメッセージを送ってやろうと思ったのだが、あいにくの電波状況のせいで『送信出来ませんでした』というエラーメッセージが表示されただけだった。全くもって間抜けな顛末である。全くもって、僕たちらしく、虚しく、馬鹿げた、酒の肴にもならないつまらん話だ。携帯をしまったポケットは、生乾きのを履いてきたせいであろう、少しばかり湿って気持ちが悪かった。
踏場もない床を踏み歩くと、足が何かを蹴る感覚がした。麻雀牌だった。あいつに負けた分の一万円を払い渋りしていることを思い出したが、何、来世に持ち越す五千円の債権が債務に変わっただけだ、さしたる差異はない。どうせ踏み倒すつもりだったのだし。
牌を放り投げてドアを開けると、夜の熱気がまとわりついた。排気ガスの臭いが漂っている。今この時間に空いている、ゴーストポケモン用のポケモンフーズを売っている店などどこにあるというのだろうか。戻って来る頃には汗だくになっているに違いない、と思った。
マヌケ面の非常食がふわふわとついてくる。髭面の大男もあんまりだが、貧相な痩せ男の隣はそれはそれで非常食にしか見えないだろう。こいつもつくづく哀れなヤツである。
タマムシの空は面白みのない明るさをしているものだ。星もロクに見えないし、月は薄らボンヤリという明るさである。閉じた扉の向こうからは、飽きもせずに蠢くベトベターの、ぐちゃぐちゃなどという音が聞こえてきた。それはすぐに、近くを走るパトカーだか消防車だかのサイレンに掻き消されてしまったが気にはならない。湿ったジーンズはどうにも気持ちが悪く、浮かれポンチのオレンジ色は目に痛い。夏休みは、まだ、始まったばかりである。
町のベンチで横になる事一時間。
それだけの時間が、俺には必要だった。ウインディにゲロを吐かなかった事だけは、少し後悔している。
吐いちまえば良かった。ただ俺の隣で、今はのんびり欠伸をしているこいつを見ると、心底そう思う。
走っている時でさえ、俺がどれだけ止めようとも走り続けやがったし。
カイリューも、それを追って更に速度を上げるし。今は人の方を興味津々で眺めているだけで、こいつも俺の事を心配しねぇ。
畜生。俺の休日が。
はぁ。吐き気は収まったものの、気分が悪いのには変わらない。車で来れば良かったか?
いや、ボンネットが更に凹まされるのもな。面倒だな。
困った。
立ち上がって「行くぞ」と二匹に声を掛ける。
ウインディはやはり、何も罪悪感が無い顔で、俺を眺めた。何も出ねぇぞ。
隣にウインディ、後ろにカイリュー。
そんな大型二匹を連れて町を歩く俺は、流石に少し浮いている。帽子型にカットされたトリミアン。ピチュー、ピカチュー、ライチュウを連れたトレーナーはわざとそうしているのではないかと不安に思う。ぼげーっとしたコダックを抱きかかえて歩いているトレーナーは、重たそうなビニール袋を両腕に更に引っ提げて、けれど満足した顔で歩いている。
俺も、浮いているとは言えその程度に見られていると良いのだが。ただ、カイリューが野生だとまでは、誰も分からないだろう。
今日は何をするの? と言うような目つきでウインディが俺の方を見て来る。
「さぁな」
と俺ははぐらかした。俺も、どこに行けば良いのか、良く分かってない。警察? 市役所? それとも?
お堅い場所じゃ、返って面倒な事になりそうだし。
「保険、かぁ」
呟いて、頭に浮かぶものは、強力なボール。勿論手には入らないが、マスターボールを投げれば……、掴んで返されそうだな。
次に浮かんだのは、荒っぽい手口。麻酔銃……、んなもん同じく手に入らないわ。
それに刺さっても、効くかぁ?
効くとしても、あの巨体じゃあかなり時間掛かりそうだし。
はぁ。
そもそも、万が一、何て事考える必要があるかと思う。その万が一が起こった時、被害が悲惨を越える程になるが。
ボールに入ってくれない。入らせる事も出来ない。
参った、なぁ。
道中、コイキング焼きが売られていたので、二匹にも買って、俺も食う。
ウインディの上に座って、ぼうっと考える。どうすれば、良いかな。目の前で、バクフーンが怒りの形相で走り去って行くのが見えた。
車より速かった。それでいて通行人の間を見事にすり抜けたりして、どこかへ向っていた。
「お前も怒ったら、あんな風になるのか?」
カイリューは口に付いたあんこを小さな指で拭って舐めとりながら、首を傾げるだけだった。
言葉さえも通じないし。放ってその万が一が起こらないようにするしかないのかもしれない。
ぶらぶらと歩き、どこにも寄る事も無く、気付いたら町の外れに出ていた。
でかいポケモン二匹を連れた俺を見て、小さな野生ポケモン達が逃げて行く。
そんな中、ばりぼり、と何かを食う音が聞こえた。
うん? 何が残っているんだろう。そう思って、その音の方へ近付いてみる。
ココドラだった。打ち捨てられた配管を夢中で食べていて、近付いても俺の方に気付いてなかった。
……頑丈、がむしゃら。
そしてウインディの神速。
これで良いか。ウインディ以外のポケモンを今まで持ってなかった俺だが、それは単に俺がポケモントレーナーではなかったからだ。集める趣味も無いし、そんなに愛情を沢山ばらまけるような人間でも無い。
「でもまあ、三匹位までなら、な」
大した事は無い。
ウインディは俺がココドラを捕まえるのに驚いたように見た。
「こいつがいりゃ、カイリューが万が一暴れた時、役に立つんだよ」
その為だけにこいつをゲットするのは、少し憚れるが、まあ、特別好きなポケモンではないが、嫌いじゃない。
今更、ん? と振り返ったココドラに、モンスターボールを投げると簡単に入った。
さて、がむしゃらの技マシン、この町で手に入るか。
それだけが問題だな。ボールから出して、持ち上げようとして、その小さな体の割りにとんでもなく重い事に気付く。
「んん、んぐぅ」
ぎりぎり、持ち上がる。普通の成人男性位の重さはありそうだ。暴れられて、すぐに落としてしまった。
ふん、と鼻息を鳴らしてまた配管を食べ始める。
カイリューが配管ごと持ち上げて、少し重そうにしながらも、抱き抱えた。
ココドラは抱き抱えられても全く恐れていなかった。
「お前とは大違いだな」
そう言うと、ウインディはちょっとふて腐れた。
「さて、昼飯でも食うか」
ポケモンも入れる場所。そう言う場所だとちょっと値段が高くなったりするが、その程度の金なら十二分にあった。
そして、それから技マシンを買おう。
安くて一万円、高くても二万円で、大体終わるだろう。
町中へ戻る事にした。
ウインディは、飯と聞いて、すぐに態度を変えて俺を急かしてきた。
本当に、現金というか何というか。
まあ、そこがこいつの良い所でもある。
体調もそこそこ治って来ていた。
眠れない夜というのはいつでも嫌なものだ。
普段は全く気にならないようなベッドバットの微妙な固さ、体の下のスプリングの微かなきしみ、空調機の低く唸る音、そういったもの全てがいたずらに体のどこかの神経を逆側に撫でていくような小さないらつきが始終襲ってくる。
ベッドライトの橙色の灯りだけが、太陽の一欠片を閉じ込めたようにこの無機質な部屋を細やかに照らしている。それも消してしまおうかと思ったが、視界が黒一色になると他の感覚が余計に研ぎ澄まされてしまうような思いに囚われて、腕をそちらへ動かすこともできなかった。布団とベッドの間にある右腕の感覚に気づけば、これもまた神経を無意味に逆立てていくので、いっそ宙に浮かんで全ての感覚、全ての余計な考えから解き放たれたまっさらな状態で眠りたい、という馬鹿げた希望が俺の頭に浮かんだ。強力なエスパーポケモンがいればそんな空想もあるいは現実になるのかもしれないが、あいにくと俺の手持ちに超能力が使えるポケモンはいない。
灯りを消すことができない理由はもうひとつあった。放たれた橙色がいくらも進まないうちにその色を失い、やがてベッドから落ちて闇に溶けてしまう、そのギリギリの距離から静かに耳に届く二匹分の寝息。彼らは灯りのない夜を嫌がった。タマゴを授かってからは特にそうだった。鳥は夜目のきかない夜を嫌うというが、飛べない翼しか持たない身の彼らにも、立派に鳥ポケモンとしての血が流れているのだ。壁に向き、寝返りをうつことすら億劫なこの身では確認できないが、きっとその二匹は今夜も、自分たちのー正確には、自分たちのものだと思っているタマゴに両側からぴたりとくっついて、ひとかたまりの小山のようになって眠っているのだろう。タマゴを貰い受けたあの日から彼らはずっとそうしているのだ。昼は俺が持ち歩くタマゴが何かの拍子に割れたりしないかどうか、ずっと足元から見張られている。休憩、食事、それからこうして寝るときなどの、俺の手からタマゴが離れる時は、タマゴがフリーになった瞬間、赤いのと青いのの両方がすっ飛んできて、ひしと抱きかかえて離れない。どちらかがボールに入ることすら頑なに拒否し続けて、ずっと一日中タマゴのことばかりを気にかけ続けているのだ。
「ほんとの親でもないのにー」
その言葉はただのため息となって俺の口から小さく漏れた。罪のない安らかな二匹分の寝息をこんな残酷な言葉で途切れさせたくはなかった。規則正しくすうすうと空気が揺らぐ音が俺の神経に触らないのは、無機質なスプリングや空調機なんかと違って、生きているものが立てる音だからかもしれない。ただ、その音は俺のもっと深い所―俺の心を静かに責めたてていた。もちろん無邪気に眠っているだけの二匹にはそんなつもりは毛頭ないだろう。ただ俺の心に後ろ暗いところがあるからこそ、こんな穏やかで優しいだけの寝息にすら怯えなければならないのだ。
俺のポケモン、アチャモとポッチャマ。俺は彼らにとんでもない嘘をついている。
彼らが自らの命を削り、心を砕くようにして慈しんでいるタマゴ。
あのタマゴは、彼らのものではない。別のトレーナーの育てていた、バシャーモとエンペルトのペアから見つかったタマゴを譲り受けたものだ。
***
現メンバーの中で一番新参であるアチャモが俺を育て屋まで引っ張ってきたのは、朝のトレーニングを終えて木陰で少し遅い朝食をとっていた時の事だった。彼はふと食器から顔を上げて、くるりと向きを変えたかと思うと、いきなり一目散に走りだしたのだ。慌てて後から駈け出した俺が追いかけっこの果てに見たものは、アチャモが見えない翼を得たように大きく跳躍し、育て屋の柵を飛び越えるところだった。一瞬たじろいだ俺はすぐに気を取り直し、早く戻れと怒鳴ろうとしたが、俺の声が喉から出るより先にもう一匹が足元から柵に飛びついたのには完全に面食らい、言葉も失ってしまった。
そいつは俺の最初のポケモンで、交換でやって来た新メンバーのアチャモを特別気にかけていたのは知っていた。アチャモがそいつに懐いていたのもよく知っていた。そいつは俺のピチューがタマゴから孵るところにも立ち会っていたはずだし、そのタマゴを見つけたライチュウとは何やら最近よく話し込んでいた。だから、何とかして柵の中に潜り込もうと、ぺたんこに伏せてもがいているそいつと、柵の内側から必死に声をかけて励ましている様子のアチャモが何を望んでいるのかなんてのは、誰に聞かなくても分かった。
自分のポケモン達がここまでしているのを見れば、大抵のトレーナーは喜んで、一も二もなく育て屋のドアを叩くだろう。だが、俺はそれを実行するまでにいくらかの時間と思考の逡巡を要した。
俺の最初のポケモンであるポッチャマも、新参のアチャモも、どちらもオス同士なのだから。
ポケモンのオス同士、メス同士を育て屋に預けてタマゴが見つかった事例はこれまで確認されていない。こんなのはポケモン研究者のみならず、その辺のポケモントレーナーでも鼻で笑うくらいの常識だ。シゼンのセツリがどうとか、セイブツガクテキにどうとか、そういう尤もらしい言葉で否定される「当たり前」のことだ。
「だって、オス同士でどうやって『ヤル』んだよ?」
そんな下品な言葉を吐きながら、腹を抱えて笑うようなトレーナーだっているだろう。厳密にはタマゴはそうやって生まれてくるものでは無いらしいのだが、俺も詳しくは知らないし、知識があったところでこういう種類のトレーナーに通じる話ではない。
騒ぎを聞きつけてやって来た育て屋の老夫婦に「いたずらでポケモンが入ってしまいました、すみません」と平謝りし、両脇に大暴れする赤と青の小鳥を抱えて逃げ出した俺は、彼らの入ったモンスターボールを両の手に握り、交互に見つめながらそういうことを考えていた。
彼らが俺の目の前で繰り広げた光景。セイブツガクテキにありえないこと。それならアチャモは柵に入ってこようとするポッチャマを蹴り飛ばすのが正しかったのだろうか?
ぐるぐると色々な考えが巡った挙句に、俺がたどり着いた答えは「とりあえず二匹を育て屋に預けて、タマゴが見つからないことを知って諦めてもらう」というものだった。
育て屋の庭に勇んで駆け出していく二匹の背を見送りながら、俺が育て屋の受付をしているおばあさんに言った最初の言葉は確か、オス同士ですけど良かったんでしょうか、みたいな台詞だったと思う。本当はこういう台詞を、育て屋の側から言われるものだと思っていた俺は、手続きの間そうしたことを全く一言も確認されなかったので、思わず自分のほうから切り出してしまったのだ。
ためらい気味の俺の言葉におばあさんは全く動じず、穏やかな笑みをたたえたままで
「ええ、全然問題ありゃしませんよ。時々おります、ああいう子たち」
と、その顔通りの柔和な口調で返してくれたのだった。その言葉に俺がどれだけ安心できたかなんて、とても言い尽くすことはできない。
おばあさんの言うには、同じ性別同士―というか、これまでタマゴが見つかったことのない組み合わせで育て屋に預けられるポケモンはたまにいて、いつも一緒でいないと不安になってしまうペアや、よく一緒に特訓をしているようなペアが来たりもするのだそうだ。それからやはり、単純に好き同士で一緒にいたいペアも。
そういうペアの話になるとどうしても俺は次の言葉を切りださざるを得なくなる。即ち、もしもそういうペアがタマゴを欲しがった場合はどうすればいいのかと。もしかしたら俺のポケモン達は、そうなのかもしれない、と。
それまでずっと陽だまりのような笑顔を浮かべていたおばあさんの顔が、俺の質問の後、不意に真顔になってしまったのを見て、俺は瞬時に酷い後悔に苛まれた。この優しいひとを困らせてしまったこと、おかしな質問をしてしまったこと。やっぱり俺のポケモン達は変だったんだ。俺はすぐにでも庭のポケモン達を引き取って逃げ出したくなった。自分が最初にそうしたように。
でも、すぐに先ほどまでの笑顔を取り戻したおばあさんが発した言葉は、立ち上がろうとする俺を椅子に押しとどめた。
「そういうポケモンにタマゴを授けることも、うちではしていますよ。でもまぁ…2,3日様子を見てからの、最後の手段のようなものだと思っといてください」
2,3日待つというのは、タマゴが見つからないはずのペアのポケモン達が本当にタマゴを欲しがっているか見定めるため。その間トレーナーに「最後の手段」について考えてもらって、改めて意思を確認するため。そして、万が一にもタマゴが見つかる可能性を考慮しての事だった。
俺は2日目の夜に育て屋へ向かった。夜ならば二匹は眠っているだろうと考えたからだ。あまり彼らに話を聞かれたくはなかったし、人間だけで話をしたかった。
育て屋の入り口で俺を待っていてくれた小柄なおじいさんは、やっぱり優しそうな顔で、お地蔵さんを思わせる雰囲気の人だった。
「二匹の様子はどうですか」
「そうだのう、ちょっと庭を見てくれりゃあわかるが…一日中走り回っとる。タマゴを探してな」
俺はちらと庭を見やった。庭の中までは暗くてよくわからないが、柵の外側に土が撒かれたように落ちている。それを一瞥しただけで大体のことは察することができた。
「初めはお互い全く一緒におらんもんだから、あまり仲が良くないのかと思っとったが、ありゃ手分けして探しとるんだな。夜になると疲れて二匹で並んでぼーっとしとるんじゃ」
「そうなんですか…」
視界の隅、柵の向こう側で、ちらと何かが動いた気がした。俺はそれを気にしないようにした。
「タマゴは…見つかってないですよね、やっぱり」
「そうじゃのう」
一言で俺の僅かな希望は打ち砕かれてしまった。もしもシゼンのセツリとやらを吹き飛ばすような奇跡の一つでも起きて「彼ら」のタマゴが見つかっていれば、平和に事が済んでいたのだ。だがそれは起こらなかった。即ち俺は決断しなければならない。最後の手段を使うか、使わないか。
最初から俺の答えは決まっていた、はずだった。元々「タマゴが見つからないことを彼らに分かってもらい、諦めてもらう」のが育て屋に二匹を預けた理由なのだから。
だが、そんな俺の耳を突然、二匹の叫びが貫いた。
「どうしたんだ、お前たち?」
慌てて柵に駆け寄って声をかけても、返ってくるのはメチャクチャに笛を吹き鳴らすような鳴き声ばかり。ポケモンの言葉が分かるわけでもないのだが、喉が裂けんばかりに声を上げ、千切れんばかりに羽をばたつかせて俺に訴えたいことが今こいつらに何かあるとすれば、それは一つだけだろう。俺は何も言えずにただ二匹の頭を軽く撫でると、おじいさんの元へ戻っていった。選択肢の一つは彼らの声の前に儚く消えてしまった。そうするとどうしても俺は、もう一つの選択肢を選ばざるを得なかった。
「―この育て屋では、トレーナーの方が育てられないと言われたタマゴを預かって保管しとります。そうしたタマゴを、タマゴが見つからないペアのポケモン達に授けて、そのペアのタマゴとして育ててもらうこともできます。ただ、人のタマゴを貰うということで少し考えたいトレーナーさんもおるでしょうから、最後の手段ということになっとります」
脳裏におばあさんの言葉が蘇る。この選択肢を使うということは、自分のポケモンに嘘をつくということだ。もちろん自分たちが自然のやり方で繁殖することができないことはポケモンたちにもわかっているだろう。だが、タマゴが「生まれる」のでなく「見つかる」ものである以上、この庭で自分たちが見つけたタマゴは紛れも無く「自分たち」のタマゴなのだ。
例えそれが、元は他のペアのタマゴだったとしても。例えそれが、他のトレーナーから「いらない」と言われたタマゴだったとしても。
「…おじいさん。あいつらに、あのタマゴを渡してやってください。置いてるところを見られないように」
「それで、ええんじゃな」
「はい。あいつら見てると、なんだか不憫で。本当はあいつらのじゃなくても、このまま見つからないままよりはずっといいかなって…」
「ええよ、ええよ、それでええ」
おじいさんは俺の背中を労るようにポンポンと優しく叩きながら、
「全部『運び手』さんの思し召しだからの」
と、不思議なことを言った。
「何ですか、その『運び手』さんって」
俺が聞くとおじいさんはにっこり笑って
「運び手さんは運び手さんじゃよ。タマゴを運んでくるから運び手さん。それだけじゃよ」
とだけ言い、それ以上は何も言わなかったのだった。
***
そんなわけで俺のアチャモとポッチャマがタマゴを貰い受けたのが4日ほど前になる。この一週間で俺は一生分の頭を使ったような気がして、もう何も考えたくなかった。だが俺の後ろにいる二匹と、そいつらに挟まれているタマゴがそれを許さない。
俺はあいつらにとんでもない嘘をついている。その罪の意識が俺を眠らせない。
だが、タマゴを受け取らずにあのまま連れ戻したとして、それが正解だったのか?
わからない。
わからないまま俺はすっかり考え疲れ、いつしか何も聞こえない眠りについていた。
朝の日差しが俺の目を突き刺し、それに呼応するように頭がズキンと痛んだ。俺は咄嗟に帽子を深めに被り、情けなさに小さくうなり声を漏らした。部屋を片付け、ポケモンセンターを出ても抜けない体の怠さ。頭痛薬を喉に流し込んでも全く引かない頭痛。結局眠りにつくこと自体はできたが、全く眠ったという気がしなかった。俺の足元をうろちょろする赤と青の小鳥も、時折ふらついては首をぶんぶん振って疲れを吹き飛ばそうとしている。出発の前にポケモンセンターで診てもらってはいるが、元々ボールにすらろくに入らず寝ている間も気を張り続けているものが、そうそうすぐに回復するものでもない。
俺の手の中のタマゴは今朝方から時折小さく左右に揺れ動くようになった。このタマゴというのはなんとも不思議な物体で、掌で撫でてみるとすべすべと硬いが、爪を突き立ててもコツリとも言わず、石やコンクリートにそうした時のような、反発する硬質な感覚もない。むしろ指が爪先からタマゴの中に、つぷりと入ってしまいそうだ。恐ろしいのでやろうとも思わないが。
ぴょこっとタマゴが動くのを見たポッチャマが目を真ん丸にしてアチャモに知らせる。アチャモはヘタっていたトサカをピンと立て、俺の周りをそわそわとうろつきだした。
「あんまり寄ると蹴飛ばしちまうぞ」
ぴょこん。俺の言葉に呼応するようにタマゴが揺れる。それを目の当たりにしたアチャモは甲高い歓喜の叫びをあげながら何度も何度も飛び跳ねた。こいつに普通の鳥ポケモンのような翼があったら喜びのあまり宇宙までぶっ飛んでいただろう。
喜びのだいばくはつが一段落して、ちゃもちゃも、ちゃまちゃまと引っ切り無しに何やら嬉しそうに話している二匹を見やりながら、俺は複雑な思いに囚われていた。
タマゴが揺れる、ということは、そろそろ孵化が近くなった、ということだ。生まれてくるポケモンは恐らくポッチャマだろう。育て屋で聞いた話だと、このタマゴはオスのバシャーモとメスのエンペルトのペアから見つかったタマゴであるからだ。ポケモンの顔なんて人間からはほとんど見分けがつかないが、それでも自分のポケモンの顔くらいなら見分けはつく。ポケモン同士なら尚更だろう。もし、俺のポッチャマと全然違った容姿、全く異なった雰囲気のポッチャマが生まれてきたら、あいつらはどう思うんだろう。俺は何と言えばいいだろう。
かと言って、今からあいつらに全てを説明するか?人間の言葉で、人間の事情を、ポケモンの彼らにどう分かってもらえばいいのだろう。喜びと期待にあふれている彼らの顔を、俺の言葉で悲しみの色に塗り替えてしまったら?
朝からの頭痛が俺の頭を余計に暗く押し付けて、視界が足元の方へ向かう。腕の中のタマゴは、石のように重かった。
***
「はあ…疲れた。ちょっと休憩な。昼飯にしよう」
そう言って木陰に座り込む俺を、待ってましたとばかりに二匹の小鳥が取り囲む。お目当てのものをそっと彼らの前に置いてやれば、彼らは歓声を上げてそれに飛びつき、撫でてやったり声をかけてやったりしていた。
今日ここまででしたことといえば、何てこともない、ズイタウンの近くの遺跡まで歩いて戻ってきただけだ。なにか見たかったものがあるわけでもないし、用事があったわけでもない。
元々俺は気ままなポケモントレーナーだ。ムクホークに乗って行きたい街に行き、バトルがしたければその辺の血の気の多いトレーナーとバトルをし、このポケモン育てたら楽しそうだな、と思えばぶらりと捕まえに行く。ピチューのタマゴを孵したのも、アンコールを覚えたライチュウをバトルで使うと面白い、とトレーナー仲間から聞いたからである。
そんな俺がズイタウンの周辺で何日も、バトルをすることもポケモンを育てることも、ほとんど何もせずただ留まっている。それは自分がこれからどうすべきか、道を見失っていることの証明でもあった。ただ残された時間はそう多くない。このタマゴが孵るまでには、俺は決めなければならない。俺のついた嘘にどう始末をつけるべきか。
残りのポケモン達もボールから出して、並べたステンレスの食器にポケモンフードをザラザラと開けていく。それからコンビニで適当に買ったカレーパンとミネラルウォーターをリュックから出した。もちろんこれは自分用だ。
いただきます。俺の言葉でみんな一斉にそれぞれのやり方で食事にとりかかる。ピチューはライチュウの手から食べさせてもらうのが好きだし、ムクホークは食べている間も何度も顔を上げて警戒を怠らない。アチャモとポッチャマはお互いのフードを交換しあっている。そしてもちろん二匹の間にはタマゴが鎮座している。
食事を終えて思い思いに安らぐ時間が来ると、ライチュウがアチャモとポッチャマのところへやって来て、そっとタマゴを抱き上げた。そしてピチューがタマゴだった時によくそうしていたように、両手でぎゅっと抱きしめて愛しげに頬をすり寄せた。二匹の小鳥たちが見守る中、彼女はしばらくじっとそうしていた。
やがてピチューが彼女の足元で小さく跳ねて何かを主張する。にわかに小鳥たちの警戒が強まった。心配そうにオロオロするポッチャマと、しきりに何かを訴えるアチャモ。ライチュウはタマゴを持ったまましばらく何か考えたようだが、やがてそっとタマゴをピチューの目の前に置いた。ピチューは弾かれたようにタマゴに飛びつく。自分と同じくらいの大きさのタマゴに、ピチューは体いっぱいに抱きついて、「ちゃあ」と幸せそうに一言鳴いた。
よく見ればその小さな体にはライチュウのミトンのような手がかかっていて、その尻尾の先の稲妻は地面にしっかりと張り付けられていた。恐らくポッチャマたちはピチューの不安定な電撃がタマゴに影響をあたえることを心配していたのだろう。そしてライチュウはそれを察したのだ。
ムクホークはどうしたのかと思えば、皆がタマゴの元に集っている、その側の木の上で、やっぱり何か恐ろしいことが起きないか、野生のポケモンが襲ってこないかと見張っているのだった。
皆、タマゴがやってきたことを喜んでいた。皆、タマゴからポケモンが無事に孵るのを待ち望んでいた。その光景を見ていると、俺は、俺の頭の中に立ち込めている重苦しい霧が、幾ばくか晴れていくような気がした。セイブツガクテキに云々、といった言葉がいつからか自分の頭からなくなっていたことにも気がついた。自分のポケモンに嘘をついている、という罪悪感に全ての考えが押しつぶされていたからかもしれないが、その重みが幾分取り払われて生まれた隙間に、もうそうした類の言葉が入る余地はなかったのだ。もちろん普通に生きていたら一生出会わなかったかもしれないし、お互い野生で生きていたらペアになんかならなかったかもしれない。だがそれが何だ。俺のポケモン達はアチャモとポッチャマのオス同士の間にやって来たタマゴを喜んでくれているぞ、このやろう!俺は誰にともなくそう叫んで走り出したいような気持ちになっていた。
だが、気持ちが軽くなったとはいえ、俺が俺のポケモンに嘘をついている、というのは、紛れも無い事実なのだ。だが俺は、もう弱音を吐いて逃げ出す気にはならなかった。
***
お腹いっぱいになって木陰で眠っているポケモン達を、俺はそっとモンスターボールに回収していく。タマゴを受け取ってから一度たりともボールに戻らなかったアチャモとポッチャマにも、心の中で謝りながらその体をボールに収めさせてもらった。ばさりと音を立てて俺の前に舞い降りてきたムクホークを最後に回収すると、俺はタマゴを拾って歩き出した。
後で聞くと、育て屋のおばあさんは、俺がタマゴを返しに来たのだと思ったらしい。
だからタマゴを抱えた俺が育て屋のドアから顔をのぞかせた時、戸惑ったような顔をさせてしまったのだろう。思えば、受け取らなければよかったかもしれないと迷いはしても、一度貰ったタマゴを手放す気など最初から俺にはなかったように思う。
俺が育て屋に戻ってきた理由はこうだった。
「すみません、このタマゴの本当の親…バシャーモとエンペルトのことが分かる、写真か何かがありませんか」
ほとんどダメ元で聞いた質問だった。タマゴは保管していても写真まで保管しているかわからないし、トレーナーがそんなもの提供しているかも不明だ。それにそういう写真がもしあったとしても、そんな個人情報に関わりそうなものをほぼ無関係の俺にホイホイと渡してくれるようなものでもないだろう。写真がなければ少しの情報でも良かった。二匹がどんなポケモンで、トレーナーはどんな人だったか、とか。
だが、おばあさんの答えは思いもよらないものだった。
「写真はありゃしませんけどね。タマゴを引き取った方が連絡を取りたいと言われた時にどうするか、はトレーナーさんの方で決めてもらっとります。このタマゴの元々のトレーナーさんは確か、連絡してええと言われたはずですよ。あぁ書類があった。うん、連絡してええと書いてある。連絡、取りましょうか」
俺は「ぜひ」とも「結構です」とも言いかねて、「あ、あぁ…」なんて返事にならない返事をしてしまった。頭の中はグルグルと回っていた。まさかこんな展開になろうとは。俺はただ写真の一枚でも貰えれば、生まれたポッチャマと、アチャモたちのペアが落ち着いた頃にその写真を見せてゆっくり本当の話をしよう、と思っていただけなのに。
「どうしましょうか」
おばあさんは畳み掛けるように質問をしてくる。ええい、乗りかかった船だ。
「お願い、します」
絞りだすように返事をした。心臓は跳ねるように鼓動をうち、タマゴはぴょこ、ぴょこと、それに合わせるように腕の中で揺れた。
***
ポケモンセンターの前で小さなベンチに座り、タマゴを抱いて、茜色の空を忙しく横切る雲を見上げている俺は、傍から見ればのんびり休んでいるようにでも見えるだろう。しかし本当はこうして動くものを見続けていないと緊張で気がおかしくなりそうなのだった。
この日まで、このタマゴの本当の、というか元々のトレーナーのことは、ほとんど無意識的に考えないようにしていた。せっかく見つかったタマゴを「いらない」と言うようなトレーナーなのだからきっと碌でもないやつなのだろう、と勝手に決めつけて、そのまま考えるのを放棄したのだ。だからその、意識の向こうに追いやった存在が実態を持って今から自分に会いに来る、というだけで、俺は叫びたくなった。さっき育て屋に行ったときの勇気はどこへやらだ。だって一体何を話せばいい?「あなたの捨てたタマゴを私が請け負って育てることにしました」に続く会話なんて、どう転んでも楽しい話にはなりそうもない。
空の色が濃く暗くなりだした頃、一際大きな影が雲の下を横切った。向きを変えたその影はどんどん大きくなっていく。こちらへ向かってくる。ああ、あれが、そうなのだ。
影は竜の形になり、やがて赤い色をまとい、最後にリザードンの姿になって俺の隣に舞い降りた。そしてその背からひょいと飛び降りたのは、小柄な女の子だった。
「カスガ、といいます。タマゴを引き取っていただき、本当にありがとうございます」
何も言えないでいる俺に、その子は丁寧に頭を下げた。リザードンも横で神妙に目を閉じている。声と背格好だけから判断すると多分俺よりも年下で、中学に通っていてもおかしくないくらいに見えるが、傍らにいるリザードンは、パッと見ただけでも感嘆するような堂々とした体躯をしていた。きっとトレーナーとしての腕が相当に高いのだろう。
「どうしても今、水ポケモンは育てることができなくて。だから育て屋さんにお返ししたんです」
「育てられない?」
「はい。今、私、炎タイプのポケモンを育てる修行をオーバさんのところでしていて」
「オーバ…さん!?」
俺は面食らった。オーバさんといえば四天王の一角じゃないか。じゃあこの子は本当に実力のあるトレーナーなのだ。そんなトレーナーが目の前にいることが信じられなかった。これまで俺がバトルしたりつるんだりしてきたトレーナーは、本当にただの趣味でトレーナーをやっていたり、遊ぶのや旅が好きだったりするだけの奴らだったからだ。
カスガさんは続ける。
「デンジさんと勝負して勝った後、私の育てたリザードンの力量を買われてオーバさんの元で修行させてもらえることになったんです。それで今、炎ポケモンを育ててるんですけど、私のバシャーモが、エンペルトとじゃないと修行にならないって…あ、エンペルトって私の最初のポケモンなんですけど、オーバさんのとこに連れて来られなくて、その」
「それで育て屋に預けたら、タマゴが見つかってしまったと」
わたわたしてしまうカスガさんに、俺は助け舟を出す
「そういうことです。あそこなら二匹だけで他の炎ポケモンに邪魔とかしないで修行できるなって思っちゃったんです。軽率でした。里親も探したんですけど結局ダメで…すみません」
カスガさんは再び頭を下げた。俺は慌てて両手を振って、君が謝ることじゃない、と返した。タマゴの元々の持ち主として名乗りでて出会ってくれたこと、そしてタマゴを預けるに至った経緯をきちんと話してくれたこと、それで充分だった。そもそも「あ、このタマゴいりません」とゴミでも捨てるように言えるようなトレーナーだったら、名乗り出ることすらしなかったろう。
「わかりました。君のタマゴは俺が責任を持って育てるから、安心してください」
「ありがとうございます!」
こう会話を締めくくることができて、俺は心からほっとした。
それからは、あれやこれやの雑談に話が弾んだ。
「デンジさんに勝つってことはバッジ今何個?」
「あ、7つです。8つ目行く前にオーバさんに取られちゃいました。あははっ」
「えー!マジで、すげぇな…見せて見せて」
と、ぴかぴかのバッジがずらりと並ぶバッジケースを見せてもらったり。
「私の…っていうかもう貴方のタマゴですね、今誰が面倒見てるんですか?」
「アチャモとポッチャマ。どっちもオス。今ちょっと寝てるから起こせないけど」
「えー!!マジで?凄い!超凄いです!」
と、何故か超ハイテンションで食いつかれたり。
そんなこんなで俺達は仲良くなり、最後には連絡先の交換をして、それからバシャーモとエンペルトの写真も撮らせてもらった。二匹ともやはり、惚れ惚れするような無駄のない体つきをしていて、俺は必要以上に熱心に写真を撮ってしまい、カスガさんに笑われてしまった。
そして俺達は、タマゴが孵ったらまた出会う約束をして、小さなプレゼントを貰って、別れた。
***
―夜。ポケモンセンターの一室にて。
ピチューはライチュウの腕に抱かれてその時を待っていた。ムクホークは油断なく目を光らせ、静かにその時を待っていた。
アチャモとポッチャマはその側に寄り、交互に声をかけ、時折外側から軽くその殻をつついてやる。ヒビの入ったタマゴの中からは少し高めのポッチャマらしき鳴き声が返ってきた。
俺は、時折鞄の内ポケットの奥底にしまったバシャーモとエンペルトの写真を見ながら、そしてスマホのアルバムに残されたカスガさんの笑顔を見ながら、育て屋のおじいさんと話したことを思い出していた。
「運び手」の話だ。俺は結局それが何なのか分からず、カスガさんと会った帰りにその話をおじいさんとして来たのだ。
「―わしらはな、わしらの知らんうちにタマゴを運んでくる「何か」がおると思っとる。それを『運び手』さんと呼んでおるんじゃ」
そこでおじいさんは俺の方を見て、目をキラっと光らせると、
「時として『運び手』は人がその役目をやることもある。だがの、結局は人がそのタマゴを運ぶ役目を仰せつかることも、タマゴを通して人と人が結びつくことも、『運び手』さんの思し召しなんだとわしは思うとるよ」
と言って、また俺の背中をポンポンと叩いたのだった。
タマゴは大きく傾いで、また反対に揺れ戻る。二匹の小鳥の歓声が響く。
俺はカスガさんがくれたプレゼントをそっと握りしめて、その時を待つ。
この世界のこの場所にこのタマゴを運んでくれたもう一人の人ともう二匹のポケモン。離れていても俺達が繋がっている証、空にかかる橋の色、虹の色のリボンを右手に。虹の向こう側にいる、素敵な友達の物語を胸に。
ライチュウが微笑み、ピチューがぱちぱちと小さな光を飛ばし、ムクホークも密かに目を細める。
アチャモは何度も跳ねながら、ポッチャマは小さく体を震わせながら、皆がその時を待っていた。
その一瞬、部屋は百万個のフラッシュを炊いたように眩しくなった。太陽が生まれたようだった。
そしてその次の瞬間には、誰もがこの言葉を胸に、その光の生まれた場所に小さく座る、青い小鳥の元へ駆け寄っていった。
「おめでとう、ようこそ!!」
そのポッチャマは、白いペンキが剥げかかった木の柵にもたれて、夕焼け空をじっと見上げていました。
昼間はあんまり眩しくて目を向けることもできないのに、こうして夕方になると太陽は少しだけ光をおさえて、その本当の姿を少しだけ地球の生き物たちに見せてくれます。白い雲が通りかかって溶けかけたアイスクリームのようになった、白くて真ん丸なその星を見ているポッチャマの目は、なんだか寂しそうでした。
ポッチャマは大きく伸びをすると、背中を柵につけたまま、ぺたりと座り込み、大きくため息をつきました。ポッチャマの見ている先には、彼の背丈ほどの花畑が植わっていましたが、その花畑はよく見れば、あちこち踏み倒されていたり、掘り返されていたりして、ずいぶんひどい有り様でした。さらにもっとよく見てみると、柵の内側の地面には足あとだらけ。綺麗な水がはってあったらしい小さな池の水は半分くらいになっています。緑の芝生がしきつめられていたらしい場所はほとんど茶色くなってしまって、足あとがついていない地面がほとんどないほどでした。
たくさんの足あとは、どうやら二匹のポケモンによってつけられたものでした。ひとつは小枝をあちこちに落としたような形で、もうひとつは大きな葉っぱを丁寧に押し付けたような形をしています。葉っぱのような足あとの主はもちろん、このポッチャマ。そして、小枝のような足あとの主のもう一匹は、ポッチャマのいる柵のちょうど斜め向かいの、小さな花をつけた木の影から黄色いトサカをのぞかせて、疲れた様子のポッチャマを見つけると嬉しそうに駆け寄っていきました。ポッチャマも座ったまま、そのポケモンに小さな羽を振って迎えます。ポッチャマの横にちょこんと座ったそのポケモンは、アチャモの男の子でした。
「ねえ、今日は見つかった?」
「ううん、今日もダメだった…」
「そっか…ボクもだよ…」
二匹はささやくような声で何かを確かめ合うと、お互いの答えを聞いて、同時にため息をつきました。アチャモのトサカが元気のなくなったナゾノクサのようにへたりと倒れ、それを見たポッチャマは悲しそうにうつむきました。
二匹は隣り合ってくっついて、柵にもたれて座っています。時々柵の外側にある真っ直ぐな道を通る人間やポケモンが、珍しそうに二匹をちらっと見たりしながら忙しげに通り過ぎていきます。
ポッチャマは外のことなんか気にならず、ただアチャモのしっかりした足をじっと見つめていました。この柵に囲まれた小さな庭でも、ポッチャマの足では端から端まで行くのによちよち歩きで500歩くらいかかります。アチャモの足ならその半分もいらないで、あっという間に一周回って戻ってこられるでしょう。四本の強い爪がついた足は、どこまでだって走っていけそうで、いつでもポッチャマの憧れでした。
「僕もそういう足が良かったな」
ポッチャマが悲しげに言います。するとアチャモはすぐさま
「ボクはね、キミの羽のがうらやましいよ」
と返事をしました。ポッチャマはそれを聞いてどこかホッとしたような顔をします。きっとこのやりとりは、二匹の間で何度もくり返されてきたのでしょう。
「でも僕の羽、飛べないじゃないか」
「キミのは飛ぶんじゃなくて泳ぐ時の羽でしょう?ボクちっとも泳げないから、泳ぐってどんな感じかなって思うし、キミは泳げてすごいなって思う」
アチャモは早口で、一生懸命ポッチャマを励まします。ポッチャマはその間にアチャモへの励ましの言葉を考えていたようで、アチャモの言葉が終わるのを待つように、こう返しました。
「…ありがとう。僕も君みたいに思いっきり走ってみたらどんなに楽しいだろうって、よく思うよ」
「走るの気持ちいいよ!ビュンビュンって!まわり全部見えなくなるの、すごいよ!」
アチャモはトサカをピンと立て、肩のまわりの可愛い小さな羽をふわあっと膨らませて一息に答えました。アチャモのその様子を見たポッチャマは本当に嬉しそうな顔で、ほうっと息を吐きました。
「…もしも…もしも、さ」
少しの沈黙の後、アチャモがためらいがちにポッチャマに話しかけます。
「ボクとキミのタマゴが見つかったとして、ボクの足とキミの羽がついてたら、最高だよね?」
少し震える声でそう言ったアチャモの瞳は、木々の間に落ちる夕陽の最後の光を受けて、湖のように輝いていました。
その輝きを受けたポッチャマは、かなしばりにかかったようにしばらくアチャモを見つめていましたが、やがてゆっくりまばたきをしながらうなずいて、
「うん、きっとどこにでも行けるポケモンになるね」
と、返事をしたのでした。
***
―「本当になんにもしないでも、タマゴがいきなり見つかるの?」
「ええ、なあんにもしないでいいの」
それは二匹がここにやって来る少し前のことでした。人間のご主人や他のポケモン達と一緒に夕食をとっていたポッチャマは、一緒に旅をしている仲間で一匹だけタマゴを見つけたことがあるポケモンであるライチュウに、何度も何度もこういう質問をしていました。
「あの柵に囲まれた小さい庭に、二匹でただ一緒にいればいいの。そうしたらいつのまにか、そばにあるのよ」
このライチュウはたいそう優しい性格で、例えそれが食事の時間でも、前に答えたことのある質問でも、自分が食べるのを止めていくらでもこの熱心なポッチャマに付き合ってくれたのでした。特にこの話―ライチュウがタマゴを見つけたまさにその瞬間の話は、ポッチャマだけでなくアチャモもお気に入りで、二匹とももうすっかり覚えてしまったのですが、この時もまた、ポッチャマはいつものようにその話をしてもらいました。
「そうねえ、あの日はお日様が気持ちよかったから、少しうたた寝してしまったの。まわりはみんなお花に囲まれてて、暑すぎも明るすぎもしない、気持ちいい場所だったわ。どのくらい眠ってたかは覚えていないけど、目を覚ましてもお日様はまだ空の高いところにいて、起き上がったらすぐ横に、この子のタマゴがあったの」
ライチュウはそこで決まって、そのコッペパンのようなふかふかの暖かい手で、見つかったタマゴからかえったピチューの頭を優しくなでるのでした。
「にいたん、おんぶ」
ピチューがあどけない声でポッチャマに両手を差し出します。ポッチャマはくるりと背を向けてかがむと、小さいけれどしなやかで強い羽でピチューをその背に持ち上げました。ピチューが歓声をあげ、テーブルで食事をとっていた人間のご主人が微笑みます。
「ねえライママ、一緒にいた相手のポケモンはー」
アチャモがそこまで言いかけて、はっとした顔で口をつぐみました。ポッチャマも不意をつかれたように真顔になりました。ピチューの笑い声がやみました。アチャモの頭をパシリと大きな灰色の翼が叩き、アチャモとポッチャマは同時に目をぎゅっとつむりました。
「やめておけ」
それだけ言ってアチャモをにらみつけているのは、この旅仲間のリーダーであるムクホークでした。とても無口で厳しい性格で、敵には全く容赦しないので、ポッチャマやアチャモにとっては、頼れるけれど近寄りがたくもありました。
そんなリーダーに叱られたことでアチャモはすっかりしおれてしまい、
「ごめんなさい」
と、ライチュウに頭を下げました。
「いいのよ、ムク」
ライチュウはやっぱり笑って、しみじみとした様子で首を振りました。
「確かにタマゴが見つかってからあのピクシーとは会っていないけれど、彼は別に私やこの子のー」
ライチュウはそこで言葉を切って、ポッチャマとピチューの方を見やりました。ピチューは不安そうな顔で小さくふるえ、ピリピリした痺れと痛みはポッチャマの体まで伝わっていました。
「ううん、やめましょう。とにかく、今はこの子が私にとって一番大事だから」
ライチュウは目を閉じ、誰にともなくそう言うと、
「さあ、おいで、かわいい坊や」
と、さっきまでの笑顔を取り戻して両手をポッチャマの方に広げました。ポッチャマがそっと腰を下ろすと、「坊や」はとん、と一瞬だけ地面を踏んで、ライチュウの腕の中に思い切り飛び込みました。
「おんぶしてもらってよかったねぇ。楽しかった?」
「うん!」
ピチューはモモンの実のようなほっぺをライチュウのふわふわの胸元にすり寄せてうなずき、全身でそのぬくもりを感じているようでした。
何にもしなくても、一緒な庭に二匹でいるだけで、タマゴが見つかるということ。
それは、ピチューにとっては、ピクシーもライチュウも本当の家族ではないかもしれない、ということです。このピチューが本当はどこからやって来たのか知っているポケモンは、だれもいません。けれど、もしもそれを誰かがピチューの前で言ってしまったら、ピチューの小さな心はきっとこわれてしまうでしょう。そして、そうしてピチューの心がこわれてしまわないよう思いはからっているライチュウがピチューの「ママ」ではないなんて、誰がどうして言えるでしょうか。
ライチュウがポッチャマたちに話してくれた、どこからかやってくるふしぎなタマゴの話。ライチュウがピチューを本当の子供として可愛がっている姿。それが、ポッチャマとアチャモがここへやって来た理由でした…
***
「―ねえ、起きて。起きてよ。アオ…」
柵にもたれて座ったまま、いつの間にか眠ってしまっていたポッチャマに、アチャモが小声で呼びかけています。
アオ、と呼びかけられたポッチャマは、よっぽど疲れていたのか、なかなか夢から覚めません。
「アオってば!」
左のほおをくちばしで軽く小突かれて、やっとアオは目を開けました。
「うーん、どうしたの、ヒバナ…」
どうやら旅仲間のライチュウが仲間たちから「ライママ」と呼ばれるように、ライチュウがムクホークのことを「ムク」と呼ぶように、この二匹には、人間のご主人には秘密の、お互いだけの呼び方があるようです。アオが両目をこすっていると、ヒバナがしきりにくちばしで、柵の向こうを見るよう示してきました。そしてアオがそちらに顔を向けるとーなんと人間のご主人がいるではありませんか!
二匹はあせりました。もしかしたら人間のご主人は、僕らを連れ戻すつもりでやってきたのじゃないだろうか。もうすっかり暗くてよくわかりませんが、庭の入り口に建っている小屋の明かりは、小屋の側にいる二人分の人間の姿をぼんやり照らしています。一人はアオとヒバナのご主人で、もう一人はこの庭の世話をしているおじいさんのようです。大きな影ぼうしのような姿の二人は何かを話しあっているのですが、二匹には何を言っているのかわかりません。人間の言葉は難しい言い回しが多くて、ご主人が話しかけてくれる言葉はなんとなくわかっても、人間同士で話していることはわからないのです。それに、二匹の背丈は、人間たちの会話をきちんと聞くには少し低すぎました。けれど、落ち込んだような真剣なような二人の声の調子を聞くと、どうやらそれが良い内容の話でないらしいことはわかりました。
「やっぱり僕ら、連れ戻されるんだ」
「ボクらがタマゴを見つけられなかったから…」
小さな二匹はお互いに、きっとそうだと言い合って、悲しみに肩を落としました。でも、いつまでも黙って下を向いていてはいられないことも、二匹には分かっていたようでした。元々人間のご主人にも相当なわがままを通して二匹でここへ来させてもらったのだから、ここであきらめてしまっては何もしなかったのと同じだと、二匹はうなずきあいました。
「ねえヒバナ、ご主人にもう一回お願いしよう。まだここへ来てから、お日様も2回しか登っていないよ。3回目の朝には何か見つけられるかもしれないもの」
「そうだね、ボクもう一度大きな声でお願いしてみるよ。アオの願いを叶えてあげたいから」
アオはそれを聞いて一瞬だけ困ったような悲しいような顔になり、すぐに何か言おうとしたようですが、それはきちんとした言葉にならず、ただ一言
「ありがとう、ヒバナ」
と言えただけでした。
二匹はすくっと立ち上がると、小屋の方へ走りました。アオは葉っぱのような足で精一杯走り、ヒバナは何度も立ち止まって振り返りながら、アオに合わせて走りました。
そして二匹は小屋のすぐ側まで来ると、話しこんでいる二人に向かって大声をあげました。人間のご主人がすぐに気づいて、柵の向かいに駆け寄ります。
「どうしたんだ、おまえたち?」
しゃがみこんで二匹と同じ目線でかけてくれた言葉は、アオにもヒバナにもはっきり分かりましたので、二匹も精一杯に声を張り上げて
「僕たち、まだ帰りたくないんです!」
「タマゴを見つけさせてください!」
と叫びました。それが人間のご主人に届いたのかどうか、よくは分かりませんでしたが、人間のご主人は、必死に小さな翼をばたつかせてお願いする二匹に少し辛そうな笑顔を見せて、その頭を軽くなでると、立ち上がっておじいさんの元へ戻って行きました。それからまた二人で何か話していたようですが、話の内容は、アオもヒバナも柵にぴったりくっついて聞き耳を立ててみても、やっぱり分かりませんでした。やがて人間のご主人の足音が闇夜に遠ざかっていくのが聞こえ、おじいさんも小屋に戻ったらしく外には誰もいなくなりました。そして庭にも静かな時が訪れました。
アオとヒバナは、庭の奥の花畑へ戻ってきました。どうやら今夜連れ戻されることはないようでした。安心と疲れと花の香りが、二匹を眠りの世界に誘おうとしていましたが、草花でそれぞれの寝床をこしらえて横になっても、アオはまだ眠ることができませんでした。
「ねえ、ヒバナ」
真っ暗な空に点々と光る星明かりを見上げたまま、アオはヒバナに声をかけました。少し離れたところから
「どうしたの、アオ」
と返事がかえってきました。それから少しアオは次の言葉にためらい、ヒバナはアオの言葉を待っていました。
「ごめんね」
そのアオの言葉はヒバナを驚かせたようで、ヒバナは弾かれたように寝床から半分体を起こして
「何が?どうして?アオが謝ることが何かあるの?」
と、アオに向かって質問の雨を降らせました。アオは困ったように答える言葉を探して黙りこみ、ヒバナは半分起きた格好のままアオの方をじっと見つめていました。
やがてアオは慎重に話しだしました。
「さっき、ね、ご主人が来た時に、ヒバナは僕の願いをかなえてあげたいと言ったでしょう。もしヒバナが本当はそんなにタマゴを欲しくないのに、無理やり僕のわがままに付き合ってくれてるんだったらー」
「違う!」
ヒバナは大声を上げました。アオはその声にびっくりして飛び起きましたが、ヒバナ自身も自分の出した声があんまり大きいのに驚いて目を丸くしていました。でもすぐにヒバナはぶんぶんと首を横に振って、アオの目をしっかりと見て言いました。
「確かにタマゴが欲しいって最初に言ったのはアオだよ。アオの願いを叶えてあげたいのも本当だよ。でも、ボクが本当はタマゴが欲しくない、なんて思ってたら、ここに一緒にいさせてくださいってご主人に頼んだり、この庭までご主人を連れてきたりなんかしなかったよ!そうでしょ?」
「…ヒバナ」
アオの声は少し涙ぐんでいました。ヒバナはにっこり笑って
「ボクとアオのタマゴからかえるのは、どこにでも走っていけて、どこまでも泳いでいける、最高のポケモンなんだよ。ね?」
と、アオに言いました。アオはもう何にも言えなくなって、涙をこぼしながら何度も何度もうなずきました。
それから二匹はまたそれぞれの寝床に寝転んで、眠りの時が訪れるまで星を眺めながらぽつりぽつりと色んな事を話しました。
「ご主人、ここに連れて来られた時は目を丸くしてたよね」
「みんなでご飯食べてる時に、突然自分のポケモンが逃げ出したら、そりゃご主人はびっくりするよ」
「確かにそれもだけど、ボクが柵を飛びこえてこの庭に入っちゃった時のご主人の顔ったら、もうおかしくってさ!」
「その顔、僕も見てみたかったなあ。ご主人もヒバナも足があんまり速くて、僕、追いかけるのが大変だったよ」
「あはは、ごめんごめん。絶対に作戦を成功させなきゃって思って、他のことは考えられなかったんだ」
ヒバナの声が弾んでいます。アオは自分の足の遅いことを考えてまた少し切ないような気持ちになりました。でもこれはヒバナが悪いのではないのです。元々アチャモはあかあかと燃える炎のような明るさと情熱を、ポッチャマは吹雪の中で耐え忍ぶための辛抱強さと思慮深さを持って生まれたポケモンなのですから。そしてそのお互いにない部分をこそ、二匹はお互いに素晴らしいと思っているのです。
「やっぱりヒバナの足が羨ましいよ。柵だって簡単にこえられてさ。僕も頑張ったけど無理だったもん。下からくぐるのも失敗したし、かっこ悪かったなあ」
「でも、ご主人が分かってくれてよかったよね。僕らがここにいたいってこと」
「そうだね。ありがとうヒバナ、作戦に協力してくれて」
「ボクの方こそ、いい作戦を考えてくれてありがとう、アオ」
「明日はきっとタマゴを見つけようね」
「うん、きっと見つけようね」
二匹はしっかりとした声でそう言い合って、それから交互におやすみを言いました。
***
次の日の朝は、空に雲ひとつない、まことに良いお天気でした。お日様の光にさそわれて、アオはうっすらと目を開けましたが、ポカポカとした陽気とひんやりとした草の感触に包まれて、すぐにまた眠りの世界に戻りたくなるような心地になりました。
そんなアオの眠気を一気に吹き飛ばしたのはヒバナの声でした。
「アオ!!こっちに来て!早く!!早く!!」
明らかにいつもと違う、興奮で爆発しそうな大声に、アオは何かとても凄い、素晴らしい出来事が起きたことを感じました。そしてそれはきっと、
「タマゴがあったんだよー!ボクたち、とうとう見つけたんだよ!!」
やっぱり思った通りの言葉が聞こえてきましたが、アオはもうその声も半分聞こえず、自分の遅い足のことも忘れて、小屋の影のあたりで本物の火花のように飛び跳ねるヒバナの元へ向かって全力で駆け出していました。
二匹の胸くらいまである大きさの、ころんとしたタマゴは、触るとなんだかしっとりとしていて、アオは、なんだかそれ自体が生きているポケモンであるような、ふしぎな気持ちがしました。
「あのね、アオ、ボク今朝起きてね、あくびして背伸びしてね、そしたらね、小屋の近くのここの地面の上に、何か石みたいなのがあるのが見えてね、近づいてみたらね!タマゴがあって!うれしくってもう、本当に、本当に!」
ぴょこぴょこと跳ねてトサカをゆらしながら、ひっきりなしにしゃべり続けるヒバナの横で、アオは上の空でうん、うんとうなずきながら、タマゴのあちこちを両方の羽で触ったり、なでたり、耳を当ててみたりしています。まるで、そこにあるそれが本当にタマゴであることを確かめるように。
「ねえってば、アオ!」
ヒバナが怒ったようにアオのほおをくちばしで小突いたので、アオはびっくりして固まり、目を白黒させてヒバナの顔を見ました。
「アオは嬉しくないの?せっかくタマゴが見つかったのに、いつまでもむっとした顔で、ボクの話も聞かないで…嬉しくないの?」
ヒバナは最初は怒った声でしゃべり始めたのですが、アオに怒りをぶつけているうちにだんだんと炎が小さくなるようにしゅんとした顔になっていったので、アオは慌てて
「違う、違うんだよ、ヒバナ。嬉しいよ。本当に、凄く嬉しい。でも…まだ信じられないんだ。本当に僕たちのタマゴが見つかったって、まだ頭がぼうっとしてて、分からないんだ」
と、一生懸命に、そして正直に自分の気持ちを話しました。ヒバナは最後までじいっと真面目に聞いていましたが、悲しい顔をしていたのが突然ニッと笑ったかと思うと、アオのほおに思いっきり「みだれづき」を食らわせました。
「いたっ、いたたたっ、いたい!!」
何度も何度もつつかれて、アオは必死に羽で顔をかばいます。ヒバナはそれを見てつつくのをやめ、おかしそうに笑いながら、
「ね、痛いならこれは夢じゃないんだよ!もうわかったでしょう?本当の本当にボクたちのタマゴが見つかったんだよ!!」
と、高らかに歌うように喜びの声をあげて、何度もその場で飛び跳ねました。アオはほおをさすりながらそんなヒバナを見て、困ったような、その日初めての笑顔を浮かべました。
それからアオはタマゴを両方の羽で大事に包み込むように触れて、ヒバナは反対側から自分の体でタマゴを温めるようにそっと寄り添い、
「生まれてきたら、呼び方を考えようね」
「色んな所に一緒に行きたいね」
「速く走るやり方、教えてあげてね」
「じゃあキミは泳ぎ方を教えてあげてね」
「楽しみだね」
「本当に全部、楽しみだね」
と、そんな話を、いつまでも続けていました。
やがて小屋から出てきたおじいさんがタマゴを挟んで寄り添う2匹を見つけ、人間のご主人が鳴らす自転車のベルが聴こえるまで、いつまでも。
二匹のポケモンが一緒にいると、いつの間にかタマゴが現れるという、ふしぎな庭。
そこへやって来たのは、アチャモの男の子と、ポッチャマの男の子でした。
二匹は朝から晩まで一生懸命にタマゴを探すのですが、全くタマゴは見つかりません。
さあ、二匹はタマゴを見つけることができるでしょうか?
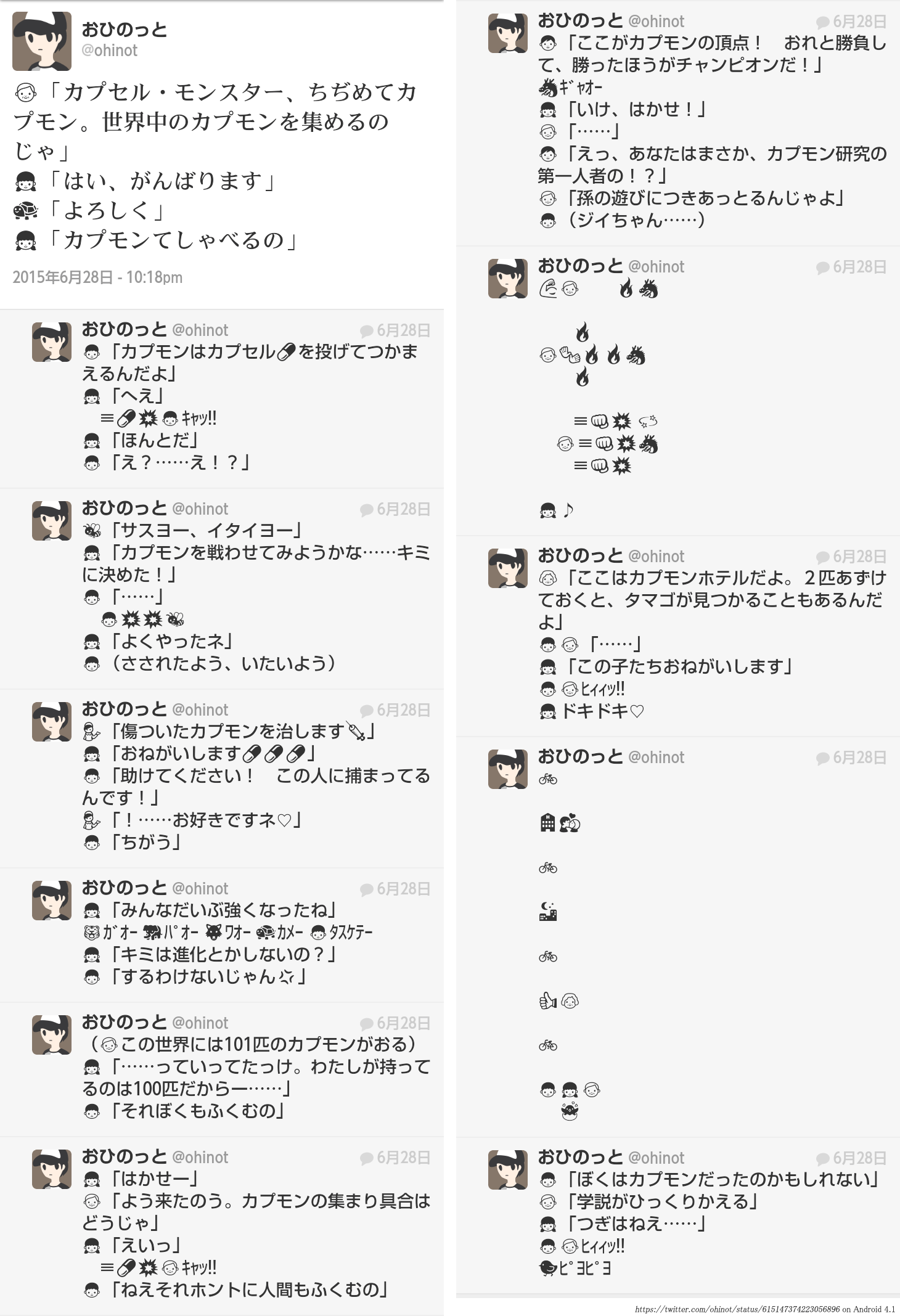
初出は2015年6月28日 https://twitter.com/ohinot/status/615147374223056896 以下です。 |
カイリューは何をする事も無かった。
あれから、休日を除く日は仕事に行こうが付いて来る事も無ければ、俺とウインディ、それとムシャーナにちょっかいを掛ける事も無かった。
俺から貰うポケモンフーズをぽりぽりと食べ、俺が居ない時は外をぶらぶらと回って近所を騒がせ、俺が居る時は俺とウインディと一緒にテレビを見たり。
正に居候そのものだった。
ここに来てからは俺にとって害になる事もしなかったし(食費やら近所への説明やらはあったが)、かと言ってこれと言って益になる事もしなかった。
ドラゴンタイプの生命力、それは近付けば慣れた今でも少し畏怖を感じる程にあるのだが、このカイリューには活気が無かった。
生命力を持て余しているような、そんな気もした。
そんなカイリューは、くぁ、と俺の近くで欠伸をする。長く、大きく口を開けて。口の割りには小さな歯が並んでいるのが見える。
そしてむずむずと鼻を動かして、体を丸めて大きくくしゃみをした。
居眠りをしていたウインディが跳ね上がる。慣れた今でも、俺も少しびびる程の反応をしてしまう。
そのままガラスに向けてやられたら、ガラスがはじけ飛ぶ気がした。
そんな事がありながらも、俺の日常はそこまで変わっていなかった。
朝起きて、ウインディを連れて仕事に行く。カイリューがぶらぶらと外を散歩する。
仕事を終えて、ウインディと一緒に帰って来る。カイリューが庭で待っている。
テレビを見ながら二匹と一緒に夜飯を食べる。シャワーを浴びて寝る。
大して変わらない日常だった。
同僚に話すと、とても珍しがられた。
俺もそう思う。
その一番の理由は、カイリューも俺も、互いに大して何も要求していないからだと思えた。
……と言うよりかは、俺はカイリューに対して大それた事を要求出来なく、そしてカイリューは俺に対して、ここで暮らす事以外を要求していない、と言った方が正しいか。
カイリューが暴れたら、俺とウインディには為す術も無い。ただ居るムシャーナも、戦う姿を見た事は無いが一緒だろう。
それを恐れずには居られなかった。ここに居るなら俺のものになれとボールに入れる事すら出来ない。そんなでもお人よしにカイリューに飯を与えているのだが。
けれども、それでも別に良かった。
ただ隣に居るだけ。それだけで俺はカイリューが居ない時より満たされていた。きっと、カイリューも同じだった。
それ以上、カイリューも俺も、今は望んでいなかった。
休日、起きるとムシャーナが居なくなっていた。
妻は、どう思うのだろうか。きっと、カイリューが居る事も伝わる筈だ。
とは言え、どうなる事でも無いだろう。俺が曲がらない限り、きっと帰って来ない。そして、曲がるつもりは無い。
それだけの事がきっとずっと続くのだろう。
互いに曲がらずに、子も為さずに、離婚も再婚もせずに、そのまま終わるのも有り得ると思う。
目覚ましを掛けなかった今日の朝、いつもより遅めに起きる。ウインディは器用に自分でドアを開けて外にもう既に出ている。カイリューも居なかった。
欠伸をして、目を擦って、起き上がった。でも、二度寝する事にした。少し疲れている。
暫くして、ウインディが俺を起こしに来る足音が聞こえた。圧し掛かってべろべろ舐められる前に起き上がる。
頭を掻きながら、ドアを開けられるならポケモンフーズも自分で取って食えよと言いたくなる。それはそれで困るが。
寝室にウインディが入って来て、跳び掛かられる前にベッドから降り、そして跳び掛かって来たので横に避けた。
まともに跳び掛かられて、蝉ドンされ、そのままウインディが壁に爪を立てながらずるずる床に落ちた日何て、本当に何とも言えない気持ちが一日中続く羽目になった。
躱すとカイリューが入って来て、壁からずり落ちるウインディを不思議そうに眺めた。
「……飯にするか」
とは言え、休日だろうと食う物は大して変わらないのだが。
飯を食い終え今日はどうするか少し悩む。
ただぼうっとしているのも、ここにずっといるのも余りしたくはなかった。
また魚釣りにでも行くか、と思うが、カイリューを連れて行く事になると、傍にいるだけで釣れなくなりそうな気がした。
「……町にでも、行くか」
ただ居候しているだけ。きっと俺やウインディを害する事は無いだろう。そうは思えても、保険は欲しかった。
外へ出る。カイリューも今日が俺にとっての休日だと分かっているらしく、ラフな格好の俺に付いて来た。
ウインディの背に乗って、「町に行くぞ」と言うと、意気揚々と走り出す。
後ろを振り返ると、カイリューも空を飛んで追って来ていた。小さな翼なのに、余裕のある飛び方だった。
ウインディもそれを見て、負けじと足を速める。カイリューが付いて来る。
足を速める。カイリューがそれを追う。
やめてくれ、と言おうとした時にはもう遅かった。俺は下手に走る車何かよりとても速く走るウインディの背中にしがみつくのが精いっぱいだった。
吐くかもしれないと思った。
タブンネを倒すと、経験値が多く得られる。だから一部のトレーナーは、飽くことなくタブンネを倒す。延々と流血を強いる。
勿論、僕も頻繁に倒された。夥しい程の攻撃を受けた。意識が途切れる際の、朦朧とした感覚には慣れた。だから僕は、人間を憎んだ。それは至極、当たり前のことだ。
六番道路には、他にも沢山のポケモンが住む。だが人間がなぎ倒すのは、タブンネのみ。その他は眼中に全くない。
この、こっちが不幸になる情報が広まったのは、割とつい最近のことだった。何故か人間はやたらと、知識の伝達が早い。一人知れば、数時間後には千人が知る。コラッタが増えるより早いペースで、彼らはデータを拡散させていく。
僕は、他のタブンネから、良くこう称される。自己中心的だ、と。けれども、僕はこう思う。僕以外が、他人を思いやり過ぎなのだ、と。
あるタブンネは、人間に襲われたとき、ボールから出てきたポケモンが既に傷だらけで、だから可哀想に感じて、癒しの波動を使ってしまった。彼はその後、彼が癒やした獣に突進された。
またあるタブンネは、人間が傷薬を岩の上に忘れたから、それを教えてあげたくなって、忘れ物を掴んで正面に立った。彼もその後、悲劇に見舞われた。
どう考えても、その行動は異常だ。彼らの思考回路が、さっぱり理解できない。何故憎むべき相手に、優しくするのか。攻撃する者を助けるのか。
僕は仲間から、利己的という欠点を責められた。一部からは、完全に避けられた。タブンネは、基本的に優しい。誰かを批難するなんてしない。けれども、他人に優しくしない者には、頗る彼らは厳しくなる。
確かに僕は、人間から食べ物を盗む。だが、それぐらいだ。何度も、瀕死状態にしてくる奴らだ。その程度の被害なら、賜ってやってもいいだろう。
それは、突然のことだった。
タブンネ達に大きな、とても大きな転機が訪れた。
条例か、法律か、はたまた憲法だったか、良く分からない。とにかく、タブンネを倒してはいけない、という決まりごとができた。タブンネを見かけたら、無視して逃げろ。危害を加えては駄目だ。ほぼ全ての人間は、その命令にしぶしぶ従った。
何故このような、決まりごとが作られたか。理由は、だいたい想像がつく。一部の人間が、幾度となく攻撃され続けるタブンネを憂いだ。そして、抗議をしたのだろう。
こうして僕らは、地獄の日々から逃れられた。実にあっさりだった。こちらからは、何もしなくても済んだ。
僕も仲間も、当然の如く喜んだ。喜ばないタブンネなどいなかった。木の実を集めて宴をした。しかも、その宴は三日も続いた。
ただ僕は、人間を恨むことを止めなかった。これまで、酷い仕打ちを受けた。だから、一生恨んでも許される。自分は人間から、食べ物を盗み続けた。何の罪悪感も抱かずに、悪事ではない悪事を働いた。
六番道路にはもう、人間は来ない。誰もがそう、考えていた。僕は、もう食べ物は盗めなくなるけど、まあ別にいいかと思っていた。
ところが、その予想は見事に覆された。
人間は、今もなおやってきた。そして彼らは、タブンネ以外のポケモンを倒していった。多種多様な悲鳴が、六番道路に響き渡った。人間が去った後には、多種多様なポケモンが、傷だらけで横たわっている光景が広がった。
習慣。人間は、この場所で手持ちを育成するということが、日常の一部となっていた。習慣とは、急に変えることのできないもの。だから彼らは、未だに訪れる。そして、タブンネ以外のポケモンを傷つけていく。
誰かが幸せになれば、その分誰かが不幸になる。タブンネが人間から狙われなくなれば、他のポケモンが狙われるようになる。
こうなったことに、罪悪感を抱いている者が、タブンネの中にはいた。自分らさえいじめられていれば、みんな幸せだったのに、等とぶつぶつ呟いていた。いや、それで己を責めるのは筋違いだろう。こうなったのは、タブンネのせいではなく、紛れもなく人間のせいなのだから。
多くのタブンネは、地面に横たわるポケモンを見かけては、癒しの波動で立ち上がらせた。自分は、やらなかった。他のタブンネがやっているなら、自分はやらなくて良いと思っていた。
そうして、三日が経過した。
この日僕は、目撃した。草むらに、堂々と放置されたリュックがあった。そして、そのリュックのチャックを、必死になって開けようとしている、一匹のシキジカがいた。
自分はそのシキジカに、とても親近感が沸いた。憎むべき相手から、盗もうとしている。僕と同じように。
けれどもそのシキジカは、非常に不慣れであった。歯でチャックを開けるのに、かなりもたついていた。
そして、予想通り悲劇に見舞われた。やっとのことでチャックを開け、中を漁っていたちょうどそのとき、持ち主であるトレーナーがやってきたのだ。
人間の顔は、怒りに満ちていた。ボールからポケモンを出した。経験値を貰う。盗みを働いた罰を与える。この二つを、同時に行おうとしているのだ。
シキジカは、咥えていた木の実を即放り投げる。まだ三日目。やられ慣れていないシキジカの足は震えていた。
数分後、酷い傷を負ったシキジカが、眼前に横たわっていた。怒りを買った分、余計に痛めつけられた。
ボロボロの体でシキジカは、必死に立とうとしていた。さすがに僕は、胸がちくちくと痛んだ。周囲に、仲間がいないか確認した。けれども、こんなときに限ってどこにもいない。
僕は自然と、体が動いていた。
「ありがとうございます。おかげで助かりました」
癒しの波動を二回使ったことにより、シキジカは全回復した。
投げ飛ばしたモモンの実を見つけ、シキジカはそれを運んでいった。僕は後ろからこっそりついていった。運んでいった先には、息も絶え絶えのシキジカがいた。毒状態であった。このシキジカは、仲間のために、危険な行為を遂げようとしていたことが、発覚した。
シキジカはモモンの実を仲間に喰わせた。しかし、それだけでは体力は回復しない。ここは僕の出番か。と、思ったら。
シキジカはなんと、宿り木の種を使い始めた。仲間に向かって、幾多の種を飛ばした。それは、体力を余計に減らす愚行だ。
しかし、倒れているシキジカは、少しずつながらも元気になっていった。そしていつの間にやら、立てるくらいに元気になった。一方で、宿り木の種を使った者は、少々足がふらついていた。
宿り木の種の使い方は、本来逆である。どういう原理か知らないが、こんなこともできるポケモンが存在した。思いやりの心があるシキジカだからできるのか、と想像した。
シキジカは、自分の体力を犠牲にしてまで仲間を回復させた。本当に絶対に、自己中心的なんかではない。
それに引き換え、自分は。
自分と同極だと思っていた存在は、むしろ対極に位置していた。自分はだんだんと、今までの自分が、自己中心的であったことを自覚してきた。
ああ、なんて自分は、愚かだったのだろう。
僕は、自分か利己的であったことを認めた。タブンネ達がおかしいんじゃない。僕がおかしかったのだ。
シキジカの行動に浄化され、考えを改めた僕はそれ以降、倒れているポケモンを見かけたら、すかさず助けるようにした。助けると必ず、お礼を言われた。お礼を言われるのは気持ちが良かった。
そうなってから、周りのタブンネの視線も変わった。僕を避けていたヒト達も、寄ってくるようになった。
誰かを助ける行為は、嬉しいという感情以外を生み出さなかった。
そうして、またときが経過した。
やってくる人間は、半分に減った。それに伴い、被害も減ってきた。
しかし、この日は違った。
一人の人間が、やってきた。その人間は、酷かった。醜かった。人間は、ただ只管にポケモンを倒しまくった。本当に、これはいつまで続けるつもりだろうというくらい倒し続けた。人間は六匹のポケモンを持っていた。その全てを、大きく成長させようとしていた。
ようやく、人間は作業を終えた。被害は膨大だ。草むらの至る所に、ポケモンが倒れている。僕はすぐに体が動いた。彼らを回復させてやらねば。
いつもの通り一匹ずつ、癒しの波動で回復させていく。ボケモンの数が膨大で、PPが切れないか心配だった。
一匹に、癒しの波動を二回使ってやることはできなかった。PPは後二つ余ってはいるが、二匹だけ特別扱いするわけにもいかない。だからこれでいい。後は全員自然回復する。
さあ、これで安心。僕はここから去ろうとした。
けれども、そのときだった。僕の正面に、先程倒れていたポケモン達が表れた。
「なんで全回復してくれないんだ」
彼らの中のハトーボーが、このように言ってきた。
「PPが足りなかったんだ。済まない」
「それは君の問題だろう。俺達が悪いんじゃない」
タマゲタケが、強い口調で言ってくる。彼らの怒りの形相の意味が、僕には分からなかった。僕は、彼らを回復させた。良いことをしたのだ。だから本来は、お礼を言われるべき立場だ。
「仕方がないじゃないか。半回復でもさせて貰えるだけ、ありがたいと思えよ」
「ふざけるな。誰のせいでこうなったと思っているんだ」
誰のせい? 勿論人間だろう。
いつの間にか、囲まれていた。
「お前意外のタブンネに同じことを言ったら、申し訳ない顔をして謝ってきたぞ。謝るってことは、タブンネ達が悪いって認めるってことじゃないか。だから回復して貰うのは、当然のことなんだよ」
ふざけるな。そんなの、利己的すぎる。
あまりに理不尽な言い分。僕はあっけにとらわれて、反論ができなくなった。黙っている僕を見たポケモンたちは次の瞬間、とんでもない行動を取った。僕に襲い掛かってきたのだ。
逃げ場はなかった。完全に袋叩きにされた。怒りのこもった攻撃が、僕の体を何度も抉った。
倒れてもなお、攻撃を止めなかった。助けを呼ぼうと、辺りを見回す。どこにも仲間はいない。なんでいつも、肝心なときに。
ようやく、彼らは満足していなくなった。
辛うじて、意識はあった。しかし、このままではいずれ終わってしまうことが、感覚で分かった。
僕は、自分で自分を回復できないか試みた。奇跡に賭けた。常識を覆せと自分を念じた。けれども、傷はいつまでも癒えない。やはり無理なのだ。癒しの波動は、他人のみを回復させる、思いやりに溢れた技だから。
死にたくなかった。ようやく地獄の日々から逃れて、これからってときだ。もう一度仲間がいないか探す。激しく痛む首を無理やり回す。木の後ろにいた一匹の、シキジカを発見した。
そのシキジカは、僕がこの間助けたシキジカだった。これは、明らかなチャンス。
「おい聞こえるか! 死にそうなんだ助けてくれ! 仲間を呼んできてくれ!」
できる限りの大声を発した。絶対に聞こえている筈だった。それなのに、シキジカは動かない。
「早くしてくれ! 一刻を争う!」
ようやく、シキジカは走った。自分はほっと安堵する。仲間の到着をじっと待った。
けれども、待てど待てども、仲間はやってこなかった。
シキジカは、恐らく仲間を呼んでいない。僕は、裏切られたのだ。同種族はすごく思いやるが、関係のない者は助けない。そういう奴なのだろう。僕の視点から見れば、シキジカは自己中心的だった。
シキジカに対して、怒りは感じなかった。不思議と、シキジカを許せた。良く考えれば、仕方がないことだ。僕を助けたら、僕を痛めつけた連中に何をされるか。仲間になんて思われるか。ハイリスクな上に、見返りがない。だから、仕方がないのだ。自己中心的だけど、仕方がないのだ。
シキジカを許すと同時に僕は、全てを許した。恩を仇で返してきた、あの連中も許した。そして、長らく僕を苦しめてきた、人間達も許した。
薄れていく意識の中、一人僕は考える。
僕は、間違っていた。自己中心的でいることを、むしろ肯定すべきだったのだ。ぶれてはいけなかった。自己中心的でいるのなら、徹底的にそうであるべきだった。誰も助けてはいけなかった。誰も回復させてはいけなかった。経験値を得るためにポケモンを倒す人間も自己中心的で、そのストレスを発散しようとした野生のポケモン達も自己中心的で、僕を助けなかったシキジカもそうで。みんな自己中心的で、正しかったのだ。なのに僕だけが、タブンネだけが優しくて、他人のことばかり考えてても、バランスを崩すだけなのだ。
このまま死ぬのか。諦めるしかないのか。
僕はとうとう、来世のことを考え始めた、何に生まれ変わるのだろう。何になろうとも僕は、自己中心的でありたい。そう、思った。
「今度は絶対に、自分のことだけを考えて生きてやる!」
最後の力を振り絞り、空に向かってそう叫ぶ。
そして、最後の足掻き。もう一度、癒しの波動を使ってみる。
何も、起こらない。
そう、思っていた。
ところが、数秒経ってから。右手の傷跡が、だんだんと薄くなっていくのが確認できた。そして、体が楽になってきた。
成功したのだ。自身を回復させることに。
僕は、シキジカが宿り木の種を使って、他人を回復させていたことを思い出した。僕が今やったのは、その逆だ。
ポケモンの技は、時折本来とは、違う効果を発揮する。
タブンネのくせに、自己中心的な思考だった僕は、これが可能だったのだろうか。
もう一度、癒しの波動を使った。またしても成功。僕は全回復した。あの連中は、半回復だけど。
僕はこれで、生命の危機から逃れることができた。
僕はもう、他のポケモンを回復させるのを止めた。
これで再び、他のタブンネから嫌われる。そう思っていたが、そうではなかった。あの一件を知ったタブンネの中には、僕に対して、同情する者も多くいた。中には、自分もこれからは利己的で生きてみるよ、と僕に向かって言ってくるタブンネもいた。他のポケモンを救うタブンネの数も減った。
人間達はまだ、ここにいるポケモンを狙っていた。けれども、それもあと少しで終わる。
やがて人間は、タブンネに次ぐ、あるいは同率程度の、能率の良い経験値マシーンを、発見するのだろう。そして、そのポケモンのみが犠牲になるのだ。
その後人間は、そのポケモンを倒してはいけない、という決まりごとを作るかもしれない。そしたら、また別のポケモンが標的になって。それが、いつまでも終わらない。いつまでも終わらないことに気がついた人間は、そんな決まりごとは意味がないことを悟る。そうすると、タブンネを倒してはいけないという決まりも撤廃される。そうすれば、またタブンネが狙われることになる。
その流れを予想している、仲間は多かった。
今だけなのだ。こうして、体に傷をつけずに暮らしていけるのは。
「この間、ハブネークが吐き出した毒の塊が、僕にかかっちゃって。強い毒だったから、すごく苦しかった。でも、癒しの心を使って、毒を取り除けたんだ。すごいでしょ。癒しの波動は、まだ覚えてもいないけど。でも、覚えたらきっと、お兄ちゃんみたいに、自分を回復させられると思うよ」
そう言った後、まだ幼いタブンネが、僕に向かって笑顔を見せて駆けていく。僕も笑顔で手を振った。自己中心的になったタブンネは、癒しの波動や癒しの心を、自分のために使うことができる。どうやらそれは真実のようだ。
誰かが不幸になれば、誰かが幸せになる。その循環は、終わることはない。だから、自分が幸せなときは、遠慮なく、その幸せを味わっていこうと思った。
思えば夏に葬式をやってばかりだ、とぼやいた父の声を、僕は暑さに揺らぐ視界の中で聞いていた。
夏の葬式とは体力を削るものだと初めて知った、大学三年生の夏のことである。
冬に厳寒に襲われるこのシンオウの土地も夏の猛暑には音をあげたようで、カントーほどでは無いにしろ、全身に纏わりつくような暑さがひたすらに重たかった。残暑と呼ぶにはまだまだ少しも収まる様子の無い熱気に、第一ボタンまで締めた首筋に汗が伝う。夕刻の空はまだ青く、西方の太陽は明るかった。
「タタラ製鉄所の方までお願いします」
ハクタイジム前で捕まえたタクシーに乗り込んで運転手に告げる。空調の効いた車内は少し寒かった。ハンドルを切り始めた男の二の腕が覗く、半袖のワイシャツの白が眩しかった。
車窓の向こうに見える景色が流れ出す。訪れる毎に整備されていくように感じる街並は、西陽を反射してぎらぎらと輝いていた。最後にこの街を見たのはいつだっただろうかと思った僕のことを垣間見て、窓硝子越しにムックルが飛んでいった。
祖父の訃報を父から受けたのは今日の朝だった。タマムシゲームコーナーの帰り、大学の友人宅に集まっていつものように無為な時間を過ごしていたら、見慣れぬ電話番号から着信が入った。酒の抜けない起き抜けの頭で夢現に取った電話口で、父は平坦な声で話していた。
友人達に事情を告げ、リザードの入ったモンスターボールをその中の一人に預けて帰った自宅は静まり返っていた。危篤の知らせに父は二日前からカントーを発っていたし、母も先に家を出たようだった。食卓の椅子に、成人式以来袖を通していないスーツと、数日分の着替えが入りそうな大きさの鞄と、黒のネクタイが置いてあった。母が用意してくれたものだと思われた。
数時間の航空を終えて飛行機から降りると、乗り込む前よりも些か冷たい空気が漂っていた。それは風土の違いだけでなく、僕自身の内部から湧き上がる寒気であったのかもしれない。電車に揺られてハクタイに着く頃には消えてしまったその感覚は、祖父の家で感じるそれとよく似ているようにも捉えられた。
「森を越えた辺りにある住宅街に向かって進んでください」
交通の便を良くするためにと、ハクタイの森を抜ける道路が整備されたのは、もはや私が生まれるよりも前のことであろう。これが出来るよりも前は案内人を雇って森を抜けるか大回りして電車に乗るかしか無かったのだから大変だったと、かつてはそうしていた父に度々聞かされたことがある。
森に住むポケモンの生活を出来る限り守るために多少の迂回がされた道路であるが、そういった考え方は一体いつからなされていたのだろうか。考え自体は遥か昔にあっただろうけれど、そちらの方が尊重され、まかり通るのになったのは恐らくそう古い日のことでも無いだろう。
汗を掻いた身体が冷房によって冷たくなる。下がった体温に肌が粟立った。空調の臭いと煙草とエンジンの臭い、消臭剤の芳香に混じって鼻腔を突くものは獣臭さだった。
「すみませんね、先程お乗せした方がビーダルを連れていまして。当社はポケモンをボールに入れずに乗れるタクシーを売りにしてるんですよ」
まるで僕の思考を読み取ったかのように運転手がいい、車窓がするすると下りていく。流れ込むのは冷房よりも穏やかな涼風と、森の木々が茂る葉の臭いだった。
この臭いを嗅ぐと、僕は帰省を実感する。傾いた日に目を細めながら見やった空には回る風車のシルエットが浮かび上がり、フワンテと思しき球体がいくつか漂っていた。
◆
ソノオとハクタイの中間部に位置する住宅街に差し掛かった辺りでタクシーを降りた。製鉄所などの連なる工場地帯で働く人の多く住むここから少し奥まった所に、祖父の屋敷は建っている。去っていく黒の車を見送ると、東の空には折れそうな月が浮かんでいた。
家並みを抜けて屋敷へ向かう。どこかの家庭が夕飯の匂いを漂わせていた。電柱に貼られた求人案内のポスターは剥がれかけていて、連絡先と書かれた電話番号を読むことが出来ない。そのポスターよりも上方で無機質な柱に張り付いたテッカニンが数匹、ジワジワと弱い鳴き声を響かせていた。
幾人かの住民とすれ違いながら歩くと、やがて鳴き声が話し声に変わっていった。声を顰めたざわめきの方へ進んで角を曲がると、長い塀の周りに弔問客が集まっているのが見て取れた。
軽く頭を下げながら黒の群を縫っていく。冠木門の向こうに顔を覗かせると、誂えられた受付で見知った顔の女性が客達を出迎えていた。父の姉にあたる鏡子伯母だった。前を通り際にこちらも礼をすると、彼女は年齢よりも若々しい口元を緩めて「久しぶり」と言った。僕は小さく頷いて、屋敷の奥へと足を踏み入れた。
やたらと広い屋敷は既に葬式の準備を粗方済まされているようで、行き来する弔問客の声や足音が夏風に混じって響いている。喪服に身を包んだ彼らは祖父の会社の人たちや近所の住人だと思われ、親戚の姿はなかなか見当たらなかった。通夜という場に遠慮しているのかそれとも祖父の生前の様子がそうさせるのかはわからないが、ポケモンを出している人はおらず、ただ庭に訪れる野生ポケモンの声だけが長閑であった。
うっすら暗くなってきた屋敷に置かれた照明が、弔問客達を浮かび上がらせている。行き交う影と喪服の黒が混ざり合い、どこか異世界めいた風情を醸し出していた。黒が動く度に漂う汗の臭いと、彼らに出された茶の香りが屋内の湿気に蒸されて強くなる。
盆に乗せた茶を運ぶ母の姿を前方に見つけたが、あくせくと忙しそうであったため声をかけるのは躊躇われた。話すのは後回しにしてそのまま進む。何度目かの障子を横切ると、この屋敷で恐らく最も広いであろう座敷の前に辿り着いた。
祖父の祭壇はそこに設えられていた。葬式など幼児期に一度行ったきりである僕にとって、それは今ひとつ現実味に欠けるものであった。シートの敷かれた畳に鎮座する棺に祖父が入っているというのも想像がつかなかった。
「明久君」
弔問客の密やかな会話をぼんやりと聞きながら佇んでいた僕の名を呼ぶ人がいた。声の方を見やると、祭壇前に並べられたパイプ椅子に座る女性が控えめに手を上げるのが視界に映った。
彼女は鏡子伯母の姉で、名を桜子という。平素の彼女は品の良い夫人を絵に描いたような人であったが、流石に今は全体的に窶れ、弱っている風な印象を受けた。
「お正月以来ね」首だけを動かして伯母が言う。
「はい」
「鏡子達が手伝ってくれたから助かったわ。最近どうも腰が痛くて、あまり動けないものだから。千穂さんにもよろしく言っておいてね」
千穂とは僕の母親の名である。
「はい」
「覚悟はしてたけど、急だったから慌ただしくて。この家も広いし、会社の方々もいらっしゃるから色々手間取ったわ」
「お疲れ様です」
「遺影も碌に探せなくてね」
そう言った伯母の横に腰掛けて祖父の遺影と向き合うと、写真のくせに鋭い眼光がまるでこちらを射抜かんとしているように思えた。深い怒りに何かを睨み付けるかの如き祖父の遺影は、他にもっと別の写真があっただろうと思わせる一方で、これ以上無いほどに祖父という人間を表しているようにも感じられた。
「あんな写真しか無かったのよね。もっとも、お父さんはいつもあんな顔だったから当然なのだけど」
半ば独り言のように伯母が呟いた。くっきりとした紅に彩られた、半開きの唇が微かに歪む。黒い着物から覗く首元に刻まれた皺に、うっすらと汗が滲んでいた。
庭の木に止まりに来たと思しきホーホーの声が、僕たちの間を滑っていった。額の中の祖父は微動だにせず、ただただこちらを睨んでいた。
◆
祖父は近くの工場地帯で、食品加工の工場を経営していた。若い頃の祖父はイッシュで炭鉱をやっていたと聞くので、起業したのはおおよそ五十年ほど前のことだと思われる。
屋敷を建てたのは祖父の祖父、僕にとっては高祖父にあたる江角総次郎だった。江角家初代とも言われる総次郎はカントーの武士の出であったが次男坊であることと維新の風に流され、シンオウの開拓に身を乗り出したという。当時のシンオウは今程までに人の手が入っておらず、自然とポケモンが大きを占める土地であった。
そこで総次郎が如何にして開拓を成功させたのか、それを詳しく知る者は誰一人としていない。祖父は知っているのかもしれないが、それが父達に語られることは遂に無かった。先住民との衝突や行く手を塞ぐ森に歯向かい、誰もが辛酸を舐めたシンオウ開拓を身一つで成し遂げた高祖父の活躍は、ある種伝説となって語り継がれている。
開拓の成功によって得た資産により、総次郎は製鉄業を立ち上げ、同時にこの屋敷を建てた。製鉄工場は祖父の起業に伴い売り払われ、現在は江角でない者達によって経営されている。祖父の屋敷に来る道中に見える、灰色の煙を空へと吐き出す煙突が連なる中のいずれかが、その製鉄工場のものだ。
祖父はこの屋敷に一人きりで暮らしていた。父の母で祖父の妻たる巴さんは父が子供の時に亡くなってしまったから、父達子供が家を出てからは祖父と共に屋敷に住む者はいなかったのだ。一年半前に脳梗塞で倒れたのを機に僕の姉が住み込んで身の回りの世話をしていたのだが、それでも何十年かの間、祖父はこの広い屋敷に一人だった。
大学に上がる折、祖父に挨拶へ出向いたことがある。前年の夏にシンオウの大学を勧められていたのだが、結局僕は自宅から通える大学を選択した。
入学式の季節であった。まだ寒い空気が満ちる屋敷で、僕は祖父と二人で向き合っていた。庭に吹く風が木々を揺らす音と、池の水面が揺蕩う音、時たま野生のポケモンが鳴く声の他には何も聞こえなかった。祖父の部屋は庭へと面していて、いつでも葉の匂いと濡れた土の匂いが充満していた。
屋敷は穏やかに時を刻み、入学を報告する僕の声を響かせた。祖父が終始黙っているのが気まずかったが、それ以上に唯々僕の話を聞くだけの祖父の瞳が怖かった。何か後ろめたいことも怒られる理由もある訳でないのに、何故だか針の筵に座らせている心地であった。
祖父が傾ける杯の縁で、透明の酒がゆらゆらと揺れていた。そこに映る祖父の顔が、幾つにも砕かれ割れていた。自分の声に混ざるハトーボーの鳴き声が、恐ろしく遠くのものに感じられた。
祖父は酒を舐めながら、静かにこちらを睨み付けていた。未だ冷たい春風に散らされた木の葉が何枚か座敷に吹き込んでも、その視線が揺らぐことは決して無かった。
◆
そして、あの時と何ら変わらない視線は今も遺影の中から僕を射抜く。
世間話などを交わしていた桜子伯母は、寺の方が来たという呼び声に席を立って座敷を出ていった。儀式が始まるまでまだ時間があるようだったが、一人で祖父の睨み顔を眺めているのも気が進まない。伯母の足音が消えて数分後、僕もパイプ椅子から腰を上げた。
「ああ、明久」
廊下や中庭で何某かを話している弔問客の中を歩いていると、向かいからやってきた人影が僕を呼んだ。祖父の世話をしていた姉の小春だった。
「姉ちゃん」
「お父さんに会った?」
「まだ会えてない。母さんには会ったけど」
姉は日頃から明るく活発な性格をしており、気難しい祖父の世話も上手くこなしていたのだが、今は流石に顔を曇らせていた。それは祖父が亡くなったという事実と葬式の準備に追われた忙しさだけが理由では無いように思われた。
長い髪を一つに結わえた姉は腰に手を当て、「この暑い中、ねぇ」と中庭を見やって溜息をついた。この屋敷は今時いくつも残っていないであろう日本家屋だが、広々とした中庭を囲うようにして建てられているのが特徴的だった。
一本の大樹と、トサキントなどを泳がせた池を中心に緑の葉が多く生い繁る庭が暮れてきた空の下にぼんやり広がる様子は、まるで小さな森が屋敷に閉じ込められたようである。
「大往生だったんだけど」
「そりゃ、八十七年も生きれば」
「それはそうなんだけどね」姉は声を落とした。
「最期が苦しそうだったから」
庭には勝手に入ってきた野生ポケモンが彷徨いており、弔問客が愛でたり指差して話したりしていた。ブタクサの上で転がるスボミーに、近隣の住民と見える初老の女性が手を伸ばして軽く撫でる。「毒を持ってるから気をつけてほしいな」話題を変えるように姉が言う。「ま、スボミー程度なら大したこともないか」
玄関の方が若干騒がしくなってきた。先ほど伯母が迎えにいった、寺の者が入ってきたのだと思われた。そろそろ始まるのであろう、客達もその気配を感じて庭から動き始めた。
何か手伝えることは無いかと一応問うてみると、これと言った仕事は粗方終わってしまったという答えが返ってきた。白粉を塗った姉の横顔に、風に吹かれた細い髪が一房かかった。
「相変わらずじめじめしてるね」
姉がそれを手で払いながら鼻を小さく鳴らした。
「この家はいつも湿気が酷い」
◆
平坦な声の読経が屋敷に響く間も、祖父の死を実感するということは無かった。
木魚を叩く僧侶を睨み付ける祖父の遺影は今に動き出し、心経を聞く我々を蹴散らして座敷に立ちはだかるかのように思われた。或いは畳でじっと横たわっている棺の中から、痩せ細った身体が怒気を滲み出して這い出てくるのではないかと感じられた。暑苦しい背広とワイシャツに覆われた背中が、薄い底冷えに数度震えた。
入れ代わり立ち代わり、弔問客が焼香するために座敷中に線香の匂いが漂っていた。庭から流れてくる緑臭さと充満する湿気とが混ざり合う臭いは、盆にここを訪れるたびに嗅覚を刺激するものであった。そのため僕の中ではこの臭いは盆のものであり、夏休みのものであり、同時に何時まで経っても慣れない畏怖を感じる祖父の元で過ごすことを実感させるものだった。
読経に被せるようにして、庭でホーホーが一つ鳴いた。横目で見遣った庭は薄暗く、座敷から漏れ出た光が木々や草を照らしていた。
庭寄りの端に置かれたパイプ椅子に腰かけた僕の蟀谷を、庭からの風がのっそりと撫でていった。植物の生臭さを運ぶそれはしかし、湿った空気の満ちる座敷に居ては渇きのものとして捉えられた。視界の不明瞭な庭をずっと眺めるのも気が滅入り、視線を祖父の遺影に戻した。隣に座る姉の向こうに、母、そして父の姿が僅かに見える。
大学で教鞭を揮う父は歳の割に姿勢が良く、伸びた背筋は平時と変わりないものであったが、顔色は悪く青白いものとして僕の目に映った。この屋敷に訪れると、父はいつも顔色を悪くしていた。
◆
「どうにも蒸し暑いな」
読経が終わり、弔問客が帰り出してからようやく父と口を聞いた。母と姉は食堂で夕食の支度をしている。黒のネクタイを緩めながら、父は薄い唇を少しだけ舐めた。
「いつ来たの」
「昨日の夜中だ。ホウエンに近づいている台風のせいで、飛行機が少し遅れていた」
「僕の時はそんなことなかったけど」
「台風が逸れたんだな。さっきニュースでやっていたよ」
父との会話に割り込んできたのは哲人叔父であった。哲人叔父は父の弟で、件のホウエンからここまで来たはずである。垂れ目がちの童顔と日焼けした肌が相俟って、ジグザグマをどこか彷彿とさせた。
「こっちに来ている間に上陸して、家が倒壊したりしないか不安だったが杞憂だった。今向こうは晴天そのものらしい」
「結構なことだ、ぱっとしない空よりずっといい」
縁側に出た父が視線を上へと向けて言った。濃紺の空に浮かぶ星は一つとして無く、まるで朦朧とした灰色の雲が天球の全てを薄く覆っていた。折れそうな月だけが鈍い光をひたすらに放っており、蒸されるような中庭を見下ろしているようであった。
頰と首筋に吹き出る汗を同じように湿り気を帯びた手で拭おうとすると、傍からタオルを差し出された。
振り向いた先にいたのは鏡子伯母で「姉さん」僕よりも先に叔父が声をかけた。何となく口を開くタイミングを失った僕は黙ってタオルを受け取り汗を拭く。冷たく乾いたタオルは母や姉が外へ行く時には匂わせているのに程近い、化粧品の香りがした。
「お寺さんは帰ったの」
「今ね。ご近所の方と話してたんだけど、やっと」
「ああ、この辺に住んでる人なのか」
「お父さんのことも知っていたらしいわよ」
「そりゃあこんなに大きい家に住んでれば有名人にもなるものよね」
僧侶の見送りから座敷に戻ってきた桜子伯母が会話に入ってきた。縁側に祖父の子が四人揃った。
「姉さん、今夜はどうするの」
「まあ、寝ずの番をやっておかないと」
「不安だな、そこまで保つかどうか」
寝ながらの番になってしまいそうだ、と冗談めかして言った叔父に、鏡子伯母が「お父さんが怒って出てくるかもよ」と混ぜ返した。
「洒落にならん」父が言う。
「でも、親父はそんなことで怒る器でもないか」
続けられた言葉に、父の姉たちと弟は一様に頷いた。庭で眠るブイゼルを見つけた桜子伯母がそれを指差し皆で笑っている彼らが背にする、彼らの父の遺影は誰が見ても怒りの表情であった。しかし、滅多なことでは怒らぬ祖父が何に対して忿怒の感情を向けているのか、それは恐らく子供たちの知るところですらも無いのだろう。
◆
父は後妻の子であった。
祖父には元々、正代さんという妻がいて、その人が桜子伯母と鏡子伯母の母である。しかし正代さんは伯母たちが小学生の頃に家を出てしまった。二人の姉妹は父と共に屋敷に取り残され、そして今まで実母の顔を再び見たことは無いという。
それから暫くして屋敷の門を潜ったのが父と、父の母であった。父は私の祖母にあたる巴さんの連れ子で、江角という苗字を得た時にはまだ三つか四つという幼子だった。父にはこの屋敷に来る以前の記憶がほとんど欠落しており、それまでどこに住んでいたのか、実父がどのような人であるのか、どういう経緯でここに来ることになったのかなどをまるで知らない。ただ母の柔い手を握り締めて、草木の薫りが満ちる門の向こう側へと足を踏み入れたことだけが鮮明に残っている。
巴さんが祖父の妻となり、二年が経とうとした頃に哲人叔父が生まれた。伯母は二人揃って、頻りに父や叔父の面倒を見た。十幾つも歳の離れた弟たちが可愛かったのと、近寄り難い雰囲気を醸し出す祖父の姿が幼心には怖く見えることを知っていたからである。事実、身体が弱く早くに亡くなった実の母たる巴さんよりも、父や叔父は姉たちに世話を焼かれていた。
やがて桜子伯母はジョウトへ嫁に行き、次いで鏡子伯母が大学を中退して遅まきのトレーナー修行に旅立った。彼女がエリートトレーナーとして名を馳せる頃、父も大学進学を機にカントーに発ちそのまま学校に残り続け、そして哲人叔父もホウエンの大学に入ることになった。姉弟の分散は桜子伯母の所在が夫の転勤によりイッシュへ移った今も変わることなく、四人の子は祖父を一人屋敷に残してそれぞれの土地で生きている。
父たちは仲の良い姉弟であった。それは今でも同じだろう。
ただ、その彼らが屋敷から散るようにして居なくなったのは何やら父たちにもわからない理由があったのだろうか。次々に門の外へと出ていく子供たちを見送る時も尚、祖父の瞳が放つ光の鋭さが弱まることは一度も無かった。
◆
村佐という、祖父の会社の後継者が挨拶に来たため僕は父たちから離れて座敷を出た。村佐は恰幅が良く如何にも企業の取締役という風情で、祖父の体格とはまるで正反対であった。神妙な顔で頭を下げていた彼だが、祖父に後釜と認められるまでに一体どれだけの辛苦を積んできたのかということは計り知れなかった。
「今日は皆様、朝まで起きていらっしゃるのですか」
「ええ、まあ。通夜と呼ぶものですから」
「明日のこともありますし、あまり無理はなさらずに」
桜子伯母は村佐と面識があるようであった。部屋の連なる家屋を繋ぐ長い廊下を歩くと、母らの作っている夕食の匂いが漂ってきた。
この屋敷には中庭と別に、渡り廊下と家屋に挟まれた小さなスペースがあった。祖父はそこで、オドシシとメブキジカを一匹ずつ育てていた。メブキジカは昔、祖父が巴さんとイッシュへ旅行に行った時に連れて帰ってきたもので、当時はまだシキジカだったらしいが今ではオドシシに負けず立派な角を備えていた。
中庭を背に渡り廊下に立つと、彼らの様子を見ることが出来た。大きなポケモンと遊べるのが楽しくて、ここに来ると僕は決まって彼らを構っていた。しかし今では二匹の鹿は揃って寝ているらしく、草に覆われた薄暗い空間にはこんもりした塊が二つ、丸くなっているのが影として見て取れた。
祖父と同じく、彼らもまた高齢である。どちらも雄であるため、子を成すことはなくここでひっそりと過ごしていた。動かぬ二つの影の向こうには家屋、さらに向こうの塀を越えたところにある林地から葉擦れの音が流れてきた。
廊下を渡り終え、幾つ目かの部屋に入る。改築された食堂や便所などを除けば、ここは屋敷で唯一の洋間であった。茶と紫のどちらともつかぬ真紅の絨毯が敷かれたこの部屋を作ったのは、旧き佳き和の建築を好んだ高祖父でも機能美を愛した祖父でもなく、華美と豪奢に惹かれた曽祖父の伸之介だ。
伸之介は派手好きで、芸術を分かりもしないのに遍く手を出していた。
祖父があまり足を踏み入れないせいで何時でも埃っぽい絨毯に一歩を進めると、靴下越しのふかふかとした感触と共に鼻の奥がむず痒さを訴えた。特にここの部屋に用も無いだろうから、姉も滅多に掃除などしていないのであろう。大理石の机や、本棚に詰まった本の頁には細かな塵が積もっていた。
絨毯を踏みしめ幾らか歩くと、棚に置かれた洋燈が目に留まった。カロスの舶来だというそれには、虹色の角を持つ鹿と色鮮やかな花々がステンドグラスで描かれており、僕は父や伯母、叔父などにこの洋燈を灯してもらうのが好きであった。煌びやかな絵が内側から照らし出される様子をまた見たい気もしたが、洋燈の隣にある古いマッチはとうに湿気っていて、洋間に火を灯すことは不可能だと思われた。
ただ光源は引き戸の隙間から漏れ出る廊下の灯のみである、視界のきかない洋間をぐるりと見渡す。小説や学術書、何やら読めない文字の並ぶ背表紙が敷き詰められて僕を睨みつける。壁に掛けられたファイアローの群れが躍る絵の入れられた額は、端に黴が生えていた。数えきれぬ金の瞳を描いた絵の具だけがひたすら鮮やかに、薄汚れたガラスの向こうで輝いている。
しっとりと茶色い、四角のピアノの蓋に指を走らせると指紋いっぱいに埃が張り付いた。曽祖父が果たして音楽に精通していたのか、また楽器を奏でる腕があったのかは不明であるが、そんなことなど我々子孫たちには関係の無いことであった。幼い頃、この屋敷に親戚一同が集まると好き勝手にピアノを叩いて遊んだものである。曽祖父は既にいないし祖父は洋間に無関心であったから、我々を叱る者は存在しなかった。
重い蓋を開けてみると、つんと黴臭さが鼻をついた。黄ばんだ白鍵を右の人差し指で押さえてみると、篭った音が濁った空気を微かに震わせた。この湿気にやられたのであろう、昔に姉が軽やかなワルツを披露した鍵盤は、今ではその命を尽かせかけたかのように白と黒を黙って並ばせていた。
ピアノの蓋を元に戻して、僕は絨毯に腰を下ろした。足をだらしなく投げ出して天井を見上げる。瀟洒だが実用性に欠けるシャンデリアが取り付けられたそこには、幾何学模様が描かれている。
何ともつかないこの模様は、幼心にはどうにも不気味に見えてならなかった。こうして床に寝そべって天井を見ると、さながら自分が深い水底に沈められて揺れる水面を眺めているような、或いは巨大な生物の腹の中で自らの運命が決まるのを待っているような、はたまた逃げることの出来ない巧妙な罠に捕らえられて途方に暮れているような、そんな気分になったものだ。さっさと起きて部屋を出てしまえばよい話なのだが、言い知れぬ不安は身体を洋間に縛り付けてしまうらしく、僕はいつでも姉や両親などが呼びにきてくれるのを待っていた。
今は流石にそのようなことは無いけれど、不規則な曲線や図形の並ぶ天井は変わらず気味が悪かった。まるで蠢いているような、その癖時を止めているかのようなその模様に覆い尽くされそうになるのを、引き戸からの光とのか細い夜鳴きが繋ぎ止めていた。
◆
洋間を出て父たちの元へ戻ると、村佐はもういなかった。桜子伯母の姿が見えないのは、村佐の見送り際に、祖父のかかりつけであった井上医師が尋ねてきたからだという。井上医師は、診察が立て込んで読経に間に合わず、今になってようやくここを訪れることが出来たらしかった。
「明兄ちゃん! どこ行ってたんだよ、さっき話しかけられなかったから探してたんだ」
村佐と入れ替わりで座敷にいた、従兄弟にあたる大貴が縁側の障子から顔を覗かせて手を振ってきた。父である哲人叔父と似た垂れ気味の目が、くりくりと丸かった。今年十五になるという彼は、半年ほど前に顔を合わせた時よりも更に背が伸びていた。
「悪いね、ピアノの部屋に行ってたんだ」
持主の成長に追いつけない黒のズボンから垣間見える、硬そうな踝を視界の片隅に捉えながら言うと、大貴は大して興味も無さそうに「ふうん」とだけ答えた。幼さの残る、日によく焼けた顔は既に庭のポケモンなどに移っており、興味を失われた僕は苦笑した。
「またあの部屋に行ってたの?」
大貴の代わりに会話を引き継いだのは、それまで彼の隣で笑っているばかりであった少女だった。
「明久君はあそこが好きだよね」
彼女は大貴の姉で、名を菜美子といった。菜美子は僕よりも歳が一つ下で、今は大学に通う傍、ポケモン研究員である哲人叔父の仕事を手伝っていると聞いている。黒のワンピースに身を包んだ彼女の、緩くパーマをかけたような癖っ毛が緑めいた夜風に吹かれて揺れていた。
僕が曖昧な頷きを返すと、菜美子はふっくらとした頬を緩ませた。赤い唇が綻ぶ様子に何となく視線を逸らす。僕はこの、柔らかな笑みを浮かべる従姉妹がどうにも苦手である。彼女に明久君、と呼ばれると、今も昔も耳の奥がくすぐったくなる心地に陥るのだ。
「お父さんたちは今夜ずっと起きてるみたい」僕らそっちのけで明日のことなどを話している父たちの方を見て菜美子が言う。
「ああ、さっき聞いた。寝ずの番をするらしいね」
「お酒の用意とかしてたよ、いいな。俺も混ざりたい」
「別に楽しいものじゃないだろうよ。明日もずっと何かしらあるんだから、僕たちは早く寝ておくべきだろう」
年長者ぶってそんなことを言ってみると大貴は口を尖らせて、わかってるよ、と軽くぼやいた。弟の年相応そのものな素振りに菜美子が笑う。
廊下から漂ってくる、腹の中を刺激する匂いが一層強まった。縁側へと目を向けると、父の吐き出した煙草の煙が夜の空へと溶けていくのが障子の間から見え隠れした。
空に流れる灰色の雲と紫煙との区別がつかなくなる。夕食が出来た旨を姉が知らせに来たのは、それから間もなくのことであった。
◆
夢に魘されて目を覚ますと、木張りの天井がやっと見えるくらいの明るさしか屋敷には残っていなかった。
あの後親戚一同で夕食を取り、夜食の準備をする母や姉、通夜の支度に追われる父とその姉弟を横目に風呂に入った。特にすることも無くそのまま眠りに就いたのだが、気味の悪い夢によって僕は起きてしまったのだ。
寝巻きの下の皮膚は、脂汗でじっとりと湿っていた。ただでさえ湿気の中で寝ているせいで蒸されている感覚が絶えないのに、その上汗まで掻いては耐えがたい。湿り気を帯びたTシャツを脱ぎ捨て、僕は鞄から取り出した予備のそれに腕を通した。
寝起きついでに便所へ行くことにしたが、どうやら目が冴えてしまったようである。襖を開いて廊下に出ると、夜露に濡れた土の匂いがした。隣の部屋の母や姉は元より、親戚の誰もがよく眠っているらしく屋敷は静まり返っていた。飽きもせず鳴いているのはホーホーやヨルノズクだけである。
タイル張りの便所はひんやりと冷たかった。空の色に濃厚な墨を落としたような蒼のタイルが、白熱灯の光にてらてらと照らし出されていた。目を凝らすとその一つ一つに無数の自分が映し出されるのを見て取れたが、冴えぬ顔を沢山見たところで得るものも無く、僕は水が流れ落ちる音を背にして便所を後にした。
すぐに部屋へと戻れば良いのだが、ふと父たちのことが気になった。寝ないで夜を明かすと話していたが、屋敷の静まりようから考えるにその志は果たされなかったと推し量られた。道中、渡り廊下から降りて睡眠中の鹿たちを撫でてそんなことを考える。草と獣の臭いをした二つの塊を覆う毛は細く硬く、僕の手の動きに合わせて低い呻き声を上げた。
微かに軋む音を立てる縁側を歩き、祖父の遺影がある部屋に入ってみると、大方予想していた通りの光景が薄明るい部屋に広がっていた。藺草の匂いに酒や煙草の強いそれが重なって、一瞬奇怪な息苦しさに囚われた。ほぼ空になった何瓶かの酒瓶の側に置かれた、夜食の皿には何も残っていなかった。
「父さん、起きて」
煮染が盛られていたと思しき皿の隣に転がる父に声をかける。軽く肩などを叩いてみると、父は「うう」と唸って身体を起こした。
「俺は何を」
「寝てたんだよ。叔父さんも伯母さんもみんな酔い潰れてる」
「今は何時だ」
「12時過ぎたあたりかな」
「そうか。思ったよりもたなかったんだな」
俺たちももう歳だ、父はそう言って頭を押さえた。流石に酔いは醒めたようであるが、目元は明らかに眠そうな上に呂律も覚束ない。「おい起きろ、姉さん。哲人」父が叩き起こして回った他三人の様子を見ても、このまま通夜を続けるのは困難だと思われた。
「ああ、寝てしまってたのね。いつの間に」
「やはり父さんのようにはいかないな。僕たちはいつまで経っても酒に弱い」
「ともかく、みんなもう寝た方がいいですよ。後は僕が片付けておきますから」
「じゃあ、悪いけれどお言葉に甘えさせてもらおうかしら。もうこれ以上続けられる気はしないわ」
瞼を擦る桜子伯母の言葉に父たちは頷く。「まあ、それで親父が怒ることもないだろう」父は大きく伸びをしながら遺影に向かって呟いた。「親父の一番嫌うのは酒に弱い奴が無理してする酒盛りだから」
足をふらつかせた大人たちが自室へ去っていく。欠伸をする鏡子伯母の細い首筋に浮かぶ、青の血管がやけに目立って見えた。むにゃむにゃと夢現に何事かを言っている哲人叔父の背中を押して歩く父が「そういえば明久」と座敷を出て生きざま、思い出したように振り向いた。
「さっき俺を呼んだか。恭介、と。俺の名を」
「父さんのことは、父さんとしか呼んでないはずだけど。何時頃の話なの」
「俺が寝ている間だ。俺を、起こす前に」
一言一言噛み締めるような父の言葉には、思い当たる節が全く無いため正直に首を横に振った。そうか、と父は緩く頷き、哲人叔父と共に部屋を出ていった。乱れ気味の足音がしばらく響き、遠ざかってやがては聞こえなくなる。
食堂と座敷を往復して、夜食の皿だの空の酒瓶などを片付けてしまうと、祖父の遺体を前にして自分が一人であることを強く思い知らされた。もう幼い子供でもあるまいし、不機嫌な遺影や黒塗りの棺が怖いわけでは無いけれど、むしろ生きている祖父と独り対面しているような緊張感に襲われた。物言わぬ祖父は死して尚僕を睨みつけ、生前と同じ無言を以て自分以外の者を気圧している。
何となく居た堪れなくなり、手近にあった線香を焚いてみた。慣れない手つきと湿気に火がつかぬことを案じたが、それは杞憂に終わった。香に灯された小さな火は、蛍光灯に照らされた部屋の中で音も立てずに燃えていた。
薄ら寂しい匂いに手を合わせ、うろ覚えのお経を心中で唱えていると、背後で軽い音がした。父か親戚が戻ってきたのかと振り向いたが、そこにいたのは僕の予想していたどの人物でもなかった。
「水を飲もうと思って食堂に行ったのだけれども、物音がしたから」
「菜美子」
涼しげな寝巻き姿の菜美子は、「ここまできたらどうにも目が冴えてしまったようで」と廊下側の下桟を踏み越えて言う。白い裸足が微かに押され、仕切の凹凸の形に潰れるのがどうにも艶かしかった。
「明久君も、そうなの」
「大体は、うん。父さんたち、寝ずの番出来そうにないって」
「そう」
菜美子が畳を踏むだけの微小な音が鼓膜を擽った。祖父の遺影と向き合う僕の横に彼女が座ると、床が幽かに軋む音がした。
「どうせ眠れそうにないし。お父さんたちの続きでもしようかな」
独り言のように呟きながら菜美子が線香に火を点ける。僕よりも慣れているように見えるその手つきに、灯された線香がか細い煙を吐き出した。度重なる焼香によって酒や煙草や畳、また庭からの土の臭いは香のそれに取って代わった。どこか非日常的なその香りが強く鼻腔を突くせいで噎せ返るようである。
僕は何も言わなかったし、菜美子も敢えて何かを言うことをしなかった。しかし僕が自分の寝床に戻らなかったように、菜美子もまたこの座敷から動く様子を見せなかった。
隣では菜美子が手を合わせているし、眼前には祖父の祭壇が鎮座している。奇妙なことになったな、と二重の緊張を覚えながら、僕はじっとりという湿気の中にふうと息を吐いた。
◆
昔、こうして菜美子と共に縁側で庭を眺めていた記憶がある。
夏の夜だった。夕飯が出来るのを待っていたのか、或いは食後の夕涼みをしていたのかは定かではないが、僕たちは縁側に腰掛け生温い風に吹かれていた。
桜子伯母が、自分や弟妹の過去に着ていた浴衣を出してくれて、僕と菜美子はそれに身を包んでいた。白地に朝顔を描いた菜美子の浴衣の裾に、一対のメガヤンマが舞っていた。麻の生地越しに感じられる木目が少し痛かった。
当時、屋敷では家政婦を雇っていたのだが、交代で派遣されてくる彼女らの誰かが気を利かせてくれたらしく、僕たちに甘露を作ってくれた。ミツハニーの蜜とカイスの汁を水と混ぜ合わせたそれを縁側に置いておくと、バルビートやイルミーゼが何処からともなく集まってくるのだ。
甘やかな匂いがする皿を間に挟み、僕と菜美子は蛍たちが飛び交う中庭を眺めていた。彼らの光は不規則な軌道を描いて行き来し、僕は時折その柔らかな輝きが眩しくて目を細めた。暗い庭のせいで彼らの身体は見えず尻の光だけが浮かび上がっているのが少し怖くて、膝を隠す浴衣の布をぎゅうと握り締めていた記憶がある。自分の太腿に拳を押し付けていると、子供特有の柔らかな肉を感じることが出来た。
「綺麗だね」
そんな僕とは対照的に、菜美子は頻りに喜んでいた。蛍の舞を表現する豊かな語彙も、何も言わない選択肢も知らぬ時分の彼女は繰り返し、その言葉を繰り返した。曖昧な頷きだけを返す僕の首筋に汗が垂れていたのは、もしかすると蛍のせいだけでは無かったのかもしれない。庭の中央に位置する大樹の葉が風に騒めく度、幾何匹の蛍たちはその周りをぐるぐると回った。
◆
それから十年以上の月日が経った今、中庭に飛ぶ蛍はいない。祖父が倒れたことを皮切りにして家政婦を雇うことはなくなったし、夏の夜に甘露を作る者もいなくなった。僕と菜美子の間に挟まれているのは薄ら甘い水ではなく、父たちが残していった何本かの酒瓶である。
我々も育ち、あの頃着ていた浴衣などとうに着れなくなっているだろう。あの頃は縁側からぶらつかせていた両足も今や地面につき、むしろ縁の高さが足りないようにすら思えた。土を踏む裸足の皮膚が、湿り気を帯びた冷たさを訴える。茶黒の土は濡れていた。
「大学はどうなの」
「それなりに。むしろお父さんの手伝いの方が忙しいかも。明久君は」
「毎日を不毛に過ごしてるよ」
戯けて言うと、菜美子が息だけで笑ったのが鼓膜に伝わった。半袖の寝間着から覗く彼女の二の腕は白く、闇夜に照らし出されたそれはふっくらという印象が見受けられた。記憶の中の幼い菜美子もお饅頭のような子供であり、僕は菜美子に会う度に内心、チョウジの銘菓が口恋しくなったものだ。
縁側に出たため、座敷の灯りは消してしまった。視界を助ける光源は塀の向こうの街灯と、ハクタイが近いせいかやたらと明るい夜の空と、叢雲に覆われた細い月だけである。奇妙に薄暗い空の下で、あの日から変わることのない大樹が風に葉を揺らしていた。巨大な影が中庭に浮かび、その様子はまるで何か大きな化物が体躯を震わせているかのようにも感じられた。
何くれとなく大樹を眺めながら、菜美子と取り留めのない話をしていたのだが、やがて話は彼女の弟である大貴のことに差し掛かった。「旅は順調なのかな」トレーナー修行のために数年前から旅を続けている彼の笑顔を脳裏に描いて僕は問う。この質問は菜美子と言葉を交わす毎にしているし、先程見た彼の逞しく元気な姿から考えるに聞くまでも無いのだろうけど、それでも僕は飽きもせずに毎度毎度尋ねていた。
「うん。三月からアルミア地方に行ってるみたい。今日は飛行機で駆けつけたみたいだけど」
「すごいなぁ、レンジャー志望かな」「どうだろう。そんなことも言ってたけど、すぐに興味が変わる子だから」
ついこの前はドラゴン使いになるって張り切ってたのにね、と菜美子はそう言って肩を竦めた。頭の中に、ボーマンダに乗って空を飛び回る大貴の姿が現れる。想像上の従兄弟は、晴れ渡った空を背にして眩しい笑みをこちらに向けていた。
ひとたび現実に戻ればしかし、はっきりとしない空が我々の上に広がっている。手に収めた猪口に映り込む空は、流れるような灰色の雲をひたすらに浮かべていた。猪口の底には墨絵のハンテールが描かれており、注いだ酒が揺れるのと一緒になってゆらゆらと揺蕩った。
細長い身体が揺らめいて、雲の藻に幾つもの斑点が見え隠れする。「でもねぇ」菜美子が酒に口をつけて言った。彼女の使う猪口にはサクラビスが描かれているはずだった。
「ああして、ここで元気にしてるのが、まだ信じられないことがあるんだよねぇ」
ここに来るといつもそう思う。この屋敷で大貴が普通に笑ってるのを見るとね。
大樹やその他の木々が起こす葉擦れの音が、菜美子の声に被さった。濡れた空気を吸い込むと、深緑が肺の奥まで流れ込んできた。猪口を摘む右手の指が、薄く汗を掻いている。
大貴は昔、この屋敷で生死を彷徨ったことがあった。
◆
僕が十になった頃のことであった。
盆のために屋敷へ僕の家族と菜美子の家族が集っており、まだ四つになるかならないかという幼さの大貴もここに訪れていた。
その時、僕はあの洋間で菜美子と共に、姉に本を読んでもらっていた。無論洋間にあるような読めない文字で書かれた本ではなく、前日に祖父が本屋で買ってくれた子供向けの冒険小説だった。ホエルオーに呑み込まれた主人公が胃の中から巨大な鯨を攻撃し、脱出を試みるシーンであったと記憶している。
母が持ってきてくれたジュースを飲みながら、僕たちは洋間で緩い時間を過ごしていた。よく晴れた午後で、けたたましいテッカニンの鳴き声に姉の朗読が重なるのが心地良かった。湿気はやはり満ちていたが、廊下から吹く風は涼しかった。
菜美子や大貴の母親の悲鳴が聞こえたのはそんな折だった。言葉にならない言葉をただ音として表したような叫び声は、長い廊下を渡って僕たちの元まで届いてきた。
最初に反応したのは姉で、次いで菜美子が弾かれたように立ち上がった。それからのことは怒涛のようで、詳しいところまで把握することは不可能だった。父や母、叔父の叫ぶ声や怒号が飛び交い、菜美子や彼女の母親が泣く音もした。僕はどうすることも出来ず、一人洋間に取り残されて呆けたように座り込んでいた。ジュースの入っていたコップが空になって床に倒れていた。姉や菜美子が立った衝撃でそうなったのかと思い、絨毯に染み込んでいないかを霞んだ頭で心配した僕は足元の天鵞絨を指でなぞってみたが、酷い湿り気のせいで僕の指も絨毯も、元から濡れていたようなものであった。毒々しいほどに鮮やかな紫の、香料がきつい液体は一滴も残っていなかった。
ふらつく足でようやく廊下に出た。洋間の外は湿気が一層酷かった。救急車のサイレンが聞こえて、運ばれていく従兄弟の姿が一瞬だけ見えた。柔らかで健康的な小さい手足はぐったりと投げ出されていて、噴き出た汗のせいかぬらぬらと光っていた。
一つ、はっきり記憶に残っていることがある。
救急車への同乗を許可されたのは大貴の母親だけで、自分もついていくと強く訴えた父や菜美子は屋敷に残るよう命じられた。
そうしたのは他ならぬ祖父であった。救急隊員に縋りつく菜美子たちを引き剥がし、祖父は酷く恐ろしい声で、自分の部屋に戻ること、そして中庭には絶対に近づかないようにすることを怒鳴っていた。後にも先にも、祖父があれだけ激しく感情を露にしていたのはあの時だけである。
「水を飲め」
祖父はそんなことも強く言い聞かせていた。濃厚な湿気と水の臭いが充満する廊下で、僕はぼんやりと中庭に目を向けた。
陽炎の揺れるそこに鎮座する大樹は我々の騒ぎなど御構い無しに翠の葉を繁らせていた。隆々とした幹の根元、大樹の隣に位置する池の水がすっかり干上がって、中を泳ぐトサキントとアズマオウが美麗な腹を仰向けにしてごろごろと転がっていた。
◆
大貴は脱水症状を引き起こしていた。
暑い夏の昼間であったからそれ自体は何ら不思議なことではない。幼い子供は熱中症にもなりやすいのだから、目を離した少しの間に大貴がそうなってしまったのも無理のない話である。
不可解なのは、大貴がどうして、一人で中庭へ向かったのかということだった。当時の彼は今と違って大人しく、また母親に甘え盛りであったためにそばを離れて何処かへ行ってしまうなどということは滅多に無かった。その上、彼がいたのは渡り廊下の向こう側の家屋であり、縁側から中庭へすぐに行けるということも無い。彼が中庭に行くのなら、屋敷にいる誰かしらが気がついても良さそうだった。
大貴は、大樹の根元に倒れていたという。小さい身体からは水分が失われ、丸い目は全くもって閉じられていた。
「あの時、大貴が死んだのだと思った」
薄明るくぼやけた空を見上げて菜実子は言った。
「もう大貴は、ここにいないんだって考えたの。救急車が運んでいったあれは大貴の抜け殻で、本物の大貴は、この庭に閉じ込められてしまったんじゃないかって」
「でも、大貴は戻ってきたじゃないか」
「そう。戻ってきた。信じられなかった」
生死の境を彷徨うこと数日、大貴は無事に回復した。後遺症なども特段無くて、まるで何事も無かったかのようでった。むしろ歳を重ねるにつれて彼は活発になり、命の危機を垣間見たとは感じさせないほどに健康そのものである。しかし菜実子は、また彼らの父や母は、ふとした瞬間に彼がまた死に向かってしまうのではないかと不安になるという。それは単なる過去への恐怖というよりは、この屋敷に訪れると無条件に襲いくるものだと菜実子は述べた。露に濡れてぬらぬらと光る、大樹の葉を見る毎に、自分の弟がどこか違う世界へ連れて行かれる思いに駆られるのだ。水気の満ちる空気に、大貴が溶けてしまうかのような錯覚を覚えるのだ。
「それでも、大貴がここに踏み入ることは流石に無いのだけれどね」
「そりゃそうだ。いくら小さい頃といっても、何と無く覚えているのだろう。自分が死にかけた場所になんて、入りたくないに違いない」
菜実子の言葉に頷きながら、僕は杯に揺れる酒を舐めた。眼前の中庭に生える大樹は、あの日と何も変わらずに青々という葉を只管に繁らせている。
大貴が病院へ運ばれた後、祖父があの下に立っているのを見た覚えがある。何をしているのかはわからなかった。炎天下の中、大樹を強く睨みつけている祖父は、汗の一つも掻かずに太い幹の前で仁王立ちをしていた。少しも鳴り止まぬテッカニンの声が、警鐘のように何処か遠くから聞こえてきた。
「そう、庭に入らないといえば、明久君が怒られたことがあったね」
その祖父も今はもういない。話題を逸らした菜実子に、僕は苦笑と軽い溜息を返した。自分の口から吐き出された酒精の匂いが夜風に運ばれる。
「怒られたというほどではないだろう」
「まあね。おじいちゃんはいつもああいう顔だから、怒っているのかどうかもわからないし」
でも、あれは怖かったよと菜実子が笑った。首肯を以てそれに応えながら、僕は友人の家に置いてきた相棒のことを考えていた。
◆
僕が初めてポケモンを持ったのは、トレーナー免許を取れる最低年齢から三年遅れた中学一年生の時だった。
友人の中には旅に出る者もいたし、そうでなくとも自分のポケモンを持つ者もそれなりにいたが、ポケモンといるよりかは本を読んだりゲームをしたりという方が好きだった僕は、取り立ててポケモンが欲しいとも思っていなかった。祖父の家に来ればオドシシやメブキジカと遊べるし、平素は友人や学校のポケモンを見たりするだけで十分だったのだ。家にいたポリゴンは姉のものであったが、ほぼ共同のポケモンであるようにしていたのも一因と言える。
その僕がポケモンを持つ機会となったのは、菜実子の中学進学であった。進学祝いにポケモンを欲しがった菜実子は、研究者である哲人叔父のツテで初心者向きのポケモンを用意してもらえることになったのだが、もしよければ一緒に来ないかという誘いが僕にもきたのだ。その頃はまだ大貴も幼くポケモンを持てる年齢では無かったため、菜実子が一人でポケモンと対面するのは心細いと叔父に訴えたらしかった。
父も母も、そして僕もポケモンを持つのに反対する理由は特に無かったため、菜実子の家へ遊びに行くのも兼ねて申し出に甘えることにした。カントー地方から菜実子たちのいるホウエンまで、生まれて初めて自分だけで飛行機に乗った。着替えを詰めた鞄がこれほどまでに重いのかと思ったのも、機内の無機質な空気がやけに重苦しかったのも、あの時が最もそうだった。
空港で待っていてくれた哲人叔父一家に迎えられた僕は早速、菜実子と共に研究所へ向かった。駆け出しのトレーナーに適しているようなポケモンが何種類か、リノリウム張りの床で好き勝手に走り回っていた。僕は一番大人しそうな、柱の陰で退屈そうに丸まっていたヒトカゲを抱き上げた。これといって抵抗もせず、かといって喜びを見せるわけでもない橙色の柔らかい物体と顔を付き合わせている僕の後ろで、菜実子が頬をぷくりと膨らませ、小さなアチャモを追いかけまわしていた。
そうして僕はヒトカゲを連れて家に帰り、特段問題も無い日々を過ごしていた。ヒトカゲは予想以上に怠惰な性格であった。炎を司る種族であるくせに暑いのが苦手なようで、夏が近づくにつれて丸々とした腹を天井に向けて我が部屋で転がっているのをよく見た。
やがて盆の季節になり、祖父の屋敷に行く時期が来た。ポケモンを持ったことを祖父に報告しなさいと父が言ったため、ヒトカゲも連れて行くことにした。ボールに入れられた彼はいつも通りにぼんやりとしていて、眠たげに身体を丸まらせていた。
屋敷に着き、僕はヒトカゲをボールから出して祖父の元に向かった。ヒトカゲは自分で歩くことを面倒臭がるため、僕が抱きかかえて運んでやった。激しい湿気と夏の暑さに加え、腕の中にいる高体温の生き物が汗腺を執拗に刺激した。
「そいつを今すぐに戻せ」
ヒトカゲを見た、祖父の第一声はそれだった。
「その火を持ち込むな」
座敷に胡座をかいた祖父は微動だにせずそう言った。怒鳴っているわけではないし、激昂されたというわけでもない。ただ、有無を言わせぬ声で、僕は立ち退きを命じられた。
呆然と立ち竦み、戸惑う僕の後ろで、同じようにアチャモを見せようとしていた菜実子が赤い雛をそそくさと後ろに隠しているのが視界の端に見えた。菜実子は存外ちゃっかりした性格であった。抱きかかえたヒトカゲの爪が、腕を回された首筋に食い込むのが微弱な痛みとなった。鱗に覆われた尻尾の先で燃える炎が揺らめき、無言で我々を見ている祖父の姿を、まるで陽炎のように溶かしていた。
僕は何も言えずに祖父の部屋の扉を閉め、菜実子と共にポケモンたちをボールに戻した。悲しみや怒りといった感情は、唐突な驚きにすっかり掻き消されてしまっていた。廊下から見える中庭だけが変わらぬ様子で、大樹に繁る葉がばさばさと音を立てていた。
あれからずっと、屋敷にヒトカゲを連れて行っていない。それは彼がリザードになってからも同じだし、菜実子もまたそうだった。もう怒られるのは御免であるという理由も勿論あるが、それ以上にボールを握った我々の手が屋敷の門を越えるのを押しとどめているのは、あの時の祖父が放った声であった。
低く告げられた、地の底から響くような声。水気の多い空気を静かに揺らしたそれは、祖父の身体の奥深くから発せられたように思えたものだったと記憶している。
◆
ヒトカゲに限らず祖父は、中庭に誰かが立ち入ることにあまり良い顔をしなかった。
野生のポケモンが勝手に入ってくるのには何も干渉しないのに、我々が敢えて連れ込んだりすることは祖父の気に入らない部類であるようだった。
父に聞いた話である。
父が中学に上がる頃には既に桜子伯母は嫁に行ってしまったし、鏡子伯母もトレーナーとして各地を回っていたため、屋敷に残されたのは父と、小学生であった哲人叔父だけだった。家政婦が通っているとはいえ祖父は日中家を空けているし、二人の母親は幼い頃に亡くなっていたため、取り残された兄弟は必然的に揃って行動するようになっていた。
哲人叔父は昔から兄たる父によく懐き、憧れている部分があったから、二人の趣味嗜好は似通っていた。父と叔父は夏休みになると、午前中に図書室へ出かけ、昼になると帰ってきて食事をとり、あとは一日借りてきた本を読み耽るという生活を送っていたという。余談であるが、今現在の叔父が研究者であることと、父が大学教授という職に就いたことはその頃の過ごし方が深く関係しているのだろう。ともかく、父たち兄弟の生活は夏休み中変わることが無く、彼らは障子を開け放した座敷に本をいっぱいに広げて時間が過ぎるのを待っていた。部屋に寝転がる兄弟は蒸し暑くも穏やかな夏に包まれており、中庭を臨む縁側からは緑臭い風が時折涼しさを流してきた。桜子伯母が帰郷した際に持ってきた、薄い硝子にぽってりというラブカスを描いた風鈴がその度に、水粒を転がしたような音を立てた。薔薇の花弁にも見える海水魚達が、陽光を乱反射させてゆらゆら泳ぐ。
その日、祖父は珍しく一日屋敷にいた。仕事がひと段落ついて休みを取っていたのか、或いは家ですべき業務があったのか、誰かをもてなしていたのかは定かで無い。それに祖父がいたからといって父たちと共に遊ぶというわけではなかったため、父も叔父もいつも通りに二人で過ごしていた。
父はカントーの生態系変化について書かれた本を読んでいた。生物学に興味を持っていた父の真似をし、叔父は分厚い植物図鑑の頁をせっせと捲っては並ぶ草花の写真をに指をなぞらせていた。図鑑は古く、日に焼けて黄ばんだ頁を一枚捲る毎に乾いた音がか細く聞こえた。紙の酸化した臭いが少年の鼻をつく。
そうして写真を見ているうちに、幼い叔父は見覚えのある植物を本の中に見つけた。それはついぞ先日、縁側から見た中庭の光景にあったものだった。叔父は、汗で畳と張り付いてしまった膝を起こして中庭の方へと向かった。真っ白のタンクトップから露出する腕には、畳の目の跡がびっしり走っていた。
「どうしたんだ」活字が犇めき合う本から少し顔を上げて父が問うた。「あれを探しに行くの」叔父は答えながら開いたままの図鑑を指差したが、幾種類かの植物が載った中のどれを言っているのか、父に見当がつくはずもなかった。「ふうん」父は緩く頷き、細かな文字の海へと意識を戻してしまった。
物静かな兄の反応が芳しくないのはいつものことであるため、叔父は特段不満に思うこともなく中庭へと降り立った。覆うもののない足の裏が土を踏む。地下から伝わる冷たさと、炎天に焼かれた熱さが同時に皮膚を襲った。叔父は跳ねるようにして中庭の奥へ進んでいった。紺青の空は眩しかったが、大樹の落とす広い影は中庭を程良い明るさにしていた。
図鑑の写真と似通ったものを目指し、叔父が一歩を踏み出した時だった。叔父の左腕を掴み、強く引っ張る者がいた。
「何をしている」
それは祖父であった。いつの間に近づいていたのか、縁側に立った家着姿の祖父は小さな息子の腕を掴んでただ問いかけた。「何をしているんだ」
「あの葉っぱを探すの」
叔父は素直に答えた。彼の指が先ほど兄へとそうしたように、座敷の図鑑を指差した。図鑑の近くでは、祖父が急に現れたことに驚く父が頁を捲る手を止めて身体を硬直させていた。
答えた叔父に、祖父は怒るでもなく笑うでもなく、そうか、とだけ返した。しかし細っこい手首を握る、骨張った手が離されることはなかった。縁側から叔父を見下ろしたまま、祖父は淡々と言った。
「あまりこの庭に出ない方がいい。毒に触れると危ないから」
「毒のある葉っぱがあるの」
「葉っぱだけじゃないから危ないんだ」
障子の向こうで交わされる会話は、聞いていた父からすると微妙に噛み合っていないものに思えたという。玻璃の如き青空を背にした親子の姿を見ていると目が霞み、眼下の文字列が得体の知れぬ微小な生物が蠢いている様子に感じられた。座敷に満ちた湿気に蒸された頭は、藺草の臭いだけを執拗に捉えて少年の意識を朦朧とさせた。
◆
玄関へ続く廊下に置かれた柱時計が、深く低い音を一度鳴らした。屋敷の床を伝って響くその音は、今我々の後ろで棺に収まっている祖父の声を思わせた。
薄暗い中庭で、どこから来たのか、コロボーシの鳴く声がし始めた。彼らが震わせる夜の空気は冷えていたが、それを凌ぐ蒸し暑さが全身を覆うように漂っていた。
「おじいちゃんはいつも怒っていたようで怖かったけど」
菜実子が違う酒瓶に手を伸ばしながら言う。
「でも、一度おじいちゃんと二人だけでお祭に行ったことがあるの」
杯に注がれたのはどうやら果実酒だったようで、甘さと酸っぱさの混じり合う匂いがつんと鼻腔を突いてきた。緋色の曇りのある透明な瓶には筆絵のヒメリが描かれている。菜実子の杯で、黄金色の液体が小さく波打ちちゃぷんと音を立てた。水底のサクラビスが身体を翻す。
「そんなことあったっけ」
「八歳の頃。明久君たちはその次の日にくる予定で、本当は私たちの家族とおじいちゃんで行くつもりだったんだけど、大貴の準備が手間取ったから。私と、おじいちゃんだけで先に行ってなさいって」
「なるほど」
「自分で言うのも何だけど、その時のことはよく覚えているの」
菜実子の白い喉が、酒を飲んでこくりと音を立てた。金の水が流れる動きに合わせ、首の皮膚が盛り上がったり元に戻ったりした。
それがどうにもグロテスクで、僕は庭へと視線を戻す。杯に残っていた酒を飲み干し、枝を広げる大樹の葉の隙間から、無理くりに夜空を見ようなどと無意味な試みを徒にした。熱を持った目元は霞んで、視界に捉えた青墨色が単に木の葉がぼやけたものなのか、それとも本当に夜の雲居であるのか、決めることは出来なかった。
◆
ソノオの神社で毎年行われる夏休みへ、祖父に手を引かれた菜実子は向かっていた。
祖父の歩くスピードは速く、菜実子の小さな歩幅ではついていくのが精一杯だった。慣れない浴衣も足を開きにくい一因となり、裾に描かれたシャワーズの見返りの絵柄も着た当初に比べて色褪せたものに感じられた。腰に締められた赤い金魚帯がどんどんきつくなった。
自分の腕を掴んで先へ先へと進んでいってしまう祖父は、菜実子にとって恐怖の対象であった。怒られているわけでも叱られているわけでもなく、むしろ祭に連れて行ってくれているということは理解しているのだが、それでも仏頂面で終始無言の祖父はその気が無くても高圧的な印象を与えざるを得なかった。年の割に背が低く、祖父を見上げるためには首を痛くなるほどに傾けなくてはならなかったのもその一因かもしれない。
祭に浮き足立つ参拝客の間を縫いながら、菜実子は今頃家で準備をしているだろう両親や弟のことを考えていた。本当ならば今自分の手を引いているのは祖父ではなく、人好きのする優しげな丸顔の父であったろうし、或いは勝気だけども笑顔を絶やさぬ母であったであろう。そうでなくても、サンダースを描いた紺の浴衣に身を包んだ、やわやわとした弟の片手を自分が引っ張っていたかもしれなかったのだ。人ごみの中に弟ほどの年頃である幼児を見つける度、菜実子の心はどっしりと重くなった。
早歩きをしたせいで、小さい菜実子はすっかり疲れ果ててしまっていた。この日のために父が買ってくれた下駄の鼻緒は指の付け根を幾度となく擦り、薄い皮膚は裂けて滲んだ血が黄色の鼻緒にこびりついた。人波に熱された空気は息苦しく、階段を上りきる頃には肺が悲鳴を上げていた。がやがやと絶えることのない参拝客らの話し声や行き来するポケモンたちの鳴き声、屋台から放たれる呼び声が一緒くたになって鼓膜を揺さぶった。本殿から聞こえてくるお囃子の、篠笛の甲高さは浴衣の下の肌を粟立たせた。お好み焼きや焼きそばの屋台から漂ってくるソースの匂いは例年ならば食欲を引き起こすものであったが、滅入った気分をさらに悪くするだけだった。
ただ、そんな菜実子の心中を祖父も察していたようで、険しい表情こそ崩さないものの、立ち並ぶ屋台に近寄ってはあれやこれやと買い与えて孫の機嫌をとったらしい。甘ったるい水飴を舐め、粉末ソースと砂塵とが混じったお好み焼きで腹が膨らむと、菜実子の緊張も幾らか和らいだ。ビニールのプールに浮かんだスーパーボウルを赤と緑と白地に金筋、そしてマルマインの顔を描かれたそれを祖父が見事掬い上げたので菜実子は歓声を上げた。
サーナイトのお面を買ってもらい、側頭部にそれをつけて菜実子は上機嫌であった。相変わらず祖父が菜実子の歩く速さを待ってくれることは無かったが、靴擦れの痛みも帯の苦しさもいつの間にか忘れていた。すれ違った、桃色の浴衣の少女が掌に弾かせる水ヨーヨーが鈍い音を響かせる。かき氷屋の暖簾の下で、グレイシアが熱気を凌ぐようにして地面に伸びていた。
「なんだ、怖いのか」
不意に菜実子が祖父の手を強く握った。それはお面屋に並んだ面に混じって舌を出している、悪戯なゴースを見つけて驚いたことによるものだったが、祖父にそれは伝わらなかったようだった。祖父は、お面屋の向こうにある本殿を見て菜実子が怯えているのだと思ったらしかった。
朱塗りの本殿では軽やかなお囃子に合わせて舞が披露されていた。緋色の袴と純白の舞衣に身を包んだ巫女が四人、透けた般若の面を着けた男と赤帯の女を挟み込むようにして舞っていた。当時の菜実子にわかるところでは無かったが、毎年披露されるその舞は神社が出来た由縁、ソノオの花畑を氷雪に包み込み人々を苦しめていた邪神たるオニゴーリとユキメノコが術師に封じられた末、二度とそのようなことの無いように祀られたという様子を表すものである。
祖父はそのことを知っていたのであろう。邪神を封じた焔に見立てた真赤の鶏頭が大きく振られて靡く本殿を見やり、握った手の先にいる菜実子にこう言った。
「怖がる必要は無い。遥か昔に奴等の力は潰えたのだし、それに」
祖父の空いた片手が、本殿と逆方向にある鳥居を指す。「それに」
「あれがある限り、どうせ出ることなど出来るまい」
声や演奏などの騒音の中で、祖父の声は妙に響いていたように菜実子の耳に届いた。木で組まれた鳥居はどっしりと、暮れかけた空を背にして聳え立っていた。組み木の間から一番星の弱々しい輝きと、紫色の空に溶けるようにして飛んでいくムウマの姿が見て取れる。闇色をした小さな魔物はふわりふわりと浮遊して、橙の西空へと消えていった。
祖父の言葉の意味を、菜実子は理解することが出来なかった。手にしていた綿飴が参拝客の熱気で蕩け出し、幼い片手と薄青の袖をべたつかせた。溶けたそれよりも大分重そうな鈍色の雲が、本殿の遥か上空に浮かんでいた。
射撃ィ、という禿頭の呼び声がどこか遠くに聞こえたような気がした。同時に鳥居の向こう側に見つけたのは、ようやくやってきた両親と弟の姿であった。支度時にぐずったままに泣き跡を残した弟の顔を見るなり、菜実子は祖父の手を離して勢いよく駆け出した。
その拍子に落としてしまった精霊の面を、祖父が拾い上げる音を背中に聞いた。
◆
「結局、あの時振り払ったっきり、おじいちゃんと手を繋いでないんだ」
それで、あれっきり。果実酒で喉を潤す菜実子は微かに息をついた。視界に映る天空の半分を覆い隠す軒は殺風景で、いつかあったような風鈴などは外されたままであった。透き通る器を打ち鳴らす音の代わりに今聞こえるのは、鈴の音の如き蟲の鳴き声である。不規則に思えてその実規則的な声は、まるで耳元のすぐ近くで小さな銀の鈴を只管鳴らされているかのような心地にさせた。
「今思うと、おじいちゃんがあんなことを言うのも珍しかったかもしれない」
「あんなって」
「出てこれないだとか、怖がる必要は無いだとか。おじいちゃん、そういうの信じなそうだもの」
杯を両の手に乗せた菜実子の顔がこちらを向く。白く膨らんだ頰に月の灯りが当たって、柔らかな肉がどこか青白く映し出されていた。僕は少しだけ豆大福のことを思い出したが、そういうと菜実子は決まって僕を叱りつけるために黙っておくことにした。
丸い頰から視線を外して下方へ移す。「それでも、あのくらいの歳の人なら普通のことか」一人で納得する菜実子の手首の先、頰と同じ程の白さをした手は昔ほどでは無いにしろ、強く握れば蕩けて消えてしまいそうな心持ちを抱いた。この手を握り、引き、そうしてするりと抜けだされたしまった時の祖父は一体どのように思っていたのだろうか。「シンオウの人だしね、そういうの大切にしてるのかも」濡れた綿菓子が瞬く間に、ほんの少しの名残だけを後に消し去られてしまうような心地に襲われたりは、しなかっただろうか。
神社の雑踏。不気味さを伴う祭囃子。鳥居の中に祀られるは、遠い昔に封じられた邪神。
自分の手から、繋いだ手が抜け出てしまった祖父はその時も、あの珍重とした態度を崩さずに在ったのだろうか。
「信仰心とか、そういうやつなのかな。それなら、ひいおじいちゃんの方があった気がするけど」
菜実子の言葉に合わせて漂動する甘酸っぱい匂いに、足元の草の臭いが被さって奇妙な感覚を嗅覚に与える。池の中でアズマオウが跳ねる音がした。「あれは信仰といっていいのかな」半ば呟くように返した僕に、菜実子は一言「そうだね」と鈴の音程度の小さな声で言った。
◆
曽祖父、つまり祖父の父たる伸之助には総之助という兄がいた。
しかし生まれつき身体が強くなかった総之助は、二十を目前としたところで早い死を迎えたため、総次郎の後を継いだのは次男たる伸之介だった。
江角家初代総次郎は商売に関して俊豪であったが、伸之助にその能力が受け継がれることは無かったようである。総次郎の商才が血と共に流れ出て総之助の脆弱な身体を巡っていたのか、或いは彼らの妹でジョウトの宿屋の女将になった養女に継承されていたのか、それかはたまた、広い屋敷の湿気となって空虚に溶けてしまったのかは依然わからない。ともかく総次郎亡き後、伸之助は父の工場を継いだは良いが父のように切廻すことは出来ず、シンオウ指折りとも呼ばれた江角の名は、緩やかな坂を転がり落ちるように少しずつその輝きを鈍らせていった。
父の持つ商才は全く以て受け継がなかった伸之助だが、しかし強情で牢固たる性格の方はそっくりそのまま写し絵をしたかのように似通っていた。伸之助の危うい経営に周囲の者は度々口を挟もうとしたが、荒い気性と狷介ぶりはそれらを全て跳ね除けた。
結果的に工場の経営は破綻し、伸之助は限界まで膨れ上がった借金を抱えることになる。それらを処理して回ったのが、それこそ総之助の生まれ変わりかとも囁かれる鬼才であった江角家三代目、僕の祖父たる重雄であった。
◆
総次郎の死は、質素で堅実と言えども栄光たる人生を歩んできた男に似つかわしく無い、呆気ないものだった。
彼は息を引き取るその日も工場で采配を揮っていた。その頃の総次郎は優秀な部下に囲まれ、また慕われてはいたものの、いまいち光るところの無い息子の教育に始終頭を痛めていたという。総次郎とて他の者を後釜にする選択肢くらい思い浮かべたであろうが、世襲が当たり前であった時分、差しあたって心身共に健康である実子を却下してまでわざわざ別の後継者を探す理由も無かった。伸之助自身に後継ぎの意志があったのも、彼が江角を継ぐことになった原因の一つである。そのため総次郎は不安を抱えつつも、伸之助が自分の座に就けるように刻苦していた。
長いことそのような生活を続けてきたように、総次郎はその日も工場から帰り、風呂に入り、夕食を摂り、毎夜の習慣だった一杯の酒を飲んで床に就いた。それが彼の最期であった。夏の夜で、蒸した屋敷はさながら熱帯夜とでも呼ぶべき暑さであった。
夏用の掛布団にくるまれ、総次郎が動かなくなっているのを最初に見つけたのは洗濯のため部屋に出入りしていた使用人であった。普段ならばとうに総次郎の起きている時間であったから、使用人はいつも通りに彼の部屋に入ったのだが、いざ布団を持ち上げようとしたらその中にいたのは硬くなった主人であった。
まさに眠るようにして亡くなった総次郎だったが、一つだけ不可解なことがあった。総次郎は酒盛りを好む他には極めて健康的な生活を送っていたにも関わらず、死後に調べた結果内臓や消化器官、骨など体内の隅々に渡るまで、まるで酷使されたかのように壊滅的だったという。何物かに食い荒らされたかとも思えるその様子は異常であったが、その原因に思い当たる者は誰もいなかった。
果たして総次郎の死は謎のまま、江角の名を伸之助が継いだのである。
◆
「ひいおじいちゃんのことは、あの場所でしか知らないからなぁ」
白い頬を薄紅に染めた菜実子が言う。
あの場所、というのは中庭の向こうにある家屋を隔てたさらに向こう側、塀との間に設えられた蔵のことである。
石造りの蔵はかなりの古さを感じ取れるものの非常に丈夫であり、雨に打たれても雪に降られても壊れる兆しを見せずに建っていた。所々が罅割れて不規則な溝を作っているその蔵には、曽祖父伸之助が集めた品の数々が収められていた。もっとも、本当に芸術的価値があったりまたありそうなものは、屋敷を立て直す際に祖父の手によって粗方売り払われているのだから、今現在あそこにあるのは眉唾ものか贋作、そうでなければ路傍の石とも呼ぶべき無名の代物で、単なるがらくた部屋に過ぎないであろう。
「あの物置か。どうだろう、昔は何度か入ったこともあるけれど、よく覚えてないな」
「暗くてよく見えないしね。私、あそこ苦手だったんだ。なんだか怖いから」
「父さんたちは悪いことをすると、決まってあそこに閉じ込められたらしい」
僕の言葉に、菜実子は呼吸だけで笑ってみせた。弦楽器をはじいたように鳴く、コロトックが揺らす空気に菜実子の息が溶けていった。首を少し動かして座敷の方を見てみると、未だ線香の匂いが僅かに残る部屋は薄暗く、祖父が只々眠っていた。
蔵の中は洋間と同じ空気をしていた。埃と黴が鬩ぎ合う、太陽の光から遮断された狭い密室は、世界の外側へ放り出された箱庭の如き静寂さを帯びていた。しかしその癖限りなく小さく寂しいはずの無人の世界では絶えず何者かの呼び声が聞こえ、無数の瞳が自分のことを見張っており、壁を越えればどこかも知らぬ場所へと行けるようにすら思えることもあった。
蔵の中に何があるか、僕はほとんど覚えていない。大体の印象は洋間のような空間だったと記憶している。奇妙な凹凸をした壺、紙魚が酷くて読めない書物、襤褸といった方が適切であろうほどに劣化した羽織。かと思えば、やけに綺麗で美しい状態を保っているグラエナの剥製などが、蔵の片隅で硝子玉の眼を眈々と光らせており、どうにも不気味な場所であったことは確かであった。
「あそこに入った時に見たもので、一つすごい覚えてるものがあるの」視線を杯に落とした菜実子が言う。揺れる酒に映った菜実子の顔はほろほろと崩れては元に戻り、そうしてまたその形を幾つかの破片に変わるのであった。
「何を?」
「巻物。いつのものかわからないけど、とても古かった」
どんな、と尋ねた僕の方へ菜実子が顔の向きを変えた。丸い瞳が僕を見る。その中に映り込む自分の姿は、以前同じ場所で同じように彼女の瞳に入った時同様に、どうにも間の抜けた顔をしていた。
「酒呑童子の」
菜実子はそこまで言って一度口を閉じ、少しだけ俯いて「酒呑童子のお話だった」思い出しながら話し始めた。「昔の絵本みたいなものなんだと思う」
「鬼を酔わせて退治する話だったっけ」
「そう、それがあった」
「何でそれだけあるんだろう」
「わからないよ」
菜実子が困ったように口を尖らせる。特別薄くも厚くも無い唇は酒に濡れていて、彼女が何かを言う毎に合わせて光った。
酒呑童子の絵巻とやらに見覚えは無いが、かといってそんなものは絶対に無かったとも言い切れない。何が収められているのかすらも把握出来ないあの蔵に、それがあっても不思議なことではなかった。
「おじいちゃんがお酒好きだったからかな」
小首を傾げた菜実子が、人差し指と中指で杯の縁をついとなぞった。陶器の擦れる幽かな音が響く。自分の噂をされていることなど露知らず、後方に眠る祖父は唯々静かなままである。
「酒が好きだった割には、あの口癖はどうかと思うけど」
「そうね。でも、それこそ酒呑童子っぽいし」
「なるほど、確かに鬼っぽい。仲間が酒でやられたから戒めとして言い続けてた、か」
「ちょっと、怒られるよ。鬼だなんて」
けらけらと笑う菜実子が、僕の肩を軽く叩きながら目だけで祖父の方を指す。薄い布越しに弱く感じる体温はしかし確かに熱く、湿気に汗ばんだ肌の温度を殊更に上げた。
庭の草の根を視線で掻き分けると、勝手に住み着いたらしい、フローゼルの母が影に丸くなっているのが見えた。柔らかな毛に覆われた腹に守られてめいめい寝息を立てているのは、一見毛玉かと見紛うブイゼルの子供たちだった。明るい茶色の毛がくっつき合って並ぶ様子はまるで鞠のようであった。
「あの口癖。私は、数える程しか聞いたことのないのだけど」
「僕もそうだ。しかし父さんは何度も言われたらしい」
獣の親子が眠る上空には、葉を繁らせた大樹の姿がある。
天高く伸びるその幹は太く隆々としており、あたかも鬼の剛腕の如き風体を醸し出していた。
◆
酒は毒だ。
それが祖父の口癖だった。その癖祖父はかなりの酒豪で、夜毎に酒瓶を一本は空けるかというほど酒を飲んだ。酒に強いのは父親譲りで、その伸之助も父総次郎から受け継いだ数少ないものとして、酒精への不敗を徹底していた。
親譲りの酒豪たる祖父はとにかくよく飲んだ。どれだけ飲んでも顔を赤くする素振りすら見せることなく、涼しい風体で盃を傾け続けていた。その様子を見て、まるで水を飲んでいるようだと揶揄する者もあったけれども、水とてあんなにすいすいと飲むことは困難であろう。
食べ物に好き嫌いが無い祖父は、酒にもとやかく言う性分では無かったが、しかし贔屓にしていた酒はあった。その酒は薄紫をした硝子瓶に入っていて、凹凸の少ない素朴なデザインの容器は陽に当たると菫の花弁の如き光影を地面に落とすのだった。透き通った硝子瓶はそれほど大きくなく、酒が入っている状態でも片手で持ち上げられるほどであった。
その酒の銘柄を僕は知らない。僕だけでなく、菜実子や、父たち祖父の子供も同様である。一般的に売られている酒とは違い、その酒瓶には何のラベルも貼られていなかったし、何かが書かれていることもなかった。祖父は知っていたのかもしれないが、結局誰にもそれを言わないまま死んでしまったのだから、あの酒が如何なるものだったのかは謎のままである。逢魔ヶ刻と呼ばれるような黄昏の空を流し込んだような、青とも黒ともつかぬ紫色の瓶の中で揺れる液体がどんな名を持っているのか、何で出来ているのか、誰によって造られているものなのか、今となっては果たして迷宮入りだ。
その秘密を知ってか知らずか、祖父は兎角その酒を好んで飲んだ。桜子伯母が物心つく頃には既にそうであったし、僕の姉が屋敷に住み込んでから禁酒を医者に命じられる直前まで、祖父は紫の硝子瓶に揺蕩う酒を飲み続けた。
◆
座敷に転がっていた箱から煙草を取り出し火をつける。羽を広げたウォーグルが一羽、濃紺の背景に描かれたその箱は哲人叔父の忘れ物だと見受けられた。祖父は火事を案じていたため屋敷内での喫煙を嫌ったが、この湿度ではたとえ庭の草木に火が燃え移ったとしても、膨れ上がる前に立ち消えてしまうのでは無いかと思われた。肌に貼りつく湿気の中、一緒にあったライターで数回の失敗を経て点火する。
「煙草は普段から吸うの」
「いや。友達からたまにもらうくらいかな」
「高いものね」
最近、また値上がりしたし、という菜実子の言葉に頷きながら息を吸い込むと、肺の奥で熱と芳香が渦巻くのを脳が認識した。身体の中で何か別のものが生成されるこの感覚にいつまで経っても慣れることが出来ず、僕はこの、薬草を乾かしただけのこの物体を咥える度に、飽くことも無く鼓動を速めているのだった。熱くなった胸の内が加速する。自分の半身が奇妙な熱に侵されていく心地は、僕が自分自身でない何者かに乗っ取られ、それに作り変えられていくようにさえ思えるのだ。
胸中で作られた煙をほうと吐き出す。独特の匂いが闇に解け、庭に生える植物の臭みにぶつかった。我が口から漂うその匂いは湿気によって強められ、いつも同じものを纏っている叔父がすぐそこにいるという錯覚を僅かに引き起こした。
「煙草の味の違いなど、僕にはわからないからなぁ」
そもそも美味しさ自体がわからない。そのことを菜実子に告げると、彼女は「それならどうして吸うの」と呆れたように口を開けた。ごもっともなその意見に頷いて、僕はもう一度煙を吐いた。環状の気体が浮かび上がる。
「酒豪の血も流れてないから、酒の審美も出来やしない」
「それはどの道、お父さんたちの誰も受け継いでいないじゃないの」
「その通りだ」
一晩飲み明かすと言った癖して、日が変わるまでが精々であった父たち姉弟を思い出した僕は苦笑した。けらけらと笑いつつも杯に紅い口をつける、隣に座った菜実子の方がまだ彼らよりも酒に強い部類であろう。祖父まで続いた三代の酒豪の血は、誰にも譲られないまま何処かに流れ出てしまったらしい。
指の間に光る小さな炎は赤かった。その先から上がる煙と、先程自分が吐き出した煙が揃って天へと向かっており、月と我が目を隔てる雲と重なり合って両者の見分けをつかなくしていた。
◆
鏡子伯母が初めて酒を飲んだのは、彼女が十六の時だった。
今でこそ活発に各地を飛び回り、老いを知らぬ盛んな血気を評判としているが、昔の鏡子伯母は大変生真面目な性格をしていたらしい。よく言えば淑やかで清廉な症状であったが、はっきり言って愚直な世間知らずである、とは今の鏡子伯母本人の言葉である。
人一倍能天気で天真爛漫とした姉の桜子伯母と一緒にいると、その真面目さはより一層際立った。社交的で好奇心が強く、何事にも積極的に介入していく奔放な姉と、内気で保守的なところがあるが、与えられた課題を黙々とこなす実直な妹を比べ、二人を知る近所の者などは度々その様子を、それぞれ攻撃と防御に特化する、化石から復元された二種の龍に擬えていた。
当時女学生だった鏡子は、学業と嫁入り修行、そして幼少の砌より続けていた薙刀の稽古に打ち込んでいた。手を抜くということを知らない彼女はそのどれもに心血を注いでおり、一瞬たりとも気を休ませることのない日々を送っていた。母はとうの昔に家を出てしまっていたし、父も仕事で日夜多忙であるから、呑気な姉に代わって自分がしっかりしなくてはという自負もあったのかもしれない。長い黒髪を三つ編みにひっつめた鏡子は両眼をきっと吊り上げて、朝は机で書物と睨み合い、昼が過ぎると汗を流して薙刀を振るい、夜が更けるまで己の中の女を磨き上げるのだった。
しかし彼女の気概も無限では無く、秋めいた風の吹く頃に、鏡子は緊張の糸がぷつりと切れたように寝込むこととなる。
迫る女学校の試験に向け根を詰めていたのが原因か、或いは薙刀の大会出場を目指して鍛錬に入れ込みすぎたのが祟ったのかはわからないが、疲労よりくる熱に三日三晩魘された鏡子は呆けたように布団で横たわっていた。あれほど忙しなく動かしていた両手両足も力を失い、絶えず燃える火の如く奮い立たせ続けてきた気勢もすっかり萎んでしまったようであった。広くも質実な自室の天井をじっと見上げ、鏡子はただぼんやりと現に暮れていた。寝続けているせいで日の匂いを失い、部屋の湿り気と微かな体臭を帯びた布団に埋れていれば、何もかもが自分を忘れて進んでいくようにさえ感じられた。
庭に面した障子が開いて、冷たい風がすいと畳を滑っていった。枕に乗せた頭だけを動かしてそちらを見ると、彼女の父の立ち姿が若干の逆光となっているのが視界に入った。秋風よりも静かに現れた父に、平素の彼女ならば何らかの言葉をかけていたのかもしれないが、その時の鏡子は口を動かすことすらも億劫であった。表情というべき表情の無い親子は無言で向き合い、塵一つない部屋の空気を風が揺らす音に耳を澄ませていた。
「来い」
先に言葉を発したのは父の方だった。仏頂面のままそう言った彼は鏡子が何か返事をするよりも先に踵を返し、障子の向こうへと歩き出してしまった。
身勝手な父の行動に鏡子は全く不満を抱かなかったわけではないが、怒るよりも大人しく従った方が楽であると彼女は推測した。薄い掛け布団を剥いで、寝間着の鏡子は起き上がった。自分の身体が鉛のようであるなどと感じるのはこれが初めてのことだった。汗ばんだ肌に、使用人の用意してくれた濡れた布を這わせると、思考を霞ませる熱から少しは解放されるようで心地良かった。
重い足を引きずり、先を歩く父についていく。連れてこられたのは父の部屋だった。
小さな箪笥が一竿と、鎮座する文机。人のことが言えた筋合いでも無いが、いつ訪れても殺風景な部屋だと鏡子は思った。自分の部屋がいつでも片付いているのは几帳面な性質がそうさせているのだと彼女は自負していたが、祖父の部屋がきっちりと整頓されている光景はそういった気性の問題というよりも、生活感と呼ぶべきものが存在していないような印象を与えた。
鏡子は畳に正座し、文机の向こうの祖父と対面していた。障子の外に広がる中庭は緑と茶、赤や黄色が混在して妙な様相を呈していた。部屋に訪れる道中に見えたメブキジカの角に黄金色の葉が茂っていたのを思い出す。焦げたように色付く木々の上空には、細かく千切られた綿によく似た雲が幾つも浮かんでいた。
文机の上には薄紫の酒瓶と杯が二つ置かれていた。素焼きの杯の底にはそれぞれ満ちた月と、そこに目掛けて羽ばたくカイリューが描かれていた。父は口を閉じたまま、カイリューの杯に酒瓶の中身を注ぎ始めた。水が流れて打ち付け合う音が鏡子の鼓膜を弱く揺さぶる。霞みがかった頭に目を閉じると、文机の上に現れた小さな滝がこんこんと清水を落としているようであった。
杯になみなみ酒が注がれると、父は鏡子の方へそれを押し出した。鼠色の器をどうするべきかと戸惑う鏡子に、父は「飲みなさい」と告げた。酒を飲むなどそれまで考えたことも無かった鏡子は驚き、そして渋るように父親から視線を逸らしたが、彼はそれでもじっと動かないままだった。
「飲みなさい」
繰り返される言葉に、鏡子は苦々しい顔をしつつも杯に手を伸ばした。音も立てずに揺れる液体は甘い匂いがした。食欲の無さと、大樹が庭から流す青臭さのせいで、鏡子の気分は少々悪くなった。
父の方を睨みつけても何も言わないため、鏡子は諦めて杯に口をつけた。一思いに傾けてしまうと喉の奥に流れ込んできたのは体内を灼きつくすかのような熱と、苦いほどの甘ったるさであった。朝から白湯しか含んでいなかった胃が弱々しげな悲鳴をあげた。
全身を駆け巡る熱さに目を白黒させ、鏡子は身体を丸めて軽く噎せた。その様子を見、父はやはり何も言わずに酒瓶を手にし、満月の描かれた杯へとその中身を注いでいつものように飲み始めた。
鏡子の咳が収まると、彼は再度龍の杯に酒を注いだ。鏡子もそれ以上何も言わなかった。落ち着いて口に含んだその甘露は先程よりも熱くはなく、また舌に心地良い控えめな甘さであった。今まで体感したことの無い味をしている、と鏡子は思った。
細い喉を鳴らして酒を飲み込んだ鏡子と向き合い、父は淡々と杯を傾けていた。薄紫の瓶の中身はみるみるうちに空になっていった。つい数刻前とは別な類に浮かされている頭で、父はこの酒を一体どこから調達しているのだろうと鏡子は疑問を抱いた。
鏡子の具合はその日のうちに回復した。それから何度か彼女は父と共に杯を交わし、時にはその酒を飲むこともあったけれど、いつか抱いた疑問を口にすることは終ぞ無かった。
◆
底冷えの激しい冬の早朝、若き頃の桜子伯母は虚ろな両眼で縁側に座っていた。
ジョウトへ嫁に行った彼女は腹に子を授かり、旦那方の家の勧めもあって出産のため帰郷していた。生まれ育った地の方が心休まるだろう、と口を揃えて言う夫やその両親たちの心遣いは確かに桜子にとって嬉しいものではあったが、何時でも無表情を貫く父親の居る屋敷がそれほどまでに落ち着く場所かと問われると、実際のところそうでもなかった。どんな心変わりか、可愛がっていた内気な妹がトレーナー修行に出てしまったため家を空けているのも寂しいことだった。それでも、一年半ほど前に出来た小さな弟と優しくて美しいその母親、そして新たに誕生した哲人という次弟に会いたさもあったため、桜子は郷里についたのだった。
しかし元来身体が丈夫な方では無かった桜子の出産は難儀なものだった。どうにか桜子の命は無事だったものの、宿った子は産声を響かせるよりも前に、十月の生に幕を引いてしまった。
体調が回復しても、桜子は全身の力を抜かれたように部屋から動けずにいた。螺子の回りきった人形のように部屋で動かず、彼女はただただ障子の外を見つめていた。連日酷い寒さが続いており、中庭は解けぬ雪で覆われていたが、極寒にも関わらず屋敷の中には奇妙な生暖かさで満ち溢れてもいた。
障子を開け放して中庭を見遣る、桜子の佇まいは異常なほどに存在感に欠けていた。特別痩せているというわけでは無いが身体は一回りも二回りも細いものに感じさせ、艶のあった髪は乱れ、紅色の頰はすっかり痩けてしまった。天真爛漫な笑顔を振りまき、誰にでも好かれる彼女の愛らしさは何処かに消え失せたようであった。
少し目を離せば、降り積もった雪の白銀に溶け込んでしまいそうな桜子の様子を皆心配した。巴さんや弟も、報せを受けて飛んで帰ってきた鏡子も、見舞いにきた旦那家族や使用人たちも、揃って同じような不安を抱いた。
その時の桜子は余りに儚げで、そして何もかもが希薄であった。産道を通るままに三途の川の向こう岸へと旅立った子のように、彼女もまた、縁側から立ち上がると同時に彼岸に消え去ってしまいそうだった。陰を落とした桜子の両眼に映るのは、枯れた葉を数枚残して寒さに耐えている大樹の筈なのに、まるで自らの妄執から成る閻魔大王の裁きに頭を垂れているかのように思われた。
「桜子」
そんな彼女に声をかけたのは父であった。桜子は聞こえているのかいないのか、或いは音としてそれを捉えてはいるものの脳が処理することを拒んでいるのか、庭を眺める姿勢のまま動かなかった。
「桜子」
しかしそれでも父は動じることなく、娘の名を繰り返して呼んだ。揺れの無い、落ち着き払った声であった。今回の件で動揺を見せなかったのは、生まれて間もない哲人を除けば、この父だけだった。
ゆるゆると力の無い動きで、桜子は首だけを回して父を見た。丸い瞳は濁りきって、氷を孕んで天空に広がる薄鼠の雲とよく似ていた。視線の先こそ父に向いているけれど、本当に桜子が見ているものが何であるのかは不明瞭であった。
「来なさい」
が、やはり父は御構い無しで、淡々とそう口を動かした。有無を言わせぬ声だった。桜子の返事を聞くよりも前に廊下を歩き出してしまった父に、経験上何かを言っても仕方ないと知っていたからか、それかそうするという選択肢まで頭が回らなかったか、彼女は至極生気に欠けた動作で腰を上げた。
父の後についていくと、辿り着いたのは父の部屋であった。何度来ても極限まで片付けられている、と桜子は暈けた頭の片隅で感じた。整えられた部屋にいると自然と落ち着くものであるが、父の部屋は整頓されすぎているため、むしろ妙な居心地の悪さを桜子はいつも抱かなくてはならなかった。
部屋に置かれた数少ない家具である文机を挟み、父は黙って桜子と対面していた。彼の前には薄紫色の酒瓶と、硝子で出来た二つのグラスが置かれていた。光に当てると色とりどりの破片を落とすそのグラスにはそれぞれ、朱色の翅を広げる太陽に似た巨大な蛾と、艶かしげな緑色の鱗を持つ長い胴の蛇が描かれていたが、桜子にはそれが何であるのかはわからなかった。父が酒を注ぎ入れると、硝子が描いた蛾と蛇は乱反射してその色を僅かに変えた。
寒風が吹くのも構わず、父は中庭と座敷を隔てる障子を開け放していた。庭から届くぼんやりした光によって輝く蛾のグラスを、父は桜子の方へと押しやった。
だが、桜子はそれを受け取りも拒みもせずにただ座敷に正座していた。グラスの中で揺れる酒の揺れる音もやがて収まり、二人の耳に届くものは冬にも負けないらしいハトーボーの鳴き声だけだった。桜子はまさに心此処に在らずといった様相で、真正面に座る父の顔を見つめ返していた。
「桜子」
父が娘の名を呼んだ。桜子はそこでようやく、二重瞼の下の眼を動かした。「飲むんだ」父が視線だけで指したグラスを、桜子は緩慢な手つきで持った。力の抜けた手は震えており、彼女の右手に収められたグラスの中で酒が危なっかしく揺れた。小刻みに震える水面で、死人とも見紛う桜子の顔が無数に分断されていた。
「飲むんだ」
父はもう一度言った。桜子がその刹那に何を考えたのかを知る者はいない。当の桜子でさえも、一瞬のうちに駆け巡った思考の全てを把握しているはずも無いだろう。
彼女は目を閉じ、グラスの中身を一気に煽った。冬の寒気に冷やされたグラスは氷で出来ているようだった。その中に注がれた酒もまた、遥か北にある氷海を飲み干したように感じられたのに、その実地獄の業火の如き熱を以て桜子の身体を激しく焼いた。
桜子は薄紫の瓶に入ったこの液体を何度か飲んだことはあったが、これほどまでに体内を揺さぶられるのは未知のことであった。燃えるような熱水に口許を押さえながら、桜子は涙を流していた。その涙は次から次へと溢れてきて、やがて嗚咽へと移り変わっていった。産後、彼女は初めて泣いた。
滂沱する桜子の正面で、父は何も言わずに蛇のグラスを傾けていた。慰めることも、言葉をかけることも無かった。彼はただ、甘くて苦い、薄紫色の酒瓶の中身を喉の奥へと流し込んでいた。
桜子の咽び泣く声が響いていく。緑を失った真冬の庭は枯れた草木の匂いで満ちていた。張り詰めた空気は凍りついていたがその一方で、消えることの無い湿り気が、地に落ちた白の塊をだんだんと侵食しているようだった。
◆
カントーでは桜の開花が報じられたが、屋敷にはまだ冷たい空気が満ちていた。
哲人はホウエンの大学に進むため、屋敷を出て一人で暮らすことが決まっていた。高校の卒業式も終わり卯月へ月日が刻々と進む頃、哲人の出発もあと数日というところに迫った。
あれはいらないこれは持ってく、と哲人は連日荷造りに追われていた。捨てられない性分の弟の尻を叩くため、帰省した兄の恭介も彼の仕度を手伝っていた。子供の頃によく読んだ絵本などを逐一持っていくと哲人が宣うため、恭介はその度に弟を宥めなくてはならなかった。
それもようやくひと段落つき、あとは引越し業者に荷物を預けるだけという段階に差し掛かった時だった。すっかり綺麗になった哲人の部屋に父が現れ、自室に来るよう伝えてきた。哲人は戸惑い、忙しいからと一度は断ってみたものの父は折れず、またやるべき片付けなどは恭介が請け負ってしまったがために父を拒む理由もなくなってしまった。哲人は仕方無く、父に言われるままに障子の外に出たのだった。
廊下はとても冷たく、哲人は氷の上を歩いているような気分になっていた。父と話すのは久方ぶりであった。ここ数ヶ月の間父は仕事が忙しいようで、家へ帰ってくるのは毎晩遅くなってからだった。また哲人の方も受験勉強に苦しめられていたり度重なる試験や予備校のため外出が続いていたものだから、顔を突き合わせることすら長いことしていなかったかもしれなかった。とはいえ以前ならば頻繁に話していたというわけでもなく、父との間にいつも訪れる沈黙を想像して哲人は重い気持ちになった。渡り廊下を歩く際に目に入った、長い角に新芽を宿した鹿の片割れにその不安を訴えてみたが、四季折々に移ろう角を持つ鹿は無視を決め込み、足元に群れる雑草を食していた。
父の部屋は幼い頃からの印象そのままに静寂に包まれていた。いや、記憶の奥底に潜ってみると、この静寂はある時を境により深まっているようにも思える。それは哲人がまだ幼い頃に迎えた母の死であったように考えられたが、如何せん薄い記憶では判断のしようも無かった。
哲人はこの部屋をあまり好んではいなかった。一見整頓されており、必要最低限のものすらも無いように感じられるほどに殺風景なのだが、反面、ここに来るとどうにも圧迫される心地がしたのだ。目には見えない何かが部屋一杯を占拠しているようで、哲人はここで父と向き合う度に、恐ろしい怪物に首や腹を締め付けられる幻覚に襲われた。それは部屋の至る所から生まれてくるようにも思えたし、対峙する父そのものが怪物であるようにも思えた。
それは大学進学を控えた今になっても変わることなく、文机の向こう側の父を前にして哲人は身体を縮こまらせていた。せめて兄についてきてもらえば良かった、などと情けない後悔に駆られたが既に遅く、哲人は父親と二人、居心地の悪い湿気が蔓延する部屋に座っていた。
父は哲人の苦悩など知らぬ顔で、薄紫色の酒瓶の蓋を開けていた。酒瓶の隣にちんと並べられている朱塗りの盃は、チェリムの姿が描かれていた。はらはらと散る桜の花弁は金箔によるもので、注がれた酒の中でも尚可愛らしい輝きを放っているのだった。
庭から差し込む光に合わせて瞬く金の花弁に、哲人が満開になった想像上の桜に溺れていると、片方の盃が自分の方に押しやられた。意味が飲み込めずに次の行動を決めかねる哲人を、器の中に踊る桜の精霊が笑って見上げていた。愛嬌のあるその顔に首を捻っていると、やっと父が「飲め」と口を開いた。
「入学祝いだ」
成る程そういうことか、と哲人は恭しく盃を手に取った。酒を飲むのはこれが初めてだったが、不安よりも好奇心の方が余程先立っていた。鼻に近づけると優しい風が鼻腔を突いた。哲人は警戒するように数秒考えていたが、やがてほんの一口、舐めるように盃の中身を咥内に含んだ。
途端、春の訪れに香る花の芽のような、夏に感じる茹る程の熱のような、秋の夜更けに在る酩酊感のような、冬の極寒が孕む棘のような、かといってそれらの何れともつかない感覚が哲人を襲った。それはとても衝撃的なものだったが、同時に彼は何か幸せ夢を見ている気分にもなった。
盃を手に収め、ほやほやと目元を赤くしている哲人の向かいで、父は無表情を崩さぬままに自分の器を空にしていた。身体と頭が温かくなった哲人は、父の前に置かれた薄紫色の酒瓶が酷く美しいものだと思ってやまなかった。奇妙に美味である酒をその身に収め、鎮座しているその瓶は、どこか遠くにある異世界の空を溶かし込んでいるように感じられた。
「酒にはくれぐれも気をつけるように」
たった盃一杯で惚けている哲人に、父も思うところがあったのだろう。厳しい声でそう言い含めたという。加えてもう一言、父は息子に何かを伝えたらしいが、既に意識の幾分かを幻惑の中に旅立たせていた哲人の記憶には残らなかったようである。
そうして家を出た哲人は、その後何度か酔いの所為であらぬ揉め事を引き起こしたり引き起こされたり、巻き込んだりしたのであるが、それらの出来事の原点にあるのが、父と交わした朱塗りの一杯だった。雪解けも大分進み、中庭の草木にはちらほらと緑色が現れ始めた頃だった。寒いくせに奇妙な蒸し暑さの漂うそこで、せっかちなハネッコやポポッコがどこに向かうでも無く浮かんでいた。薄く広がる青空に点在する桃色や黄色に、酔いにうかされた哲人叔父は楽園を見た。
◆
「そのお酒を、明久君が見たことはあるの」
「さぁ。それらしいものは何度か目にしたことがある気もするけれど、本当にそうなのかはわからない。それに、父さんは飲んだことが無いんだ」
鏡子伯母が、桜子伯母が、哲人叔父が彼らの父親と酒を酌み交わしながら眺めた中庭を、今は僕と菜実子が眺めている。それぞれの抱える事情に関係無くいつでも杯を傾けていた祖父と同じように、翠の葉をいっぱいに繁らせた大樹もまた、変わることのない風格で庭の中央に聳えていた。コロボーシの奏でる鈴の音に重なるホーホーの声は朧な月のせいかどこか物哀しげで、何かに啜り泣いているように聞こえた。
「父さんはその酒の味を知らない」
祖父は、僕の父に薄紫の瓶の中身を飲ませることは無かった。酒を飲むこと自体を禁じていたわけではない。むしろ父と杯を交わすのを祖父は好んでいた節すらあり、長期休暇にタマムシの大学から父が帰郷すると、決まって酒を飲ませていたようである。
しかしその酒だけは別だった。父と同席すら際に自分だけ口にすることはあっても、それを父の杯に注ぐことは決して無かった。父とて好奇心というものを人並みに持ち合わせているから、一口味わわせてもらえないかと何くれと無く尋ねてみたものの、祖父の返事はにべもなかった。「お前にこれを飲ませるわけにはいかん」という断定的な口調に父もそれ以上言及する道理を見出せず、花とも果実とも付かない甘やかな香りを放つそれを飲み干す祖父の姿を見ながら、自分は別の酒を飲むというのが親子の決まった図式となっていった。
「菜実子は、無いの」
「無いよ。お父さんから少し聞いたことはあるけど」
「そもそも僕たちが酒を飲む歳になったのも最近のことか」
「私は一緒に飲んだことすら無いもの」
その祖父も晩年には酒を飲むこと叶わず、医者に禁酒を命じられたまま死んでいった。姉の話によると祖父は、「酒が飲みたい」と最期まで訴えていたらしい。水が入った器を姉が渡すと、これじゃないと激昂するため姉はほとほと困り果てていたという。
「巴さんがいれば、また違ったのかもしれないけど」
僕は言いながら杯に酒を注ぐ。底に描かれたハンテールは芳香の中でゆらゆらと泳いでいた。池のアズマオウが跳ねる音がする。墨絵のハンテールが跳躍したのかと酔った頭が早合点をしたが、少々不気味な斑模様の深海魚は未だ酒の海に沈んだままであった。
口に流し込むこの液体を、慣れた味だと感じるようになったのは一体いつのことであっただろう。「おばあちゃんの話」語尾が上がり気味の菜実子の言葉に軽く頷く。酔いに温まられた身体を外側から熱するのは未だかつて消えたことのない屋敷の湿気であり、大樹が屹立する中庭の空気が纏った水っぽさだ。
◆
巴さんは父の母親で、また哲人叔父の母でもある。
祖父が再婚相手の巴さんを連れてきたのは、桜子伯母が十九と十七の時だった。幼い頃に実母が家を出ていったきり、使用人を除けば顔をよく知る肉親は祖父だけであった二人は、どちらかと言えば母となる人というよりも自分たちの友人のような若さであった巴さんを見て、飛び上がるほど驚いた。しかしそれ以上に娘たちを仰天させたのは、実に幼い、新しく弟となった幼児であった。
それが父である。父は巴さんの連れ子で、母親と共に海の向こうからやってきた。巴さんはルネの出身ということだったが、海峡を渡る際に自らの過去を置いてきたらしい彼女の半生は、実の息子である父にすら語られないままであった。祖父は何か知っていたのかもしれないが、祖父とて語らないのだから同じことである。この屋敷に来る以前の父の記憶はほぼ欠落しており、系譜を辿った先にある最も古い情報は、屋敷の門をくぐった時の蒸した空気と繋いだ母の手の柔らかさだった。
巴さんについては、父や叔父よりも二人の伯母の方がよく知っている。僕は彼女を写真で見たことしか無いが、ほっそりと美しい女性という印象を抱いた。それは概ね合っているらしく、伯母たちの言葉によると巴さんはその見た目通り、優しくて儚げな人だったらしい。
巴さんは、穏やかな微笑を常に失わなずに屋敷に在った。気難しい祖父の妻など苦労が絶えないだろうと伯母たちは揃って気を揉んだが、それは杞憂に終わった。新しい伴侶が来たからといって祖父が変わることは無かったが、巴さんはその隣で、いつでも柔らかな笑みを浮かべていた。桜子伯母と鏡子伯母はこの綺麗で優しい母親を好いたし、歳の離れた弟をよく可愛がった。
やがて桜子伯母は嫁に行き、鏡子伯母が旅に出て暫く経ったところで、巴さんは男児を産んだ。その名は言うまでも無く、哲人である。
◆
「姉さんは巴さんに似ているらしい。勿論顔だけで、性格や振る舞いは全然違うのだろうけど」
竹を割ったような性格で表情のよく変わる姉と、写真の中の見果てぬ祖母を重ね合わせて僕は言う。同じことをしたのであろう、菜実子がくすりと口許を緩ませた。
「巴さんのこと、お父さんもよく覚えていないの。何かしてもらったっていうとすぐに伯父さんか、お手伝いさんか、そうじゃなかったらおじいちゃん。だからおばあちゃんって感じがしないんだ、どうにも」
「僕もだ。巴さんは、いつまでも巴さんのままだ」
灰皿に押し付けられ、火の潰えた煙草はぐにゃりと曲がって転がっている。浅い銀の器の中で丸まったその様子はまるで何かの死骸のようで、微かに飛び散った灰は、何か取り返しのつかないことをしてしまった時の感覚を呼び起こした。
それ以上見ている気も起きず、僕は庭へと視線を向けた。大樹を中心に様々な草木が群生するこの中庭は、短い間だけれども巴さんによって整えられていた。というより、今のように多種の植物が持ち込まれたのも巴さんが来てからである。それまでは外側の庭に植木屋を呼ぶことはあっても中庭はほぼ手付かずの状態で、池の魚たちに各人が餌をやる程度だったのだ。
白くて細い体躯の巴さんに庭仕事など務まるだろうか、気分を崩して倒れやしまいかと伯母二人や使用人たちは心配したが、巴さんは存外体力のある者だったようで、その身体のどこからそこまでの精気が湧いて出るのかという勢いで働いた。
巴さんが手入れを始めてから、中庭はそれなりに見るに堪えるものに変わった。雑草が好き勝手に群れるだけだった地面にも色々な草花が持ち込まれ、緑一色の庭に黄色や桃色などの花が咲くようになった。時には祖父に談判し、秋に葉を綺麗に染め上げる木を新しく植えることまでした。しかし彼女の方針として、植物の育成を助けるような薬品を使うことは滅多に無かった。そのため訪れ、棲み着く野生ポケモンが減るということも無く、中庭は大分立派なものになった。
「植物は、心を込めて育てれば必ず応えてくれる」
「何、それ」
「巴さんの口癖だったらしい」
そうして彼女はその言葉の通り、丹精込めて庭の世話を続けていた。今でこそまた雑草も増えてきたが、それでも巴さんが来る前に比べれば、多様な草葉を見ることが出来る。それらの王の如く鎮座する中央の大樹も、雑草で荒れ果てた庭から脱却出来て嬉しいだろう。夜風に揺れる葉が落とす影は広く大きく、幾種類もの草花に闇を乗せていた。
しかしその巴さんも、この庭と関わるようになってそう長くは無いうちに亡くなってしまう。
◆
巴さんが奇妙な死を迎えたのは、哲人叔父がまだ三つになるかならない頃のことだった。
夏日で、数日間雨の降らない状態が続けていた。青い空はどこまでも高く晴れ渡り、欠片ほどの雲もそこには存在していなかった。屋敷はいつにも増して蒸し暑く、また刺すような射光を容赦無く放つ太陽によって着々と燻されていた。
その日、父と叔父は近所に住む親子と共に市民プールへと遊びに行っていた。父の通う幼稚園で同じ組になった少年は活発な性分で、どういうわけか気の合ったらしい、おとなしい子供だった父を連れ回すことを好んだ。彼の母親も気の良いもので、忙しい祖父と屋敷から滅多に出ない巴さんに代わって父兄弟を外に連れ出してくれた。
母の死に関して、父は全てが終わってから知らされた。母親の命日と聞いて僕の父が思い出す記憶は激しい塩素の臭いの充満する市民プールの人混みである。泳ぐ水は客の体温と日光で生ぬるく、プールサイドを歩くとぬるぬると気色の悪い感触が足の裏にあった。友達の母親が着ていたチーゴ柄の水着、彼女が抱えていたのは確か、目一杯の空気を入れられてパンパンに膨らんだラプラス型の浮き袋だ。赤い浮き輪に嵌った弟が流れていくのを、友達は笑いながら追いかけていた。歓声と水の跳ねる音で賑わう中、打ち寄せる人口波に揉まれて空を見上げると、ケンホロウが悠々と飛んでいくのが見えた。弟が自分を呼んでいる。友達親子も。しかしどうしてか父は空を見たままの姿勢から動くことが出来ず、薬品臭いプールの中に立ち尽くしていた。
旱天に飛翔する大鳥の姿に父が何を見たのかは父自身にもわからない。
巴さんは、屋敷からやや離れた所にある水路で死んでいた。水死ということだったが柵の中へ故意に入らなければ落ちることも無いそこに、何故巴さんがいたのかは不明である。揉み合った痕跡も無く、自殺するような理由も見当たらない。日頃屋敷を空けない巴さんが、その日にどうして水路へ向かったのかも謎であった。
苔が生える、湿った水辺に倒れていた巴さんの周りには、数匹のベトベターが群れていた。平素水路の周りで見ることのないそのポケモンたちの所為か、辺りは鼻を摘みたくなるような悪臭に包まれていた。ベトベターは軟体の身体を這わすようにして、びっしりと生い茂った苔の上を行き来していた。腐臭をいち早く察知したのではないかという声が警察の一人から上がったが、その正否は誰にも判別つかなかった。
巴さんは青白い身体を横たえ、眠るように亡くなっていた。猛暑の中行われた母親の葬式で、父は暑さに眩む目を開けているのが精一杯だった。涙は出なかった。母の死への実感が湧かなかったという。そうしてそれは今でも変わっていない。
泣いている姉二人と、退屈してぐずりだした弟に挟まれ、父は黒の半ズボンから覗く足を無作法に揺り動かしていた。汗で湿った膝から顔を上げ、彼は父親の姿を見た。いつもと変わらぬ仏頂面には汗の一つも無く、ただ、睨むようにして、巴さんの遺影と正対しているのだった。
◆
柱時計の鐘が二度鳴った。地響きのようなそれに満ちる屋敷は物音一つせず、誰もが深い夢の中に落ちてしまっていることを暗に示していた。気づけばホーホーやコロボーシたちの鳴き声すらも消えていて、僕と菜実子を包むのは僅かな鐘の残響を除けば静寂のみだった。
草木も眠る丑三つ刻というが、中庭のそれらも確かに寝ているように見えた。しかし反面、風に葉擦れの音を立てる大樹だけはまだ意識を残したままで、我々のことを眈々と見張っているかのようだ。それはまるで今は亡きはずの祖父の威風にも酷似していて、知らず識らずのうちに後方の祭壇から目の前の大樹へと移り変わったのではないかと錯覚に陥った。
「そういえば、彩音さんは来なかったね」
言葉と共に吐かれた菜実子の息は、酒の甘い匂いを含んでいた。
彩音さんとは僕たちの従姉妹で、桜子伯母の娘である。血は繋がっておらず、伯母がこの屋敷で流産を経て六年後、ジョウトの養護施設から引き取ったと聞いている。桜子伯母と父たち兄弟の歳が離れているため、僕や菜実子と彩音さんもまた歳に開きがあった。
彩音さんには久しく会っていない。彼女は何時からか、ここに訪れることをやめてしまったのだ。そもそも菜実子や大樹、親戚たちと会う機会など祖父の屋敷に集まる以外で滅多に無いのだから、ここに来ないのならば態々僕が年上の従姉妹と会う理由も存在しなかった。
「ポケウッドの衣装だっけ、仕事。忙しいのかな」
「そりゃあ、僕みたいな暇な大学生と彩音さんは違うだろうけど。でも、多分」
「多分?」
「彩音さんはここが嫌いなんだ」
「嫌いって」
「気味の悪い夢を見るから」
桜子伯母によると、彩音さんは昔から、この場所を怖がっていた。いつ見ても怒っているような祖父や、古風な家の感じがそう思わせている面もあったのだろうが、それ以上に彼女の足を遠のかせたのは、ここで見る夢であった。
彩音さんは屋敷を訪れると、いつも同じ夢を見るという。特段悪夢というわけではないが、毎度必ず見ることと、どうにも不安になる雰囲気をその夢が持っていたことから、次第に恐怖心を抱くようになったのだ。結果彼女はトレーナー修行の旅に出たのをきっかけに、ここに来るのをやめてしまった。
「何、夢って」
「知らないの」
「知らないよ」
「ここに来ると決まってみる夢がある」
「そんなもの無いもの」
「僕はさっきも見たんだ」
彩音さんの話に、僕は思い当たる節があった。この屋敷に来ると見る夢。それと同じものを屋敷の外で見たことは無い。夜に布団で寝ている時、ささくれた畳に転がって惰眠を貪っている時、何をするでも無く天井の木目を無為に数えている時。屋敷で眠ると僕は必ずその夢を見た。そうして夢から覚めると、有無を言わせぬ倦怠感と疲労感、また全身を纏う脂汗に襲われる。どこもかしかも汗だくのその状態は、まるで水の中から這い上がってきたばかりのようであった。
毎度毎度、欠けることのない瞼の裏に広がる情景。不安を与える空気。それと恐らく同じものを、僕もまた味わっていた。
そうわかった時、僕はどこか安堵した。奇妙な夢を見るのが自分だけでないというのなら、きっと悪戯なポケモンでも棲み着いているのだろうと思うことが出来たからだ。エスパータイプやゴーストタイプのポケモンの中には、他者に悪夢を見させる技を操る者もいる。フローゼルの親子のように、ここに住んでいるポケモンたちの仕業であろうと考えたのだ。
しかし、そうでは無いと菜実子は言った。
「菜実子は、見ないの」
「見ないし、知らない。夢だなんて」
「いつも見るんだ」
「どんな夢」
そう、菜実子が尋ねた時だった。赤らんだ唇から漏れたその問いに、僕は乾いた口を開きかけた。しかし僕の声が菜実子の鼓膜を揺らすよりも先に、僕たちの後ろ、祖父の祭壇の方で、何かが動く気配と物音があった。
僕と菜実子は飛び上がらんばかりに驚き、一瞬の間を置いてそちらを振り返った。
座敷の暗闇に目を鳴らす僕たちに、気配の主が声を発した。
「御免下さい。酒を届けに参りました」
◆
夢の中の僕は薄暗い道を歩いている。その道が何処なのか、また何処から歩いてきたのか、そして何処へ向かっているのかは全く以てわからない。かなり長い距離を進んできたようにも思えるし、今しがた出発したばかりのようにも思える。ひどく疲れているようにも感じられるし、疲労を知らずに永遠に歩き続けられるようにも感じられる。どのくらい続いているのかも不明な道を、僕は唯々歩いているのだ。
その道は堅い壁に覆われている。壁の向こうがどうなっているのかは知らない。何で出来ているのかわからないが、つるりと平らな壁は三百六十度を囲っており、道と外界を隔てている。とてもじゃないがその壁は破れそうになく、パイプ状の道に閉じ込められた僕は土管の中にいるような錯覚にしばしば陥る。
道の先は見えない。通ってきたはずの後方も見えない。光が存在しない暗闇というよりは、僕の視力が働いていないのだと思う。ともすれば、歩いている自分の姿さえも見失ってしまいそうだ。
僕の足音に混じって聞こえる音がある。何の音なのだろう。何かが迫っているような音だ。地面の下で何者かが這うように動いたならば、こういう音がするかもしれない。轟音と呼ぶには余りに遠すぎるが、恐らく近くで聞けばかなりのものなのだろう。何かが勢いよく動き続けるその音は、静寂の中で僕の耳に流れ込む。
道の中は奇妙な涼しさを常に浮かべている。空気に多分の水が含まれているのはわかったが、どういうことか蒸し暑さは感じない。居心地の良い川辺などを歩いている気分だ。ひんやりとした冷たさは全身に纏わりつき、目を瞑るとまるで水底に身体を沈めているようである。
僕は歩き続けている。右足と左足をひたすら交互に動かしている。何故そうしているのか、その理由を僕は忘れてしまった。誰かに会いにいくのだと、そして誰かに何かを届けにいくという目的があったように思う。しかしそれも定かでない。ただ、海の中を漂い続ける難破船の如く、僕は道を進むのである。
壁の向こう側から、或いは道の終着点から、誰かが呼ぶ声がする。
おい。
おおい。
声のする方に進み続けても、僕は一向にそこへ辿り着けない。どれだけ歩いたところで道はずっと続くのだから、僕は声の主に会うことは叶わない。
声は呼び続けている。
おおい。おおい。おおい、と。
壁に覆われた道に深く響き渡る低い声は、身の毛がよだつほどの恐ろしさを持っているくせに、どこか哀しげである。何か僕には想像することも不可能である、巨大な存在の慟哭のようだ。
声は誰かを呼んでいる。それは僕の名では無いと思う。知っている誰かの名前だった気がするが、それが誰かはわからない。
それでも、この言葉だけはわかるのだ。
声は言う。
声は叫ぶ。
先の見えない道の終わりで、声はこうやって呼んでいる。
江角、と。
◆
酒屋であると名乗ったその人は、何故だか顔を白い布で覆い隠していた。風で微にはためくその布には、円の中に点を一つ、眼玉を模したような記号が描かれていた。墨をつけた筆で描かれたそれは何だか動いている風に見えて、アンノーンを一匹布の中に閉じ込めているようであった。
たった今来たところであるという酒屋は、暗闇に物も言わず佇んでいた。足袋に包まれた両足から黒い影が伸びていることがむしろ不自然で、化物の類であると説明された方がよっぽど納得出来たかもしれない。
「重雄様のことは、誠にご愁傷様でございます」
仰々しく礼をする酒屋の、紺色の着物から覗く骨張った手は男のものと見て取れた。しかし夜の空気によく溶ける、耳障りの良い声は女らしかった。布越しの顔を見ることは出来ず、どこか機械めいた振る舞いと妖怪じみた雰囲気を持つその姿に、僕と菜実子はどう接して良いかわからず顔を見合わせた。
「本日は御注文いただきました品をお届けに参りまして」
「ま、待ってくださいよ。急に言われてもわかりませんし、そもそもこの時間ですよ」
手から提げていた冷却箱を畳に降ろした酒屋に慌てて言葉を発する。単に僕たちが聞いていないだけである可能性も低くないが、しかし真夜中に宅配にくる酒屋というのは素直に受け入れられるものではなかった。また、姉などが買い出しに行っていたのだから、わざわざ宅配を頼むというのもおかしな話であった。
狼狽える僕と菜実子から十歩ほど離れた場所にいる酒屋は、不可解そうに首を傾げた。「そう言われましても」何かを喋る度に白の布がひらひらと揺れる。揺れが作る凹凸は須臾にして作り変えられ、アンノーンの如き眼玉が絶えず動いているようである。
しかしその文字の表すところを僕は知り得ない。
「お電話をいただいたのですが」
「何時の話ですか」
「今日の朝方ですよ。この時間にいつものものを持ってこい、と」
「いつもの、とは」
「重雄様には昔から懇意にしていただいておりまして。多様な酒をお買い上げいただいていたのですが、その中でも決まって御注文なさるものがあったのです」
「祖父がですか」
「ええ。この頃体調を崩されたということで、此方の門をくぐることもめっきり無くなったのですが。お医者様に禁酒でも命じられたのかと勘繰っていたのですが、朝方に訃報の御連絡をいただきまして」
「何故、屋敷の中にいたのです」
「重雄様は私に鍵をお預けになったのですよ。勿論最初は私も驚いて、お返ししようと思ったのですが、届ける毎に玄関までいかなくてはならないのが不便だとおっしゃったものですから、もう暫くのことそうしておりました」
「直接持ってこいと祖父が言ったのですか」
「ええ。何時もこの部屋に伺ってお渡しいたしました」
酒屋が懐から取り出した銀の鍵が、塀の向こうの街灯の光を反射して鋭く輝いた。この者が嘘をついているとは思えなかったが、腹の底どころか表情すら見て取れない事実は、喉元をひやりとさせるような不安を僕に与えた。
祖父が酒屋に酒の宅配を頼んでいたなど、況してや鍵まで渡していたなどという話は未だ嘗て聞いたこともない。もっとも僕の姉が屋敷に住み込むようになった時点では既に、祖父の飲酒は禁じられていたのだから、雇っていた家政婦の誰かが伝えなくては知る由も無いと言えばそうである。買い物になど繰り出さない祖父が、どうやって酒を常備していたのかも酒屋の宅配があったからというなら説明がつく。鍵を渡していたのも合理的ではあるし、防犯意識等の問題があるといってもこの酒屋がそのような、俗世間めいた事をするとは良くも悪くも思えなかった。
蒸した座敷でようやく冷えてきた頭でそんなことを考えると、背中を一筋、冷たい汗が伝っていくのがわかった。僕の隣では菜実子が困惑と疑惑を丸顔に浮かべ、すべやかな指を無意味に組み合わせたりしていた。
「その電話というのは、誰からのものでしたか」
「さぁ、お名前を伺おうとしたら切れてしまったのですよ」
「声の感じは」
「何とも言えませんな。何分電話ですから、成人した男性の声であったのは確かでしたが」
背にした中庭から葉の匂いがする。いくらシンオウ夜とはいえ夏の道を、しかも冷却箱を抱えてきたというのに、酒屋は汗の一つも掻いていなかった。袖口から伸びる手首は陶器のように白く滑らかで、よく出来た機巧人形かとも思えた。首の後ろで束ねられた黒髪は背中ほどに長く、穏やかに流れる小川を連想させた。
僕はそれ以上の質問が言葉とならず、菜実子と共に立ち尽くす他無かった。恐らく待ってくれていたのであろう酒屋は、僕たちのそんな様子に「それでは御注文のお品ですが」と今度こそ箱の蓋に手をかけた。
開いた箱の中から白の煙がもくもくと立ち昇る。無機質な銀の冷却箱には細かな氷が詰められていた。
「いつものを、一本。よく冷やしてくるようにとのことでしたので」
「あの、お代は」
「結構ですよ」
以前にまとめてお支払いいただきましたから。やや高めである酒屋の声が、布の向こうから僕の耳元を擽った。
酒屋が箱から取り出した酒を見て、僕たちは言葉を失った。
氷に埋れていたその酒は、薄紫色の小瓶に入っていた。それは様々な話の中に登場する、祖父が好んで飲んでいたという酒であった。酒屋の白い手はまるで赤ん坊を抱きかかえる時のように、優しく、酒瓶を扱っていた。
「では、私はこれで失礼致します」
酒瓶に目を奪われていた僕の意識を酒屋の声が引き戻した。ぴんと伸びた背筋を曲げて一礼し、立ち去ろうとする酒屋を引き留めなくてはならない気もしたが、何を言えばよいのか判別がつかなかった。
そのまま酒屋は障子の向こうに行ってしまいそうであったが、「おや」と不意に呟いて僕と菜実子を振り返った。
「ひとつ、お聞きしてよろしいでしょうか」
「何ですか」
「重雄様が体調を崩されてから、何か新しいポケモンを住まわせ始めましたか」
その質問に僕は答えることが出来なかった。野生ポケモンは勝手に出入りしているし、祖父の行動はほとんどわからない。姉は何も言っていないはずだが、敢えて言うことでも無かったのかもしれない。
口籠った僕に、酒屋は数秒動かず考え込んでいたようだが、やがて「いや、私の気のせいでしょう」と話を打ち切った。「以前は聞こえなかった鳴き声がしたようでしたから」
その意味を問い返そうと口を開きかけた時には既に、酒屋の姿はそこに無かった。風が吹くよりも気づかぬうちに帰ったらしい酒屋がいた場所には薄闇と湿気、そしてほんの僅かな残り気配しか存在していない。頭の中で、白の布に浮かぶ大きな一つ目がぎょろりとこちらを睨みつけた。
縁側に取り残されたのは立ち尽くす僕と菜実子、そして間に置かれた薄紫の酒瓶だった。畳にそっと置かれたその酒瓶は、何も無い世界に一輪咲いた菫のようであり、また、祖父の隣に寄り添う写真の中の巴さんのようでもあった。
僕も菜実子も、佇んだまま動かない。背中に感じるのは中庭の大樹が揺れる音と、生温く空気を掻き回す風だった。
◆
祖父の元妻が屋敷を出ていった時の話である。
彼女は祖父がイッシュの鉱山開発に出稼ぎへ赴いていた際に出会った女で、貿易商の父を持つハイカラな娘であった。二人の間にどのような経緯があったのかは不明だが、ともかく二人は結婚し、桜子と鏡子という娘を授かった。娘たちが生まれて間もなく祖父が伸之助の工場を売って事業を始めることとなり、その際家族揃ってシンオウに移り住んだ。
シンオウの屋敷に住むようになってからというもの、彼女は気掛かりなことがあった。それは祖父の飲酒に関する問題であり、また謎でもあった。
自分の旦那が元来酒好きな方で、出会った当初よりよく飲んでいたことは知っていたが、屋敷に来てからの祖父は酒の飲み方が少し変わったのだ。何か粗相を起こしたり、厄介ごとを招くといったことではない。ただ、彼女の知らぬ酒を一人で飲むようになった。
その酒は薄紫色の瓶に入っていた。好奇心に駆られた彼女はその中身を飲ませてくれるよう頼んだが、祖父は断固として認めなかった。そんなことが何度か続いたある時、彼女が祖父の目を盗んでその酒を飲もうとしたところを祖父が見つけてしまい大喧嘩となった。
何日にも渡った悶着の末、彼女は屋敷を去ってしまった。取り残された祖父は何も言わなかったし、幼い二人の娘も今ひとつ事態を飲み込めずにいた。そのまま時間は流れ、彼女の面影は屋敷にほとんど残っていない。祖父は彼女の話題を出すことも無かったし、桜子伯母や鏡子伯母も記憶に薄い実母に対しての思慕は驚く程に欠落している。
何が彼女をそれほどまでに掻き立てたのか、彼女の天性の性格がそうさせたか、或いはそうではないのか、それはわからないままだ。
◆
その酒が、今、僕の目の前にある。
酒屋が置いていったそれは冷却箱と外気との温度差で、薄紫の瓶の表面には丸い水滴がびっしりと張り付いていた。結露の一部は既に流れ落ち、歪んだ筋を描いて畳を濡らして輪染みを作った。針金で固定された陶製の栓は、何やら重大な秘密を守っているかのように閉じられていた。
まさに話題としていたものの突如なる登場に、僕も菜実子もどうするべきかを図りかねた。僕たちの間で、一本の酒瓶は静かに座作している。薄暗闇に浮かぶ透き通った紫の中で、無色透明の液体がごく僅かに揺れていた。
伝聞した酒は想像よりも呆気のない見た目だった。謎多き祖父にまつわる話に頻出する存在であるこの酒に、僕は知らず識らずに幻想的なイメージを抱いていたのかもしれないが、実際蓋を開けてしまえばなんてことの無いただの小さな瓶であった。黄昏に暮れる空を溶かし込んだような色は確かに美しかったが、祖父が毎晩のように飲み、そして時には人に分けるのを惜しむほどのものとは思えなかった。
「どうしようか、これ」
ようやく菜実子が口を開いた。内股気味の素足が、戸惑うように畳を擦る。丸っこい指はケムッソの腹を連想させた。「誰かが注文したのかな」
「でも誰が。そんな話は聞いてないよ」
「お父さんとか叔父さんとか。伯母さんかもしれないし。酔って忘れちゃったんじゃないかな」
「それにしても、『いつもの』を父さんたちが知ってるとも思えない」
どれだけ考えたところで、酒屋に電話をかけた者を特定することは不可能であるように思われた。屋敷に寝ている全員を叩き起こして問い詰め、また祖父の関係者や弔問客を片端から当たるなど、現実に行動を起こせば、もしかしたら見つかるのかもしれない。しかしそのようなことをしたところでわかるとは思えなかったし、それにこの瓶を目にしてから、根拠の無い不安が頭の中に渦巻いていた。詮索してはいけないのだと思った。知ってはならないことなのかもしれない、という感覚が胸の奥底から湧き上がった。
どうすれば良いのかわからなかった。そもそもこの中身が、祖父の好んだ酒であるという保証もない。瓶の見た目がよく似ているだけで他の酒なのかもしれないし、単なる水であるかもしれないのだ。それに考えてみれば、薄紫色の瓶というのも僕にとっては人から伝え聞いた話でしかなく、これぞ何であるという確証などどこにも存在していなかった。
普通に考えるのならば余計な干渉をせず、明朝目を覚ましてくる伯母たちに尋ねるのが最も現実的な選択であろう。事実僕はそうするつもりであり、それ以外の選択肢など思いつかなかった。
しかし菜実子は違ったようである。彼女の言葉に反対しなかった僕も本心ではそうでなかったのかもしれない。蒸すような暑さか酔った頭か、はたまたこの薄紫を纏った小さな海か、何が僕たちにそうさせたのかは不明である。ともかく菜実子は、足元の酒瓶に暫く視線を落とした後、ぽつりと唇を動かしたのだった。
「ねえ明久君」
「なに」
「飲んでみようか」
僕は返事らしい返事は何一つしなかったが、しゃがみ込んで酒瓶を手に取る菜実子を止めることもしなかった。丸い背中が屈められて、寝間着の薄い生地越しに肩甲骨の膨らみが現れた。彼女のうなじに、肩ほどの長さである黒髪がかかって覚束ない動きをした。
菜実子の手の中で酒瓶が鈍く光る。結露に濡れた薄紫はぬらぬらという輝きを幽かに放っており、僕は何となくその光景が夢で見た何某かに似ているような心地になった。
僕たちは縁側に戻り、先ほどの位置に腰掛けた。酒屋が来て、そして帰ってからも変わることなく中庭は湿った緑の臭いを漂わせていたし、大樹は重々しい風格を醸し出していた。更けた夜の草木の間にはゴーストポケモンすらも現れず、ただただ風のみが通り過ぎていく。菜実子が栓を開ける、小気味の良い音が僕たちの周囲にある湿気を少しばかり軽くした。
菜実子が瓶を鼻に近づけ数度呼吸を繰り返した。目をぱちぱちさせて何とも言えぬ表情になった彼女は首を捻りながら僕にも近づけてきたが、同じように臭いを嗅いだ僕もまた、眉間に皺を寄せてしまった。
栓の抜かれた硝子の穴から漏れるそれが良い匂いなのか、不快なものなのか、今ひとつの判断がつかなかった。似ているというわけではないが香水のようなもので、好いものにも臭いものにも受け取れるあの感覚を思い出させた。香り立つ花のそれにも似ていたし、甘ったるい果実のそれにも近いようだった。高校の頃付き合っていた彼女のポケモンだった、ロゼリアの振りまく匂いはこんな印象だったかもしれない。長らく頭の奥から引き出されることのなかったその存在を、持ち主であった癖毛の少女と共に、僕は薄紫色の瓶に幻視した。
しかしどちらにせよ、酒らしい臭いには思えなかった。菜実子もそう感じたらしく「何で出来てるんだろう」と訝しむように呟いたが、思い当たる節は全く無かった。僕たちは数秒、知らぬ世界の風を閉じ込めているかのような瓶を挟んで向かい合っていた。
腰かけた縁側は湿り気を帯びていた。そっと瓶を傾けた菜実子が杯に酒を注ぐと、澄んだ液体がとくとくと流れ落ちた。先程嗅いだ臭いが一気に広がり、むせ返るような思いだった。それはソノオの花畑に降り立った時の感覚に似通っていたが、中庭の湿気の所為で、ノモセの湿原に放り出されたかの如き不快感も存在していた。そのどちらにも、祖父と共に行ったことを想起した。大湿原にある広葉樹に樹液が溜まっており、その湿気た臭いと甘ったるさに思わず顔をしかめた僕に、祖父は呆れたような視線を向けていた。
菜実子から杯を受け取った。注がれた酒はやはり色味も濁りも無く、底を泳ぐハンテールの姿がよく見えた。横目で菜実子の手の中を見ると、白く柔らかな右手に乗せられた杯の深海に、桃色の魚が潜んでいるのを捉えることが出来た。
二匹の深海魚をそれぞれ掌中に収め、僕と菜実子はしばし無言でいた。水底に沈んだまま動かぬ魚たちは嵐の通過を待っているようであり、また、何か恐ろしい敵から身を隠しているようでもあった。海は彼らを包み込み、畏怖すべき存在に怯える者たちを守っている。その海の外にいる僕は、自分を取り巻くものが蒸した空気のみである現状がひどく頼りなく思った。
聞こえるはずの無い、粒子の流れる音を聞いている錯覚に陥った。菜実子がこちらを見た。僕は杯に視線を落とした。口元まで持ち上げると酒が揺らめいて、グロテスクな形状を刹那に成して零れそうになった。名状し難い幽香がより一層の激しさを持ち、鼻腔の奥底まで絡みついた。
杯の縁に口をつける。陶器のすべすべした感触が唇に貼りついた。「いただきます」菜実子の囁きが耳を掠った。いただきます。
一口飲み込んだ途端、喉を内側から抉られるような嫌悪感に襲われた。口の中が焼かれたようであった。胃や食道ごと噴き出したくなる嘔吐感と、全身の血液が心臓に押し寄せてくる圧迫感を一度に味わった。何が起こったのかわからない僕の視界で、白と黒の明滅を只管繰り返していた。
怒濤のような気持ちの悪さに咳き込む僕を、菜実子が「どうしたの」と不安げに見つめた。彼女は火照った頬を除けばごく普通の様子であり、中身が半分ほど減った杯を持つ手にも何ら変化は見当たらなかった。無意識のうちに杯を握り締めていたらしい僕の手から零れた酒が安物の寝間着を濡らしていた。
「大丈夫、明久君」
「いや。気管に入ったのかもしれない」
「おいしいまずいのか、よくわからない味がするよ」
言いながら、菜実子は杯を斜めにしている。白い喉が形を変えて、あの液体が彼女の身体へ流れ込んでいく。
「口を漱いでくる」僕は縁側から立ち上がった。見上げる菜実子の太腿の隣に、ハンテールの杯が乱雑に置かれて転がった。僕が中身を零してしまった所為で空になった器から優しい海はすっかり失われ、外界に打ち捨てられたハンテールは干からびて死んでしまった水棲生物そのものであった。
「足元に気を付けてね」という、菜実子の声は酔いからか少し上擦っていた。右手と手首と足の付け根、酒を零した箇所が炙られるような痛みを訴えた。
◆
父と祖父が向かい合っている。
夏の午後だった。入道雲が巨人の腹のように膨らんでいた。その遥か上空で太陽が輝いていた。中庭の草木はどこからか集まってきた露に濡れており、丸い雫は日光に当たる度に眩い輝きを放っていた。
祖父の部屋は不思議な涼しさに満ちていた。屋敷のどこにいても感じる蒸し暑さを、ここでは覚えないのが父にとって違和感だった。同年の正月にもこの部屋には訪れたはずだが、その時にどうであったかは思い出すことが出来なかった。
テッカニンのじわじわという声が庭から響いていた。幾重もの混声になったそれは鳴り止むこと無く、汗の引いて冷たくなった父の耳を煩わせるのだった。平素タマムシの大学で聞く声とは違っていた。こちらの方がより夏という監獄に押し込められている心地になると父は思った。
祖父は父の真向かいに鎮座していた。二人を隔てる文机が、父にとっては刑務所の外壁よりも堅牢なものに感じられた。血の繋がらない父親と馴れ合った記憶など存在しないが、しかしこれ程までに彼と自分が遠いものに思えたこともまた初めてであった。
父は大学院に進みたいという旨を伝えに来ていた。博士課程は教授からも強く勧められていたし、そうするだけの意欲を父は持っていた。研究したいことは山ほどあった。
背筋を伸ばして話す父の言葉を、祖父は黙って聞いていた。その表情からは是も、また非も読み取ることが不可能で、息子の申し出を彼がどう考えているかを推し量ることは誰に出来る芸当でもなかった。
父が話し終えても尚、祖父は声を発しなかった。庭からの音が反響するため、父は四方八方からテッカニンの声に取り囲まれていた。じわじわというその声は果たして本当に蝉たちの鳴き声なのか、本当は自分を見張っている怪物の息遣いなのではないか、或いは逃れられぬ暗殺者が今まさに忍び寄ってきている気配なのではないか、などという非現実的な妄想が彼の頭に浮かんでは消えた。
文机には、色の無い硝子で出来たグラスが二つ並べられていた。その隣に置かれていたのは、やはり二つの酒瓶だった。
片方の酒瓶は大吟醸酒のそれであり、相当な上物であることが見て取れた。達筆な墨汁が躍る付紙には雲を突き破って翔るギャラドスが描かれていた。獰猛な紅は鬼の血よりも地獄の釜の炎よりも濃く、向かう先にいるであろう天照神すらをも喰らい尽くすかの如き凄烈さであった。
その陰に隠れるように立っているのは、薄紫色をした酒瓶だった。
祖父は大吟醸を片方のグラスに注ぎ、もう片方には薄紫の中身を注いだ。無色透明の器に入れられたそれは一見見分けがつかず、どちらがどちらなのか判別し難かった。
「飲むといい」
しかし父は、祖父のその言葉と共に自分の側へと押しやられたグラスの中身が、どちらの酒なのかを理解していた。
グラスの水面に映る父の顔は青く、自らが何に恐怖しているのかわからぬことが恐怖だった。
◆
何度か嗽をしても、口から喉にかけての違和感は拭いきれなかった。手足に酒を零したところも水で軽く濯いでみたのだが鼻に纏わりつくような芳香はとれないし、皮膚を弱く焦がす熱っぽさも未だ残っているように感じられた。口の中がぴりぴりと痺れる心地だった。
洗面所の空気はひんやりとしていて、蛍光灯の白い光が無機質な清潔さを演出している。消毒薬の匂いがした。隣接する風呂場から漂ってくるものだと思われた。
蛇口から水が漏れていた。限界までハンドルを回してもそれは収まらず、白のシンクに一定の間隔で水滴が打ちつけられては音を立てた。落ちた雫は傾斜を流れ、排水口へと消えていった。パッキンの不調ならば今はどうすることも出来ないので、明日誰かに伝えることにした。
暗さに覆われた視界で進んだ廊下には、僕の足音しか響いていなかった。暑さで起きてしまうような夜であるけれど、誰もが深く眠っているようだった。渡り廊下を歩きながらオドシシたちの様子を見遣ったが、薄闇の中からは草木の陰と幾つかの塊しか見出せず、寝息の一つも聞こえてこない。それ以上目を凝らす気も起きず、僕は祭壇のある座敷へと戻る足を再び動かした。
「菜実子か」
座敷と廊下の間にある縁を踏んだ途端、祭壇の前に佇む影が目に入った。それが何であるかを一瞬図りかねたのと、鈍い動きで揺らめいたのとで、僕の心臓は一瞬高く跳ね上がった。しかしすぐにそれは菜実子であるとわかった僕は肩の力を抜き、座敷の中に踏み入った。
一歩進むと、先程までよりも一層激しくなった湿気がある種の熱量を持って襲いかかってくるように感じた。絡みつく蒸し暑さに吐き気がした。「明久君」祭壇を見つめていた菜実子が首を動かしてこちらを向く。「おかえり」
「どうしたの。こんなところに立って」
「何か聞こえる気がして」
「聞こえるって」
「明久君は聞こえないの」
菜実子は訝しむような眼で僕を見た。何が聞こえるの、と尋ねると「何かが通る音」そんな答えが返ってきた。
「ざーっ、って。あと、さらさら、っていうのも。それと、何かが落ちていく感じの音もした」
菜実子の説明は正鵠を得ないものであったが、僕はそれに覚えがあるような気がした。彼女が聞こえるという音はわからないけれど、それをどこか別の場所で聞いたことがある風な感覚に囚われた。別の場所ですら無いようにも思った。
何かが通る音。落ちていく感じの音。
通り過ぎていくものは、果たして何であるのか。
「今は聞こえないや。明久君が来るまでしてたんだけど」
「どこから聞こえてたの」
そう聞くと、菜実子は黙って前方を指差した。祖父の祭壇であった。
「なるほど。きっと僕たちが酒盛りしてるのが羨ましくなったに違いない」
酒の味もわからないくせに、自分を差し置いて何をやってるんだ、ってさ。戯けて言うと、菜実子はくすりと微笑んだ。形の良い耳にかかる黒の髪が、彼女の笑みに合わせて頼りなげに揺れた。
「じゃあ、おじいちゃんも一緒に飲もうか」
「コップが無い。父さんたちが持っていったかな」
「台所から取ってこようか」
「いや。僕の使ってたのでいいだろう。せっかく届けてくれたんだから、あの酒にすべきなのだろうし」
「それはそうね」
言いながら菜実子が身体の向きを変えて縁側に足を踏み出した。酒瓶と杯を取りに行った彼女の後ろ髪を見、僕は祭壇に視線を向けた。暗がりの中の祖父の遺影はやはり顰めっ面で、手持ち無沙汰に佇むだけの僕を強く睨みつけていた。
「ひッ」
すると、障子の外に出た菜実子の悲鳴が聞こえた。慌ててそちらに目を戻すと、菜実子がやや丸い身体をよろめかせ、柱にしがみ付いているのが見えた。
「どうした」
「池、池が」
声を震わせてそう言った菜実子の指がさす方に僕は顔を向ける。中庭の池を指していることはわかったが、何しろ暗いのと、大樹の影になっているせいでよく見えなかった。しかし細めた眼で暫く凝視してみると、池の中が何やら蠢動しているような光景がそこにあった。
腰を抜かしたらしく、崩れ落ちた菜実子を背中に僕は庭に出た。縁側から降りると土の冷たさが足の裏に伝わった。しかしそれ以外はじっとりと暑く、前髪の下にある額が汗を掻いた。
静寂であったはずの庭に、ぐちゃぐちゃという音が低く響いていた。むっとするような生臭さが立ち込めていた。飲んだ酒が腹の底からせり上がってきそうになるのを押さえつけながら、その臭いの元へと歩を進めると、大樹と隣り合う池へと着いた。
「水が無い」
思わず呟いた僕の後ろで、菜実子が息を呑む音がした。
平素冷たい水が揺蕩うそこは干上がっており、水底の岩肌を露わにしていた。トサキントとアズマオウが球体のような腹を仰向けにして、びちびちという音と共にのたうちまわっていた。まだ湿り気を帯びている鱗が不気味に輝いている。青白い血管が浮かぶ腹に緋色の斑点を散らした金魚は、厚い唇を開けたり閉じたりと苦しげであった。
鮮麗の象徴たる彼らが、鰭を振り乱して辛苦を訴える様子はとても醜く、また見るに堪えないものだった。あたかも地獄絵図であるようなこの状況をどうしたものか、と途方に暮れた頭の中に思い描かれるものがあった。それを僕は実際に目にしたことが無いくせに、ひどく鮮明に夢想出来る。まるで今まさに目の前で体現されているかの如きその一齣は、吐き気を催すこの臭いと共に僕を包み込むのだ。
◆
伸之助の蒐集癖は昔からのものであったが、父総次郎の死後、それは益々激しくなって歯止めが利かなくなっていった。その悪化が何をきっかけとするものなのかははっきりとはわからないが、慕っていた父親の死と折り重なるように彼を襲った、彼の妻の病死であったと言われている。一人息子であった祖父重雄が家を出たきり戻る気配も無く、何処か遠い場所に行ってしまったことも関係しているのかもしれない。屋敷に一人取り残された伸之助は、まるでその淋しさを蒐集によって埋めるかのように、泥沼の中へと潜り込んでいった。
彼の集めたものは多様である。壺や皿、根付などの骨董品から始まり、楽器や絵画などにも手を出した。伸之助に見る目など無かったものだからそれらの価値は天上から地の底までに差があり、何もかもが入り乱れている有様であった。伸之助は奇妙な逸話のある品を好んだものだから、やれ額縁の中のレントラーが夜な夜な抜け出して人を喰らうだとか、やれ皮を剥がれたニャースの霊が三味線で恨み節を奏でるだとか、やれ海の向こうから買い取った洋燈に憑いた悪霊の蒼い炎は人の寿命を燃やし尽くすのだとか、そんな噂が使用人を中心に流れていた。
人々を君悪がらせたのは何も骨董品だけでなく、同じく伸之助の蒐集の対象であったポケモンたちもそうだった。伸之助は珍しいポケモンを集めていたのだが、それらもまた、ただのポケモンでは無いのだと実しやかに囁かれていた。冥府へと繋がる結い紐を持つニンフィア、人骨を被り人語を話すガラガラ、百面相のナッシー。天を泳ぐホエルオーは満天の海に蕩けて誰にも見えない。屋敷に響くピジョットの咆哮は、頭がエテボース、四肢がウィンディ、ヒヒダルマの胴を持ち、ミロカロスの尾を轟かせるという鵺だと言われた。
伸之助の転落を決定的なものとなったのは、彼が妙なものたちを集め出してから五年ほどが経過した時であった。伸之助は日頃より様々な者を座敷に出入りさせており、骨董屋や古本屋といった商人は勿論のこと、画家や楽師や書生、奇術師や僧侶、猛獣使いなど伸之助を尋ねる者は多岐に渡った。中には霊能力者を名乗る者や王家の末裔を自称する者もいて、得体の知れない人影も次々と屋敷の門をくぐっていた。
そのような者たちを集め、伸之助は大掛かりな樽俎を開催した。誰が参加したのかという明確な情報は無く、何をしていたのかもわからない。酒宴であったとも言われ、旋律の歌姫を招いた大規模な音楽祭が開かれたのだとも言われた。或いは人とポケモンが入り乱れた殺し合いが繰り広げられたとも伝えられて、血飛沫を上げながら揉み合う来客たちの様子を、伸之助は呵呵大笑して見物していたとも言われている。
その日、屋敷は渾沌と混迷の限りが尽くされた。赤や紫や黄色など色とりどりの提灯に火が灯され、座敷も、廊下も、中庭でさえも艶めかしげな光に照らされていた。廊下には怪しげな形状の壺が並べられ、その中には鈍く光るパールルが一匹ずつ収められていた。軒下にはカゲボウズがずらりと並び、抉られたように巨大な眼玉をひっきりなしに動かしては、灰色の襤褸を裂いた口で嘲るように嗤うのだった。天井付近には桃色のハクリューが舞い踊り、長い渡り廊下を腐臭を撒き散らすダストダスが這い蹲って移動した。石壁にびっしりと貼りつくバチュルは互いに蠕きあっており、硝子玉のような無数の碧い瞳が血の池に泳ぐ亡者たちのそれであるかの如くぎらぎらと哀しげであった。
泡沫の光が泳ぐ屋敷へと、無秩序な者たちが吸い込まれていった。ある者はネイティオの面で顔を覆った着流しの男であったし、ある者は黒のドレスに身を包んだ青髪の美女だった。またある者は異臭を放つ巨大な花を頭に飾った踊り子に猿轡を噛ませた幼い少女であり、またある者は惜しみなく身に着けた煌びやかな宝石を牙の覗く口に放り込んで噛み砕いている若者でもあった。
そんな彼らを招き入れ、伸之助は何をしていたのか。狂気の渦に飲み込まれた屋敷でその晩、何があったのかを語る者は誰もいない。
樽俎の催された夜が明けた後、伸之助の人生はもはや引き返せない闇の中へと踏み込んでいた。正体不明の恐怖を抱かせた屋敷へは誰も寄り付かなくなり、江角の工場と手を組んでいた者たちも次々と退いた。工場にいた労働者の中には逃げ出す者もいた始末で、またそうしなかったものや出来なかった者も、勤務先で伸之助の姿を見ると、苦々しげに目を逸らしたり指の先を震えさせたりした。屋敷にいた使用人たちも辞めてしまい、いよいよ伸之助と江角の屋敷は怪奇と化物の支配する、暗澹たる世界であるかのように思われた。
そんな伸之助から実権を奪い、祖父は江角を立て直した。工場を同業者に売る傍らで、出稼ぎ時代に出来た交友関係を利用し事業を始めた。伸之助を良いようにしていた骨董屋や霊媒師などを屋敷から徹底的に追い払い、蒐集された品も片端より売り払ったため、今現在は伸之助のコレクションはほとんど残っていない。屋敷に棲んでいる怪物と称されたポケモンたちは皆、祖父がぼんぐりに詰めて遠く離れた海の底に沈めてしまったらしく、噂の真偽を知ることは不可能となった。
伸之助は屋敷の一室に閉じ込められ、そこで生涯を終えることになる。晩年の彼は口をきくことも自ら歩くこともなく、日がな一日暗い部屋の中でじっと動かなかった。その顔は髑髏のように瘦せこけており、怒りも絶望も哀しみも浮かべられず、感情を抱くという機能が失われているのだと思わせた。死神を生き写したかの如き伸之助を幼い伯母姉妹は怖がり、また祖父の元妻は気味悪がったために近寄らず、伸之助はただただ孤独に生きていた。しかし自分が孤独であるという認識すらも無かったかもしれない。新たに雇われた使用人の出入りも禁止され、彼と接する時間があったのは、食事を運び入れる祖父のみであった。
祖父は実父へと、簡素な飯と一本の酒瓶を毎日運んでいた。その酒瓶は薄紫色をしていた。伸之助が押し込められた四畳半は狭苦しく、大樹の落とす影のせいで日中でも暗闇に覆われていた。
一切の光を奪われたその部屋で、伸之助は闇と同化するように亡くなった。伸之助が横たわっていた黴臭い畳には、空になった酒瓶が無造作に転がっていた。
◆
「とりあえず一回、バケツか何かに水を汲んでこよう」
水の枯れた池で苦しげにしているトサキントたちだが幸いまだ息はあるようで、すぐに処置をとればまだ間に合うように思えた。池が駄目になっているのならばここに水をまた入れるよりも、浴槽などに移した方がよいかもしれない。水を運ぶ手間が惜しく感じられ、直接手で抱えて持っていこうかと、僕はやけに冷静になった頭で考えた。
池は広く、そこに棲まわされた金魚たちの数はおよそ十匹弱と見えた。とてもじゃないが一人で運べる数ではなく、池に屈みこんでいた僕は立ち上がって縁側へと戻った。菜実子に手伝ってもらうか、誰かを呼んできてもらおうと口を開いた。
「菜実子」
しかし、その依頼は言葉にならず、代わりに弱い溜息が自分の口から吐き出されたのを感じた。
縁側にへたり込んだ菜実子の顔には、玉のような汗が一面に張り付いていた。平素は白くとも健康的な丸顔は朧の月光に照らされて青白く見える反面、赤黒く染まっているようにも捉えられた。どちらにせよ気分が悪いことは明白であり、菜実子は顔を覆う汗を拭う素振りも見せず、半開きの口で小刻みに呼吸を繰り返していた。
ぬちゃぬちゃという音が未だに聞こえる池を中心に中庭は生臭く、息の詰まるような湿気が充満している。あの残酷な光景も相まって、精神面の衝撃が体調の不調となり現れているのだと思われた。
「休んだ方がいい。叔母さんたちの部屋に行こう」
そう言って手を差し伸べると、菜実子はこくりと頷いて僕の手を取った。その手はやはり汗に濡れており、掴まれた瞬間に互いの掌がぬらりと滑った。
汗ばんだ肩を支えるようにして縁側に立つ。洗髪剤の香りと酒の匂い、そして微かな体臭が鼻をついた。よろめく菜実子の横顔は中庭の影になって見えなかったが、伏せられた目に黒の睫毛が乗っているのだけはわかった。
「ん」
座敷に足を踏み入れた刹那、僕は小さく声を上げた。出した一歩が妙に冷たく感じられた。言い知れぬ不気味さを覚えながらもう一歩を踏み出す。「え」今度は菜実子が息を呑んだ。
「濡れてる」
独り言のように彼女が言った。僕らの裸足と接している畳は湿っているを通り越してもはや濡れており、歩く度にぴしゃ、と弱々しげな水音が耳をついた。雨上がりの地面を歩いた時の感覚に似たそれは、プールサイドを小走りになった時のものに近いかもしれない。ぴしゃり、ぴしゃり、とごく僅かな水飛沫をあげ、濡れた畳は水辺のように薄く光っていた。
一体どういうことだ、と僕は首筋に汗を伝わせた。どこからか、下水などが壊れて水が漏れているのだろうと考えることは勿論出来たのだが、心の中にいる沢山の自分のうち、一人が否定の意を示していた、大多数の自分で彼を押さえつけ、黙らせてしまうことは容易であるはずなのに何故だか出来ず、僕は菜実子を支えたまま足を止めてしまった。
足の裏に冷たさを感じたまま立ち竦んでいると、土付随に微弱な、しかし確かに何かが押し付けられる感覚がした。畳の含んだ水は飽和状態を超えたらしく、日に焼けた藺草を表面張力のように薄く覆っていた。
その水には流れがあった。屋敷が傾いているなどとも思いたくないが、畳を滑る水は確実な動きを持って僕たちの足元でぴしゃぴしゃと波打っていた。流れの元に視線を這わせると、祖父の祭壇に行き当たった。仏頂面の遺影が飾られたその場所から、この水は流れているのだった。
「ねえ、聞こえるでしょ」
心臓を跳ねさせた僕が何か言うよりも先に、菜実子の震えた声が鼓膜に響いた。彼女の指が僕の寝間着の袖を掴んで引っ張った。一刻も早くここから立ち去るべきだという思いと、もう何処へも行けないのだという思いが交差する中で、僕は菜実子の体温を感じながら目を閉じた。視界に暗闇が訪れる。水の臭いに満ちた暗闇だ。
音がする、と先ほど菜実子は言った。何が聞こえるのか、そう問いたかったが口が動かなかった。じっとりと重い空気の中、水気に耳を澄ましていると、何かが移動していくような、地響にも似た音がした気がした。かなり地下深くを通っているらしいように聞こえるそれは、誰にも気付かれないままに、陰乍に進んでいるのであった。何の影一つも見えぬ暗闇の底を、刻々と、流れていくのだ。
ざあー、という落下音がした。ぽつ、ぽつ、という、何かを打ち付けるような音もした。びちゃ、と叩きつけられるような音、ばしゃり、とひっくり返る音。さあ、と降り注ぐ音も聞こえた。そして、その影には常に、あの轟くような振動が響いている。
この音は、一体何であろうか。どこかで聞いたことがあると思ったが、やはりそれがどこであるのかを思い出せない。想起しようとすると頭が酷く痛み、胃を握り締められるような不快感に襲われた。思い出さなくてはならない、思い出してはいけない、その二者に板挟みになり、意識が揺さぶられているように感じた。
「明久君ッ」
途端、菜実子の鋭い声が名を呼んだ。袖口を激しく引かれる感覚に目を開ける。若干の時間をかけて夜眼を取り戻した僕は、呆然とするあまり呼吸を忘れた。
祖父の祭壇がぐらぐらと揺れていた。火の消えた線香が床に落ち、香る薬草を水に浸らせた。献花が次々に落下しては花弁を広げて転がり、遊惰の権化となって散らばった。激化する振動に終に遺影が落ちる。額が悲鳴のような音を立てて割れた。
孵化したばかりの怪物のように、祭壇は数度、震えるみたいに揺れ動いた。そして、最後に小さな振動を残し、祭壇の下から水が噴出した。それと同時に足元の水嵩が増した。天井から俄雨のように水が激しく滴り落ちた。鉄砲弾のような乾いた音が何発かして、壁を破った鋭い水が吹き込んできた。
縺れる手足で菜実子を抱きかかえ、僕は縁側に出てまた絶句した。両隣から水流が押し寄せてきていた。水分を吸って重くなった寝間着はひどく冷たくて、どうすることも出来ない寒気を覚えた。
菜実子と寄り添い、僕は早鐘のような鼓動を鳴らしていた。フローゼルの親子が毛玉が転がるように駆け出して、スボミーの群れが甲高い声を出しながらひたすら逃げ惑ってはまた鳴いた。木々にとまっていたホーホーやヤミカラスたちが一斉に飛び立ち、全てを掻き消すほどの羽音が響く。混迷に満ちた中庭において、四方八方を取り囲むこの水の流れが向かう先にある大樹だけが動かずにいた。
◆
祖父が死ぬ一月前から、いよいよ病状は思わしくないものへと変わっていった。それまでは体調は常に優れないものの起きたり横になったりを繰り返していたのだが、ついにそれもままならなくなり、何をするにも姉の手を借りるようになっていた。
とある日のことである。喉が渇いた、と訴える祖父に姉は水を持っていった。透明のコップに注いだ水を姉は手渡したが、しかし祖父は勢いよくそれをはたき落した。
「水なんか飲めるか」
そして祖父は「酒を持ってこい」と激昂したように叫ぶのだった。聞き分けの悪い子供のようにそう言い続ける祖父に姉は辟易したが、医者に禁じられている手前、酒を与えるわけにもいかず、無理であることを懇々と言い聞かせる以外の道はなかった。
姉がいくら説得しても、祖父は酒が飲みたいと譫言のように訴え続けていた。唸り声すら上げて強請るその顔は悪鬼のようであり、修羅のようであり、そのくせ涙を流す亡霊のようであり、姉は只管、咳き込む祖父の背中を摩ることしか出来なかった。
「酒を」
死ぬ間際まで、祖父はそのままであった。
蒲団の中から天井を睨みつけ、何かを呪うかの如き眼光を放っている祖父の姿は、ひどく恐ろしくて哀しい生き物のようであったと姉は記憶している。
◆
祖父の葬式から半年ほどが過ぎたあたりで、菜実子の一家がカントーへと遊びに来た。
お互いの家族で時間を合わせて食事でもしようということになったのだが、菜実子と菜実子の母親、そして母と姉は買い物に行ったまま戻ってこないため、僕と父と哲人叔父は適当な喫茶店でひたすら待ち惚けを食らっているのだった。ガラス窓から見える空はどんよりと曇っていたが、大貴の旅先に広がる空は今頃どうなのであろうなどという、妙な感傷が心中を過った。
何杯目かになる珈琲の香りが内側と外側、どちらからも鼻腔を刺激する。紙のカップに描かれた、このチェーンのトレードマークであるジュゴンはこちらを目指して泳いでいた。無意味に口にする話題も早々に尽き、我々はめいめい身体を凝り固まらせながら時間をやり過ごしているのだった。
「親父のことなんだけれども」
窓の外の通りを、リードをつけたラクライの散歩をしている初老の女性が歩いていく。沈黙に耐えかねて口を開くのはいつも哲人叔父であった。僕と父は何か返事こそしなかったが、携帯電話だの本だのに落としていた視線を上げて叔父の方を見た。
「いや、親父というか母さんのことだ」
叔父は「もっとも僕が幼い頃で朧気な記憶だから単なる妄言に過ぎないかもしれないが」と前置きして話し始めた。
それは巴さんが亡くなる前の晩の記憶であった。幼い叔父は夜中に目を覚まし、隣に母親が寝ていないことに気がつき不安に駆られた。逆隣の蒲団にいる兄を起こそうにもぐっすり眠っていてとても目覚めてくれそうになく、叔父は巴さんを探しに廊下に出た。
暗い廊下の中に唯一、灯りの漏れる部屋があった。祖父の部屋であり、叔父にとっては父の部屋だった。普段入ることは滅多に無い場所であったが、その時は叔父をほっとさせた。
こっそり部屋に近づいていくと、巴さんと祖父が文机を挟んで何かを話していた。その内容は叔父の知るところではない。ただ、二人の間にある薄紫色の酒瓶が美しかったことだけが目に焼きついた。
祖父が巴さんに紫の玉が連なったものを手渡した。受け取った巴さんの手の中で、それはぽろぽろと音を立てていた。その綺麗な何かが数珠であるとわかったのは、叔父がもっと大きくなってからのことだった。
「そういえば、母さんが死んだ時に、その数珠をつけていたなあ」
黙って話を聞いていた父がぽつりと言った。叔父が「そうだったのか」と頷きを返す。カップに半分ほど残った珈琲は冷めきっていた。
「あの数珠の色が、ずっとあの酒瓶の色と重なるんだ」
◆
凄まじい量の水が、大樹へ向かって流れていく。この水がどこから来ているのか、それを知る術は恐らく無い。轟音を立てて辺りを埋め尽くしていく水に負けないよう、立っているのが精一杯であった。
庭の草木が薙ぎ倒されていく。祭壇が押し流されていくのが見えた。背後に聞こえるめきめきという音は、屋敷の柱が水圧によって折れていくものなのだと直感で理解した。僕と菜実子は障子が剥がれてしまった柱にしがみついていたが、これも何時までもってくれるかわかったものではなかった。
水に濡れ、揺らぐ視界の中で祖父の棺を探す。せめて遺体だけは流されないようにしなくてはならないと思った。飛沫が頰に飛ぶ。冷たさと生臭さに吐きそうになる。既に胸ほどの高さまである水は大きく揺れ動き、何を見るにもままならない。
菜実子が短い悲鳴をあげた。反射で掴んだ彼女の腕に、翠色の蔓が巻きついていた。腕だけでなく、首や腹、水中に捥がく脚にも同じものが見える。愕然として蔓の根元を辿ると、水に流れていく祖父の棺があった。
菜実子が蔓に引っ張られる。彼女の根元と頰を濡らす雫が涙なのか水なのか、そのどちらであるのか僕にはわからない。目を見開いて叫ぶ菜実子の声は奔流の轟く音に掻き消される。悴んだ手で蔓を解こうとしたが固く絡みついたそれは菜実子から離れず、より一層絡みを強めるだけであった。
菜実子の腕を掴み、大樹に近寄らせないようにするのが限界だった。渦巻く水の中で菜実子は俯き、息を荒くして堪えている。気管に水が入ったらしく、鼻の奥から頭にかけてがつんと痛くなった。耳にも水が入ってきたのか、それともあまりの轟音なのか、僕たちは低い唸り声のような音の中に飲み込まれていた。
押し寄せる水流と共に、無数の記憶と誰かの想起と聞いた話と妄想が、一緒くたになって脳裏を駆け巡っていく。
屋敷を常に包み込んでいた湿気。広い中庭。祖父と歩く祭囃子。朱塗りの鳥居。幼い大貴の青い顔。入れなかったリザード。桜子伯母の流産。洋間に飾られた絵画と蔵に詰められた蒐集品。酒呑童子の絵巻。伸之助が育てていたという化物と、正体不明の催事。夢の中で通るあの暗く涼しい道。酒屋の影。巴さんの死。薄紫色の酒瓶が傾けられる。父はそれを飲むことが出来ない。「酒は毒だ」祖父が言った。
草木が育つための必要条件とは何であったか。
頭の中に水底がある。水面は遠く、遥か上にあった外の様子を見ることは出来ない。柔らかな陽が差し込んで、水と共にゆらゆらと揺蕩う様子は穏やかであった。
その中に、裸体の女が沈んでいる。身体を丸まらせて蹲っている女は、水底の近くをゆっくりと漂っている。それは菜実子であるように見え、巴さんであるように見える。
水底を囲うのは、薄紫色の透き通った壁であった。
奔流に乗って、あの酒瓶が流れてきた。
三分の二ほどの中身が残ったそれを掴み取った僕は無我夢中で、酒瓶を大樹に向かって放り投げた。
◆
「会社を継ぐ気はないのか」
夏の座敷で祖父が問う。祖父と父は文机を挟んで向かい合っている。文机の上には二本の酒瓶と二つのグラスが置かれている。グラスの片方は手付かずであり、もう片方は半分ほど減っている。
「いいえ」
若き日の父はそう答える。「勉強を続けたいのです」
「そうか」
祖父は怒りもせず、かと言って表情を和らげることもせずに、ただそう言うだけであった。父は祖父の顔を見れずに俯いている。グラスの表面に現れた結露が滴り落ちて、木製の文机を濡らしている。中庭では相変わらずテッカニンが鳴いており、室内に反響しては万華鏡のように幾重の声となる。
「父さん」
父は顔を上げる。祖父と視線が合い、父の背中を冷たい汗が伝う。喉の奥で変な音がした。
薄紫の瓶が、光を浴びて美しく輝いている。
「何故、その酒を俺は飲めないのですが」
父は尋ねた。祖父は黙っている。じわじわという鳴き声だけが響いている。どれほどの時間が流れているのか父にはわからない。祖父の部屋だけが時間の流れから取り残されたようである。祖父が時を止めているようでもある。この須臾は永遠であった。
「酒は毒だ」
祖父はそう答えた。それだけであった。他には何も言わなかった。
毎度聞かされるその口癖に、父は「そうですか」と呟いた。差し出された方のグラスには口を付けていない大吟醸がなみなみと注がれている。手を伸ばそうとしたが動かなかった。祖父の手にしたグラスの中で揺蕩う、無色透明の海がゆらりゆらりと揺れて、父はそこにもう亡き母親の面影を見た気がした。
◆
酒瓶は放物線を描き、渦巻く水流の中へと吸い込まれていった。濡れた前髪が額に貼り付いて気持ちが悪い。夢と現も判別付かない頭の中に、哀しげな慟哭が響いた気がした。ひどく重くなった身体はもはや自分のもので無いように感じられ、感覚の無くなった片手で菜実子を掴んでいることだけが唯一現実味を伴っていた。
その片手が不意に軽くなった。勢い余って蹌踉た菜実子を抱き止めて、僕は目の前の光景に息を潜めていた。
あれほど轟いていた水があっという間に引いていった。どこに消えていくのかはわからない。庭の土に吸い取られるようにして、或いは塀の下を通って屋敷の外へと逃げるようにして、中庭に集まっていた洪水は瞬く間に無くなってしまった。
腕の中の菜実子が息を飲み、小さく身体を震えさせる。彼女の目線の先には祖父の棺が、濡れた状態で打ち捨てられていた。流水によって蓋は外れてしまっており、祖父の遺体が転がり出ている。
全てを跳ね除けるような、不屈という言葉を具現化したかの如き表情は死んでいても変わらない。その事実はある種の安堵ともなり得たのかもしれないが、今はそれすらも絶句の理由でしかなかった。
祖父の身体を突き抜けて、幾本もの蔓が長く伸びていた。菜実子を水流の中へと引き込もうとしたそれは今でこそだらりと垂れ下がっているが、青々という鮮やかさを今も尚、朧月の光に湛えていた。突き破られた皮膚は表面こそ水に濡れてしまったものの乾いているように見え、痛そうなどと感じないのが不思議であった。その様子は、まるで祖父とこの蔓が初めから一体であったかのような、馬鹿げた妄想を引き起こした。
しかしそれ以上に我々の目を惹いたものがあった。水浸しになった中庭は泥濘んでおり、まだ残っている水が足を微かに叩くのが奇妙に心地良かった。彼方此方に流されたトサキントやアズマオウが再び水を失い、散らばった先で各々のたうち回っていた。彼らが持つ、美しい鰭が地面に打ち付けられる度に、びちびちと濡れた音が強く響いた。
その中庭の、中央に位置していた大樹が大きく傾いている。一杯に生い茂らせた葉は僕たちの知るままの姿であったが、筋骨のような幹から繋がる、猛々しい根元の先が月明かりの下に晒されていた。
奔流によって大地が抉られたからか、それとも故意にそうしたのかは知る由も無い。半壊した屋敷に囲まれるようにして、恐ろしいほどに巨大なドダイトスが、大樹諸共中庭を背負ってその身を投げ出していた。
ドダイトスは冷たい水に浸され、ぎらぎらと輝いているように見えた。切株程もある四肢は力を失って、苔に覆われた両眼は固く閉じられていた。額に寄せられた皺は苦しげであったけれど、巨躯は驚くほど綺麗なままであり、畏怖すべき美しさが眼前に顕現していた。
僕も菜実子も、無言で佇んでいた。濡れた土の匂いと、噎せ返りそうになるほどの深緑の薫りが満ちていた。何処かでドンカラスが鳴いた気がした。父や母、姉、親戚たちが僕たちを呼ぶ声が聞こえてきた。
◆
屋敷から三十分ほど車に揺られた先にある火葬場はこじんまりと静かであった。周りに広がる草原が穏やかで、暑くも心地良い空気が漂っていた。大きな尻尾を揺らして駆けていくパチリスの上空を、夏型のアゲハントがひらりひらりと舞う。雲の無い空は青く、今にも落ちてしまいそうに綺麗だった。
あの後、崩れ掛かった屋敷は大騒ぎになったが、皆必要以上に慌てたり騒いだりすることは無かった。地面を割って現れたドダイトスが何故そこにいたのか、どうしてあれほどまでに大きいのか、また、何を思って今日この日に出てきたのかということも、誰も触れなかった。大貴でさえも黙っていた。蔓に裂かれた祖父の遺体の不気味さがそうさせるのか、埋まっていたはずのドダイトスの身体がつい先ほどまで生きていたかのような美しさであったことが原因なのか、或いはもっと、深いところに理由があるのかはわからない。蒸し暑さの消え失せた屋敷は祖父の葬式当日であるはずなのに、祖父の話をする者は誰もいなかった。
葬式の食事は豪華な寿司が出たが味など分からず、粘土を頬張っているような心地であった。夜、菜実子と過ごしたあの時間は夢の延長だったのではないかと僕は考えていた。しかし、薄紫の酒瓶の中身を飲んだ時の痺れも、干上がった池の生臭さも、押し寄せる水流の圧も棺から伸びる蔓も菜実子の横顔も、夢というには実に鮮明に、僕の脳裏に刻まれていた。
やや離れた席では、村佐さんと哲人叔父が寿司をつつきながら話していた。村佐さんはこの辺りに昔から住む血筋らしく、過去の話などを叔父に聞かせていた。
江角家初代、総次郎が若い頃の話だというそれは、シンオウの開拓時代だという前置きから始まった。カントーから訪れた開拓団によりシンオウは切り開かれていったのだが、とある場所の住民たちがいつになっても了承しないため、開拓団は手を焼いていた。
が、ある時住民たちは、一つの話を開拓団の一人に持ちかける。この近くには邪神がいる、自分たちはそいつを鎮めなくてはいけないからここから動けない、森を広げる邪神の機嫌を損ねると祟られるから怖くて出ていけない、と彼らは嘆いた。そして、その邪神をどうにかしてくれさえすればすぐにでも立ち退こう、とも。それより間も無く住民たちはそこを去り、開拓は滞りなく推し進められた。開拓に多大な貢献をした一人の男にはかなりの対価が支払われたらしいが、その男がそれを何に使ったのか、開拓団を抜けた後にどうしたのか、そして如何にして開拓を成功させたのかは杳として知れない。
村佐さんはそんな話をした。哲人叔父は黙って頷いていた。茶と共に飲み込んだ寿司に塗りたくられた山葵が、喉の奥でつんと香った。
二人と別の一角では、桜子伯母と鏡子伯母が、遺産相続の手続きについて話していた。屋敷の崩れた土地は売り払い、得た金はシンオウの自然保護に取り組む団体に全額寄付するなどという会話が聞こえた。ドダイトスの亡骸は丁重に供養した後、かつて森があった処へ帰してやろうなどと伯母たちは言った。
彼女たちが持っていた屋敷の間取り図を覗き込み、僕は思わず言葉を失った。妙な部屋の並びをしていると思っていた屋敷の形を図式化したそれは、歴とした鳥居の形を成していた。
「どうせ、出てこれまい」菜実子が聞いた祖父の声が頭に反響する。地面に作られた大きな鳥居は、地下深くという社にいる神を封じているかのようだった。
食後に運ばれてきたロメは熟し過ぎているように思った。苦いほどの甘さを持つそれを口内へと押し込みつつ、僕は斜め前に座る菜実子を盗み見た。喪服姿の彼女は白い頬に薄く紅を塗っていた。スプーンで掬われた緑の果肉が小さな口へ運ばれる。前髪に隠れた菜実子の、あまり手を入れられていない眉が微かに見える度、僕は現と夢の区別がより一層つかなくなるのだった。
祖父が焼かれているのを待つ間、我々は手持ち無沙汰に草原に立っていた。母が手洗いに行ってしまったため、僕は父と姉と並んで何くれとなく空を見上げていた。
わざとそうしようとしているのか、僕たちは取り留めもない話を口にして母を待っていた。父は僕の大学のことを聞きたがり、姉は友人のポケモンがコンテストに出たことなどを話した。
姉の話が、不意に「そういえば、変な夢を見たの」という内容に差し掛かった。
「水道の中を歩いてる夢なのよ」
「水道?」
聞き返した僕に姉は頷いて、片手を頬に当てながら考え込んだ。細い手首に骨が浮かんでいる。手の触れた顳顬を汗が一筋伝っていた。
「なんだか、水道の中みたいなところ歩いてるのよ。ぐるりと壁に覆われて、水が流れていく音が聞こえるから、水道」
水が流れてる菅ってだけでそう決めるのは安直かしら。汗を拭う姉は言った。「でも、それしか例えようもないしね」
「でも、毎晩同じ夢を見てたのよ。ここに住み込んでから、いえ、もっと前から、ずっと」
「小さい時から、ずっと、か」
呟くような姉の言葉に父が口を挟んだ。普段父はあまり喋らない性分だったし、こうして誰かの話を遮るような真似をしなかったから、僕は少々驚いた。意外であると感じたのは姉も同じだったようで、目を数回開けたり閉じたりしてから返事をした。
「そうだけど。お母さんに言っても信じてもらえなくて。でも、何でわかったのよ」
もしかしてお父さんもそうだったとかじゃないでしょうね、という姉の言葉に父は返事をしなかった。ただ少しだけ口許を緩めた父は、汗の浮かんだ瞼を数秒閉じた。
「道の向こうに、親父が歩いていった。俺はそれを追いかけるんだが、どれだけ急いでも、親父との距離は開くばかりなんだ。親父の向かう先に、親父に似ている男が二人歩いていた。俺は親父に手を伸ばした。だが、」
父が話し出した。それは僕たちに話しているというよりも独り言のようであり、またここにいない誰かに語りかけているかのようにも感じられた。
「後ろから引っ張られて、親父の方へは行けなかった。振り解こうとすると地面が揺れて足が縺れた。ずっと聞こえていた音が、轟々と鳴り響いていた」
それは果たして、昨日にだけ見た夢なのだろうか。父の話を聞いていた僕の頭の中で、ふとそんな疑問が首を擡げた。
しかしそれを確かめる術はもうあるまい。いや、最初から無いだろう。父の見た夢の意味するところは、父にすら永劫にわからない。
「引っ張ってくれたのは、母親だったように思う」
父はそこで目を覚ましたという。夢から引き戻された父を待っていたのは屋敷が崩れる現実の震動と、蒲団から出た自分の妻が慌ただしげに障子の外を覗く姿であった。血相を変えた姉が廊下を走ってきて、その後を追った父が中庭の惨状を見るのはその数刻後である。
水が流れてるから水道だと姉は言った。水の通り道となる管に、またそれと隣り合っている道に、僕は思い出すものがあったが、今となっては全て終わったことであるため黙っていた。
「声は呼んでいた。何度も聞こえた」
僕も姉も、父の話に何かを言うことをしなかった。その夢は僕もよく知っているようであり、また全くの未知であるようでもあった。姉もきっと同様であろう。僕たちは黙りこくったまま、父の声だけが頭の奥に溶けていった。
その声が何を言っていたのか、僕は昔から知っている。姉も、そして父もだ。何を訴えているのか、何を読んでいるのか、僕たちは皆、その声を長く聞いていた。
「江角、と」
しねしねしね。テッカニンの鳴き声が響いてくる。この鳴き方を聞くのは久方ぶりであった。以前に聞いたのはずっと昔のことで、やはり屋敷に訪れた際だったのは覚えているが、その時隣に誰がいたのかは記憶に残っていない。ただ、夏という監獄の檻となって自分を責め立てるようなものに感じられたことだけが、今も尚はっきりと思い出せる。死ね、という慟哭となって。
煙突からは白い煙が細く上がっている。終わっちゃったねぇ、と姉が気の抜けた声で言う。父が小さく頷き、取り出したハンカチで汗を拭う。青一色の空を突き進む煙は、祖父らしからぬ緩慢さで天へと向かう。
首筋を伝った汗がワイシャツの襟に染み込んだ。火葬場を囲う木々の緑が、鮮やかな色をして風に揺れていた。
江角が殺し、江角を呪った神を、江角の血をひかない僕が葬ったのだと、そう思った。
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | |